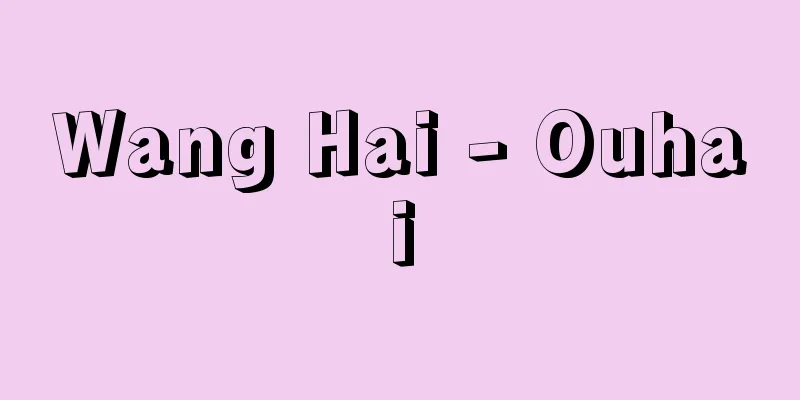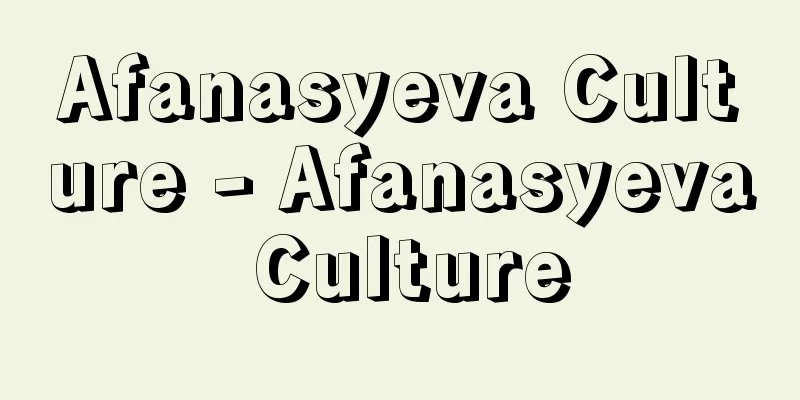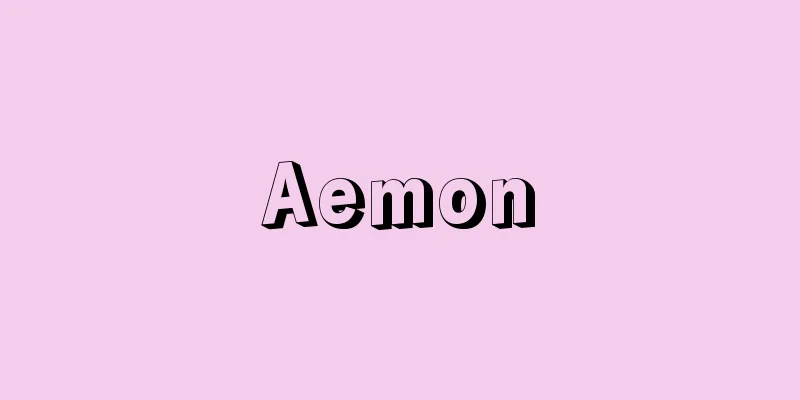United States of America

|
A federal republic occupying the center of North America. Abbreviated as USA. Also known simply as America. It consists of 50 states, including the 48 mainland states and two states, Alaska and Hawaii, and one capital district (District of Columbia). It also has overseas territories such as Puerto Rico, the Virgin Islands, Eastern Samoa, and Guam. Its area is 9,629,091 square kilometers (UN statistics, 2002), with a population of 299,398,000 (estimated for 2006) and 308,750,000 (estimated for 2010). [Yasushi Watanabe] OverviewCountry nameSince 1607, there have been 13 British colonies in the Americas, with little mutual relationship between them. However, as the conflict with the British mainland intensified in the late 18th century, they needed to unite with each other, and often acted as the United Colonies of America. Eventually, in the Declaration of Independence on July 4, 1776, they were called the United States of America, and in the Articles of Confederation adopted by the Continental Congress in November 1777 (and officially came into effect in March 1781), they were defined as The United States of America (since the Treaty of Peace and Amity between the United States and Japan in 1853, it has been translated as the United States in Japan). In the United States Constitution drafted in 1787, each state was given a certain degree of national status, and the federal government was established in April 1789 as a higher-level confederate organization. The United States is characterized by being a federal system with strong dual national characteristics, a republic without a monarch, and a republic of unprecedented size in history. [Yasushi Watanabe] Geographical locationThe United States is about 25 times the size of Japan (California alone is slightly larger than Japan). The Atlantic Ocean is often said to have been the source of "free security" for the United States. The fact that the United States was separated by the Atlantic Ocean meant that it was less subject to military, political, and cultural influence from European powers, which enabled the United States to pursue a so-called isolationist diplomacy and fostered a sense of American civilization as distinct from European civilization. The vast continental nation of the United States developed into the world's leading agricultural nation (it is still the world's largest food producer as of 2012), and by the end of the 19th century it had become the world's leading industrial nation. With this high level of productivity as a backdrop, and with the Spanish-American War of 1898 as a turning point, the United States began to take on a strong character as a maritime and Pacific nation. After World War II, it exercised influence as the "leader of the Western camp," and after the end of the Cold War, it exercised influence as the "sole superpower." However, in recent years, the relative decline of the United States' national power has been pointed out, due to the rise of emerging countries such as China and India, and the financial crisis of the fall of 2008. [Yasushi Watanabe] Historical AttributesUnlike Europe, the United States of America did not go through the Middle Ages, feudalism, or absolutism, but began almost at the same time as the modern era. It is also an experimental nation that created the first democratic republic in human history, free from the rule of the British king and with the absence of aristocracy (the United States gained independence 13 years before the outbreak of the French Revolution). In addition, because the country possessed vast tracts of land and the role of the federal government was limited, ideas such as self-employment (individualism), equal opportunity (egalitarianism), free competition (liberalism), and success (prosperity) came to be emphasized. In other words, it can be said that the United States has sought to achieve "unity in diversity" through these "American values." Furthermore, there is a tendency to equate "American values" with "universal values" due to their affinity with modern values. As a result, there are many instances in which America seems overly self-superior and overly charged with a sense of chosenness or missionary mission, especially when it comes to foreign countries. This idea, also known as "American exceptionalism," was the logic that supported isolationism (from Europe) in the 19th century, and at the same time, it was also the logic that supported America's global expansionism in the 20th century. [Yasushi Watanabe] What is an American?Since British colonization began in the early 17th century, immigrants to America were overwhelmingly of British descent (so-called WASPs: White Anglo-Saxon Protestants), and the theory of "Anglo-conformity," which claimed that other immigrants should also conform to British culture, was prevalent. However, as the number of new immigrants from Eastern and Southern Europe and Asia increased rapidly, the "melting pot" theory, in which various races and ethnicities melt together to become "Americans," became a new metaphor for social integration. Furthermore, around the time of World War I, America was imagined as a "mosaic" of different races and ethnicities, and the so-called "salad bowl" theory became popular. It was around this time that the writer Louis Adamic (1898-1951) coined the rhetoric that "diversity is strength," quoting Walt Whitman's "a nation of nations." However, both the "melting pot" theory and the "salad bowl" theory are status quo-positive and predestined, and fail to adequately explain the structures of discrimination and oppression that exist in American society. In particular, the 1960s and 1970s saw the rise of not only the civil rights movement, but also a counterculture against established values, particularly among young people, and saw the rise of the hippie movement, student movements, and anti-Vietnam War movements that advocated a return to nature. The idea of "multiculturalism" was born out of this trend of thought that was sensitive to ruling power, and has been supported by liberals since the 1980s. Multiculturalism means the idea of rejecting the hierarchy between cultures and actively promoting the coexistence and coexistence of different cultures. In particular, it aims to actively recognize the rights of people who are in a weaker position in terms of race, ethnicity, religion, gender, class, physicality, etc. Examples of this include "affirmative action," which requires a certain number of blacks or other ethnic minorities to be employed at a workplace, or a certain number of minorities to be admitted to a school. However, criticism that multiculturalism is separatist is growing, especially among conservatives, and tensions between multiculturalism and liberals continue. [Yasushi Watanabe] Flag and anthemThe flag and anthem also play an important role as symbols of social integration. In June 1777, the prototype of the Stars and Stripes was established, with red and white horizontal stripes representing the 13 independent states and a white star on a blue background in the upper left corner representing each state. The design has been updated 27 times, and the current version has been used since Independence Day (July 4th) in 1960. There are 50 stars, the same as the number of states. The national anthem is commonly known as the Star-Spangled Banner, written by lawyer Francis S. Key during the War of 1814, and was designated the national anthem by a federal act in March 1931. In addition to the flag and anthem, the Declaration of Independence and the United States Constitution also function as symbols of integration. The metaphor "We must become a city upon a hill," preached John Winthrop, a Christian Protestant leader who traveled to New England in the early 17th century, on his ship. The American Dream, symbolized by Lincoln, who embodied the "log cabin to the White House," is also frequently used and continues to inspire the American people. The same can be said of Lincoln's description of America as "the last, best hope of earth," and his "government of the people, by the people, for the people" in the Gettysburg Address (1863), delivered at the dedication ceremony of the National Cemetery. [Yasushi Watanabe] The United States in the 3rd centuryJuly 2011 marks the 35th year since the United States celebrated its 200th anniversary of independence on July 4, 1976. The history of America since entering this third century has been a tumultuous one. In foreign affairs, the Vietnam War, which had been in full swing since the 1960s, became bogged down, causing serious setbacks for Americans who had enjoyed "Pax Americana." America's diplomatic prestige was then restored from the 1980s to the 1990s. The Cold War came to an end with the reunification of East and West Germany in 1990 and the dissolution of the Soviet Union the following year, resulting in the victory of the liberal camp, and the world transformed from the bipolar confrontational structure of the Cold War era into a unipolar structure with the United States at its center. Symbolizing this was the victory in the Gulf War, which began with Iraq's invasion of Kuwait in 1990. However, the new international order under the US-centered unipolar structure was far from stable. In the 1990s, local conflicts occurred frequently in places such as Somalia, Kosovo, and Bosnia. On September 11, 2001, the terrorist attacks carried out by the Islamic extremist group Al-Qaeda deeply damaged the US, and its foreign policy changed drastically in the name of the "war on terror." The retaliatory attacks on Afghanistan that began in October 2001 and the Iraq War that began in March 2003 were formally "coalitions of the willing" with countries that joined the multinational forces, but in reality they were based on US unilateralism. Barack Obama, who took office as president in 2009, put forward the principle of international cooperation. However, with the assassination of Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda and the perpetrator of the 9/11 terrorist attacks on an international wanted list, American diplomacy in the middle of the third century is once again facing a major turning point, including how the "war on terror" will change. Within the country, the wave of social reforms that had been going on since the 1960s, such as the civil rights movement and gender equality, stalled in the mid-1970s. Government-led affirmative action for African-Americans, indigenous peoples, and women created "reverse discrimination" against white men. Furthermore, from the late 1970s to the 1990s, various states introduced legal restrictions on "hate crimes," which are crimes motivated by hatred or prejudice against people belonging to certain categories, such as race, religion, or ethnicity, and harsher penalties were imposed than for ordinary crimes. However, it is not easy to impose heavier penalties based on the criminal's "mental problem," i.e., hatred for those different from oneself, and the content of hate crime-related laws varies from state to state. On the other hand, the increase in Hispanic (Latino) and Asian immigrants from Central and South America has been noticeable since the 1980s, triggered by the 1965 Immigration Law Reform, and the "face" of America is changing dramatically. The pace of population growth of Latinos has been particularly remarkable, increasing by more than 40% in the 20 years from 1980 to 2000, and in the 2000 census, the number of Latino/Hispanic residents slightly surpassed that of African residents to become the largest racial minority. According to the Census Bureau, the proportion of whites in the total population of the United States was about 70% in 2000, but is expected to fall to about 50% by 2050, causing whites to lose their "majority" status, and the very concept of "minority" is expected to change significantly. The belief that immigrants, or "new blood," bring diversity to America, and that diversity creates the nation's vitality, leads to the logic of pluralism, which sees political power in America being decentralized. The national motto, "E PLURIBUS UNUM" (unity in diversity), engraved on coins and other items, shows that the foundation that supports American democracy is an attitude of accepting immigrants. However, nativist (anti-foreigner) public opinion that seeks to exclude immigrants due to cultural differences, such as "immigrants cannot assimilate into America," still coexists. In addition, various conflicts between conservatives and liberals over the role of government in policy areas such as ethical issues surrounding abortion and homosexuality, welfare, poverty, and education have been heating up since the 1980s, when conservatives began to gain prominence, and since the beginning of the 21st century, the theory of "two Americas" has emerged, polarizing the nation as conservatives and liberals face off in fierce conflict. As the "face" of America is changing, a major issue going forward is how the two nations can overcome this conflict and coexist. [Maeshima Kazuhiro] NatureTopography and geologyThe topography of the United States can be broadly divided into four parts: (1) the old, eroded highlands in the east; (2) the coastal plain stretching from the eastern Appalachians to the Gulf of Mexico; (3) the vast central plain of the Mississippi River basin; and (4) the new, high mountain ranges in the west. The United States Geological Survey also divides the country into eight major physiographic provinces, 25 intermediate physiographic provinces, and 86 minor physiographic provinces based on a combination of geology and topography. This article will provide a brief description of the eight major physiographic provinces of the United States Geological Survey. (A) Laurentian Plateau Located at the southern end of the Canadian Shield, it is part of the oldest landmass on Earth, with the Precambrian world exposed. It is a plateau-like plateau that has been eroded by continental glaciers during the Quaternary ice age. It is home to the Mesabi Iron Mountains, famous for their high quality. (B) Coastal Plain: A plain extending from the Atlantic coast of southern New York State to the Gulf of Mexico. Old marine deposits gently slope toward the sea, with newer sediments on top. Many rivers flow from the Appalachians along the Atlantic coast, developing fall line cities at the foothills, while on the coast subsidence formed estuaries that nurtured many port cities, including New York. The plain widens toward the Gulf of Mexico, becoming a rich agricultural region. A typical bird's-toe delta can be seen at the mouth of the Mississippi River. (C) Appalachian Highlands An old eroded folded mountain range consisting mainly of Paleozoic rocks that runs from northeast to southwest in the eastern United States. It is divided into three ranges: the Old Appalachian in the east, the New Appalachian in the center, and the Appalachian Plateau in the west. The Southern Old Appalachian is the highest, with its highest peak, Mount Mitchell (2,037 meters). The Allegheny (Appalachian) Plateau contains the world's largest bituminous coalfield (the Pennsylvania coalfield), which became the basis of the prosperity of the United States. (D) Inland Plains The Inland Plains are broadly divided into a low inland plateau in the east that continues to the Appalachians, the central lowlands, and the Great Plains in the west. The central lowlands are a structural plain made up of nearly horizontal strata from the Paleozoic era, forming a cuesta topography. The Great Lakes are formed by water filling the gap between the deposits of continental glaciers and the lowlands of the cuesta. The Great Plains are a plateau made up of Tertiary strata from the Mesozoic era, and the elevation increases the further west you go. (E) Inland Highlands The Inland Highlands are an extension of the Allegheny Plateau that reappears across the central plains of the Mississippi River. The Ozark Plateau produces lead and zinc. (F) Rocky Mountain System The Rocky Geosyncline of the Paleozoic era was uplifted by the Laramide Orthogonal Movement, and after it became a peneplain, it rose rapidly by the Cascade Orthogonal Movement at the end of the Tertiary Period, reaching an elevation of over 4,000 meters. It is divided into the Southern Rockies, Wyoming Basin, Central Rockies, and Northern Rockies, with several rows of mountain ranges and longitudinal valleys between them, forming basins in the wider areas. Glaciers still exist in the north, and the area is designated as Glacier National Park, straddling Canada. (G) Intermountain Plateau The intermountain plateau is divided into the Columbia Plateau, which is made up of thick layers of volcanic basalt, the Colorado Plateau, where ancient strata from the Paleozoic and Mesozoic eras are distributed almost horizontally, and the large basin in between, with its unique landscapes including large canyons and dry deserts. (H) Pacific Cordillera System: The Sierra Nevada, Cascade, Coast Ranges, and the rifts between them. It is part of the Pacific Belt of Fire and contains many volcanoes. (F), (G), and (H) are collectively called the Cordillera System, which is part of the Circum-Pacific orogenic belt and occupies about one-third of the width of the United States. [Tatsuo Ito] climateApart from Alaska, which has tundra (permafrost) and taiga (boreal coniferous forest), and Hawaii, which is an island with perpetual summer, most of the mainland United States belongs to the temperate and subarctic (cold) zones, with a small amount of tropical rainforest in the southern half of Florida. This article describes the climate of the mainland. Climate is influenced by the characteristics of topography, ocean, ocean currents, wind, etc., and in a land mass like the United States that stretches 4,500 km from east to west, there are large differences between the coast and the inland, so there are a variety of climate types within the country. Looking at the big picture, the Appalachian and Rocky mountain ranges on both the east and west sides of the continent make it difficult for the influence of the ocean to reach the inland, and the Rocky Mountains in particular are high, forming a wide dry zone inside. On the other hand, there are almost no topographical obstacles in the north-south direction that prevent the influence from Canada in the north and Mexico in the south, so in winter, Arctic air masses tend to move south, and cold air masses flow from the Great Lakes coast to the central inland, while in summer, moist air masses accompanied by hurricanes move north from the Gulf of Mexico to the interior, bringing rain. In addition, in the coastal areas, the Pacific coast is washed by the California Current (cold current), while the Atlantic coast is washed by the Gulf Stream (warm current) so there are differences in temperature and precipitation even at the same latitude. The difference is further exacerbated by the Westerly winds on the west coast of the continent and the monsoons on the east coast. The eight main climatic regions of the United States are as follows: (1) Tropical climate zone in the southern half of the Florida peninsula. This is the only tropical zone in the continental United States, with savanna climate (Aw) characteristics. It has distinct rainy and dry seasons, making it an ideal winter getaway. Miami Beach, lined with luxurious resort hotels, is a world-famous tourist resort. Everglades National Park near the southern tip of the peninsula is famous for its wetlands with rare tropical trees and as a habitat for many species of wild birds. (2) Eastern Monsoon Climate Region This is a monsoon climate (Cfa) that extends over a wide area from the coastal plain stretching from the eastern Atlantic coast to the Gulf of Mexico to the interior of Arkansas and Oklahoma. It has four distinct seasons, and the climate in the mid-Atlantic coast is similar to that of Japan, with New York having a climate similar to that of Sendai. The Gulf of Mexico coast is close to the subtropics, and inland, the alternation of dry and rainy seasons and high temperatures are ideal for growing cotton, making it a world-class cotton-growing region. (3) The west coast marine climate zone in the northwestern part of the continent. Although it is the same humid and warm climate, the Pacific coasts of Washington and Oregon are strongly influenced by the westerly winds, and have a small annual temperature range, a cool climate, and an average amount of precipitation throughout the year. This climate type does not exist in Japan, and it has a mild climate with beautiful deep greenery and flowers throughout the year. (4) Subarctic (cold) climate zone around the Great Lakes in the northeast The area from New England to the border of the inland Great Plains has a subarctic climate (Dfa, Dfb), which covers more than a quarter of the mainland. New England has a climate similar to Hokkaido, but as you move inland, the annual and daily temperature ranges become larger, precipitation decreases, and the characteristics of a continental climate become stronger. In the south, corn and winter wheat are cultivated by taking advantage of the high summer temperatures, but as you move north, the summers become cooler and the area becomes a spring wheat, fruit, and dairy farming region. Winters inland are severe, with temperatures of around -20°C not uncommon in Chicago. (5) Mediterranean Climate of California The mid-latitude region on the west coast of the continent has a unique Mediterranean climate (Cs), with dry summers and precipitation in winters. As a result, citrus fruits and grapes, which can withstand the dry summers, are cultivated, and where irrigation water is available, rich agriculture is carried out. The famous foggy scenery of San Francisco is caused by the California Current flowing south and coming into contact with warm air, generating fog, which is then carried by the sea breeze and flows into the area. (6) Dry Grasslands of the Great Plains If you go inland beyond 100 degrees west longitude, you will find a steppe (short grass prairie) climate (BS) with almost no rain. This is a land of cowboys who graze their cattle. Some areas have been cultivated thanks to the development of dry farming methods that make use of the little rainfall. (7) Desert Climate The area between the Rocky Mountains and the Pacific Coast Mountains is isolated from the ocean and is located in the mid-latitude high pressure zone, resulting in a desert climate (BW). Famous places include the Salt Lake and the Mojave Desert. (8) Alpine Climate The high altitudes of the Rocky Mountains and Cascade Mountains are covered with ice and snow all year round, which is called the alpine climate (H). The Southern Rockies contain Mount Elbert (4,399 meters), the highest peak in the United States. [Tatsuo Ito] BiotaThe flora of the continental United States is roughly divided into four types: the forests that occupy the eastern half of the country, the grasslands of the Great Inland Plains, the forests of the northern Pacific coast, and the dry semi-desert and desert of the south. The forests of the east are further divided into a tropical system dominated by cypress in the southern Florida peninsula, an evergreen coniferous system dominated by pines to the north, a mixed system of deciduous broadleaf trees and evergreen conifers further north, a deciduous broadleaf system from southern New England to the southern Central Plain, a cool-weather system from northern New England to the Great Lakes area that is a mixture of deciduous trees such as maple, ash, tulip tree, and beech with evergreen conifers such as spruce and fir, and a cold-weather system north of the Great Lakes. The plains with warm-climate vegetation are now mostly cultivated, and fertile farmland has developed. Westward across the Mississippi River, the forests become sparse hardwoods and then give way to grassland of long grass species such as Kentucky bluegrass, which is a member of the Pecococcus genus. This is the prairie. Further west, in the Great Plains, the landscape changes to a landscape of short grass species such as grama grass, buffalo grass, and needle grass, interspersed with shrubs. The prairies are primarily used for farming, while the Great Plains are primarily used for ranching. From the Rocky Mountains to the Pacific coast, the topography and climate are complex, and the flora is diverse. Pine and fir are predominant in the lowlands south of latitude 50, and mixed forests of oak and fir can be found around Puget Sound. There are few trees on the Columbia Plateau, and there are prairies with short grass. The intermountain highlands and basins south of the Great Basin and Wyoming Basin have an arid climate, with trees growing in the highlands, but as you go down to the lowlands, the temperature rises and shrubs and short grass appear, and in the south, it becomes a desert where cacti are the only vegetation. In the Mediterranean climate zone of central California, evergreen broad-leaved trees and mesquite, a type of legume, are predominant, but in the dry summer the mountain surfaces turn brown and die. The fauna of the mainland United States shows similar characteristics to the vegetation distribution, but species that live throughout the country include Virginia deer, American black bear, lynx, puma (American lion), river otter, mink, beaver, musk rat, and gray wolf. The coyote and American bison of the western prairies are known as endemic species and are designated as protected animals. Animals and birds are generally close to Asian species, but there are quite clear differences between marine animals on the Atlantic and Pacific coasts, and the California sea lion, which has a long neck and protruding ears, does not live on the Atlantic coast. [Tatsuo Ito] Geography
[Tatsuo Ito] Northeast Atlantic CoastThis region is a huge urbanized area called Megalopolis, including the six New England states, which boast the longest traditions in the colonial history of the United States, New York, the world's largest city, which is the gateway to the United States and a symbol of prosperity, and Washington, the capital. It stretches about 800 kilometers from north to south, and is an area equivalent to the main part of Honshu, from Tokyo to Onomichi in Hiroshima Prefecture in Japan. The coast facing the Atlantic Ocean is submerged, and the rivers flowing from the Appalachian Mountains form estuaries at their mouths, which became the location of many good ports such as Boston, New York, and Baltimore. Boston, the center of New England, is a port city founded by Puritans in 1630, and the Tea Party, which started the War of Independence, took place here. There are many historical buildings, including Harvard University, the oldest and most prestigious university in the United States, as well as many universities and museums, and the old, calm townscape is reminiscent of Europe. The surrounding area has a cool climate and has been eroded by continental glaciers, making the soil poor, and agriculture is not doing well, but dairy farming is thriving. The coast is one of the four largest fishing grounds in the world, and as the name Cape Cod suggests, fishing for herring and cod is still an important industry. Gloucester and Providence are also famous as fishing ports, and Boston's wharves are lined with restaurants specializing in seafood, and many tourists travel far to visit. Boston also has the oldest history of industrialization in the United States, and textiles, shipbuilding, leather, and machinery have supported the development of the United States, but in recent years, research and development departments have been concentrated in collaboration between universities and companies, and the city is transforming into a brain industrial area. Since the opening of the New York State Barge Canal (Erie Canal) in 1825, New York has become the only waterway leading inland from the Atlantic Ocean across the Appalachian Mountains, and has developed rapidly, replacing Boston as the front door to the United States. The skyscrapers of Manhattan Island are a symbol of the intersection of economic exchange between Europe and the United States, and its role as a focal point of the world economy has not diminished to this day. Philadelphia and Baltimore, which lie to the south, are also cities with ports and industry at their core. It is widely known that the capital, Washington, D.C., was built as a planned political city on the border between the North and South after the Civil War. The entire city can be said to be a park, and it is one of the representative cities designed as a capital. In general, this region is not only the birthplace of the United States, but also the heart of the United States in terms of economy, politics, and culture, and it is no exaggeration to say that everything about the United States is concentrated here. [Tatsuo Ito] Midwest Great Lakes Regionになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Meanwhile, the Southwest Great Lakes to the Upper and Middle Mississippi River are the richest agricultural areas in the United States, known as the Prairie (long grass prairie). The region from Michigan to Wisconsin in the north is slightly cool, with dairy farming mainly through pasture cultivation, with Milwaukee being the center of this. The southwest states of Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska and Kansas are fertile, and the high summer temperatures are suitable for cultivating corn, wheat, soybeans, etc., and beef cattle and pigs are raised using corn as feed. This is a commercial mixed agricultural area called the Corn Belt. Agricultural and livestock products are exported to foreign countries, and Japan is the largest export destination for corn and soybeans. The region's centrality of the region, which is the characteristic of the United States' industry, is Chicago, the third largest city in the United States. The city is also a transportation city connecting the eastern and western areas, and is known as the United States' first in terms of route concentrations in railway and aviation networks, but its population peaked at 3.62 million in 1950, and has continued to decline since then, reaching 2.78 million in 1990. [Tatsuo Ito] Southern Gulf CoastIt is a vast area that covers the southern Atlantic coast, including the Florida Peninsula and the Gulf Coast, covering almost a quarter of the United States. It was once known as the Poor South (poor South), a black labor force, but in recent years it has been reconsidered as a new industrialization ground, and has been renamed "New America," "The Shining South," and "Sunbelt," and has made significant strides. The eastern Atlantic coast of this region was a founding state that took part in the War of Independence, except for Florida, but in the Civil War it supported slavery and opposed the north. Agriculture, which mainly produces cotton and tobacco, is still flourishing on the Piedmont Plateau at the foot of the southern Appalachian mountains. Florida is a state that was acquired from Spain in 1819, and is carried out in warm horticultural farming that makes use of the subtropical climate. The Atlantic coast, where large sandbars are developed, has a wonderful landscape, and the largest cold-relieving areas in the United States have emerged, and the luxurious hotels along the Miami coast are world-famous. The four central states - Kentucky, Tennessee, Alabama and Mississippi, are central to the so-called cotton belt. Alabama and Mississippi are particularly agriculture-dependent regions called the Deep South, along with states such as Arkansas and Louisiana on the opposite banks of the Mississippi River, and discrimination against black people remains strong. Although the South has this tradition, it has been undergoing major changes in recent years. In addition to its development as a tourist resort in Florida, its wide land, abundant labor and warm climate have been reassessed in states such as Georgia, Alabama, Texas, and Oklahoma, and the spread of large-scale air conditioning facilities have led to new industries such as electronic, precision, aviation, and space. Florida and Texas are among the highest population growth rates in the United States, and cities such as Atlanta, Houston, Dallas, and San Antonio have been remarkably concentrated, with the continued re-flow of populations from the north to the south, leading to a much higher position in the United States. In the 2000 census, Texas' population surpassing New York, making it the second largest in the United States after California. [Tatsuo Ito] Western Rocky Mountainsになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The low-rainfall steppe zone at the eastern foothills of the Rocky Mountains is a large-scale corporate grazing zone called the Great Plains, and was once a world where cowboys were active, but helicopters and jeeps are now used, and some have transformed into extremely productive large-scale corporate farms with feed crops and wheat as their main crops, thanks to the spread of snowmelt water-based irrigation facilities. It has a rich mineral resource, and new mines of oil, uranium and non-ferrous metals have also been discovered. State such as Nevada, Arizona and Utah were desert regions with little rain, but they were developed as water use plans such as Hoover Dam progressed. Artificial oasis emerged under dry air and the shining sun. The gambling elegance of Las Vegas and Reno have also been changing the city's states since the 1990s, with high-tech companies and research and development institutes located there. National parks such as Waterton Glacier International Park, Yellowstone, Canyonlands, Capitol Reef, Grand Canyon, Grand Teton, Blythe Canyon and Rocky Mountain, and the natural landscape is one of the most spectacular in the United States. These factors attract people, businesses and factories from cities on the eastern and west coast, leading to rapid growth. [Tatsuo Ito] Western Pacific CoastThe three states, Washington, Oregon, and California, run north and south facing the Pacific Ocean. The climate changes from the mild western coastal ocean to California's bright Mediterranean, but both are comfortable climates. The United States has expanded its territory to the west and west, but it has since developed as a base for expanding into Asia and Oceania. The ports in Seattle, San Francisco and Los Angeles are all US windows open to the Pacific region. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [Tatsuo Ito] history
Over time, a sense of self-government grew, and a sense of belonging to the home country faded, and on the other hand, the Continental Congress was established in 1773, triggered by the Boston Tea Party incident, and the war of independence was fought with the British from 1775 to 1783, and on July 4, 1776, the conference declared independence of 13 states. This day is considered Independence Day, but the United States officially launched and the first President Washington took office in 1789. After independence, the territory was expanded one after another, taking advantage of the chaos of European countries, and in 1846 the ownership of the almost current Mainland Land (mainland), and in 1867 Alaska and Hawaii in 1998 Hawaii in 1998, the 50 states today were promoted to both regions in 1959. The Civil War (1861-1865) was the catalyst for the transition from an agricultural country to an industrial country, but since then, it steadily built its ground as a modern capitalist nation, becoming a victorious nation in both World War I and the Second World War, and during this time it was able to accumulate the world's strongest economic power. After World War II, it had long reigned as the leader of Western countries, but with Japan and European countries reconstructed and developed, and the East-West Cold War ended, and the world entered an era of multipolarity. However, the United States' position in world peace, economy, and culture remains high. [Tatsuo Ito] Politics, diplomacy, defenseCharacteristics of American politicsThe foundation of the American nation is two political ideals: "freedom" and "equality." If we look at the two ideals: freedom to escape oppression and bondage, and equality, which is the maximum average of rights, it may actually be contradictory, but it is no exaggeration to say that the history of creating political conflicts and urgently sought these two ideals is American political history. Democracy is a practical application to the rules of politics in line with these two ideals. Democracy is the fundamental principle of American politics, indicating that political decisions are left in the hands of the people. In American politics, as represented by the town meetings in New England during the colonial era (local autonomy system based on direct democracy), democracy has been institutionalized from an extremely early stage, achieving a high level of political participation by the people. Democracy is an institution where people make political decisions on an equal footing based on their free will. However, if certain forces unite and become the "majority tyranny" described by Alexis de Tocqueville (1805-1859, a French political thinker of the 19th century), then neither freedom nor equality exists. Therefore, a separation of powers in which state power is not concentrated on a particular force is the most emphasized in the American Constitution. State governance is carried out through constitutionalism, and the emphasis is on limiting the state's power over citizens. The two ideals of freedom and equality cannot be achieved through the constitution alone. In America, a diverse nation made up of immigrants, the people are often separated. In order to prevent the majority tyranny and keep people together, the importance of unity (also known as volunteer organizations) by the free will of citizens, such as volunteer organizations, has been placed on the importance of the unity of citizens, represented by volunteer organizations. In addition, the spirit of self-government and the ties that connect people like Christian faith have greatly influenced the principles of behavior of American society. These cultural aspects are also a major feature of American politics. [Maejima Kazuhiro] Dividing powerPolitics distributes limited resources in conflicts of different values. The political system is meticulously created to prevent the majority tyranny where one particular force monopolizes political power in the process of distribution. Compared to a country with a parliamentary cabinet system where legislative and executive branches overlap, the degree of separation of power in the United States is remarkable and is the most important feature of American politics. The people who drafted the Constitution (framers, fathers of the constitutional establishment) shared the awareness that "new federal government should not threaten the freedom of its people." Therefore, the authority given to the central government (federal government) was clearly stated in the constitution (enumerated authority), and the rest were left to the authority of states, which are closer to the people. The enumerated authority includes taxes, the establishment of the army and navy, declaration of war, regulation of commercial transactions between multiple states, and mint the currency. By retaining the powers of states, the federalism (federalism), where the federal government and the state government coexisted. Each state has its own constitution and has its own political system. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. This is characterized by the fact that Congress, the president, and the courts divide their powers and distribute them. Furthermore, since parliament, which has the closest connection to the people, is so susceptible to the influence of "specific forces," they are divided into two chambers of both houses of Senate to avoid excessive concentration of power. They have the same differences in terms of terms, choice, and election periods for which the senators (6 years for office, two from each state), House members (two years for office, number of members is based on the population ratio of each district), presidents (4 years for office, one for indirect election), and federal court judges (with the exception of some cases such as bankruptcy courts, lifetime terms, such as presidential appointments, and approval by the Senate), preventing majority tyranny by not concentrating them at certain times. Furthermore, the constitutional drafters assumed that in the "expansion republic" where the republic expands as the new nation expands, more people will be involved in politics, preventing certain minority groups from controlling politics. The idea is that by accepting diverse people and opinions as the nation develops and expands, power can be avoided from being concentrated on specific groups. Along with pluralism, expanded republic has become the cornerstone of the growth of the American nation. [Maejima Kazuhiro] United States ConstitutionThe United States Constitution was enacted in 1787 and entered into force the following year in 1788, and is the world's oldest written constitution, and is composed of seven articles based on principles such as separation of power, federalism, republicanism, and pluralism, as well as 27 amendments. になったんです。 English: The first thing you can do The Constitution utilizes various experiences during the colonial era when the British government was oppressed and the American Revolution (the War of Independence), and clearly shows what the federal government should not do at the same time as the power given to the federal government. For example, Article 1, Section 9 prohibits the suspension of the privileges of the Habeas Corpus to allow detainees to appear in court to hear the facts and reasons of detention for habeas. In addition, in order to ensure civil liberties, ten articles of amendments guaranteeing human rights, such as "Freedom of Faith, Speech, Publication, and Assembly" (First Amendment), "Prohibition of Unjust Search and Arrest" (Fourth Amendment), and "Right to Trial by Jury" (Sixth and Seventh Amendments), the First to Tenth Amendments are called the "Bill of Rights." The constitution has since been amended along with significant changes in American political history, such as the "Prohibition of Slavery and Trouble" (13th Amendment), the "Suffrage Provisions for Women" (19th Amendment), and the "Prohibition of Three Presidents" (22nd Amendment). Both amendments have been proposed by Houses of Congress with more than two-thirds of the support and ratification of more than three-quarters of states. [Maejima Kazuhiro] CongressThe federal legislature is the legislative body that creates rules (laws) to move politics. There is no dissolution, and the House of Representatives has a fixed term of two years and the Senate has a fixed term of six years. Two senators are elected from 50 states (total of 100). House members are elected in a single-member system based on the number of allocations per district, which is calculated by population ratio of 435 members, but at least one person from each state is elected. The number of allocations is adjusted based on the national census every ten years. The House of Representatives is the Speaker of the House, and is elected from the majority party. Party members will not leave, and will gather their party members together with the second position of the House of Representatives (majority leaders, majority leaders), the main figure of the party they belong to. The Senate president is customarily the Vice President, but he has little or no role to play except that when bill votes reach equal 50-50 in the Senate, the Vice President has the power to decide. The bill is approved (passed) in both Houses of Representatives and Senate, and then passed with the President's signature. Since the bill is rarely passed in the Senate and House of Representatives, it is then referred to the President after passing both Houses of Representatives and House of Representatives, and after meetings of both Houses of Representatives and councils are held and coordinated. The bills are broad and include a variety of policies and budgets. The bills are submitted by federal lawmakers, who represent the people. The president can recommend bills and budget proposals to the parliament, but he cannot submit the bills themselves. Furthermore, in addition to the specific budgets and policies of bills implemented by the president, the parliament also has the function of monitoring how specific policies are being implemented by the president, so the powers of the legislative assembly, which is a very large body of legislative body. In the form, everything is legislative legislation, and this is in contrast to Japan, where the majority are Cabinet laws (mes submitted by the Cabinet). As a result, lawmakers are required to have a deep knowledge of policies and a high ability to create bills, and a large number of parliamentary staff are in charge of creating bills. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Other powers granted to Congress are detailed in Article 1, Section 8 of the Constitution, including taxation, the establishment of the Army and Navy, declarations of war, regulation of commercial transactions between multiple states, and currency mints. Compared to Japan, where the House of Representatives has priority for the prime minister's nomination and budget proposal, the Senate and House of Representatives are basically completely equal in law, and there are often cases where legislation is not progressing due to conflict between the Senate and the House of Representatives. However, both houses are equal in power, but senators with fewer members and longer term office are more well-known and prestigious than members of the House of Representatives. Regarding the difference between the Senate and the House, the Senate has the right to ratify the treaty and the role of approving and denying high-ranking government officials appointed by the president, while the House has the power to precede the budget. The House is representative of small districts, while the Senate is representative of the state. Also, many people have the familiar feelings of "my representative" to the House of Representatives. However, some people have the image that the president and Congress are representatives of special interests, and the difference between the two images of the two: good feelings towards the lawmakers who have been elected by their constituency and bad feelings towards the Congress and the President (hate Washington). Both houses have permanent committees for each policy field, such as agriculture and military, and subcommittees are established for each of the standing committees for detailed policies. Special committees have also been established depending on the policy needs. There are also limited purpose joint committees made up of members from both Houses of Representatives. As of 2011, the Standing Committee was the Senate 16 and the House 20, the Subcommittee was the Senate 74 and the House 94, and the Special Committee was the Senate 4 and the House 2. The key to legislation is committee activities. The number of bills proposed to parliament is enormous, and only bills deemed necessary by the subcommittee are narrowed down to the plenary session. As the chairman and subcommittee chairperson of each committee is monopolized by political parties that hold the majority of the Senate and House of Representatives, the majority party will have a greater intention to decide which bill to be discussed. The leaders of minority parties in the committee are called the lead committee (ranking committee member), and are responsible for negotiating with the chairman, who is primarily the leader of the opposing party. [Maejima Kazuhiro] presidentIn Japan, the US president is recognized as the head of state. The president is also the chief diplomat and the chief of diplomat, and also the commander in chief of the three military, and also the supreme military commander (commander in chief). Congress has the power to decide systems for implementing diplomatic and military policies, including budgetary measures, but the president has the power to enforce actual foreign policies that require prompt response. In the 20th century, when the position of America was dramatically increased, the president's diplomatic and military role became extremely important. The main constitutional role of the president in domestic politics is to head the executive branch, which operates laws created by Congress. The president leads a cabinet made up of the chiefs of 15 ministries. The ministers are appointed by the president. Ministers are prohibited from being held from co-hosted with lawmakers, and are separated as much as possible from parliament based on the principle of separation of power. The president is the only one who is responsible for the administration, and ministers are responsible only to the president in direct assistance. As the powers of the executive have become extremely large in the post-World War II, the powers of the president have become much larger than what the constitutional drafters expected. As the president's powers grow, the importance of the president's legislative recommendations, which demands the president's legislative recommendations in the form of a written teaching that the president desires to create the laws he desires. However, in addition to the constitutional separation of powers, such as separation of powers and federalism, and the binding of bills within political parties is weak, the laws the president wants are not necessarily well legislated. Although the president has the right to sign or veto the bill approved by Congress, the president himself cannot formally submit the bill itself, and neither the cabinet composed of the president and chief ministers of major ministries, nor the bureaucratic organization, which is the practical organisation of the president's administrative powers, he is able to propose the bill to Congress in a way like a textbook, but the actual deliberations are left in the hands of the parliament, and the legislative process can result in a bill that is very different from the president's intentions. There may be cases where the treaty is not ratified due to opposition from the Senate, such as the League of Nations under the Wilson administration and the Kyoto Protocol under the Clinton administration, which could lead to international issues. There are also executive orders, but this is only part of the president's administrative management to interpret and implement laws decided by Congress, and it is very little binding compared to the laws. If the administration changes, past executive orders will be rewritten. 近年では、大統領がテレビなどのメディアを通じて国民に直接に訴えて世論の支持を取り付けることで議会を動かすゴーイング・パブリック戦略が頻繁に使われている。さらにテレビへの頻繁な出演を背景にして、国民統合の象徴、市民宗教の司祭としての大統領の役割も注目されている。たとえば、大災害などが起こった場合などに大統領が国民に向ける癒(いや)しのことばは宗教における司祭のことばそのものであり、政治的役割を超えて大統領の社会文化的な役割も重視されるようになっている。 [前嶋和弘] Executive branch行政府は行政府の長(チーフ・エグゼクティブ)である大統領の行うさまざまな行政政策の実務組織である。行政府は軍を含めると計400万人もの職員が働いている巨大な官僚組織である。行政府は大別して15の省、独立諸機関、大統領行政府の3部門に分かれている。15の省は農務、商務、国防、教育、エネルギー、保健社会福祉、国土安全保障、住宅・都市開発、内務、司法、労働、国務、運輸、財務、退役軍人である。 各省の長官は大統領によって任命され、議会上院によって承認される。大統領、副大統領とこの15省の長官で内閣を構成する。しかし、長官はsecretary(元の意味は「秘書」)としてあくまでも大統領を直接補佐する役割を担っており、首相を核とした内閣そのものに行政権がある日本とは対照的である。 独立諸機関は省に比べ比較的規模が小さい行政機関で郵政公社、連邦預金保険公社、航空宇宙局、中小企業庁、環境保護局などがあり、いずれもその長官は大統領によって任命、議会上院によって承認され、大統領の監督の下に置かれている。 大統領行政府は、大統領を補佐するために大統領直結の特定政策分野の行政機関や大統領への助言・諮問さらには行政府全体の監督や統制の機能を持った諸機関を総称するもので、1939年に大統領F・D・ルーズベルトにより創設された。外交政策決定の中枢である国家安全保障会議や大統領の経済財政政策の審議や助言を行う経済諮問委員会と国家経済会議、大統領が予算をうまく管理し行政府全体を統括するための行政予算管理局、対外通商業務を担う合衆国通商代表部などの機関がある。また、大統領にもっとも近い組織で大統領の手足となって働くホワイトハウス・オフィスも大統領行政府の一部である。大統領の仕事の増大と複雑化に伴って規模が拡大し続けている。 [前嶋和弘] courtアメリカの司法システムは連邦裁判所と州裁判所の二本立ての系列があり、それぞれが独自に完結している。連邦裁判所で扱われる裁判は憲法解釈のほか、連邦法の違反事件や州を超える事件に限られている。州法によって争われる事件は州の最高裁判所の判断が最終的なものであり、連邦裁判所へ控訴することはできない。 州裁判所では基本的に刑事事件の大多数、交通事故、遺言、軽犯罪などの裁判が行われる。州裁判所の裁判官の多くは選挙で選出されており、人事面でも民主的に運営されているが、裁判官立候補者は集票組織を有する政党と関係をもつことも多く、政治的党派性がみられるのが大きな特徴である。裁判では原則として陪審制がとられており、一般市民が陪審員として無作為抽出されて事実問題の認定を担当するのも民主的な裁判を象徴している。陪審には被疑者を起訴すべきか否かを判断する大陪審と陪審員が裁判に参加して被告の罪の有無を判定する小陪審とがある。 連邦裁判所は、全国93の連邦地方裁判所と12の連邦控訴裁判所および最高裁判所からなっている。連邦裁判所が注目されるのは憲法の解釈である。連邦裁判所は、議会がつくった法律、大統領の法解釈と運用について憲法に照らし合わせてチェックする。この連邦裁判所の権限を司法審査とよび、日本の違憲立法審査に相当する。問題がある場合は立法を無効にすることや大統領の行政措置を止めることができる。 ただし、憲法の解釈には判事のイデオロギーによって幅があるのもアメリカの司法の特徴である。そのため、最高裁を中心に判決には強い政治性があり、判決そのものが政治を揺るがしてきたこともある。黒人奴隷の憲法上の地位を争い、南北戦争につながっていったドレッド・スコット事件判決(1857)や、南部諸州の人種分離法に違憲判決を下し、公民権法制定への起爆剤となったブラウン対教育委員会判決(1954)、人工妊娠中絶を合法化させたロウ対ウエイド判決(1973)など枚挙にいとまがない。 連邦裁判所裁判官は大統領によって任命される。とくに最高裁の場合は大統領がどのような政治的立場の人物を任命するのかが大きな政治的な争点となり、任命承認を行う議会上院との駆け引きが大きなニュースとなる。アール・ウォーレンEarl Warren(1891―1974。在任期間1953~1969)が最高裁長官を務めた1950年代から1960年代にかけては最高裁の9人の裁判官の多くが政治的にリベラル派で、さまざまな判決で連邦政府による積極的な社会改革を先導していった。一方、1980年代後半以降最高裁長官をウィリアム・レンキストWilliam Rehnquist(在任期間1986~2005)、ジョン・ロバーツJohn Roberts(在任期間2005~ )が務めるようになると保守派の裁判官の数がしだいに増え、リベラル派と保守派の裁判官の数が拮抗しながらも保守的な判決が増えるようになってきた。 高度に政治的な判断を要する争点について司法独自の判断を控える日本などと比較するとアメリカの裁判所は司法積極主義であり、国の政策や社会的に重要な争点について積極的な裁定者となる傾向がある。そのため、公民権運動に代表されるように市民運動などの政治活動の第一歩として裁判闘争戦術が採用されてきた。 アメリカの政治制度は権力の分立を前提にしており、司法の独立が強調されるため連邦裁判官は終身の任期(原則として引退するまでその地位にとどまる)と優れた年金制度で身分が保障されている(州裁判官の場合は任期制のところが大多数である)。また、連邦議会議員、大統領が国民によって選ばれているのに対して連邦裁判所の裁判官は任命制であるため、民主的な国民の意思を司法が破棄することにもつながりかねない。このような背景のなか、アメリカの政治過程では司法の圧政をめぐる議論も活発である。 [前嶋和弘] Political partiesアメリカは、建国してまもない18世紀末から現在まで二つの巨大政党(共和党、民主党)が政治の中心にある二大政党制である。先進民主主義諸国において二大政党制は必ずしも多くなく、しかも長期にわたって同じ二つの巨大政党による二大政党制が続くのは珍しい。他の政党は総称して第三政党とよばれるが、基本的にはきわめて弱小でアメリカ国民にとってもなじみがない。 合衆国憲法には政党についての記載がない。これは政治的な権力を独占する特定の勢力を徹底的に排除することが憲法起草者たちの願いであり、政党は特定勢力と考えられたためである。 アメリカの政党には他国の政党にはみられない特徴がある。その一つが、党首にあたる役職が存在しないことである。共和党と民主党の全国委員会には委員長職が置かれているが事務局長的な役割である。政党組織は分権的で、全国委員会は50州の党委員会の連合体的な要素が強い。党員資格もあいまいで有権者登録や予備選挙の登録の際に党名を記入する欄があり、そこに記入すれば党員となる。党費納入や活動への参加義務もないに等しく、党員というよりも党支持者に近い感覚である。 アメリカの政党の最大の特徴は、議会での党としての規律が緩やかなことである。ヨーロッパなどの政党に比べて政党は結束力が弱く、議会内の同じ党の議員でも政策に対する立場の差が大きい。法案に対する党議拘束は基本的にはなく、大統領と議会多数派が同じ政党でも政策に対する立場が異なることも多く、政党の議会内執行部(院内総務、院内幹事など。下院の多数派の場合下院議長も含む)の方針に抵抗する議員も少なくない。 政党の規律が緩やかで党議拘束がないことから、連邦議会では政党の違いを超えた連携がかつては頻繁に行われた。たとえば、同じ党内や対立党の議員に対して法案成立への協力を約束するかわりに、自分が立法化したい法案に協力させるログローリング(票の貸し借り)も一般的であった。しかし、1970年代から南部での共和党勢力の拡大、党内の組織改革が行われたことなどの影響によって各政党内でのイデオロギー的な結束が強まったことや民主・共和両党間のイデオロギー差の拡大などから、政党の党議拘束もしだいに強化されてきている。 民主・共和両党の対立が進むなか、大統領を擁する政党と議会の上下院のどちらか(あるいは両方)の多数党が異なる状況が恒常化し、法案の立法化がまったく進まずに政策形成のグリッドロック(行き詰まり)化をもたらす政治システム上の問題もしばしば起きている。 [前嶋和弘] Voters基本的に18歳以上のアメリカ国籍を有するすべての国民に選挙権が与えられている。南北戦争(1861~1865)後の奴隷解放のあとでも、投票税や識字テストのようなアフリカ系住民を投票から実質的に排除する通称ジム・クロウ法が南部を中心に長年存在していた。1950年代から1960年代の公民権運動で人種差別的な措置は撤廃されたが、アフリカ系住民やラテン系住民などの人種的マイノリティの投票率は白人に比べて低くなっている。 他の先進民主主義国と同じように、アメリカでも政党は有権者にとっては政策を示すレッテルである。ただ、二大政党制が定着しているため、政党というレッテルに対する愛着度は有権者の政治参加の度合いやイデオロギーなどを示す指標となっている。出身地、職業、年収、人種・エスニシティ(民族性)など、有権者の属性そのものも政党への支持態度(政党帰属性)をみれば明らかになる。アメリカの選挙の場合、民主・共和いずれかの党への帰属性が高ければ高いほど投票に行く確率が高いだけでなく、政治に対する知識や関心も高い。また、共和・民主いずれかの党に強い政党帰属性をもっている人は、ほぼ自分の帰属性の高い政党に投票するため、政党帰属性をみれば選挙の大勢が予測できる。これが民主・共和両党にとっては自分の党を支えるコアとなる層である。このコア層以外の中道を押さえるのが選挙を制する方程式である。 近年、アメリカでも無党派層が増えており、中道は有権者のほぼ3割を占めている。政治的な傾向をさらに分析すると、共和党(保守)寄り中道、中道のなかの中道、民主党寄り中道の三つに分かれている(選挙区によって割合は異なっている)。共和党寄り中道は基本的に共和党、民主党寄り中道は基本的に民主党にそれぞれ投票する確率が高い。一方、中道のなかの中道は無関心層にあたり棄権する確率が高い。 [前嶋和弘] Interest Groupsアメリカの政治過程で特徴的なものに利益団体の存在があり、アメリカ政治を知るうえで重要である。国是である多元主義のなかで、利益団体を通じて自分たちの利益を確保しようと訴えることは政策過程に必要となる民主主義的な政治参加の手法である。 利益団体は労働団体(労働組合)、公共利益団体、イデオロギー団体のほかに特定の争点を追うシングルイシュー団体、企業を母体とする業界団体の一部がなっているケースなどもあり多様である。公共利益団体とは環境保護団体のような広く多くの人の利益を実現しようとする団体である。 利益団体のなかには、共和党支持、民主党支持など党派性をもつものが多い。共和党支持者が参加する利益団体の代表的な例としては、産業界の意見を代弁するアメリカ商工会議所、ビジネス円卓会議などの企業を母体とする団体のほか、キリスト教保守派のイデオロギー団体であるキリスト教徒連合、シングルイシュー団体では銃規制に反対する全米ライフル協会や減税・政府支出の健全化と納税者の権利擁護を主張する全米納税者連盟などがある。民主党支持者が参加する利益団体には労働組合のAFL-CIO(労働総同盟産別会議)やシエラクラブに代表される環境保護団体、リベラル政策を支持する市民団体・人権団体であるACLU(アメリカ市民自由連合)、人種・エスニック集団を母体とする団体NAACP(全米黒人地位向上協会)、消費者保護の市民団体パブリック・シティズンなどが含まれている。 利益団体については、多元主義を体現し、国民の政治参加を促すという政治的理想の追求とする考えがある一方で、特定の利益団体の力が強くなりすぎてグループ間の自由で民主主義的な競争が成立しにくい状況になっているという見方もある。利益団体は議員や行政府の関係者を取り込んで三者による強固な利益連合である鉄の三角形を形成し、閉鎖的な下位政府として政策に大きな影響力を行使しているという見方がその代表的なものである。利益団体のなかには議会対策の専門家であるロビイストに活動を代行させているところもあり、金権政治の温床となっているという指摘もある。多額の献金や過度なロビー活動を続け、民主主義的な政治プロセスをゆがめる団体を特殊利益団体と否定的によぶことが定着しつつある。 鉄の三角形が排他的な政策過程モデルであるのに対して、実際の政策形成の過程はさらに柔軟であり、利益団体を含む特定の政策・争点で知識や情熱をもった人々が相互に結びつくことで政策に対する争点ネットワークがつくられ、政策を形成していくとする見方もある。 [前嶋和弘] 州政府・地方政府アメリカ政治の特徴の一つが、連邦主義に基づいた州の権限の強さである。連邦を構成する州がそれぞれ主権と憲法をもっており、州が主権の一部を連邦政府に移譲する形で連邦と州の関係が築かれている。連邦政府の権限は防衛、関税、通商など憲法の条文に列挙された事項(列挙権限)に限られ、それ以外の部分はすべて州および国民に留保されるのがアメリカの連邦制の基本となっている。 さらに、州政府(地方)内でも権力を分散させ、州議会(立法府)、州知事(行政府)、州裁判所(司法)が互いにチェック・アンド・バランスの関係にある。各州政府は、連邦政府とはまったく別の政治的な力学で動いている独立国のようなものである。 このように、連邦政府-州政府という2層構造のなか、州政府の下部にあるのが地方政府である。地方政府はカウンティ(郡。ルイジアナ州ではパリッシュ)、ミュニシパリティ(市)が中心であり、そのほか特定の目的のための特別区や局もある。カウンティは州の行政区分であり、出先機関という色彩が強い。ミュニシパリティは憲章を採択し、自治権が認められている。 連邦政府と州政府がすみ分ける連邦主義に基づいて、建国から20世紀初めごろまでは政策そのものの大半が州政府によって行われてきた。連邦裁判所も19世紀前半には州の権限を強調する立場(州権論)をとっていたが、19世紀末ごろから連邦政府の権限を拡大解釈する傾向が目だってきた。20世紀の二度にわたる世界大戦と大恐慌が連邦政府の権限を強化する決定的契機になったことはいうまでもない。1933年のルーズベルト大統領のニューディール政策以降は福祉国家化の流れに従って、連邦政府が積極的な政策上のリーダーシップをとることが増え、連邦政府の権限が拡大し、それに伴う人的資源や予算も飛躍的に増大している。州と連邦政府のバランスが変わっていくなか、連邦政府の肥大化を非難する意見も保守派を中心に根強い。 連邦政府はさまざまな政策決定を行うが、たとえば福祉政策などでは政策を直接担当する連邦政府の機関は限られているため、実行部隊としての州政府や地方政府の協力が必要である。連邦と州、そして地方政府が協力しながら行う協力的連邦制がアメリカの行政機能の特徴となっている。 3割自治とよばれるように財政的に国に保護されている日本の地方自治体とは対照的に、アメリカの州は財政的に国から独立している。その分、財源確保や効率的な行政サービスは自治体にとって死活問題であり、各種の行政改革が導入されている。連邦での政策革新のもととなるアイデアが、州政府や都市で行われた政策革新に起源を発するケースも多い。有力州の知事のなかから正副大統領候補が頻繁に生まれることを考えても、州の影響力は大きい。 [前嶋和弘] 政治とメディアアメリカ政治では「メディアを中心に動く政治media-centered politics」という概念が定着している。ほかの先進国と比べても、アメリカの場合は共生関係といえるほど政治とメディアとの関係は密接である。大統領府、議会、利益団体、シンクタンクなどの政治アクター(政治活動を行う機関・団体・人)が広報戦略をメディアに依存する度合いが大きく、メディアを使いこなす能力はもっとも重要な資質の一つとなっている。メディアを介して自分の主張の正当性をかちとり、政策を動かすことが官僚や議員だけでなく、政治コンサルタントやシンクタンク研究員などの政策関係者の仕事の中心とさえなっている。 政治でのマス・メディアの役割は、大統領、議会などの政治アクターや国民に対して政治情報を提供すること、つまり政治インフラにほかならず、新聞、ラジオ、テレビのネットワークニュースが客観的な情報提供の場となってきた。 一方で、政治とメディアは強い共生関係を生み出してきた。閣僚や議員だけでなく、シンクタンク、利益団体などの政治アクターはメディアにとって情報提供者として必要不可欠であり、各アクターも政策形成のために意図的にメディアを使い、政敵の動きを牽制(けんせい)し、世論を動かそうとすることは常套(じょうとう)手段となっている。メディアと政治の共生関係が深まるなかで、しだいにメディアが政治のインフラから政治の主役として機能するケースが増えてきた。メディアが明確に政治イデオロギーを表明し、特定の政治アクターに焦点をあてて報じることによって、メディアはインフラであることを超え、主体的な意志をもった政治アクターの一つとなっているという見方である。各政治アクターは自分の政治色にあったメディアと親和的な関係になり、メディアは特定の政治的立場からの報道を続けて政策に影響を与えていく。アクターとしてのメディアが使う評論家は客観的なコメンテーターではなく、特定の政治イデオロギーの立場から発言する特定メディアの代弁者となっている。ただ、あくまでも政治のインフラとしての立場にとどまろうとするメディアも健在であり、新聞や地上波テレビネットワークの多くがジャーナリズムの基本である客観性を希求し、異なった政治的意見に対してはバランスを配慮した報道を心がけている。 2011年時点でアメリカのマス・メディアを総合的にみれば、政治インフラでありつつ、アクターにもなっているメディアも存在しており、それらはアメリカ政治のなかのトリックスター(ひっかき回し役)的な存在になっている。インターネットの爆発的な普及のなかで、ブログなどを通じて誰もが政治メディアになれる時代を迎え、トリックスター的なメディアの増大は顕著になってくるとみられている。 [前嶋和弘] 保守とリベラルアメリカのイデオロギー対立は、自由主義対社会主義のような体制イデオロギー間の対立ではない。歴史的にアメリカでは固定した階級社会がなく、経済体質として慢性的に労働力不足であり、賃金も比較的高かったため、労働者階級の不満はガス抜きされてきた。土地が広く、労働者が自営農民になることも困難ではなかった。また選挙権も早期に普及したため、社会主義運動や労働運動、普通選挙権獲得運動が一体となることもほとんどなく、社会主義運動の盛り上がりは欠けていた。 アメリカはあくまでも自由主義が支配的な社会であるため、伝統や自由主義的競争を維持しようとする保守派と自由主義体制内で可能な政府による積極的な社会改革を志向するリベラル派の対立が軸となってきた。 リベラル(自由主義)とはもともと「政府が個人を抑圧しない」という意味であったが、現在では平等主義的な改革思想や運動をさしている。具体的には国民の平等や自由を政府のリーダーシップで達成することを意味している。たとえば貧困や社会福祉などの社会的問題に対しては政府の何らかの政策で解決しようとすることに賛同し、環境問題では政府による規制を強化することで公害の除去・予防や環境保全を進めようとする考えを支持している。アメリカのリベラル派はヨーロッパや日本の社会民主主義政党よりも中道寄りで、社会主義や共産主義の革命を目ざしているわけではなく、あくまでも自由競争を重視した市場経済のなかでのリベラルである。ルーズベルト大統領のニューディール政策が修正資本主義とよばれており、それを象徴している。 社会問題については、伝統にとらわれない価値観(社会的リベラル)をさす。キリスト教徒の多いアメリカで大きな社会問題となっている妊娠中絶については容認の立場(女性の選択を重視するという意味からプロ・チョイス派とよばれる)がリベラルの見方である。アメリカでは結婚を男女のものと信じる敬虔(けいけん)なキリスト教徒がきわめて多いため、同性愛者の権利そのものが社会的な議論となっているが、同性愛者の権利についても擁護するのがリベラル派である。社会の少数派を重視し、人種やエスニシティ間の平等に敏感なのもリベラル派の特徴である。 一方、同じ「自由」ということばから生まれた自由放任主義(リバタリアニズム)は現代のリベラルとは対極にある考え方で、保守派の中心的な政治思想である。リバタリアニズムとは徹底した自由競争を重視し、レッセ・フェール(自由放任)を目ざすものである。リバタリアニズムまではいかないまでも「政府の経済活動や私生活への干渉をできるだけ少なくすべきである」というのが保守派の基本的な政治的立場である。リベラル派が訴える政府の積極的なリーダーシップによる政策は、保守にとっては大きな政府にすぎない。また、社会問題については、伝統的価値を重視する社会的保守であり、具体的にはキリスト教的な倫理を重視する社会生活を意味している。 ここにあげたリベラルのイデオロギーは、現在では民主党が重視する考え方であり、保守のイデオロギーは共和党が重視する立場である。そのためリベラル派の支持政党は民主党となり、保守派の支持政党は共和党となるが、南部は伝統的に保守的な民主党支持者が多かったため、支持政党とイデオロギーの関係は完全に一致はしていない。また、高所得者の場合は共和党支持が多いが、教員、政府職員などの比較的所得が高いホワイトカラーには民主党支持者が多い。低中所得者層にはブルーカラーの労組関係者やアフリカ系、ラテン系住民などが含まれており、リベラル派として所得再分配的な政策を志向する民主党支持者が多いが、南部を中心に敬虔なプロテスタント諸派に属する低中所得者層は保守的な人たちも多く、共和党支持者も多い。 カトリックやユダヤ系などアメリカでは少数派の宗教信者にリベラル派が多いほか、地域的には北東部に伝統的にリベラルが多い。少数派の権利を擁護するため、前述のマイノリティ人種のほか、ゲイ、レズビアン、貧困層が集まる都市部住民にリベラル派が多い。保守派は南部や中西部に多く、宗教的にはプロテスタント、人種は白人が多い。 2010年の中間選挙で一躍脚光を浴びたティーパーティ運動(政府支出の増大に反対し、小さな政府を唱える保守派の政治運動)は、典型的な保守のポピュリスト(大衆迎合主義者)運動で、草の根運動として大きな輪に拡大した。しかし、もっとも代表的な主張の「小さな政府」(減税と財政規律)は、景気低迷で税収が減少するなか減税は困難であり、実質的な戦時下(イラク、アフガン戦争の継続。2011年8月時点)で軍事費がかさむため緊縮財政は理論的にかなりむずかしいとされている。そのため、ティーパーティの運動は論理性に欠けているとして穏健派保守層からやや距離を置かれている。 [前嶋和弘] 外交政策の決定大統領は、上院の助言に従い、その同意を得て、条約を締結する権限をもつ。しかし条約締結の過程において、交渉と批准とは区別されており、上院が関与するのは批准についてだけであって、交渉はもっぱら行政府により処理されるべきものとされている。条約の批准は出席議員の3分の2の同意を必要とする。条約の批准同意権を上院だけに与え、しかも3分の2の条件付き多数決としたのは、憲法制定当時の政治状況によるものであるが、今日では、上下両院の承認と単純多数決が望ましいとする意見も強い。 行政府において外交を担当する部門は国務省である。国務長官には政治的に第一級の人物が任命されることが多く、伝統的に国務省は高い威信を誇ってきた。しかし最近では、国務省の地位はむしろ低下しており、重要な政策決定は、大統領府のなかに置かれている国家安全保障会議で行われることが多い。国家安全保障会議は、大統領、副大統領、国防・国務両長官によって構成され、国家の安全保障にかかわる外交政策と軍事政策全般について大統領の政策決定を補佐する。必要に応じて、統合参謀本部議長や中央情報局(CIA)長官も列席する。事務局長は国家安全保障担当の大統領補佐官で、対外政策に関する助言者として大きな役割を果たすことが多い。 [阿部 齊] 外交政策の伝統アメリカの外交政策の伝統的特質は、イデオロギー第一主義である。西欧諸国の外交が基本的に国益優先の立場をとってきたのに対して、アメリカ外交はなによりもまずイデオロギーを優先させる立場をとってきた。それは、アメリカが特定の理念、すなわち「生命・自由および幸福の追求」を確保するためにつくられたからである。これらの価値を重視するのは自由主義にほかならないから、アメリカは自由主義を実現するためにつくられた国家だといってよく、対外政策においてもアメリカ自由主義が唯一のイデオロギー的基準として作用する。こうした特性は、具体的には孤立主義と膨張主義としてアメリカの対外政策を支配した。孤立主義は、アメリカと西欧諸国の相互不介入をもってアメリカ外交の原則とする立場であり、アメリカを西欧国際社会から孤立させようとする立場である。他方、膨張主義は、南北両アメリカおよびアジアにアメリカが無限に膨張することの必然性を是認する立場である。この孤立と膨張という一見矛盾する二つの原則は、いずれもアメリカの唯一のイデオロギーである自由主義と関連をもつ。 まず孤立主義についていえば、アメリカの自由主義的同質性は、異質で多様なイデオロギーに対して嫌悪感をもつ。アメリカ自由主義は、自己の純粋性を保つためにヨーロッパからの孤立を図るのである。また膨張主義についていえば、アメリカ自由主義は、その普遍性の確信のゆえに、発展途上にあるラテンアメリカやアジアに対しては無限の適用可能性をみいだすことになる。このように、孤立主義も膨張主義もイデオロギー第一主義の具体的な現れであるが、いずれも対等な交渉相手を想定していないという点で、西欧的外交の標準的な形式からは逸脱している。今日では、イデオロギー第一主義の徹底的な追求は不可能であるが、それが完全に払拭(ふっしょく)されたとはいえない。 [阿部 齊] Defense policy1947年の国家安全保障法により、陸海空三軍の統合が行われ、陸海空各省の上に国防省(通称ペンタゴン)が置かれて、文官の国防長官が大統領を補佐し、三軍を指揮統轄することになった。同時に設置された統合参謀本部は、陸軍参謀総長、海軍作戦部長、空軍参謀総長、海兵隊司令官と、それを統轄する統合参謀本部議長によって構成され、作戦面で大統領・国防長官を補佐する。大統領―国防長官―各軍司令官の文官支配が確立されている。 2005年時点の戦略核戦力は、ICBM(大陸間弾道ミサイル)550基、SLBM(潜水艦発射ミサイル)432基、弾道ミサイル搭載原子力潜水艦18隻、戦略爆撃機114機となっている。通常戦力は、陸上戦力が陸軍約49万、海兵隊約18万、海上戦力が潜水艦70隻を含む艦艇1120隻(約577万トン)、航空戦力は、空軍・海軍・海兵隊をあわせて3450機を擁している。 アメリカの伝統は、戦時と平時を厳格に区別し、軍事力の行使を、道徳的な正当性を付与しうる場合に限ることであった。軍事力の行使には慎重であるが、いったん行使されれば、敵国が無条件に降伏するまで戦うことになる。西欧諸国のごとく、平時においても外交交渉と軍事力行使とを代替的に併用することは、アメリカの伝統にはなかった。しかし今日では、国際環境の変化によって、軍事力を政治的手段として日常的に使用する方向に変わりつつある。 [阿部 齊] Economy and Industryアメリカ経済発展の基礎独立当時のアメリカは、大陸の東の端に散在する小さな農村の連合体で、ヨーロッパ経済の辺境であった。商業は内陸との取引よりもヨーロッパとの取引のほうが大きく、輸出品は農産物であり、工業品はほとんど輸入に頼っていた。しかしその後のアメリカ経済の発展は目覚ましかった。19世紀なかばにはアメリカは世界最大の農業国になり、19世紀末には世界最大の工業国となった。そして20世紀なかばには、第二次世界大戦後の特殊事情もあったが、世界の総生産の半分以上をアメリカが生産したのである。その後アメリカ経済の比重は低下して1980年には世界の総生産の21.5%となったが、それでも今日アメリカが世界最大の経済国であることに変わりはない。このようなアメリカ経済の発展は、なににもまして経済の拡大が長期にわたって着実に続いたことによって達成された。 1800年ごろのアメリカの国民総生産がどれほどであったかは、推定値に差があって確定していない。しかしおおむね、1952年価格で計って、1人当り250~300ドルの範囲であったと考えられる。この数値はその時代のヨーロッパ先進国に比べて遜色(そんしょく)がない。それは主としてアメリカが広大で肥沃(ひよく)な土地に恵まれていたためであったと思われる。1800年から1830年代の終わりごろまで、アメリカの1人当り国民総生産の伸びは低く、1%を下回る水準であった。しかし、1840年代からアメリカ経済の成長率は高まり、平均すると1人当り国民総生産は年率1.64%、つまり43年ごとに2倍になる速度で増加した。そして1960年の1人当り実質国民総生産は1830年代の約7倍となった。このような経済の発展は、経済に対する投入資源の増加と技術の進歩によって達成された。アメリカに豊かに存在した土地と天然資源、急速な人口の伸びは投入資源の増加をもたらしたが、経済成長に対する貢献度からいえば、科学知識の進歩、経営方法の改善、労働者の教育水準向上などを含めた技術進歩のほうが大きかった。 [榊原胖夫] 1960年代以降の概観1960年代のアメリカ経済は未曾有(みぞう)の繁栄を記録した。年平均成長率は4.2%、失業率の平均は4.8%で、生産性向上率、実質賃金の伸び、物価の安定など、どの指標をとってみても歴史上かつてなかった繁栄の10年であった。しかし1970年代に入ると事情は一変した。1973年には強い米ドルに依存して成り立ってきた固定為替(かわせ)相場制の維持が困難になり、多くの国が変動相場制に移行、戦後の世界経済を支えてきたアメリカ体制が崩壊したとささやかれた。同年には石油危機が発生し、資源制約が一挙に顕在化した。各国とも物価上昇に悩み、金融を引き締めた。経済は不況に陥ったが物価は安定せず、高い失業率とインフレが共存する「スタグフレーション」になった。その調整が十分に進まないまま1979年に第二次石油危機が発生した。1970年代アメリカ経済の年平均成長率は3.2%、失業率は6.2%、実質賃金はまったく上昇せず、消費者物価の年平均上昇率は7.1%になった。 1980年初めにアメリカ経済は不況に陥った。1983年から実質国内総生産は回復に向かったが、1991年にはふたたび不況にみまわれた。1980年から1991年までの実質成長率は年平均2.3%、失業率は7.1%と1970年代より悪化し、消費者物価は1980年を100とすると165となり、多少とも鎮静化したが、生産性の伸びは、1960年代年平均3.2%、1970年代年平均2.1%、1980~1991年は1.4%と低下している。不況のため新規投資が減少したこと、新規投資は生産を増加させる方向に向けられず、公害対策など生活の質の向上に向けられたことがその主たる原因であった。 1970年から1991年までの長い不況期に、アメリカ経済は大胆な改革を実行し、1992年以降の息の長い上昇の基礎を築いた。1970年代初めから自動車、金属製品などの伝統的な産業は相対的に衰退し、コンピュータ、テレコミュニケーション、航空などの新しい産業が拡大した。新しい産業の勃興(ぼっこう)は第二次産業革命といえるほど急激で、またその影響が及ぶ範囲は広かった。アメリカ経済は「産業革命」にすばやく順応し、政府も旧秩序を守ろうとはせず、むしろ積極的に変化に対応した。何よりもまず規制緩和と競争の促進が必要であった。規制緩和への努力は第一次石油危機直後、ニクソンのあとを継いだフォード大統領のときに始まった。フォードはインフレの原因の一つに不必要な規制があると考え、交通を中心に既得権益への挑戦を始めた。フォードのあとの歴代大統領も民主党、共和党の別なく、小さな政府、規制撤廃、競争の重視という点では一致していた。 1981年に大統領に就任したレーガンは、インフレと失業を同時に低下させアメリカ経済の再生を図ることを目的として、歳出削減、減税、規制緩和、安定的金融政策を四本柱とする経済再建計画を発表した。再建計画は従来の短期的な総需要管理政策にかわって長期的な供給政策を重視したもので、理論的にも政策的にも大胆な実験であった。これらの政策のうち、減税、規制緩和、安定的金融政策は実行に移されたが、歳出削減は思うように進まず、その結果生じた財政赤字の増大は、金融市場を圧迫して高金利をもたらした。そのため各国とも利子率引下げなどの景気刺激策をとることができず、アメリカは世界の不景気を永続させているとして非難の的となった。国際収支の面でアメリカは、1976年以降赤字の傾向が定着し、金額的にもしだいに大きくなった。そのため1980年代から1990年代初めには、財政の赤字とあわせて、双子の赤字とよばれた。貿易の不均衡に加えて雇用不安が高まったことから保護主義が台頭した。とくに自動車や電気製品などアメリカの主力製品と競合して輸出を急増させた日本に対する非難が高まった。 しかし1990年代に入ると、財政赤字は歳出削減努力、ソ連の崩壊による軍事支出の減少と好景気による歳入の増加などによって徐々に縮小し、1997年にひとまず均衡が達成された。また貿易では雇用不安の消滅とともに保護主義の動きも静まり、むしろ外国の門戸開放、不公正な貿易慣行是正などによる輸出の増大を目ざすようになった。しかし国際収支の均衡にはいましばらく時間がかかりそうである。 1970年代以降の技術革新は情報の移動を容易にするものが多く、経済の国際化を促す要因となった。地球上に複数の生産拠点をもつ企業は多国籍企業とよばれたが、今日では資本も経営も労働も多国籍化した「世界企業」が増加している。 1992年以降アメリカ経済は継続的な成長を遂げ始めた。失業率は完全雇用水準に近くなり、生産性も上昇傾向をたどり、物価も安定した。1993年にはクリントンが大統領に就任した。クリントンはレーガン、G・H・W・ブッシュとは違い、民主党であった。しかしその経済運営は前政権と大きく異ならず、その意味で民主党と共和党の経済政策における差は縮まった。2001年には、ふたたび共和党のG・W・ブッシュが大統領に就任、ITバブル崩壊や同時多発テロの影響で、景気後退の局面をむかえたが、その後は緩やかな回復が続いた。しかしブッシュ政権期の後半には、上昇を続けていた住宅価格が2006年を境に鈍化、低所得者向けの住宅ローンであるサブプライムローンの延滞が増加した。このローンを証券化した金融商品が世界中に販売されていたこともあり国内外経済への影響は大きく、アメリカのみならず諸外国の景気を後退させる原因となった。アメリカ国内においては、2008年の大手投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻(はたん)、大手保険会社AIGへの公的資金注入、また基幹産業である自動車産業の経営不振等、サブプライムローン問題は深刻な影響を及ぼした。これらへの経済対策は2009年発足のオバマ政権に与えられた大きな課題の一つとなった。 [榊原胖夫] 資源と労働アメリカの地下資源は豊かで、東のアパラチア山系では石炭、鉄鉱石、ボーキサイト、銅などが生産され、西のロッキー山脈の両側からテキサスにかけては石油や天然ガスが生産されている。アメリカの石炭産出量は世界の約26%(2001)、石油は8%(2004)、天然ガス21%(2002)、銅鉱石8%(2003)などとなっている。アメリカの鉱業生産額は相対的に低下しているが、それは資源が枯渇(こかつ)したというよりも、他国の安い製品を輸入しているからである。たとえば、1970年代に入ってアメリカの石油輸入が急増した。アメリカで産出される石油は、中近東その他の新興産油国に比べると産出コストが高くなったためである。アメリカの1人当りエネルギー消費量は、アラブ首長国連邦とカタールを除けば、世界でもっとも多く、エネルギー輸入量も世界でもっとも大きい。 1995年(かっこ内は2003年の数値)のアメリカの労働力人口(軍関係を除く)は1億3230万(1億4651万)人であった。労働力率(人口に占める労働参加者の割合)は長期的に上昇しつつあり、1970年の60.4%から1995年には66.6(66.2)%になっている。労働力率の上昇は女性の労働参加が進んだためで、1970年の男性の労働力率は79.9%、女性は43.3%であったが、1995年には男性75.0(73.5)%、女性58.9(59.5)%になっている。朝鮮戦争後のベビーブーム世代が成年に達した1970年代を過ぎると、増加率は安定し、労働の質も向上したといわれている。失業率は1980年代初めの不況時に9%を超え、1930年代の大不況以来もっとも高い率となった。1980年代、経済の停滞を反映して高い失業率が続いた。1990年代に入ってからは1992年に7.5%を記録したものの、その後は好景気を反映して低下し、2000年には4.0%まで下がった。しかしその後は増加傾向にある。 1995年の失業率は5.6%であった。これを男女別、人種別、年齢別にみると、アメリカの複雑な雇用情勢を知ることができる。1995年では白人の失業率は4.9%(男4.9%、女4.8%)、黒人の失業率は10.4%(男10.6%、女10.2%)であった。失業率の男女差はほとんど消滅したが、それは賃金の安い第三次産業において女性の雇用が拡大したためと考えられている。一方黒人と白人とでは失業率に2倍以上の差がある。その差のかなりの部分は教育水準によって説明される。1995年に25歳以上で四年制大学を卒業したものは白人男性27.2%、女性21.0%であるのに、黒人では男性13.6%、女性12.9%である。もちろんそのような差を生んだ背景に歴史的に存在した差別があることを否定することはできない。 最大の雇用問題はティーンエイジャーの高い失業率である。白人男性15.6%、女性13.4%、黒人男性37.1%、女性34.3%で、ここでも黒人は白人の2倍を超え、黒人ティーンエイジャーの2.7人に1人は失業していたことになる。 アメリカは雇用労働者の国である。労働力人口に占める雇用労働者の比率は91%に達している。また1995年をとると国民所得のなかで雇用労働者が稼いだ所得は72.6%であった。個人経営の農場や商店の少ないことがその大きな原因である。アメリカの雇用労働者は自らを中産階級と考えており、階級意識は低い。非農業雇用労働者のうち約20%は労働組合に参加しており、組合員の80%はAFL-CIO(アメリカ労働総同盟・産業別組合会議)に属している。近年労働者の組織率は低下傾向にあるが、それは産業構造の変化に伴って、労働組合を組織しやすい製造業や交通運輸業の労働者数が相対的に減少し、組織化がむずかしいか不可能なサービス業や政府機関に属する労働者が増えたためである。1970年代、1980年代アメリカでは労働争議の件数も、参加者もそれによって失われた労働日数も多かった。1970年にストライキで失われた人・日は全労働人・日の0.29%であった。その後ストライキの数は減り、1994~1995年では0.02%にすぎなくなっている。一方1993年の調査では、職場でコンピュータを用いている労働者の数は5100万人で、労働力人口の46%に達している。 [榊原胖夫] Agriculture, forestry and fishingアメリカが世界最大の工業国であることはよく知られているが、世界最大の農業国であることは忘れられがちである。アパラチアからロッキー山脈に至る大平原は世界でも有数の肥沃(ひよく)な土地で、北から南へ帯状に小麦、トウモロコシ、綿花の生産地が広がっている。そのほかにも米、大麦、ライ麦、ジャガイモ、サツマイモ、大豆、ピーナッツ、葉タバコなど、それぞれの適地で生産され、小麦、トウモロコシ、大豆、綿花などではアメリカは世界最大の輸出国になっている。また果物はカリフォルニア、フロリダを中心に各地で生産され、牧畜、養鶏も盛んで、牛乳、乳製品、卵、ワインなどの生産量は着実に増えている。 世界最大の農業国であるとはいっても、アメリカ人のなかで農業に従事している人の数は少なく、労働力人口の2.1%にすぎない。アメリカの農業は肥沃な土地と機械化、商業化、品種改良などによる高い生産性に支えられている。農業生産性の伸び率は製造業の生産性伸び率と比べて劣っていない。生産性向上とともに農場数は減少し、平均農業規模は拡大した。1982年の農場数は約224万(1950年538万)、平均農業規模は約440エーカー(1950年215エーカー)であったが、2002年にはそれぞれ213万、441エーカーになっている。また1000エーカー以上の農場の数は全体の8.4%にすぎないが、全体の66.9%の農地を保有している。 アメリカ農業の最大の悩みは生産過剰、価格の低下、農業所得の減少であった。ニューディール期に農産物価格支持制度が発足したが問題は解決されず、1970年代になって廃止された。しかしその後ロシアをはじめ海外の農作物が不振で、輸出が好調であるため、活況をとりもどしている。1995年アメリカの農作物輸出は金額でみると世界の農産物輸出の14%を占め、肉類、魚介類、トウモロコシ、果物、採油用種子、綿花などで世界一となっている。 1992年、総森林面積は7億3700万エーカーで、そのうち商業用森林面積は4億9000万エーカーである。西部には商業化されずに残されている森林が多い。商業用森林の73.1%は民間所有である。1994年の材木生産高は世界の材木生産高の14.3%、輸出は世界の総輸出の15.0%を占めている。 アメリカは中国、日本、ペルー、チリなどと並ぶ漁業国で、2003年の漁獲高は499万トンであった。近年の健康ブームにのって食料としての魚介類に注目が集まり、漁業はさらに盛んになる兆しをみせている。 [榊原胖夫] 産業構造アメリカ経済の構造変化を国内総生産の構成からみると、製造業の相対的低下と金融・保険・不動産業およびサービス業の増大が認められる。そのうち金融・保険・不動産業の増大はおもに1980年代以降であるが、そのほかは第二次世界大戦後の一貫した傾向である。たとえば製造業の国内総生産に占める割合をとってみると、1947年に26.9%、1972年23.4%、1990年15.5%、1998年15.4%、2003年には12.7%になっている。産業構造の変化は就業労働者の割合をとってみるといっそう明確になる。1980年に22.1%であった製造業の労働者は2003年には12.3%になっている。労働者の割合を大きくくくって物財を生産している産業、無形財を生産している産業に分けると、その比率は1970年で37.5:62.4、1980年32.7:67.3、1990年27.8:72.2、2003年22.7:77.3である。実に80%近い就業者が交通・運輸、卸・小売、金融、保険、不動産、サービス、政府部門など無形財の生産に従事していることになる。国内総生産と就業者から判断すると、製造業では生産性の向上が達成しやすく、無形財生産ではむずかしいことがわかる。無形財部門の増大は主として就業者数の増加によってまかなわれてきたのである。今後もっとも早く増加すると予想されている職種は、高齢者に対するヘルパーで、続いてシステム・アナリスト、コンピュータ技術者などで、減少が続くと想定されているのはいわゆる一般事務職と技術進歩のなかで取り残された機械のオペレーターである。 製造業のなかでは1974年の石油危機以降かなり急激な構造変化が生じている。1973年以前の業種間の売上高の伸び率における格差は1974年以降の業種間格差に比べるとかなり小さい。雇用や設備投資や研究開発投資の伸び率における格差の広がりはいっそう大きくなっている。成長しつつある産業は、コンピュータ、事務機器、半導体、通信機、その他精密機械、石油、航空、宇宙開発、エレクトロニクス、化学、電気などで、不振に陥っているのは、伝統的な主力産業、つまり鉄鋼、自動車、繊維、ゴム・タイヤなどである。一般に知識集約型、高付加価値産業の比重が高まりつつあるといえる。高成長産業は東北部よりは西部や南部に多く立地したため、地域間所得格差は縮小した。しかし物財生産における所得分配に比べると無形財生産における所得分配のほうがはるかに不平等で、そこには技術先端産業に雇用される高給の技術者から、給料の低いスーパーのレジ係まで含まれている。したがって無形財生産の拡大は所得分配を不公平にする傾向があり、このままでは社会の安定の基盤である中産階級が消滅するのではないかと心配する人もある。また1980年代、1990年代には巨大企業への資産の集中が進んだ。現代の技術革新が企業の最適規模を大きくする性格のものであり、それによって経営の多角化、国際化が可能になったことを示している。 [榊原胖夫] 交通・通信アメリカの広大な国土は、もっともよく発達した交通・通信網で覆われている。西部開拓史は交通発展の歴史であるといわれるように、交通の発達がアメリカの経済発展を支えてきたといえる。 2001年の道路延長は約637万8000キロメートルで、そのうち高速道路、自動車専用道路などの主要道は約70万3000キロメートルである。高速道路は都市周辺部や橋梁(きょうりょう)を除くとたいてい無料である。乗用車の保有数は約1億3763万台、商用車をあわせると2億台を超え、二輪車も含めると人口1000人当り808台になる。多くのアメリカ人にとって自動車は足の延長であり、その意味でアメリカは自動車文明の国である。 1994年の鉄道軌道の延長は約36万キロメートルで、1980年と比べても、11万キロメートルほど減少している。鉄道は旅客を航空に、貨物をトラックに奪われ、斜陽をかこっているが、とくに旅客輸送の減少は著しい。1971年に開始されたアムトラックAmtrak(全米鉄道旅客輸送公社)による旅客輸送も、石油危機当時脚光を浴びたが、ふたたび赤字が増大し破産状態に陥った。しかし、1990年代後半には、貨物輸送においては復権の兆しをみせた。すなわち、重くてかさばる農産物、鉱産物は大陸の中央部で生産されるものが多いため、その輸送はいまでも多く鉄道に頼っている。鉄道による都市内大量輸送ではサンフランシスコのバート、ワシントンDCのメトロ、アトランタのマルタなど新設された線路も少なくない。また、2000年にはニューヨーク、ボストン間に高速鉄道のアセラ・エクスプレスが営業を開始している。 航空輸送は旅客・貨物とも輸送量において他の諸国を大きく引き離して、トップの座を占めている。1978年の法律で航空に対する経済規制が全面的に廃止されると競争が激しくなり、運賃は大幅に低下、需要の拡大につながった。しかしそれは一方で航空会社の経営を圧迫し、その統廃合が進んだ。国際線ではアメリカの航空会社のコスト優位性が目だち、それを背景にアメリカは外国に自由な航空協定を結び、競争を促進するように求めている。 アメリカの商船保有は、1074万トン(2004)であるが、パナマ、ギリシア、リベリアなどへの便宜置籍船もあり、海港はコンテナ輸送を中心に活況を呈している。しかし、従来型のバース(保留施設)が不要になって再開発されたところも多い。 アメリカは確かに交通がよく発達した国であるが、国土が大きく、主要産品に重くてかさばる種類のものが多いせいで、国民総生産が1%伸びるにあたって必要な輸送量の伸びは、日本やヨーロッパ諸国に比べて大きく、その意味では不効率であるともいえる。1991年には「インターモーダル交通効率化法」が成立し、交通政策の基本的スタンス(構え)が示された。それは交通機関の間の連携を密にして全体として効率的な体系をつくろうとするもので、その効率には環境に対する負荷を軽減することも含まれている。 テレビ、ラジオ、電話機などの1人当り保有率、郵便受取数、新聞雑誌、図書などの発行部数なども世界のなかで群を抜いて多い。 1990年代に入るとインターネットが爆発的にその規模を拡大した。インターネットは国防総省の高等研究計画局(ARPA)による軍事目的のARPANET(アーパネット)や大学など研究機関のネットワークから発展したが、1993年9月にクリントン政権によって国家情報基盤(NII)構想(情報スーパーハイウェー構想)が発表され通信基盤がさらに強化された。今日、全世界でインターネットに接続されるホストコンピュータの数は2億1915万台(2003)と推計されているが、そのうちアメリカは1億6221万台で、世界一を誇っている。 [榊原胖夫] 国土の開発と保全広大な国土をもつアメリカは、歴史的にみても、つねに内陸開発に積極的であった。しかし開発の促進主体はおもに州ないしは地方自治体であった。連邦政府の手による大規模開発事業は、1930年代のTVA(テネシー川流域開発公社)に始まる。そして1960年にはアパラチア地域開発事業が始まり、1965年には経済開発庁(EDA)も設立された。一方アメリカには環境保全運動も古くから存在し、1856年のニューヨークのセントラル・パーク設置条例、1872年のイエローストーン国立公園をはじめとして、各都市、各地域に同種の公園が続々と誕生した。またニューディール期には工場の地方分散化計画やグリーンベルト構想がたてられている。1960年代後半から1970年代初めにかけて農薬、中性洗剤、産業排水による水質汚濁、工場の排煙、自動車の排ガスによる大気汚染が問題となり、環境保全のための多くの法律が制定された。そのなかには1970年の大気清浄化法改正法(いわゆるマスキー法)や同年の国家環境政策法がある。後者によって連邦環境保護庁が設立されている。いかにして開発と環境保全とのバランスを維持するかがそのおもな役割である。 [榊原胖夫] 財政・通貨・金融先進国の財政はどこも、景気停滞による歳入の頭打ち、福祉関係その他歳出の硬直化によって困難の度を加えているが、アメリカも例外ではなかった。連邦政府の財政赤字は1980年代に入って急増し、1992年には2904億ドルと戦後最悪を記録した。すでに述べたようにその後1997年には、1969年以来初めて財政収支の均衡が達成された。しかし、2002年にはふたたび財政赤字となっている。1995年では財政収入のうち個人所得税が44%ともっとも大きく、社会保険36%、法人所得税12%、間接税4%などとなっている。歳出では所得保障が15%、国防費17%、利子支払16%、社会保障負担22%、メディケア(老人医療保険)13%などとなっている。なお、固定資産税は地方税で、そのほかに地方が独自に設けている所得税や間接税がある。また教育、交通などの支出においては地方政府の役割が大きい。政府支出に占める連邦支出の割合は、1993年には62%で、低下傾向をたどっている。また国内総生産に占める政府部門の割合は1980年で20.6%、1995年で18.7%で、軍事費の割合が6.3%から4.8%に低下したことが大きい。 アメリカの通貨単位はドルで、1973年変動相場制移行以来、円、ドイツ・マルク、スイス・フランなどの通貨に対して大きく減価した。しかし1990年代に入ってアメリカ経済が好調のため、ドルは高めに推移している。アメリカの銀行制度は日本やヨーロッパと違い、全国に支店網をもつ市中銀行が存在しなかった。銀行はもともとそれが存在する都市と周辺農家のためのものであり、地域性がきわめて強かった。もっとも資金量が豊かで巨大化した商業銀行は存在した。バンク・オブ・アメリカ、チェース・マンハッタンなどはその例である。銀行の認可権はいまでも州にあるが、1994年以降他州における支店開設規則は撤廃された。2002年の銀行店舗数は商業銀行、貯蓄・貸付銀行をあわせて約8万7000である。そのうち本店の数は約9000であり、1行1店舗の銀行がまだ多いことを示している。しかし銀行数も店舗数も合併、併合などによって急速に減少しつつある。金融市場のなかに占める銀行の相対的位置は、金融商品の多様化に伴って低下している。ウォール街には銀行以外に投資金融業者が数多くあり、投資信託会社が巨大化している。また巨大な保険会社の動向が金融市場に与える影響も無視することはできない。これらの資金がどこに向かうかによって特定の国に通貨不安が生じるなど、国際経済の不安定要因になる可能性がある。金融における規制の撤廃は1970年代に始まり、1990年代も進行中である。金融システムは情報技術とコンピュータ化の影響を受けて業務形態を変えつつあり、アメリカ人のもつ金融資産も多様化している。それを受けて金融改革は、銀行、証券などの業種間の垣根を取り払うこと、規制を撤廃して競争をいっそう盛んにすること、預金者保護を強化することに向けられている。1980年代に多くの貯蓄・貸付銀行の経営が破綻(はたん)した苦い経験から、自己資本規制の強化と連邦預金保険公社の拡充が実行に移された。 アメリカの中央銀行制度は連邦準備制度とよばれる。連邦準備制度が発足したのは1913年で、他の先進諸国よりかなり遅れている。独立当初から1833年まで合衆国銀行とよばれる国立銀行が存在したが、ジャクソン大統領のとき、権力の集中を危惧(きぐ)して免許を更新しなかったため消滅した。連邦準備銀行はアメリカ本土に12行あり、その運営は連邦準備制度理事会によって行われている。連邦準備銀行は連邦準備制度に加入しているメンバー銀行によって所有されているが、メンバー銀行が連邦準備銀行の政策に影響を及ぼすことはまずない。これらの連邦準備銀行は連邦準備紙幣を発行し、メンバー銀行の準備を保持し、必要とあればメンバー銀行に資金を貸し出す。理事会は準備率の変更、割引率の決定を行う。近年ではマネタリスト(通貨政策重視派)たちの影響がきわめて強く、全体的な通貨供給の管理が最優先されている。また連邦準備銀行と市中銀行との関係は、他の国の場合ほど密接とはいえず、アメリカの銀行は自由銀行制度時代の独立性を精神的なよりどころにしているものが多い。 [榊原胖夫] 貿易・国際収支・対外援助アメリカの対外貿易は1875年から1970年(1888年、1889年、1893年を除く)までほぼ100年間にわたり、つねに黒字であった。しかし1976年以降は慢性的な赤字となった。2003年の経常収支の赤字幅は5300億ドルに達している。貿易相手国ではカナダがもっとも大きく、中国が急速に伸びて2位となり、ついでメキシコ、日本、ドイツの順となっている。資本収入は1993年まで黒字であったが、1994~1995年ではわずかに赤字となった。 昔からアメリカでは国内市場が大きく、対外貿易の比重が小さいとされてきた。確かに国民総生産に占める輸出および輸入の割合(輸出依存度、輸入依存度)は、1960年まで5%を超えたことはなかった。しかし1960年代後半から急速に上昇し始め2003年では輸出6.6%、輸入11.9%になっており、輸入について日本よりもかなり高くなっている。その分アメリカ経済と世界経済のつながりが深くなったといえる。 アメリカは第二次世界大戦後、対外援助において指導的な役割を果たしてきた。ほかの先進諸国の援助額が増えたためアメリカの比重は減少してきたが、1990年代なかばでもアメリカは世界でもっとも多い500億ドルから700億ドルの経済協力支出を行っている。なお、2004年の政府開発援助(ODA)の実績では、アメリカは約1900億ドルでもっとも多いが、対GNI(国民総所得)比では0.16%で、世界21位にとどまっている。 [榊原胖夫] Society and Cultureアメリカ社会・文化の特質と変貌アメリカ合衆国の社会や文化は、日本の場合と比べるとはるかに複合的、多角的である。広大な国土、強い州権による地域的な特色、多人種・多民族からなる人口構成などがそのおもな原因であるが、それでいてなお全体を統合する強い特質をもっている。 始めその特質の核となったのは、WASP(ワスプ)(White Anglo-Saxon Protestant白人、アングロ・サクソン、プロテスタント)たちであった。このことばが生まれたのはずっとのちになってからであるが、第1回国勢調査(1790)当時、住民の約80%は白人であり、その白人の約61%はイギリス系であった。建国当時から、WASP中心の生活様式や価値観が支配的だったのである。このため、独立してからもアメリカの文化はなおイギリスの模倣が多かった。西方へ延びる広い国土に対して人口密度は非常に低かったので、どうしても屋外の肉体労働が多くなり、生活自体の要求が先行して、アメリカ独自の文化の発展を遅らせた。ところがそのような先住民アメリカ・インディアンと広い土地を相手にする生活のなかから、つまり大衆の日常生活のなかから、アメリカ文化の基盤がしだいに養われていくのである。こうしてアメリカ独自の文化がつくられるようになったのは、モンロー宣言が出されてからアメリカ人という意識の高まるようになった1830年代である。南北戦争(1861~1865)後から20世紀初めにかけては、南欧や東欧からのWASPではない移民が急増し、言語や宗教などが急速に多様性を帯び、そのため社会的な混乱もおこるようになって、1924年には移民割当法が成立し、日本移民はこのとき禁止されて、無制限に移民を受け入れていた時代は終わった。 しかしこの1920年代に、世界に先駆けてアメリカが高度の大衆消費時代を実現させた点は、特筆されてよい。産業革命はイギリスから始まったが、このときまでにアメリカの豊富な資源や自由なエネルギーがみごとに昇華し、国民の多くが自動車を所有できるような大衆消費時代を、イギリスよりも一足先につくりあげることに成功したのである。このためアメリカ人の生活文化は、第二次世界大戦後に空前の軍事力と経済力を伴って世界中に広まった。コカ・コーラなどに象徴されるアメリカ的生活様式は、のびのびとした中産階級の層の広がりをみせ、多くの国の人々のあこがれの的となった。各種の文化もニューヨークなどの大都市を中心に充実して多彩な動きをみせ、ヨーロッパだけが文化の中心舞台であった時代は終わった。とくに映画、テレビ、ミュージカルなどの大衆文化や、情報文化、若者の文化などにおいては、アメリカが完全に世界をリードするようになった。 しかし、1960年代に入って、アフリカ系住民(黒人)を中心とする公民権運動が高まり、そのほか各種のマイノリティ・グループの発言権が増大するにつれて、WASPの価値観はしだいに地盤沈下をきたすようになった。このことは、アメリカの社会や文化をいっそう多様化させる結果となっている。WASP以外の人々も、従来のようにWASPのコピーにならず、それぞれの特色を発揮することにむしろ誇りと意義を感じるようになったからで、これは一種の大きな意識革命といえるものである。このほか、1960年代を特色づける一連の現象、大学紛争やベトナム反戦運動、ウーマン・リブ運動、公害反対運動、ヒッピーなどのカウンター・カルチャー運動などを経て、かつての自信に満ちていた時代のアメリカ的生活様式は、かなりの変貌(へんぼう)をみせるようになった。1970年代に入って、石油危機やウォーターゲート事件、ベトナムからの撤退などは深い挫折(ざせつ)感をアメリカ人の心のなかに刻み込み、これが屈折した形で生活の各方面ににじみ出してきた。 いまアメリカの社会や文化は大きな曲がり角に差しかかっている。あまりにも多様な要素が絡み合っているので、ときには秩序が破壊されたり、荒廃した一面をさらけ出したりすることもある。しかしまた、自分たちの価値観や生活様式だけが世界のなかで唯一最高のものであると考えていたことの誤りを、アメリカ人はいま苦痛をもって学びつつあるという一面ももっている。しかし、依然として全人類の実験場としての壮大なスケールの性格を失ってはいない。だからこそ全世界の人々が、いまもなおアメリカの社会や文化の動向に、熱い視線を注いでいるのである。 [渡辺 靖] 住民(人種・民族)合衆国は世界でも有数の多民族国家である。先住民としてのネイティブ・アメリカン(アメリカン・インディアン)を除けば、すべて他国から過去3世紀以内に移住してきた者およびその子孫たちから成っている。独立戦争から間もない1790年までに約60万人が合衆国に移住したが、その約3分の2がイギリス系だった(当時の総人口は約315万人)。その後、19世紀中盤にかけて西欧や北欧からの移民(イギリス系、アイルランド系、ドイツ系など)が、そして19世紀末からは東欧や南欧からの新移民(イタリア系、ポーランド系、ユダヤ系など)が急増した。民族的にはラテン系やスラブ系、宗教的にはキリスト教カトリックやギリシア正教、ユダヤ教が多く、従来の旧移民(民族的にはアングロ・サクソン系ないしゲルマン系、宗教的にはキリスト教プロテスタント=新教徒)とは文化的背景を大きく異にした。加えて、外見や風俗習慣がさらに異なる中国系や日系などアジア系の新移民も加わるようになり、新移民の入国数が旧移民を上回るに至った。1901年からの10年間には旧移民191万人に対し、新移民は623万人を記録する。1900年当時の総人口が約7600万人なので、毎年総人口の1%にあたる移民が入国したことになる。 移民の急増に伴い移民排斥の動きも活発になった。とりわけ秘密結社クー・クラックス・クラン(KKK)は有名で「100%のアメリカニズム」を唱え、彼らが「アメリカ的」ではないとみなした人々、たとえばアフリカ系住民、カトリック教徒、新移民などへ暴力や脅迫を繰り返し、なかでもアフリカ系住民へのリンチ行為は凄惨さを極めた。KKKの活動のピークは1920年代だが、日本が排日移民法とよんだ移民割当法が制定され、事実上、日本からの移民が認められなくなったのもこのころである。 合衆国は、建国以来、5000万人以上の移民を迎え入れ、今日もなお年間70万人を受け入れる移民大国である。民族的出自に関する自己意識にまつわる調査(2005)によると、ドイツ系(15.2%)、アイルランド系(10.9%)、イギリス系(8.7%)を筆頭に白人が全体の約75%を占める一方で、ヒスパニック系14.5%、アフリカ系12.1%、アジア系4.3%、先住民0.8%となっている。全都市の約6分の1にあたる505都市では、20歳以下の人口に占める少数民族の割合が白人を超え「多数派」になっている。2005年に2億9600万人だったアメリカの人口は、現在の傾向が続けば、2050年には4億3800万人に増加し、白人が占める比率は人口全体の47%になるという予測もある。それは、過半数を占める「多数派」の人種がなくなるという、合衆国史上初の状態を意味する。 その一方で、不法移民(不法入国者)の存在も深刻度を増しており、その数は1200~2000万人と推定され、大半がメキシコから出稼ぎ目的で国境を渡ってきたヒスパニック系とされている。アメリカ人から職を奪う、麻薬が持ち込まれる、国民の税金で支えられている社会福祉制度に大きな負担となるなどの理由で取り締まり強化を求める声も強い。しかし、破格の低賃金で雇える不法移民は、合衆国全体の就労人口のすでに5%を占めるともいわれ、まさに産業の底辺を支えているという現実も無視できない。また、取り締まり強化は不法移民に同胞意識をもつ合衆国内のヒスパニック系住民の反発を買う恐れもあり、政治的に非常にデリケートな問題となっている。 [渡辺 靖] language合衆国憲法はいかなる言語も合衆国の国語とは定めていない。つまり、英語は合衆国の国語(公用語)ではない。州レベルでも英語を公用語に指定しているのは50州中30州にとどまっている。国勢調査(2000)によると、国民の82%が家庭で英語のみを使用しているが、アメリカ国民の5人に1人は英語以外の言語を使用している。英語をアメリカの国語に定めようという動きはつねに存在するが、英語以外の言語を日常的に使用している多くの国民が社会的に不利な状況に置かれかねないという懸念から、これまで連邦レベルで法制化されることはなかった。英語を国語とすることで社会をより効率的に運営することが可能になるかもしれないが、その代償として損なわれてしまうアメリカ社会の魅力や活力が多いという判断である。 [渡辺 靖] National life生活水準の高さはかつて世界中の羨望の的であったが、貧富の差、そしてそこに密接に絡むドラッグ、人種差別、ギャング抗争、学校崩壊といった社会問題も深刻である。 1930~1960年代にかけてニューディール政策の再分配政策により貧富の差が縮小し、大量の中産階級(ミドルクラス)が誕生した。しかし、1970年代以降、「小さな政府」のイデオロギーが主流となるなか、福祉政策の切り詰めなどによって貧富の差が広がり、とりわけ中産階級の没落が顕著になった。2007年には上位10%の富裕層が所得全体に占める割合は48.5%とほぼ半数に達し、富裕層のみ所得が1割増となった。その一方、米住宅都市開発省(2007)は、公園や道路などで寝泊まりしているホームレスが75万人に達していると発表した。単純に比較はできないが、その数は日本の約30倍に相当する。また、食料安全保障報告(2008)は、全米の14.6%にあたる1714万世帯が、同年中に収入不足などから家族全員に十分な食事を与えられない「食料不足」を経験したことがあると伝えている。 こうした貧富の差を背景に、防犯のため地域全体を塀で囲んで、中に入れる人を制限する高級住宅地「ゲーテッド・コミュニティ」の居住人口は1995年には400万人だったが、1997年には800万人、2006年には全米5万か所で2000万人規模にまで拡大している。その一方、塀で遮断されたもう一つのコミュニティである「刑務所」の服役者数も倍増し、2006年には収監者数が230万人に達している。 相対的に、東部・北部の諸州は比較的豊かであるのに対し、南部の諸州は貧困層が多い。「1人当り州民所得」(2006)によると、最高所得がコネチカット州で4万9852ドル、全米平均(3万6276ドル)を100とした場合の相対値が137、最低所得がミシシッピー州で2万6535ドル、相対値が73となっている。 [渡辺 靖] National Characterイギリスによる植民地支配の経験から、アメリカの独立13州では連邦政府を創設することに対し当初から強い危惧の念が存在した。つまり、せっかくイギリス王政への隷従のくびきを脱したのに、連邦政府という名の新たな支配者を君臨させたのでは、何のために独立戦争を戦ったのかわからないという発想である。その結果、合衆国では家族を中心にした自分の住む地域、コミュニティへの帰属意識が強い。市町村にしても日本のように行政主導で制定されるのではなく、個々のふれあいから村ができ、町ができ、市ができ、やがては州へ(すなわち、下から上へ、個から全体へ)と自治が発展していった。とくに、ニューイングランド地方で発達したタウンホール・ミーティングに代表される住民集会は、王や宗教に頼ることなく、参加者の討議と自発的な約束によってルールを形成するアメリカ民主主義の原型とされる。 1831年に合衆国を訪れたフランスの貴族アレクシ(ス)・ド・トクヴィルAlexis-Charles-Henri Clerel de Touquvill(1805―1859)は名著『アメリカのデモクラシー』において、合衆国では自発的結社の活動が宗教・政治・学術・慈善・公益など多岐にわたっていることに注目し、こうした結社の活動こそは、孤立しがちな個人に、他人と協力して何ごとかをなすための術を教えていると賞賛した。 コミュニティや結社はいまなおその自治の土台をなすものである(日本のような全国紙がない一因もそこにあるとされる)。連邦政府に対して情報開示を求め、市民としての公正な権利を求めることはアメリカ人にとって大きな意味を有する。中央政府への懐疑と合衆国への忠誠が必ずしも矛盾しない点がアメリカの国民性を理解するうえで重要である。 [渡辺 靖] education歴史的な経過をみると、日本と決定的に異なるのは、初等教育がまだ整備されていないうちに、高等教育機関が拡充していった点である。ハーバード・カレッジが創立されたのは1636年であり、合衆国建国より1世紀以上古い。2005年時点で、大学進学率は64.6%であり、同年の日本の52.3%を大きく上回っている(文部科学省「教育指標の国際比較」による)。また、大学院以上の進学者も25歳以上の人口の9%を占めており、高学歴化が進んでいる。一般に私立大学が名門難関、州立大学が大衆的であるが、総じて世界的に著名な大学が多いのも合衆国の特徴である。 しかし、歴史的に、国民の大部分にとっては初等教育すら受けられない状態が長く続いた。リンカーン大統領が受けた教育は合計1年足らずであり、西部開拓熱の高かった1840年の国民平均修学年数は約1か年であった。現在でも、初等中等教育に関しては寄宿舎制度を有する名門私学が存在する一方で、貧しい地域では財政や治安の点で問題を抱える公立学校も少なくない。 1990年代からは特別認可charter、あるいは達成目標契約により認可された公設民間運営校(チャーター・スクール)が増加している。これは、地域住民、教師、市民団体らが、その地域で新しいタイプの学校の設立を希望し、その運営のための教員やスタッフを集め、その学校の特徴や設立数年後の到達目標を定めて設立の申請を行うもので、認可された場合、公的な資金の援助を受けて学校が設立される(運営は設立申請を行った民間のグループが担当する)。また、学校に通学せず、家庭に拠点を置いて学習を行うホームスクーリングは全州において合法とされており、宗教上の理由などから、近隣の学校の教育方針に同意できない家庭を中心に広がりをみせている。 [渡辺 靖] religion合衆国では「政教分離」の原則が貫かれているが、これは国教の制定のように、国家が特定の宗教団体を優遇・差別しないという意味で、宗教を政治から排除することを意味しない。むしろ、戦場であろうとどこであろうと祈りたいという国民がいるなら、政府はそれに応えることが信教の自由を守ることだと考えられている。 世界価値観調査(2005)によると、「自分の生活にとって神は非常に重要だ」という回答者の割合は、アメリカでは54.8%と、ドイツ9.5%、イギリス22.4%、フランス11.4%、日本5.4%と比べて際だって高くなっている。事実、大統領の就任式なども宗教色が強いし、合衆国のドル札や5セント硬貨などには、“IN GOD WE TRUST(私たちは神を信じる)”と刻まれている。この場合の「神」とは特定の宗教の神ではなく、より概念的な存在としての神をさす。諸宗教から最大公約数的な要素を抽出し、それを公の場に組み込むという意味で「市民宗教civil religion」ともよばれている。 特筆すべきは、1970年代末からの保守的なキリスト教勢力の巻き返しである。カウンターカルチャーの結果、伝統的規範にとらわれない文化やライフスタイルが広がったが、彼らは、そうした道徳的退廃が離婚の増加、家庭の崩壊、ドラッグの蔓延(まんえん)、犯罪の増加といった社会問題を引き起こしていると考えた。こうした保守的なキリスト教徒、とくにプロテスタントたちは「原理主義(根本主義)者fundamentalist」「右派・右翼」「福音派evangelical」ともよばれる。現在、福音派はアメリカ全人口の約3分の1を占め、リベラルなプロテスタントは保守派より少ない。福音派のなかには2000人以上の信徒を有するメガチャーチ(巨大教会)を有するものもあり、1970年にはわずか10だったその数は、1990年には250、2003年には740、2004年には840と近年急増した(2005年には1000を超えた)。 アフリカ系住民、カトリック教徒、ユダヤ教徒などのように、価値観では保守的であっても、政治的には伝統的にリベラル派が多い。1990年代には、こうした保守派と穏健・リベラル派の対立が増し、人工妊娠中絶、同性愛者の権利、宗教教育(礼拝・反進化論教育)、尊厳死、ES細胞の研究開発などの争点をめぐり「文化戦争culture war」と称されるほど論争が政治化した。大統領オバマは就任演説(2009)において、合衆国が「キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、そして無宗教の人々の国だ」と述べ、宗教的多様性や無神論者への配慮を鮮明にしたが、その一方で、キリスト教保守派は宗教的な要求を掲げてロビー活動、選挙活動を続けている。 [渡辺 靖] gender1960年代のウーマン・リブ運動を直接の契機として、従来の「男らしさ」「女らしさ」という価値に縛られない生き方への許容度が高まった。ただし、合衆国において女性参政権が制定されたのは1920年で、「人種で投票権を制限しない」と定めた憲法修正条項第15条の成立(1870)より50年も遅れたことなど、「人種」に比べて「女性」への偏見が根強いことを批判する声も少なくない。女性の生活水準が離婚後に急激に落ちる傾向や、子供の養育権をかちとった女性の大半が、十分な養育費を受け取れない傾向はその一例である。批判者の多くは、合衆国における仕事、学校、医療が、いまだに1950年代の核家族の規範をもとに組織されていると主張する。すなわち、各家庭にはいつでも母親がいて、日中に子供たちを医者や歯医者に車で連れて行ったり、登下校の際には小学校まで子供を送り迎えすることができ、また子供がインフルエンザにかかったときは家にいるという役割である。 その一方で、1990年代以降、ジェンダーをめぐる運動は、性の役割改革から性意識そのものの改革へと発展している。社会が新たに承認すべき性別の頭文字を組み合わせたLGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル[両性愛者]・トランスジェンダー/セクシュアル[性別違和/性の不一致])という呼称が考案され、2009年大統領に就任したオバマはこうした社会的少数派の人権擁護を標榜(ひょうぼう)した。 日本では憲法によって「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定されているが、合衆国憲法ではこうした制限はなく、現時点では、同性婚の承認そのものは各州の判断に委ねられている。権利運動そのものは1970年代から存在していたが、本格化したのは1990年代で、2003年秋にマサチューセッツ州の最高裁が同性結婚を認めたことが大きな転機となった。2010年時点で、コネチカット、アイオワ、バーモント、ニューハンプシャーの各州でも同性婚が認められている。各種の世論調査をみると、2000年代になってからアメリカ人は同性結婚に対して寛容になってきている。20代から30代前半までは半数が容認している。住民投票などでは同性婚への反対が多数を占め、宗教保守派からの反発も激しいが、州の司法判断で承認されるケースが多く、その判断をもとにさらに他州へと広がりをみせている。 [渡辺 靖] family一人前になった子と親が同居することはまれで、2世代世帯や3世代世帯はほとんど存在しない。子に負担をかけるよりも老人ホームに入ることを選択する親がほとんどである。実際は仕事や学業、結婚などによって遠く離れて暮らすことが多いが、「スープの冷めない範囲」の近くに住み、互いに助け合おうという気持ちは強い。親子や兄弟姉妹の写真が多くの家庭に飾られており、感謝祭やクリスマスに再会を楽しむ光景が全米各地で見受けられる。 見合い結婚の風習はなく、恋愛に基づく結婚が当然視され、夫婦関係は日本に比べるとより対等である。愛情確認の挨拶(あいさつ)もきわめて日常化している。しかし、その一方で、結婚の約半数が破綻(はたん)している現実もある(19世紀末までに合衆国の離婚率はすでに世界一であった)。女性の社会進出や物価上昇に伴い、男性が一家の稼ぎ手である家族はもはや一般的ではない。国勢調査(2000)によると、稼ぎ手としての父親と在宅の母親で構成される家庭は全世帯の1割にすぎない。また、個人の自由裁量と選択肢が拡大した結果、単身者世帯、単親世帯、内縁関係(異性愛者同士あるいは同性愛者同士など)などにみられるように、1950年代には8割近かった異性カップルの婚姻に基づく夫婦世帯(核家族)は50.7%にまで減少している。親が離婚した家族、未婚のカップルが子育てをする家族、共稼ぎ家族、同性カップル、働いている配偶者がいない家族、再婚などによる混合家族、子供が巣立った家族等など、家族の形態はますます多様化しているといえる。 [渡辺 靖] welfareアメリカでは自助の精神に基づき「政府は原則として個人の生活に干渉すべきではない」という政治文化が根強い。そのため国民の税金を使った政府による福祉政策の対象については長年議論が続いてきた。障害者や高齢者などに対しては社会のセーフティネットとして社会福祉政策の対象となるという社会的合意があるものの、貧困者に対する公的扶助などについてはだれが恩恵を受けるべきかという線引きが政治的争点となってきた。政府のリーダーシップによる社会改革を希求するリベラル派は、所得再分配的な制度の一環として貧困者に対する社会福祉を充実させようという立場に立つことが多い。一方、福祉国家化は連邦政府の肥大化につながるとして「大きな政府」を否定する声も保守派のなかでは目だっている。長年の争点だった無保険者対策のための医療保険改革が2010年まで実現しなかったのも、両者の意見の対立があったためである。 ただ、国際的にみるとアメリカの社会福祉制度の開始は遅いわけではない。アメリカでは民間病院やコミュニティが中心となり、社会福祉を提供してきた歴史があり、ソーシャルワーカーという職業も世界に先駆けて20世紀初めに登場している。1935年に立法化された社会保障法は、社会保障に関する法律として世界で初めて制定されたものだった。同法に基づき、高齢者年金、遺族年金、障害年金などの公的年金制度を中心とする社会保障制度が整備されたほか、「要扶養児童家族扶助(AFDC)」なども制定された。さらに、1965年には高齢者と障害者向けの「メディケア」、低所得者向けの「メディケイド」という公的医療保障制度も導入された。第二次世界大戦後の福祉国家化の流れのなかで、アメリカでも福祉関連予算が飛躍的に増大した。 各制度の実際の運用については連邦制ゆえに州への権限移譲が目だっており、連邦と州、そして州以下の地方政府が協力しながら行っている。また、非政府組織も福祉政策の運用のうえで大きな役割を果たしている。連邦政府は非政府組織への助成を進め、非政府組織が政府にかわって貧困者支援などを行っている。民間医療保険の目覚ましい発達など、アメリカにおける社会福祉制度にはさまざまなユニークな特徴がある。 社会福祉の各種制度のうち、自ら掛金を払い恩恵を受ける高齢者年金制度などについては、自助の精神と合致するところもあり世論は好意的である。しかしAFDCなどについては、働くことができるのに働かず、社会福祉給付を要求するような福祉依存ともいえる状況が目だってきたこともあって、制度に対する世論がしだいに厳しくなった。1996年のビル・クリントン政権期に行われた福祉改革の結果、AFDCは「一時的貧困家庭扶助(TANF)」に改定された。これによって福祉給付期間に制限が加えられるとともに、就労可能な福祉受給者に就労義務が課せられた。ただ、低賃金職への就労が高い点など、貧困者の生活水準の向上については疑問の声も多い。公正な社会福祉をめぐる議論には当分終わりがない。 一方、社会福祉をめぐる激しい議論とは異なり、障害者の「機会の平等」を重視する点では、アメリカ国内にはコンセンサスがあるといえる。これを象徴するのが、1973年に成立したリハビリテーション法や1990年に成立したアメリカ障害者法(ADA)である。アメリカ障害者法は、障害をもつ者に対する差別を非合法とする画期的な法律である。肌の色や人種、信仰、性別などとともに、障害による差別も公民権侵害にあたるという見解から立法化された。ソーシャルワーカーという職業が、障害者の「機会の平等」を下支えするという重要な役割を担っている。 社会福祉のおもな受益者となる高齢者層は比較的投票率が高いため、高齢者をめぐる社会福祉の問題はつねに選挙戦の争点となってきた。高齢者は自らが組織をつくり、アメリカ退職者協会(AARP)という強力な利益団体を立ち上げている。この団体は、医療保険改革などで大きな役割を担った。このように、グレイパワーが目だっているのもアメリカの福祉政策をめぐる大きな特徴である。2011年時点で、アメリカの財政は赤字が急激に膨んでおり、高齢者福祉の財源にメスを入れざるをえない状況になっている。今後、高齢者福祉をめぐる激しい政治的な対立が予想されている。 [前嶋和弘] artアメリカの芸術がもつ特色をもっとも端的に表現すれば、ダイム・ノベルdime novel(10セント読み物)、ジャズ、ミュージカル、ハリウッド映画、ポップ・アートなどにみられるような大衆性、ということができよう。そしてこの大衆性は、芸術をひたすら高尚なもの、孤高なもの、精神性の高いものと考えてきた日本の知識人の間で、長い間低俗なものとして軽蔑(けいべつ)されてきた。しかしそれでいながら、アメリカの大衆芸術は日本人の心を、いや全世界の人々の心をとらえ続けてきた。いわば文化における平等性とでもいうべき特色が、20世紀の人々の普遍的な魅力となったのである。 もちろん文学の分野でいえば、高度な小説や詩がいくらも書かれているし、ノーベル文学賞を受賞するような文学者が何人も輩出している。しかしそれはヨーロッパ諸国においても同じである。ダイム・ノベルやその伝統を受け継いだたくさんの大衆小説、スーパーマーケットや新聞売場に氾濫(はんらん)する大衆小説こそ、アメリカのもつムードにふさわしい。また各地にはそれぞれ誇るべきシンフォニー・オーケストラがあるが、それだけならば、これまたヨーロッパ諸国と変わりはない。ブルース、ジャズ、カントリーなど、次から次へ大衆の間から生まれたポピュラー・ミュージックこそ、アメリカの体臭ということができるだろう。ハリウッド映画がいち早く大衆のものとなり、テレビが各家庭に入り込む。映像と漫画がマス・メディアの発達にのって、大衆一人一人のものとなっていく。こうしてみると、アメリカの芸術は都市のものであり、技術によって広がったものであり、若者のエネルギーに支えられたものであり、そしてなによりも、大衆が心から歓迎したものなのである。 [猿谷 要] Mediaデモクラシーの伝統の強い国なので、報道の自由はすでに植民地時代から確立されており、知る権利の重要性については、世界中にアメリカ人ほどよく認識している国民はいないであろう。世論が国を動かすアメリカで、マスコミがもっともよく発達しているのは当然のことである。2003年にテレビは1730局、ラジオは1万1009局となり、ケーブルテレビはなんと9038局となった。一方、新聞は1995年の発行部数が、『USAトゥデイ』214万部、『ウォールストリート・ジャーナル』180万部、『ニューヨーク・タイムズ』111万部という程度の部数である。あまりにも巨大になった各種媒体が、一方的、画一的に情報を押し付けることの弊害についても、反省が生まれるようになった。それにしても、ベトナム戦争の実態をとらえた報道写真やテレビ放送、ウォーターゲート事件の真相を究明した『ワシントン・ポスト』『ニューヨーク・タイムズ』などの政治権力との闘争は、おそらく世界に冠たる業績というべきであろう。なおギャラップ、ハリスその他、世論調査機関がよく発達し、大衆は情報を伝えられるばかりではなく、情報への反応を逆に伝え返し、それがまた国家の政策に影響を与えるほどの力をもっている点は、いかにもアメリカはマスコミの国、ということができるほどである。 [猿谷 要] Cultural Facilities歴史の浅い国であるにもかかわらず、国の豊かさを十分に発揮して、各種の文化施設が充実している。しかし博物館、美術館などは、世界的にその名を知られているようなものは、ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィア、ワシントン、シカゴなど、おもに北東部の大都市に集中し、富の偏在を物語っている。もちろん小規模なものは全米各地にもあるが、いままで貧しかった南部、歴史のいっそう浅い西部などには、北東部にみられるほど充実したものがまだ見当たらない。それにしても、ニューヨークのメトロポリタン美術館、自然史博物館、近代美術館、グッゲンハイム美術館、ボストンの美術館、ワシントンの国立美術館、スミソニアン博物館などは、質量ともまさに世界の超一流ということができる。ゆっくり見学するにはそれぞれ数日かかるほど規模が大きい。 図書館は公立のものがよく普及している。司書は一般の事務職とは違った特別職であり、図書館業務についての理解はよく行き渡っている。老若男女を問わず利用者が多く、簡単な手続ですぐ本を借り出すことができる。細かな点は地域によって異なるが、公共の観念が強いため、返済が1日でも遅れれば罰金を支払わなければならない。大学の図書館も非常に充実していて、図書館は大学生活の中心であるという考えにたっている。 シンフォニー、オペラ、各種演劇などの劇場は主として大都市に集中している。西海岸のサンフランシスコ、ロサンゼルスなどにもいろいろな文化施設がつくられてはいるが、劇場は、やはりその中心がニューヨークで、ブロードウェーおよびその周辺はまさに劇場が軒を並べた感じである。 歴史が浅い国だけに、史跡をたいせつにしようとする努力は実に積極的である。プリマス、ジェームズタウン、セント・オーガスティンなど、植民開始当初の史跡はそのまま保存されたり、復原されたりしているし、ウィリアムズバーグのように町全体が植民地時代のままの姿で維持されている例もある。独立戦争や南北戦争の戦場跡はみなみごとに整備され、戦場国立公園となって、訪ねる人々も多い。 [猿谷 要] Relations with Japan日米関係のあけぼのアメリカ合衆国と日本との関係は、ペリー来航の半世紀以上前から始まっていた。1791年(寛政3)にはアメリカ船2隻が紀州の島に寄航したし、1797年から1809年にかけては、イギリスの攻撃を恐れるオランダ東インド会社に雇われたアメリカ船が、毎年のごとく長崎に入港した。1820年代に入ると、アメリカの捕鯨船が大挙して日本近海に押しかけ、遭難して日本に漂着する船員もいた。1837年(天保8)には有名なモリソン号事件が起こる。それ以後、アメリカ海軍による日本開国への圧力はしだいに強まり、1853年(嘉永6)のペリー来航は、いわばその最終的な仕上げにほかならなかった。翌1854年、日米和親条約が結ばれて日本はアメリカに門戸を開き、1858年(安政5)には、初代駐日総領事タウンゼンド・ハリスとの間に日米修好通商条約が結ばれた。 日本側は1840年代から、オランダ書や中国書を通じて、アメリカ知識を育て始めていた。中浜万次郎や浜田彦蔵らの漂流民のアメリカ体験も、貴重な情報源になった。ペリーらの強圧的態度は激しい攘夷(じょうい)運動を巻き起こしたが、反面、西洋文明の力を思い知らせ、それを学び取らせる態度も日本人の間に生むことになった。さらにハリスは、アメリカが平和的で友好的な国であることを説得するのに成功、1860年(万延1)には最初の遣米使節が派遣され、その警護の名目で太平洋を渡った咸臨(かんりん)丸の一行ともども、アメリカ文明について見聞を広めてきた。勝海舟、横井小楠(しょうなん)、坂本龍馬(りょうま)など維新期の指導者も、アメリカの自由や共和の制度に共鳴するところが大きかった。 [亀井俊介] 蜜月時代明治初期から約4分の1世紀は日米蜜月(みつげつ)時代とよばれよう。イギリス、フランス、ロシアなどが明らかな形で東洋侵略国であったのに対して、アメリカはそういう罪科を背負わず、政治的にも、日米両国は衝突すべき利害関係をまだもっていなかった。この時期、日本は国民総がかりで「文明開化」運動を展開したが、西洋中でもっとも新しく開けた文明国のアメリカは、その最良のモデルの一つとなった。文明開化の最大の指導者福沢諭吉は、「純粋の共和政治にて、事実人民の名代人たる者相会して国政を議し、毫(ごう)も私なきは亜米利加(アメリカ)合衆国を以(もっ)て最とす。亜米利加は建国以来既に百年に近しと雖(いえ)ども、嘗(かつ)て国法の破れたることなし」(『西洋事情』1866~1870)と、ほとんど手放しでアメリカを賛美した。同様のアメリカ・イメージはほかにも多くの人が提示している。 文化面でみると、まずキリスト教が文明の根底をなすものとして広範な知識人をひきつけたが、その普及にもっとも働いたのはアメリカ人だった。横浜のブラウン塾やヘボン塾(後の明治学院)、熊本洋学校のL・L・ジェーンズ、札幌農学校(後の北海道大学)のW・S・クラークらは、多くの明治指導者を育てた。女子の高等教育は、ミッション・スクールがほとんど一手に引き受ける観さえあった。日本人のキリスト教学校もたくさんできた。内村鑑三がアメリカをキリスト教の「聖地」と思い込んだのも、ごく自然なことであった(『余は如何(いか)にして基督(キリスト)信徒となりし乎(か)』1895)。 世俗的な教育においても、アメリカの影響は大きかった。大学南校(後の東京大学)の教頭となったギドー・バーベック、文部省(現、文部科学省)顧問となったデビッド・マレーらは、日本の高等教育の中枢に参加していた。お雇い外国人教師も、アメリカ人が約3分の1を占めていた。教科書もアメリカのものが多かった。初等教育においてすら、文部省編纂(へんさん)『小学読本』巻1(1873)は『ウィルソン・リーダー』の翻訳だった。留学生も多くはアメリカへ行った。 広くいえば、この時代のもつ開化の雰囲気そのものに、アメリカの文明は働いていた。合理主義や実利思想は、当時、封建的制度からの解放感と結び付いていたが、ベンジャミン・フランクリンはその偉大な実践者だった。ロングフェローの詩(『人生讃歌(さんか)』など)さえ、能動的生き方の教訓として読まれた。アメリカは広い意味で「自由」の聖地でもあった。 [亀井俊介] 緊張の時代しかし、日本が天皇を上にいただく国家組織を確立し、帝権盛んなドイツの憲法をモデルとした帝国憲法(1889)や儒教的な教育勅語(1890)を発布するころまでに、アメリカの自由や共和の制度は日本の危険な対極となっていた。明治20年代、国粋主義の興隆とともに、文化的にも、日米は緊張時代とよぶべきものに入っていった。1891年(明治24)の内村鑑三の「不敬事件」による第一高等学校追放が象徴するように、キリスト教は排斥され、ミッション・スクールは衰退した。帝国大学を筆頭として、学問・思想の世界でも、ドイツ的な権威主義が重んじられ、ヨーロッパの高尚で精神的な「文化」に対し、アメリカは低俗で物質的な「文明」の国といった観念が広まった。文学の面でも、日本人の目はアメリカよりヨーロッパに向いた。 日米の緊張関係は、アメリカ・スペイン戦争とハワイ併合(1898)や日露戦争(1904~1905)の結果、両国がアジアではっきりした利害の衝突をみるようになり、さらに高まった。カリフォルニアの日本人移民に対する差別排斥問題は、それに拍車をかけた。1909年、アメリカの将軍ホーマー・リーHomer Lea(1876―1912)が『無知の勇気』 The Valor of Ignoranceという本で、日本人のアメリカ占領の可能性を警告すると、ただちに2種類の邦訳が出た。「日米もし戦わば」的な議論が、このころから太平洋の両側でなされるようになった。それでも、日本の制度や文化の主流から締め出されたり、それに反抗する者にとって、アメリカは有力な支えとなり続けた。キリスト教徒、自由主義者、社会改革家、在野的な教育者や学者、あるいは芸術的洗練を重んじる日本文学の伝統に思想性や野性を注入しようと思う文学者などの多くは、アメリカに学ぶところが大きかった。 日米の緊張に一時的な融和が訪れたのは、「大正デモクラシー」時代である。第一次世界大戦(1914~1918)でドイツは敵国となったし、時代思潮たるデモクラシーの総本山はアメリカである。文化面でも、アメリカに倣(なら)った「新教育」が入ってきたし、プラグマティズムも盛んに伝えられた。デモクラシーの詩人ウォルト・ホイットマンが大いに喧伝(けんでん)されもした。 しかし1924年(大正13)、アメリカにおける「排日移民法」の成立は、日本人の間に広範な反米感情を生んだ。また日本の強引なアジア大陸武力進出は、アメリカの強い反対を招いた。日本の軍国主義指導者にとって、アメリカはその政治から文明までひっくるめて敵性のものとなった。そしてついに、日米は緊張時代を通り越し、1941年(昭和16)から1945年にかけて、戦争時代に突入した。アメリカとその国民は「洋鬼(ヤンキー)」と称された。 [亀井俊介] 揺れる日米関係と強まる同質化第二次世界大戦後の日本は、アメリカの占領とリーダーシップによって、第二の文明開化をしたといえよう。文明の根底は、今度はデモクラシー教だった。民主主義の旗印のもとに、思想も教育も文化も、つまるところアメリカをモデルとし、そのミニアチュアをつくろうとしてきた観がある。この第二の蜜月関係は、日本の独立回復後、またもや何度かの危機にあい、さまざまな形で反米・嫌米運動も起こって、断続的に緊張関係の色合いを強めてきた。そして日米経済摩擦の果て、文化摩擦も説かれている。 アメリカ合衆国と日本との関係は、こうして、日本側の視点からいうと、拝米と排米の間を大きな振幅をもって揺れてきた。これからも揺れ続けるように思われる。ただし、この底で、ほとんど一貫して結び付きを強めてきた面もある。日常的な生活文化や大衆文化の面である。最初の文明開化時代から、日本人の生活は著しく西洋化したが、そのかなりの部分はアメリカ化であった。小麦粉をメリケン粉と称したのは、食生活における一つの例にすぎない。ビール、缶詰などもアメリカからきた。電灯、電話、市電、自動車、あるいは百貨店などもそうである。さらには家庭だんらんを重んじる文化住宅やその生活も、アメリカをモデルとした部分が大きい。蓄音機、社交ダンスもアメリカからきた。野球を筆頭として、スポーツにもアメリカ伝来のものが多い。やがて映画がすっかり日本人の心をとらえた。ラジオ放送も、ジャズも同様である。昭和初期には、アメリカのフラッパーに倣(なら)ったモガやモボが都会を闊歩(かっぽ)するようにもなった。 アメリカ的な生活は、「俗悪」として伝統派から顰蹙(ひんしゅく)を買い、軍部からいったんは抑圧もされたが、第二次世界大戦後ほとんど自発的に再生し、ますます激しい勢いで日本人の間に広まった。占領軍のいわゆる救援物資によって飢えをしのいだ時代から、白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫を「三種の神器」としてあがめた1960~1965年ごろ、カラーテレビ、ルームクーラー、マイカーのいわゆる「3C」を追い求めた1965~1970年ごろを経て、Tシャツやジーンズがまったく日常化し、ディスコもエアロビクスもありきたりの風俗となる時代まで、アメリカの生活文化を手に入れることが日本人の努力目標であり続けた。そしていまや、恋愛や結婚の仕方から、高度な機械技術まで、アメリカの影響があまりにも浸透したため、それを影響として意識しなくなっているほどである。日米関係の大きな動揺にもかかわらず、日本人の生活はこのようにしてアメリカとの同質性を広め、両国は日常的な文化のレベルで共通した地盤にたつようになってきた。そして現在、共通した問題も抱えているといえよう。単に政治や経済の分野に限らず、社会や文化においても、同質の目標と悩みとをもっている。日本とアメリカとのさまざまな摩擦は、したがって両国文化の異質性とこの同質化との両方を踏まえて考察、検討されなければならない。部分的な局面を観念的に裁断するのでなく、両国の関係をトータルにとらえ、その相互に持続的に利益となる方向を現実的に探求していくことが、これからますます必要であろう。 [亀井俊介] 『齋藤眞・金関寿夫・亀井俊介・岡田泰男監修『アメリカを知る辞典』(1986・平凡社)』 ▽ 『トクヴィル著、岩永健吉郎訳『アメリカにおけるデモクラシー』(1990・研究社)』 ▽ 『亀井俊介監修『アメリカ』(1992・新潮社)』 ▽ 『ハワード・ジン著、猿谷要監修『民衆のアメリカ史』全3巻(1993・TBSブリタニカ)』 ▽ 『齋藤眞著『アメリカとは何か』(1995・平凡社)』 ▽ 『本間長世著『思想としてのアメリカ』(1996・中央公論社)』 ▽ 『M・B・ノートン他著、本田創造監修『アメリカの歴史』全6巻(1996・三省堂)』 ▽ 『ジョン・ボドナー著、野村達朗他訳『鎮魂と祝祭のアメリカ』(1997・青木書店)』 ▽ 『ビル・ブライソン著、木下哲夫訳『アメリカ語ものがたり』上下(1997・河出書房新社)』 ▽ 『正井泰夫著『日米都市の比較研究』(1977・古今書院)』 ▽ 『渡辺光編『アングロアメリカ』(『世界地理13』1980・朝倉書店・所収)』 ▽ 『飽戸弘著『アメリカの政治風土』(1980・日本経済新聞社)』 ▽ 『三宅一郎・山川雄巳編『アメリカのデモクラシー』(1982・有斐閣)』 ▽ 『砂田一郎著『現代アメリカ政治 第3版増補』(1989・芦書房)』 ▽ 『宇佐美滋著『揺れるアメリカ外交』(1990・バベル・プレス)』 ▽ 『阿部齊著『アメリカの政治』(1992・弘文堂)』 ▽ 『阿部齊著『アメリカ現代政治』第2版(1992・東京大学出版会)』 ▽ 『五十嵐武士・古矢旬・松本礼二編『アメリカの社会と政治』(1995・有斐閣)』 ▽ 『嘉治元郎編『アメリカの経済』(1992・弘文堂)』 ▽ 『B・エーレンライク著、中江桂子訳『「中流」という階級』(1995・晶文社)』 ▽ 『横田茂編『アメリカ経済を学ぶ人のために』(1997・世界思想社)』 ▽ 『榊原胖夫他著『アメリカ経済をみる眼』(有斐閣新書)』 ▽ 『猿谷要編『総合研究アメリカ第1巻 人口と人種』(1976・研究社)』 ▽ 『大橋健三郎編『総合研究アメリカ第6巻 思想と文化』(1976・研究社)』 ▽ 『ラッセル・ナイ著、亀井俊介訳『アメリカ大衆芸術物語』全3巻(1979・研究社)』 ▽ 『J・L・ブラウン他著、青木克憲訳『現代アメリカの飢餓』(1990・南雲堂)』 ▽ 『ダニエル・J・ブアスティン著、新川健三郎訳『アメリカ人』上下(1992・河出書房新社)』 ▽ 『明石紀雄・飯塚正子著『エスニック・アメリカ』新版(1997・有斐閣)』 ▽ 『齋藤眞・本間長世・亀井俊介編『日本とアメリカ――比較文化論』全3巻(1973・南雲堂)』 ▽ 『亀井俊介著『メリケンからアメリカへ――日米文化交渉史覚書』(1979・東京大学出版会)』 ▽ 『開国百年記念文化事業会編『日米文化交渉史』全6巻(1980・原書房)』 ▽ 『シーラ・ジョンソン著、鈴木健次訳『アメリカ人の日本観』(1986・サイマル出版会)』 ▽ 『細谷千博・本間長世編『日米関係史・新版』(1991・有斐閣)』 ▽ 『グレン・S・フクシマ著、渡辺敏訳『日米経済摩擦の政治学』(1992・朝日新聞社)』 [参照項目] |||||||||||||| |||||| |||| |||||| ||||||||||||||| | |[補完資料] |"> United States flag ©Shogakukan Illustration/Shogakukan Creative "> アメリカ合衆国位置図 ©Shogakukan "> アメリカ合衆国の州区分 ©Shogakukan "> アメリカ合衆国の地形区分 ©Shogakukan "> アメリカ合衆国の土壌分布 ©Shogakukan "> アメリカ合衆国の地誌区分 コロラド川によって刻まれた大峡谷。名称は、スペイン人のカルデナスがスペイン語で「Grand Cañon(大峡谷)」とよんだことに由来するという。世界自然遺産「グランド・キャニオン国立公園」(アメリカ・1979年登録) アメリカ アリゾナ州©Shogakukan "> グランド・キャニオン 1815~29年に再建されたアメリカ合衆国大統領の公邸。J.ホーバンの設計による、新古典様式の白亜の殿堂である。地上4階、地下2階で、132室を有する。アメリカ ワシントン©Shogakukan "> The White House 首都ワシントンの中心にあるアメリカの議事堂(ユナイテッド・ステーツ・キャピトル)。1793年起工後、改修・増築ののち1861年にほぼ現在の姿となった。アメリカ ワシントン©Shogakukan "> Capitol ニューヨーク証券取引所(写真右端)をはじめ、銀行、証券会社などが建ち並ぶ、アメリカの金融の中心地。アメリカ ニューヨーク©NetAdvance "> Wall Street 証券市場の代名詞「ウォール街」にある世界最大の証券取引所。設立は1792年。古代ローマの神殿を思わせる現在の建物は1903年に建てられた。アメリカ ニューヨーク©NetAdvance "> New York Stock Exchange Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
|
北アメリカ大陸中央部を占める連邦制共和国。略号USA。単にアメリカともいう。本土48州にアラスカおよびハワイの2州を加えた計50州と、1首都地区(コロンビア特別区District of Columbia)からなり、海外にプエルト・リコ、バージン諸島、東サモア、グアムなどの諸領をもつ。面積962万9091平方キロメートル(国連統計2002年)、人口2億9939万8000(2006年推計)、3億0875万(2010年推計)。 [渡辺 靖] 総論国名アメリカ大陸には、1607年以来、相互に関係性の薄い13のイギリス領植民地が存在していたが、18世紀後半にイギリス本国との対立が深まるにつれ、相互に連合する必要が生じ、しばしばUnited Colonies of America(アメリカ連合植民地)として行動した。やがて1776年7月4日の独立宣言においてUnited States of America(アメリカ諸邦連合)と称され、1777年11月に大陸会議で採択(1781年3月に正式発効)した連合規約においてThe United States of Americaと規定された(1853年の日米和親条約以来、日本ではアメリカ合衆国と訳されている)。1787年に起草された合衆国憲法において、各state(州)に一定の範囲内での国家性が付与され、かつその上位の連合組織として、1789年4月に連邦政府が発足した。二重国家的色彩の強い連邦制であること、そして君主の統治しない共和国(リパブリック)であり、歴史的にも前例のない規模の大きさを有する共和国であることが合衆国の特徴である。 [渡辺 靖] 地理的位置づけアメリカ合衆国は日本の約25倍の面積を有する(カリフォルニア州だけでも日本をやや上回る)。しばしば大西洋は合衆国にとって「無償の安全保障」の源泉だったと称される。大西洋をへだてることによってヨーロッパ列強の軍事的・政治的・文化的影響が少なかったことが、合衆国のいわゆる孤立主義外交を可能にするとともに、ヨーロッパ文明と異なるアメリカ文明という意識をはぐくんだという意味である。広大な大陸国家である合衆国は世界一の農業国として発展し(2012年時点でも世界最大の食料生産国である)、19世紀末には世界一の工業国になった。その高度な生産力を背景に、そして1898年の米西戦争を契機に合衆国は海洋国家かつ太平洋国家としての性格を色濃く帯びるようになった。第二次世界大戦後は「西側陣営の盟主」として、そして冷戦終結後は「唯一の超大国」として影響力を行使している。しかし、近年は、中国やインドなど新興国の台頭や2008年秋の金融危機など、合衆国の国力の相対的低下が指摘される。 [渡辺 靖] 歴史的特質アメリカ合衆国は、ヨーロッパのように中世、封建制、絶対主義体制を経ることなく、ほぼ近代とともに始まった国である。それはまた、イギリス国王の支配を脱し、貴族が存在しないことを背景に、人類史上初の民主的共和国をつくり上げた実験国家でもある(アメリカ合衆国独立はフランス革命勃発の13年前)。加えて、広大な土地を有していたことや、連邦政府の役割が限定的だったこともあり、独立自営(個人主義)、機会均等(平等主義)、自由競争(自由主義)、そして成功(繁栄)といった考えが強調されるようになった。換言すれば、こうした「アメリカ的価値」によって「多様性のなかの統一」を図ろうとしてきたともいえる。 なお、近代的価値との親和性から「アメリカ的価値」を「普遍的価値」と同一視する傾向も見受けられる。そこに起因する形で、とりわけ国外に対しては、ある種の自己優越に満ちた、選民的ないし宣教師的な使命感を帯びすぎているようにみえることも少なくない。いわゆる「アメリカ例外主義」ともいわれる考えであるが、これは19世紀の(ヨーロッパからの)孤立主義を支えた論理であると同時に、20世紀におけるアメリカの世界的な拡張主義を支えた論理でもあった。 [渡辺 靖] アメリカ人とはイギリスからの植民が始まった17世紀初頭以来、アメリカへの移民は圧倒的にイギリス系(いわゆるWASP:白人アングロ・サクソン系プロテスタント)が主流だったことから、他の移民もイギリス系の文化に従うべきだとする「アングロ・コンフォーミティ(同化)」論が有力だった。 しかし、東欧や南欧、アジアからの新移民が急増するにしたがい、さまざまな人種や民族が溶けて「アメリカ人」になるという「るつぼ(メルティング・ポット)」論が社会統合の新たなメタファー(たとえ)となる。さらに第一次世界大戦前後になると、異なる人種・民族の「モザイク」としてアメリカはイメージされ、いわゆる「サラダ・ボウル」論が隆盛になる。作家ルイス・アダミックLouis Adamic(1898―1951)がウォルト・ホイットマンの「多民族からなる一つの国家a nation of nations」を引用しながら述べた「多様性は力なり」というレトリック(言い回し)が生まれたのもこのころである。 しかし、「るつぼ」論も「サラダ・ボウル」論も現状肯定的・予定調和的であり、アメリカ社会に厳存する差別や抑圧の構造をうまく説明できなかった。とりわけ1960~1970年代は、公民権運動のみならず、若者を中心とする既成の価値観への対抗文化が花開き、自然回帰を提唱したヒッピー運動や学生運動、ベトナム反戦運動が盛り上がりをみせた。支配権力に敏感な思潮のなかから「多文化主義」(マルチカルチュラリズム)という考えが生まれ、1980年代以降、リベラル派によって支持された。 多文化主義は文化間の序列を否定し、異文化の共存・共生を積極的に推進してゆこうとする考えを意味する。とくに、人種・民族、宗教、ジェンダー、階級、身体性などの面で弱い立場にある人々の権利を積極的に承認することを目標とした。職場で一定数の黒人ないしその他の少数民族を雇うことや、学校に一定数のマイノリティを入学させる「アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)」はその一例である。しかし、多文化主義が分離主義的だとする批判が保守派を中心に高まり、リベラル派との間の緊張関係が続いている。 [渡辺 靖] 国旗と国歌社会的統合の象徴として国旗や国歌も重要な機能を果たしている。1777年6月、独立13州を示す紅白の横縞、各州を表す左上の青地に白の星よりなる星条旗の原型が制定された。これまでにデザインは27回更新され、1960年の独立記念日(7月4日)より現在のバージョンが用いられている。星の数は州の数と同じ50である。国歌については、法律家フランシス・S・キイFrancis Scott Keyが1814年の米英戦争中に作詞した「星条旗Star-Spangled Banner」が一般に使用され、1931年3月に連邦議会法によって国歌として指定された。国旗と国歌のほかにも「独立宣言」や「合衆国憲法」なども統合の象徴として機能している。 17世紀前半にニューイングランドへ渡ったキリスト教プロテスタント指導者ジョン・ウィンスロップが船上で説いた「我々は丘の上の町City upon a Hillになるべき」というメタファーもしばしば用いられる。また、「丸太小屋からホワイトハウスへ」を体現したリンカーンに象徴される立身出世の「アメリカン・ドリームAmerican Dream」の言説も繰り返し語られては、国民を鼓舞し続けている。そのリンカーンがアメリカを形容した「地上の最後で最良の希望the last, best hope of earth」ということばや、国立戦没者墓地の奉献式で行ったゲティスバーグ演説(1863)のなかの「人民の、人民による、人民のための政治」も同様である。 [渡辺 靖] 第3世紀のアメリカ合衆国アメリカ合衆国が1976年7月4日に独立200年を迎えて以来、2011年7月で35年目となった。この第3世紀目に入ってからのアメリカの歴史はこれまで激動そのものであった。 外交においては、1960年代から本格化していたベトナム戦争が泥沼化し、「アメリカの平和(パックス・アメリカーナ)」を享受してきたアメリカ人にとっては深刻な挫折(ざせつ)感を味わうことになった。その後、1980年代から1990年代にかけて、アメリカの外交的な威信は復活する。東西冷戦は1990年の東西ドイツの再統一、翌1991年のソ連解体により自由主義陣営の勝利という形で幕を閉じ、冷戦時代の二極対立構造からアメリカを中心とする単極構造に世界は変貌(へんぼう)した。これを象徴するのが、1990年のイラクのクウェート侵攻に端を発する湾岸戦争の勝利である。 しかし、アメリカ中心の単極構造下での新しい国際秩序は安定的なものとはほど遠かった。1990年代にはソマリア、コソボ、ボスニアなどの各地で局地的紛争が頻発した。2001年9月11日には、イスラム過激派組織アルカイダが実行したアメリカ同時多発テロでアメリカは大きく傷つき、「テロとの戦い」の名のもと、外交政策は一変した。2001年10月開始のアフガニスタンへの報復攻撃、2003年3月開始のイラク戦争は、形の上では多国籍軍に参加した国々との「有志連合」であるが、実際はアメリカの単独行動主義に基づいていた。 2009年に大統領に就任したバラク・オバマは国際協調主義を前面に打ち出した。しかし、2011年5月には、アルカイダのリーダーで、同時多発テロの首謀者として国際手配されていたオサマ・ビンラディン殺害で「テロとの戦い」がどのように変貌していくのかを含め、第3世紀中盤のアメリカ外交はふたたび大きな転換点に直面している。 国内においては、公民権運動や男女の平等など1960年代から続いていたさまざまな社会改革の波は1970年代なかばに行き詰まった。アフリカ系住民や先住民、女性に対する政府主導のアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)は、白人男性に対する「逆差別」を生んだ。 また、1970年代末から1990年代にかけて人種、宗教、民族性など特定のカテゴリーに属する人々に対する憎悪または偏見に基づく犯罪である「ヘイトクライム」(憎悪犯罪)への法的規制が各州で導入され、通常の犯罪による刑罰より厳しい罰則が適用された。しかし、自分とは異なったものに対する憎悪という犯罪者の「心の問題」を基準に罰則を重くすることは容易ではなく、ヘイトクライム関連の法律の内容は各州でばらばらである。 一方、1965年の移民法改正に端を発する中南米からのヒスパニック系(ラテン系)移民やアジア系移民の増加が1980年代から目だっており、アメリカの「顔」が大きく変貌しつつある。とくにラテン系住民の人口増加のペースは目覚ましく、1980年から2000年までの20年間で40%以上増加し、2000年の国勢調査ではラテン系・ヒスパニック系住民数がアフリカ系住民数をわずかながら抜き、最大の人種マイノリティとなった。国勢調査局によれば、アメリカの総人口のなかでの白人の割合は2000年時点で70%程度であるが、2050年には50%程度に下がり、白人が「多数派」の地位を失う状況が予想され、「少数派」という概念そのものが大きく変わるとみられている。 移民という「新しい血」がアメリカに多様性をもたらし、多様性が国の活力を生み出すという信念は、アメリカの政治権力が分散されているというプルーラリズム(多元主義)を是とする論理につながっていく。硬貨などに刻まれている国是の「エ・プルビウス・ウヌムE PLURIBUS UNUM」(多様のなかの統一)は、アメリカの民主主義を支える根底に移民を受け入れる姿勢があることを示している。ただ、「移民はアメリカに同化できない」という文化的な違いから移民を排斥しようというネイティビズム(反外国人感情)的な世論も依然として共存している。 また、人工妊娠中絶や同性愛をめぐる倫理問題、福祉、貧困、教育など、政策分野における政府の役割についての保守派とリベラル派の間にあるさまざまな対立は、保守派の台頭が目だった1980年代から加熱してきており、21世紀に入ってからは保守とリベラルが激しい対立をしながら二極分化する「二つのアメリカ」論が台頭している。今後、アメリカの「顔」が変わりつつあるなか、どのようにしてこの対立を超えて共存していけるかが大きな課題となっている。 [前嶋和弘] 自然地形・地質合衆国の地勢は、大別すると次の四つの部分に分けられる。(1)東部の侵食の進んだ古い高地。(2)アパラチア東側からメキシコ湾岸に及ぶ海岸平野。(3)ミシシッピ川流域の広大な中央平原。(4)西部の新しい高峻(こうしゅん)な山地。また、合衆国地質調査所は、地質・地形の組合せによって、全国を八つの大地形区、25の中地形区、86の小地形区に区分している。ここでは合衆国地質調査所の八大地形区を中心に略述する。 (A)ローレンシア台地 カナダ楯状地(たてじょうち)が張り出した南端にあたり、先カンブリア界が露出する地球上もっとも古い陸地の一部。第四紀の氷期に大陸氷河に覆われた侵食の進んだ高原状台地。高品位で名高いメサビ鉄山がある。 (B)コースタル・プレーン(海岸平野) ニューヨーク州南部の大西洋岸からメキシコ湾岸に展開する平野。古い海成層が緩やかに海へ向かって傾斜し、その上に新期堆積(たいせき)物がのっている。大西洋岸ではアパラチアから多くの河川が注ぎ、山麓(さんろく)に滝線(たきせん)都市を発達させ、海岸では沈降した河口がエスチュアリー(三角江)をつくり、ニューヨークなど多くの港湾都市を育てた。メキシコ湾岸に向かうほど平野が幅を増して、豊かな農業地帯となる。ミシシッピ川河口には典型的な鳥趾(ちょうし)状三角州がみられる。 (C)アパラチア高地 合衆国東部に北東から南西に走る、主として古生代の岩石よりなる古い侵食された褶曲(しゅうきょく)山地。東の古期アパラチア、中央の新アパラチア、西のアパラチア台地の3列に分かれる。古期アパラチア南部がもっとも高く、ここに最高峰のミッチェル山(2037メートル)がある。アレゲニー(アパラチア)高原には世界最大の瀝青(れきせい)炭田(ペンシルベニア炭田)があり、合衆国繁栄の基礎となった。 (D)内陸平野 アパラチアに続く東部の低い内陸台地、中央低地、西のグレート・プレーンズに大別される。中央低地は古生代のほぼ水平な地層からなる構造平野で、ケスタ地形をなす。五大湖は、大陸氷河の堆積物とケスタの低地との間に水をたたえたものである。グレート・プレーンズは中生代第三紀層の高原で、西へ行くほど高度を増す。 (E)内陸高地 アレゲニー高原の延長がミシシッピ川の流れる中央平原を挟んでふたたび現れたのが内陸高地で、オザーク台地では鉛、亜鉛を産する。 (F)ロッキー山系 古生代のロッキー地向斜がララミー変動で隆起し、準平原化したのち、第三紀末のカスケード変革によって急上昇したもので、標高4000メートルを超える。南部ロッキー、ワイオミング盆地、中央ロッキー、北部ロッキーに分かれ、数列の山脈とその間の縦谷が並列し、広い所は盆地状をなす。北部には氷河が現存し、カナダにまたがってグレーシャー(氷河)国立公園に指定されている。 (G)山間台地 火山性の玄武岩の厚い岩層からなるコロンビア台地、古生代と中生代の古い地層がほぼ水平に分布するコロラド台地、その中間の大盆地に分けられ、大峡谷や乾燥砂漠など特異な景観がみられる。 (H)太平洋山系 シエラ・ネバダ山脈、カスケード山脈、コースト・レンジス(海岸山脈)、およびその間に挟まれた地溝とからなる。太平洋火山帯に属し、多くの火山がある。(F)(G)(H)はあわせてコルディエラ山系とよばれて環太平洋造山帯の一部をなし、合衆国全幅の約3分の1を占める。 [伊藤達雄] 気候ツンドラ(永久凍土帯)とタイガ(寒帯針葉樹林)のアラスカ、常夏の島ハワイを別にして、アメリカ合衆国本土の大部分は温帯と亜寒帯(冷帯)に属し、フロリダ南半に熱帯がわずかに存在する、ほぼ中緯度気候帯の国である。ここでは本土の気候について述べる。 気候は地形、海、海流、風などの特性によって影響されるとともに、合衆国のように東西が4500キロメートルにも及ぶ陸塊では沿岸と内陸でも大きな差異が生じるので、国内には多様な気候タイプがみられる。大観すると、大陸の東西両側にアパラチアとロッキーの山系があって海からの影響を内陸に届きにくくしており、とくにロッキー山系は高峻(こうしゅん)でその内側に広い乾燥帯を形成している。これに対して南北方向には、北のカナダ方面、南のメキシコ方面からの影響を防ぐ地形的障害がほとんどないので、それだけ冬は北極気団が南下しやすく、五大湖沿岸から中部内陸まで寒冷気団が流れ込み、夏はメキシコ湾から奥地までしばしばハリケーンを伴う湿った気団が北上して降雨をもたらす。また海岸部では、太平洋岸がカリフォルニア海流(寒流)に洗われるのに対して、大西洋岸ではメキシコ湾流(暖流)が北上するので、同緯度であっても気温や降水量に差がある。さらに大陸の西岸ではウェスタリー(偏西風)、東岸ではモンスーン(季節風)が卓越して、その差を拡大している。合衆国のおもな気候区としては次の八つがあげられる。 (1)フロリダ半島南半の熱帯気候区 合衆国本土で唯一の熱帯で、サバンナ気候(Aw)の特性をもつ。明瞭(めいりょう)な雨期と乾期があり、冬の避寒地として最適。豪華なリゾートホテルの並ぶマイアミ・ビーチは世界的な観光保養地である。半島南端に近いエバーグレーズ国立公園は、珍しい熱帯樹の繁る湿地帯と多種の野鳥の生息地として有名。 (2)東部の季節風気候区 東部大西洋岸からメキシコ湾に及ぶコースタル・プレーンから、アーカンソー州、オクラホマ州の内陸までの広い範囲に広がるモンスーン気候(Cfa)である。四季が明瞭で、とくに大西洋岸中部は日本と似ており、ニューヨークは仙台とほぼ同様の気候環境である。メキシコ湾岸は亜熱帯に近く、その内陸では乾期と雨期の交代や高温が綿花育成に好適で、世界的な綿花地帯となっている。 (3)大陸北西部の西岸海洋性気候区 同じ湿潤温暖でも、ワシントン州、オレゴン州の太平洋岸は偏西風の影響を強く受け、気温の年較差が小さく、冷涼で降水量もほぼ年間平均している西岸海洋性気候(Cfb)である。この気候型は日本にはないもので、深い緑と四季の花が美しい温和な気候である。 (4)北東部五大湖周辺の亜寒帯(冷帯)気候区 ニュー・イングランドから内陸グレート・プレーンズの境までは亜寒帯気候(Dfa, Dfb)で、本土の4分の1以上を覆う。ニュー・イングランドは北海道と似た気候であるが、内陸に進むにしたがって、気温の年較差、日較差が拡大し、降水量も少なくなり、大陸性気候の特性が強まる。南部では夏の高温を利用してトウモロコシ、冬小麦が栽培されるが、北へ向かうにつれて夏も冷涼となり、春小麦、果樹、酪農地帯となる。内陸の冬の寒さは厳しく、シカゴで零下20℃ぐらいは珍しくない。 (5)カリフォルニア州の地中海性気候 大陸西岸の中緯度地域には、夏季に乾燥し冬季に降水のある特異な地中海性気候(Cs)がみられる。そのため、夏季の乾燥に強い柑橘(かんきつ)類、ブドウなどが栽培され、灌漑(かんがい)用水の得られる所では豊かな農業が営まれる。また、有名なサンフランシスコの霧の風景は、カリフォルニア海流が南下してきて暖かい空気に触れ、霧が発生し、それが海風に運ばれて流れ込むものである。 (6)グレート・プレーンズの乾燥草原 西経100度を越えて内陸に入るとほとんど雨の降らないステップ(短草草原)気候(BS)となる。ウシの放牧をするカウボーイの天地である。わずかな降水を利用する乾燥農法の発達で耕地化されている所も点在する。 (7)砂漠気候 ロッキー山系と太平洋岸山系の間は海から隔絶され、しかも中緯度高圧帯に位置するため砂漠気候(BW)となっている。ソルト・レーク(塩湖)やモハーベ砂漠などが有名。 (8)高山気候 ロッキー山脈、カスケード山脈などの高所には、年中氷雪に覆われた高山気候(H)がある。南ロッキーには合衆国最高峰のエルバート山(4399メートル)がある。 [伊藤達雄] 生物相合衆国本土の植物相は、東半分を占める森林、内陸大平原の草原、太平洋岸北部の森林、南部の乾燥半砂漠・砂漠の四つに大別される。東部の森林はさらに、フロリダ半島南部のイトスギを主とする熱帯系、その北のマツ類を主とする常緑針葉樹系、さらにその北の落葉広葉樹と常緑針葉樹の混交系、ニュー・イングランド南部から中央平地南部にかけての落葉広葉樹系、ニュー・イングランド北部から五大湖周辺のカエデ、トネリコ、ユリノキ、ブナなどの落葉樹に、トウヒ、モミなどの常緑針葉樹が混じる冷帯系、五大湖以北の寒帯系に分けられる。暖地性植生の平地は、現在ではほとんど耕地化されて肥沃(ひよく)な農地が展開している。 ミシシッピ川を越えて西へ進むと森林はまばらな堅木となり、イチゴツナギ属のケンタッキー・ブルーグラスとよばれる長草の草原となる。これがプレーリーである。さらに西のグレート・プレーンズではグラマグラス、バッファローグラス、ニードルグラスなど、丈の短い草原の間に低木が散見される景観となる。プレーリーは農地に、グレート・プレーンズは牧場としておもに利用されている。 ロッキー山系から太平洋岸にかけては、地形、気候が複雑で、植物相も多様である。北緯50度以南の低地では、マツ、モミが主で、ピュージェット湾周辺には、カシ、モミの混交林もある。コロンビア高原上は樹木が少なく短草のプレーリーがある。大盆地、ワイオミング盆地以南の山間高地や盆地は乾燥気候で、高地には樹木が生えるが、低地へ下がるにつれて気温があがり、低木、短草となり、南部ではサボテンが唯一の植生の砂漠となる。カリフォルニア中部の地中海性気候区では照葉樹やメスキートとよぶマメ科の植物が主であるが、夏は乾燥のため山肌は茶色に枯れる。 合衆国本土の動物相は、植生分布と同様な特性を示すが、全土にわたって生息するものとしては、バージニアシカ、アメリカクロクマ、オオヤマネコ、ピューマ(アメリカライオン)、カワウソ、ミンク、ビーバー、ジャコウネズミ、ハイイロオオカミなど。西部草原のコヨーテ、アメリカバイソンなどは固有種として知られ、保護獣に指定されている。動物や鳥類は、全体としてはアジア系に近いが、海生動物では大西洋岸と太平洋岸ではかなり明瞭な相違があり、首が長く耳が突き出たカリフォルニアアシカは大西洋岸には生息しない。 [伊藤達雄] 地誌
[伊藤達雄] 北東部大西洋岸この地域は、合衆国の植民史のなかではもっとも伝統を誇るニュー・イングランド6州と、合衆国の玄関口であるとともに繁栄のシンボルである世界最大の都市ニューヨーク、それに首都ワシントンを含み、メガロポリスとよばれる一大都市化地帯である。南北約800キロメートル、日本でいえば東京から広島県尾道(おのみち)ぐらいまでの本州主要部に相当する範囲である。大西洋に面する海岸は沈水地形で、アパラチア山脈から注ぐ各河川は河口にエスチュアリー(三角江)を形成し、これがボストン、ニューヨーク、ボルティモアなど多くの良港の立地要因となった。 ニュー・イングランドの中心ボストンは1630年に清教徒によって創設された港町で、独立戦争の発端となった茶会事件はここで起こった。合衆国最古で世界的権威をもつハーバード大学をはじめ多くの大学や博物館など歴史的建造物があり、古く落ち着いた町並みはヨーロッパを思わせる。周辺は冷涼な気候に加えて大陸氷河の侵食を受けたため土壌はやせていて農業は振るわないが、酪農が盛ん。沿岸は世界四大漁場の一つで、コッド(タラ)岬の名が示すように、ニシン、タラなどの漁業は現在も重要産業である。グロスター、プロビデンスなどは漁港としても名高く、ボストンの埠頭(ふとう)には魚介類を専門とするレストランが並び、遠路をわざわざ訪れる観光客も多い。工業化の歴史も合衆国最古で、繊維、造船、皮革、機械などが合衆国の発展を支えてきたが、近年は大学と企業の協同による研究開発部門が集中して頭脳産業地帯への脱皮が図られている。 ニューヨークは、1825年のニューヨーク州バージ運河(エリー運河)が開通して以来、大西洋からアパラチア山脈を横断して内陸へ通ずる唯一の水路の入口となり、急速に発展、ボストンにかわって合衆国の表玄関となった。マンハッタン島の摩天楼は、ヨーロッパと合衆国の経済交流の接点の象徴であり、世界経済の焦点としての役割はいまも衰えていない。その南に続くフィラデルフィア、ボルティモアも港湾と工業を核とする都市である。首都ワシントンは南北戦争後、北部と南部の境界に計画的につくられた政治都市であることは広く知られている。都市全体が公園といってよく、首都として設計された都市の代表の一つである。総じてこの地域は、合衆国の発祥の地であるばかりでなく、経済、政治、文化のいずれの面からみても合衆国の中枢部であり、合衆国のすべてが凝集しているといって過言ではない。 [伊藤達雄] 中西部五大湖周辺五大湖周辺は、近代工業の成立発展に不可欠であった石炭と鉄鉱石の資源に恵まれ、なかでも製鉄原料として最適の強粘結性炭を産するアパラチア炭田、良質の鉄鉱石で知られるメサビ鉄山は世界的にも大規模なものである。これを五大湖の水運で結び付け、内陸のピッツバーグをはじめ、湖岸のシカゴ、ゲーリー、クリーブランドなどを含む世界最大の鉄鋼業地帯を発達させた。自動車工業のデトロイト、化学工業のアクロンなどもその基盤のうえに成立したものである。ニューヨークへつながるニューヨーク州バージ運河、大西洋へのセント・ローレンス水路の開発も発展に大きく貢献した。しかし、1970年代以降、鉄鋼業や自動車産業が日本やアジア諸国の追い上げを受け、工業の主流が精密機械や電子工業などに移行するにつれて、産業構造の転換がこの地域の大きな課題となっている。 一方、五大湖南西部からミシシッピ川上・中流は、プレーリー(長草草原)地帯とよばれる合衆国でももっとも豊かな農業地帯である。北部のミシガン州からウィスコンシン州にかけての地帯はやや冷涼で、牧草栽培による酪農が主であり、ミルウォーキーがその中心である。その南西のオハイオ、インディアナ、イリノイ、アイオワ、ネブラスカ、カンザスなどの諸州は、地味(ちみ)が肥え、夏の高温がトウモロコシや小麦、大豆などの栽培に適し、トウモロコシを飼料として肉牛やブタを飼育する。これがコーンベルト(トウモロコシ地帯)とよばれる商業的混合農業地帯である。農畜産物は外国にも輸出され、とくにトウモロコシ、大豆の輸出先として日本は最大である。工業と農業という合衆国産業の特徴を担うこの地域の中心は、合衆国第三の大都会シカゴで、同市は東部と西部を結ぶ交通都市でもあり、鉄道網、航空網の路線集中では合衆国第一として知られているが、人口は1950年の362万人をピークに以後減少を続け、1990年には278万人となってロサンゼルスに抜かれる。 [伊藤達雄] 南部メキシコ湾岸大西洋岸南部からフロリダ半島、メキシコ湾岸を含み、合衆国のほぼ4分の1にわたる広大な地域である。かつて黒人労働を主体とする「プアー・サウス」(貧しい南部)といわれた地域であるが、近年は工業化の新天地として見直され、「ニュー・アメリカ」「輝ける南部」「サンベルト」などと呼び名も新しく、躍進が著しい。この地域の東部大西洋岸はフロリダを除いて独立戦争にも参加した建国州であるが、南北戦争では奴隷制を支持して北部に対抗した。いまもコースタル・プレーンとアパラチア南部山麓(さんろく)ピードモント台地に、綿花、タバコを主作物とする農業が盛んである。 フロリダは1819年にスペインから買収された州で、亜熱帯気候を生かした暖地性園芸農業が行われる。大規模な砂州が発達した大西洋岸は景観もすばらしく、合衆国最大の避寒地が出現しており、マイアミ海岸に並ぶ豪華なホテル群は世界的に有名である。中部のケンタッキー、テネシー、アラバマ、ミシシッピの4州はいわゆるコットンベルト(綿花地帯)の中心部である。とくにアラバマ、ミシシッピはミシシッピ川を挟んで対岸のアーカンソー、ルイジアナなどの州とともに、ディープ・サウス(深南部)とよばれる農業依存度の高い地域で、黒人への差別意識も根強く残っている。 こうした伝統をもつ南部ではあるが、近年大きく変貌(へんぼう)しつつある。フロリダの観光保養地としての発展に加え、ジョージア、アラバマ、テキサス、オクラホマといった諸州で、広い土地と豊富な労働力、温暖な気候が再評価されるとともに、大規模空調設備の普及によって新しい電子、精密、航空、宇宙などの諸工業が相次いで立地している。フロリダ、テキサスは合衆国でも人口増加率の高い州に含まれるし、アトランタ、ヒューストン、ダラス、サン・アントニオなどの都市の人口集中が目覚ましく、北部から南部への人口の還流が続き、合衆国における南部の地位は格段に高まっている。2000年の国勢調査では、テキサス州の人口がニューヨーク州を抜いて、カリフォルニア州に次ぐ全米第2位となっている。 [伊藤達雄] 西部ロッキー山地合衆国のなかではもっとも開発が遅れ、最後のフロンティア(辺境)とよばれてきた。ロッキー山系の自然に囲まれた国立公園地帯であるが、観光産業の著しい発展と居住地としての快適な環境が知られるにつれて、人口の急増が続いている。1970年から2000年までの30年間に、ネバダ州の人口は4.1倍の増加という驚異的な記録を示し、全米第1位の増加率である。第2位は2.9倍になったアリゾナ州、第3位はフロリダ州の2.4倍、第4位はユタ州の2.1倍、第5位はコロラド州の1.9倍であり、南部のフロリダ州を除いて人口急増州の上位を独占している。そのほかアイダホ州は1.8倍で8位、ニューメキシコ州は1.8倍で9位となっている。この山岳州の地域全体で2.2倍の増加を示し、北東部大西洋岸、中北部などのほとんど増加をみせず低迷傾向にある地域とは対照的に、合衆国でもっとも急速な成長を遂げている地域である。 ロッキー山系の東麓(とうろく)の降雨の少ないステップ地帯は、グレート・プレーンズとよばれる大規模企業的放牧地帯で、かつてカウボーイが活躍する世界であったが、いまはヘリコプターやジープが用いられ、一部は融雪水を利用した灌漑(かんがい)施設の普及によって飼料作物や小麦を主作物とするきわめて生産性の高い大規模企業的農場に変容している。鉱物資源も豊富で、有名なビンガム銅山(ユタ州)があるのをはじめ、石油、ウラン、非鉄金属の新鉱山も発見されている。 ネバダ、アリゾナ、ユタなどの州は降雨が少なく砂漠地帯であったが、フーバー・ダムなどの利水計画が進むにつれて開発された。乾いた空気と輝く太陽のもとに人工のオアシスが出現したのである。ギャンブルで名高いラス・ベガス、リノなども、1990年代以降はハイテク企業や研究開発機関が立地して都市の風格が変わりつつある。ウォータートン氷河国際公園、イエローストーン、キャニオンランズ、キャピトル・リーフ、グランド・キャニオン、グランド・ティートン、ブライス・キャニオン、ロッキー・マウンテンなどの国立公園が連続し、その自然景観の雄大さは合衆国随一であろう。こうした諸要素が、東部や西海岸の諸都市からの人々や企業、工場を引き付け、急成長をもたらしているのである。 [伊藤達雄] 西部太平洋岸ワシントン、オレゴン、カリフォルニアの3州が太平洋に面して南北に連なる。気候は、北部の穏やかな西岸海洋性からカリフォルニアの明るい地中海性まで変化するが、ともに快適な風土である。西へ西へと領域を拡大してきたアメリカ合衆国のいわば終着地であるが、その後はアジア、オセアニアへの進出基地として発展した。シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルスの各港はいずれも太平洋地域に開く合衆国の窓である。 ワシントン州、オレゴン州は森林資源に、カリフォルニア州は豊かな太陽に恵まれている。とくにカリフォルニア州は水資源の開発に成功してから小麦、水稲、柑橘(かんきつ)、蔬菜(そさい)など多様な農業地帯として躍進し、日本からの移民の定住も行われるなど日本とも関係が深い。また、映画産業のメッカとなり、第二次世界大戦を契機に自動車、兵器、航空機など新しい工業を中心に新しい工業地帯を形成した。カリフォルニア州立大学、スタンフォード大学など高い水準の文化も育っている。近年は電子工業などの先端産業の発達も目覚ましく、発展するアジア市場へ向けた合衆国の拠点として期待の大きい地域といえる。1970年以来カリフォルニア州はニューヨーク州を抜いて人口第1位の州となり、ロサンゼルスは1990年にシカゴを抜いて第2位の都市となった。 [伊藤達雄] 歴史
時がたつにつれて自治意識が高まり、本国への帰属意識が薄れ、逆に対抗することが多くなり、ついに1773年ボストン茶会事件をきっかけに大陸会議が発足、イギリスとの間に1775年から1783年まで独立戦争が戦われ、その最中の1776年7月4日に同会議は13州の独立を宣言した。この日が独立記念日とされているが、合衆国が正式に発足し、初代大統領ワシントンが就任するのは1789年である。独立後はヨーロッパ諸国の混乱に乗じて次々と領土の拡張を行い、1846年にほぼ現在のメイン・ランド(本土)の領有を完成、さらに1867年にアラスカを、1998年ハワイを加え、1959年の両地方の州昇格によって今日の50州となった。 南北戦争(1861~1865)は農業国から工業国への転換の契機であったが、以後、資本主義近代国家として着々と地歩を築き、第一次・第二次世界大戦ともに戦勝国となり、しかも戦災を被ることなく、この間、世界最強の経済力を蓄えることができた。第二次世界大戦後は西側諸国の盟主として長く君臨してきたが、日本やヨーロッパ諸国が復興、発展し、東西冷戦が終結するとともに、世界は多極化の時代に入った。しかし世界の平和と経済、文化に占める合衆国の地位は依然として高い。 [伊藤達雄] 政治・外交・防衛アメリカ政治の特徴アメリカ国家の基盤には「自由」と「平等」という二つの政治的な理想がある。圧制や束縛から逃れる自由と、権利の最大限の平均化である平等という二つの理想をつきつめていけば、現実的には矛盾しかねないが、政治的な対立を生みながらも、この二つの理想を強く求めてきた歴史がアメリカの政治史であるといっても過言ではない。 この二つの理想に即して、実際に政治のルールに応用したものが民主主義(デモクラシー)である。民主主義はアメリカ政治の根本原則であり、政治の決定が国民の手にゆだねられていることを示している。アメリカ政治では植民地時代のニュー・イングランドにおけるタウン・ミーティング(直接民主制による地方自治制度)に代表されるように、民主主義がきわめて早い時期から制度化され、高い水準の国民の政治参加が実現されてきた。 民主主義は、国民が自由意志に基づき平等な立場で政治的な決定を行う制度である。だが、特定の勢力が結束し、トクビルAlexis de Tocqueville(1805―1859。19世紀のフランス人政治思想家)のいう「多数派の暴政」になってしまっては、自由も平等も成り立たない。そのため、国家の権力が特定の勢力に集中しない権力分立制はアメリカ憲法のなかでもっとも強調されている。国家の統治は憲法に基づく立憲主義を通じて行われ、市民に対する国家の権力を限定することに重点が置かれている。 自由と平等という二つの理想は、憲法だけで達成されるものではない。移民でできた多様な人々の国家であるアメリカでは、ともすれば国民がばらばらになってしまう。多数派の暴政を防ぎ、人々をつなぎとめるために、ボランティア団体に代表されるような市民の自由意志による団結(結社)が建国のころから重視されてきた。また、セルフガバメント(自治)の精神やキリスト教信仰のような人々をつなぎ合わせるための紐帯(ちゅうたい)もアメリカ社会の行動原理に大きく影響している。このような文化的な側面もアメリカの政治の大きな特徴である。 [前嶋和弘] 権力の分立政治というものは異なる価値観の対立のなかで限られた資源を分配するものである。分配の過程で一つの特定の勢力が政治的な権力を独占する多数派の暴政を防ぐために、政治システムは細心の注意を払ってつくられている。立法府と行政府が重なりあっている議院内閣制の国と比較すると、アメリカの権力分立の度合いは目覚ましく、アメリカ政治のもっとも重要な特徴となっている。 憲法を起草した人々(フレーマー、憲法制定の父祖)たちは、合衆国憲法制定の際に「新しくできる連邦政府が国民の自由を脅かすものであってはならない」という意識を共有していた。そのため、中央政府(連邦政府)に与えられた権限を憲法に明示し(列挙権限)、それ以外は国民により密接な存在である州の権限のままにとどめておくこととした。列挙権限には、租税、陸軍と海軍の設立、戦争の宣言、複数州間の商取引の規制、通貨鋳造などがある。州の権限を保持することで、連邦政府と州政府が共存する連邦主義(フェデラリズム)を徹底させた。各州はそれぞれ独自に憲法を備え、独自の政治システムを構築している。 連邦政府についてはさまざまな権力分立の考えが適用されている。まず、イギリスのジョン・ロックやフランスのモンテスキューによって提唱された三権分立を本格的に取り入れ、国家権力を立法権、行政権、司法権の三権に分け、互いに監視しあうチェック・アンド・バランス(抑制と均衡)を徹底した。たとえば、法律をめぐっては、立法(連邦議会)が作成した法案に対して、行政(大統領)は理由を付して議会に送り返すことができる拒否権をもっている。しかし、大統領が拒否権を発動しても、連邦議会の上下両院がそれぞれ3分の2以上の多数でふたたび採択すれば拒否権にもかかわらずその法案は連邦法として発効する(オーバーライド)。ただし、それでもその法律の実際の解釈と運用は大統領に任されている。司法(連邦裁判所)は法律そのものや大統領の法解釈と運用について、憲法解釈の観点から司法審査(ジュディシャル・レビュー)を行い、違憲判決を下すことができる。議会は新しく法律をつくり直すか、憲法の修正条項を作成することができる。このように議会、大統領、裁判所が権限を分割しながら権力を分散させているのが特徴である。 また、国民ともっとも密接な関係にある議会はそれだけ「特定の勢力」の影響を受けやすいため、権力が集中しすぎないように上下両院の二院に分けている。そして、上院議員(任期6年、各州から2人)、下院議員(任期2年、議員数は選挙区ごとの人口比による)、大統領(任期4年、1人。間接選挙)、連邦裁判所判事(倒産裁判所など一部を除いて任期は終身。大統領の任命、上院の承認による)のように、任期、選び方、選ぶための選挙の期間にも差をもたせ、一定の時期に集中させないことで多数派の暴政を防いでいる。 さらに憲法起草者たちは、新国家の拡大とともに共和国が広がっていく「拡大共和制」のなかで、より多くの人々が政治に参加することになり、特定の少数集団が政治を牛耳(ぎゅうじ)ってしまうことを防ぐことができると想定した。国が発展・拡大していくなかで多様な人々や意見を受容することで、特定のグループに権力が集中するのを避けることができるという考えである。拡大共和制は多元主義とともに、アメリカ国家の成長の礎(いしずえ)となった。 [前嶋和弘] 合衆国憲法アメリカ合衆国憲法は1787年に制定され、翌1788年に発効した世界最古の成文憲法で、権力の分立、連邦主義、共和制、多元主義などの原則に基づいた七つの条文と、27の修正条項で構成されている。 アメリカはもともと13の独立した植民地の連合体からスタートした。独立革命で13植民地は連合規約を結び、アメリカ連邦(連合会議)を形成して対英戦争(イギリスからの独立を目ざしたアメリカ独立戦争)を行い、独立後も当初は基本的に各州政府の自治が許され、連邦(連合会議)の権限は非常に弱かった。1787年に開かれた憲法制定会議では、中央(連邦)政府による圧政を恐れて州の権限の確保を望む意見とある程度強力な中央政府の樹立を主張する意見が対立し激しい議論を続けた。連邦政府創設を訴える連邦主義派(フェデラリスト)と州の権限を主張する反連邦主義派(アンチ・フェデラリスト)はそれぞれが新聞紙上で意見を闘わせた。激しい対立の結果生まれた合衆国憲法では、連邦主義とともに中央(連邦)政府の権限が大きくなりすぎないように限定政府(リミテッド・ガバメント)を基盤とするなど、州権派(反連邦主義者)に配慮したものになっている。 憲法には、イギリス政府の圧政があった植民地時代とアメリカ革命期(独立戦争期)のさまざまな経験が生かされており、連邦政府に与えられた権限と同時に連邦政府が行ってはならない事項が明確に示されている。たとえば第1条9節では人身保護の目的で、拘禁の事実・理由などを聴取するため被拘禁者を出廷させる人身保護令(ヘイビアス・コーパス)の特権を停止することが禁じられている。また、市民の自由を確保するために、憲法制定後の1791年「信仰・言論・出版・集会の自由」(修正第1条)、「不当な捜索や逮捕の禁止」(修正第4条)、「陪審による裁判の権利」(修正第6・第7条)など、人権を保障する10か条の憲法修正条項をつけた。この憲法修正第1条から10条までを「権利の章典」とよんでいる。 その後、1865年「奴隷、および苦役の禁止」(修正第13条)、1920年「女性の参政権規定」(修正第19条)、1951年「大統領の3選禁止」(修正第22条)など、アメリカ政治史上重要な変革とともに憲法は修正され続けている。いずれの修正条項も連邦議会の各院が3分の2以上の賛成で発議し、4分の3以上の州の批准をもって成立している。 [前嶋和弘] 連邦議会政治を動かすためのルール(法律)をつくる立法府が連邦議会である。解散はなく、下院は2年、上院は6年の任期が固定している。上院議員は50州からそれぞれ2人ずつ選出される(計100人)。下院議員は435人を人口比で割り出した選挙区ごとの配分数によって小選挙区単記制で選出されるが、各州から最低1人は選出される。配分数は10年ごとの国勢調査に基づいて調整される。 下院議員の中心が下院議長であり、多数派党から選出される。党籍は離脱せず、自分が所属する政党の中心的な存在として下院の2番目の地位である多数派党リーダー(マジョリティ・リーダー、多数派党院内総務)とともに自らの党の下院議員をまとめる。上院議長は副大統領が慣習的に兼務するが、上院で法案投票が50対50の同数になった際に副大統領に決定権があること以外はほとんど実質的な役割はない。 法案は上下両院で承認(通過)されたのち、大統領の署名で成立する。上院と下院とでまったく同一の法案が可決されることはほとんどないため、上下両院を通過したのち、両院協議会が開かれて調整した後に大統領に付託される。 法案の内容は幅広く、さまざまな政策から予算までを含んでいる。法案の提出は国民の代表である連邦議員が行う。大統領は議会に対して法案や予算案を推薦することはできるが、自ら法案を提出できない。さらに、大統領が運用する法案の具体的な予算や政策の内容は議会がつくったものに従うほか、議会には具体的な政策が大統領によってどのように運用されているのかを監視する機能もあるため、立法府である議会の権限は非常に大きい。形式上はすべて議員立法であり、閣法(内閣が提出する法案)が大多数を占める日本とは対照的である。その分、議員には政策に対する知識の深さや法案作成能力の高さが求められており、多数の議員スタッフが法案作成を担当している。 立法活動以外の議会の権限には大統領の弾劾があり、政治システム上大きな意味をもっている。議会は大統領が重大な罪過を犯したと認められる場合に限り、大統領を弾劾する権限を与えられている。弾劾については、下院が単純過半数の賛成に基づいて訴追し、上院が弾劾裁判を行う。上院では出席議員の3分の2以上の賛成で弾劾を決定する。ただし、過去弾劾裁判にかけられたのは1868年のアンドリュー・ジョンソン(南部再建について議会と対立)と1998年のクリントン(司法妨害)の2人だけである(いずれも有罪は成立しなかった)。1970年代のウォーターゲート事件に関与したニクソンの場合は、司法妨害、権力の乱用、議会に対する侮辱の三つの理由で下院司法委員会が弾劾を勧告し、下院全体で弾劾手続きが開始される時点で大統領を辞任した。 そのほか議会に与えられている権限は憲法第1条8節に詳しく記載されており、租税、陸軍と海軍の設立、戦争の宣言、複数の州の間の商取引の規制、通貨鋳造などがある。 首相指名、予算案の衆議院優先権がある日本に比べて、上院、下院は基本的には法律上はまったく平等である点が特徴的であり、上院と下院の対立で法案の立法化が進まないケースも頻繁にある。ただ、両院は権限のうえでは対等であるが、議員数が少なく任期も長い上院議員が下院議員よりも知名度、威信も高い。 上院と下院の違いについては、上院には条約批准同意権と大統領が任命した政府高官の承認・非承認を行う役割があるのに対し、下院には予算の先議権がある。下院が小さな選挙区の代表であるのに対して上院は州の代表である。また、下院議員に「私の代表my Representative」という親しみの気持ちをもっている国民は少なくない。しかし国民のなかには、大統領や議会は特殊利益の代弁者というイメージをもつ者もおり、自分の選挙区選出の議員に対する好感情と議会・大統領に対する悪感情(ワシントン嫌い)という二つのイメージの差はきわめて興味深い。 両院には農業、軍事などの政策分野ごとに常設の委員会が設けられ、さらに細かな政策ごとに各常設委員会に小委員会が設置されている。また、政策的な必要性に応じて特別委員会も設置されている。上下両院の議員から構成される、目的の限定された合同委員会もある。2011年時点で常設委員会は上院16、下院20、小委員会は上院74、下院94、特別委員会は上院4、下院2である。 立法の要(かなめ)となるのが委員会活動である。議会に提案される法案の数は膨大で、小委員会、委員会で議論する法案を絞り、委員会が必要と認めた法案だけが本会議に上程される。各委員会の委員長・小委員長は、上院、下院の多数派を占める政党が独占するため、どの法案を論じるかなどは多数派党の意向が大きくなる。委員会内の少数派党のリーダーは筆頭委員(ランキング委員)とよばれ、少数派党をまとめ、主に対立党のリーダーである委員長との折衝を担当する。 [前嶋和弘] 大統領日本では、アメリカ大統領は国家元首(ヘッド・オブ・ステート)と認識されている。大統領は主席外交官(チーフ・ディプロマット)として外交の最高責任者であるほか、三軍の司令官(コマンダー・イン・チーフ)として、軍事上の最高者(最高司令官)も兼ねている。予算措置なども含め外交・軍事政策執行のための制度を決める権限は議会にあるが、迅速な対応が必要な実際の外交政策を執行する権限は大統領にある。国際関係において、アメリカの地位が飛躍的に高まった20世紀には大統領の外交・軍事上の役割が非常に重要になった。 国内政治における大統領の憲法上の主な役割は、議会がつくった法律を運用する行政府の長である。大統領は15の省の長官らで構成される内閣を統率する。閣僚(長官)は大統領によって任命される。閣僚は議員との兼職を禁止され、権力分立の原則に基づいて議会から可能な限り分離されている。行政に関して国民に責任を負うのは大統領だけであり、閣僚は直接補佐する形で大統領に対してだけ責任を負う。 第二次世界大戦後の福祉国家化で、行政の権限がきわめて大きくなったこともあって、大統領の権限は憲法起草者が予想したものに比べ、非常に大きくなっている。大統領の権限が大きくなるにつれ、大統領が望む法律づくりを教書という形で議会に要求する大統領の立法勧告権の重要性も増している。 それでも、三権分立や連邦主義など憲法上に規定されている権力分立のほか、政党内の法案拘束も弱いため大統領が望む法律が必ずしもうまく立法化されるとは限らない。大統領には議会が承認した法案の署名権や拒否権はあっても、形式上大統領自身が法案そのものを提出することはできないし、大統領と主要省庁の長官で構成される内閣、大統領の行政権の実務組織である官僚組織のいずれも法案は提出できない。大統領は教書のような形で法案を議会に提案することはできるが、実際の審議は議会の手にゆだねられており、立法化の過程で大統領の意図とは大きく異なる法案になってしまうこともある。 ウィルソン政権時の国際連盟、クリントン政権時の京都議定書のように、上院の反対で条約が批准されないようなケースが生じることもあり、国際問題化してしまう場合もある。また、大統領令はあるが、これはあくまでも議会が決めた法律を大統領が解釈・運用するための行政運営の一環であり、法律に比べると拘束力は非常に小さい。政権が変われば、過去の大統領令は書き換えられてしまう。 近年では、大統領がテレビなどのメディアを通じて国民に直接に訴えて世論の支持を取り付けることで議会を動かすゴーイング・パブリック戦略が頻繁に使われている。さらにテレビへの頻繁な出演を背景にして、国民統合の象徴、市民宗教の司祭としての大統領の役割も注目されている。たとえば、大災害などが起こった場合などに大統領が国民に向ける癒(いや)しのことばは宗教における司祭のことばそのものであり、政治的役割を超えて大統領の社会文化的な役割も重視されるようになっている。 [前嶋和弘] 行政府行政府は行政府の長(チーフ・エグゼクティブ)である大統領の行うさまざまな行政政策の実務組織である。行政府は軍を含めると計400万人もの職員が働いている巨大な官僚組織である。行政府は大別して15の省、独立諸機関、大統領行政府の3部門に分かれている。15の省は農務、商務、国防、教育、エネルギー、保健社会福祉、国土安全保障、住宅・都市開発、内務、司法、労働、国務、運輸、財務、退役軍人である。 各省の長官は大統領によって任命され、議会上院によって承認される。大統領、副大統領とこの15省の長官で内閣を構成する。しかし、長官はsecretary(元の意味は「秘書」)としてあくまでも大統領を直接補佐する役割を担っており、首相を核とした内閣そのものに行政権がある日本とは対照的である。 独立諸機関は省に比べ比較的規模が小さい行政機関で郵政公社、連邦預金保険公社、航空宇宙局、中小企業庁、環境保護局などがあり、いずれもその長官は大統領によって任命、議会上院によって承認され、大統領の監督の下に置かれている。 大統領行政府は、大統領を補佐するために大統領直結の特定政策分野の行政機関や大統領への助言・諮問さらには行政府全体の監督や統制の機能を持った諸機関を総称するもので、1939年に大統領F・D・ルーズベルトにより創設された。外交政策決定の中枢である国家安全保障会議や大統領の経済財政政策の審議や助言を行う経済諮問委員会と国家経済会議、大統領が予算をうまく管理し行政府全体を統括するための行政予算管理局、対外通商業務を担う合衆国通商代表部などの機関がある。また、大統領にもっとも近い組織で大統領の手足となって働くホワイトハウス・オフィスも大統領行政府の一部である。大統領の仕事の増大と複雑化に伴って規模が拡大し続けている。 [前嶋和弘] 裁判所アメリカの司法システムは連邦裁判所と州裁判所の二本立ての系列があり、それぞれが独自に完結している。連邦裁判所で扱われる裁判は憲法解釈のほか、連邦法の違反事件や州を超える事件に限られている。州法によって争われる事件は州の最高裁判所の判断が最終的なものであり、連邦裁判所へ控訴することはできない。 州裁判所では基本的に刑事事件の大多数、交通事故、遺言、軽犯罪などの裁判が行われる。州裁判所の裁判官の多くは選挙で選出されており、人事面でも民主的に運営されているが、裁判官立候補者は集票組織を有する政党と関係をもつことも多く、政治的党派性がみられるのが大きな特徴である。裁判では原則として陪審制がとられており、一般市民が陪審員として無作為抽出されて事実問題の認定を担当するのも民主的な裁判を象徴している。陪審には被疑者を起訴すべきか否かを判断する大陪審と陪審員が裁判に参加して被告の罪の有無を判定する小陪審とがある。 連邦裁判所は、全国93の連邦地方裁判所と12の連邦控訴裁判所および最高裁判所からなっている。連邦裁判所が注目されるのは憲法の解釈である。連邦裁判所は、議会がつくった法律、大統領の法解釈と運用について憲法に照らし合わせてチェックする。この連邦裁判所の権限を司法審査とよび、日本の違憲立法審査に相当する。問題がある場合は立法を無効にすることや大統領の行政措置を止めることができる。 ただし、憲法の解釈には判事のイデオロギーによって幅があるのもアメリカの司法の特徴である。そのため、最高裁を中心に判決には強い政治性があり、判決そのものが政治を揺るがしてきたこともある。黒人奴隷の憲法上の地位を争い、南北戦争につながっていったドレッド・スコット事件判決(1857)や、南部諸州の人種分離法に違憲判決を下し、公民権法制定への起爆剤となったブラウン対教育委員会判決(1954)、人工妊娠中絶を合法化させたロウ対ウエイド判決(1973)など枚挙にいとまがない。 連邦裁判所裁判官は大統領によって任命される。とくに最高裁の場合は大統領がどのような政治的立場の人物を任命するのかが大きな政治的な争点となり、任命承認を行う議会上院との駆け引きが大きなニュースとなる。アール・ウォーレンEarl Warren(1891―1974。在任期間1953~1969)が最高裁長官を務めた1950年代から1960年代にかけては最高裁の9人の裁判官の多くが政治的にリベラル派で、さまざまな判決で連邦政府による積極的な社会改革を先導していった。一方、1980年代後半以降最高裁長官をウィリアム・レンキストWilliam Rehnquist(在任期間1986~2005)、ジョン・ロバーツJohn Roberts(在任期間2005~ )が務めるようになると保守派の裁判官の数がしだいに増え、リベラル派と保守派の裁判官の数が拮抗しながらも保守的な判決が増えるようになってきた。 高度に政治的な判断を要する争点について司法独自の判断を控える日本などと比較するとアメリカの裁判所は司法積極主義であり、国の政策や社会的に重要な争点について積極的な裁定者となる傾向がある。そのため、公民権運動に代表されるように市民運動などの政治活動の第一歩として裁判闘争戦術が採用されてきた。 アメリカの政治制度は権力の分立を前提にしており、司法の独立が強調されるため連邦裁判官は終身の任期(原則として引退するまでその地位にとどまる)と優れた年金制度で身分が保障されている(州裁判官の場合は任期制のところが大多数である)。また、連邦議会議員、大統領が国民によって選ばれているのに対して連邦裁判所の裁判官は任命制であるため、民主的な国民の意思を司法が破棄することにもつながりかねない。このような背景のなか、アメリカの政治過程では司法の圧政をめぐる議論も活発である。 [前嶋和弘] 政党アメリカは、建国してまもない18世紀末から現在まで二つの巨大政党(共和党、民主党)が政治の中心にある二大政党制である。先進民主主義諸国において二大政党制は必ずしも多くなく、しかも長期にわたって同じ二つの巨大政党による二大政党制が続くのは珍しい。他の政党は総称して第三政党とよばれるが、基本的にはきわめて弱小でアメリカ国民にとってもなじみがない。 合衆国憲法には政党についての記載がない。これは政治的な権力を独占する特定の勢力を徹底的に排除することが憲法起草者たちの願いであり、政党は特定勢力と考えられたためである。 アメリカの政党には他国の政党にはみられない特徴がある。その一つが、党首にあたる役職が存在しないことである。共和党と民主党の全国委員会には委員長職が置かれているが事務局長的な役割である。政党組織は分権的で、全国委員会は50州の党委員会の連合体的な要素が強い。党員資格もあいまいで有権者登録や予備選挙の登録の際に党名を記入する欄があり、そこに記入すれば党員となる。党費納入や活動への参加義務もないに等しく、党員というよりも党支持者に近い感覚である。 アメリカの政党の最大の特徴は、議会での党としての規律が緩やかなことである。ヨーロッパなどの政党に比べて政党は結束力が弱く、議会内の同じ党の議員でも政策に対する立場の差が大きい。法案に対する党議拘束は基本的にはなく、大統領と議会多数派が同じ政党でも政策に対する立場が異なることも多く、政党の議会内執行部(院内総務、院内幹事など。下院の多数派の場合下院議長も含む)の方針に抵抗する議員も少なくない。 政党の規律が緩やかで党議拘束がないことから、連邦議会では政党の違いを超えた連携がかつては頻繁に行われた。たとえば、同じ党内や対立党の議員に対して法案成立への協力を約束するかわりに、自分が立法化したい法案に協力させるログローリング(票の貸し借り)も一般的であった。しかし、1970年代から南部での共和党勢力の拡大、党内の組織改革が行われたことなどの影響によって各政党内でのイデオロギー的な結束が強まったことや民主・共和両党間のイデオロギー差の拡大などから、政党の党議拘束もしだいに強化されてきている。 民主・共和両党の対立が進むなか、大統領を擁する政党と議会の上下院のどちらか(あるいは両方)の多数党が異なる状況が恒常化し、法案の立法化がまったく進まずに政策形成のグリッドロック(行き詰まり)化をもたらす政治システム上の問題もしばしば起きている。 [前嶋和弘] 有権者基本的に18歳以上のアメリカ国籍を有するすべての国民に選挙権が与えられている。南北戦争(1861~1865)後の奴隷解放のあとでも、投票税や識字テストのようなアフリカ系住民を投票から実質的に排除する通称ジム・クロウ法が南部を中心に長年存在していた。1950年代から1960年代の公民権運動で人種差別的な措置は撤廃されたが、アフリカ系住民やラテン系住民などの人種的マイノリティの投票率は白人に比べて低くなっている。 他の先進民主主義国と同じように、アメリカでも政党は有権者にとっては政策を示すレッテルである。ただ、二大政党制が定着しているため、政党というレッテルに対する愛着度は有権者の政治参加の度合いやイデオロギーなどを示す指標となっている。出身地、職業、年収、人種・エスニシティ(民族性)など、有権者の属性そのものも政党への支持態度(政党帰属性)をみれば明らかになる。アメリカの選挙の場合、民主・共和いずれかの党への帰属性が高ければ高いほど投票に行く確率が高いだけでなく、政治に対する知識や関心も高い。また、共和・民主いずれかの党に強い政党帰属性をもっている人は、ほぼ自分の帰属性の高い政党に投票するため、政党帰属性をみれば選挙の大勢が予測できる。これが民主・共和両党にとっては自分の党を支えるコアとなる層である。このコア層以外の中道を押さえるのが選挙を制する方程式である。 近年、アメリカでも無党派層が増えており、中道は有権者のほぼ3割を占めている。政治的な傾向をさらに分析すると、共和党(保守)寄り中道、中道のなかの中道、民主党寄り中道の三つに分かれている(選挙区によって割合は異なっている)。共和党寄り中道は基本的に共和党、民主党寄り中道は基本的に民主党にそれぞれ投票する確率が高い。一方、中道のなかの中道は無関心層にあたり棄権する確率が高い。 [前嶋和弘] 利益団体アメリカの政治過程で特徴的なものに利益団体の存在があり、アメリカ政治を知るうえで重要である。国是である多元主義のなかで、利益団体を通じて自分たちの利益を確保しようと訴えることは政策過程に必要となる民主主義的な政治参加の手法である。 利益団体は労働団体(労働組合)、公共利益団体、イデオロギー団体のほかに特定の争点を追うシングルイシュー団体、企業を母体とする業界団体の一部がなっているケースなどもあり多様である。公共利益団体とは環境保護団体のような広く多くの人の利益を実現しようとする団体である。 利益団体のなかには、共和党支持、民主党支持など党派性をもつものが多い。共和党支持者が参加する利益団体の代表的な例としては、産業界の意見を代弁するアメリカ商工会議所、ビジネス円卓会議などの企業を母体とする団体のほか、キリスト教保守派のイデオロギー団体であるキリスト教徒連合、シングルイシュー団体では銃規制に反対する全米ライフル協会や減税・政府支出の健全化と納税者の権利擁護を主張する全米納税者連盟などがある。民主党支持者が参加する利益団体には労働組合のAFL-CIO(労働総同盟産別会議)やシエラクラブに代表される環境保護団体、リベラル政策を支持する市民団体・人権団体であるACLU(アメリカ市民自由連合)、人種・エスニック集団を母体とする団体NAACP(全米黒人地位向上協会)、消費者保護の市民団体パブリック・シティズンなどが含まれている。 利益団体については、多元主義を体現し、国民の政治参加を促すという政治的理想の追求とする考えがある一方で、特定の利益団体の力が強くなりすぎてグループ間の自由で民主主義的な競争が成立しにくい状況になっているという見方もある。利益団体は議員や行政府の関係者を取り込んで三者による強固な利益連合である鉄の三角形を形成し、閉鎖的な下位政府として政策に大きな影響力を行使しているという見方がその代表的なものである。利益団体のなかには議会対策の専門家であるロビイストに活動を代行させているところもあり、金権政治の温床となっているという指摘もある。多額の献金や過度なロビー活動を続け、民主主義的な政治プロセスをゆがめる団体を特殊利益団体と否定的によぶことが定着しつつある。 鉄の三角形が排他的な政策過程モデルであるのに対して、実際の政策形成の過程はさらに柔軟であり、利益団体を含む特定の政策・争点で知識や情熱をもった人々が相互に結びつくことで政策に対する争点ネットワークがつくられ、政策を形成していくとする見方もある。 [前嶋和弘] 州政府・地方政府アメリカ政治の特徴の一つが、連邦主義に基づいた州の権限の強さである。連邦を構成する州がそれぞれ主権と憲法をもっており、州が主権の一部を連邦政府に移譲する形で連邦と州の関係が築かれている。連邦政府の権限は防衛、関税、通商など憲法の条文に列挙された事項(列挙権限)に限られ、それ以外の部分はすべて州および国民に留保されるのがアメリカの連邦制の基本となっている。 さらに、州政府(地方)内でも権力を分散させ、州議会(立法府)、州知事(行政府)、州裁判所(司法)が互いにチェック・アンド・バランスの関係にある。各州政府は、連邦政府とはまったく別の政治的な力学で動いている独立国のようなものである。 このように、連邦政府-州政府という2層構造のなか、州政府の下部にあるのが地方政府である。地方政府はカウンティ(郡。ルイジアナ州ではパリッシュ)、ミュニシパリティ(市)が中心であり、そのほか特定の目的のための特別区や局もある。カウンティは州の行政区分であり、出先機関という色彩が強い。ミュニシパリティは憲章を採択し、自治権が認められている。 連邦政府と州政府がすみ分ける連邦主義に基づいて、建国から20世紀初めごろまでは政策そのものの大半が州政府によって行われてきた。連邦裁判所も19世紀前半には州の権限を強調する立場(州権論)をとっていたが、19世紀末ごろから連邦政府の権限を拡大解釈する傾向が目だってきた。20世紀の二度にわたる世界大戦と大恐慌が連邦政府の権限を強化する決定的契機になったことはいうまでもない。1933年のルーズベルト大統領のニューディール政策以降は福祉国家化の流れに従って、連邦政府が積極的な政策上のリーダーシップをとることが増え、連邦政府の権限が拡大し、それに伴う人的資源や予算も飛躍的に増大している。州と連邦政府のバランスが変わっていくなか、連邦政府の肥大化を非難する意見も保守派を中心に根強い。 連邦政府はさまざまな政策決定を行うが、たとえば福祉政策などでは政策を直接担当する連邦政府の機関は限られているため、実行部隊としての州政府や地方政府の協力が必要である。連邦と州、そして地方政府が協力しながら行う協力的連邦制がアメリカの行政機能の特徴となっている。 3割自治とよばれるように財政的に国に保護されている日本の地方自治体とは対照的に、アメリカの州は財政的に国から独立している。その分、財源確保や効率的な行政サービスは自治体にとって死活問題であり、各種の行政改革が導入されている。連邦での政策革新のもととなるアイデアが、州政府や都市で行われた政策革新に起源を発するケースも多い。有力州の知事のなかから正副大統領候補が頻繁に生まれることを考えても、州の影響力は大きい。 [前嶋和弘] 政治とメディアアメリカ政治では「メディアを中心に動く政治media-centered politics」という概念が定着している。ほかの先進国と比べても、アメリカの場合は共生関係といえるほど政治とメディアとの関係は密接である。大統領府、議会、利益団体、シンクタンクなどの政治アクター(政治活動を行う機関・団体・人)が広報戦略をメディアに依存する度合いが大きく、メディアを使いこなす能力はもっとも重要な資質の一つとなっている。メディアを介して自分の主張の正当性をかちとり、政策を動かすことが官僚や議員だけでなく、政治コンサルタントやシンクタンク研究員などの政策関係者の仕事の中心とさえなっている。 政治でのマス・メディアの役割は、大統領、議会などの政治アクターや国民に対して政治情報を提供すること、つまり政治インフラにほかならず、新聞、ラジオ、テレビのネットワークニュースが客観的な情報提供の場となってきた。 一方で、政治とメディアは強い共生関係を生み出してきた。閣僚や議員だけでなく、シンクタンク、利益団体などの政治アクターはメディアにとって情報提供者として必要不可欠であり、各アクターも政策形成のために意図的にメディアを使い、政敵の動きを牽制(けんせい)し、世論を動かそうとすることは常套(じょうとう)手段となっている。メディアと政治の共生関係が深まるなかで、しだいにメディアが政治のインフラから政治の主役として機能するケースが増えてきた。メディアが明確に政治イデオロギーを表明し、特定の政治アクターに焦点をあてて報じることによって、メディアはインフラであることを超え、主体的な意志をもった政治アクターの一つとなっているという見方である。各政治アクターは自分の政治色にあったメディアと親和的な関係になり、メディアは特定の政治的立場からの報道を続けて政策に影響を与えていく。アクターとしてのメディアが使う評論家は客観的なコメンテーターではなく、特定の政治イデオロギーの立場から発言する特定メディアの代弁者となっている。ただ、あくまでも政治のインフラとしての立場にとどまろうとするメディアも健在であり、新聞や地上波テレビネットワークの多くがジャーナリズムの基本である客観性を希求し、異なった政治的意見に対してはバランスを配慮した報道を心がけている。 2011年時点でアメリカのマス・メディアを総合的にみれば、政治インフラでありつつ、アクターにもなっているメディアも存在しており、それらはアメリカ政治のなかのトリックスター(ひっかき回し役)的な存在になっている。インターネットの爆発的な普及のなかで、ブログなどを通じて誰もが政治メディアになれる時代を迎え、トリックスター的なメディアの増大は顕著になってくるとみられている。 [前嶋和弘] 保守とリベラルアメリカのイデオロギー対立は、自由主義対社会主義のような体制イデオロギー間の対立ではない。歴史的にアメリカでは固定した階級社会がなく、経済体質として慢性的に労働力不足であり、賃金も比較的高かったため、労働者階級の不満はガス抜きされてきた。土地が広く、労働者が自営農民になることも困難ではなかった。また選挙権も早期に普及したため、社会主義運動や労働運動、普通選挙権獲得運動が一体となることもほとんどなく、社会主義運動の盛り上がりは欠けていた。 アメリカはあくまでも自由主義が支配的な社会であるため、伝統や自由主義的競争を維持しようとする保守派と自由主義体制内で可能な政府による積極的な社会改革を志向するリベラル派の対立が軸となってきた。 リベラル(自由主義)とはもともと「政府が個人を抑圧しない」という意味であったが、現在では平等主義的な改革思想や運動をさしている。具体的には国民の平等や自由を政府のリーダーシップで達成することを意味している。たとえば貧困や社会福祉などの社会的問題に対しては政府の何らかの政策で解決しようとすることに賛同し、環境問題では政府による規制を強化することで公害の除去・予防や環境保全を進めようとする考えを支持している。アメリカのリベラル派はヨーロッパや日本の社会民主主義政党よりも中道寄りで、社会主義や共産主義の革命を目ざしているわけではなく、あくまでも自由競争を重視した市場経済のなかでのリベラルである。ルーズベルト大統領のニューディール政策が修正資本主義とよばれており、それを象徴している。 社会問題については、伝統にとらわれない価値観(社会的リベラル)をさす。キリスト教徒の多いアメリカで大きな社会問題となっている妊娠中絶については容認の立場(女性の選択を重視するという意味からプロ・チョイス派とよばれる)がリベラルの見方である。アメリカでは結婚を男女のものと信じる敬虔(けいけん)なキリスト教徒がきわめて多いため、同性愛者の権利そのものが社会的な議論となっているが、同性愛者の権利についても擁護するのがリベラル派である。社会の少数派を重視し、人種やエスニシティ間の平等に敏感なのもリベラル派の特徴である。 一方、同じ「自由」ということばから生まれた自由放任主義(リバタリアニズム)は現代のリベラルとは対極にある考え方で、保守派の中心的な政治思想である。リバタリアニズムとは徹底した自由競争を重視し、レッセ・フェール(自由放任)を目ざすものである。リバタリアニズムまではいかないまでも「政府の経済活動や私生活への干渉をできるだけ少なくすべきである」というのが保守派の基本的な政治的立場である。リベラル派が訴える政府の積極的なリーダーシップによる政策は、保守にとっては大きな政府にすぎない。また、社会問題については、伝統的価値を重視する社会的保守であり、具体的にはキリスト教的な倫理を重視する社会生活を意味している。 ここにあげたリベラルのイデオロギーは、現在では民主党が重視する考え方であり、保守のイデオロギーは共和党が重視する立場である。そのためリベラル派の支持政党は民主党となり、保守派の支持政党は共和党となるが、南部は伝統的に保守的な民主党支持者が多かったため、支持政党とイデオロギーの関係は完全に一致はしていない。また、高所得者の場合は共和党支持が多いが、教員、政府職員などの比較的所得が高いホワイトカラーには民主党支持者が多い。低中所得者層にはブルーカラーの労組関係者やアフリカ系、ラテン系住民などが含まれており、リベラル派として所得再分配的な政策を志向する民主党支持者が多いが、南部を中心に敬虔なプロテスタント諸派に属する低中所得者層は保守的な人たちも多く、共和党支持者も多い。 カトリックやユダヤ系などアメリカでは少数派の宗教信者にリベラル派が多いほか、地域的には北東部に伝統的にリベラルが多い。少数派の権利を擁護するため、前述のマイノリティ人種のほか、ゲイ、レズビアン、貧困層が集まる都市部住民にリベラル派が多い。保守派は南部や中西部に多く、宗教的にはプロテスタント、人種は白人が多い。 2010年の中間選挙で一躍脚光を浴びたティーパーティ運動(政府支出の増大に反対し、小さな政府を唱える保守派の政治運動)は、典型的な保守のポピュリスト(大衆迎合主義者)運動で、草の根運動として大きな輪に拡大した。しかし、もっとも代表的な主張の「小さな政府」(減税と財政規律)は、景気低迷で税収が減少するなか減税は困難であり、実質的な戦時下(イラク、アフガン戦争の継続。2011年8月時点)で軍事費がかさむため緊縮財政は理論的にかなりむずかしいとされている。そのため、ティーパーティの運動は論理性に欠けているとして穏健派保守層からやや距離を置かれている。 [前嶋和弘] 外交政策の決定大統領は、上院の助言に従い、その同意を得て、条約を締結する権限をもつ。しかし条約締結の過程において、交渉と批准とは区別されており、上院が関与するのは批准についてだけであって、交渉はもっぱら行政府により処理されるべきものとされている。条約の批准は出席議員の3分の2の同意を必要とする。条約の批准同意権を上院だけに与え、しかも3分の2の条件付き多数決としたのは、憲法制定当時の政治状況によるものであるが、今日では、上下両院の承認と単純多数決が望ましいとする意見も強い。 行政府において外交を担当する部門は国務省である。国務長官には政治的に第一級の人物が任命されることが多く、伝統的に国務省は高い威信を誇ってきた。しかし最近では、国務省の地位はむしろ低下しており、重要な政策決定は、大統領府のなかに置かれている国家安全保障会議で行われることが多い。国家安全保障会議は、大統領、副大統領、国防・国務両長官によって構成され、国家の安全保障にかかわる外交政策と軍事政策全般について大統領の政策決定を補佐する。必要に応じて、統合参謀本部議長や中央情報局(CIA)長官も列席する。事務局長は国家安全保障担当の大統領補佐官で、対外政策に関する助言者として大きな役割を果たすことが多い。 [阿部 齊] 外交政策の伝統アメリカの外交政策の伝統的特質は、イデオロギー第一主義である。西欧諸国の外交が基本的に国益優先の立場をとってきたのに対して、アメリカ外交はなによりもまずイデオロギーを優先させる立場をとってきた。それは、アメリカが特定の理念、すなわち「生命・自由および幸福の追求」を確保するためにつくられたからである。これらの価値を重視するのは自由主義にほかならないから、アメリカは自由主義を実現するためにつくられた国家だといってよく、対外政策においてもアメリカ自由主義が唯一のイデオロギー的基準として作用する。こうした特性は、具体的には孤立主義と膨張主義としてアメリカの対外政策を支配した。孤立主義は、アメリカと西欧諸国の相互不介入をもってアメリカ外交の原則とする立場であり、アメリカを西欧国際社会から孤立させようとする立場である。他方、膨張主義は、南北両アメリカおよびアジアにアメリカが無限に膨張することの必然性を是認する立場である。この孤立と膨張という一見矛盾する二つの原則は、いずれもアメリカの唯一のイデオロギーである自由主義と関連をもつ。 まず孤立主義についていえば、アメリカの自由主義的同質性は、異質で多様なイデオロギーに対して嫌悪感をもつ。アメリカ自由主義は、自己の純粋性を保つためにヨーロッパからの孤立を図るのである。また膨張主義についていえば、アメリカ自由主義は、その普遍性の確信のゆえに、発展途上にあるラテンアメリカやアジアに対しては無限の適用可能性をみいだすことになる。このように、孤立主義も膨張主義もイデオロギー第一主義の具体的な現れであるが、いずれも対等な交渉相手を想定していないという点で、西欧的外交の標準的な形式からは逸脱している。今日では、イデオロギー第一主義の徹底的な追求は不可能であるが、それが完全に払拭(ふっしょく)されたとはいえない。 [阿部 齊] 防衛政策1947年の国家安全保障法により、陸海空三軍の統合が行われ、陸海空各省の上に国防省(通称ペンタゴン)が置かれて、文官の国防長官が大統領を補佐し、三軍を指揮統轄することになった。同時に設置された統合参謀本部は、陸軍参謀総長、海軍作戦部長、空軍参謀総長、海兵隊司令官と、それを統轄する統合参謀本部議長によって構成され、作戦面で大統領・国防長官を補佐する。大統領―国防長官―各軍司令官の文官支配が確立されている。 2005年時点の戦略核戦力は、ICBM(大陸間弾道ミサイル)550基、SLBM(潜水艦発射ミサイル)432基、弾道ミサイル搭載原子力潜水艦18隻、戦略爆撃機114機となっている。通常戦力は、陸上戦力が陸軍約49万、海兵隊約18万、海上戦力が潜水艦70隻を含む艦艇1120隻(約577万トン)、航空戦力は、空軍・海軍・海兵隊をあわせて3450機を擁している。 アメリカの伝統は、戦時と平時を厳格に区別し、軍事力の行使を、道徳的な正当性を付与しうる場合に限ることであった。軍事力の行使には慎重であるが、いったん行使されれば、敵国が無条件に降伏するまで戦うことになる。西欧諸国のごとく、平時においても外交交渉と軍事力行使とを代替的に併用することは、アメリカの伝統にはなかった。しかし今日では、国際環境の変化によって、軍事力を政治的手段として日常的に使用する方向に変わりつつある。 [阿部 齊] 経済・産業アメリカ経済発展の基礎独立当時のアメリカは、大陸の東の端に散在する小さな農村の連合体で、ヨーロッパ経済の辺境であった。商業は内陸との取引よりもヨーロッパとの取引のほうが大きく、輸出品は農産物であり、工業品はほとんど輸入に頼っていた。しかしその後のアメリカ経済の発展は目覚ましかった。19世紀なかばにはアメリカは世界最大の農業国になり、19世紀末には世界最大の工業国となった。そして20世紀なかばには、第二次世界大戦後の特殊事情もあったが、世界の総生産の半分以上をアメリカが生産したのである。その後アメリカ経済の比重は低下して1980年には世界の総生産の21.5%となったが、それでも今日アメリカが世界最大の経済国であることに変わりはない。このようなアメリカ経済の発展は、なににもまして経済の拡大が長期にわたって着実に続いたことによって達成された。 1800年ごろのアメリカの国民総生産がどれほどであったかは、推定値に差があって確定していない。しかしおおむね、1952年価格で計って、1人当り250~300ドルの範囲であったと考えられる。この数値はその時代のヨーロッパ先進国に比べて遜色(そんしょく)がない。それは主としてアメリカが広大で肥沃(ひよく)な土地に恵まれていたためであったと思われる。1800年から1830年代の終わりごろまで、アメリカの1人当り国民総生産の伸びは低く、1%を下回る水準であった。しかし、1840年代からアメリカ経済の成長率は高まり、平均すると1人当り国民総生産は年率1.64%、つまり43年ごとに2倍になる速度で増加した。そして1960年の1人当り実質国民総生産は1830年代の約7倍となった。このような経済の発展は、経済に対する投入資源の増加と技術の進歩によって達成された。アメリカに豊かに存在した土地と天然資源、急速な人口の伸びは投入資源の増加をもたらしたが、経済成長に対する貢献度からいえば、科学知識の進歩、経営方法の改善、労働者の教育水準向上などを含めた技術進歩のほうが大きかった。 [榊原胖夫] 1960年代以降の概観1960年代のアメリカ経済は未曾有(みぞう)の繁栄を記録した。年平均成長率は4.2%、失業率の平均は4.8%で、生産性向上率、実質賃金の伸び、物価の安定など、どの指標をとってみても歴史上かつてなかった繁栄の10年であった。しかし1970年代に入ると事情は一変した。1973年には強い米ドルに依存して成り立ってきた固定為替(かわせ)相場制の維持が困難になり、多くの国が変動相場制に移行、戦後の世界経済を支えてきたアメリカ体制が崩壊したとささやかれた。同年には石油危機が発生し、資源制約が一挙に顕在化した。各国とも物価上昇に悩み、金融を引き締めた。経済は不況に陥ったが物価は安定せず、高い失業率とインフレが共存する「スタグフレーション」になった。その調整が十分に進まないまま1979年に第二次石油危機が発生した。1970年代アメリカ経済の年平均成長率は3.2%、失業率は6.2%、実質賃金はまったく上昇せず、消費者物価の年平均上昇率は7.1%になった。 1980年初めにアメリカ経済は不況に陥った。1983年から実質国内総生産は回復に向かったが、1991年にはふたたび不況にみまわれた。1980年から1991年までの実質成長率は年平均2.3%、失業率は7.1%と1970年代より悪化し、消費者物価は1980年を100とすると165となり、多少とも鎮静化したが、生産性の伸びは、1960年代年平均3.2%、1970年代年平均2.1%、1980~1991年は1.4%と低下している。不況のため新規投資が減少したこと、新規投資は生産を増加させる方向に向けられず、公害対策など生活の質の向上に向けられたことがその主たる原因であった。 1970年から1991年までの長い不況期に、アメリカ経済は大胆な改革を実行し、1992年以降の息の長い上昇の基礎を築いた。1970年代初めから自動車、金属製品などの伝統的な産業は相対的に衰退し、コンピュータ、テレコミュニケーション、航空などの新しい産業が拡大した。新しい産業の勃興(ぼっこう)は第二次産業革命といえるほど急激で、またその影響が及ぶ範囲は広かった。アメリカ経済は「産業革命」にすばやく順応し、政府も旧秩序を守ろうとはせず、むしろ積極的に変化に対応した。何よりもまず規制緩和と競争の促進が必要であった。規制緩和への努力は第一次石油危機直後、ニクソンのあとを継いだフォード大統領のときに始まった。フォードはインフレの原因の一つに不必要な規制があると考え、交通を中心に既得権益への挑戦を始めた。フォードのあとの歴代大統領も民主党、共和党の別なく、小さな政府、規制撤廃、競争の重視という点では一致していた。 1981年に大統領に就任したレーガンは、インフレと失業を同時に低下させアメリカ経済の再生を図ることを目的として、歳出削減、減税、規制緩和、安定的金融政策を四本柱とする経済再建計画を発表した。再建計画は従来の短期的な総需要管理政策にかわって長期的な供給政策を重視したもので、理論的にも政策的にも大胆な実験であった。これらの政策のうち、減税、規制緩和、安定的金融政策は実行に移されたが、歳出削減は思うように進まず、その結果生じた財政赤字の増大は、金融市場を圧迫して高金利をもたらした。そのため各国とも利子率引下げなどの景気刺激策をとることができず、アメリカは世界の不景気を永続させているとして非難の的となった。国際収支の面でアメリカは、1976年以降赤字の傾向が定着し、金額的にもしだいに大きくなった。そのため1980年代から1990年代初めには、財政の赤字とあわせて、双子の赤字とよばれた。貿易の不均衡に加えて雇用不安が高まったことから保護主義が台頭した。とくに自動車や電気製品などアメリカの主力製品と競合して輸出を急増させた日本に対する非難が高まった。 しかし1990年代に入ると、財政赤字は歳出削減努力、ソ連の崩壊による軍事支出の減少と好景気による歳入の増加などによって徐々に縮小し、1997年にひとまず均衡が達成された。また貿易では雇用不安の消滅とともに保護主義の動きも静まり、むしろ外国の門戸開放、不公正な貿易慣行是正などによる輸出の増大を目ざすようになった。しかし国際収支の均衡にはいましばらく時間がかかりそうである。 1970年代以降の技術革新は情報の移動を容易にするものが多く、経済の国際化を促す要因となった。地球上に複数の生産拠点をもつ企業は多国籍企業とよばれたが、今日では資本も経営も労働も多国籍化した「世界企業」が増加している。 1992年以降アメリカ経済は継続的な成長を遂げ始めた。失業率は完全雇用水準に近くなり、生産性も上昇傾向をたどり、物価も安定した。1993年にはクリントンが大統領に就任した。クリントンはレーガン、G・H・W・ブッシュとは違い、民主党であった。しかしその経済運営は前政権と大きく異ならず、その意味で民主党と共和党の経済政策における差は縮まった。2001年には、ふたたび共和党のG・W・ブッシュが大統領に就任、ITバブル崩壊や同時多発テロの影響で、景気後退の局面をむかえたが、その後は緩やかな回復が続いた。しかしブッシュ政権期の後半には、上昇を続けていた住宅価格が2006年を境に鈍化、低所得者向けの住宅ローンであるサブプライムローンの延滞が増加した。このローンを証券化した金融商品が世界中に販売されていたこともあり国内外経済への影響は大きく、アメリカのみならず諸外国の景気を後退させる原因となった。アメリカ国内においては、2008年の大手投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻(はたん)、大手保険会社AIGへの公的資金注入、また基幹産業である自動車産業の経営不振等、サブプライムローン問題は深刻な影響を及ぼした。これらへの経済対策は2009年発足のオバマ政権に与えられた大きな課題の一つとなった。 [榊原胖夫] 資源と労働アメリカの地下資源は豊かで、東のアパラチア山系では石炭、鉄鉱石、ボーキサイト、銅などが生産され、西のロッキー山脈の両側からテキサスにかけては石油や天然ガスが生産されている。アメリカの石炭産出量は世界の約26%(2001)、石油は8%(2004)、天然ガス21%(2002)、銅鉱石8%(2003)などとなっている。アメリカの鉱業生産額は相対的に低下しているが、それは資源が枯渇(こかつ)したというよりも、他国の安い製品を輸入しているからである。たとえば、1970年代に入ってアメリカの石油輸入が急増した。アメリカで産出される石油は、中近東その他の新興産油国に比べると産出コストが高くなったためである。アメリカの1人当りエネルギー消費量は、アラブ首長国連邦とカタールを除けば、世界でもっとも多く、エネルギー輸入量も世界でもっとも大きい。 1995年(かっこ内は2003年の数値)のアメリカの労働力人口(軍関係を除く)は1億3230万(1億4651万)人であった。労働力率(人口に占める労働参加者の割合)は長期的に上昇しつつあり、1970年の60.4%から1995年には66.6(66.2)%になっている。労働力率の上昇は女性の労働参加が進んだためで、1970年の男性の労働力率は79.9%、女性は43.3%であったが、1995年には男性75.0(73.5)%、女性58.9(59.5)%になっている。朝鮮戦争後のベビーブーム世代が成年に達した1970年代を過ぎると、増加率は安定し、労働の質も向上したといわれている。失業率は1980年代初めの不況時に9%を超え、1930年代の大不況以来もっとも高い率となった。1980年代、経済の停滞を反映して高い失業率が続いた。1990年代に入ってからは1992年に7.5%を記録したものの、その後は好景気を反映して低下し、2000年には4.0%まで下がった。しかしその後は増加傾向にある。 1995年の失業率は5.6%であった。これを男女別、人種別、年齢別にみると、アメリカの複雑な雇用情勢を知ることができる。1995年では白人の失業率は4.9%(男4.9%、女4.8%)、黒人の失業率は10.4%(男10.6%、女10.2%)であった。失業率の男女差はほとんど消滅したが、それは賃金の安い第三次産業において女性の雇用が拡大したためと考えられている。一方黒人と白人とでは失業率に2倍以上の差がある。その差のかなりの部分は教育水準によって説明される。1995年に25歳以上で四年制大学を卒業したものは白人男性27.2%、女性21.0%であるのに、黒人では男性13.6%、女性12.9%である。もちろんそのような差を生んだ背景に歴史的に存在した差別があることを否定することはできない。 最大の雇用問題はティーンエイジャーの高い失業率である。白人男性15.6%、女性13.4%、黒人男性37.1%、女性34.3%で、ここでも黒人は白人の2倍を超え、黒人ティーンエイジャーの2.7人に1人は失業していたことになる。 アメリカは雇用労働者の国である。労働力人口に占める雇用労働者の比率は91%に達している。また1995年をとると国民所得のなかで雇用労働者が稼いだ所得は72.6%であった。個人経営の農場や商店の少ないことがその大きな原因である。アメリカの雇用労働者は自らを中産階級と考えており、階級意識は低い。非農業雇用労働者のうち約20%は労働組合に参加しており、組合員の80%はAFL-CIO(アメリカ労働総同盟・産業別組合会議)に属している。近年労働者の組織率は低下傾向にあるが、それは産業構造の変化に伴って、労働組合を組織しやすい製造業や交通運輸業の労働者数が相対的に減少し、組織化がむずかしいか不可能なサービス業や政府機関に属する労働者が増えたためである。1970年代、1980年代アメリカでは労働争議の件数も、参加者もそれによって失われた労働日数も多かった。1970年にストライキで失われた人・日は全労働人・日の0.29%であった。その後ストライキの数は減り、1994~1995年では0.02%にすぎなくなっている。一方1993年の調査では、職場でコンピュータを用いている労働者の数は5100万人で、労働力人口の46%に達している。 [榊原胖夫] 農業・林業・漁業アメリカが世界最大の工業国であることはよく知られているが、世界最大の農業国であることは忘れられがちである。アパラチアからロッキー山脈に至る大平原は世界でも有数の肥沃(ひよく)な土地で、北から南へ帯状に小麦、トウモロコシ、綿花の生産地が広がっている。そのほかにも米、大麦、ライ麦、ジャガイモ、サツマイモ、大豆、ピーナッツ、葉タバコなど、それぞれの適地で生産され、小麦、トウモロコシ、大豆、綿花などではアメリカは世界最大の輸出国になっている。また果物はカリフォルニア、フロリダを中心に各地で生産され、牧畜、養鶏も盛んで、牛乳、乳製品、卵、ワインなどの生産量は着実に増えている。 世界最大の農業国であるとはいっても、アメリカ人のなかで農業に従事している人の数は少なく、労働力人口の2.1%にすぎない。アメリカの農業は肥沃な土地と機械化、商業化、品種改良などによる高い生産性に支えられている。農業生産性の伸び率は製造業の生産性伸び率と比べて劣っていない。生産性向上とともに農場数は減少し、平均農業規模は拡大した。1982年の農場数は約224万(1950年538万)、平均農業規模は約440エーカー(1950年215エーカー)であったが、2002年にはそれぞれ213万、441エーカーになっている。また1000エーカー以上の農場の数は全体の8.4%にすぎないが、全体の66.9%の農地を保有している。 アメリカ農業の最大の悩みは生産過剰、価格の低下、農業所得の減少であった。ニューディール期に農産物価格支持制度が発足したが問題は解決されず、1970年代になって廃止された。しかしその後ロシアをはじめ海外の農作物が不振で、輸出が好調であるため、活況をとりもどしている。1995年アメリカの農作物輸出は金額でみると世界の農産物輸出の14%を占め、肉類、魚介類、トウモロコシ、果物、採油用種子、綿花などで世界一となっている。 1992年、総森林面積は7億3700万エーカーで、そのうち商業用森林面積は4億9000万エーカーである。西部には商業化されずに残されている森林が多い。商業用森林の73.1%は民間所有である。1994年の材木生産高は世界の材木生産高の14.3%、輸出は世界の総輸出の15.0%を占めている。 アメリカは中国、日本、ペルー、チリなどと並ぶ漁業国で、2003年の漁獲高は499万トンであった。近年の健康ブームにのって食料としての魚介類に注目が集まり、漁業はさらに盛んになる兆しをみせている。 [榊原胖夫] 産業構造アメリカ経済の構造変化を国内総生産の構成からみると、製造業の相対的低下と金融・保険・不動産業およびサービス業の増大が認められる。そのうち金融・保険・不動産業の増大はおもに1980年代以降であるが、そのほかは第二次世界大戦後の一貫した傾向である。たとえば製造業の国内総生産に占める割合をとってみると、1947年に26.9%、1972年23.4%、1990年15.5%、1998年15.4%、2003年には12.7%になっている。産業構造の変化は就業労働者の割合をとってみるといっそう明確になる。1980年に22.1%であった製造業の労働者は2003年には12.3%になっている。労働者の割合を大きくくくって物財を生産している産業、無形財を生産している産業に分けると、その比率は1970年で37.5:62.4、1980年32.7:67.3、1990年27.8:72.2、2003年22.7:77.3である。実に80%近い就業者が交通・運輸、卸・小売、金融、保険、不動産、サービス、政府部門など無形財の生産に従事していることになる。国内総生産と就業者から判断すると、製造業では生産性の向上が達成しやすく、無形財生産ではむずかしいことがわかる。無形財部門の増大は主として就業者数の増加によってまかなわれてきたのである。今後もっとも早く増加すると予想されている職種は、高齢者に対するヘルパーで、続いてシステム・アナリスト、コンピュータ技術者などで、減少が続くと想定されているのはいわゆる一般事務職と技術進歩のなかで取り残された機械のオペレーターである。 製造業のなかでは1974年の石油危機以降かなり急激な構造変化が生じている。1973年以前の業種間の売上高の伸び率における格差は1974年以降の業種間格差に比べるとかなり小さい。雇用や設備投資や研究開発投資の伸び率における格差の広がりはいっそう大きくなっている。成長しつつある産業は、コンピュータ、事務機器、半導体、通信機、その他精密機械、石油、航空、宇宙開発、エレクトロニクス、化学、電気などで、不振に陥っているのは、伝統的な主力産業、つまり鉄鋼、自動車、繊維、ゴム・タイヤなどである。一般に知識集約型、高付加価値産業の比重が高まりつつあるといえる。高成長産業は東北部よりは西部や南部に多く立地したため、地域間所得格差は縮小した。しかし物財生産における所得分配に比べると無形財生産における所得分配のほうがはるかに不平等で、そこには技術先端産業に雇用される高給の技術者から、給料の低いスーパーのレジ係まで含まれている。したがって無形財生産の拡大は所得分配を不公平にする傾向があり、このままでは社会の安定の基盤である中産階級が消滅するのではないかと心配する人もある。また1980年代、1990年代には巨大企業への資産の集中が進んだ。現代の技術革新が企業の最適規模を大きくする性格のものであり、それによって経営の多角化、国際化が可能になったことを示している。 [榊原胖夫] 交通・通信アメリカの広大な国土は、もっともよく発達した交通・通信網で覆われている。西部開拓史は交通発展の歴史であるといわれるように、交通の発達がアメリカの経済発展を支えてきたといえる。 2001年の道路延長は約637万8000キロメートルで、そのうち高速道路、自動車専用道路などの主要道は約70万3000キロメートルである。高速道路は都市周辺部や橋梁(きょうりょう)を除くとたいてい無料である。乗用車の保有数は約1億3763万台、商用車をあわせると2億台を超え、二輪車も含めると人口1000人当り808台になる。多くのアメリカ人にとって自動車は足の延長であり、その意味でアメリカは自動車文明の国である。 1994年の鉄道軌道の延長は約36万キロメートルで、1980年と比べても、11万キロメートルほど減少している。鉄道は旅客を航空に、貨物をトラックに奪われ、斜陽をかこっているが、とくに旅客輸送の減少は著しい。1971年に開始されたアムトラックAmtrak(全米鉄道旅客輸送公社)による旅客輸送も、石油危機当時脚光を浴びたが、ふたたび赤字が増大し破産状態に陥った。しかし、1990年代後半には、貨物輸送においては復権の兆しをみせた。すなわち、重くてかさばる農産物、鉱産物は大陸の中央部で生産されるものが多いため、その輸送はいまでも多く鉄道に頼っている。鉄道による都市内大量輸送ではサンフランシスコのバート、ワシントンDCのメトロ、アトランタのマルタなど新設された線路も少なくない。また、2000年にはニューヨーク、ボストン間に高速鉄道のアセラ・エクスプレスが営業を開始している。 航空輸送は旅客・貨物とも輸送量において他の諸国を大きく引き離して、トップの座を占めている。1978年の法律で航空に対する経済規制が全面的に廃止されると競争が激しくなり、運賃は大幅に低下、需要の拡大につながった。しかしそれは一方で航空会社の経営を圧迫し、その統廃合が進んだ。国際線ではアメリカの航空会社のコスト優位性が目だち、それを背景にアメリカは外国に自由な航空協定を結び、競争を促進するように求めている。 アメリカの商船保有は、1074万トン(2004)であるが、パナマ、ギリシア、リベリアなどへの便宜置籍船もあり、海港はコンテナ輸送を中心に活況を呈している。しかし、従来型のバース(保留施設)が不要になって再開発されたところも多い。 アメリカは確かに交通がよく発達した国であるが、国土が大きく、主要産品に重くてかさばる種類のものが多いせいで、国民総生産が1%伸びるにあたって必要な輸送量の伸びは、日本やヨーロッパ諸国に比べて大きく、その意味では不効率であるともいえる。1991年には「インターモーダル交通効率化法」が成立し、交通政策の基本的スタンス(構え)が示された。それは交通機関の間の連携を密にして全体として効率的な体系をつくろうとするもので、その効率には環境に対する負荷を軽減することも含まれている。 テレビ、ラジオ、電話機などの1人当り保有率、郵便受取数、新聞雑誌、図書などの発行部数なども世界のなかで群を抜いて多い。 1990年代に入るとインターネットが爆発的にその規模を拡大した。インターネットは国防総省の高等研究計画局(ARPA)による軍事目的のARPANET(アーパネット)や大学など研究機関のネットワークから発展したが、1993年9月にクリントン政権によって国家情報基盤(NII)構想(情報スーパーハイウェー構想)が発表され通信基盤がさらに強化された。今日、全世界でインターネットに接続されるホストコンピュータの数は2億1915万台(2003)と推計されているが、そのうちアメリカは1億6221万台で、世界一を誇っている。 [榊原胖夫] 国土の開発と保全広大な国土をもつアメリカは、歴史的にみても、つねに内陸開発に積極的であった。しかし開発の促進主体はおもに州ないしは地方自治体であった。連邦政府の手による大規模開発事業は、1930年代のTVA(テネシー川流域開発公社)に始まる。そして1960年にはアパラチア地域開発事業が始まり、1965年には経済開発庁(EDA)も設立された。一方アメリカには環境保全運動も古くから存在し、1856年のニューヨークのセントラル・パーク設置条例、1872年のイエローストーン国立公園をはじめとして、各都市、各地域に同種の公園が続々と誕生した。またニューディール期には工場の地方分散化計画やグリーンベルト構想がたてられている。1960年代後半から1970年代初めにかけて農薬、中性洗剤、産業排水による水質汚濁、工場の排煙、自動車の排ガスによる大気汚染が問題となり、環境保全のための多くの法律が制定された。そのなかには1970年の大気清浄化法改正法(いわゆるマスキー法)や同年の国家環境政策法がある。後者によって連邦環境保護庁が設立されている。いかにして開発と環境保全とのバランスを維持するかがそのおもな役割である。 [榊原胖夫] 財政・通貨・金融先進国の財政はどこも、景気停滞による歳入の頭打ち、福祉関係その他歳出の硬直化によって困難の度を加えているが、アメリカも例外ではなかった。連邦政府の財政赤字は1980年代に入って急増し、1992年には2904億ドルと戦後最悪を記録した。すでに述べたようにその後1997年には、1969年以来初めて財政収支の均衡が達成された。しかし、2002年にはふたたび財政赤字となっている。1995年では財政収入のうち個人所得税が44%ともっとも大きく、社会保険36%、法人所得税12%、間接税4%などとなっている。歳出では所得保障が15%、国防費17%、利子支払16%、社会保障負担22%、メディケア(老人医療保険)13%などとなっている。なお、固定資産税は地方税で、そのほかに地方が独自に設けている所得税や間接税がある。また教育、交通などの支出においては地方政府の役割が大きい。政府支出に占める連邦支出の割合は、1993年には62%で、低下傾向をたどっている。また国内総生産に占める政府部門の割合は1980年で20.6%、1995年で18.7%で、軍事費の割合が6.3%から4.8%に低下したことが大きい。 アメリカの通貨単位はドルで、1973年変動相場制移行以来、円、ドイツ・マルク、スイス・フランなどの通貨に対して大きく減価した。しかし1990年代に入ってアメリカ経済が好調のため、ドルは高めに推移している。アメリカの銀行制度は日本やヨーロッパと違い、全国に支店網をもつ市中銀行が存在しなかった。銀行はもともとそれが存在する都市と周辺農家のためのものであり、地域性がきわめて強かった。もっとも資金量が豊かで巨大化した商業銀行は存在した。バンク・オブ・アメリカ、チェース・マンハッタンなどはその例である。銀行の認可権はいまでも州にあるが、1994年以降他州における支店開設規則は撤廃された。2002年の銀行店舗数は商業銀行、貯蓄・貸付銀行をあわせて約8万7000である。そのうち本店の数は約9000であり、1行1店舗の銀行がまだ多いことを示している。しかし銀行数も店舗数も合併、併合などによって急速に減少しつつある。金融市場のなかに占める銀行の相対的位置は、金融商品の多様化に伴って低下している。ウォール街には銀行以外に投資金融業者が数多くあり、投資信託会社が巨大化している。また巨大な保険会社の動向が金融市場に与える影響も無視することはできない。これらの資金がどこに向かうかによって特定の国に通貨不安が生じるなど、国際経済の不安定要因になる可能性がある。金融における規制の撤廃は1970年代に始まり、1990年代も進行中である。金融システムは情報技術とコンピュータ化の影響を受けて業務形態を変えつつあり、アメリカ人のもつ金融資産も多様化している。それを受けて金融改革は、銀行、証券などの業種間の垣根を取り払うこと、規制を撤廃して競争をいっそう盛んにすること、預金者保護を強化することに向けられている。1980年代に多くの貯蓄・貸付銀行の経営が破綻(はたん)した苦い経験から、自己資本規制の強化と連邦預金保険公社の拡充が実行に移された。 アメリカの中央銀行制度は連邦準備制度とよばれる。連邦準備制度が発足したのは1913年で、他の先進諸国よりかなり遅れている。独立当初から1833年まで合衆国銀行とよばれる国立銀行が存在したが、ジャクソン大統領のとき、権力の集中を危惧(きぐ)して免許を更新しなかったため消滅した。連邦準備銀行はアメリカ本土に12行あり、その運営は連邦準備制度理事会によって行われている。連邦準備銀行は連邦準備制度に加入しているメンバー銀行によって所有されているが、メンバー銀行が連邦準備銀行の政策に影響を及ぼすことはまずない。これらの連邦準備銀行は連邦準備紙幣を発行し、メンバー銀行の準備を保持し、必要とあればメンバー銀行に資金を貸し出す。理事会は準備率の変更、割引率の決定を行う。近年ではマネタリスト(通貨政策重視派)たちの影響がきわめて強く、全体的な通貨供給の管理が最優先されている。また連邦準備銀行と市中銀行との関係は、他の国の場合ほど密接とはいえず、アメリカの銀行は自由銀行制度時代の独立性を精神的なよりどころにしているものが多い。 [榊原胖夫] 貿易・国際収支・対外援助アメリカの対外貿易は1875年から1970年(1888年、1889年、1893年を除く)までほぼ100年間にわたり、つねに黒字であった。しかし1976年以降は慢性的な赤字となった。2003年の経常収支の赤字幅は5300億ドルに達している。貿易相手国ではカナダがもっとも大きく、中国が急速に伸びて2位となり、ついでメキシコ、日本、ドイツの順となっている。資本収入は1993年まで黒字であったが、1994~1995年ではわずかに赤字となった。 昔からアメリカでは国内市場が大きく、対外貿易の比重が小さいとされてきた。確かに国民総生産に占める輸出および輸入の割合(輸出依存度、輸入依存度)は、1960年まで5%を超えたことはなかった。しかし1960年代後半から急速に上昇し始め2003年では輸出6.6%、輸入11.9%になっており、輸入について日本よりもかなり高くなっている。その分アメリカ経済と世界経済のつながりが深くなったといえる。 アメリカは第二次世界大戦後、対外援助において指導的な役割を果たしてきた。ほかの先進諸国の援助額が増えたためアメリカの比重は減少してきたが、1990年代なかばでもアメリカは世界でもっとも多い500億ドルから700億ドルの経済協力支出を行っている。なお、2004年の政府開発援助(ODA)の実績では、アメリカは約1900億ドルでもっとも多いが、対GNI(国民総所得)比では0.16%で、世界21位にとどまっている。 [榊原胖夫] 社会・文化アメリカ社会・文化の特質と変貌アメリカ合衆国の社会や文化は、日本の場合と比べるとはるかに複合的、多角的である。広大な国土、強い州権による地域的な特色、多人種・多民族からなる人口構成などがそのおもな原因であるが、それでいてなお全体を統合する強い特質をもっている。 始めその特質の核となったのは、WASP(ワスプ)(White Anglo-Saxon Protestant白人、アングロ・サクソン、プロテスタント)たちであった。このことばが生まれたのはずっとのちになってからであるが、第1回国勢調査(1790)当時、住民の約80%は白人であり、その白人の約61%はイギリス系であった。建国当時から、WASP中心の生活様式や価値観が支配的だったのである。このため、独立してからもアメリカの文化はなおイギリスの模倣が多かった。西方へ延びる広い国土に対して人口密度は非常に低かったので、どうしても屋外の肉体労働が多くなり、生活自体の要求が先行して、アメリカ独自の文化の発展を遅らせた。ところがそのような先住民アメリカ・インディアンと広い土地を相手にする生活のなかから、つまり大衆の日常生活のなかから、アメリカ文化の基盤がしだいに養われていくのである。こうしてアメリカ独自の文化がつくられるようになったのは、モンロー宣言が出されてからアメリカ人という意識の高まるようになった1830年代である。南北戦争(1861~1865)後から20世紀初めにかけては、南欧や東欧からのWASPではない移民が急増し、言語や宗教などが急速に多様性を帯び、そのため社会的な混乱もおこるようになって、1924年には移民割当法が成立し、日本移民はこのとき禁止されて、無制限に移民を受け入れていた時代は終わった。 しかしこの1920年代に、世界に先駆けてアメリカが高度の大衆消費時代を実現させた点は、特筆されてよい。産業革命はイギリスから始まったが、このときまでにアメリカの豊富な資源や自由なエネルギーがみごとに昇華し、国民の多くが自動車を所有できるような大衆消費時代を、イギリスよりも一足先につくりあげることに成功したのである。このためアメリカ人の生活文化は、第二次世界大戦後に空前の軍事力と経済力を伴って世界中に広まった。コカ・コーラなどに象徴されるアメリカ的生活様式は、のびのびとした中産階級の層の広がりをみせ、多くの国の人々のあこがれの的となった。各種の文化もニューヨークなどの大都市を中心に充実して多彩な動きをみせ、ヨーロッパだけが文化の中心舞台であった時代は終わった。とくに映画、テレビ、ミュージカルなどの大衆文化や、情報文化、若者の文化などにおいては、アメリカが完全に世界をリードするようになった。 しかし、1960年代に入って、アフリカ系住民(黒人)を中心とする公民権運動が高まり、そのほか各種のマイノリティ・グループの発言権が増大するにつれて、WASPの価値観はしだいに地盤沈下をきたすようになった。このことは、アメリカの社会や文化をいっそう多様化させる結果となっている。WASP以外の人々も、従来のようにWASPのコピーにならず、それぞれの特色を発揮することにむしろ誇りと意義を感じるようになったからで、これは一種の大きな意識革命といえるものである。このほか、1960年代を特色づける一連の現象、大学紛争やベトナム反戦運動、ウーマン・リブ運動、公害反対運動、ヒッピーなどのカウンター・カルチャー運動などを経て、かつての自信に満ちていた時代のアメリカ的生活様式は、かなりの変貌(へんぼう)をみせるようになった。1970年代に入って、石油危機やウォーターゲート事件、ベトナムからの撤退などは深い挫折(ざせつ)感をアメリカ人の心のなかに刻み込み、これが屈折した形で生活の各方面ににじみ出してきた。 いまアメリカの社会や文化は大きな曲がり角に差しかかっている。あまりにも多様な要素が絡み合っているので、ときには秩序が破壊されたり、荒廃した一面をさらけ出したりすることもある。しかしまた、自分たちの価値観や生活様式だけが世界のなかで唯一最高のものであると考えていたことの誤りを、アメリカ人はいま苦痛をもって学びつつあるという一面ももっている。しかし、依然として全人類の実験場としての壮大なスケールの性格を失ってはいない。だからこそ全世界の人々が、いまもなおアメリカの社会や文化の動向に、熱い視線を注いでいるのである。 [渡辺 靖] 住民(人種・民族)合衆国は世界でも有数の多民族国家である。先住民としてのネイティブ・アメリカン(アメリカン・インディアン)を除けば、すべて他国から過去3世紀以内に移住してきた者およびその子孫たちから成っている。独立戦争から間もない1790年までに約60万人が合衆国に移住したが、その約3分の2がイギリス系だった(当時の総人口は約315万人)。その後、19世紀中盤にかけて西欧や北欧からの移民(イギリス系、アイルランド系、ドイツ系など)が、そして19世紀末からは東欧や南欧からの新移民(イタリア系、ポーランド系、ユダヤ系など)が急増した。民族的にはラテン系やスラブ系、宗教的にはキリスト教カトリックやギリシア正教、ユダヤ教が多く、従来の旧移民(民族的にはアングロ・サクソン系ないしゲルマン系、宗教的にはキリスト教プロテスタント=新教徒)とは文化的背景を大きく異にした。加えて、外見や風俗習慣がさらに異なる中国系や日系などアジア系の新移民も加わるようになり、新移民の入国数が旧移民を上回るに至った。1901年からの10年間には旧移民191万人に対し、新移民は623万人を記録する。1900年当時の総人口が約7600万人なので、毎年総人口の1%にあたる移民が入国したことになる。 移民の急増に伴い移民排斥の動きも活発になった。とりわけ秘密結社クー・クラックス・クラン(KKK)は有名で「100%のアメリカニズム」を唱え、彼らが「アメリカ的」ではないとみなした人々、たとえばアフリカ系住民、カトリック教徒、新移民などへ暴力や脅迫を繰り返し、なかでもアフリカ系住民へのリンチ行為は凄惨さを極めた。KKKの活動のピークは1920年代だが、日本が排日移民法とよんだ移民割当法が制定され、事実上、日本からの移民が認められなくなったのもこのころである。 合衆国は、建国以来、5000万人以上の移民を迎え入れ、今日もなお年間70万人を受け入れる移民大国である。民族的出自に関する自己意識にまつわる調査(2005)によると、ドイツ系(15.2%)、アイルランド系(10.9%)、イギリス系(8.7%)を筆頭に白人が全体の約75%を占める一方で、ヒスパニック系14.5%、アフリカ系12.1%、アジア系4.3%、先住民0.8%となっている。全都市の約6分の1にあたる505都市では、20歳以下の人口に占める少数民族の割合が白人を超え「多数派」になっている。2005年に2億9600万人だったアメリカの人口は、現在の傾向が続けば、2050年には4億3800万人に増加し、白人が占める比率は人口全体の47%になるという予測もある。それは、過半数を占める「多数派」の人種がなくなるという、合衆国史上初の状態を意味する。 その一方で、不法移民(不法入国者)の存在も深刻度を増しており、その数は1200~2000万人と推定され、大半がメキシコから出稼ぎ目的で国境を渡ってきたヒスパニック系とされている。アメリカ人から職を奪う、麻薬が持ち込まれる、国民の税金で支えられている社会福祉制度に大きな負担となるなどの理由で取り締まり強化を求める声も強い。しかし、破格の低賃金で雇える不法移民は、合衆国全体の就労人口のすでに5%を占めるともいわれ、まさに産業の底辺を支えているという現実も無視できない。また、取り締まり強化は不法移民に同胞意識をもつ合衆国内のヒスパニック系住民の反発を買う恐れもあり、政治的に非常にデリケートな問題となっている。 [渡辺 靖] 言語合衆国憲法はいかなる言語も合衆国の国語とは定めていない。つまり、英語は合衆国の国語(公用語)ではない。州レベルでも英語を公用語に指定しているのは50州中30州にとどまっている。国勢調査(2000)によると、国民の82%が家庭で英語のみを使用しているが、アメリカ国民の5人に1人は英語以外の言語を使用している。英語をアメリカの国語に定めようという動きはつねに存在するが、英語以外の言語を日常的に使用している多くの国民が社会的に不利な状況に置かれかねないという懸念から、これまで連邦レベルで法制化されることはなかった。英語を国語とすることで社会をより効率的に運営することが可能になるかもしれないが、その代償として損なわれてしまうアメリカ社会の魅力や活力が多いという判断である。 [渡辺 靖] 国民生活生活水準の高さはかつて世界中の羨望の的であったが、貧富の差、そしてそこに密接に絡むドラッグ、人種差別、ギャング抗争、学校崩壊といった社会問題も深刻である。 1930~1960年代にかけてニューディール政策の再分配政策により貧富の差が縮小し、大量の中産階級(ミドルクラス)が誕生した。しかし、1970年代以降、「小さな政府」のイデオロギーが主流となるなか、福祉政策の切り詰めなどによって貧富の差が広がり、とりわけ中産階級の没落が顕著になった。2007年には上位10%の富裕層が所得全体に占める割合は48.5%とほぼ半数に達し、富裕層のみ所得が1割増となった。その一方、米住宅都市開発省(2007)は、公園や道路などで寝泊まりしているホームレスが75万人に達していると発表した。単純に比較はできないが、その数は日本の約30倍に相当する。また、食料安全保障報告(2008)は、全米の14.6%にあたる1714万世帯が、同年中に収入不足などから家族全員に十分な食事を与えられない「食料不足」を経験したことがあると伝えている。 こうした貧富の差を背景に、防犯のため地域全体を塀で囲んで、中に入れる人を制限する高級住宅地「ゲーテッド・コミュニティ」の居住人口は1995年には400万人だったが、1997年には800万人、2006年には全米5万か所で2000万人規模にまで拡大している。その一方、塀で遮断されたもう一つのコミュニティである「刑務所」の服役者数も倍増し、2006年には収監者数が230万人に達している。 相対的に、東部・北部の諸州は比較的豊かであるのに対し、南部の諸州は貧困層が多い。「1人当り州民所得」(2006)によると、最高所得がコネチカット州で4万9852ドル、全米平均(3万6276ドル)を100とした場合の相対値が137、最低所得がミシシッピー州で2万6535ドル、相対値が73となっている。 [渡辺 靖] 国民性イギリスによる植民地支配の経験から、アメリカの独立13州では連邦政府を創設することに対し当初から強い危惧の念が存在した。つまり、せっかくイギリス王政への隷従のくびきを脱したのに、連邦政府という名の新たな支配者を君臨させたのでは、何のために独立戦争を戦ったのかわからないという発想である。その結果、合衆国では家族を中心にした自分の住む地域、コミュニティへの帰属意識が強い。市町村にしても日本のように行政主導で制定されるのではなく、個々のふれあいから村ができ、町ができ、市ができ、やがては州へ(すなわち、下から上へ、個から全体へ)と自治が発展していった。とくに、ニューイングランド地方で発達したタウンホール・ミーティングに代表される住民集会は、王や宗教に頼ることなく、参加者の討議と自発的な約束によってルールを形成するアメリカ民主主義の原型とされる。 1831年に合衆国を訪れたフランスの貴族アレクシ(ス)・ド・トクヴィルAlexis-Charles-Henri Clerel de Touquvill(1805―1859)は名著『アメリカのデモクラシー』において、合衆国では自発的結社の活動が宗教・政治・学術・慈善・公益など多岐にわたっていることに注目し、こうした結社の活動こそは、孤立しがちな個人に、他人と協力して何ごとかをなすための術を教えていると賞賛した。 コミュニティや結社はいまなおその自治の土台をなすものである(日本のような全国紙がない一因もそこにあるとされる)。連邦政府に対して情報開示を求め、市民としての公正な権利を求めることはアメリカ人にとって大きな意味を有する。中央政府への懐疑と合衆国への忠誠が必ずしも矛盾しない点がアメリカの国民性を理解するうえで重要である。 [渡辺 靖] 教育歴史的な経過をみると、日本と決定的に異なるのは、初等教育がまだ整備されていないうちに、高等教育機関が拡充していった点である。ハーバード・カレッジが創立されたのは1636年であり、合衆国建国より1世紀以上古い。2005年時点で、大学進学率は64.6%であり、同年の日本の52.3%を大きく上回っている(文部科学省「教育指標の国際比較」による)。また、大学院以上の進学者も25歳以上の人口の9%を占めており、高学歴化が進んでいる。一般に私立大学が名門難関、州立大学が大衆的であるが、総じて世界的に著名な大学が多いのも合衆国の特徴である。 しかし、歴史的に、国民の大部分にとっては初等教育すら受けられない状態が長く続いた。リンカーン大統領が受けた教育は合計1年足らずであり、西部開拓熱の高かった1840年の国民平均修学年数は約1か年であった。現在でも、初等中等教育に関しては寄宿舎制度を有する名門私学が存在する一方で、貧しい地域では財政や治安の点で問題を抱える公立学校も少なくない。 1990年代からは特別認可charter、あるいは達成目標契約により認可された公設民間運営校(チャーター・スクール)が増加している。これは、地域住民、教師、市民団体らが、その地域で新しいタイプの学校の設立を希望し、その運営のための教員やスタッフを集め、その学校の特徴や設立数年後の到達目標を定めて設立の申請を行うもので、認可された場合、公的な資金の援助を受けて学校が設立される(運営は設立申請を行った民間のグループが担当する)。また、学校に通学せず、家庭に拠点を置いて学習を行うホームスクーリングは全州において合法とされており、宗教上の理由などから、近隣の学校の教育方針に同意できない家庭を中心に広がりをみせている。 [渡辺 靖] 宗教合衆国では「政教分離」の原則が貫かれているが、これは国教の制定のように、国家が特定の宗教団体を優遇・差別しないという意味で、宗教を政治から排除することを意味しない。むしろ、戦場であろうとどこであろうと祈りたいという国民がいるなら、政府はそれに応えることが信教の自由を守ることだと考えられている。 世界価値観調査(2005)によると、「自分の生活にとって神は非常に重要だ」という回答者の割合は、アメリカでは54.8%と、ドイツ9.5%、イギリス22.4%、フランス11.4%、日本5.4%と比べて際だって高くなっている。事実、大統領の就任式なども宗教色が強いし、合衆国のドル札や5セント硬貨などには、“IN GOD WE TRUST(私たちは神を信じる)”と刻まれている。この場合の「神」とは特定の宗教の神ではなく、より概念的な存在としての神をさす。諸宗教から最大公約数的な要素を抽出し、それを公の場に組み込むという意味で「市民宗教civil religion」ともよばれている。 特筆すべきは、1970年代末からの保守的なキリスト教勢力の巻き返しである。カウンターカルチャーの結果、伝統的規範にとらわれない文化やライフスタイルが広がったが、彼らは、そうした道徳的退廃が離婚の増加、家庭の崩壊、ドラッグの蔓延(まんえん)、犯罪の増加といった社会問題を引き起こしていると考えた。こうした保守的なキリスト教徒、とくにプロテスタントたちは「原理主義(根本主義)者fundamentalist」「右派・右翼」「福音派evangelical」ともよばれる。現在、福音派はアメリカ全人口の約3分の1を占め、リベラルなプロテスタントは保守派より少ない。福音派のなかには2000人以上の信徒を有するメガチャーチ(巨大教会)を有するものもあり、1970年にはわずか10だったその数は、1990年には250、2003年には740、2004年には840と近年急増した(2005年には1000を超えた)。 アフリカ系住民、カトリック教徒、ユダヤ教徒などのように、価値観では保守的であっても、政治的には伝統的にリベラル派が多い。1990年代には、こうした保守派と穏健・リベラル派の対立が増し、人工妊娠中絶、同性愛者の権利、宗教教育(礼拝・反進化論教育)、尊厳死、ES細胞の研究開発などの争点をめぐり「文化戦争culture war」と称されるほど論争が政治化した。大統領オバマは就任演説(2009)において、合衆国が「キリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒、ヒンドゥー教徒、そして無宗教の人々の国だ」と述べ、宗教的多様性や無神論者への配慮を鮮明にしたが、その一方で、キリスト教保守派は宗教的な要求を掲げてロビー活動、選挙活動を続けている。 [渡辺 靖] ジェンダー1960年代のウーマン・リブ運動を直接の契機として、従来の「男らしさ」「女らしさ」という価値に縛られない生き方への許容度が高まった。ただし、合衆国において女性参政権が制定されたのは1920年で、「人種で投票権を制限しない」と定めた憲法修正条項第15条の成立(1870)より50年も遅れたことなど、「人種」に比べて「女性」への偏見が根強いことを批判する声も少なくない。女性の生活水準が離婚後に急激に落ちる傾向や、子供の養育権をかちとった女性の大半が、十分な養育費を受け取れない傾向はその一例である。批判者の多くは、合衆国における仕事、学校、医療が、いまだに1950年代の核家族の規範をもとに組織されていると主張する。すなわち、各家庭にはいつでも母親がいて、日中に子供たちを医者や歯医者に車で連れて行ったり、登下校の際には小学校まで子供を送り迎えすることができ、また子供がインフルエンザにかかったときは家にいるという役割である。 その一方で、1990年代以降、ジェンダーをめぐる運動は、性の役割改革から性意識そのものの改革へと発展している。社会が新たに承認すべき性別の頭文字を組み合わせたLGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル[両性愛者]・トランスジェンダー/セクシュアル[性別違和/性の不一致])という呼称が考案され、2009年大統領に就任したオバマはこうした社会的少数派の人権擁護を標榜(ひょうぼう)した。 日本では憲法によって「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定されているが、合衆国憲法ではこうした制限はなく、現時点では、同性婚の承認そのものは各州の判断に委ねられている。権利運動そのものは1970年代から存在していたが、本格化したのは1990年代で、2003年秋にマサチューセッツ州の最高裁が同性結婚を認めたことが大きな転機となった。2010年時点で、コネチカット、アイオワ、バーモント、ニューハンプシャーの各州でも同性婚が認められている。各種の世論調査をみると、2000年代になってからアメリカ人は同性結婚に対して寛容になってきている。20代から30代前半までは半数が容認している。住民投票などでは同性婚への反対が多数を占め、宗教保守派からの反発も激しいが、州の司法判断で承認されるケースが多く、その判断をもとにさらに他州へと広がりをみせている。 [渡辺 靖] 家族一人前になった子と親が同居することはまれで、2世代世帯や3世代世帯はほとんど存在しない。子に負担をかけるよりも老人ホームに入ることを選択する親がほとんどである。実際は仕事や学業、結婚などによって遠く離れて暮らすことが多いが、「スープの冷めない範囲」の近くに住み、互いに助け合おうという気持ちは強い。親子や兄弟姉妹の写真が多くの家庭に飾られており、感謝祭やクリスマスに再会を楽しむ光景が全米各地で見受けられる。 見合い結婚の風習はなく、恋愛に基づく結婚が当然視され、夫婦関係は日本に比べるとより対等である。愛情確認の挨拶(あいさつ)もきわめて日常化している。しかし、その一方で、結婚の約半数が破綻(はたん)している現実もある(19世紀末までに合衆国の離婚率はすでに世界一であった)。女性の社会進出や物価上昇に伴い、男性が一家の稼ぎ手である家族はもはや一般的ではない。国勢調査(2000)によると、稼ぎ手としての父親と在宅の母親で構成される家庭は全世帯の1割にすぎない。また、個人の自由裁量と選択肢が拡大した結果、単身者世帯、単親世帯、内縁関係(異性愛者同士あるいは同性愛者同士など)などにみられるように、1950年代には8割近かった異性カップルの婚姻に基づく夫婦世帯(核家族)は50.7%にまで減少している。親が離婚した家族、未婚のカップルが子育てをする家族、共稼ぎ家族、同性カップル、働いている配偶者がいない家族、再婚などによる混合家族、子供が巣立った家族等など、家族の形態はますます多様化しているといえる。 [渡辺 靖] 福祉アメリカでは自助の精神に基づき「政府は原則として個人の生活に干渉すべきではない」という政治文化が根強い。そのため国民の税金を使った政府による福祉政策の対象については長年議論が続いてきた。障害者や高齢者などに対しては社会のセーフティネットとして社会福祉政策の対象となるという社会的合意があるものの、貧困者に対する公的扶助などについてはだれが恩恵を受けるべきかという線引きが政治的争点となってきた。政府のリーダーシップによる社会改革を希求するリベラル派は、所得再分配的な制度の一環として貧困者に対する社会福祉を充実させようという立場に立つことが多い。一方、福祉国家化は連邦政府の肥大化につながるとして「大きな政府」を否定する声も保守派のなかでは目だっている。長年の争点だった無保険者対策のための医療保険改革が2010年まで実現しなかったのも、両者の意見の対立があったためである。 ただ、国際的にみるとアメリカの社会福祉制度の開始は遅いわけではない。アメリカでは民間病院やコミュニティが中心となり、社会福祉を提供してきた歴史があり、ソーシャルワーカーという職業も世界に先駆けて20世紀初めに登場している。1935年に立法化された社会保障法は、社会保障に関する法律として世界で初めて制定されたものだった。同法に基づき、高齢者年金、遺族年金、障害年金などの公的年金制度を中心とする社会保障制度が整備されたほか、「要扶養児童家族扶助(AFDC)」なども制定された。さらに、1965年には高齢者と障害者向けの「メディケア」、低所得者向けの「メディケイド」という公的医療保障制度も導入された。第二次世界大戦後の福祉国家化の流れのなかで、アメリカでも福祉関連予算が飛躍的に増大した。 各制度の実際の運用については連邦制ゆえに州への権限移譲が目だっており、連邦と州、そして州以下の地方政府が協力しながら行っている。また、非政府組織も福祉政策の運用のうえで大きな役割を果たしている。連邦政府は非政府組織への助成を進め、非政府組織が政府にかわって貧困者支援などを行っている。民間医療保険の目覚ましい発達など、アメリカにおける社会福祉制度にはさまざまなユニークな特徴がある。 社会福祉の各種制度のうち、自ら掛金を払い恩恵を受ける高齢者年金制度などについては、自助の精神と合致するところもあり世論は好意的である。しかしAFDCなどについては、働くことができるのに働かず、社会福祉給付を要求するような福祉依存ともいえる状況が目だってきたこともあって、制度に対する世論がしだいに厳しくなった。1996年のビル・クリントン政権期に行われた福祉改革の結果、AFDCは「一時的貧困家庭扶助(TANF)」に改定された。これによって福祉給付期間に制限が加えられるとともに、就労可能な福祉受給者に就労義務が課せられた。ただ、低賃金職への就労が高い点など、貧困者の生活水準の向上については疑問の声も多い。公正な社会福祉をめぐる議論には当分終わりがない。 一方、社会福祉をめぐる激しい議論とは異なり、障害者の「機会の平等」を重視する点では、アメリカ国内にはコンセンサスがあるといえる。これを象徴するのが、1973年に成立したリハビリテーション法や1990年に成立したアメリカ障害者法(ADA)である。アメリカ障害者法は、障害をもつ者に対する差別を非合法とする画期的な法律である。肌の色や人種、信仰、性別などとともに、障害による差別も公民権侵害にあたるという見解から立法化された。ソーシャルワーカーという職業が、障害者の「機会の平等」を下支えするという重要な役割を担っている。 社会福祉のおもな受益者となる高齢者層は比較的投票率が高いため、高齢者をめぐる社会福祉の問題はつねに選挙戦の争点となってきた。高齢者は自らが組織をつくり、アメリカ退職者協会(AARP)という強力な利益団体を立ち上げている。この団体は、医療保険改革などで大きな役割を担った。このように、グレイパワーが目だっているのもアメリカの福祉政策をめぐる大きな特徴である。2011年時点で、アメリカの財政は赤字が急激に膨んでおり、高齢者福祉の財源にメスを入れざるをえない状況になっている。今後、高齢者福祉をめぐる激しい政治的な対立が予想されている。 [前嶋和弘] 芸術アメリカの芸術がもつ特色をもっとも端的に表現すれば、ダイム・ノベルdime novel(10セント読み物)、ジャズ、ミュージカル、ハリウッド映画、ポップ・アートなどにみられるような大衆性、ということができよう。そしてこの大衆性は、芸術をひたすら高尚なもの、孤高なもの、精神性の高いものと考えてきた日本の知識人の間で、長い間低俗なものとして軽蔑(けいべつ)されてきた。しかしそれでいながら、アメリカの大衆芸術は日本人の心を、いや全世界の人々の心をとらえ続けてきた。いわば文化における平等性とでもいうべき特色が、20世紀の人々の普遍的な魅力となったのである。 もちろん文学の分野でいえば、高度な小説や詩がいくらも書かれているし、ノーベル文学賞を受賞するような文学者が何人も輩出している。しかしそれはヨーロッパ諸国においても同じである。ダイム・ノベルやその伝統を受け継いだたくさんの大衆小説、スーパーマーケットや新聞売場に氾濫(はんらん)する大衆小説こそ、アメリカのもつムードにふさわしい。また各地にはそれぞれ誇るべきシンフォニー・オーケストラがあるが、それだけならば、これまたヨーロッパ諸国と変わりはない。ブルース、ジャズ、カントリーなど、次から次へ大衆の間から生まれたポピュラー・ミュージックこそ、アメリカの体臭ということができるだろう。ハリウッド映画がいち早く大衆のものとなり、テレビが各家庭に入り込む。映像と漫画がマス・メディアの発達にのって、大衆一人一人のものとなっていく。こうしてみると、アメリカの芸術は都市のものであり、技術によって広がったものであり、若者のエネルギーに支えられたものであり、そしてなによりも、大衆が心から歓迎したものなのである。 [猿谷 要] マスコミデモクラシーの伝統の強い国なので、報道の自由はすでに植民地時代から確立されており、知る権利の重要性については、世界中にアメリカ人ほどよく認識している国民はいないであろう。世論が国を動かすアメリカで、マスコミがもっともよく発達しているのは当然のことである。2003年にテレビは1730局、ラジオは1万1009局となり、ケーブルテレビはなんと9038局となった。一方、新聞は1995年の発行部数が、『USAトゥデイ』214万部、『ウォールストリート・ジャーナル』180万部、『ニューヨーク・タイムズ』111万部という程度の部数である。あまりにも巨大になった各種媒体が、一方的、画一的に情報を押し付けることの弊害についても、反省が生まれるようになった。それにしても、ベトナム戦争の実態をとらえた報道写真やテレビ放送、ウォーターゲート事件の真相を究明した『ワシントン・ポスト』『ニューヨーク・タイムズ』などの政治権力との闘争は、おそらく世界に冠たる業績というべきであろう。なおギャラップ、ハリスその他、世論調査機関がよく発達し、大衆は情報を伝えられるばかりではなく、情報への反応を逆に伝え返し、それがまた国家の政策に影響を与えるほどの力をもっている点は、いかにもアメリカはマスコミの国、ということができるほどである。 [猿谷 要] 文化施設歴史の浅い国であるにもかかわらず、国の豊かさを十分に発揮して、各種の文化施設が充実している。しかし博物館、美術館などは、世界的にその名を知られているようなものは、ニューヨーク、ボストン、フィラデルフィア、ワシントン、シカゴなど、おもに北東部の大都市に集中し、富の偏在を物語っている。もちろん小規模なものは全米各地にもあるが、いままで貧しかった南部、歴史のいっそう浅い西部などには、北東部にみられるほど充実したものがまだ見当たらない。それにしても、ニューヨークのメトロポリタン美術館、自然史博物館、近代美術館、グッゲンハイム美術館、ボストンの美術館、ワシントンの国立美術館、スミソニアン博物館などは、質量ともまさに世界の超一流ということができる。ゆっくり見学するにはそれぞれ数日かかるほど規模が大きい。 図書館は公立のものがよく普及している。司書は一般の事務職とは違った特別職であり、図書館業務についての理解はよく行き渡っている。老若男女を問わず利用者が多く、簡単な手続ですぐ本を借り出すことができる。細かな点は地域によって異なるが、公共の観念が強いため、返済が1日でも遅れれば罰金を支払わなければならない。大学の図書館も非常に充実していて、図書館は大学生活の中心であるという考えにたっている。 シンフォニー、オペラ、各種演劇などの劇場は主として大都市に集中している。西海岸のサンフランシスコ、ロサンゼルスなどにもいろいろな文化施設がつくられてはいるが、劇場は、やはりその中心がニューヨークで、ブロードウェーおよびその周辺はまさに劇場が軒を並べた感じである。 歴史が浅い国だけに、史跡をたいせつにしようとする努力は実に積極的である。プリマス、ジェームズタウン、セント・オーガスティンなど、植民開始当初の史跡はそのまま保存されたり、復原されたりしているし、ウィリアムズバーグのように町全体が植民地時代のままの姿で維持されている例もある。独立戦争や南北戦争の戦場跡はみなみごとに整備され、戦場国立公園となって、訪ねる人々も多い。 [猿谷 要] 日本との関係日米関係のあけぼのアメリカ合衆国と日本との関係は、ペリー来航の半世紀以上前から始まっていた。1791年(寛政3)にはアメリカ船2隻が紀州の島に寄航したし、1797年から1809年にかけては、イギリスの攻撃を恐れるオランダ東インド会社に雇われたアメリカ船が、毎年のごとく長崎に入港した。1820年代に入ると、アメリカの捕鯨船が大挙して日本近海に押しかけ、遭難して日本に漂着する船員もいた。1837年(天保8)には有名なモリソン号事件が起こる。それ以後、アメリカ海軍による日本開国への圧力はしだいに強まり、1853年(嘉永6)のペリー来航は、いわばその最終的な仕上げにほかならなかった。翌1854年、日米和親条約が結ばれて日本はアメリカに門戸を開き、1858年(安政5)には、初代駐日総領事タウンゼンド・ハリスとの間に日米修好通商条約が結ばれた。 日本側は1840年代から、オランダ書や中国書を通じて、アメリカ知識を育て始めていた。中浜万次郎や浜田彦蔵らの漂流民のアメリカ体験も、貴重な情報源になった。ペリーらの強圧的態度は激しい攘夷(じょうい)運動を巻き起こしたが、反面、西洋文明の力を思い知らせ、それを学び取らせる態度も日本人の間に生むことになった。さらにハリスは、アメリカが平和的で友好的な国であることを説得するのに成功、1860年(万延1)には最初の遣米使節が派遣され、その警護の名目で太平洋を渡った咸臨(かんりん)丸の一行ともども、アメリカ文明について見聞を広めてきた。勝海舟、横井小楠(しょうなん)、坂本龍馬(りょうま)など維新期の指導者も、アメリカの自由や共和の制度に共鳴するところが大きかった。 [亀井俊介] 蜜月時代明治初期から約4分の1世紀は日米蜜月(みつげつ)時代とよばれよう。イギリス、フランス、ロシアなどが明らかな形で東洋侵略国であったのに対して、アメリカはそういう罪科を背負わず、政治的にも、日米両国は衝突すべき利害関係をまだもっていなかった。この時期、日本は国民総がかりで「文明開化」運動を展開したが、西洋中でもっとも新しく開けた文明国のアメリカは、その最良のモデルの一つとなった。文明開化の最大の指導者福沢諭吉は、「純粋の共和政治にて、事実人民の名代人たる者相会して国政を議し、毫(ごう)も私なきは亜米利加(アメリカ)合衆国を以(もっ)て最とす。亜米利加は建国以来既に百年に近しと雖(いえ)ども、嘗(かつ)て国法の破れたることなし」(『西洋事情』1866~1870)と、ほとんど手放しでアメリカを賛美した。同様のアメリカ・イメージはほかにも多くの人が提示している。 文化面でみると、まずキリスト教が文明の根底をなすものとして広範な知識人をひきつけたが、その普及にもっとも働いたのはアメリカ人だった。横浜のブラウン塾やヘボン塾(後の明治学院)、熊本洋学校のL・L・ジェーンズ、札幌農学校(後の北海道大学)のW・S・クラークらは、多くの明治指導者を育てた。女子の高等教育は、ミッション・スクールがほとんど一手に引き受ける観さえあった。日本人のキリスト教学校もたくさんできた。内村鑑三がアメリカをキリスト教の「聖地」と思い込んだのも、ごく自然なことであった(『余は如何(いか)にして基督(キリスト)信徒となりし乎(か)』1895)。 世俗的な教育においても、アメリカの影響は大きかった。大学南校(後の東京大学)の教頭となったギドー・バーベック、文部省(現、文部科学省)顧問となったデビッド・マレーらは、日本の高等教育の中枢に参加していた。お雇い外国人教師も、アメリカ人が約3分の1を占めていた。教科書もアメリカのものが多かった。初等教育においてすら、文部省編纂(へんさん)『小学読本』巻1(1873)は『ウィルソン・リーダー』の翻訳だった。留学生も多くはアメリカへ行った。 広くいえば、この時代のもつ開化の雰囲気そのものに、アメリカの文明は働いていた。合理主義や実利思想は、当時、封建的制度からの解放感と結び付いていたが、ベンジャミン・フランクリンはその偉大な実践者だった。ロングフェローの詩(『人生讃歌(さんか)』など)さえ、能動的生き方の教訓として読まれた。アメリカは広い意味で「自由」の聖地でもあった。 [亀井俊介] 緊張の時代しかし、日本が天皇を上にいただく国家組織を確立し、帝権盛んなドイツの憲法をモデルとした帝国憲法(1889)や儒教的な教育勅語(1890)を発布するころまでに、アメリカの自由や共和の制度は日本の危険な対極となっていた。明治20年代、国粋主義の興隆とともに、文化的にも、日米は緊張時代とよぶべきものに入っていった。1891年(明治24)の内村鑑三の「不敬事件」による第一高等学校追放が象徴するように、キリスト教は排斥され、ミッション・スクールは衰退した。帝国大学を筆頭として、学問・思想の世界でも、ドイツ的な権威主義が重んじられ、ヨーロッパの高尚で精神的な「文化」に対し、アメリカは低俗で物質的な「文明」の国といった観念が広まった。文学の面でも、日本人の目はアメリカよりヨーロッパに向いた。 日米の緊張関係は、アメリカ・スペイン戦争とハワイ併合(1898)や日露戦争(1904~1905)の結果、両国がアジアではっきりした利害の衝突をみるようになり、さらに高まった。カリフォルニアの日本人移民に対する差別排斥問題は、それに拍車をかけた。1909年、アメリカの将軍ホーマー・リーHomer Lea(1876―1912)が『無知の勇気』The Valor of Ignoranceという本で、日本人のアメリカ占領の可能性を警告すると、ただちに2種類の邦訳が出た。「日米もし戦わば」的な議論が、このころから太平洋の両側でなされるようになった。それでも、日本の制度や文化の主流から締め出されたり、それに反抗する者にとって、アメリカは有力な支えとなり続けた。キリスト教徒、自由主義者、社会改革家、在野的な教育者や学者、あるいは芸術的洗練を重んじる日本文学の伝統に思想性や野性を注入しようと思う文学者などの多くは、アメリカに学ぶところが大きかった。 日米の緊張に一時的な融和が訪れたのは、「大正デモクラシー」時代である。第一次世界大戦(1914~1918)でドイツは敵国となったし、時代思潮たるデモクラシーの総本山はアメリカである。文化面でも、アメリカに倣(なら)った「新教育」が入ってきたし、プラグマティズムも盛んに伝えられた。デモクラシーの詩人ウォルト・ホイットマンが大いに喧伝(けんでん)されもした。 しかし1924年(大正13)、アメリカにおける「排日移民法」の成立は、日本人の間に広範な反米感情を生んだ。また日本の強引なアジア大陸武力進出は、アメリカの強い反対を招いた。日本の軍国主義指導者にとって、アメリカはその政治から文明までひっくるめて敵性のものとなった。そしてついに、日米は緊張時代を通り越し、1941年(昭和16)から1945年にかけて、戦争時代に突入した。アメリカとその国民は「洋鬼(ヤンキー)」と称された。 [亀井俊介] 揺れる日米関係と強まる同質化第二次世界大戦後の日本は、アメリカの占領とリーダーシップによって、第二の文明開化をしたといえよう。文明の根底は、今度はデモクラシー教だった。民主主義の旗印のもとに、思想も教育も文化も、つまるところアメリカをモデルとし、そのミニアチュアをつくろうとしてきた観がある。この第二の蜜月関係は、日本の独立回復後、またもや何度かの危機にあい、さまざまな形で反米・嫌米運動も起こって、断続的に緊張関係の色合いを強めてきた。そして日米経済摩擦の果て、文化摩擦も説かれている。 アメリカ合衆国と日本との関係は、こうして、日本側の視点からいうと、拝米と排米の間を大きな振幅をもって揺れてきた。これからも揺れ続けるように思われる。ただし、この底で、ほとんど一貫して結び付きを強めてきた面もある。日常的な生活文化や大衆文化の面である。最初の文明開化時代から、日本人の生活は著しく西洋化したが、そのかなりの部分はアメリカ化であった。小麦粉をメリケン粉と称したのは、食生活における一つの例にすぎない。ビール、缶詰などもアメリカからきた。電灯、電話、市電、自動車、あるいは百貨店などもそうである。さらには家庭だんらんを重んじる文化住宅やその生活も、アメリカをモデルとした部分が大きい。蓄音機、社交ダンスもアメリカからきた。野球を筆頭として、スポーツにもアメリカ伝来のものが多い。やがて映画がすっかり日本人の心をとらえた。ラジオ放送も、ジャズも同様である。昭和初期には、アメリカのフラッパーに倣(なら)ったモガやモボが都会を闊歩(かっぽ)するようにもなった。 アメリカ的な生活は、「俗悪」として伝統派から顰蹙(ひんしゅく)を買い、軍部からいったんは抑圧もされたが、第二次世界大戦後ほとんど自発的に再生し、ますます激しい勢いで日本人の間に広まった。占領軍のいわゆる救援物資によって飢えをしのいだ時代から、白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫を「三種の神器」としてあがめた1960~1965年ごろ、カラーテレビ、ルームクーラー、マイカーのいわゆる「3C」を追い求めた1965~1970年ごろを経て、Tシャツやジーンズがまったく日常化し、ディスコもエアロビクスもありきたりの風俗となる時代まで、アメリカの生活文化を手に入れることが日本人の努力目標であり続けた。そしていまや、恋愛や結婚の仕方から、高度な機械技術まで、アメリカの影響があまりにも浸透したため、それを影響として意識しなくなっているほどである。日米関係の大きな動揺にもかかわらず、日本人の生活はこのようにしてアメリカとの同質性を広め、両国は日常的な文化のレベルで共通した地盤にたつようになってきた。そして現在、共通した問題も抱えているといえよう。単に政治や経済の分野に限らず、社会や文化においても、同質の目標と悩みとをもっている。日本とアメリカとのさまざまな摩擦は、したがって両国文化の異質性とこの同質化との両方を踏まえて考察、検討されなければならない。部分的な局面を観念的に裁断するのでなく、両国の関係をトータルにとらえ、その相互に持続的に利益となる方向を現実的に探求していくことが、これからますます必要であろう。 [亀井俊介] 『齋藤眞・金関寿夫・亀井俊介・岡田泰男監修『アメリカを知る辞典』(1986・平凡社)』▽『トクヴィル著、岩永健吉郎訳『アメリカにおけるデモクラシー』(1990・研究社)』▽『亀井俊介監修『アメリカ』(1992・新潮社)』▽『ハワード・ジン著、猿谷要監修『民衆のアメリカ史』全3巻(1993・TBSブリタニカ)』▽『齋藤眞著『アメリカとは何か』(1995・平凡社)』▽『本間長世著『思想としてのアメリカ』(1996・中央公論社)』▽『M・B・ノートン他著、本田創造監修『アメリカの歴史』全6巻(1996・三省堂)』▽『ジョン・ボドナー著、野村達朗他訳『鎮魂と祝祭のアメリカ』(1997・青木書店)』▽『ビル・ブライソン著、木下哲夫訳『アメリカ語ものがたり』上下(1997・河出書房新社)』▽『正井泰夫著『日米都市の比較研究』(1977・古今書院)』▽『渡辺光編『アングロアメリカ』(『世界地理13』1980・朝倉書店・所収)』▽『飽戸弘著『アメリカの政治風土』(1980・日本経済新聞社)』▽『三宅一郎・山川雄巳編『アメリカのデモクラシー』(1982・有斐閣)』▽『砂田一郎著『現代アメリカ政治 第3版増補』(1989・芦書房)』▽『宇佐美滋著『揺れるアメリカ外交』(1990・バベル・プレス)』▽『阿部齊著『アメリカの政治』(1992・弘文堂)』▽『阿部齊著『アメリカ現代政治』第2版(1992・東京大学出版会)』▽『五十嵐武士・古矢旬・松本礼二編『アメリカの社会と政治』(1995・有斐閣)』▽『嘉治元郎編『アメリカの経済』(1992・弘文堂)』▽『B・エーレンライク著、中江桂子訳『「中流」という階級』(1995・晶文社)』▽『横田茂編『アメリカ経済を学ぶ人のために』(1997・世界思想社)』▽『榊原胖夫他著『アメリカ経済をみる眼』(有斐閣新書)』▽『猿谷要編『総合研究アメリカ第1巻 人口と人種』(1976・研究社)』▽『大橋健三郎編『総合研究アメリカ第6巻 思想と文化』(1976・研究社)』▽『ラッセル・ナイ著、亀井俊介訳『アメリカ大衆芸術物語』全3巻(1979・研究社)』▽『J・L・ブラウン他著、青木克憲訳『現代アメリカの飢餓』(1990・南雲堂)』▽『ダニエル・J・ブアスティン著、新川健三郎訳『アメリカ人』上下(1992・河出書房新社)』▽『明石紀雄・飯塚正子著『エスニック・アメリカ』新版(1997・有斐閣)』▽『齋藤眞・本間長世・亀井俊介編『日本とアメリカ――比較文化論』全3巻(1973・南雲堂)』▽『亀井俊介著『メリケンからアメリカへ――日米文化交渉史覚書』(1979・東京大学出版会)』▽『開国百年記念文化事業会編『日米文化交渉史』全6巻(1980・原書房)』▽『シーラ・ジョンソン著、鈴木健次訳『アメリカ人の日本観』(1986・サイマル出版会)』▽『細谷千博・本間長世編『日米関係史・新版』(1991・有斐閣)』▽『グレン・S・フクシマ著、渡辺敏訳『日米経済摩擦の政治学』(1992・朝日新聞社)』 [参照項目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [補完資料] |"> アメリカ合衆国の国旗 ©Shogakukan 作図/小学館クリエイティブ"> アメリカ合衆国位置図 ©Shogakukan"> アメリカ合衆国の州区分 ©Shogakukan"> アメリカ合衆国の地形区分 ©Shogakukan"> アメリカ合衆国の土壌分布 ©Shogakukan"> アメリカ合衆国の地誌区分 コロラド川によって刻まれた大峡谷。名称は、スペイン人のカルデナスがスペイン語で「Grand Cañon(大峡谷)」とよんだことに由来するという。世界自然遺産「グランド・キャニオン国立公園」(アメリカ・1979年登録) アメリカ アリゾナ州©Shogakukan"> グランド・キャニオン 1815~29年に再建されたアメリカ合衆国大統領の公邸。J.ホーバンの設計による、新古典様式の白亜の殿堂である。地上4階、地下2階で、132室を有する。アメリカ ワシントン©Shogakukan"> ホワイトハウス 首都ワシントンの中心にあるアメリカの議事堂(ユナイテッド・ステーツ・キャピトル)。1793年起工後、改修・増築ののち1861年にほぼ現在の姿となった。アメリカ ワシントン©Shogakukan"> 連邦議会議事堂 ニューヨーク証券取引所(写真右端)をはじめ、銀行、証券会社などが建ち並ぶ、アメリカの金融の中心地。アメリカ ニューヨーク©NetAdvance"> ウォール街 証券市場の代名詞「ウォール街」にある世界最大の証券取引所。設立は1792年。古代ローマの神殿を思わせる現在の建物は1903年に建てられた。アメリカ ニューヨーク©NetAdvance"> ニューヨーク証券取引所 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
>>: National Science Foundation
Recommend
Dissolution Judgment
…In (2), a dissolved company will immediately cea...
Mannheim, A. (English spelling) MannheimA
...A tool designed to simplify calculations such ...
Cabinet Taxi - Cabinet Taxi
...France has been developing systems such as ARA...
Voronezh - Voronezh (English spelling)
The capital of Voronezh Oblast in the western par...
Wairakite (English spelling)
Also known as Wairake zeolite. Ca-type analcime. C...
Louis-Eugène-Félix Néel
French physicist. He studied under Weiss at the U...
Internal deposits - Shanaiyokin
A company deposits a portion of employees' wa...
Baisenyaroku - Baisenyaroku
This is an unofficial history compiled by Hwang Hy...
Segonzac - André Dunoyer de Segonzac
French painter. His surname was Dunoyer de Segonz...
Superovulation - Superovulation
… The frequency of multiple births varies dependi...
Takasada Enya
Year of death: 4th year of Rekio/2nd year of Kōkok...
National Alliance Association - National Alliance Association
Before the Russo-Japanese War, Konoe Atsumaro, cha...
Giroud, F.
The term "new wave" is used in French t...
Threshold - Threshold
A horizontal bar laid on the floor when dividing ...
Auditor - Kanji
An institution within a corporation that supervis...
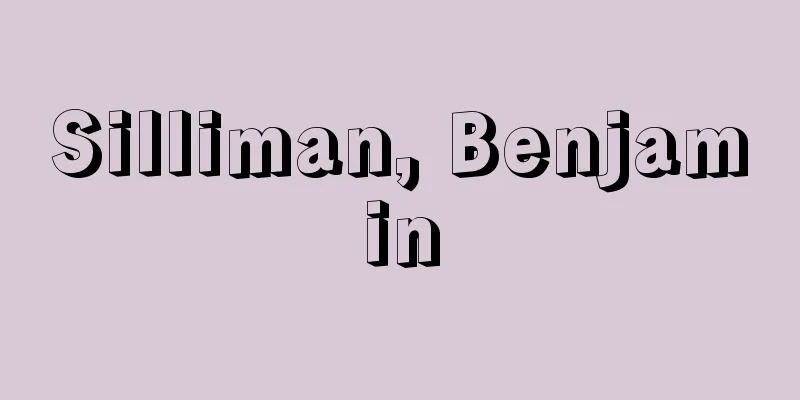

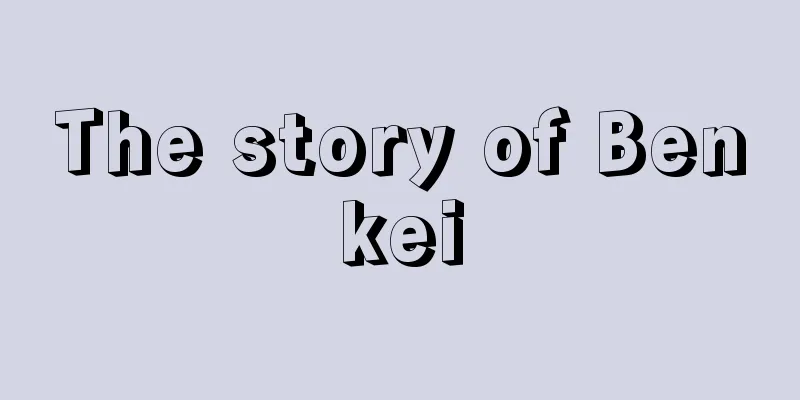
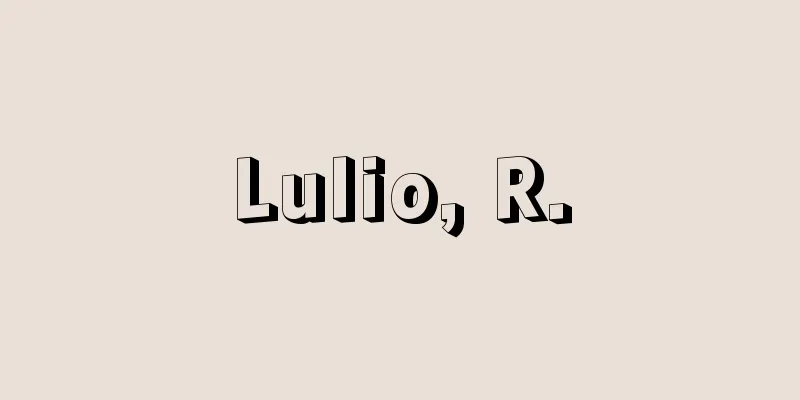
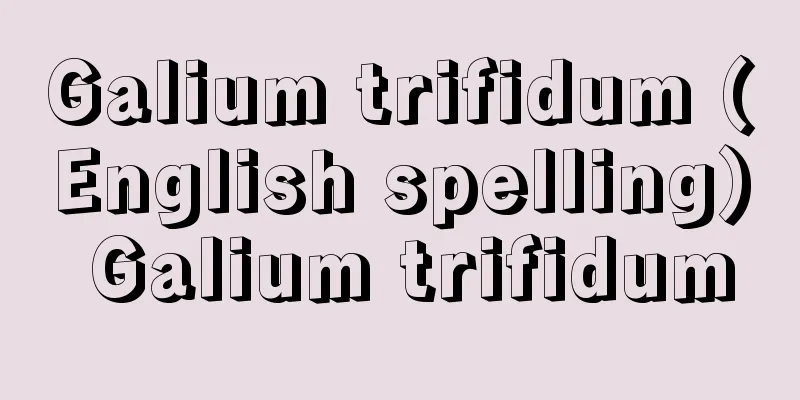
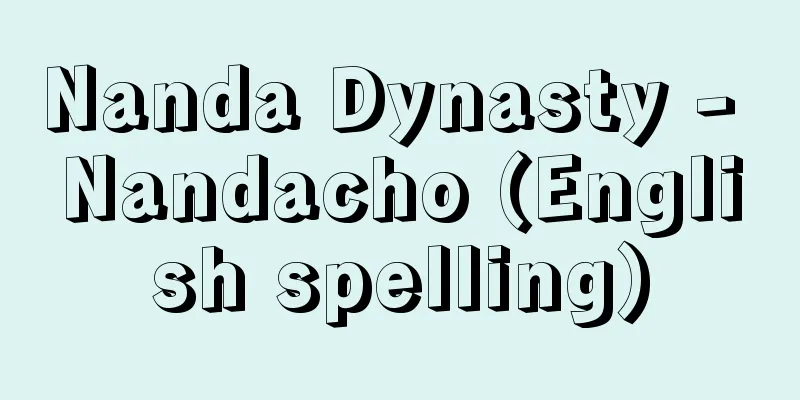
![Asai [town] - Azai](/upload/images/67cad28a93c98.webp)