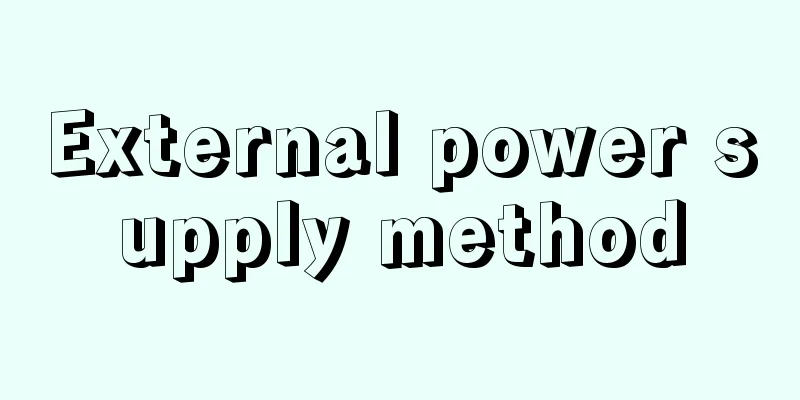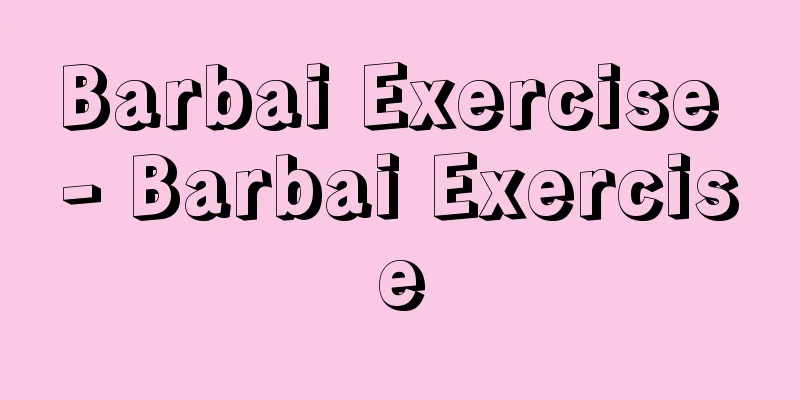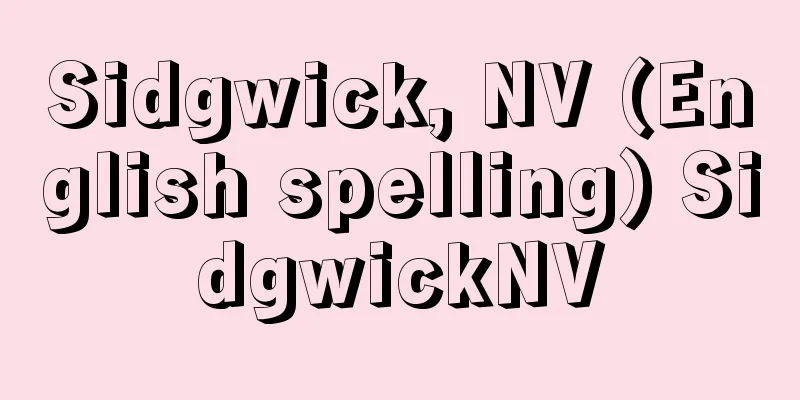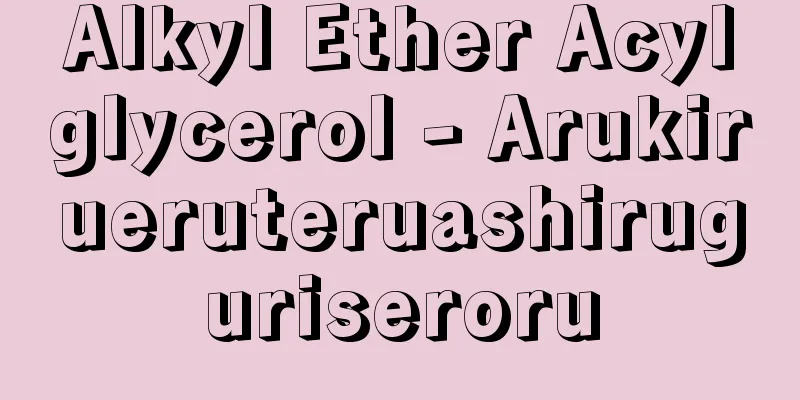United Kingdom - Igirisu (English spelling) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Overview
The national flag is the Union Jack, which is a combination of the St. George's Cross of England, the St. Andrew's Cross of Scotland, and the St. Patrick's Cross of Ireland. The national anthem is the world's oldest, "God Save the Queen (King)," and both are well known in Japan. The United Kingdom, together with the Republic of Ireland, occupies the British Isles. The British Isles are made up of about 5,000 islands, large and small, and are located off the northern coast of the Western European continent. The main island, Great Britain, is bounded to the south by the English Channel, to the east by the North Sea, to the north by the Atlantic Ocean, and to the west by the Irish Sea and St. George's Channel. Northern Ireland, which occupies a part of the northern part of the second island, the island of Ireland, is bounded to the east by the Irish Sea and North Channel, to the north by the Atlantic Ocean, and to the west and south by the Republic of Ireland. Great Britain is further divided into three regions: England, Wales, and Scotland, but the population is biased towards England. As of 2008, 84% of the total population of the UK is distributed in England, 8% in Scotland, 5% in Wales, and the remaining 3% in Northern Ireland. Although Britain is located in a corner of Western Europe, its geographical location, separated from the continental countries by the English Channel, has meant that for hundreds of years Britain has always maintained a position that is separate from the continental countries. Following the scientific revolution in the 18th century, Britain also led the world in the industrial revolution, and its enterprising people, a maritime nation, made remarkable advances overseas, building the British Empire with the world's largest industrial production capacity and colonies by the mid-19th century. In this way, Britain established a world order with Britain at its center, and as a result, Britain became more conscious of itself as a leader as a world power than as a member of Europe. However, after the First and Second World Wars, the nation's power was exhausted, and especially after the Second World War, the colonies that had supported the British economy gained independence one after another, and on the other hand, with the rise of the two great powers, the United States and the Soviet Union, Britain lost its status as a world power and had to be content with being just one country in Western Europe. Although Britain had temporarily turned its back on the EEC (European Economic Community), it was permitted to join when the expanded EC (European Community) was established in 1973, and it can be said that for the first time Britain became a part of Western Europe in both name and reality. Britain is one of the few countries that still has a monarchy after World War II, but the basis of its politics is a constitutional monarchy with Parliament, consisting of both houses of parliament, as the highest organ of state power, and the power of the Queen (King) is nominal, as is clear from the famous expression "I reign but I do not rule." Currently, the country is under the rule of Queen Elizabeth II, who succeeded to the throne in 1952. Britain has also led the world in culture, and one of the characteristics of British culture is that it strongly reflects the realistic national character of the British people. The country is still at a high level in the systems that drive real society, such as politics and economics, science and technology, and pragmatic theory. In the field of art, Britain has produced excellent works of literature and theater that depict realistic people, but its contributions in fields such as fine arts and music are somewhat low. Since the 19th century, Britain has been actively working to solve social problems, and after World War II, it has had the most comprehensive social welfare system in the world. However, on the other hand, the people's desire to work has not been high in recent years, which shows the future of a mature capitalist developed country. [Noboru Iuchi] NatureGeographyThe British Isles are located on the continental shelf less than 200 meters deep in the Atlantic Ocean, northwest of the European continent. It is clear that they were originally part of the continent, as their geology, strata, and topography all show that they are an extension of the continent, and it is believed that they were connected to the present-day Strait of Dover until about 8,000 years ago. Although the British Isles are all small islands, they have developed a variety of topography and a complex geological structure. However, broadly speaking, they can be divided into two parts by a line connecting the mouth of the River Tees on the east coast of Great Britain and the mouth of the River Exe on the Cornish Peninsula in the southwest: Highland Britain, which is made up of rocks older than the Carboniferous period in the west, and Lowland Britain, which is made up of rocks younger than the Carboniferous period in the east. In the UK Highlands, the Caledonian Great Fold Mountains, which extend from the Scandinavian Peninsula, run from the Scottish Highlands in the north to Northern Ireland and northern Wales in the west, in a northeast-southwest direction, and are composed mainly of old Palaeozoic rocks such as gneiss, crystalline schist, and granite. The Scottish Highlands have become peneplains due to erosion over a long period of time, and are now plateau-like, as the name Highlands suggests. The highest peak, Ben Nevis, is only 1,343 meters above sea level, but the terrain is rugged due to intense fault movement and glacial erosion in the younger geological period. In the southwest of the UK Highlands, the Hercynian Fold Mountains, which were created by folding during the Hercynian period at the end of the Palaeozoic era, lie. The mountain range that forms the main ridge of this mountain range extends from southwest Ireland through the Cornish Peninsula to the Brittany Peninsula in France, and the folding direction is roughly east-west. The area between these two great folded mountain systems consists of Carboniferous and later strata, and the Pennines, the backbone of the British Isles, run north to south here. Large coalfields have developed where the area borders the Hercynian Mountains. On the other hand, lowland Britain is mainly composed of Mesozoic and Cenozoic rocks, and is gently folded and tilted. Many of the rocks in the southeast have been folded by the Tertiary Alpine orogeny, which causes the strata to gradually tilt lower to the southeast. In this region, soft mudstone and clay layers are often alternated with hard limestone, sandstone, granite, etc., but because they have different resistance to erosion, when these alternate layers are exposed to the surface by tilting, the hard rocks remain and form steep slopes, while the softer strata become gentler, resulting in the development of stepped topography called cuestas. The British Isles, except for the southern part of Great Britain, were once covered by glaciers, and the effects of glacial erosion can be seen everywhere in the British topography. The coastline is also characterized by typical fjords formed by the submergence of glacial mountains along the west coast of Scotland, and submerged coastlines are widely seen along the west coast, with many inlets and bays. The east and south coasts are dotted with sandy beaches, with estuaries that open wide into the sea, and sea cliffs like those at Dover. [Noboru Iuchi] climateThe British Isles are located at almost the same latitude as the Kamchatka Peninsula (Russia) and the Labrador Peninsula (North America) on the east coast of the continent, and although the difference in latitude between north and south is 11 degrees, the Isles have cool summers and warm winters. This is a characteristic of the oceanic climate found on the west coast of the continent, and corresponds to the temperate rainy Cfb type in the Köppen climate classification. This favorable climate is largely due to the warm Gulf Stream and the westerlies that flow to the west. However, the climate of the British Isles is governed by the Icelandic low in the north, the Azores high in the south, and the rise and fall of the low pressure systems that appear in summer and the high pressure systems in winter on the European continent, which affect the climate of the UK in complex ways and bring about drastic weather changes. In particular, small migratory low pressure systems that are generated secondarily from the Icelandic low periodically pass over and around the Isles, mainly from autumn to winter, and due to the diverse topography, the weather in the UK changes rapidly. Thus, the weather in the UK is changeable and fickle. The annual temperature range is surprisingly small compared to Japan. For example, the average minimum and maximum temperatures in various regions are 8°C in the Hebrides off the west coast of Scotland and 11°C in the Cornwall Peninsula southwest of England, a difference of only 3°C. However, since the summer isotherms run east-west, while the winter isotherms run north-south, there are considerable differences between regions. For example, if the UK is divided into four parts by the 54th parallel north and the 4th parallel west, the northeast is cool in summer and cold in winter, while the southeast is hot in summer and warm in winter but somewhat cold. The northwest is cool in summer but warm in winter, and the southwest is hot in summer and warm in winter. The monthly average temperatures in Lerwick in the Shetland Islands at the northern end are 4°C in winter from December to February and 12°C in summer from June to August, but in the Isle of Wight at the southern end, the minimum in winter is 5°C and the maximum in summer is 16°C. In major cities, in London in the south, temperatures are 4°C in January and 17°C in July and August, while in Aberdeen in the north, temperatures are 2°C in January and 14°C in July. The UK is humid throughout the year, with an average annual rainfall of 1,100 mm across the country, but there are large regional differences depending on the terrain and distance to the coast. In general, the western and northern regions facing the Atlantic Ocean receive more rain than the eastern regions. The west coast of Scotland receives the most rain, with 250 rainy days per year and a total rainfall of 2,000 to 4,700 mm. Other areas that receive more than 4,000 mm include Mount Snowdon in Wales and the Lake District in northwest England. The Pennines receive 1,500 to 2,500 mm, the Welsh mountains receive 1,000 to 1,500 mm, and the Cornish Peninsula in the southwest receives 1,300 to 2,000 mm. However, it gradually decreases in the east, with only 600 to 700 mm in the eastern part of England. The rainfall in the UK does not vary much throughout the year, but in general, the rainy season is light from March to June, and heavy from October to January. It is exceptional for there to be no rain for more than three weeks, and even then it occurs only locally. Because the amount of rain is stable throughout the year, the flow of rivers in Britain is constant and gentle. This led to the development of a network of canals, mainly in the lowlands of England, which served as important transportation routes until the early 19th century. Rivers are generally short, with the Thames (338 km) and the Severn (290 km) being the two most important. [Noboru Iuchi] Fauna and vegetationLarge animals native to the British Isles, such as wolves, bears, wild pigs, cattle, and reindeer, have already become extinct. Foxes and deer are protected for hunting and can be seen in various places. Small animals include squirrels, mice, hedgehogs, various types of rats, and moles. Approximately 460 species of birds have been recorded in various places, of which 200 are resident and the rest are migratory. About 30 species of freshwater fish live in the rivers and lakes, and salmon, eels, trout, and carp are farmed for fishing purposes. Britain's climate and soil are suitable for tree growth, and in ancient times the land surface below 300 meters above sea level was covered in virgin forest, but thousands of years of human use have resulted in most of the forest being cut down, and now forests make up only 10% of the country's land area, with pastureland, farmland and wasteland making up more than 60% instead. After the glaciers retreated, birch and pine trees grew first, and now they can be found throughout the country along with oaks. Beech is suited to the chalky soil of the south, and elm and ash are planted all over the country as hedges to mark land boundaries, adding color to the British countryside. [Noboru Iuchi] Geography
The UK can be divided into four regions, England, Wales, Scotland, and Northern Ireland, based on differences in political, economic, and cultural characteristics. Currently, England, where the population, politics, economics, and cultural activities are overwhelmingly concentrated, is the region that represents the UK in both name and reality. Wales and Scotland not only have their own unique cultures, but also have strong regional characteristics in the fields of politics and economics. Compared to the three regions of the British Isles, Northern Ireland has only recently become part of the UK, and can be said to be somewhat of an anomaly within the UK. [Noboru Iuchi] EnglandEngland, which occupies the majority of the island of Great Britain, is mostly made up of plains and hills, except for the low mountains of the Pennines in the north and the Cornish Peninsula in the southwest. The southeast region centered on London, the Midlands spreading south of the Pennines, and the northeast region are home to some of the UK's largest metropolitan areas and industrial regions. Meanwhile, Anglia in the east and the coastal area of Lancashire in the west are the UK's main agricultural and livestock regions. [Noboru Iuchi] Southeast RegionThe South East region surrounding London is the most developed region in the UK. The population of the central county of Greater London (since 1987, Greater London) has been declining since the Second World War, dropping to 6.38 million in 1991, before recovering to the 7 million range and reaching approximately 7.39 million in 2003. Meanwhile, the population of the entire South East region is still growing, and the London region, which is the London commuter area, has a population of over 12 million, making it the most densely populated region in the UK. The South East region is blessed with a warm climate and beautiful scenery, and is the closest to the European continent, so many companies, various institutions, and organizations have moved here since the Second World War, and there are plenty of employment opportunities. This makes it a strong magnet for young people looking for work and retired people. [Noboru Iuchi] MidlandsThe area south of the Pennines, known as the Midlands, is the UK's largest industrial region. The Midlands are further divided into the Black Country, centered around Birmingham, Yorkshire on the east side of the Pennines, and Lancashire on the west side. The Black Country is blessed with abundant coal and iron ore, and from the late 19th century to the early 20th century, it achieved remarkable development as a heavy industrial region centered on the steel industry. Birmingham, the center of the region, is the second largest city in the UK, and is surrounded by many industrial cities, including Nottingham and Coventry. In the industrial region centered around Birmingham, black smoke spewed from countless chimneys of factories covered the sky day and night, and buildings were stained black with soot, so the area came to be called the Black Country. Many of the cities in this region are close to each other, and as industry developed, these large and small city groups connected to form huge urban clusters. In the UK, such urban clusters are called "conurbs." After the Second World War, the conurbations in the Midlands were functionally linked to the conurbations of Greater London in the south and Manchester-Liverpool in the north, forming a huge metropolitan region stretching from the Midlands to the Southeast. The textile industrial areas of Lancashire and Yorkshire were created in the foothills of the Pennines on the east and west sides during the Industrial Revolution, and many of these textile industrial cities developed along the waterfalls at the foothills. The Yorkshire region to the east was originally an agricultural and livestock region, but after Flemish craftsmen introduced wool weaving to the area at the end of the Middle Ages, the wool industry developed there. Representative cities include Leeds, Bradford, and Huddersfield. Meanwhile, the cotton industry developed in the Lancashire region to the west, centering on Oldham, Burnley, Rochdale, and Boulton. Its largest city, Manchester, became the world's center of the cotton industry in the 19th century, and further developed as a commercial city in the 20th century, becoming the political, economic and cultural center of the northern half of England today. The Mersey River, which is connected to Manchester by a canal, is the artery of shipping in the region, and Liverpool, located at its mouth, once flourished as an international trading port, but today there is no trace of that past. [Noboru Iuchi] Northeast RegionThe area along the River Tyne in the north of Yorkshire is called Tyneside, and blessed with abundant coal and iron ore, in the late 19th century, along with the Midlands, it became a major industrial region centered on the steel industry. However, this region is far from major domestic markets, and as raw materials dried up and factory facilities became decrepit between the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, it rapidly declined, and the labor force flowed out to the newly developed southeast region. Since the 1930s, the government has been promoting industry in this region, and after the Second World War, it has continued to provide assistance for a long period of time, such as introducing modern industries such as electrical, chemical, and mechanical industries, mainly in Newcastle, but the recession has become chronic and there are no signs of recovery. [Noboru Iuchi] Farming regions of EnglandAgriculture was a major industry in the UK until the Industrial Revolution, but since the second half of the 19th century, the country has become dependent on imports of agricultural products from overseas. However, as of 2003, the country's self-sufficiency rate for agricultural products remains at around 70%. East Anglia in the east of England, the Fens to the west, and the strip of land stretching from Durham to Wiltshire to the north are the UK's largest agricultural regions, with arable farming predominating in East Anglia and the Fens, and mixed farming combining livestock farming and arable farming from Durham north. Fertile land also spreads across the coastal plains from Lancashire in the west to the Welsh mountains to the south, where cattle and sheep are mainly raised and dairy farmed. [Noboru Iuchi] ScotlandBroadly speaking, Scotland is divided into Lowland Scotland in the south and Highland Scotland in the north, but it has few plains and is dominated by mountains. [Noboru Iuchi] Lowland ScotlandThe lowlands to the south are the largest plain in Scotland, and with a warm climate despite its high latitude, agriculture is centered on livestock farming and the cultivation of fruit trees and vegetables. Edinburgh, on the east bank, was the capital of the Scottish Kingdom, and remains the political and cultural center of Scotland today. It is rich in cultural heritage, including castles and buildings from the old kingdom, and its beautiful townscape is said to be one of the best in Europe. In recent years, a coastal industrial zone has developed in the northern suburbs. Glasgow, on the west bank, is the third largest industrial city in the UK, developed at the mouth of the River Clyde, and was the center of British shipbuilding before World War II. [Noboru Iuchi] Highlands ScotlandThis region (also known as the Highlands) has rugged beauty created by steep rocky mountains carved by glacial action, the countless valleys and long, narrow lakes called lochs that lie between them, and the sparse vegetation caused by the cool climate. Fishing is practiced along the coast and agriculture is practiced in some areas, but apart from sheep farming, there is no industry in the inland area. Of the limited products, whiskey and tweed are internationally renowned products created by the Highlands. Scotland is known around the world for this rugged nature, and for the unique folk customs and specialty products of this region that are rooted in that nature. [Noboru Iuchi] WalesIt occupies the western part of Great Britain and is mainly mountainous. It has a small population, mostly found along the coast. It has been integrated into England for a long time, but the Welsh language and Celtic customs remain in some areas. The mountainous areas are not suitable for agriculture, and livestock farming is the main industry, but the southern coast produces high-quality coal, and its proximity to London has led to the development of the steel industry. The central city, Cardiff, had the world's largest coal shipping port at the beginning of the 20th century. The mountains are generally low, but geologically they are old, and the famous "Cambrian Period", a period of the Paleozoic Era, was named after the Cambrian Mountains in Wales. [Noboru Iuchi] Northern IrelandThe area occupies about one-sixth of the northeast of the island of Ireland, and has been part of the current United Kingdom since 1922. The main industries are agriculture and livestock farming and manufacturing, and mainly in the central lowlands, mixed management is practiced with raising cattle, pigs, and poultry, as well as dairy farming and arable farming. The main crops for arable farming are barley, oats, and potatoes. Industry is concentrated in two cities, Belfast and Londonderry, with shipbuilding and linen manufacturing in Belfast and machinery, chemicals, textiles, and other industries thriving in Londonderry. Belfast has the largest port in Northern Ireland and is the political, economic, and cultural center. In Northern Ireland, there has been a bloody conflict between the Protestant population, which makes up two-thirds of the population, and the minority Catholic population, who want to separate from the UK. As a result, the country has a bicameral parliament, but has continued to be governed by the British government. A comprehensive peace agreement was reached in 1998 to end the conflict, and the Northern Ireland Self-Government was established in 1999. However, due to turmoil within the self-governing government, direct rule by the British government was restored in 2002. Since then, the self-governing government's functions have been suspended, but triggered by the declaration of an end to armed struggle by Catholic extremists, the British government encouraged the resumption of self-governing government, and after a parliamentary election in March 2007, self-governing government in Northern Ireland was restored in May of the same year for the first time in four years and seven months. [Noboru Iuchi] history
[Hiroshi Imai] Politics, Diplomacy, and DefenseThe nature of British politicsIn the UK, parliamentary politics developed earliest in the world under a constitutional monarchy, and a stable representative democracy has been established even in modern times. Therefore, the UK's politics are often regarded by other countries around the world as the mother country or model of parliamentary politics. The historical characteristic of British politics is that it has gradually achieved a transformation into a modern and democratic one without revolutionary changes, while preserving the ancient traditions that were considered worth preserving. This was the case in the history of British politics after the Glorious Revolution (1688), which confirmed the superiority of Parliament over the monarchy as a result of the struggle for royal power in the 17th century. Following the establishment of the "Habeas Corpus Act" (1679) and the "Bill of Rights" (1689), tolerance of political opponents gradually emerged, and in the first half of the 18th century, during the Walpole government (1721-1742), a parliamentary cabinet system was established, the opposition party gained citizenship, and the two major aristocratic party systems, the Tories and the Whigs, were established. In the 19th century, faced with socio-economic changes accompanying the Industrial Revolution and growing public demand for political participation, the government and parliament were able to respond with a series of electoral reforms and other reforms, in stark contrast to contemporary France. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. This political culture supports the continuity of bipartisan diplomacy and foreign policy, and allows for various domestic reforms, making it a condition for political stability. After World War II, the UK's national power and international status fell sharply. In particular, the negative aspects of the welfare state and mixed economic system began to surface, causing economic stagnation and a British illness of serious labor disputes. The fiscal crisis also plunged into a crisis in 1976. Successive governments continued to struggle with measures to deal with it, but British illness was overcome under the Thatcher Cabinet (1979-1990), a "politics of confrontation," which fundamentally reviewed the postwar system and pledged to transform the country. Thatcher's social and economic policies were passed down to the Conservative Major Cabinet (1990-1997), and to the Labour Party's Blair Cabinet (1997-2007), which abandoned public ownership from the party's covenants, and the "politics of agreement" began again. Furthermore, the issue of the modern political system is that under the welfare state system, the executive authority in policy decisions has increased significantly, leading to centralization, and consultations between the government and pressure groups have also been institutionalized, resulting in a phenomenon that the role of the legislative body (parliament) is relatively reduced. Therefore, decentralization and the restoration of parliamentary politics are the problems of today's British politics. [Kazuo Inudo] Political systemConstitutionになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The political powers that the King once possessed have now been transferred to parliament, represented by the Prime Minister and the House of Commons. The King is also the popular ruler of the Church of England, representing the dignified part of the structure of the state. [Kazuo Inudo] ParliamentThe legislative highest body, the House of Commons (House) and House of Lords (Senate). The parliament from election to disbanding is up to five years from the House term, with one year per session. The average number of days required for attendance in each session is 158 days in both houses. The dissolution of the parliament, enacting the general election, and the convening of the new parliament will be carried out in the form of a royal declaration with the advice of the Prime Minister. At the beginning of each session, both houses propose a draft policy that consists of the basic government policies and legislative plans in the form of King's (Queen's) Speech. [Kazuo Inudo] House of Commonsになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Fourth, the House has the function of teaching the public about political issues through parliamentary debate. [Kazuo Inudo] House of Peersになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Under this Parliamentary Act, non-monetary bills had the authority to delay the passage of two years, but were shortened to one year by the Parliamentary Act of 1949. Furthermore, due to the Life Aristocratic Act and the Aristocratic Response Act, the House of Lords gradually became the stronghold of the Conservative Party. In 1999, the Labour Party's Blair administration began reforming the House of Lords, which had been pledged to, and reduced the number of approximately 800 hereditary noble lawmakers to 92. As of March 2011, 792 seats were deemed to be held. [Kazuo Inudo] Cabinetになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The Prime Minister also serves as the leader of the ruling party, controls the parliament, and has substantial authority to ordain and dissolve the House. The bureaucracy of each ministry in the central government is called the Whitehall Machine. Approximately 500,000 national civil servants under the central government are assigned to each ministry, and is based on a hierarchical system ranging from the top administrative managers to the lower executive class. Those in the top class of 2,500 people below the vice minister's level are responsible for politically important tasks. [Kazuo Inudo] Judicial systemになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Appeals from the summary court go to the High Court Family Division, while appeals from the prefectural court and the High Court go to the Civil Division of the Court of Appeals. As mentioned above, the final court has moved from the House of Lords to the Union Kingdom Supreme Court. The final court of Scotland's criminal crimes is the Supreme Court of Scotland. [Kazuo Inudo] Local systemになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Local assembly members have a term of four years, and the right to vote is those over 18 who have registered as electors in the area, and those over 18 who meet the requirements for registering as voters in the area. The central government provides subsidies to local government projects, and local central dependence increases year by year, accounting for more than half of local government revenue. The local government's main source of revenue is the taxes called council taxes on housing, including homeowners and rentals. [Kazuo Inudo] Decentralized Parliamentになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. On the other hand, in Wales, the referendum on decentralization was a close vote, but the support of the West and Southern people who preserved the traditions of the Welsh language and culture was strong, and this decentralization was established, and the Welsh Parliament was established in Cardiff. Although the Parliament had no legislative powers, it took up the secondary importance of reviewing the contents, and it can be said that it has democratically controlled the Welsh Office, the Welsh Office of the Wales Province. Assembly elections for the Scottish Parliament (129 seats) and the Welsh Parliament (60 seats) took place in May 1999, and the executive branch was established in June. [Kazuo Inudo] Political partiesPolitical parties play an important role in parliament, government and local governments. Without political parties, political systems would not have developed. Most of today's major political parties are known as organized parties or national parties. Already in the second half of the 19th century, the Conservative and Liberal parties had become parties that adopted the working class as a base. In the 20th century, the Labour Party, which replaced the Liberals, grew into a party based on the middle class as well. All of the main parties' pledges to seek support from the national classes. The two major conservative and labor systems were highly stable for a quarter century after World War II. The combined vote shares of both parties reached 96.8% in 1951. However, in 1974 it fell to around 75%, and in 1979 it somehow returned to the 80% range in 1983, but fell to 70% in 1983. The economic conditions that had been worse since the 1960s led to the departure of the two major parties, showing signs of revitalization in the Liberal Party, and the rise of the nationalist Scottish Nationalist Party and Pride Camry.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. However, Labour significantly reduced seats in this election, leading to the Conservatives and Liberal Democrats. In the 2010 general election, the Conservatives became the leading party. However, the seats did not reach the majority, and they launched a coalition government with the Liberal Democrats. [Kazuo Inudo] electionになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The statutory election fees are £5,110 for urban districts with 60,000 voters under the 1985 Election Act. The Anti-Corruption Impact Act, enacted in 1883, before 1885, when the single-member district system was introduced, gradually cleansed up and took place within the legal fees. [Kazuo Inudo] Pressure Groupになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. From the 1960s to the 1970s, the TUC and CBI were incorporated into the government's policy-making organization, and were represented by many important government agencies, including the NEDC (National Economic Development Council). The decision-making method was also known as Tripartism or Corporatism, but it was not passed down to the Conservative government in 2018, which began with the Thatcher administration. TUC significantly reduced the political influence that was known as Union Power, but the influence on the Citi administration, which is considered an informal pressure group representing the CBI, banks, securities, insurance, and other industries, increased. This relationship between the government and pressure groups was also maintained under the Labour Party's Blair administration. [Kazuo Inudo] DiplomacyImperial conservation and balance of powerになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The collapse of the Liberal Party Cabinet over the Irish Autonomy Bill in 1886, and the proposal passed through the House of Commons in 1892 but was rejected by the House of Lords, indicating that the policy of imperial conservation had become deeply ingrained. However, since World War I, its policy gradually changed shape. After this war, Britain was no longer a military and economic power of the world. After the civil war, Ireland became independent and the Indian independence movement progressed. There was also a tendency to divorce the country of its own territory. As such, the British Empire transformed into the British Federation, and the Commonwealth countries became equal in the Westminster Charter in 1931. After World War II, it was simply called the Federation, but it was formed as an economic zone with preferential tariff system in the Great Recession of the 1930s, and until it entered the European Community (EC) after the war, it was the main economic zone of Britain until it entered the European continent. The balance of power policy for the European continent was taken in various ways since the 199th century when the national power began decline, but it fell due to the decline in British national power due to the emergence of the powerful Germany and the arrival of the American era. [Kazuo Inudo] The current state of diplomacyになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. This is because the national argument was divided between the federal and the e-commerce. In 1961, the MacMillan Cabinet began negotiations for membership, and the UK joined the e-commerce when the Heath Cabinet was in January 1973. However, in 1975, the Wilson Labour Party Cabinet voted in a referendum on whether or not they would continue to join the e-commerce, and it was approved for membership. The UK was a powerful member of the e-commerce, along with West Germany, France and Italy. In the 1980s, the opposition Labour Party strengthened its involvement in joining the e-commerce. Until then, the Conservative government had been more deeply involved with the e-commerce than the Labour Party, but as the EC entered further political and economic integration, including the monetary unification, it was plagued by conflicts between European skeptics and Europeans who opposed it. Meanwhile, the UK signed the Maastricht Treaty, which further strengthened integration (the progress from the EC to the EU), at the end of 1991 on the condition that the single currency and the social charter were excluded, and the treaty was ratified by Parliament in July 1993. The Labour Party, which returned to power for the first time in 18 years in the May 1997 general election, has a foreign policy that is more pro-EU than the Conservative Party, with the acceptance of the Social Chapter of the Social Charter.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The Blair Labour administration actively supported the US war on terrorism after the September 2001 terrorist attacks. In 2003, the US also participated in the US invasion of Iraq, citing the development of weapons of mass destruction, and even after the war ended, it stationed troops in Iraq. However, in July 2005, a simultaneous terrorist attack occurred in London, causing many casualties. The government agencies responsible for external relations are the Minister of Foreign Affairs and Federal Affairs, who leads the Ministry of Foreign Affairs and Federal Affairs. Aside from national defense relations, it is the Ministry of Foreign Affairs and Federal Affairs who prepares foreign policies, and the Ministry consults with the relevant ministries to prepare policies for issues related to other ministries. [Kazuo Inudo] defenseThe military's highest commander is nominally the king, but in reality the Prime Minister and Cabinet are responsible for national defense. The Prime Minister is the chairman of the National Defense and Foreign Policy Committee, consisting of ministers such as the Minister of Defense, Foreign Minister, Finance Minister, and Minister of Home Affairs, and this agency decides national defense policy. Below that, the National Defense Council is chaired by the Minister of State and the Minister of State for the Army, Navy and Air Force. The National Defense Council also includes the Chief of National Defense Staff, Chief of Staff by the Army, Navy and Air Force, Vice Minister of Defense, and Planning and Research Council. The three Defense Council are governed by the Army, Navy and Air Force members of the National Defense Council. After World War II, Britain became a country with nuclear forces second only to the US and Soviet Union, but it was separated by the two superpowers due to its military power, and gradually reduced its military commitment due to its financial difficulties. In 1968, the Labour Party decided to withdraw its troops from Malaysia, Singapore, and the Persian Gulf to concentrate its defense efforts on Europe. In the late 1970s, the military was also salvaged from the Mediterranean. The British national defense policy was centered around NATO, and the country contributed to NATO's strategy in the 1990s, with three Polaris nuclear submarines equipped with missiles, and the German Army and Air Force. At the end of the 1990s, Trident nuclear submarines with missiles with nuclear deterrent powers that were more effective than Polaris nuclear submarines. Looking at defense spending, defense spending was gradually reduced from about 5.5% to 4.5% of GNP from 1974 to 1975 during the Labour Party's government. Strengthening defense capabilities were attempted under the Conservative Party government, exceeding 5.2% in 1982, but fell to 3.1% in 1993, and fell to 2.4% in 2003. The size of the NATO countries is second only to the United States. Looking at the military forces, in 2004, the army was 116,800, navy 40,600, and air forces totaling 48,500, which totaled 205,900, which has decreased by nearly 200,000 since 1970, and in 2008 its total forces of approximately 180,000. [Kazuo Inudo] Economy and IndustryCharacteristics and transformation of economic structure: an overview of the pre-World War IITrade-dependent structureThe UK was the world's first industrial nation in the 18th century, and had an overwhelming productivity advantage in the world economy. The background to this was the industrial revolution that Lancashire Cotton Industry began with the introduction of Jenny spinning machines. British cotton industry relied on imports of raw cotton from the US southern and India, with 20-30% of total imports. On the other hand, exports of cotton threads and cotton products accounted for 40-50% of the total export value, and export destinations were all over the world. British cotton industry was the foundation of the UK's status as a "world factory." In addition, the steel industry became an export product in the form of railway materials exports to Europe and the US in the 1840s. In any case, during the period of capitalism, a trade-dependent industrial structure was already established in the UK. By the way, this structure already created a constant deficit in the trade balance due to its dependence on the foreign sources, but on the other hand, freight revenues caused by the development of the shipping industry, services revenues from trade credit, and interest income from capital exports, resulting in a significant surplus in the non-trade balance, covering the deficit in the trade balance. [Uchida Katsutoshi] Decreasing status in the global economyところで、19世紀末にドイツおよびアメリカ資本主義の集中・独占の傾向が進むなかで、イギリスでは独占の形成が著しく立ち後れた。世界に先駆けて産業革命を達成したイギリスは、先進工業国であっただけに、近代化を差し迫った課題としなかったという歴史的条件があったのである。とはいえ、イギリスにおいても大不況期(1873~1896)を通じて中心的産業に独占が現れてくる。すなわち、平炉法の普及に基づく鋼の大量生産と、それを中心とする造船業、兵器産業、重機工業部門が縦断的に結合するのである。また、支配の集中を目ざす株式会社形態の展開普及がみられるし、金融資本化が進んでいたのである。しかしながら、構造的な脆弱(ぜいじゃく)性は否みがたく、鉄鋼生産量ではすでに1890年代にアメリカ、ドイツに追い抜かれ、輸出市場においてもドイツに追い抜かれた。その結果イギリスは、食料、原料の大量輸入に加えて、ドイツ、アメリカから工業製品を輸入することとなったために、貿易赤字がさらに増加した。しかし、貿易決済中心地としてのロンドン金融市場は豊富な資金を集中しつつ繁栄するのである。それを支えたのは国際金本位制の展開であった。 さて、「世界の工場」としてのイギリスの地位の低下はその後も進む。まず、第一次世界大戦後の景気後退期において、綿業、石炭業、鉄鋼業、造船業などが生産、輸出ともに戦前水準を大きく下回り、停滞の様相を示した。さらに、1925年にデフレーション効果をもつ旧平価による金本位制復帰が行われた。このことはイギリス産業に負担をかけたものの、世界経済は国際金本位制が再建されたことにより相対的安定期に入り、1929年までは緩やかな拡大を続けた。この時期のイギリス産業を雇用数でみると、1929年までに旧産業の綿業、鉄鋼業、造船業の3部門の比重は低下したが、新産業の車両、化学工業、電機工業、レーヨン・絹工業の4部門は増大した。一方、世界輸出に占めるイギリスの比重は低下を続けた。とくに旧産業の輸出不振によって、経常国際収支の黒字は減少した。 [内田勝敏] 世界恐慌の影響1929年の世界恐慌は停滞に悩むイギリス経済に追い討ちをかけることとなった。世界恐慌は大量失業を引き起こした。また輸出の急激な減少を引き起こし、1929~1931年に38%減少した。他方、輸入はわずかしか減少しなかったから、貿易収支赤字が急増した。ロンドン金融市場は大量の対外短期信用を続け、国際収支の赤字の増大と財政赤字から、短期資金・金の大流出が生じ、ついに1931年9月に金本位制を放棄したのである。同時に、保護関税を導入、1932年にはオタワ経済会議によってイギリス帝国特恵関税制がとられた。その結果、輸出は地域別構成でイギリス帝国諸国の比重を高めつつ回復し、世界のブロック貿易の先駆けとなってゆく。一方、為替(かわせ)平衡勘定を設置することによって、短期資金の流出入に対するポンドの売りと買いでポンド相場を安定させつつ、ポンド通貨圏を形成していった。これはポンドの国際的信頼維持のためのものではあったが、これをきっかけにイギリスは世界的存在から、イギリス連邦という小宇宙に後退せざるをえなくなったのである。 この時期の産業の回復はどうだったか。綿工業は1936年の綿紡績法によって過剰紡績が買収されて合理化が進んだ。鉄鋼業は関税率の引上げによって保護されつつ再編成が進められ、造船業も再編・合理化が進められた。しかし石炭業はカルテルによる保護に終わった。他方、新産業の分野では、自動車、化学工業、電機工業への投資の増加がみられた。ともあれ、世界恐慌に対応してイギリス経済は福祉国家の方向を模索しつつ、イギリス連邦という限定された世界のなかで、保護関税に基づいて産業の再編成を図ったのである。 [内田勝敏] 第二次世界大戦後の経済――インフレと長期停滞第二次世界大戦はイギリス経済に巨大な消耗を強いた。海外資産の処分は48億ポンドに上り、対外債務の増加は28億ポンドを超えた。生産は低下し、輸出は戦前の約半分になって国際収支危機に陥ったのである。1945~1950年は労働党の政権下で、イングランド銀行、石炭業、鉄鋼業、通信、電力、運輸、ガスの国有化が行われ、社会保障の充実が図られた。一方、ポンドの国際的な地位が凋落(ちょうらく)し、1949年に30.5%切り下げられた。1951~1964年は保守党の政権下で、鉄鋼業の国有化が解除された。他方で国際収支が悪化し、インフレに悩まされた。この時期には、国際収支が悪化すると引締め政策をとり、国際収支がよくなると緩和する、というストップ・アンド・ゴー政策が繰り返されたために、投資が停滞し、成長が遅れた。1964~1970年はふたたび労働党政府となり、インフレ対策として賃金・物価の凍結を行ったが、国際収支の赤字は続き、1967年にポンドを14.3%切り下げた。1970~1974年は保守党政府のもとで、高度成長政策をとり、同時に法律に基づく所得政策をとったが、労使対立が激しくなった。1974年に労働党政府となり、「社会契約」によって労働組合との協調を目ざしつつ、主要産業の国有化を図って新たな経済の発展を図ったが、激しいインフレにみまわれた。1979年にサッチャー保守党政府ができて、これまでの経済政策を180度転回し、インフレ対策をもとに、長期的停滞からの脱却を図ろうとした。すなわち、公共支出を削減し、マネーサプライ(通貨供給量)を抑制し、民間経済活動に政府の介入を排除して、イギリス経済の活力をある程度回復した。 1997年5月に、労働党が18年ぶりに政権に復帰した。ブレア党首が首相となり、市場経済の原則を維持しつつも、保守党の行きすぎた競争至上主義を修正し、イギリス産業の競争力を強める方向を打ち出した。2007年ブレアの首相退任に伴い、前財務相のゴードン・ブラウンが労働党の後継党首に選出され、首相に就任した。ブラウンは新財務相に前貿易産業相のアリスター・ダーリングを任命した。 [内田勝敏] 経済の現況
[内田勝敏] Finance金融、財政面では、第二次世界大戦後、完全雇用と福祉国家を目ざして、国家による有効需要の創出に基づいて基幹産業を再編してきた。その結果、国家財政と国有産業を含む公共部門の国民経済に占める比重が一段と高まった。1950年には国防費の急減もあって全政府支出の対GNP(国民総生産)比率は39%となっており、1930年代なかばの25%と比べるとかなり高まっていた。1958~1967年には積極的な成長政策をとり、公共部門の比重が大いに高まり、1968年には約50%に達した。1967~1970年の引締め策のあと、1971年以降ふたたび成長政策に転換し、公共部門の比重は一段と高まった。1975年には54.5%に達してピークとなり、財政赤字は深刻化した。福祉国家の維持と産業の再生とは両立しがたいのである。財政主導による有効需要の拡大に基づいて産業稼動率を上昇させて近代化を図ろうという政策は、ここにおいて転換せざるをえなくなった。それがスタグフレーションを生む元凶とみられたからである。1979年のサッチャー政権のもとで、財政面では公共支出の削減、通貨面ではマネタリズム(通貨供給重視政策)に転換した。それは公共支出の削減、マネーサプライの抑制、人為的介入の排除を基盤とし、具体的には、流通通貨と居住者銀行預金の増加率の目標を設定し、公共部門の借入需要(事実上の財政赤字)をコントロールすることとなった。公共部門の圧縮は住宅部門、教育部門、公務員の削減などが行われたが、他方で、不況に直面し失業率が増大した。財政面で企業のコスト負担の軽減や設備投資の促進などを求めて、1997年5月に労働党政府ができたが、財政赤字の削減の政策は続けられている。 [内田勝敏] 産業構造経済発展のある段階で製造工業の比率が低下しはじめ、第三次産業の比率が増大する傾向がある。これは、サービス経済化あるいは脱工業化の進行ととらえられることは周知のところだが、イギリスではこの現象がとくに顕著にみられる。就業人口の業種別構成をILO(国際労働機関)の『労働統計年鑑』によってみれば、製造業(鉱業、電気ガス、水道業、建設業などを含む)の比率は、1980年に26.6%であったが、1993年25.9%、2003年23.3%となった。一方、第三次産業(卸・小売業、運輸・通信業、金融・保険・不動産業、サービス業)は、1980年に54.7%であったが、1993年には70.8%、2003年には75.3%となっている。 イギリスの産業を立地からみれば、旧産業としてはランカシャーの繊維工業、ヨークシャーの毛織物工業、北部イングランドおよびウェールズの石炭業と鉄鋼業、グラスゴーの造船業があり、新興産業として南東イングランドの自動車工業、航空機工業、バーミンガムの重化学工業がある。 ところで、第二次世界大戦後のイギリス産業は、重化学工業を基軸として国家の手厚い保護を受けて再編成を展開してきた。石炭業、鉄鋼業は1945~1950年に国有化された。石炭業は、再建と機械化のためには大規模な投資が必要であり、そのための資金調達を国家によって行ったのである。鉄鋼業は他産業より独占が進んでおり、国有化は国有民営の形態で行われた。1951年に保守党政府のもとで鉄鋼業の国有化は解除された。1950年代後半から1960年代には成長政策がとられ、とくに1966年の産業再編成公社の設立によって、多くの産業が合併・集中を行った。鉄鋼業は1967年に、鉄鋼法に基づいて13社が鉄鋼公社に株式を譲渡してふたたび国有化された。自動車工業はこの段階で大手4社に集中し、造船業はゲッデイス委員会の勧告に基づいて数社に統合された。綿業は慢性的な不況産業となっていたが、1960年代にはドラスティックな設備処理と企業合同による近代化によって、四大グループへの集中が進んだ。また電機業界は、1968年のゼネラル・エレクトリックとイングリッシュ・エレクトリックの合併によって、西ヨーロッパ最大の電気機器企業ができた。重電機を中心としてコンピュータ、通信機、宇宙開発機器、原子力発電にまで及んでいる。 さらに1968年および1972年の産業拡大法は、いっそう大型の合同を促進し、収益性の高い製造業への公有を拡大した。自動車産業におけるレイランド・モーター社とブリティッシュ・モーター社の合同によるブリティッシュ・レイランド・モーター社の成立とその国有化は代表的な例である。1975年の産業法では、国有企業庁と主要産業との計画化協定によって、産業の近代化を図った。1977年には航空機宇宙産業および造船業で国有企業ができ、北海石油販売の国有企業もできた。ところが、イギリス産業の国際競争力は依然として再生しなかった。サッチャー政権は「小さな政府」の実現を目ざして、国有産業を徐々に民営に移してゆく政策へ転換した。まず、民営化の立法を次々と制定した。それに基づいて、航空機・宇宙開発業はブリティッシュ・エアロスペース、石油業はブリティッシュ・ペトロリアム、通信事業はケーブル・アンド・ワイヤレス、ブリティッシュ・テレコム、ガス事業はブリティッシュ・ガス、航空事業はブリティッシュ・エアウェイズ、自動車工業はローバー・グループへとそれぞれ民営化された。1988年には鉄鋼業のブリティッシュ・スティール・コーポレーションへの民営化が実現したのである。 [内田勝敏] Agriculture農業は、小麦、大麦、カラスムギ、ライムギ、ジャガイモ、サトウダイコンなどの農産物を生産している。2002年には穀類の自給率は109.0%、そのうちの小麦は120.5%となっており、その他の商品も自給率は上昇している。2003年も穀物自給率は99%とほぼ100%を維持している。また、総輸入額に占める食料輸入の比率が著しく減少している。これは、1960年代以後のイギリス農業政策が、経営規模拡大、離農促進、農場合併、共同化促進に基づく構造政策によって、農業保護を行っていることによる。 [内田勝敏] traffic鉄道は、1948年に国有化されたが、独立採算制のもとで合理化に努めてきた。イギリス国鉄の労働生産性は1960年代には年率5%で向上したが、1970年代に入ると10年間でわずかに5%しか伸びなかった。当時の列車の運行は、ブリティッシュ・レール(親会社)の管轄のもとで子会社3社(インター・シティ、ネットワーク・サウスイースト、リージョナル・レールウェイズ)によって行われていた。1992年4月の改革で、列車、設備管轄権の子会社への全面的移管によって合理化を進めた。さらに、1993年11月の民営化法案によって、施設、車両は国営保有の企業(レールトラック社)がリースし、民間事業が営業権をもって運行を行うこととなり、1994年にイギリス国鉄の民営化が実施された。ついで、1996年にはレールトラック社も民営化された。しかし民営化後、鉄道の重大事故が続発し、レールトラック社も倒産したため、2001年に戦略鉄道庁が設置されている。 航空輸送面では、超音速旅客機コンコルド(2003年10月運航終了)を含むスピード化と空港の拡張、整備が行われるなか、ヨーロッパ最強の航空会社といわれるブリティッシュ・エアウェイズ(英国航空)は、1981年に民営化され、合理化が進んでいる。 1994年5月6日に着工から約6年半の歳月をかけた英仏海峡(イギリス海峡)トンネルが開業した。事業費は100億ポンド(約1兆5800億円)であった。このトンネル建設はユーロトンネル社のプロジェクトで、同社の役員構成は、フランス人8名、イギリス人7名、ベルギー人、アメリカ人各1名で発足した。これによって、イギリスとヨーロッパ大陸は陸続きとなり、ヨーロッパ統合にとっても大きい意味をもつものとなったのである。 [内田勝敏] Energyエネルギー消費量は、1990年には、31.9%が石炭、35.7%が北海石油、24.5%が天然ガス、7.1%が原子力発電でまかなわれている。北海油田の開発により石油を輸入に頼らなくてよくなったことは国際収支に大きく寄与しているといえる。しかし、近年は油田の枯渇、環境問題などで政策転換を迫られており、エネルギー・気候変動省を創設し対応を図っている。2050年までにCO 2を80%削減するとの目標を決めている。石油精製と石油化学には多国籍企業として著名なブリティッシュ・ペトロリアムがある。 [内田勝敏] Trade世界貿易に占めるイギリスの比重は著しく低下してきている。世界輸出額に占める比率は1948年の11.5%から1975年には5.6%、1979年には6.0%、1995年には4.8%、2004年には4.0%となった。GNPに対する輸出額の比率は、1977年で29.2%、1995年では22.9%、2004年ではGDPの比率で16.9%である。貿易収支は入超傾向を続けており、貿易外収支の黒字でこれを補っている。2008年の輸出における品目別構成は、電気機器・同部品4.2%、道路走行車両9.1%、石油・石油製品12.1%、医薬品7.0%、原動機6.0%が上位を占めている。そのほか、鉄鋼製品、非鉄金属、金属製品の輸出が増加している。輸入では、電気機器・同部品4.3%、道路走行車両10.1%、石油・石油製品9.8%、通信機器等4.7%、衣料品3.9%となっている。最近は北海油田の産出量減少に伴い、石油の輸入が急増している。機械・輸送具については輸出入ともに活発になっており、水平分業が進んだものとみられる。 さて、貿易相手国では、イギリスはもともとイギリス連邦諸国をおもな相手国としていた。1955年では輸出の38.0%を占めていたが、しだいにその比重が減少してきて、1979年にはわずかに12.0%になった。他方で、EU(ヨーロッパ連合)がおもな貿易相手国となってきた。輸出では1955年に20.0%だったのが1980年には42.0%、1995年には58.5%、2004年には57.8%となった(2008年には56.4%)。輸入では1955年には18.0%、1980年に40.0%、1995年には58.5%、2004年には55.2%となっている(2008年は52.2%)。 [内田勝敏] EU加盟イギリスは1963年にEC(ヨーロッパ共同体)に加盟申請してから10年にわたる長い論争のすえに、1973年1月ECに加盟した。これは、停滞したイギリス産業を活性化するためにECに加盟し、競争を挑み、市場拡大を図ろうとしたものである。他方で伝統的なイギリス連邦との結び付きを断ち切り、貿易市場の方向転換を求めたものである。これまでのところでイギリスのEC加盟のバランスシートをみると、1979年までイギリスの対EC貿易収支の赤字が続き、赤字額もきわめて大きい。とくに赤字が大幅に増大した商品として食料があげられる。食料輸入が非ECからECへ転換されたことによる。1993年11月に、EU条約(マーストリヒト条約)が発効してECはEUとなり、1999年までに通貨統合を実現した。政府のEU社会憲章やEU通貨統合への対処を通じて、イギリスの方向が決められてゆく。2002年1月にEUの統一通貨ユーロが流通し始めたが、2011年4月時点でイギリスはユーロ導入に踏み切っていない。 [内田勝敏] 日英貿易日英貿易は1963年(昭和38)に日英通商航海条約が発効してから正常な貿易関係の土台のうえに発展することとなったが、イギリス側の輸入超過が続いている。とくに、1970年代に入ってからの不均衡が大きくて、貿易摩擦を引き起こしている。日英貿易における貿易商品の変化をみると、日本の対英輸出は1960年に機械類が9.5%だったのが1980年には69.7%に増大し、1960年に食料品が51.9%だったのが1980年には0.7%に著しく減じている。とくに車両の輸出が激増したために、1975年に自主規制が行われ、乗用車はイギリス市場の11%に抑えられることになった。さらに1982年からは小型商業車もシェアを11%に抑えることとなった。2008年(平成20)のおもな対英輸出品目は自動車14.0%、船舶6.6%、原動機6.0%、対英輸入品目は医薬品20.1%、有機化合物11.1%、原動機5.6%である。 [内田勝敏] 衰退するポンドイギリスの金融の中心はシティとよばれ、イングランド銀行を中心としたわずか1平方マイル(2.59平方キロメートル)の1区画にしかすぎないが、ここには、銀行、証券会社、株式取引所、各種の商品市場、海運・保険市場が密集している。19世紀後半、世界の金本位制度のもとで、ロンドンが国際金融市場の中心となり、イギリス通貨ポンドが国際通貨として比類のない力をもち、貿易決済に広く使用された。当時のポンドは取引通貨や準備通貨の諸機能をすべて果たしており、ロンドンは為替(かわせ)取引(ポンドの売買)の決済場所の役割をなすわけで、各国の銀行が為替取引の決済資金をポンド残高としてロンドンに集中して保有した。ロンドンは国際貸借の世界的中心として「世界の銀行」となったのである。しかし、第一次世界大戦後、国際収支は不均衡に陥り、1929年世界恐慌に際してポンドの弱体化が一気に現れた。1931年に金本位制の放棄を余儀なくされてポンドが変動相場制をとったとき、イギリス連邦を中心とする諸国がこれに追随して自国通貨をポンドに結び付け、通貨ブロックが自然発生的に形成された。後のスターリング(イギリス・ポンド)地域の原型がこれである。第二次世界大戦後、固定相場制に戻ったが、イギリスは厳しい為替管理制度によってスターリング地域を強化した。1949年9月ポンド切下げを行いつつも、通貨ブロックによってポンドの国際通貨としての地位回復を求めた。1958年12月にポンドの自由交換性が回復されたあと、1960年代にポンドは投機の波にさらされ、ポンドは危機に陥った。1967年11月に再度ポンドは切り下げられた。ポンド危機との関連で重要なものにポンド残高がある。ポンド残高とは、海外にあるイギリスのポンド債務であり、第二次世界大戦前には約6億ポンドであったが、戦時中の戦費調達のために増加し、戦後も増加して1970年には47億ポンドにも上った。このために、ポンド危機が起こると、ポンドが売られて危機をいっそう強めた。ポンド支援のためのバーゼル協定(1961)が結ばれたが、その後この協定は更新のたびにポンド残高を整理し、削減するための協定に変わっていった。すなわちポンド残高価値保証協定が1968年に結ばれた。しかし、1974年末にこの協定が廃止され、名実ともにスターリング地域は消滅したのである。すでに1973年1月イギリスはECに加盟していたのであるが、同年6月、スターリング地域に与えていた為替管理法上の居住者としての特権をなくする決定をしていたのである。さらに、1979年10月に為替管理法を全廃した。ポンドの衰退は事実であるが、ロンドンはポンドのかわりにドルを使用し、ユーロ・ダラー市場の中心となって国際金融の中心としての地位を守っている。 [内田勝敏] 資本輸出資本輸出もまた第二次世界大戦後著しい変貌(へんぼう)を遂げた。もともと19世紀後半から第一次世界大戦までは最高の爛熟(らんじゅく)した状態に達したが、第一次世界大戦前に資本輸出が貿易促進的な役割を失った。1930年代の恐慌克服過程において資本輸出の余力をもしだいに失ってきて、地理的分布をもっぱらイギリス帝国に集中してきた。その内容も原料、資源開発に集中し、また国公債投資に偏ったのであった。 第二次世界大戦後いったんはスターリング地域向け投資が主となったが、その後スターリング地域の解体、EU加盟などの諸条件に基づいて、資本輸出のあり方が大きく変わった。第一に、第二次世界大戦によって海外投資残高のほぼ4分の1余りを失ったが、1960年代後半から海外投資が急速に増加し、その約7割が直接投資によって占められるに至った。これは多国籍企業の発展への対応とみられる。資本輸出の源泉は、巨大企業の成長した金融余力やユーロ・ダラー市場での資金調達や利潤再投資によるものである。第二に、イギリスの資本輸出(直接投資)地域は、スターリング地域の比重が減少して、アメリカ、EU向けが急速に増加した。他方で資本輸入地域はアメリカ、スイス、カナダ、オランダの順となっている。このような先進諸国間の海外投資の相互交流の増大は、1960年代以降の世界の資本輸出の特徴であり、これが多国籍企業の形態をとって世界的に活動領域を広げているのである。第三に、イギリス資本輸出の産業別構造をみてみよう。もともと鉄道、鉱業、農業投資が中心であった。1914年では鉄道投資が77.4%を占めていたほどである。ところが1960年代以降は製造工業投資が増大し、技術集約度の高い部門に移っている。 [内田勝敏] societyイギリス社会構造の特質異なる民族・人種や、生活様式および価値観で相異なる階級が存在するが、社会の分裂をきたすことなく共存し、調和した社会を形づくっているところにイギリス社会構造の特質がある。社会的相違性は、民族・人種および階級のみならず、イングランドの北部と南部に浮き彫りにされるような地域や、宗教・宗派にもみいだされる。そのようなものが、イギリス人の多数が共有するものの見方とか態度などに示される国民的カルチュアの下位にある、さまざまな下位カルチュアをもつ社会を構成しているのである。連合王国を構成する四つの国の民族のカルチュアと、労働者階級と中流階級のカルチュアは、その代表的なものである。イギリスの北アイルランドを除く部分が比較的よく統合されているのは、これらの下位カルチュアをもつ集団が、自己保存的なものとして存在して、他と共存し、国の諸制度に従ってきたからである。これは、かつて敬譲的国民とよばれたこの国の民衆が、今日でも有する国制や政治的権威への忠誠心の高さに示されている。また18世紀後期からの革命の時代に、この国が一度も革命の脅威に直面したことがなかったことにも表れている。 イギリス社会が世界諸国のなかでもきわめてユニークなこのような特質を有するのは、その歴史的条件と地理的ないし地政学的条件によるところが大きいとみられる。すなわち、国民国家の統一が14世紀から進展し、その後ウェールズやスコットランドを併合してイングランド化を図り、産業革命後には、新たに台頭した二大階級を次々に体制内化し、諸改革によって社会的危機を回避した漸進的で温和な社会の発展があった。つまり、社会諸集団が対抗しつつ共存できたのである。次に地理的条件として、国民国家形成後に外敵の侵略を被らずにすんだ島国の有利さや、資本主義経済が発達するうえで必要な諸資源にも恵まれていたことがあげられる。また他都市と比べてずばぬけて大きく、人口の8分の1を占める首都ロンドンとその周辺に、連合王国の政治、経済、教育、科学、文化、マスコミなどほとんどあらゆるものの中枢があることも、ウェールズやスコットランドのイングランド化に役だっているとみられる。ただし以上のことは、プロテスタントとカトリックの宗教的対立と重なって社会が二つに分裂している北アイルランドには当てはまらない。そこではイングランド化は成功しなかった。 なおイギリスの社会には、古くからの伝統的なものを残存させながら、時代とともにゆっくりと変容しつつある面が認められる。それはスコットランドやウェールズにおける分権化を求める運動にみられる。イングランド化の修正であり、より民族的なものを表出していこうという動きである。また労働者階級カルチュアというものも根強く残ってはいるが、スラムに代表される伝統的なコミュニティが減少したことや、生活水準が向上したことなどから、ひところのようではなくいくらか希釈したものに変わった。これは、労働者階級と労働党の結び付きが弱まり、選挙のときに保守党や自由党などに投票する者が増えたところにも表れている。 [Kazuo Inudo] residents民族・言語イギリスの住民は多民族からなる。その国は多民族国である。住民と言語でもっとも主要なものはイングランドのイギリス人と英語である。英語は、14世紀にイギリスがヨーロッパ大陸やローマ法王からの独立性を明らかにしたころから、国語として重要性をもつようになった。併合されたウェールズ、スコットランド、アイルランドにおいても公用語とされただけでなく、教会や商工業の世界などでも使用され普及した。英語以外の言語としてウェールズ語、スコットランド語、アイルランド語がある。いずれも同じ印欧語系のケルト語系に属し、ウェールズ語はイギリス・ケルト語、スコットランド語はスコットランド・ゲール語、アイルランド語はアイルランド・ゲール語である。 ウェールズ語は1891年に53%のウェールズ人が話していたが、1991年には19%に減少した。しかし北西部の田舎(いなか)ではこの言語が広く使用されている。公的団体として「ウェールズ語協会」もあり、この言語は、1967年のウェールズ語法で、公用語として英語と対等なものと認められた。スコットランドでもケルト語系のゲール語を話せる人は少なくなり、20世紀末期にはヘブリディーズ諸島に暮らす人々の多くを含む約7万人という。人口の1.4%である。北アイルランドでアイルランド語を話せる人はきわめて少ない。イングランド南東部コーンウォール半島には、ケルト語系コーンウォール語が存在したが、もはや生きた言語ではなくなった。ロンドンやその他の大都市にアジア人コミュニティをつくっている人種的少数民族は、英語のほかにパンジャーブ語、グジャラート語、ベンガル語のような言語をもっている。 [Kazuo Inudo] population国勢調査は1801年以来10年ごとに行われているが、それ以前のグレート・ブリテンの人口は、11世紀末に200万、17世紀末に650万と見積もられている。1801年には1050万であった。産業革命以前に人口増加がきわめて緩やかだったのは高死亡率、とくに幼児死亡率、死産率の高さによるとみられる。19世紀に入ってから人口増加のテンポは速まって、20世紀初頭に3700万になり1971年に5500万を超えた。死亡率を上回る出生率の高さ、とくに幼児死亡率、死産率の著しい減少と平均余命の伸びが、これを促した。1歳未満の幼児死亡率は1000人につき、1901年の142から2002年には5.2に下がった。全体的死亡率はこの同じ年度に1000人につき18から10.2となった。平均余命は1901年に男49歳、女52歳から2003年に男76歳、女81歳、2008年には男77.2歳、女81.7歳に延びた。 人口統計上の動向で注目されることは、まず1975年からみられる出産率の低下によって人口増加率が停滞的になったことである。次に、老齢化社会の人口構造になったことがあげられる。連合王国全体の統計によれば、男65歳以上、女60歳以上の老齢人口は、1951年の13.5%から1999年には17.4%にまで増えた。統計上のデータ分析からみると、人口は漸増していき、第二次世界大戦後のベビーブーム世代が消える2025年から人口は減少していくとみられていたが、2008年時点の国連の予測では2050年には7237万とされている。また、人口全体のなかに占める男と女の比率が1990年代には100対104になっていることも注目される。2001年の総人口では女が男より、163万人多い。出生時は男のほうが5%多いのだが、どの年齢層でも死亡率が高く、50歳で逆転するためである。過労死もあるかもしれない。なお人口は、大ロンドンをはじめとする大都市への高度な集中を示す分布型をなしている。 入国移住者と他国移住者も毎年相当数に上るが、差し引きして、1901~1979年に200万人以上(人口の4%)を失った。入国移住者についてみると、1930年代にはヨーロッパ大陸から25万人の政治的亡命者の移住があった。第二次世界大戦後には東ヨーロッパ諸国からの移住者が目だったが、1950年代なかばからはイギリス連邦諸国などからの有色移民が増大した。西インド諸島、インド、パキスタン、ウガンダ、ケニアなどからである。彼らはイギリス各地に非白人コミュニティをつくっており、1978年に全国で190万人(人口の3.5%)、1991年に318万(5.5%)、2001年に464万(7.9%)を占めている。政府は、こうした有色移民をめぐって移住制限措置をとる一方、移住した者については、雇用や住居などに関する差別を阻止するために1965年に人種関係法を制定、その後も数度の改正、再制定が行われている。 [Kazuo Inudo] 階級と社会階層19世紀中葉、ベンジャミン・ディズレーリは「二つの国民」が存在するとみて国民統合の必要性を説いた。産業革命が富者と貧者間の富の不均衡を著しくし、都市生活で階級の地理的分離をもたらしたので、階級社会の様相は歴然であった。だがこの時代ですら中流階級と労働者階級は、それぞれ階層分化しつつあった。 [Kazuo Inudo] 職業による階級イギリスにおける階級規定で一般的なものは、職業に基づくものである。階級を決定する要因としての生活様式、生活水準、社会的慣習、価値観および態度の相違が、共通性をもつ職業に基づく集団にみいだされるからである。この規定によると、世襲財産で暮らせる貴族的上流階級は一握りにすぎず、知的専門職や政府、企業などの管理者からなる上層中流階級が社会的に重要な位置を占める。その下のランクに中層中流階級がより多く存在し、並のホワイトカラーの職についているのが、中流階級の半分にあたる下層中流階級である。労働者階級といえば筋肉労働者をさし、それは熟練、半熟練、未熟練の区分けで上、中、下の3層に分けられる。20世紀のイギリスの階級構成の変化をみると、産業構造上の変化から、管理的専門職業人やホワイトカラーは増大しているが、労働者階級はどの層も減少する傾向にある。 [Kazuo Inudo] 階級帰属意識階級への同質化を示すものとして、イギリスでは他国と比較して階級間の社会移動が少なく、人々は多くの場合、親と同様な職業につくことがあげられる。労働者階級の家に生まれた者は、自分の親と同様な職を求め、結婚してもどちらかの親との同居か近隣に住み、労働者階級クラブやパブを社交の場とし、血縁、地縁を通じて階級としての特徴を表す生活様式、慣習、価値観、ことばのアクセントを保持するといわれる。中流階級にもこれに対応するものがある。住宅パターンも階級への同質化に関係がある。第二次世界大戦後スラムが浄化されて高層公営住宅にかわり、公営住宅戸数は1976年に全住宅戸数の32%を占め、その5分の4が労働者階級入居者で、持ち家戸数は全体の53%を占め中流階級の多くが持ち家に住んでいた。これが1980年代の公営住宅居住者に払い下げる国の持ち家助長政策で、1990年になると公営住宅戸数は24%、持ち家戸数は67%となった。さまざまな社会調査によれば、労働者階級でも持ち家居住者は階級帰属意識が薄く、中流階級帰属意識をもつ者も少なくない。 階級の存在が政治の世界でよく反映するのが、ともに階級の党とみられていた労働党と保守党への選挙民の選好である。1950年代には、労働者階級の6割が労働党に、中流階級の8割が保守党に投票していた。また労働者階級の3割が保守党に、中流階級の2割が労働党に投票していた。これが1970年には、労働者階級の5割と中流階級の3割が労働党に、前者の4割と後者の3分の2が保守党に投票するようになった。選挙民の選好は変わりつつあるとはいえ、階級と政党は深い関係にある。イングランド北部および北西部は労働党、南部は保守党という政治地図も、階級との関連なしには描けないものである。 しかし、こうした階級的同質性や階級と政党の連関性は、生活水準の向上、生活様式の変化、教育を受ける機会の増大、社会的上方移動の傾向などと相まってしだいに弱まった。それはなによりもまず豊かな社会の労働者階級のブルジョア化、中流階級意識にみいだされる。労働党が敗れた1979年総選挙についてみれば、投票者の53%だけが彼らの本来の階級政党に投票したにすぎない。これは1970年に60%、1964年に65%であった。熟練労働者票は労働党対保守・自由両党で1970年に1.3対1であったが、1979年には0.8対1となった。労働党は労働者階級に見捨てられて敗れたと分析される。伝統的な階級帰属意識が崩れつつあるのであり、1970年代初めまでに、労働者階級各層で自分を中流階級に属するとみる者が増え、労働者階級とみる者は減っていた。また国民の多くが、階級なる概念で自らを位置づけていない、階級帰属意識の希薄な存在でしかないのである。 [Kazuo Inudo] educationイギリスの階級制は教育制度と密接な関係をもっている。教育による国民の分類は、職業による分類と重なり合う。労働者階級は普通義務教育だけで、16歳後も学校に残る者はホワイトカラーや専門職につく中流階級である。官公庁、政・実業界などのエリートは、私立のパブリック・スクールや大学を出た中流階級出身で占められる。国の義務教育制度ができたのは1870年であった。1944年の教育改革で義務教育は14歳から15歳に、中等教育レベルまで延ばされた。さらに1973年に16歳(5~16歳)に改正された。公立中学校には進学向きのグラマー・スクールとそうでないテクニカル・スクール、モダン・スクールの3種類があり、生徒は従来11歳になるとイレブン・プラスeleven plusとよばれる試験でより分けられて進学していた。中等教育は18歳までで、16歳までの学校は、16歳以上の生徒のための課程シックスス・フォームsixth formをもっている。イレブン・プラス試験の上位者がグラマー・スクールに、次のレベルがテクニカル・スクールに進み、全体の3分の2にあたる残りがモダン・スクールに進むようになっていた。グラマー・スクールに入る多数の家庭は中流階級だが、モダン・スクールでは大部分が労働者階級である。 こうした教育上の不平等を是正すべく労働党政府は、総合中学校comprehensive schoolへの切り替えを1960年代から図った。従来の三本立て制を総合したものに改革したのである。その改革は進み、1980年にイングランドとウェールズでは、公立中学校の8割の生徒が総合中学校で教育を受けるようになった。スコットランドでは総合中学校化が完成した。イレブン・プラスのより分けはもうなくなった。公立中学校のほかにパブリック・スクールをはじめとする私立学校がある。中等教育を終えるとき16歳から施行されるのが、学外試験GCE(General Certification of Education普通教育修了資格試験)である。GCEにはOレベルとAレベルがあり、前者は16歳で、後者は18歳でとれるのが普通である。Aレベル合格者は大学入学資格を得ることになる。Oレベル合格者は中流階級の職業につく資格を得ることになる。大学は1945年に17しかなかったが、2002年に89になった。高等教育機関の規模は1960年以来3倍以上に拡大し、その学生数は1960年代に18~19歳人口の15人に1人だったのが、1979年に8人に1人、1990年に5人に1人となった。労働者階級や下層中流階級の家庭に育った者で高等教育を受ける者はきわめて少ないが、国の奨学金制度の恩恵に浴して大学に入る者は増えている。 [Kazuo Inudo] religionイギリスでは16世紀に教会がローマ・カトリックから独立して、国王を教会の首長とする国教会となった。イングランドの国教会はイギリス国教会の監督教会派で、スコットランドの国教会は長老派教会である。ウェールズでは、住民はほとんどがプロテスタントであっても監督教会派でなく、1920年に監督教会派の国教会はその地位を喪失した。グレート・ブリテンではイングランド教会と国家権力は、相互に補強しあって住民を治めてきたのである。北アイルランドでは国教会とカトリック教会が険しく対立している。国教会の牧師は軍、国立病院、監獄にもかかわっていて、国から給料を支払われている。主権者(国王)は国教会員で、大主教、司教、首席牧師は国王に任命される。イングランドでは人口の6割近くがイングランド教会で洗礼を受け、2割弱が確たる信者である。スコットランド国教会の成人教会員は約70万である。 今日プロテスタントのノンコンフォーミスト(非国教徒)教会にあたるのが、イングランド、ウェールズの自由教会とその他の教会である。しかし19世紀の非国教徒のごとき政治参加はない。自由教会のなかでもっとも大きなのがメソジスト教会で成人信者40万8000、次に組合教会とイングランド長老教会が合併した10万3000の統一改革教会、信者14万6200というバプティスト教会がある。そのほか絶対平和主義のクェーカー教徒や救世軍がある。なおローマ・カトリック教会は19世紀に復活し、今日連合王国に子供を含めて約500万の信者がいる。 [Kazuo Inudo] Social Welfare福祉国家イギリスの社会福祉制度は、国民保健サービス、社会保障制度、個人的社会サービスの三本立てである。国民保健と社会保障は、第二次世界大戦中の「ビバリッジ報告」に基づくものである。国民保健サービスは、イギリス居住者が無料か低料金で医療を受けられることを原則としている。これが始まった1948年以来、幼児死亡率が半減し、結核、ジフテリア、小児麻痺(まひ)による死亡が急減した。現在有料なのは、処方箋(しょほうせん)、義歯および歯科治療、眼鏡、個室入院などである。ただし、低所得者や年少者などには眼鏡、歯科治療、処方箋なども無料である。産婦の歯科治療も無料である。社会保障制度は、国民が基礎的生活水準を維持できるように意図され、国民保険、労災保険、児童手当、生活扶助手当などからなる。1960年代から1970年代に、収入にスライドした国民年金制になり、それは退職年金、寡婦年金、求職者(失業)手当、疾病手当、出産手当に適用されている。失業手当の給付額は2003年現在で、18歳未満の者が週32ポンド90ペンス、18歳から24歳の者が43ポンド25ペンス、25歳以上の者が54ポンド65ペンスで、給付期間は最大182日となっている。 地方自治体の責任で行われるのが、個人的社会サービスである。自発的ボランティア団体もこれに協力している。この事業の大部分は、世話を必要とする老人や身障者のための保健サービスである。孤児や精神的な障害者を救助することもある。身障者には生活上の問題で助言したり、電話やテレビの取付け、旅行や遠足の段取りをしたりする。仕事につくための訓練・教育の世話もする。老人対策は、できるだけ長く自宅に住めるよう配慮され、食事の配達、身の回りの世話、洗濯サービスなどが行われている。 福祉国家イギリスで最近深刻な問題となりつつあるのが、失業と貧困である。1960年代までは完全雇用に近かったが、1976年に133万(5.7%)となったときから大量失業は克服しがたい慢性のものとなった。1981~1987年は300万前後が続き10~23%の高い失業率であった。その後1988~1992年に一桁(けた)に下がるが、6%を割り160万以下にはめったにならない。1993年からは同年の10%から漸減して1997年は6%程度になった。2007年の失業者数は165万人、失業率は5.4%となっている。こうした高水準の失業が長期化するなかで貧困がこの国の大きな問題となっている。「貧困線(ボーダーライン)」とされる生活扶助手当(単身者で週26ポンド45ペンス、夫婦で69ポンド)以下で暮らす家庭が130万、同ライン線上とそれより上の20%以内の収入の家庭が180万もあり、1987年には人口の17%を占める800万人が貧困層をなしていることがわかった。国民のおよそ7人に1人が貧困状態にあるのである。 [Kazuo Inudo] cultureイギリス思想・文化の伝統と特質イギリス人が単一民族による簡単な構成でなく、もともとグレート・ブリテン島に先住したケルト系、ドイツから侵入してきたゲルマン系、さらにその後移住してきたラテン系というように、雑多な民族の混成であるから当然なことであるが、彼らの国民性、思想、文化もまた単一明晰(めいせき)なものではなく、複雑多様なものである。 また地理的にみても、北からの寒流と南からの暖流とがあわさり、イギリス名物の霧を生み出しているわけだが、イギリス人の精神にも濃い霧がかかっていると考えられる。物事をはっきりと、くっきりと認識し理解するのではなく、もやを通して屈折して受け取る習慣がついてしまった。 初めからできあがっている理論や思想体系に従って割り切る、という考え方に、彼らはいつも疑惑を抱く。自分の目で、経験によって、何度も何度も確かめ、自分自身の肌で納得がいったときに、初めて確信をもつ。イギリスの哲学が観念論を退けて、経験論を重んずるのも無理からぬことであった。しかも、性急に二つに一つの決着をつけるのではなく、そのどちらをもとり、両者の間にバランスを保ち、融合を図るという、しなやかで、しかししぶとい思考を身につけたのも、相矛盾する二つの要素に挟まれて生きなければならなかったイギリス人の宿命から得た処世上の知恵であった。 中庸の美徳というものが、イギリス人の生活感情のなかに深くしみ着いてしまっている。16世紀ヨーロッパを襲った宗教改革の嵐(あらし)のさなかでもイギリスは、形のうえではプロテスタントを選びながら、内容や祭式のうえでは古いカトリックを切り捨てずに中間の道をとった。「中道」(ビア・メディア)というのがイングランド教会の基本的精神である。このような聖なる問題からずっと下って、日常の俗なる次元に話題を移すと、イギリス庶民の多くは、さまざまな刻みたばこを適度に混ぜたミディアムをパイプに詰めてふかし、2種類の酒を混ぜた「ハーフ・アンド・ハーフ」をパブで注文し、ビーフステーキもミディアムに焼くよう命ずる。 このようなイギリス人独特の二元性を、以下具体的な実例によって示そう。 [小池 滋] Nationalityイギリス人気質といえば、すぐ連想するものにスポーツ愛好とユーモアがある。 彼らがスポーツを好むのは、それがあくまであるルールのもとで行われるゲーム(遊び)だからである。ルールが法や掟(おきて)と違うのは、法や掟があらゆる場合に通用する絶対の権威をもっているのに反して、ルールはある一定の約束ごとのもとでしか通用しない点である。殺人や盗みはいかなる場合でも禁じられるが、ボールを手で持っていけないのはサッカーのときだけだ。だから、ゲームの間はむきになるが、ゲームが終われば禁止条項も、罰則も、いや相手に対する敵意すらが消えてしまう。 彼らが人生をゲームとして考えるのは、唯一絶対の権威をうさんくさいものとして嫌い、すべてを相対的に眺めたいからである。なりふりかまわず、まなじりを決して、ある一方向に突進するのは、ゲームとして実に下手なやり方であることを知っているから、人生においても絶えずルールを忘れず、いかに上手にプレーするかを念頭に置く。自分も他人も等しく距離を置いて眺め、客観化することができるのは、それをゲームと考えることができればこそである。 同じことがユーモアについてもいえる。ユーモアとは、自分をも他人と同じくわきから眺めて、そのおかしさを笑うことのできる能力あるいは感覚である。他人だけを一方的に笑う人、自分が他人の目にどう映るだろうかと冷静に考えることのできない人は、ユーモアに欠けるといわざるをえない。自分を高い地位に置いて他人を見下して笑ったり、自分をわざと卑下しておせじ笑いするのではなく、自分と他者を同じ高さに置き、しかも相手に思いやりをかけて笑うときにこそ、真のユーモアが生まれ、そのときこそ笑いが人間の心を結び付ける固いきずなとなりうる。 真の意味でのスポーツ(ゲーム)にもユーモアにも共通している特質は、それがなにかほかの目的のための手段でなく、それ自身を目的とする純粋の行為、無償の行為であるという点だ。ここにイギリス人独特のアマチュアリズムの精神が生まれ、彼らの多様な趣味の世界が広がる。はたの人間からみれば、子供じみたばからしい遊びに思えること、たとえば、小さな球ころがしや、役にもたたぬがらくたのコレクションに目の色を変えているのも、働き中毒になるのを防ぐ安全弁である。パンを得るため、生活するために必要切実な手段である実社会の仕事だけに目の色を変えて、それだけを生きがいとしていちずに突進するよりも、実際の利害と無関係な子供じみた行為にふけるほうが、はるかに危険が少ないことを知っているのである。 このような仕事と遊びの使い分けは、イギリス人の公生活と私生活の演じ分けにつながる。「イギリス人の家庭は城である」とよくいわれるように、彼らは自分の私生活、プライバシーをかたくなに守り、また、外界に対して閉鎖的な態度を示し、胸の奥底を容易に他人に明かさない。他国民がイギリス人に対して疑心暗鬼となり、不可解だと首をひねるのは、これが原因である。 よく外国旅行をした日本人が、「列車の中で向かい合って同席したアメリカ人やフランス人やイタリア人とは、すぐ仲良しになり打ち解け合えるのに、イギリス人は数時間たっても一言も口をきかず、にこりともしない」といって苦情をこぼす。しかし、J・B・プリーストリーという生粋(きっすい)のイギリス人の弁論に耳を傾けよう。イギリス人は決して人づきあいが悪いのではない。人間は四六時中愛想よくしているわけにはいかないのだから、外づらの悪いイギリス人は、家庭内や親しい友同士では実に温かい人間なのだ。見知らぬ人に愛嬌(あいきょう)を振りまく人間は、親密な温かい家庭をつくることができないのではないか。 [小池 滋] artイギリスの芸術こそ、まさにイギリス人のもつ二元性がもっとも顕著に表れた一例である。シェークスピアという世界に誇る異才を生み出したイギリスの文学について、まずこれを考えてみよう。 北欧やゲルマンの神話には、暗い運命に対して勝ち目のない戦いを挑む人間の雄々しい悲劇的な姿を描いたものが多い。リア王やマクベスやハムレットの世界は、これを如実に示したものだが、シェークスピアはこれと同時に、明るい楽天的な、生きる喜びを謳歌(おうか)するラテン文学の陽光を取り入れることもできた。『真夏の夜の夢』の世界がまさにそうであるし、『ロメオとジュリエット』の世界は、悲劇的ではあるが、若さと情熱に満ちあふれた地中海文化を思わせ、霧と人生の不条理のカーテンに閉ざされた北欧の暗い空を連想させるものではない。 ゲルマンとラテンの人生観、世界観の混合のなかから、シェークスピア独特のユーモアが生まれる。行為は不道徳だが人間味の大らかさで観客を魅了するサー・ジョン・フォルスタッフ(『ヘンリー4世』『ウィンザーの陽気な女房たち』の登場人物)は、シェークスピアの創造した最高の人物といわれる。また端役として登場する道化たちの人生の知恵にあふれた滑稽(こっけい)な台詞(せりふ)もこのことを裏書きする。 さらにシェークスピアの用いる言語は、英語の集大成、その詩的表現力の絶頂を極めたものである。これは、英語のルーツたるゲルマン系のアングロ・サクソン語に、ラテン系のフランス語が加わり、この混合によって驚くべき言語の自己増殖力が生まれたからである。上流階級の教養人の雅語と、一般庶民の俗語が融合し、古い伝統的表現が新しい外来の新語によって活性化した結果、ことばの花園が生まれた。シェークスピアやディケンズなど英文学史上の偉大な文豪は、まさにそこに咲いた大輪の花であった。 美術、音楽においてイギリスは、文学におけるほどの世界的水準にまで達していないが、その根底にある特質は同じである。イギリス人は古来の伝統を重んずることで知られているが、だからといって新しい外来の要素を排除することなく、自由に取り入れて同化した。エリザベス王朝時代の音楽、18世紀の絵画が世界に誇るものを生み出したのは、この柔軟な精神のおかげであった。19世紀には高度に発達した物質文明に、音楽、美術が追い付くことができず、諸外国に比べて貧弱な状態にとどまったが、大英帝国の威光の薄れた20世紀となって、ふたたび芸術的再生の兆候が現れ始めたのは、広く外に門戸を広げるイギリス本来の姿勢を取り戻したからである。 イギリスの芸術を語るにあたって忘れることのできないものは、いわゆる高級な芸術品ではなく、民衆の生活のなかから生まれた素朴な工芸品などである。たとえば陶器、家具、織物など、日常の必要を満たすためにつくられ、同時に美的感覚を十分に満足させるものが多かった。産業革命後、これらの品物は工場による大量生産に移されたが、それに抗して古きよき民俗伝統を守ろうとする動きが各地でみられ、今日に至るまで絶えることなく続いている。 [小池 滋] Cultural Facilities博物館、美術館などは、まさに上に述べた民衆の遺産を保存し、後世に伝える役割を果たしている。イギリスの博物館といえば、すぐに大英博物館と、そこにある世界的逸品、エルギンの大理石やロゼッタ石を思い浮かべるが、それ以外に、名前はあまり広く知られていないが、多くのじみな展示品をもつ博物館が(とくに地方に)あることを忘れてはならない。美術館、工芸館についても同じである。 さらに、こうした施設が、かならずしも国家や地方自治体など、いわゆる政府の手によるものではなく、民間の有志によって支えられていることに注目すべきだろう。たとえば、古い建築物をその中の家具、装飾品とともに破壊散逸から防ぐため、「ナショナル・トラスト」という団体が管理維持を行っている。これも、すでに述べたイギリス人のアマチュアリズムの一つの現れであり、ボランティア精神の顕著な実例である。 特別の学者専門家以外あまり本を買わないイギリス人にとって、教養娯楽のための読書はもっぱら地域の公共図書館に頼ることとなる。図書館は単に求められた本を貸すだけでなく、専門教育を受けた司書による読書指導・相談、必要な本を全国的ネットワークで探し出すサービスが能率よく行われる。そのうえ、その地方の歴史、文学などの研究を促進させるための文化活動の中心となっている。ただ皮肉なことに、図書館が充実するにつれ個人の本を買う意欲が減り、出版社の経営が脅かされるので、出版社や著作者側から、図書館の貸出し回数に応じた印税を要求する声があがった。1979年に公貸権法が成立し、1982年より図書館の貸出し冊数に応じた補償金を政府の拠出金による基金より支払っている。 [小池 滋] Mediaイギリスは世界でもっとも早くから新聞の発達した国であるが、19世紀後半までは読者数もそれほどではなかった。1870年に法によって無料で小学校教育を全国民に施す方針が決まったのを契機として、国民の読み書き能力が大きく飛躍した。その結果、出版事業は、特定の教養人のみではなく、広範囲にわたる大衆を目標とするように変わった。新聞も部数の少ない高級紙と、大部数をもつ大衆紙とに分かれ、高級紙の経済的危機がしばしばうわさされ、世界的権威を誇るロンドンの『タイムズ』の存立すら危うくなってきた。新聞、出版を問わず整理統合が激しく、国外の経営者の手に渡るというケースがしばしばみられる。通信社には1851年創立のロイターなどがある。 イギリスの放送は1922年に開始され、その後、国営の英国放送協会(BBC)が独占し、一般国民の文化水準を高めるという啓蒙(けいもう)的態度を一貫してとってきた。第二次世界大戦以後テレビが加わり、娯楽的要素が強まってきた。現在テレビはBBCのほかにチャンネル4(非営利法人)、チャンネル3(ITV)とチャンネル5が全国放送を行っている。ラジオはBBCのほかに全国放送が3チャンネル、多数のローカル局がある。イギリスの放送は日本に比べればチャンネル数も少なく、放送(放映)時間も短く、よくも悪くも生活への影響は小さい。 [小池 滋] Relations with Japan
19世紀に入ると、ナポレオン戦争のすきをついてイギリスは東アジアへの進出を早め、日本近海にもイギリス船が出没するようになった。1808年(文化5)フェートン号が不法に長崎に入港し、燃料と食料を強要した。この事件は幕府に衝撃を与え、イギリスに対する関心をかき立て、幕府はオランダ語通詞に英語の学習を命じた。早くも1811年(文化8)には最初の英学入門書と英和対訳辞書が刊行され、後の日英交渉史に活躍する森山多吉郎、堀達之助らの英語専門の通詞を生む素地が固められた。1820年代には、浦賀に入港したイギリス船が通商を求めて幕府に拒否され、また水戸(みと)藩領大津浜への武装イギリス兵の上陸事件が起こるなど、幕府を刺激する事件が相次ぎ、幕府は苦肉の策として異国船打払令を出してこの情勢に対応した。アメリカのペリーが浦賀に現れた翌年の1854年(安政1)、イギリス極東艦隊司令官スターリングが4隻の軍艦を率いて長崎に入り、日英約定を結び、日英和親条約が正式に調印された。この条約に基づいて1858年エルギン卿(きょう)が江戸にきて、日英修好通商条約を結び、ここに日英間に正式の外交関係が樹立され、初代の総領事(のち公使)としてオールコックが着任した。以後ニール(代理)、パークスと続くイギリス外交団は、生麦(なまむぎ)事件(1862)にみられたような日本人の反発に対して、薩英(さつえい)戦争(1863)、四国艦隊下関砲撃事件(1864)など、力による威圧の政策をとり、さらに攘夷(じょうい)運動が薩摩(さつま)、長州を中心にしだいに開国、対英接近の姿勢に転向するのをみて、討幕運動を支援し、幕府を支持するフランスを牽制(けんせい)した。幕府のイギリス外交官にはオールコックをはじめサトー、アストン、ミットフォードなど日本紹介に多大の貢献をした人物がいる。 ところで、漂流民、水夫を除けば、正式にイギリスを訪れた最初の日本人は、幕府の遣欧使節団の一行38人であった(1862年=文久2)。メンバーには福沢諭吉、福地源一郎、箕作秋坪(みつくりしゅうへい)らが含まれ、精力的な探訪と学習とによってイギリスに対する認識を深めた。翌1863年長州藩は禁令を破って、後の伊藤博文(いとうひろぶみ)、井上馨(いのうえかおる)ら5人を密航させてイギリスに留学させた。一行は商社ジャーディン・マセソンの世話を受け、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジに学んだが、同じカレッジには1865年(慶応1)から薩摩藩留学生15人も加わった。彼らも全員変名を用い、政商グラバーの世話で密航したが、なかには森有礼(もりありのり)、日本における博物館の父、町田久成(まちだひさなり)などがいた。一方、開国後の幕府は蕃書調所(ばんしょしらべしょ)を置き、情報の収集と洋学者の育成にあたったが、そこにおいては、もはや蘭学(らんがく)の独占的地位は崩壊し、1860年(万延1)ごろから英学の担当者も現れて、英学は蘭学に次いで第二順位を占めた。1866年(慶応2)ついに渡航の自由化に踏み切った幕府は、菊池大麓(きくちだいろく)、外山正一(とやままさかず)、林董(はやしただす)ら10代後半から20歳前後の青年12人を選抜し、これに年長の川路太郎、中村正直(なかむらまさなお)を加えて、イギリスに留学生として派遣したが、彼らも薩摩、長州の留学生とともに主としてユニバーシティ・カレッジに学んだ。幕末までの留学生総計153人中、イギリスで学んだものが49人で最高位を占めているところにも、日本のイギリスに対する関心の高さがうかがえる。 文物の交流の面では、1862年(文久2)にロンドンで開かれた万国博覧会には、オールコックの斡旋(あっせん)で日本の工芸品が陳列された。日本に在住したイギリス人の活動で目覚ましかったのはジャーナリズムの分野で、最初の英字新聞が商人ハンサードAW Hansardによって長崎で創刊されたが、のちに横浜に移り、ブラックを編集者とする日刊の『ジャパン・ガゼット』へと発展した。また『イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ』の特派画家兼通信員として1861年来日したワーグマンは、『ジャパン・パンチ』を通じて日本の紹介にあたった。 幕府期にイギリスを訪れた体験の持ち主は、幕府の倒壊、明治政府の誕生という情勢のなかで、新時代のオピニオン・リーダーとして登場した。なかでも傑出した存在は、『西洋事情』『文明論之概略』などの精力的な文筆活動と慶応義塾の教育を通して、イギリスの制度、文物、思想の啓蒙(けいもう)にあたった福沢諭吉と、幕府崩壊後は静岡学問所の教授となり、スマイルズの『西国立志編』、J・S・ミルの『自由之理』を翻訳・刊行した中村正直である。2人とも明六社の同人として、自由民権思想の基盤を整えるのに大きな貢献をした。 明治時代の日英関係の劈頭(へきとう)を飾ったのは、岩倉使節団の派遣であった。正使岩倉具視(いわくらともみ)をはじめ木戸孝允(きどたかよし)、大久保利通(おおくぼとしみち)、伊藤博文など明治新政府の中心人物を網羅したこの大使節団は、アメリカに次いで1872年(明治5)8月イギリスを訪れ、4か月余り滞在し、ロンドンのみならずリバプール、マンチェスター、グラスゴー、さらにはスコットランド高地地方まで足を伸ばし、イギリスの先進的な諸制度や技術を親しく視察した。その詳細は、使節団の報告書『特命全権大使米欧回覧実記』にみることができるが、同じ小さな島国たるイギリスの富強の原因を探ろうとしたその視角は、これからのち第二次世界大戦までの日本人のイギリス観の原型となった。そして自由民権運動の展開した明治10年代には、立憲改進党が結党にあたって「万事の改革すでに成りたるイギリス」の政党に倣うと宣言し、また福沢を中心とする交詢社(こうじゅんしゃ)は、イギリス流の立憲君主制を骨格とする憲法私案を発表し、また実地の体験の尊重を旨とする英吉利(イギリス)法律学校(後の中央大学)が設立された。 一方「文明開化」を標榜(ひょうぼう)したこの時期に、イギリスは欧米列強のなかでも最多数のいわゆる「お雇い外国人」を送って、日本の近代化に多大の寄与をした。なかでも、鉄道建設の最高責任者であり、工部省の設置を進言して技術教育の基礎を固めたモレル、総員34人の教師団の団長として来日し、日本の海軍を完全にイギリス流に教育・編成したダグラスArchibald Lucius Douglas(1842―1913)、当初はその一員でのちに帝国大学で言語学、日本語学を講じたチェンバレン、また洋風建築の普及に尽力したコンドルなどの名は逸することはできない。逆に日本側も開国期よりもはるかに多数の留学生をイギリスに送り出したが、1900年(明治33)英語・英文学関係の最初の文部省派遣留学生に選ばれたのが夏目金之助(漱石(そうせき))であり、屈折を余儀なくされた留学生活を送った彼は、帰国後ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の後任として東京帝国大学で英文学を講じた。聖書と賛美歌の翻訳で始まったイギリス文化の移入も、やがてシェークスピアを筆頭とする英文学に広がり、ワーズワース、バイロン、シェリーなどは明治中期には日本人にも親しい名前となった。 かくて「世界の工場」、強大な海軍力を擁する大帝国、議会政治の母国、また、ジェントルマンの国としてのイギリスのイメージは、日本人の脳裏に強く印象づけられ、イギリスをこそ学ぶべき模範とみるイギリス観が、支配階級と知職人の一部に根強く存在し続けることになった。 他方、外交面においてイギリスは、他国よりも先に日本の不平等条約改正の主張を認め、1894年(明治27)日英通商航海条約を結び、さらに日清(にっしん)戦争後はロシアの進出に対抗して極東を重視する政策をとり、1902年(明治35)日英同盟を締結し、相互援助を約した。この同盟条約によって日本は第一次世界大戦に参戦したが、同盟はワシントン会議の四か国条約によって破棄された。昭和に入ってからの日本の中国侵略に対して、国際連盟が派遣したイギリス人リットンを長とする調査団の報告は、日本の国際連盟脱退を招き、両国の関係は太平洋戦争の破局を迎えた。第二次世界大戦後イギリスは連合国の一員として対日占領政策に参加し、サンフランシスコ条約により国交を回復した。近年イギリスの国際的地位の低下、「イギリス病」の弊害とその克服が語られるなど、日本のイギリスをみる目は大きく変化しており、新たな日英関係のよってたつ基盤が模索されている。 [今井 宏] 『杉山忠平著『イギリスの国、イギリスの人』(1967・未来社)』 ▽ 『K・B・ステフェンソン著、中村和郎訳『全訳世界の地理教科書3 イギリス――その国土と人々』(1977・帝国書院)』 ▽ 『木内信藏編『世界地理7 ヨーロッパⅡ』(1977・朝倉書店)』 ▽ 『定松正・蛭川久康他編著『風土記イギリス――自然と文化の諸相』(2009・新人物往来社)』 ▽ 『W・バジョット著、深瀬基寛訳『英国の国家構造』(1967・清水弘文堂)』 ▽ 『河合秀和著『現代イギリス政治史研究』(1974・岩波書店)』 ▽ 『R・ローズ著、犬童一男訳『現代イギリスの政治Ⅰ・Ⅱ』(1979・岩波書店)』 ▽ 『S・G・リチャーズ著、伊藤勲監訳『現代イギリスの政治』(1979・敬文堂)』 ▽ 『梅川正美・阪野智一他編著『現代イギリス政治』(2006・成文堂)』 ▽ 『渡辺容一郎著『イギリス・オポジションの研究――政権交代のあり方とオポジション力』(2009・時潮社)』 ▽ 『AH Hanson & Malcolm WallesGoverning Britain, A Guide-Book to Political Institutions (1st published 1970, Revised edition 1975, Fontana, Collins)』 ▽ 『内田勝敏著『現代イギリス貿易論』(1966・東洋経済新報社)』 ▽ 『森恒夫著『イギリス資本主義』(1975・青木書店)』 ▽ 『吉岡昭彦著『近代イギリス経済史』(1981・岩波書店)』 ▽ 『浜野崇好著『イギリス経済事情』(1981・日本放送出版協会)』 ▽ 『森嶋通夫著『イギリスと日本』正・続(岩波新書)』 ▽ 『小松芳喬著『イギリス経済史断章』(2000・早稲田大学出版部)』 ▽ 『横井勝彦編著『日英経済史』(2006・日本経済評論社)』 ▽ 『日本経済新聞社編・刊『イギリス経済再生の真実』(2007)』 ▽ 『G・M・トレヴェリアン著、藤原浩・松浦高嶺・今井宏他訳『イギリス社会史Ⅰ・Ⅱ』(1971、1983・みすず書房)』 ▽ 『R・マッケンジー、A・シルバー著、早川崇訳『大理石のなかの天使――英国労働者階級の保守主義者』(1973・労働法令協会)』 ▽ 『内藤則邦著『イギリスの労働者階級』(1975・東洋経済新報社)』 ▽ 『Trevor NobleStracture and Change in Modern Britain (1981, Batstord Academic and Education Ltd., London)』 ▽ 『J・B・プリーストリー著、小池滋・君島邦守訳『英国のユーモア』(1978・秀文インターナショナル)』 ▽ 『小野二郎著『紅茶を受皿で――イギリス民衆芸術覚書』(1981・晶文社)』 ▽ 『森嶋通夫著『イギリスと日本』正・続(岩波新書)』 ▽ 『沼田次郎編『東西文明の交流6 日本と西洋』(1971・平凡社)』 ▽ 『日本英学史学会編『英語事始』(1976・エンサイクロペディア・ブリタニカ)』 ▽ 『今井宏著『日本人とイギリス―「問いかけ」の軌跡』(1994・ちくま新書)』 ▽ 『北川勝彦編著『イギリス帝国と20世紀 第4巻 脱植民地化とイギリス帝国』(2009・ミネルヴァ書房)』 [参照項目] |||||||||||||||| |[補完資料] |"> イギリスの国旗 ©Shogakukan 作図/小学館クリエイティブ"> イギリス位置図 ロンドン中心部のウォータールー・ブリッジからシティを望む。水運に重要な役割を果たし、また観光船なども航行する。有名なロンドン・ブリッジやタワー・ブリッジなど、市内にはいくつもの橋が架かる。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka "> River Thames 12世紀ごろからあるといわれるウルクハート城と湖水。U字谷に湛水したフィヨルド湖で、怪獣伝説を思わせる神秘さよりも、明るくのどかな風景である。イギリス インバネス近郊©Masashi Tanaka "> Loch Ness 2個の立石の上に楣石をのせたトリリトン(三つの組石)。高さ約7m、立石1本の重さは25tに及ぶ。世界文化遺産「ストーンヘンジ、エーブベリーと関連する遺跡群」の一部(イギリス・1986、2008年登録) イギリス ソールズベリー近郊©Shogakukan "> Stonehenge 11世紀に建造され、のちに火災で大部分を焼失。19世紀なかばに再建され、現在は国会議事堂として使用されている。北側(写真右)にそびえる時計塔は「ビッグ・ベン」。世界文化遺産「ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター寺院および聖マーガレット教会」の一部(イギリス・1987、2008年登録) イギリス ロンドン©Shogakukan "> ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議… ダウニング街10番地にある首相官邸。旧ウェストミンスター地区は古くからイギリス国政の中心で、この通りには大蔵大臣官邸や外務省などが面している。「ダウニング街10番地」はイギリス首相の代名詞ともなっている。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka "> ダウニング街 ロンドンの中心部、シティにあるイギリスの中央銀行(写真左)。1694年の開設だが、現在の建物は1924~39年のもの。「ザ・バンク」「スレッドニードル街の老婦人」ともよばれる。写真右奥は旧王立取引所。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka "> Bank of England One of the world's largest museums, the pride of the UK. Opened in 1759. It exhibits many important ancient relics and artworks from around the world, including Egyptian civilization. The facade of the building, with its rows of Ionic columns, was designed by British architect Smirke. London, UK ©Masashi Tanaka "> The British Museum テムズ川に架けられた可動橋。1894年完成。重量1000tの可動部分の橋桁は水力によって約90秒で全開する。塔内には、橋桁開閉のメカニズムを示す展示館もある。イギリス ロンドン©NetAdvance "> Tower Bridge Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
総論
国旗は、イングランドの聖ジョージ十字、スコットランドの聖アンドリュー十字、およびアイルランドの聖パトリック十字を重ねた図柄のユニオン・ジャック。国歌は世界最古とされる“God Save the Queen (King)”――神よ女王(国王)を守りたまえ――で、いずれも日本ではよく知られている。 連合王国は、アイルランド共和国とともにイギリス諸島を占めている。イギリス諸島は大小約5000の島からなり、西ヨーロッパ大陸北岸沖に位置する。主島のグレート・ブリテン島は、南をイギリス海峡、東を北海、北を大西洋、西をアイリッシュ海とセント・ジョージズ海峡で囲まれる。第二の島アイルランド島の北部の一画を占める北アイルランドは、東をアイリッシュ海とノース海峡、北を大西洋、西と南をアイルランド共和国で囲まれている。グレート・ブリテンはさらにイングランド、ウェールズ、スコットランドの3地方に分けられるが、人口はイングランドに偏り、2008年現在、イギリス総人口の84%がイングランド、8%がスコットランド、5%がウェールズ、残りの3%が北アイルランドに分布している。 イギリスは、西ヨーロッパの一隅にありながら、イギリス海峡を隔てて大陸諸国に対するというその地理的条件から、数百年の間、大陸諸国との間につねに一線を画した立場をとってきた。18世紀の科学革命に続き産業革命でも世界に先駆け、海洋民族として進取の精神に富む国民の海外進出も目覚ましく、19世紀なかばには世界一の工業生産力と植民地をもつ大英帝国を築き上げた。こうしてイギリスを中心とする世界秩序を確立するに至り、この結果ヨーロッパの一員としての自覚よりは、世界の大国としての指導者意識が強くなった。しかしその後、第一次・第二次両世界大戦を経て国力は疲弊し、とくに第二次世界大戦後、イギリス経済を支えてきた植民地が相次いで独立し、一方では米ソ二大国の興隆もあり、イギリスは世界の大国としての地位を失い、西ヨーロッパの一国に甘んぜざるをえなくなった。一時背を向けたEEC(ヨーロッパ経済共同体)にも、1973年に拡大EC(ヨーロッパ共同体)の発足とともに参加を認められたことで、イギリスは名実ともに初めて西ヨーロッパの一員となったということができる。 イギリスは第二次世界大戦後も王制を敷く数少ない国の一つであるが、政治の基本は、上下両院からなる議会を国権の最高機関とする立憲君主制で、女王(国王)の権限は「君臨すれども統治せず」という有名な表現からも明らかなように名目的なものである。現在は、1952年に王位を継承したエリザベス2世女王の治世である。イギリスは文化に関しても世界をリードしてきたが、イギリス文化の特色の一つは、イギリス人の現実的な国民性が強く反映していることであろう。政治、経済など現実の社会を動かす制度や、科学技術、あるいは実用主義的理論では現在も高い水準にある。芸術の分野でも、現実的な人間を描く文学や演劇では優れた作品を生み出してきたが、美術、音楽などの分野での貢献はやや低いといえよう。19世紀以来、社会問題の解決に意欲的に取り組み、第二次世界大戦後は世界でもっとも充実した社会福祉制度をもつようになった。しかし反面、最近では国民の勤労意欲は高いとはいえず、成熟した資本主義先進国の将来の姿を示している。 [井内 昇] 自然地勢イギリス諸島は、ヨーロッパ大陸北西の大西洋に広がる水深200メートル未満の大陸棚にある。地質や地層構造、地形なども大陸の延長としての性質を示すことから、もともと大陸の一部であることは明らかで、約8000年前までは現在のドーバー海峡の部分で地続きであったと考えられている。イギリス諸島はいずれも小さな島であるにもかかわらず、さまざまな地形が発達し、地質構造も複雑である。しかし、大別すれば、グレート・ブリテン島東岸ティーズ川河口と、南西部コーンウォール半島のエクス川河口とを結ぶ線によって、西側の石炭紀より古い岩石からなる高地イギリスと、東側の石炭紀より若い岩石からなる低地イギリスとに二分できる。 高地イギリスでは、北部のスコットランド高地から、西の北アイルランド、ウェールズ北部にかけて、スカンジナビア半島から延びるカレドニア大褶曲(しゅうきょく)山系が北東から南西方向に走り、おもに片麻(へんま)岩、結晶片岩、花崗(かこう)岩などの古生代の古い岩石で構成されている。スコットランド高地は長い期間にわたる侵食作用により準平原化し、現在はハイランドの名が示すように高原状を呈し、最高のベン・ネビス山でも標高1343メートルにすぎないが、その後若い地質時代に激しい断層運動や氷食作用を受けたため地形は険しい。高地イギリスでも、南西部は同じ古生代末のヘルシニア期の褶曲作用によってつくられたヘルシニア褶曲山系の山地が横たわる。この山地の主脈となる山系は、アイルランド南西部からコーンウォール半島を経てフランスのブルターニュ半島に延びており、褶曲の方向はほぼ東西となっている。この二つの大褶曲山系の中間は、石炭紀とそれ以降の新しい地層からなり、ここにブリテン島の脊梁(せきりょう)山脈であるペニン山脈が南北に走っているが、ヘルシニア山系と接する部分に大きな炭田が発達している。 一方、低地イギリスはおもに中生代、新生代の岩石からなり、緩やかな褶曲や傾動を受けている。南東部の岩石の多くは第三紀のアルプス造山運動による褶曲を受けているが、この褶曲作用によって地層は南東方向にしだいに低く傾動している。この地帯では柔らかい泥岩や粘土の層と、硬い石灰岩、砂岩、花崗岩などが互層をなす場合が多いが、侵食に対する抵抗力が違うため、傾動作用によってこの互層が地表に露出すると、硬い岩石の部分は残って急斜面をつくり、柔らかい地層の部分は緩斜面となり、ケスタとよばれる階段状の地形が発達した。イギリス諸島は、グレート・ブリテン島の南部を除きかつて氷河で覆われたため、イギリスの地形には氷食作用の影響が至る所でみられる。海岸線でも、スコットランド西岸では氷食山地の沈水による典型的なフィヨルドが発達するほか、一般に西海岸一帯には沈水海岸が広くみられ、海岸線は出入りに富んでいる。東海岸と南海岸には砂浜が発達し、そこでは河口部が海に向かって大きく開けた三角江や、ドーバーのような海食崖(がい)が点在している。 [井内 昇] 気候イギリス諸島は、大陸東岸にあるカムチャツカ半島(ロシア)やラブラドル半島(北アメリカ)とほぼ同緯度にあり、南北の緯度差は11度に及ぶにもかかわらず、夏は涼しく冬は暖かい。これは、大陸西岸にみられる海洋性気候の特色で、ケッペン気候区分では温帯多雨型のCfbに相当する。この恵まれた気候は、西を流れる暖流のメキシコ湾流と偏西風によるところが大きい。しかし、イギリス諸島の気候を支配する北のアイスランド低気圧、南のアゾレス高気圧、およびヨーロッパ大陸に夏に現れる低気圧と冬の高気圧の消長が、イギリスの気候に複雑に働きかけ、天気変化に激しさをもたらしている。とくにアイスランド低気圧から二次的に発生する小さな移動性低気圧が、秋から冬を中心にイギリス諸島の上や周辺を定期的に通過するため、多様な地形の影響もあって、イギリスの天気はめまぐるしく変化する。このように、イギリスの天気は変わりやすく、気まぐれといえる。 気温の年較差は、日本に比べれば驚くほど小さい。たとえば、各地の最低・最高気温の平均をみると、年平均の最低はスコットランド西岸沖ヘブリディーズ諸島の8℃、最高はイングランド南西のコーンウォール半島の11℃で、その差は3℃にすぎない。しかし、夏の等温線が東西に延びているのに対し、冬の等温線は南北方向に延びているため、地域別にはかなりの違いがみられる。たとえば、北緯54度線と西経4度線でイギリスを4分割すると、北東部は夏涼しく冬も寒いが、南東部は夏が暑く冬も温暖だがやや寒い。北西部は夏は涼しいが冬は暖かく、南西部は夏が暑く冬も暖かい。月別平均気温は、北端のシェトランド諸島のラーウィクで冬の12~2月が4℃、夏の6~8月は12℃であるが、南端のワイト島では冬の最低が5℃、夏の最高は16℃である。大都市では、南のロンドンで1月が4℃、7~8月が17℃、北のアバディーンでは1月が2℃、7月が14℃である。 イギリスは年間を通じて湿度が高く、年降水量の全国平均は1100ミリメートルであるが、地形と海岸までの距離に応じて地域間の格差が大きい。一般的に大西洋に面する西部と北部で多く、東部で少ない。もっとも雨量が多いのはスコットランド西岸で、降雨日数は年間250日に及び、総雨量は2000~4700ミリメートルに達する。このほか、局地的にはウェールズのスノードン山やイングランド北西部の湖水地方で4000ミリメートルを超える。ペニン山脈では1500~2500ミリメートル、ウェールズ山地で1000~1500ミリメートル、南西部のコーンウォール半島では1300~2000ミリメートルとなっている。しかし、東部にかけてしだいに少なくなり、イングランド東部地方では600~700ミリメートルにすぎない。イギリスの降雨は一年中あまり差がないが、一般に3~6月は少雨期で、10~1月は多雨期といえよう。3週間以上雨が降らないのは例外的で、それも局地的に生ずるにすぎない。雨量が年間を通じて安定しているから、イギリスの河川は流量が一定で流れも緩やかである。このため、イングランド低地を中心に運河網が発達し、19世紀初期まで重要な輸送路として利用されてきた。河川は一般に短く、テムズ川(338キロメートル)およびセバーン川(290キロメートル)がもっとも重要な二大河川とされている。 [井内 昇] 動物相・植生イギリス諸島原生の大形動物であるオオカミやクマ、野生のブタやウシ、トナカイなどはすでに絶滅した。キツネやシカは狩猟用に保護され、各地でみられる。小形動物では、リス、ノネズミ、ハリネズミ、その他各種のネズミ、モグラなどが多い。鳥類は各地で約460種が記録され、そのうち200種は留鳥で、残りは渡り鳥である。河川や湖には約30種の淡水魚がすみ、サケ、ウナギのほか、マス、コイなどは魚釣り用にも養殖されている。 イギリスの気候と土壌は樹木の生育に適し、太古は高度300メートル以下の地表は原生林に覆われていたが、数千年にわたる人類の利用でその大部分は伐採され、現在、森林面積は国土の10%にすぎず、かわりに放牧地や牧場、荒れ地が60%以上を占めている。氷河が後退したあとにまずカバとマツが生育し、現在はカシとともに全国でみられる。ブナは南部の白亜質の土壌に適し、ニレとトネリコは土地の境界用の垣根として各地で植えられ、イギリスの田園風景に彩りを添えている。 [井内 昇] 地誌
イギリスは政治的・経済的・文化的特性などの違いから、イングランド、ウェールズ、スコットランド、および北アイルランドの4地方に分けることができる。現在、人口をはじめ政治、経済、文化などの諸活動が圧倒的に集中するイングランドは、名実ともにイギリスを代表する地方である。ウェールズ、スコットランドの両地方は固有の文化をもつだけでなく、政治、経済の分野でも地方色が強い。北アイルランドは、ブリテン島の三つの地方に比べると、イギリスの一員となってまだ日が浅く、イギリスではやや異質な地方といえる。 [井内 昇] イングランドグレート・ブリテン島の主要部を占めるイングランドは、北部のペニン山脈と南西部のコーンウォール半島の低い山地を除けば、大部分が平野と丘陵とからなる。ロンドンを中心とする南東地方、ペニン山脈の南に広がるミッドランド地方、および北東地方には、イギリスを代表する大都市圏や工業地帯が発達している。一方、東部のアングリア地方や西部のランカシャー地方海岸部は、イギリスの主要な農牧業地帯となっている。 [井内 昇] 南東地方ロンドンを取り巻く南東地方は、イギリス第一の発展地域である。中心の大ロンドン県(1987年以降は大ロンドン)は第二次世界大戦後人口減少が続き、1991年には638万人にまで減り、その後700万人台まで回復し、2003年には約739万人であった。一方、南東地方全体の人口はなおも増えており、ロンドンの通勤圏であるロンドン・リージョンの人口は1200万を超え、イギリス最大の人口集中地域となっている。南東地方は温暖な気候や美しい風景に恵まれ、また、ヨーロッパ大陸にもっとも近いことから、第二次世界大戦後ここに多くの企業や各種機関、団体などが進出し、雇用の機会も豊富である。このため、仕事を求める若者や退職した老齢者などを引き付ける力が強い。 [井内 昇] ミッドランド地方ペニン山脈の南のミッドランド地方とよばれる一帯は、イギリス第一の工業地帯である。ミッドランドはさらに、バーミンガムを中心とするブラック・カントリー、ペニン山脈東側のヨークシャー地方、および西側のランカシャー地方に分けられる。ブラック・カントリーは豊富な石炭と鉄鉱石に恵まれ、19世紀後半から20世紀初めにかけて、鉄鋼業を中核とする重工業地帯として目覚ましい発展を遂げた。中心のバーミンガムはイギリス第二の都市で、ノッティンガム、コベントリーをはじめとする多数の工業都市が周りを取り巻いている。このバーミンガムを中心とする工業地帯では、最盛期に工場群の無数の煙突から吐き出される黒煙が昼夜空を覆い、建物は煤(すす)で黒く汚れたため、ブラック・カントリー(黒煙地方)とよばれるようになった。この地方の都市は相互に近接するものが多く、工業の発展に伴って、これら大小の都市群がつながって巨大な都市集団が出現した。このような都市集団を、イギリスでは「コナベーション」(連接都市)とよぶ。第二次世界大戦後、ミッドランドのコナベーションは、南の大ロンドン、北のマンチェスター‐リバプールの両コナベーションとも機能的に結び付き、ミッドランド地方から南東地方にかけて巨大な大都市連接地域が形成されてきた。ランカシャー、ヨークシャーの両繊維工業地帯は、ペニン山脈の東西山麓(さんろく)部に産業革命期につくりだされたが、それらの繊維工業都市の多くは山麓部の瀑布(ばくふ)線に沿って発達した。東側のヨークシャー地方は、元来、農牧業地帯であったが、中世末にフランドルの職人が毛織業を伝えて以来、羊毛工業が発達した。代表的な都市に、リーズ、ブラッドフォード、ハダーズフィールドなどがある。一方、西側のランカシャー地方は、オールダム、バーンリー、ロッチデール、ボールトンなどを中心に綿工業が発達した。最大都市マンチェスターは、19世紀には世界の綿業の中心となり、さらに20世紀にかけて商業都市として発展、現在はイングランド北半部の政治、経済、文化の中心となっている。マンチェスターとも運河で結ばれているマージー川はこの地方の舟運の動脈で、河口部のリバプールはかつて国際貿易港として栄えたが、現在ではもはや昔日のおもかげはない。 [井内 昇] 北東地方ヨークシャー地方の北に位置するタイン川沿いの一帯はタインサイドとよばれ、豊富な石炭や鉄鉱石に恵まれ、19世紀後半にミッドランドとともに鉄鋼業を中心とする大工業地帯になった。しかし、国内の大市場から遠いこの地方は、19世紀末から20世紀初めにかけて原料が枯渇し工場施設も老朽化すると、急速に斜陽化が進み、新たに発展地域となった南東地方へ労働力が流出した。政府は1930年代以降、この地方の産業振興に乗り出し、第二次世界大戦後はニューカッスルを中心に、電気、化学、機械などの近代工業を導入するなど、長期間にわたって援助を続けているが、不況は慢性化し、回復の兆しはみられない。 [井内 昇] イングランドの農牧業地域産業革命まで、イギリスでは農業は主要産業の地位にあったが、19世紀後半以降、海外農産物の輸入に依存するようになった。しかし、2003年時点でも農産物の国内自給率は70%台を維持している。イングランド東部の東アングリア地方、その西のフェンズ地域、およびその北に続くダーラムからウィルトシャーへかけての帯状の地域は、イギリス第一の農業地域で、東アングリアとフェンズでは耕作農業が、ダーラムから北にかけては牧畜と耕作農業を組み合わせた混合農業が卓越する。西部のランカシャー地方からその南のウェールズ山地にかけての、海岸寄りの平野部にも肥沃(ひよく)な土地が広がるが、ここではおもにウシ、ヒツジの飼育や、酪農が行われている。 [井内 昇] スコットランド大別して、南の低地スコットランドと北の高地スコットランドに二分されるが、平野部に乏しく、山地が卓越する。 [井内 昇] 低地スコットランド南寄りの低地はスコットランド最大の平野部で、高緯度のわりには気候が温暖なため、牧畜や果樹、野菜などの栽培を中心とした農業が行われている。東岸のエジンバラはスコットランド王国時代の首都で、現在もスコットランドの政治、文化の中心である。旧王国当時の城塞(じょうさい)や建造物をはじめ、文化的遺産に富み、美しい町並みはヨーロッパ一ともいわれる。近年、北郊に臨海工業地帯が発達している。西岸のグラスゴーはクライド川の河口部に発達したイギリス第三の産業都市で、第二次世界大戦前はイギリス造船業の中心であった。 [井内 昇] 高地スコットランドこの地方(ハイランドともいう)は、氷河作用で削られた険しい岩山と、その間に横たわる無数の谷やロッホとよばれる細長い湖、冷涼な気候のために乏しい植生などによって、荒々しい山水美がつくりだされている。海岸部の漁業のほか、一部で農業も行われるが、内陸部では牧羊を除けば産業とよべるものはみられない。限られた産物のなかで、ウイスキーやツイード織などは、ハイランドが生み出した国際的商品である。スコットランドが世界に知られているのは、このような荒々しい自然と、その自然のなかに根づくこの地方固有の民俗や特産品によるものである。 [井内 昇] ウェールズグレート・ブリテン島西部を占め、おもに山地からなる。人口は少なく、おもに海岸部に分布する。イングランドに統合されて久しいが、いまも一部にウェールズ語やケルトの風俗が残っている。山間部は農業に適さず、牧畜がおもな産業であるが、南の海岸部は良質の石炭を産し、ロンドンにも近いため鉄鋼業が発達した。中心都市カージフは、20世紀初めには世界第一の石炭積出し港をもっていた。山地は一般に低いが、地質的には古く、古生代の紀として有名な「カンブリア紀」の名は、このウェールズのカンブリア山塊からとったものである。 [井内 昇] 北アイルランドアイルランド島北東部の約6分の1を占める地域で、1922年以来、現連合王国の一部を構成する。おもな産業は農牧業と工業で、中央部の低地を中心に、ウシ、ブタ、家禽(かきん)などの飼育や酪農と耕作を行う混合経営がなされている。耕作農業の主要作物は大麦、オート麦、ジャガイモなどである。工業はベルファストとロンドンデリーの2都市に集中し、ベルファストでは造船やリネン製造、ロンドンデリーでは機械、化学、繊維などの諸工業が盛んである。ベルファストは北アイルランド第一の港湾をもち、政治、経済、文化の中心である。北アイルランドでは、3分の2を占めるプロテスタント系住民と、イギリスからの分離を求める少数派のカトリック系住民との間で流血の争いが続いていた。そのため二院制の議会をもっているが、イギリス政府による統治が続いていた。1998年紛争を終結させるための包括和平の合意がなり、1999年に北アイルランド自治政府が発足した。しかし、自治政府内の混乱などから2002年にはイギリス政府の直轄統治が復活した。以降、自治政府の機能は停止していたが、カトリック過激派の武装闘争終結宣言などをきっかけに、イギリス政府により自治政府再開が促され、2007年3月の議会選挙を経て、同年5月北アイルランドの自治政府が4年7か月ぶりに復活した。 [井内 昇] 歴史
[今井 宏] 政治・外交・防衛イギリス政治の特質イギリスでは立憲君主制のもとに議会政治が世界でもっとも早く発達し、現代においても安定した代表制民主主義が確立している。それゆえにこの国の政治は、世界諸国から議会政治の母国とかモデルとみなされることが多かった。こうしたイギリス政治の歴史的特質は、保持する価値ありとみなされる古くからの伝統的なものを保持しつつ、近代的なもの、民主的なものへの変容を革命的変動なしに漸進的に成し遂げたところにみいだされる。17世紀の王権をめぐる闘争の結果、王権に対する議会の優位性が確認された名誉革命(1688)以後のイギリス政治史は、まさしくそうであった。「人身保護法」(1679)や「権利章典」(1689)の制定に続き、漸次政治的対抗者への寛容が生じ、18世紀前半ウォルポール内閣時代(1721~1742)に議院内閣制が成立し、野党が市民権をもつに至り、トーリーとホイッグの二大貴族政党政治が確立した。19世紀には、産業革命に伴う社会経済的変動や政治参加を求める民衆的要求の増大に面して、政府と議会は一連の選挙制度改革をはじめもろもろの改革で対応しえた。その点で同時代のフランスと対照的である。 これらの改革はトーリー、ホイッグを前身とする保守党、自由党のもとに行われたのであるが、政治的民主化への改革は、20世紀に入って、1911年の議会法と、成年普通選挙権を導入した1918年と1928年の国民代表法によってほぼ完成した。1911年の議会法は、選挙で選ばれる代表からなる庶民院(下院)の、世襲制の貴族院(上院)に対する、法制定における優越的権限を確定したものである。漸進的民主化の方向への政治変容の歩みはその後も続き、保守・労働二大政党制期にも引き継がれた。第二次世界大戦後の労働党アトリー内閣のときにできた福祉国家・混合経済体制は、保守党にも受容された。1960年代から経済危機を背景にして「対決の政治」が「合意の政治」に変わる傾向が生じているが、元来「妥協の政治」とか「取引の政治」は、近代イギリス政治エリートの政治文化をなしていた。こうした政治文化が超党派外交や外交政策の連続性をも支え、内政上の諸改革をも可能にし、政治的安定の一つの条件となっているのである。 第二次世界大戦後イギリスの国力および国際的地位は著しく低下した。とりわけ1960年代から福祉国家・混合経済体制のもつ負の側面が表面化し、経済停滞と深刻な労働争議の英国病が生じた。財政も1976年には危機に陥った。歴代政府はその対応策に苦慮し続けたが、戦後体制を根本的に見直し、国を変革すると公約した「対決の政治」のサッチャー内閣(1979~1990)の下でイギリス病は克服された。サッチャリズムの社会・経済政策は保守党メージャー内閣(1990~1997)に、そしてまた、党規約から公有化を放棄した労働党のブレア内閣(1997~2007)にも引き継がれ、「合意の政治」がふたたび始まった。なお現代の政治体制の問題としては、福祉国家体制下に政策決定における行政府の権限がとみに増大して集権化が進行し、政府と圧力団体との協議の制度化も行われて、相対的に立法府(議会)の役割の低下という現象が生じている。したがって、分権化と議会政治の復権が今日におけるイギリス政治の問題点である。 [犬童一男] 政治制度憲法イギリス憲法は、単一の文書による成文憲法の形式をとらず、法令と慣習法および慣行からなる。その憲法上の規則は、議会立法や慣行を変更、廃止、創出したりする一般的合意によって変えられる性質のものである。この憲法によれば、イギリスの統治機関は、王国の最高の立法上の権威としての立法部、政府・各省庁・地方自治体・公的法人からなる行政部、そして司法部からなる。憲法上主権者は元首たる国王である。政府はいま「女王の政府」Her Majesty's Governmentであり、連合王国はその政府が女王の名において統治する。「影の内閣」たる野党も「女王の野党」Her Majesty's Oppositionとよばれている。司法部の長も国王である。しかし国王の役割は、首相から定期的に統治に関する報告を聞くこと、議会の開会および閉会や首相の任命にかかわること、新内閣の認証式など諸儀式への出席、外国訪問などに限られている。首相の任命は議会の意向に従うのが常である。かつて国王が有した政治的権限は、今日では首相や庶民院に代表される議会に移っている。国王はイングランド教会の俗事上の支配者でもあり、国家構造における尊厳的部分を代表している。 [犬童一男] 議会立法上の最高機関たる議会は、庶民院(下院)と貴族院(上院)からなる。選挙で成立してから解散するまでの議会は、下院の任期から最長5年で、1会期は1年である。1会期で出席を要する平均日数は、両院ともに158日である。議会の解散、総選挙の施行、新議会の召集は、国王が首相の助言を受けて王室宣言の形式で行われる。各会期の冒頭に両院では、政府の基本政策と立法計画からなる施政方針案が「国王演説」King's(Queen's) Speechの形で提案される。 [犬童一男] 庶民院この下院は、成年普通選挙制(18歳以上)下に小選挙区制で選ばれる650名の議員で構成される。任期は5年。議員は、総選挙のほかに、空席が生じたとき補欠選挙で選出される。議員には年俸のほか秘書手当、調査手当、交通費、生計手当などが支給される。下院の主要な機能は、第一に立法的機能である。19世紀の議会では議員法案が重要な位置を占めたが、今日ではイギリス政府の法律家たちが作成した政府法案の審議が主である。下院の時間の50%が立法に費やされるが、その大部分が政府法案に占められる。第二に、下院において主要政党は、内閣と影の内閣のチームをつくっているので、下院は政府の人材補充源としての機能をもっている。第三に、下院は法律の実施や行政の実情を調査する機能をもっている。下院の諸委員会も行政調査を行えるが、議員は1967年に設置されたオンブズマン(議会コミッショナー)に行政調査を求めることができる。第四に、下院は議会討論を通じて政治上の問題点について国民に教える機能をもっている。 [犬童一男] 貴族院この上院は聖職者議員と世俗議員からなる。前者はカンタベリーとヨークの大司教のほか、イングランド教会の24名の司教である。後者を1978年についてみると、1963年の貴族籍返上法で貴族籍を放棄しなかった世襲貴族男女約800名、1958年の終身貴族法で生まれた終身貴族(一代貴族)男女約300名、上院の司法的職務にかかわる法官20名余りから構成された。終身貴族は1968年から10年間におよそ2倍になった。議員総数は1981年で1168名に上ったが、会議への出席率は低く、平均して約290名であった。世襲議員の3分の1は年1回しか出席しない。上院議長は大法官であったが2006年より互選により選ばれている。貴族院は1911年議会法が制定されるまで、下院を通過した法案への拒否権をもっていた。この議会法のもとでも非金銭法案については、その成立を2年間遅延させる権限を有したが、1949年議会法によって1年間に短縮された。さらに終身貴族法と貴族籍返上法により、貴族院はしだいに保守党の牙城(がじょう)ではなくなった。1999年には労働党ブレア政権は公約していた貴族院の改革に着手、約800名の世襲貴族の議員を92名に縮小した。2011年3月時点で792議席。任期は終身。 [犬童一男] 内閣内閣は、初めは国王の諮問機関である枢密院から発生した国王補佐機関であったが、18世紀のウォルポール時代に首相職が生まれ、議院内閣制ができたことから今日のようなものになった。枢密院が有した権限の多くは内閣や各省に移った。内閣は通常、下院で議席の多数を占める政党指導部によって構成される。戦争とか国家的危機の際は挙国一致の連立内閣も組織された。内閣は20名余りの閣内相のほかに、小さな省担当閣外相や政務次官など約80名の中・下級大臣を従えており、これらのポストへの首相の任命権は大なるものである。議会を母体とする内閣は、各省庁官僚の協力を得て政府法案を作成するので、そこでは立法部と行政部の緊密な融合がなされる。立法過程における行政部の役割は、立法部のそれをしのぐと評価されている。首相は与党党首を兼ねて、議会を統御し、実質的な叙任権や下院解散権をも握っている。中央政府各省の官僚機構はホワイトホール・マシーンとよばれる。中央政府下の約50万の国家公務員は、各省に配属され、トップの行政管理者階級から下位の執行階級までの階層制をなしている。事務次官級以下の2500名のトップの階級に属する者が、政治的にたいせつな仕事を受け持っている。 [犬童一男] 司法制度イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドそれぞれで法制には相違点があるが、刑法と民法が明確に区別されていることをはじめ共通するものも多い。法源は、議会立法、命令や規則などによる立法と慣習法である。経済社会問題に関するもののなかには、欧州共同体法が適用される場合もある。司法制度をみると、刑事では、第一審の段階で小事件を扱う治安判事裁判所があり、その上の段階で、より重大な事件や治安判事裁からの控訴を扱うのが、巡回判事、高等法院判事が担当する陪審制の刑事裁判所Crown Courtである。そこからの控訴は控訴院刑事部が担当する。最終審は貴族院であったが、2009年10月に連合王国最高裁判所が設立され、刑事裁判および民事裁判の最終審となっている。民事では、第一審段階で婚姻、入籍などの問題が略式裁判所で扱われ、それ以外の問題は県裁判所County Courtで扱われる。略式裁からの控訴は高等法院家族部にいき、県裁判所および高等法院からの控訴は控訴院民事部にいく。最終審は前述のように貴族院から連合王国最高裁判所に移っている。なお、スコットランドの刑事の最終審は、スコットランド最高法院である。 [犬童一男] 地方制度1974年に地方自治体の大規模な再編成が行われた。この改革によって、大ロンドンを除くイングランドとウェールズで、従来の58県、1250市区町村は、53県countyとそのなかに含まれる369地区districtに整理統合された。おのおのが住民によって選ばれた議会をもつ独立した自治体である。県は広域にわたるプランニング、公道、交通規制、消防、警察、消費者保護などの行政を行い、地区は公園、住宅などのよりいっそう地域的な行政にあたる。首都には大ロンドン県議会の下に32の特別市会とシティのロンドン市会があり、大マンチェスターのような人口密度の高い六大都市県metropolitan countyでは、県議会の下に地区会があった。スコットランドでは9圏域の下に53地区会がおかれていた。国全体が二層制two tiersの地方自治であったのである。これが、1986年に大ロンドン県議会と六大都市議会が廃止され、そこは一層制となり、1996年からスコットランドやウェールズも同様に単一制地方自治に改められた。地方議員の任期は4年、選挙権はその地域に選挙人登録をした18歳以上の者、被選挙権はその地域に有権者として登録する等の要件を満たした18歳以上の者となっている。中央政府は地方自治体の諸事業に補助金を交付しており、地方の中央依存度は年々高まり、地方自治体歳入の半分以上を占める。自治体独自の主な歳入源は持ち家、賃貸を含む住居にかかるカウンシル税とよばれる税金である。 [犬童一男] 分権制議会地方分権devolutionの声が20世紀後半から高まり、とくにスコットランドとウェールズの民族主義がこれを促した。1979年に労働党政権下で行われた住民投票では、連合王国内の二つの圏域議会という分権制は成立しなかったが、分権制議会を公約して政権の座に上ったブレア内閣の下で、1997年9月スコットランドとウェールズでの住民投票referendumが行われ、ようやく実現することになった。その結果、限定された立法権をもつスコットランド議会Scottish parliamentがエジンバラに開設され、その下に政府のスコットランド省Scottish officeに変わる執行部executiveができ、マクロ経済、防衛、外交政策は従来どおりだが、教育、法、自治体などは執行部の管轄下におかれ、大幅な権限委譲となる。ウェストミンスターの議会にはこれまでどおり議席をもつ。しかし少数派のスコットランド民族党SNPはこうした変革に対して、連合王国からの分離・独立を究極の目標としている。 他方、ウェールズでは分権に対する住民投票の結果は、賛成投票が僅差(きんさ)のものであったが、ウェールズの言語と文化の伝統を守る西・南部の人々の支持が厚く、この分権制が成立し、カージフにウェールズ議会Welsh assemblyが設けられた。議会は立法権はもたないがその内容を審査する第二次的な重要性を帯び、これまでのウェールズ省Welsh officeを民主的に統御するようになったといえる。 スコットランド議会(129議席)とウェールズ議会(60議席)の議会選挙は1999年5月に行われ、6月に行政府が発足した。 [犬童一男] 政党政党は、議会と政府、地方自治体で重要な役割を演じている。政党なくして政治制度の発達はなかったといえる。今日の主要政党はほとんどが組織政党ないし国民政党とよばれるものである。 すでに19世紀後半、保守党および自由党は、労働者階級を支持基盤に取り入れた党になっていた。20世紀に自由党にかわった労働党は、中産階級をも基盤とする党に成長した。主要政党の公約はいずれも国民諸階層の支持を求めるものである。保守・労働二大政党制は、第二次世界大戦後の4分の1世紀にわたり安定度の高いものであった。両党の得票率の合計は1951年に96.8%をマークした。だが1974年に75%前後に急落、1979年にどうにか80%台に戻ったが、1983年に70%に下がった。1960年代以来の経済状態の悪化で二大政党離れが生じ、自由党に再生の兆しがみえ、民族主義党のスコットランド民族党とプライド・カムリが台頭した。1981年には、労働党離党者を主とした27名の下院議員を擁する社会民主党が結成され、自由党との中道連合が形成され、1989年に自由民主党Liberal Democratsとなる。この党が三大に入るが、小選挙区制のせいもあって二大政党制は崩れない。二大政党の一方に難があるときは、総選挙での票と議席は他方に移るからである。また選挙で敗れた党は政権復帰を目ざして努力するからである。二大政党の得票率の合計が、1987年に73%、1992年に76%、1997年に76%弱となったことがそれを示す。しかし昨今の多党化の時代に二大政党が、1950、1960年代のような高い得票率を占めることはもうないと読むことができる。2005年の総選挙では、労働党が議席の過半数を占め、史上初の3期連続で政権を担った。しかし、この選挙では労働党は大幅に議席を減らし、保守党と自由民主党がのばした。2010年の総選挙では保守党が第一党となった。しかし議席が過半数に届かず、自由民主党との連立政権を発足させた。 [犬童一男] 選挙下院議員選挙についてみよう。全国650の小選挙区で、各区から単純多数代表制first-past-the-post systemで1名ずつ選出される。この選挙制度は二大政党に有利な結果をもたらしてきた。選挙権は18歳以上のイギリス国民とイギリスに居住するイギリス連邦諸国民、アイルランド共和国民に与えられる。被選挙権も選挙権と同じであるが居住要件はない。軍務や商船員で投票できない者には代理投票か郵便投票、身体障害や仕事で当日投票できない者には郵便投票の制度がある。投票は義務制ではないが、投票率は概して高く、1945年から1997年の総選挙では71%を割ったことはなかった。選挙人名簿が毎年10月に確定するので、実質的にはもっと高い。しかし、2001年の総選挙では59.4%、2005年の総選挙では61.3%と低下している。供託金は500ポンドで、有効投票の5%以上得票しないと没収になる。法定選挙費は、1985年の選挙法で有権者が6万人の都市区で5110ポンドである。小選挙区制が導入された1885年の前の1883年に制定された腐敗違法行為防止法によって、選挙はしだいに浄化され、法定費用の枠内で行われるようになった。 [犬童一男] 圧力団体圧力団体には、社会のある部分の特殊利益追求型と、集団の特定の態度から発する目的追求型がある。両者とも中央および地方の政策決定過程で重要な位置を占める。前者の代表的なものが、大多数の労働組合が加盟するTUC(労働組合会議。2004年に69組合、640万人)と、あらゆる分野の大から小にわたる企業が加盟するCBI(イギリス産業連盟。約20万社)である。後者にはCND(核軍縮運動)がある。経済団体のような圧力団体は政権をとりうる政党と密接な関係があり、政党と区別しがたい面がある。労働党はその人材、資金をTUCや個々の労働組合に依存している。保守党はおもな財源は財界に仰いでいる。けれどもこれらの団体にしても政党とは独自に行動する機能をもっている。政府が変わっても、政策決定に際し、どの政府とも直接協議を行うようになっている。1950年代以降、年々500を超える政府の諮問委員会、審議会に圧力団体代表が参加している。1960年代から1970年代にTUCやCBIは政府の政策決定機構に組み込まれ、NEDC(国民経済発展会議)をはじめ多くの重要な政府機関に代表を出した。決定方式がトリパルティズムtripartismとかコーポラティズムcorporatismともよばれるが、サッチャー政権に始まる18年の保守党政権には引き継がれなかった。TUCはユニオン・パワー(労組権力)とよばれていた政治内影響力を著しくなくしたが、CBIや銀行、証券、保険等の業界を代表する非公式の圧力団体とされるシティの政権への影響力は増大した。こうした政府と圧力団体の関係は、労働党のブレア政権下でも踏襲された。 [犬童一男] 外交帝国保全と勢力均衡イギリス帝国は19世紀初頭までに形成されたが、そのころからこの国の外交の基調は、自国と海外領土および権益を守る帝国保全政策であり、ヨーロッパ大陸に対しては、イギリスの地位や権益を脅かす強国の出現を恐れ、同盟国をつくって介入する勢力均衡政策であった。19世紀中葉、どの国よりも早かった産業革命で「世界の工場」となったイギリスでは、帝国経営に消極的な小イギリス派も存在し、自由貿易主義が主流となったが、その政策も帝国保全政策と根本的に対立するものではなかった。列強が植民地を求めて争う帝国主義時代に入ると、この国は世界不況(1873~1896)下に失業、労働問題が生じ、その経済的優越の時代は過ぎ去った。そこでブーア戦争(1899~1902)に至る帝国主義政策が展開され、独立を求める民族運動は武力鎮圧された。スエズ運河はこの国の死活的権益とされた。アイルランド自治法案をめぐって1886年に自由党内閣が瓦解(がかい)し、1892年には同案が庶民院を通過したのに貴族院で拒否されたことは、帝国保全政策が深く浸透していたことを示す。 だが第一次世界大戦以来その政策は徐々に形を変えた。この戦争後イギリスは世界の軍事・経済大国ではなくなった。アイルランドが内戦ののち独立し、インド独立運動も進展した。自治領諸国の離反傾向も生じた。そうしたなかでイギリス帝国はイギリス連邦に変わり、1931年ウェストミンスター憲章で連邦諸国は対等の地位をもつに至った。第二次世界大戦後は単に連邦とよばれるようになるが、1930年代の大不況下に特恵関税制をもつ経済圏として編成され、戦後もEC(ヨーロッパ共同体)に入るまでは、イギリスの主たる経済圏であった。ヨーロッパ大陸に対する勢力均衡政策は、国力の低下が始まった19世紀後葉からいろいろな形でとられたが、強国ドイツの出現、アメリカの時代の到来などによるイギリスの国力の低下で破綻(はたん)した。 [犬童一男] 外交の現状第二次世界大戦後イギリスの国際的地位は低下した。国連安保理事会の常任理事会5か国には属するが、その影響力は米ロ仏中4大国と比較すると限られたものである。その広大な属領は、1947年のインド、パキスタンの独立に始まり、1960年代にイギリス領アフリカ全部が独立し、みる影もなくなった。独立した国は連邦に加盟している。軍事力はアメリカに依存するものとなった。1953年スエズ出兵の失敗は、イギリス、フランス両国の力の限界を露呈した。ロンドンは依然国際金融の重要な機能を営んでいるが、1960年代以来の経済状態の悪化は、この国の経済力の著しい低下を如実に示している。こうした状況下にイギリスは、軍備の縮小を図り、本国とヨーロッパに軍事的コミットメントを集中し、NATO(ナトー)(北大西洋条約機構)によって安全を守る政策をとってきた。そして経済面での苦境に対処すべくEC(EUの前身)加盟を選択した。だがこれには長い年月を要した。連邦かECかで国論が分かれたからである。1961年マクミラン内閣が加盟交渉を開始し、1973年1月1日ヒース内閣のときイギリスはECに加盟した。だがその後1975年、ウィルソン労働党内閣はEC加盟継続か否かを国民投票に付し、加盟が認められた。 イギリスはECで西ドイツ、フランス、イタリアと並ぶ有力な構成国であった。1980年代なかばに野党の労働党はEC加盟への関与を強めた。保守党政権はそれまで労働党よりもECに深くかかわっていたが、1990年代を迎えてECが通貨統合を含むさらなる政治経済統合に入る段階でこれに反対するヨーロッパ懐疑派とヨーロッパ派との対立に悩まされた。そうしたなかでイギリスは、統合(ECからEUへの進展)をさらに強めるマーストリヒト条約に、単一通貨と社会憲章を除くという条件で1991年末に調印し、1993年7月同条約は議会で批准された。1997年5月総選挙で18年ぶりに政権に返り咲いた労働党は、社会憲章Social Chapterの受け入れなどで保守党よりもEU寄りの外交政策をもっている。ECはマーストリヒト条約の成立で1993年11月からEU(ヨーロッパ連合)となったが、1979年から加盟国で直接選挙される任期5年の議員からなるヨーロッパ議会を有している。1994年の選挙では加盟15か国626名の議員のなかでイギリスの議員はフランス、イタリアと同数の87名であった。2004年5月、EUに新たにバルト三国、ポーランド、チェコなど10か国が加盟したため、ヨーロッパ議会も25か国787名と議員数が増えたが、イギリスの議員数はイタリアと同数の87名のままであった(フランスは86名)。2009年6月のヨーロッパ議会選挙では加盟27か国736名の議員のなかでイギリスの議員は72名となった。EUにおいて基本法となるヨーロッパ憲法条約承認の是非を問う国民投票について、イギリスは時期尚早との判断を示していた。さらに2005年にフランス、オランダでヨーロッパ憲法の採択が国民投票によって相次いで否決されたため、イギリスでの国民投票の実施は無期延期となっている。 ブレア労働党政権は、2001年9月のアメリカ同時多発テロ以降、アメリカが進める「対テロ戦争」を積極的に支援した。2003年には大量破壊兵器開発を理由にしたアメリカのイラク侵攻にも参加、戦争終結後もイラクに軍隊を駐留させていた。しかしそのため、2005年7月にはロンドンで同時テロが発生し、多くの死傷者を出した。 対外関係にあたる政府機関の責任を負うのは、外務・連邦省を率いる外務・連邦問題相である。国防関係は別として対外政策作成にあたるのはこの外務・連邦省であり、他省に関係ある問題については、同省が関係各省と協議して政策作成を行う。 [犬童一男] 防衛軍の最高指揮官は名目上国王であるが、実質的には首相および内閣が国防の責任を負う。首相は、国防相、外相、蔵相、内相ら閣僚からなる国防・対外政策委員会の議長であり、この機関で国防政策が決定される。その下に国防相が議長となる国防会議がある。国防政策作成は、国務相と陸海空軍担当の政務次官3名に補佐される国防相の責任であるが、国防会議には国防参謀総長、陸海空軍別参謀総長、国防事務次官、企画・研究審議官なども含まれる。三軍を管理するのは、国防会議の陸軍部会、海軍部会、空軍部会である。 第二次世界大戦後イギリスは米ソに次ぐ核戦力をもつ国となったが、軍事力で両超大国に引き離され、財政的困難さにもよってしだいに軍事的コミットメントの範囲を縮小した。1968年労働党政府は、スエズ以東のマレーシア、シンガポール、ペルシア湾から兵力を撤収してヨーロッパに防衛努力を集中することを決定した。1970年代後半には地中海からの兵力引き揚げもなされた。イギリスの国防政策の基本はNATOを中心とするものであり、同国は1990年代のNATOの戦略にミサイルを搭載したポラリス原子力潜水艦3隻、ドイツ駐留陸空軍などで寄与している。1990年代末にはポラリス原潜より有効な核抑止力を備えたミサイルをもつトライデント原潜が導入された。 防衛費をみると、防衛支出は労働党政府期に、1974~1975年のGNP比約5.5%から4.5%への漸減政策がとられた。次の保守党政府下に防衛力強化が図られ、1982年に5.2%を超えたが、1993年には3.1%となり、2003年には2.4%に低下している。その規模はNATO諸国ではアメリカに次ぐものである。兵力をみると、2004年には陸軍11万6800、海軍4万0600、空軍4万8500、合計20万5900と、1970年当時から20万近く減少し、2008年には総兵力約18万となっている。 [犬童一男] 経済・産業経済構造の特徴と変貌――第二次世界大戦前の概観貿易依存の構造イギリスは18世紀に世界で最初の工業国家として、世界経済のなかで圧倒的な生産力の優位をもった。その背景には、ランカシャー綿工業がジェニー紡績機の導入を契機として開始した産業革命があった。イギリス綿工業は原料綿花のほとんどをアメリカ南部およびインドからの輸入に依存し、総輸入額中綿花が20~30%を占めた。他方、綿糸・綿製品の輸出は総輸出額中40~50%を占め、輸出先は全世界に行き渡っていた。イギリス綿工業は「世界の工場」としてのイギリスの地位の基盤をなしたといえよう。また、製鉄業は、1840年代にヨーロッパおよびアメリカ向け鉄道資材輸出の形で輸出品となった。ともあれ資本主義確立期に、イギリスではすでに、貿易依存の産業構造ができあがっていたのである。 ところで、このような構造は、原料の外国依存により早くも貿易収支の恒常的赤字を生み出したが、他方で海運業の発達による運賃収入、貿易信用によるサービス収入、資本輸出による利子収入によって貿易外収支の大幅な黒字を生み、貿易収支の赤字をカバーすることとなったのである。 [内田勝敏] 世界経済における地位の低下ところで、19世紀末にドイツおよびアメリカ資本主義の集中・独占の傾向が進むなかで、イギリスでは独占の形成が著しく立ち後れた。世界に先駆けて産業革命を達成したイギリスは、先進工業国であっただけに、近代化を差し迫った課題としなかったという歴史的条件があったのである。とはいえ、イギリスにおいても大不況期(1873~1896)を通じて中心的産業に独占が現れてくる。すなわち、平炉法の普及に基づく鋼の大量生産と、それを中心とする造船業、兵器産業、重機工業部門が縦断的に結合するのである。また、支配の集中を目ざす株式会社形態の展開普及がみられるし、金融資本化が進んでいたのである。しかしながら、構造的な脆弱(ぜいじゃく)性は否みがたく、鉄鋼生産量ではすでに1890年代にアメリカ、ドイツに追い抜かれ、輸出市場においてもドイツに追い抜かれた。その結果イギリスは、食料、原料の大量輸入に加えて、ドイツ、アメリカから工業製品を輸入することとなったために、貿易赤字がさらに増加した。しかし、貿易決済中心地としてのロンドン金融市場は豊富な資金を集中しつつ繁栄するのである。それを支えたのは国際金本位制の展開であった。 さて、「世界の工場」としてのイギリスの地位の低下はその後も進む。まず、第一次世界大戦後の景気後退期において、綿業、石炭業、鉄鋼業、造船業などが生産、輸出ともに戦前水準を大きく下回り、停滞の様相を示した。さらに、1925年にデフレーション効果をもつ旧平価による金本位制復帰が行われた。このことはイギリス産業に負担をかけたものの、世界経済は国際金本位制が再建されたことにより相対的安定期に入り、1929年までは緩やかな拡大を続けた。この時期のイギリス産業を雇用数でみると、1929年までに旧産業の綿業、鉄鋼業、造船業の3部門の比重は低下したが、新産業の車両、化学工業、電機工業、レーヨン・絹工業の4部門は増大した。一方、世界輸出に占めるイギリスの比重は低下を続けた。とくに旧産業の輸出不振によって、経常国際収支の黒字は減少した。 [内田勝敏] 世界恐慌の影響1929年の世界恐慌は停滞に悩むイギリス経済に追い討ちをかけることとなった。世界恐慌は大量失業を引き起こした。また輸出の急激な減少を引き起こし、1929~1931年に38%減少した。他方、輸入はわずかしか減少しなかったから、貿易収支赤字が急増した。ロンドン金融市場は大量の対外短期信用を続け、国際収支の赤字の増大と財政赤字から、短期資金・金の大流出が生じ、ついに1931年9月に金本位制を放棄したのである。同時に、保護関税を導入、1932年にはオタワ経済会議によってイギリス帝国特恵関税制がとられた。その結果、輸出は地域別構成でイギリス帝国諸国の比重を高めつつ回復し、世界のブロック貿易の先駆けとなってゆく。一方、為替(かわせ)平衡勘定を設置することによって、短期資金の流出入に対するポンドの売りと買いでポンド相場を安定させつつ、ポンド通貨圏を形成していった。これはポンドの国際的信頼維持のためのものではあったが、これをきっかけにイギリスは世界的存在から、イギリス連邦という小宇宙に後退せざるをえなくなったのである。 この時期の産業の回復はどうだったか。綿工業は1936年の綿紡績法によって過剰紡績が買収されて合理化が進んだ。鉄鋼業は関税率の引上げによって保護されつつ再編成が進められ、造船業も再編・合理化が進められた。しかし石炭業はカルテルによる保護に終わった。他方、新産業の分野では、自動車、化学工業、電機工業への投資の増加がみられた。ともあれ、世界恐慌に対応してイギリス経済は福祉国家の方向を模索しつつ、イギリス連邦という限定された世界のなかで、保護関税に基づいて産業の再編成を図ったのである。 [内田勝敏] 第二次世界大戦後の経済――インフレと長期停滞第二次世界大戦はイギリス経済に巨大な消耗を強いた。海外資産の処分は48億ポンドに上り、対外債務の増加は28億ポンドを超えた。生産は低下し、輸出は戦前の約半分になって国際収支危機に陥ったのである。1945~1950年は労働党の政権下で、イングランド銀行、石炭業、鉄鋼業、通信、電力、運輸、ガスの国有化が行われ、社会保障の充実が図られた。一方、ポンドの国際的な地位が凋落(ちょうらく)し、1949年に30.5%切り下げられた。1951~1964年は保守党の政権下で、鉄鋼業の国有化が解除された。他方で国際収支が悪化し、インフレに悩まされた。この時期には、国際収支が悪化すると引締め政策をとり、国際収支がよくなると緩和する、というストップ・アンド・ゴー政策が繰り返されたために、投資が停滞し、成長が遅れた。1964~1970年はふたたび労働党政府となり、インフレ対策として賃金・物価の凍結を行ったが、国際収支の赤字は続き、1967年にポンドを14.3%切り下げた。1970~1974年は保守党政府のもとで、高度成長政策をとり、同時に法律に基づく所得政策をとったが、労使対立が激しくなった。1974年に労働党政府となり、「社会契約」によって労働組合との協調を目ざしつつ、主要産業の国有化を図って新たな経済の発展を図ったが、激しいインフレにみまわれた。1979年にサッチャー保守党政府ができて、これまでの経済政策を180度転回し、インフレ対策をもとに、長期的停滞からの脱却を図ろうとした。すなわち、公共支出を削減し、マネーサプライ(通貨供給量)を抑制し、民間経済活動に政府の介入を排除して、イギリス経済の活力をある程度回復した。 1997年5月に、労働党が18年ぶりに政権に復帰した。ブレア党首が首相となり、市場経済の原則を維持しつつも、保守党の行きすぎた競争至上主義を修正し、イギリス産業の競争力を強める方向を打ち出した。2007年ブレアの首相退任に伴い、前財務相のゴードン・ブラウンが労働党の後継党首に選出され、首相に就任した。ブラウンは新財務相に前貿易産業相のアリスター・ダーリングを任命した。 [内田勝敏] 経済の現況
[内田勝敏] 金融・財政金融、財政面では、第二次世界大戦後、完全雇用と福祉国家を目ざして、国家による有効需要の創出に基づいて基幹産業を再編してきた。その結果、国家財政と国有産業を含む公共部門の国民経済に占める比重が一段と高まった。1950年には国防費の急減もあって全政府支出の対GNP(国民総生産)比率は39%となっており、1930年代なかばの25%と比べるとかなり高まっていた。1958~1967年には積極的な成長政策をとり、公共部門の比重が大いに高まり、1968年には約50%に達した。1967~1970年の引締め策のあと、1971年以降ふたたび成長政策に転換し、公共部門の比重は一段と高まった。1975年には54.5%に達してピークとなり、財政赤字は深刻化した。福祉国家の維持と産業の再生とは両立しがたいのである。財政主導による有効需要の拡大に基づいて産業稼動率を上昇させて近代化を図ろうという政策は、ここにおいて転換せざるをえなくなった。それがスタグフレーションを生む元凶とみられたからである。1979年のサッチャー政権のもとで、財政面では公共支出の削減、通貨面ではマネタリズム(通貨供給重視政策)に転換した。それは公共支出の削減、マネーサプライの抑制、人為的介入の排除を基盤とし、具体的には、流通通貨と居住者銀行預金の増加率の目標を設定し、公共部門の借入需要(事実上の財政赤字)をコントロールすることとなった。公共部門の圧縮は住宅部門、教育部門、公務員の削減などが行われたが、他方で、不況に直面し失業率が増大した。財政面で企業のコスト負担の軽減や設備投資の促進などを求めて、1997年5月に労働党政府ができたが、財政赤字の削減の政策は続けられている。 [内田勝敏] 産業構造経済発展のある段階で製造工業の比率が低下しはじめ、第三次産業の比率が増大する傾向がある。これは、サービス経済化あるいは脱工業化の進行ととらえられることは周知のところだが、イギリスではこの現象がとくに顕著にみられる。就業人口の業種別構成をILO(国際労働機関)の『労働統計年鑑』によってみれば、製造業(鉱業、電気ガス、水道業、建設業などを含む)の比率は、1980年に26.6%であったが、1993年25.9%、2003年23.3%となった。一方、第三次産業(卸・小売業、運輸・通信業、金融・保険・不動産業、サービス業)は、1980年に54.7%であったが、1993年には70.8%、2003年には75.3%となっている。 イギリスの産業を立地からみれば、旧産業としてはランカシャーの繊維工業、ヨークシャーの毛織物工業、北部イングランドおよびウェールズの石炭業と鉄鋼業、グラスゴーの造船業があり、新興産業として南東イングランドの自動車工業、航空機工業、バーミンガムの重化学工業がある。 ところで、第二次世界大戦後のイギリス産業は、重化学工業を基軸として国家の手厚い保護を受けて再編成を展開してきた。石炭業、鉄鋼業は1945~1950年に国有化された。石炭業は、再建と機械化のためには大規模な投資が必要であり、そのための資金調達を国家によって行ったのである。鉄鋼業は他産業より独占が進んでおり、国有化は国有民営の形態で行われた。1951年に保守党政府のもとで鉄鋼業の国有化は解除された。1950年代後半から1960年代には成長政策がとられ、とくに1966年の産業再編成公社の設立によって、多くの産業が合併・集中を行った。鉄鋼業は1967年に、鉄鋼法に基づいて13社が鉄鋼公社に株式を譲渡してふたたび国有化された。自動車工業はこの段階で大手4社に集中し、造船業はゲッデイス委員会の勧告に基づいて数社に統合された。綿業は慢性的な不況産業となっていたが、1960年代にはドラスティックな設備処理と企業合同による近代化によって、四大グループへの集中が進んだ。また電機業界は、1968年のゼネラル・エレクトリックとイングリッシュ・エレクトリックの合併によって、西ヨーロッパ最大の電気機器企業ができた。重電機を中心としてコンピュータ、通信機、宇宙開発機器、原子力発電にまで及んでいる。 さらに1968年および1972年の産業拡大法は、いっそう大型の合同を促進し、収益性の高い製造業への公有を拡大した。自動車産業におけるレイランド・モーター社とブリティッシュ・モーター社の合同によるブリティッシュ・レイランド・モーター社の成立とその国有化は代表的な例である。1975年の産業法では、国有企業庁と主要産業との計画化協定によって、産業の近代化を図った。1977年には航空機宇宙産業および造船業で国有企業ができ、北海石油販売の国有企業もできた。ところが、イギリス産業の国際競争力は依然として再生しなかった。サッチャー政権は「小さな政府」の実現を目ざして、国有産業を徐々に民営に移してゆく政策へ転換した。まず、民営化の立法を次々と制定した。それに基づいて、航空機・宇宙開発業はブリティッシュ・エアロスペース、石油業はブリティッシュ・ペトロリアム、通信事業はケーブル・アンド・ワイヤレス、ブリティッシュ・テレコム、ガス事業はブリティッシュ・ガス、航空事業はブリティッシュ・エアウェイズ、自動車工業はローバー・グループへとそれぞれ民営化された。1988年には鉄鋼業のブリティッシュ・スティール・コーポレーションへの民営化が実現したのである。 [内田勝敏] 農業農業は、小麦、大麦、カラスムギ、ライムギ、ジャガイモ、サトウダイコンなどの農産物を生産している。2002年には穀類の自給率は109.0%、そのうちの小麦は120.5%となっており、その他の商品も自給率は上昇している。2003年も穀物自給率は99%とほぼ100%を維持している。また、総輸入額に占める食料輸入の比率が著しく減少している。これは、1960年代以後のイギリス農業政策が、経営規模拡大、離農促進、農場合併、共同化促進に基づく構造政策によって、農業保護を行っていることによる。 [内田勝敏] 交通鉄道は、1948年に国有化されたが、独立採算制のもとで合理化に努めてきた。イギリス国鉄の労働生産性は1960年代には年率5%で向上したが、1970年代に入ると10年間でわずかに5%しか伸びなかった。当時の列車の運行は、ブリティッシュ・レール(親会社)の管轄のもとで子会社3社(インター・シティ、ネットワーク・サウスイースト、リージョナル・レールウェイズ)によって行われていた。1992年4月の改革で、列車、設備管轄権の子会社への全面的移管によって合理化を進めた。さらに、1993年11月の民営化法案によって、施設、車両は国営保有の企業(レールトラック社)がリースし、民間事業が営業権をもって運行を行うこととなり、1994年にイギリス国鉄の民営化が実施された。ついで、1996年にはレールトラック社も民営化された。しかし民営化後、鉄道の重大事故が続発し、レールトラック社も倒産したため、2001年に戦略鉄道庁が設置されている。 航空輸送面では、超音速旅客機コンコルド(2003年10月運航終了)を含むスピード化と空港の拡張、整備が行われるなか、ヨーロッパ最強の航空会社といわれるブリティッシュ・エアウェイズ(英国航空)は、1981年に民営化され、合理化が進んでいる。 1994年5月6日に着工から約6年半の歳月をかけた英仏海峡(イギリス海峡)トンネルが開業した。事業費は100億ポンド(約1兆5800億円)であった。このトンネル建設はユーロトンネル社のプロジェクトで、同社の役員構成は、フランス人8名、イギリス人7名、ベルギー人、アメリカ人各1名で発足した。これによって、イギリスとヨーロッパ大陸は陸続きとなり、ヨーロッパ統合にとっても大きい意味をもつものとなったのである。 [内田勝敏] エネルギーエネルギー消費量は、1990年には、31.9%が石炭、35.7%が北海石油、24.5%が天然ガス、7.1%が原子力発電でまかなわれている。北海油田の開発により石油を輸入に頼らなくてよくなったことは国際収支に大きく寄与しているといえる。しかし、近年は油田の枯渇、環境問題などで政策転換を迫られており、エネルギー・気候変動省を創設し対応を図っている。2050年までにCO2を80%削減するとの目標を決めている。石油精製と石油化学には多国籍企業として著名なブリティッシュ・ペトロリアムがある。 [内田勝敏] 貿易世界貿易に占めるイギリスの比重は著しく低下してきている。世界輸出額に占める比率は1948年の11.5%から1975年には5.6%、1979年には6.0%、1995年には4.8%、2004年には4.0%となった。GNPに対する輸出額の比率は、1977年で29.2%、1995年では22.9%、2004年ではGDPの比率で16.9%である。貿易収支は入超傾向を続けており、貿易外収支の黒字でこれを補っている。2008年の輸出における品目別構成は、電気機器・同部品4.2%、道路走行車両9.1%、石油・石油製品12.1%、医薬品7.0%、原動機6.0%が上位を占めている。そのほか、鉄鋼製品、非鉄金属、金属製品の輸出が増加している。輸入では、電気機器・同部品4.3%、道路走行車両10.1%、石油・石油製品9.8%、通信機器等4.7%、衣料品3.9%となっている。最近は北海油田の産出量減少に伴い、石油の輸入が急増している。機械・輸送具については輸出入ともに活発になっており、水平分業が進んだものとみられる。 さて、貿易相手国では、イギリスはもともとイギリス連邦諸国をおもな相手国としていた。1955年では輸出の38.0%を占めていたが、しだいにその比重が減少してきて、1979年にはわずかに12.0%になった。他方で、EU(ヨーロッパ連合)がおもな貿易相手国となってきた。輸出では1955年に20.0%だったのが1980年には42.0%、1995年には58.5%、2004年には57.8%となった(2008年には56.4%)。輸入では1955年には18.0%、1980年に40.0%、1995年には58.5%、2004年には55.2%となっている(2008年は52.2%)。 [内田勝敏] EU加盟イギリスは1963年にEC(ヨーロッパ共同体)に加盟申請してから10年にわたる長い論争のすえに、1973年1月ECに加盟した。これは、停滞したイギリス産業を活性化するためにECに加盟し、競争を挑み、市場拡大を図ろうとしたものである。他方で伝統的なイギリス連邦との結び付きを断ち切り、貿易市場の方向転換を求めたものである。これまでのところでイギリスのEC加盟のバランスシートをみると、1979年までイギリスの対EC貿易収支の赤字が続き、赤字額もきわめて大きい。とくに赤字が大幅に増大した商品として食料があげられる。食料輸入が非ECからECへ転換されたことによる。1993年11月に、EU条約(マーストリヒト条約)が発効してECはEUとなり、1999年までに通貨統合を実現した。政府のEU社会憲章やEU通貨統合への対処を通じて、イギリスの方向が決められてゆく。2002年1月にEUの統一通貨ユーロが流通し始めたが、2011年4月時点でイギリスはユーロ導入に踏み切っていない。 [内田勝敏] 日英貿易日英貿易は1963年(昭和38)に日英通商航海条約が発効してから正常な貿易関係の土台のうえに発展することとなったが、イギリス側の輸入超過が続いている。とくに、1970年代に入ってからの不均衡が大きくて、貿易摩擦を引き起こしている。日英貿易における貿易商品の変化をみると、日本の対英輸出は1960年に機械類が9.5%だったのが1980年には69.7%に増大し、1960年に食料品が51.9%だったのが1980年には0.7%に著しく減じている。とくに車両の輸出が激増したために、1975年に自主規制が行われ、乗用車はイギリス市場の11%に抑えられることになった。さらに1982年からは小型商業車もシェアを11%に抑えることとなった。2008年(平成20)のおもな対英輸出品目は自動車14.0%、船舶6.6%、原動機6.0%、対英輸入品目は医薬品20.1%、有機化合物11.1%、原動機5.6%である。 [内田勝敏] 衰退するポンドイギリスの金融の中心はシティとよばれ、イングランド銀行を中心としたわずか1平方マイル(2.59平方キロメートル)の1区画にしかすぎないが、ここには、銀行、証券会社、株式取引所、各種の商品市場、海運・保険市場が密集している。19世紀後半、世界の金本位制度のもとで、ロンドンが国際金融市場の中心となり、イギリス通貨ポンドが国際通貨として比類のない力をもち、貿易決済に広く使用された。当時のポンドは取引通貨や準備通貨の諸機能をすべて果たしており、ロンドンは為替(かわせ)取引(ポンドの売買)の決済場所の役割をなすわけで、各国の銀行が為替取引の決済資金をポンド残高としてロンドンに集中して保有した。ロンドンは国際貸借の世界的中心として「世界の銀行」となったのである。しかし、第一次世界大戦後、国際収支は不均衡に陥り、1929年世界恐慌に際してポンドの弱体化が一気に現れた。1931年に金本位制の放棄を余儀なくされてポンドが変動相場制をとったとき、イギリス連邦を中心とする諸国がこれに追随して自国通貨をポンドに結び付け、通貨ブロックが自然発生的に形成された。後のスターリング(イギリス・ポンド)地域の原型がこれである。第二次世界大戦後、固定相場制に戻ったが、イギリスは厳しい為替管理制度によってスターリング地域を強化した。1949年9月ポンド切下げを行いつつも、通貨ブロックによってポンドの国際通貨としての地位回復を求めた。1958年12月にポンドの自由交換性が回復されたあと、1960年代にポンドは投機の波にさらされ、ポンドは危機に陥った。1967年11月に再度ポンドは切り下げられた。ポンド危機との関連で重要なものにポンド残高がある。ポンド残高とは、海外にあるイギリスのポンド債務であり、第二次世界大戦前には約6億ポンドであったが、戦時中の戦費調達のために増加し、戦後も増加して1970年には47億ポンドにも上った。このために、ポンド危機が起こると、ポンドが売られて危機をいっそう強めた。ポンド支援のためのバーゼル協定(1961)が結ばれたが、その後この協定は更新のたびにポンド残高を整理し、削減するための協定に変わっていった。すなわちポンド残高価値保証協定が1968年に結ばれた。しかし、1974年末にこの協定が廃止され、名実ともにスターリング地域は消滅したのである。すでに1973年1月イギリスはECに加盟していたのであるが、同年6月、スターリング地域に与えていた為替管理法上の居住者としての特権をなくする決定をしていたのである。さらに、1979年10月に為替管理法を全廃した。ポンドの衰退は事実であるが、ロンドンはポンドのかわりにドルを使用し、ユーロ・ダラー市場の中心となって国際金融の中心としての地位を守っている。 [内田勝敏] 資本輸出資本輸出もまた第二次世界大戦後著しい変貌(へんぼう)を遂げた。もともと19世紀後半から第一次世界大戦までは最高の爛熟(らんじゅく)した状態に達したが、第一次世界大戦前に資本輸出が貿易促進的な役割を失った。1930年代の恐慌克服過程において資本輸出の余力をもしだいに失ってきて、地理的分布をもっぱらイギリス帝国に集中してきた。その内容も原料、資源開発に集中し、また国公債投資に偏ったのであった。 第二次世界大戦後いったんはスターリング地域向け投資が主となったが、その後スターリング地域の解体、EU加盟などの諸条件に基づいて、資本輸出のあり方が大きく変わった。第一に、第二次世界大戦によって海外投資残高のほぼ4分の1余りを失ったが、1960年代後半から海外投資が急速に増加し、その約7割が直接投資によって占められるに至った。これは多国籍企業の発展への対応とみられる。資本輸出の源泉は、巨大企業の成長した金融余力やユーロ・ダラー市場での資金調達や利潤再投資によるものである。第二に、イギリスの資本輸出(直接投資)地域は、スターリング地域の比重が減少して、アメリカ、EU向けが急速に増加した。他方で資本輸入地域はアメリカ、スイス、カナダ、オランダの順となっている。このような先進諸国間の海外投資の相互交流の増大は、1960年代以降の世界の資本輸出の特徴であり、これが多国籍企業の形態をとって世界的に活動領域を広げているのである。第三に、イギリス資本輸出の産業別構造をみてみよう。もともと鉄道、鉱業、農業投資が中心であった。1914年では鉄道投資が77.4%を占めていたほどである。ところが1960年代以降は製造工業投資が増大し、技術集約度の高い部門に移っている。 [内田勝敏] 社会イギリス社会構造の特質異なる民族・人種や、生活様式および価値観で相異なる階級が存在するが、社会の分裂をきたすことなく共存し、調和した社会を形づくっているところにイギリス社会構造の特質がある。社会的相違性は、民族・人種および階級のみならず、イングランドの北部と南部に浮き彫りにされるような地域や、宗教・宗派にもみいだされる。そのようなものが、イギリス人の多数が共有するものの見方とか態度などに示される国民的カルチュアの下位にある、さまざまな下位カルチュアをもつ社会を構成しているのである。連合王国を構成する四つの国の民族のカルチュアと、労働者階級と中流階級のカルチュアは、その代表的なものである。イギリスの北アイルランドを除く部分が比較的よく統合されているのは、これらの下位カルチュアをもつ集団が、自己保存的なものとして存在して、他と共存し、国の諸制度に従ってきたからである。これは、かつて敬譲的国民とよばれたこの国の民衆が、今日でも有する国制や政治的権威への忠誠心の高さに示されている。また18世紀後期からの革命の時代に、この国が一度も革命の脅威に直面したことがなかったことにも表れている。 イギリス社会が世界諸国のなかでもきわめてユニークなこのような特質を有するのは、その歴史的条件と地理的ないし地政学的条件によるところが大きいとみられる。すなわち、国民国家の統一が14世紀から進展し、その後ウェールズやスコットランドを併合してイングランド化を図り、産業革命後には、新たに台頭した二大階級を次々に体制内化し、諸改革によって社会的危機を回避した漸進的で温和な社会の発展があった。つまり、社会諸集団が対抗しつつ共存できたのである。次に地理的条件として、国民国家形成後に外敵の侵略を被らずにすんだ島国の有利さや、資本主義経済が発達するうえで必要な諸資源にも恵まれていたことがあげられる。また他都市と比べてずばぬけて大きく、人口の8分の1を占める首都ロンドンとその周辺に、連合王国の政治、経済、教育、科学、文化、マスコミなどほとんどあらゆるものの中枢があることも、ウェールズやスコットランドのイングランド化に役だっているとみられる。ただし以上のことは、プロテスタントとカトリックの宗教的対立と重なって社会が二つに分裂している北アイルランドには当てはまらない。そこではイングランド化は成功しなかった。 なおイギリスの社会には、古くからの伝統的なものを残存させながら、時代とともにゆっくりと変容しつつある面が認められる。それはスコットランドやウェールズにおける分権化を求める運動にみられる。イングランド化の修正であり、より民族的なものを表出していこうという動きである。また労働者階級カルチュアというものも根強く残ってはいるが、スラムに代表される伝統的なコミュニティが減少したことや、生活水準が向上したことなどから、ひところのようではなくいくらか希釈したものに変わった。これは、労働者階級と労働党の結び付きが弱まり、選挙のときに保守党や自由党などに投票する者が増えたところにも表れている。 [犬童一男] 住民民族・言語イギリスの住民は多民族からなる。その国は多民族国である。住民と言語でもっとも主要なものはイングランドのイギリス人と英語である。英語は、14世紀にイギリスがヨーロッパ大陸やローマ法王からの独立性を明らかにしたころから、国語として重要性をもつようになった。併合されたウェールズ、スコットランド、アイルランドにおいても公用語とされただけでなく、教会や商工業の世界などでも使用され普及した。英語以外の言語としてウェールズ語、スコットランド語、アイルランド語がある。いずれも同じ印欧語系のケルト語系に属し、ウェールズ語はイギリス・ケルト語、スコットランド語はスコットランド・ゲール語、アイルランド語はアイルランド・ゲール語である。 ウェールズ語は1891年に53%のウェールズ人が話していたが、1991年には19%に減少した。しかし北西部の田舎(いなか)ではこの言語が広く使用されている。公的団体として「ウェールズ語協会」もあり、この言語は、1967年のウェールズ語法で、公用語として英語と対等なものと認められた。スコットランドでもケルト語系のゲール語を話せる人は少なくなり、20世紀末期にはヘブリディーズ諸島に暮らす人々の多くを含む約7万人という。人口の1.4%である。北アイルランドでアイルランド語を話せる人はきわめて少ない。イングランド南東部コーンウォール半島には、ケルト語系コーンウォール語が存在したが、もはや生きた言語ではなくなった。ロンドンやその他の大都市にアジア人コミュニティをつくっている人種的少数民族は、英語のほかにパンジャーブ語、グジャラート語、ベンガル語のような言語をもっている。 [犬童一男] 人口国勢調査は1801年以来10年ごとに行われているが、それ以前のグレート・ブリテンの人口は、11世紀末に200万、17世紀末に650万と見積もられている。1801年には1050万であった。産業革命以前に人口増加がきわめて緩やかだったのは高死亡率、とくに幼児死亡率、死産率の高さによるとみられる。19世紀に入ってから人口増加のテンポは速まって、20世紀初頭に3700万になり1971年に5500万を超えた。死亡率を上回る出生率の高さ、とくに幼児死亡率、死産率の著しい減少と平均余命の伸びが、これを促した。1歳未満の幼児死亡率は1000人につき、1901年の142から2002年には5.2に下がった。全体的死亡率はこの同じ年度に1000人につき18から10.2となった。平均余命は1901年に男49歳、女52歳から2003年に男76歳、女81歳、2008年には男77.2歳、女81.7歳に延びた。 人口統計上の動向で注目されることは、まず1975年からみられる出産率の低下によって人口増加率が停滞的になったことである。次に、老齢化社会の人口構造になったことがあげられる。連合王国全体の統計によれば、男65歳以上、女60歳以上の老齢人口は、1951年の13.5%から1999年には17.4%にまで増えた。統計上のデータ分析からみると、人口は漸増していき、第二次世界大戦後のベビーブーム世代が消える2025年から人口は減少していくとみられていたが、2008年時点の国連の予測では2050年には7237万とされている。また、人口全体のなかに占める男と女の比率が1990年代には100対104になっていることも注目される。2001年の総人口では女が男より、163万人多い。出生時は男のほうが5%多いのだが、どの年齢層でも死亡率が高く、50歳で逆転するためである。過労死もあるかもしれない。なお人口は、大ロンドンをはじめとする大都市への高度な集中を示す分布型をなしている。 入国移住者と他国移住者も毎年相当数に上るが、差し引きして、1901~1979年に200万人以上(人口の4%)を失った。入国移住者についてみると、1930年代にはヨーロッパ大陸から25万人の政治的亡命者の移住があった。第二次世界大戦後には東ヨーロッパ諸国からの移住者が目だったが、1950年代なかばからはイギリス連邦諸国などからの有色移民が増大した。西インド諸島、インド、パキスタン、ウガンダ、ケニアなどからである。彼らはイギリス各地に非白人コミュニティをつくっており、1978年に全国で190万人(人口の3.5%)、1991年に318万(5.5%)、2001年に464万(7.9%)を占めている。政府は、こうした有色移民をめぐって移住制限措置をとる一方、移住した者については、雇用や住居などに関する差別を阻止するために1965年に人種関係法を制定、その後も数度の改正、再制定が行われている。 [犬童一男] 階級と社会階層19世紀中葉、ベンジャミン・ディズレーリは「二つの国民」が存在するとみて国民統合の必要性を説いた。産業革命が富者と貧者間の富の不均衡を著しくし、都市生活で階級の地理的分離をもたらしたので、階級社会の様相は歴然であった。だがこの時代ですら中流階級と労働者階級は、それぞれ階層分化しつつあった。 [犬童一男] 職業による階級イギリスにおける階級規定で一般的なものは、職業に基づくものである。階級を決定する要因としての生活様式、生活水準、社会的慣習、価値観および態度の相違が、共通性をもつ職業に基づく集団にみいだされるからである。この規定によると、世襲財産で暮らせる貴族的上流階級は一握りにすぎず、知的専門職や政府、企業などの管理者からなる上層中流階級が社会的に重要な位置を占める。その下のランクに中層中流階級がより多く存在し、並のホワイトカラーの職についているのが、中流階級の半分にあたる下層中流階級である。労働者階級といえば筋肉労働者をさし、それは熟練、半熟練、未熟練の区分けで上、中、下の3層に分けられる。20世紀のイギリスの階級構成の変化をみると、産業構造上の変化から、管理的専門職業人やホワイトカラーは増大しているが、労働者階級はどの層も減少する傾向にある。 [犬童一男] 階級帰属意識階級への同質化を示すものとして、イギリスでは他国と比較して階級間の社会移動が少なく、人々は多くの場合、親と同様な職業につくことがあげられる。労働者階級の家に生まれた者は、自分の親と同様な職を求め、結婚してもどちらかの親との同居か近隣に住み、労働者階級クラブやパブを社交の場とし、血縁、地縁を通じて階級としての特徴を表す生活様式、慣習、価値観、ことばのアクセントを保持するといわれる。中流階級にもこれに対応するものがある。住宅パターンも階級への同質化に関係がある。第二次世界大戦後スラムが浄化されて高層公営住宅にかわり、公営住宅戸数は1976年に全住宅戸数の32%を占め、その5分の4が労働者階級入居者で、持ち家戸数は全体の53%を占め中流階級の多くが持ち家に住んでいた。これが1980年代の公営住宅居住者に払い下げる国の持ち家助長政策で、1990年になると公営住宅戸数は24%、持ち家戸数は67%となった。さまざまな社会調査によれば、労働者階級でも持ち家居住者は階級帰属意識が薄く、中流階級帰属意識をもつ者も少なくない。 階級の存在が政治の世界でよく反映するのが、ともに階級の党とみられていた労働党と保守党への選挙民の選好である。1950年代には、労働者階級の6割が労働党に、中流階級の8割が保守党に投票していた。また労働者階級の3割が保守党に、中流階級の2割が労働党に投票していた。これが1970年には、労働者階級の5割と中流階級の3割が労働党に、前者の4割と後者の3分の2が保守党に投票するようになった。選挙民の選好は変わりつつあるとはいえ、階級と政党は深い関係にある。イングランド北部および北西部は労働党、南部は保守党という政治地図も、階級との関連なしには描けないものである。 しかし、こうした階級的同質性や階級と政党の連関性は、生活水準の向上、生活様式の変化、教育を受ける機会の増大、社会的上方移動の傾向などと相まってしだいに弱まった。それはなによりもまず豊かな社会の労働者階級のブルジョア化、中流階級意識にみいだされる。労働党が敗れた1979年総選挙についてみれば、投票者の53%だけが彼らの本来の階級政党に投票したにすぎない。これは1970年に60%、1964年に65%であった。熟練労働者票は労働党対保守・自由両党で1970年に1.3対1であったが、1979年には0.8対1となった。労働党は労働者階級に見捨てられて敗れたと分析される。伝統的な階級帰属意識が崩れつつあるのであり、1970年代初めまでに、労働者階級各層で自分を中流階級に属するとみる者が増え、労働者階級とみる者は減っていた。また国民の多くが、階級なる概念で自らを位置づけていない、階級帰属意識の希薄な存在でしかないのである。 [犬童一男] 教育イギリスの階級制は教育制度と密接な関係をもっている。教育による国民の分類は、職業による分類と重なり合う。労働者階級は普通義務教育だけで、16歳後も学校に残る者はホワイトカラーや専門職につく中流階級である。官公庁、政・実業界などのエリートは、私立のパブリック・スクールや大学を出た中流階級出身で占められる。国の義務教育制度ができたのは1870年であった。1944年の教育改革で義務教育は14歳から15歳に、中等教育レベルまで延ばされた。さらに1973年に16歳(5~16歳)に改正された。公立中学校には進学向きのグラマー・スクールとそうでないテクニカル・スクール、モダン・スクールの3種類があり、生徒は従来11歳になるとイレブン・プラスeleven plusとよばれる試験でより分けられて進学していた。中等教育は18歳までで、16歳までの学校は、16歳以上の生徒のための課程シックスス・フォームsixth formをもっている。イレブン・プラス試験の上位者がグラマー・スクールに、次のレベルがテクニカル・スクールに進み、全体の3分の2にあたる残りがモダン・スクールに進むようになっていた。グラマー・スクールに入る多数の家庭は中流階級だが、モダン・スクールでは大部分が労働者階級である。 こうした教育上の不平等を是正すべく労働党政府は、総合中学校comprehensive schoolへの切り替えを1960年代から図った。従来の三本立て制を総合したものに改革したのである。その改革は進み、1980年にイングランドとウェールズでは、公立中学校の8割の生徒が総合中学校で教育を受けるようになった。スコットランドでは総合中学校化が完成した。イレブン・プラスのより分けはもうなくなった。公立中学校のほかにパブリック・スクールをはじめとする私立学校がある。中等教育を終えるとき16歳から施行されるのが、学外試験GCE(General Certification of Education普通教育修了資格試験)である。GCEにはOレベルとAレベルがあり、前者は16歳で、後者は18歳でとれるのが普通である。Aレベル合格者は大学入学資格を得ることになる。Oレベル合格者は中流階級の職業につく資格を得ることになる。大学は1945年に17しかなかったが、2002年に89になった。高等教育機関の規模は1960年以来3倍以上に拡大し、その学生数は1960年代に18~19歳人口の15人に1人だったのが、1979年に8人に1人、1990年に5人に1人となった。労働者階級や下層中流階級の家庭に育った者で高等教育を受ける者はきわめて少ないが、国の奨学金制度の恩恵に浴して大学に入る者は増えている。 [犬童一男] 宗教イギリスでは16世紀に教会がローマ・カトリックから独立して、国王を教会の首長とする国教会となった。イングランドの国教会はイギリス国教会の監督教会派で、スコットランドの国教会は長老派教会である。ウェールズでは、住民はほとんどがプロテスタントであっても監督教会派でなく、1920年に監督教会派の国教会はその地位を喪失した。グレート・ブリテンではイングランド教会と国家権力は、相互に補強しあって住民を治めてきたのである。北アイルランドでは国教会とカトリック教会が険しく対立している。国教会の牧師は軍、国立病院、監獄にもかかわっていて、国から給料を支払われている。主権者(国王)は国教会員で、大主教、司教、首席牧師は国王に任命される。イングランドでは人口の6割近くがイングランド教会で洗礼を受け、2割弱が確たる信者である。スコットランド国教会の成人教会員は約70万である。 今日プロテスタントのノンコンフォーミスト(非国教徒)教会にあたるのが、イングランド、ウェールズの自由教会とその他の教会である。しかし19世紀の非国教徒のごとき政治参加はない。自由教会のなかでもっとも大きなのがメソジスト教会で成人信者40万8000、次に組合教会とイングランド長老教会が合併した10万3000の統一改革教会、信者14万6200というバプティスト教会がある。そのほか絶対平和主義のクェーカー教徒や救世軍がある。なおローマ・カトリック教会は19世紀に復活し、今日連合王国に子供を含めて約500万の信者がいる。 [犬童一男] 社会福祉福祉国家イギリスの社会福祉制度は、国民保健サービス、社会保障制度、個人的社会サービスの三本立てである。国民保健と社会保障は、第二次世界大戦中の「ビバリッジ報告」に基づくものである。国民保健サービスは、イギリス居住者が無料か低料金で医療を受けられることを原則としている。これが始まった1948年以来、幼児死亡率が半減し、結核、ジフテリア、小児麻痺(まひ)による死亡が急減した。現在有料なのは、処方箋(しょほうせん)、義歯および歯科治療、眼鏡、個室入院などである。ただし、低所得者や年少者などには眼鏡、歯科治療、処方箋なども無料である。産婦の歯科治療も無料である。社会保障制度は、国民が基礎的生活水準を維持できるように意図され、国民保険、労災保険、児童手当、生活扶助手当などからなる。1960年代から1970年代に、収入にスライドした国民年金制になり、それは退職年金、寡婦年金、求職者(失業)手当、疾病手当、出産手当に適用されている。失業手当の給付額は2003年現在で、18歳未満の者が週32ポンド90ペンス、18歳から24歳の者が43ポンド25ペンス、25歳以上の者が54ポンド65ペンスで、給付期間は最大182日となっている。 地方自治体の責任で行われるのが、個人的社会サービスである。自発的ボランティア団体もこれに協力している。この事業の大部分は、世話を必要とする老人や身障者のための保健サービスである。孤児や精神的な障害者を救助することもある。身障者には生活上の問題で助言したり、電話やテレビの取付け、旅行や遠足の段取りをしたりする。仕事につくための訓練・教育の世話もする。老人対策は、できるだけ長く自宅に住めるよう配慮され、食事の配達、身の回りの世話、洗濯サービスなどが行われている。 福祉国家イギリスで最近深刻な問題となりつつあるのが、失業と貧困である。1960年代までは完全雇用に近かったが、1976年に133万(5.7%)となったときから大量失業は克服しがたい慢性のものとなった。1981~1987年は300万前後が続き10~23%の高い失業率であった。その後1988~1992年に一桁(けた)に下がるが、6%を割り160万以下にはめったにならない。1993年からは同年の10%から漸減して1997年は6%程度になった。2007年の失業者数は165万人、失業率は5.4%となっている。こうした高水準の失業が長期化するなかで貧困がこの国の大きな問題となっている。「貧困線(ボーダーライン)」とされる生活扶助手当(単身者で週26ポンド45ペンス、夫婦で69ポンド)以下で暮らす家庭が130万、同ライン線上とそれより上の20%以内の収入の家庭が180万もあり、1987年には人口の17%を占める800万人が貧困層をなしていることがわかった。国民のおよそ7人に1人が貧困状態にあるのである。 [犬童一男] 文化イギリス思想・文化の伝統と特質イギリス人が単一民族による簡単な構成でなく、もともとグレート・ブリテン島に先住したケルト系、ドイツから侵入してきたゲルマン系、さらにその後移住してきたラテン系というように、雑多な民族の混成であるから当然なことであるが、彼らの国民性、思想、文化もまた単一明晰(めいせき)なものではなく、複雑多様なものである。 また地理的にみても、北からの寒流と南からの暖流とがあわさり、イギリス名物の霧を生み出しているわけだが、イギリス人の精神にも濃い霧がかかっていると考えられる。物事をはっきりと、くっきりと認識し理解するのではなく、もやを通して屈折して受け取る習慣がついてしまった。 初めからできあがっている理論や思想体系に従って割り切る、という考え方に、彼らはいつも疑惑を抱く。自分の目で、経験によって、何度も何度も確かめ、自分自身の肌で納得がいったときに、初めて確信をもつ。イギリスの哲学が観念論を退けて、経験論を重んずるのも無理からぬことであった。しかも、性急に二つに一つの決着をつけるのではなく、そのどちらをもとり、両者の間にバランスを保ち、融合を図るという、しなやかで、しかししぶとい思考を身につけたのも、相矛盾する二つの要素に挟まれて生きなければならなかったイギリス人の宿命から得た処世上の知恵であった。 中庸の美徳というものが、イギリス人の生活感情のなかに深くしみ着いてしまっている。16世紀ヨーロッパを襲った宗教改革の嵐(あらし)のさなかでもイギリスは、形のうえではプロテスタントを選びながら、内容や祭式のうえでは古いカトリックを切り捨てずに中間の道をとった。「中道」(ビア・メディア)というのがイングランド教会の基本的精神である。このような聖なる問題からずっと下って、日常の俗なる次元に話題を移すと、イギリス庶民の多くは、さまざまな刻みたばこを適度に混ぜたミディアムをパイプに詰めてふかし、2種類の酒を混ぜた「ハーフ・アンド・ハーフ」をパブで注文し、ビーフステーキもミディアムに焼くよう命ずる。 このようなイギリス人独特の二元性を、以下具体的な実例によって示そう。 [小池 滋] 国民性イギリス人気質といえば、すぐ連想するものにスポーツ愛好とユーモアがある。 彼らがスポーツを好むのは、それがあくまであるルールのもとで行われるゲーム(遊び)だからである。ルールが法や掟(おきて)と違うのは、法や掟があらゆる場合に通用する絶対の権威をもっているのに反して、ルールはある一定の約束ごとのもとでしか通用しない点である。殺人や盗みはいかなる場合でも禁じられるが、ボールを手で持っていけないのはサッカーのときだけだ。だから、ゲームの間はむきになるが、ゲームが終われば禁止条項も、罰則も、いや相手に対する敵意すらが消えてしまう。 彼らが人生をゲームとして考えるのは、唯一絶対の権威をうさんくさいものとして嫌い、すべてを相対的に眺めたいからである。なりふりかまわず、まなじりを決して、ある一方向に突進するのは、ゲームとして実に下手なやり方であることを知っているから、人生においても絶えずルールを忘れず、いかに上手にプレーするかを念頭に置く。自分も他人も等しく距離を置いて眺め、客観化することができるのは、それをゲームと考えることができればこそである。 同じことがユーモアについてもいえる。ユーモアとは、自分をも他人と同じくわきから眺めて、そのおかしさを笑うことのできる能力あるいは感覚である。他人だけを一方的に笑う人、自分が他人の目にどう映るだろうかと冷静に考えることのできない人は、ユーモアに欠けるといわざるをえない。自分を高い地位に置いて他人を見下して笑ったり、自分をわざと卑下しておせじ笑いするのではなく、自分と他者を同じ高さに置き、しかも相手に思いやりをかけて笑うときにこそ、真のユーモアが生まれ、そのときこそ笑いが人間の心を結び付ける固いきずなとなりうる。 真の意味でのスポーツ(ゲーム)にもユーモアにも共通している特質は、それがなにかほかの目的のための手段でなく、それ自身を目的とする純粋の行為、無償の行為であるという点だ。ここにイギリス人独特のアマチュアリズムの精神が生まれ、彼らの多様な趣味の世界が広がる。はたの人間からみれば、子供じみたばからしい遊びに思えること、たとえば、小さな球ころがしや、役にもたたぬがらくたのコレクションに目の色を変えているのも、働き中毒になるのを防ぐ安全弁である。パンを得るため、生活するために必要切実な手段である実社会の仕事だけに目の色を変えて、それだけを生きがいとしていちずに突進するよりも、実際の利害と無関係な子供じみた行為にふけるほうが、はるかに危険が少ないことを知っているのである。 このような仕事と遊びの使い分けは、イギリス人の公生活と私生活の演じ分けにつながる。「イギリス人の家庭は城である」とよくいわれるように、彼らは自分の私生活、プライバシーをかたくなに守り、また、外界に対して閉鎖的な態度を示し、胸の奥底を容易に他人に明かさない。他国民がイギリス人に対して疑心暗鬼となり、不可解だと首をひねるのは、これが原因である。 よく外国旅行をした日本人が、「列車の中で向かい合って同席したアメリカ人やフランス人やイタリア人とは、すぐ仲良しになり打ち解け合えるのに、イギリス人は数時間たっても一言も口をきかず、にこりともしない」といって苦情をこぼす。しかし、J・B・プリーストリーという生粋(きっすい)のイギリス人の弁論に耳を傾けよう。イギリス人は決して人づきあいが悪いのではない。人間は四六時中愛想よくしているわけにはいかないのだから、外づらの悪いイギリス人は、家庭内や親しい友同士では実に温かい人間なのだ。見知らぬ人に愛嬌(あいきょう)を振りまく人間は、親密な温かい家庭をつくることができないのではないか。 [小池 滋] 芸術イギリスの芸術こそ、まさにイギリス人のもつ二元性がもっとも顕著に表れた一例である。シェークスピアという世界に誇る異才を生み出したイギリスの文学について、まずこれを考えてみよう。 北欧やゲルマンの神話には、暗い運命に対して勝ち目のない戦いを挑む人間の雄々しい悲劇的な姿を描いたものが多い。リア王やマクベスやハムレットの世界は、これを如実に示したものだが、シェークスピアはこれと同時に、明るい楽天的な、生きる喜びを謳歌(おうか)するラテン文学の陽光を取り入れることもできた。『真夏の夜の夢』の世界がまさにそうであるし、『ロメオとジュリエット』の世界は、悲劇的ではあるが、若さと情熱に満ちあふれた地中海文化を思わせ、霧と人生の不条理のカーテンに閉ざされた北欧の暗い空を連想させるものではない。 ゲルマンとラテンの人生観、世界観の混合のなかから、シェークスピア独特のユーモアが生まれる。行為は不道徳だが人間味の大らかさで観客を魅了するサー・ジョン・フォルスタッフ(『ヘンリー4世』『ウィンザーの陽気な女房たち』の登場人物)は、シェークスピアの創造した最高の人物といわれる。また端役として登場する道化たちの人生の知恵にあふれた滑稽(こっけい)な台詞(せりふ)もこのことを裏書きする。 さらにシェークスピアの用いる言語は、英語の集大成、その詩的表現力の絶頂を極めたものである。これは、英語のルーツたるゲルマン系のアングロ・サクソン語に、ラテン系のフランス語が加わり、この混合によって驚くべき言語の自己増殖力が生まれたからである。上流階級の教養人の雅語と、一般庶民の俗語が融合し、古い伝統的表現が新しい外来の新語によって活性化した結果、ことばの花園が生まれた。シェークスピアやディケンズなど英文学史上の偉大な文豪は、まさにそこに咲いた大輪の花であった。 美術、音楽においてイギリスは、文学におけるほどの世界的水準にまで達していないが、その根底にある特質は同じである。イギリス人は古来の伝統を重んずることで知られているが、だからといって新しい外来の要素を排除することなく、自由に取り入れて同化した。エリザベス王朝時代の音楽、18世紀の絵画が世界に誇るものを生み出したのは、この柔軟な精神のおかげであった。19世紀には高度に発達した物質文明に、音楽、美術が追い付くことができず、諸外国に比べて貧弱な状態にとどまったが、大英帝国の威光の薄れた20世紀となって、ふたたび芸術的再生の兆候が現れ始めたのは、広く外に門戸を広げるイギリス本来の姿勢を取り戻したからである。 イギリスの芸術を語るにあたって忘れることのできないものは、いわゆる高級な芸術品ではなく、民衆の生活のなかから生まれた素朴な工芸品などである。たとえば陶器、家具、織物など、日常の必要を満たすためにつくられ、同時に美的感覚を十分に満足させるものが多かった。産業革命後、これらの品物は工場による大量生産に移されたが、それに抗して古きよき民俗伝統を守ろうとする動きが各地でみられ、今日に至るまで絶えることなく続いている。 [小池 滋] 文化施設博物館、美術館などは、まさに上に述べた民衆の遺産を保存し、後世に伝える役割を果たしている。イギリスの博物館といえば、すぐに大英博物館と、そこにある世界的逸品、エルギンの大理石やロゼッタ石を思い浮かべるが、それ以外に、名前はあまり広く知られていないが、多くのじみな展示品をもつ博物館が(とくに地方に)あることを忘れてはならない。美術館、工芸館についても同じである。 さらに、こうした施設が、かならずしも国家や地方自治体など、いわゆる政府の手によるものではなく、民間の有志によって支えられていることに注目すべきだろう。たとえば、古い建築物をその中の家具、装飾品とともに破壊散逸から防ぐため、「ナショナル・トラスト」という団体が管理維持を行っている。これも、すでに述べたイギリス人のアマチュアリズムの一つの現れであり、ボランティア精神の顕著な実例である。 特別の学者専門家以外あまり本を買わないイギリス人にとって、教養娯楽のための読書はもっぱら地域の公共図書館に頼ることとなる。図書館は単に求められた本を貸すだけでなく、専門教育を受けた司書による読書指導・相談、必要な本を全国的ネットワークで探し出すサービスが能率よく行われる。そのうえ、その地方の歴史、文学などの研究を促進させるための文化活動の中心となっている。ただ皮肉なことに、図書館が充実するにつれ個人の本を買う意欲が減り、出版社の経営が脅かされるので、出版社や著作者側から、図書館の貸出し回数に応じた印税を要求する声があがった。1979年に公貸権法が成立し、1982年より図書館の貸出し冊数に応じた補償金を政府の拠出金による基金より支払っている。 [小池 滋] マスコミイギリスは世界でもっとも早くから新聞の発達した国であるが、19世紀後半までは読者数もそれほどではなかった。1870年に法によって無料で小学校教育を全国民に施す方針が決まったのを契機として、国民の読み書き能力が大きく飛躍した。その結果、出版事業は、特定の教養人のみではなく、広範囲にわたる大衆を目標とするように変わった。新聞も部数の少ない高級紙と、大部数をもつ大衆紙とに分かれ、高級紙の経済的危機がしばしばうわさされ、世界的権威を誇るロンドンの『タイムズ』の存立すら危うくなってきた。新聞、出版を問わず整理統合が激しく、国外の経営者の手に渡るというケースがしばしばみられる。通信社には1851年創立のロイターなどがある。 イギリスの放送は1922年に開始され、その後、国営の英国放送協会(BBC)が独占し、一般国民の文化水準を高めるという啓蒙(けいもう)的態度を一貫してとってきた。第二次世界大戦以後テレビが加わり、娯楽的要素が強まってきた。現在テレビはBBCのほかにチャンネル4(非営利法人)、チャンネル3(ITV)とチャンネル5が全国放送を行っている。ラジオはBBCのほかに全国放送が3チャンネル、多数のローカル局がある。イギリスの放送は日本に比べればチャンネル数も少なく、放送(放映)時間も短く、よくも悪くも生活への影響は小さい。 [小池 滋] 日本との関係
19世紀に入ると、ナポレオン戦争のすきをついてイギリスは東アジアへの進出を早め、日本近海にもイギリス船が出没するようになった。1808年(文化5)フェートン号が不法に長崎に入港し、燃料と食料を強要した。この事件は幕府に衝撃を与え、イギリスに対する関心をかき立て、幕府はオランダ語通詞に英語の学習を命じた。早くも1811年(文化8)には最初の英学入門書と英和対訳辞書が刊行され、後の日英交渉史に活躍する森山多吉郎、堀達之助らの英語専門の通詞を生む素地が固められた。1820年代には、浦賀に入港したイギリス船が通商を求めて幕府に拒否され、また水戸(みと)藩領大津浜への武装イギリス兵の上陸事件が起こるなど、幕府を刺激する事件が相次ぎ、幕府は苦肉の策として異国船打払令を出してこの情勢に対応した。アメリカのペリーが浦賀に現れた翌年の1854年(安政1)、イギリス極東艦隊司令官スターリングが4隻の軍艦を率いて長崎に入り、日英約定を結び、日英和親条約が正式に調印された。この条約に基づいて1858年エルギン卿(きょう)が江戸にきて、日英修好通商条約を結び、ここに日英間に正式の外交関係が樹立され、初代の総領事(のち公使)としてオールコックが着任した。以後ニール(代理)、パークスと続くイギリス外交団は、生麦(なまむぎ)事件(1862)にみられたような日本人の反発に対して、薩英(さつえい)戦争(1863)、四国艦隊下関砲撃事件(1864)など、力による威圧の政策をとり、さらに攘夷(じょうい)運動が薩摩(さつま)、長州を中心にしだいに開国、対英接近の姿勢に転向するのをみて、討幕運動を支援し、幕府を支持するフランスを牽制(けんせい)した。幕府のイギリス外交官にはオールコックをはじめサトー、アストン、ミットフォードなど日本紹介に多大の貢献をした人物がいる。 ところで、漂流民、水夫を除けば、正式にイギリスを訪れた最初の日本人は、幕府の遣欧使節団の一行38人であった(1862年=文久2)。メンバーには福沢諭吉、福地源一郎、箕作秋坪(みつくりしゅうへい)らが含まれ、精力的な探訪と学習とによってイギリスに対する認識を深めた。翌1863年長州藩は禁令を破って、後の伊藤博文(いとうひろぶみ)、井上馨(いのうえかおる)ら5人を密航させてイギリスに留学させた。一行は商社ジャーディン・マセソンの世話を受け、ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジに学んだが、同じカレッジには1865年(慶応1)から薩摩藩留学生15人も加わった。彼らも全員変名を用い、政商グラバーの世話で密航したが、なかには森有礼(もりありのり)、日本における博物館の父、町田久成(まちだひさなり)などがいた。一方、開国後の幕府は蕃書調所(ばんしょしらべしょ)を置き、情報の収集と洋学者の育成にあたったが、そこにおいては、もはや蘭学(らんがく)の独占的地位は崩壊し、1860年(万延1)ごろから英学の担当者も現れて、英学は蘭学に次いで第二順位を占めた。1866年(慶応2)ついに渡航の自由化に踏み切った幕府は、菊池大麓(きくちだいろく)、外山正一(とやままさかず)、林董(はやしただす)ら10代後半から20歳前後の青年12人を選抜し、これに年長の川路太郎、中村正直(なかむらまさなお)を加えて、イギリスに留学生として派遣したが、彼らも薩摩、長州の留学生とともに主としてユニバーシティ・カレッジに学んだ。幕末までの留学生総計153人中、イギリスで学んだものが49人で最高位を占めているところにも、日本のイギリスに対する関心の高さがうかがえる。 文物の交流の面では、1862年(文久2)にロンドンで開かれた万国博覧会には、オールコックの斡旋(あっせん)で日本の工芸品が陳列された。日本に在住したイギリス人の活動で目覚ましかったのはジャーナリズムの分野で、最初の英字新聞が商人ハンサードA. W. Hansardによって長崎で創刊されたが、のちに横浜に移り、ブラックを編集者とする日刊の『ジャパン・ガゼット』へと発展した。また『イラストレイテッド・ロンドン・ニューズ』の特派画家兼通信員として1861年来日したワーグマンは、『ジャパン・パンチ』を通じて日本の紹介にあたった。 幕府期にイギリスを訪れた体験の持ち主は、幕府の倒壊、明治政府の誕生という情勢のなかで、新時代のオピニオン・リーダーとして登場した。なかでも傑出した存在は、『西洋事情』『文明論之概略』などの精力的な文筆活動と慶応義塾の教育を通して、イギリスの制度、文物、思想の啓蒙(けいもう)にあたった福沢諭吉と、幕府崩壊後は静岡学問所の教授となり、スマイルズの『西国立志編』、J・S・ミルの『自由之理』を翻訳・刊行した中村正直である。2人とも明六社の同人として、自由民権思想の基盤を整えるのに大きな貢献をした。 明治時代の日英関係の劈頭(へきとう)を飾ったのは、岩倉使節団の派遣であった。正使岩倉具視(いわくらともみ)をはじめ木戸孝允(きどたかよし)、大久保利通(おおくぼとしみち)、伊藤博文など明治新政府の中心人物を網羅したこの大使節団は、アメリカに次いで1872年(明治5)8月イギリスを訪れ、4か月余り滞在し、ロンドンのみならずリバプール、マンチェスター、グラスゴー、さらにはスコットランド高地地方まで足を伸ばし、イギリスの先進的な諸制度や技術を親しく視察した。その詳細は、使節団の報告書『特命全権大使米欧回覧実記』にみることができるが、同じ小さな島国たるイギリスの富強の原因を探ろうとしたその視角は、これからのち第二次世界大戦までの日本人のイギリス観の原型となった。そして自由民権運動の展開した明治10年代には、立憲改進党が結党にあたって「万事の改革すでに成りたるイギリス」の政党に倣うと宣言し、また福沢を中心とする交詢社(こうじゅんしゃ)は、イギリス流の立憲君主制を骨格とする憲法私案を発表し、また実地の体験の尊重を旨とする英吉利(イギリス)法律学校(後の中央大学)が設立された。 一方「文明開化」を標榜(ひょうぼう)したこの時期に、イギリスは欧米列強のなかでも最多数のいわゆる「お雇い外国人」を送って、日本の近代化に多大の寄与をした。なかでも、鉄道建設の最高責任者であり、工部省の設置を進言して技術教育の基礎を固めたモレル、総員34人の教師団の団長として来日し、日本の海軍を完全にイギリス流に教育・編成したダグラスArchibald Lucius Douglas(1842―1913)、当初はその一員でのちに帝国大学で言語学、日本語学を講じたチェンバレン、また洋風建築の普及に尽力したコンドルなどの名は逸することはできない。逆に日本側も開国期よりもはるかに多数の留学生をイギリスに送り出したが、1900年(明治33)英語・英文学関係の最初の文部省派遣留学生に選ばれたのが夏目金之助(漱石(そうせき))であり、屈折を余儀なくされた留学生活を送った彼は、帰国後ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の後任として東京帝国大学で英文学を講じた。聖書と賛美歌の翻訳で始まったイギリス文化の移入も、やがてシェークスピアを筆頭とする英文学に広がり、ワーズワース、バイロン、シェリーなどは明治中期には日本人にも親しい名前となった。 かくて「世界の工場」、強大な海軍力を擁する大帝国、議会政治の母国、また、ジェントルマンの国としてのイギリスのイメージは、日本人の脳裏に強く印象づけられ、イギリスをこそ学ぶべき模範とみるイギリス観が、支配階級と知職人の一部に根強く存在し続けることになった。 他方、外交面においてイギリスは、他国よりも先に日本の不平等条約改正の主張を認め、1894年(明治27)日英通商航海条約を結び、さらに日清(にっしん)戦争後はロシアの進出に対抗して極東を重視する政策をとり、1902年(明治35)日英同盟を締結し、相互援助を約した。この同盟条約によって日本は第一次世界大戦に参戦したが、同盟はワシントン会議の四か国条約によって破棄された。昭和に入ってからの日本の中国侵略に対して、国際連盟が派遣したイギリス人リットンを長とする調査団の報告は、日本の国際連盟脱退を招き、両国の関係は太平洋戦争の破局を迎えた。第二次世界大戦後イギリスは連合国の一員として対日占領政策に参加し、サンフランシスコ条約により国交を回復した。近年イギリスの国際的地位の低下、「イギリス病」の弊害とその克服が語られるなど、日本のイギリスをみる目は大きく変化しており、新たな日英関係のよってたつ基盤が模索されている。 [今井 宏] 『杉山忠平著『イギリスの国、イギリスの人』(1967・未来社)』▽『K・B・ステフェンソン著、中村和郎訳『全訳世界の地理教科書3 イギリス――その国土と人々』(1977・帝国書院)』▽『木内信藏編『世界地理7 ヨーロッパⅡ』(1977・朝倉書店)』▽『定松正・蛭川久康他編著『風土記イギリス――自然と文化の諸相』(2009・新人物往来社)』▽『W・バジョット著、深瀬基寛訳『英国の国家構造』(1967・清水弘文堂)』▽『河合秀和著『現代イギリス政治史研究』(1974・岩波書店)』▽『R・ローズ著、犬童一男訳『現代イギリスの政治Ⅰ・Ⅱ』(1979・岩波書店)』▽『S・G・リチャーズ著、伊藤勲監訳『現代イギリスの政治』(1979・敬文堂)』▽『梅川正美・阪野智一他編著『現代イギリス政治』(2006・成文堂)』▽『渡辺容一郎著『イギリス・オポジションの研究――政権交代のあり方とオポジション力』(2009・時潮社)』▽『A. H. Hanson & Malcolm WallesGoverning Britain, A Guide-Book to Political Institutions (1st published 1970, Revised edition 1975, Fontana, Collins)』▽『内田勝敏著『現代イギリス貿易論』(1966・東洋経済新報社)』▽『森恒夫著『イギリス資本主義』(1975・青木書店)』▽『吉岡昭彦著『近代イギリス経済史』(1981・岩波書店)』▽『浜野崇好著『イギリス経済事情』(1981・日本放送出版協会)』▽『森嶋通夫著『イギリスと日本』正・続(岩波新書)』▽『小松芳喬著『イギリス経済史断章』(2000・早稲田大学出版部)』▽『横井勝彦編著『日英経済史』(2006・日本経済評論社)』▽『日本経済新聞社編・刊『イギリス経済再生の真実』(2007)』▽『G・M・トレヴェリアン著、藤原浩・松浦高嶺・今井宏他訳『イギリス社会史Ⅰ・Ⅱ』(1971、1983・みすず書房)』▽『R・マッケンジー、A・シルバー著、早川崇訳『大理石のなかの天使――英国労働者階級の保守主義者』(1973・労働法令協会)』▽『内藤則邦著『イギリスの労働者階級』(1975・東洋経済新報社)』▽『Trevor NobleStracture and Change in Modern Britain (1981, Batstord Academic and Education Ltd., London)』▽『J・B・プリーストリー著、小池滋・君島邦守訳『英国のユーモア』(1978・秀文インターナショナル)』▽『小野二郎著『紅茶を受皿で――イギリス民衆芸術覚書』(1981・晶文社)』▽『森嶋通夫著『イギリスと日本』正・続(岩波新書)』▽『沼田次郎編『東西文明の交流6 日本と西洋』(1971・平凡社)』▽『日本英学史学会編『英語事始』(1976・エンサイクロペディア・ブリタニカ)』▽『今井宏著『日本人とイギリス―「問いかけ」の軌跡』(1994・ちくま新書)』▽『北川勝彦編著『イギリス帝国と20世紀 第4巻 脱植民地化とイギリス帝国』(2009・ミネルヴァ書房)』 [参照項目] | | | | | | | | | | | | | | | | | [補完資料] |"> イギリスの国旗 ©Shogakukan 作図/小学館クリエイティブ"> イギリス位置図 ロンドン中心部のウォータールー・ブリッジからシティを望む。水運に重要な役割を果たし、また観光船なども航行する。有名なロンドン・ブリッジやタワー・ブリッジなど、市内にはいくつもの橋が架かる。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka"> テムズ川 12世紀ごろからあるといわれるウルクハート城と湖水。U字谷に湛水したフィヨルド湖で、怪獣伝説を思わせる神秘さよりも、明るくのどかな風景である。イギリス インバネス近郊©Masashi Tanaka"> ネス湖 2個の立石の上に楣石をのせたトリリトン(三つの組石)。高さ約7m、立石1本の重さは25tに及ぶ。世界文化遺産「ストーンヘンジ、エーブベリーと関連する遺跡群」の一部(イギリス・1986、2008年登録) イギリス ソールズベリー近郊©Shogakukan"> ストーンヘンジ 11世紀に建造され、のちに火災で大部分を焼失。19世紀なかばに再建され、現在は国会議事堂として使用されている。北側(写真右)にそびえる時計塔は「ビッグ・ベン」。世界文化遺産「ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター寺院および聖マーガレット教会」の一部(イギリス・1987、2008年登録) イギリス ロンドン©Shogakukan"> ウェストミンスター宮殿(イギリス国会議… ダウニング街10番地にある首相官邸。旧ウェストミンスター地区は古くからイギリス国政の中心で、この通りには大蔵大臣官邸や外務省などが面している。「ダウニング街10番地」はイギリス首相の代名詞ともなっている。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka"> ダウニング街 ロンドンの中心部、シティにあるイギリスの中央銀行(写真左)。1694年の開設だが、現在の建物は1924~39年のもの。「ザ・バンク」「スレッドニードル街の老婦人」ともよばれる。写真右奥は旧王立取引所。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka"> イングランド銀行 イギリスが誇る世界最大級の博物館。1759年開館。エジプト文明をはじめとする世界各地の重要な古代遺物や美術品などを数多く展示する。イオニア風の円柱が並ぶ建物正面は、イギリスの建築家スマークの設計。イギリス ロンドン©Masashi Tanaka"> 大英博物館 テムズ川に架けられた可動橋。1894年完成。重量1000tの可動部分の橋桁は水力によって約90秒で全開する。塔内には、橋桁開閉のメカニズムを示す展示館もある。イギリス ロンドン©NetAdvance"> タワー・ブリッジ 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
<<: Anglo-Afghanistan War - Anglo-Afghanistan War
Recommend
Acetaminophen Method - Sweat and Aminofenho
...Gastric emptying function tests are one of the...
Ishida [town] - Ishida
A former town in Iki County, northeastern Nagasaki...
Ajune - Ajune
Aquitaine is a region in southwestern France, mai...
Onimushi - Sleepyhead
...These locusts have been causing great damage i...
Usulu School
…The 17th century Akhbar school was known for its...
Muraoka [town] - Muraoka
A former town in Mikata County in northern Hyogo P...
Lake Galilee - Galilaya
→ Tiberias [Lake] Source : Heibonsha Encyclopedia ...
Ottoman Turkey - Osman Torko
...The basic plan was based on the simple flat-ro...
Germania Prima (English spelling) Germania Prima
The Alamanni's occupation of Agri-Decmatez an...
Iron chloride
Compounds of iron and chlorine. Compounds with ox...
Regensburg - Regensburg (English spelling)
A city in Bavaria in southeastern Germany. It is ...
Enkato - Enkato
…The Japanese word toshi (city) was used in the m...
Ataka Fuyuyasu
1528-1564 A military commander and poet of the Se...
Princess Long-legged - Princess Long-legged
She was the wife of Emperor Chuai, the protagonis...
Hutton, W.
...Other industries include aircraft and food. Un...