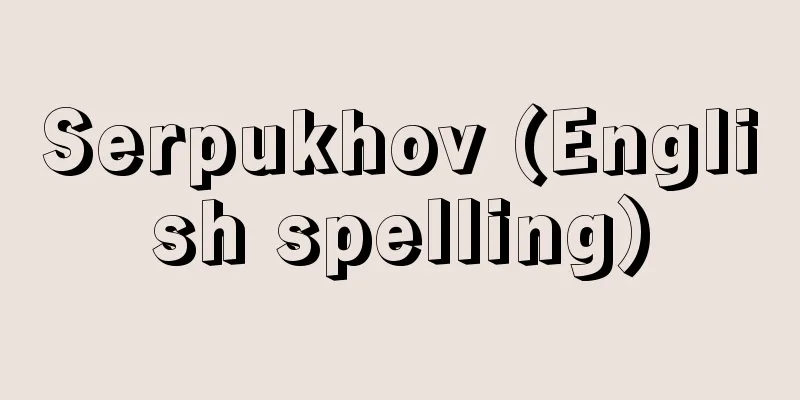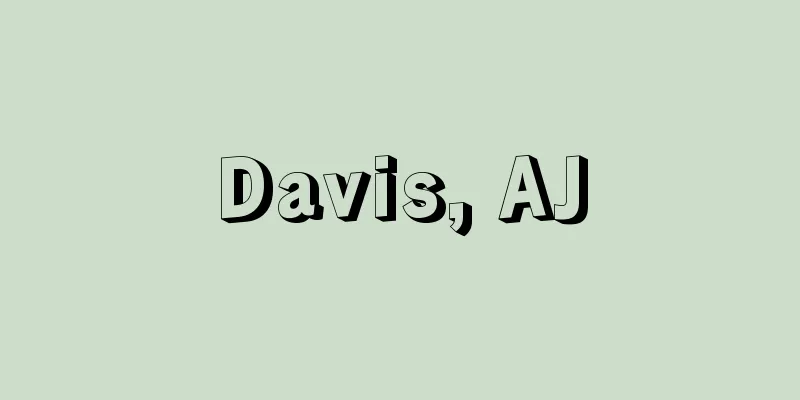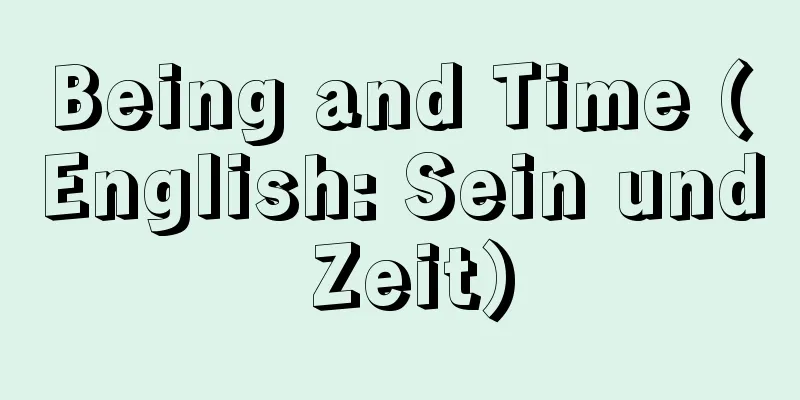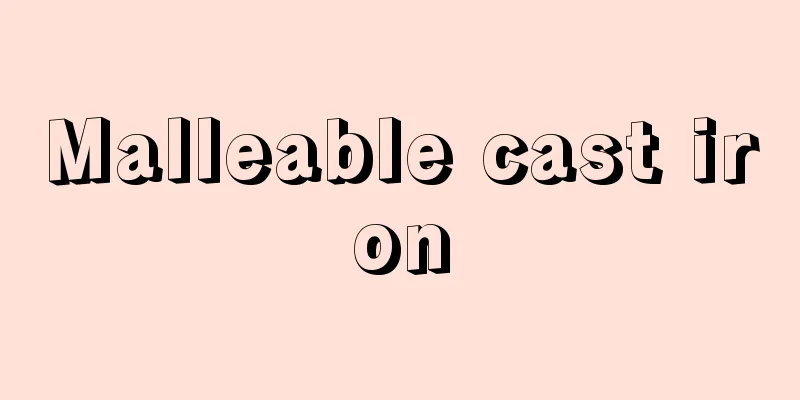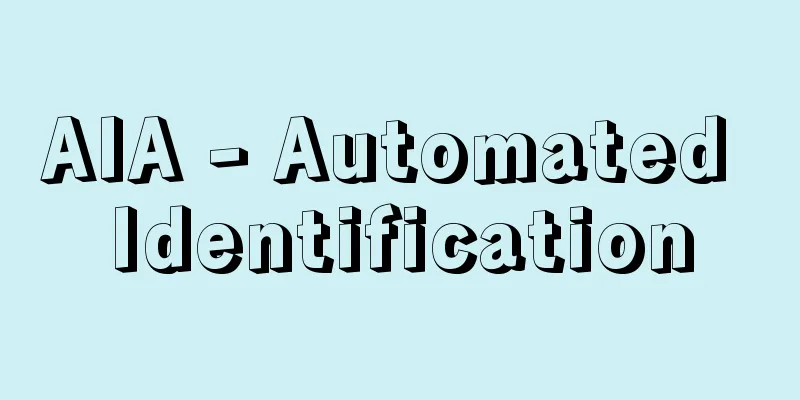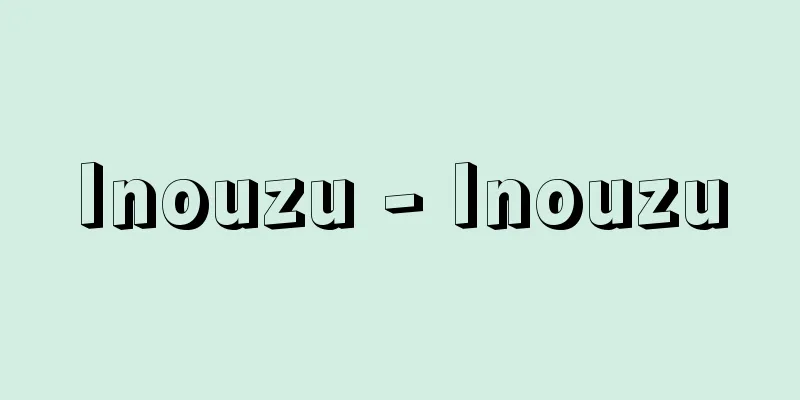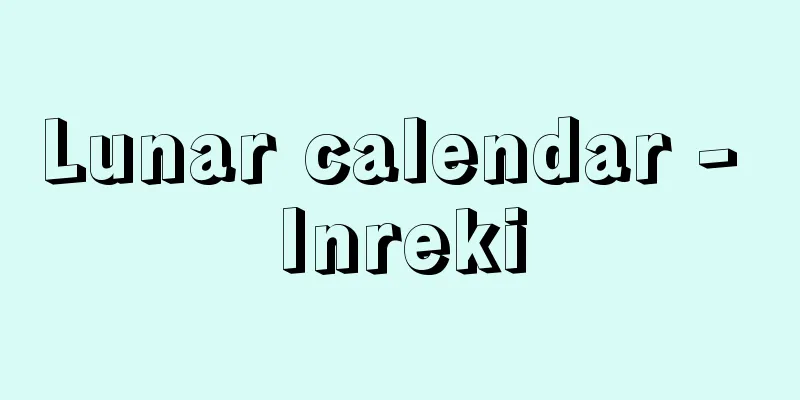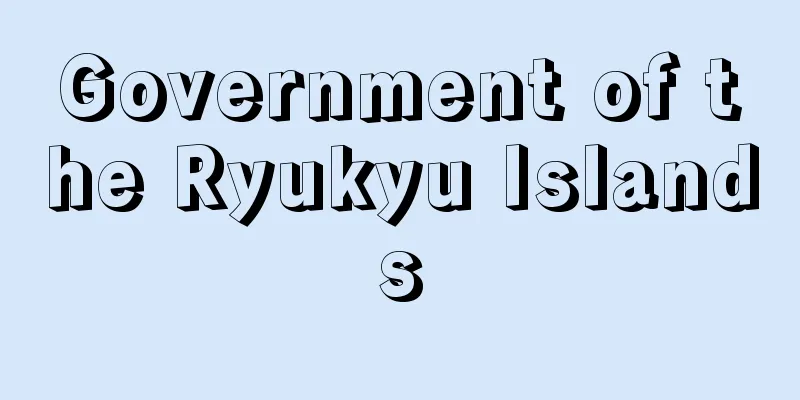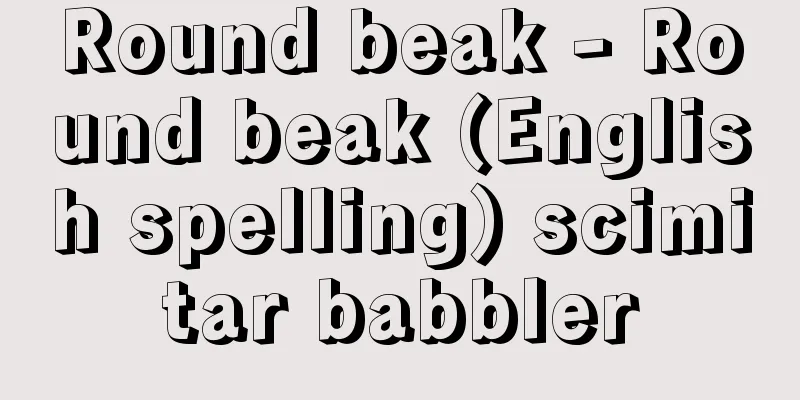Olympics - Orinpikku (English spelling) Olympic Games

|
Modern sports were organized in the UK from the middle of the 19th century, and developed and spread through the training of athletes in the US, which put a lot of effort into facilities. The Olympics are the comprehensive synthesis of these various sports, and are a modern revival of the sports festival that originated in ancient Greece. The French aristocrat Coubertin advocated education reform in order to rebuild his country, which had been defeated in the Prussian-French War (1870-1871), and became fascinated with ancient Greek physical education, which aimed for harmony between the body and the mind. In 1894, he founded the International Olympic Committee (IOC), and succeeded in holding the Olympics every four years as a festival of peace for young people all over the world. The IOC called on all countries to participate in the Olympics, and strictly prohibited discrimination on the grounds of religion, race, or politics. There were protests from some countries, but overcoming these protests established the Olympics as a solid foundation. In the early 20th century, each sport organized its own IF (International Sports Federation) and established internationally accepted rules. In the 1980s, political issues were brought to the IOC, and its traditions were shaken. In the 1980 Moscow Games, many major powers did not participate in protest of the Soviet invasion of Afghanistan. In response, the Soviet Union and Eastern European countries did not participate in the 1984 Los Angeles Games. In addition, the voice of each IF and each country's NOC (National Olympic Committee) has become stronger. However, even under such circumstances, the fact that all the world's sports competitions, including regional competitions recognized by the IOC (Asian Games, Pan American Games, etc.), have the Olympic Games as their sole representative is a testament to its traditional strength. Since the Seoul Games in 1988, the games have been held without any such problems. [Suzuki Yoshinori] Ancient OlympiaCommonly known as the Ancient Olympic Games, they were ancient Greek festival games that were reportedly held regularly for about 1,200 years. The festivals dedicated to the gods of Mount Olympus began to change when the second wave of the Indo-European migration, which began in the 13th century BC, settled in the Peloponnese. After the Trojan War, military contests were held for the funeral of heroes and for the entertainment of the troops, and these were added to the festival events. The Olympias, which was dedicated to the chief god Zeus at Olympia, is said to have been revived in 776 BC, but the accepted theory is that its origins lie in ancient rituals held among the Dorians. There are various theories about the year of the revival, including one that says that the first tournament was held in 776 BC, when writing was introduced from Phoenicia and the names of the winners began to be recorded, and another that says that the tournament was founded in 1580 BC, 1195 BC, or 884 BC. After that, the Pythia Games (582 BC) held at the sanctuary of Apollo in Delphi, the Isthmian Games (582 BC) held in Corinth to celebrate the sea god Poseidon, and the Nemea Games (573 BC) for Zeus began, and these are known as the four great Greek festivals. Olympia was located on the northwestern border of the peninsula, so it was not affected much by civil wars or the rise and fall of cities, and the Olympias Games continued until 393 AD, when it was a Roman province. For reasons that are unclear, the festival was held every four years, and later, Timaeus of Sicily (356?-260? BC) and others named these four years an Olympiad. The games were held in the first year, and as far as records go, they continued for 293 times. However, according to J. Toynbee, an unofficial "Hidden Olympias" was held at Cape Taenaron until the end of the 9th century. Like other Greek shrines, Olympia was small (about 25,000 square meters), so at first there was only one short-distance event (one stadium, 191.27 meters at Olympia), and from 724 BC, middle-distance races, long-distance races, pentathlon (long jump, discus, sprints, javelin, wrestling), wrestling, and boxing were gradually added, and chariot racing and horse racing, which had been popular since the heroic age, were not introduced until the 7th century BC. After that, pankration (a kind of event that combines wrestling and boxing), armed races, trumpeting competitions, and messenger competitions were held, but there were different types of chariot racing, such as two-horse and four-horse, sprinting, and mule races, and there were also different types of horse racing, so about 19 events were held throughout the entire Games. In addition, competitions for boys under the age of 18 began in the 7th century BCE, and included five events: sprints, wrestling, the pentathlon, boxing, and pankration. Not all events were held at one tournament, and even in its heyday, it is said that there were about a dozen events. The festival was held in midsummer from July to September (January to March in Greek at that time), and until the 22nd Games (692 BC), it lasted only one day, but in the middle of the 5th century BC, after Greece's victory over Persia, it reached the height of its prosperity, and the Olympias expanded to five days. During the five days, the athletes' oath-taking ceremony, ceremonies, and a banquet for the winners were held, and the first day was always a full moon. The Olympias, which had become extremely extravagant, became a promotional venue for politicians, soldiers, and writers, and each participating city was obsessed with winning, even if it meant using unfair means, in order to gain honor, and was completely corrupt internally, poaching promising athletes, bribing the judges (which started out as one, but grew to 12 at its peak) and the opposing athletes, etc. The eligibility requirements were strict: participants had to be of pure Greek blood, hold citizenship, have never been punished, and have done nothing blasphemous to the gods. In its heyday, participants also trained in their own city and, before the festival, spent a month in a training camp in the region of Elis on the Peloponnese peninsula, where participants were judged based on their performance. Not only were women without citizenship not allowed to participate, but they were also strictly prohibited from spectating the competition. Participants competed completely naked, except for those driving the chariots and horses. Rules were also established, and if you killed your opponent in a combat match, you lost by decision and were fined, and it was also forbidden to stick your fingers in someone's eyes or kick someone in the groin. One winner was determined, and no other rankings were recognized. Officially, the only privileges for the winners were to receive an olive wreath and an invitation to a feast in the sanctuary on the last day of the games, but in reality, when they returned to their own city, they received social status and a large prize money, which led to athletes being scouted and bought by other cities, thus tainting the games. There was also no official recognition of the winners' records. Since each city held the festival in high regard, an agreement to suspend all armed conflicts for three months before and after the festival was well-observed between the cities until the time of the victory in the Persian Wars. However, this also collapsed around the time of the Second Attic Naval League (377 BC), and Olympia was burned down even during the games (364 BC). It is also important to note that a trend emerged among Greeks in general to value oratory over physical education. The fact that Socrates, who enjoyed philosophical conversations with young people at the Athenian gymnasium, was accused of leading them away from physical training and in an undesirable direction shows that this trend had an influence that could not be ignored by rulers. Philip II of Macedonia was the first non-Greek to win a horse race (356 BC) in the face of the disapproving gaze of Greek spectators who feared his conquest. His son Alexander the Great ruled all of Greece, but he himself showed less interest in the sports than his father. Later, Greece was conquered by Rome, and at one point all the adult athletes were transported to Rome and only the boys' games were held at Olympia (80 BC), and the festivals were delayed by two years due to Nero's participation (67 AD), and the festivals became corrupt in both name and reality. Early Christianity, which regarded the body as merely a slave to the soul, steadily gained ground in the Roman Empire, and in 380 AD Emperor Theodosius established Christianity as the state religion and suppressed paganism. In 394, the year after the last Olympic Games, the Olympian festivals were banned, and the temple was destroyed shortly thereafter. The gold and ivory statue of Zeus made by Phidias was carried away, and Olympia was left in total ruins, and was buried for a long time by earthquakes and floods. The location of Olympia was unknown until the beginning of the 19th century because the names of places around the area had changed to Slavic, the language of the settlers. Famous athletes include Leonidas (races), Philomplotus (pentathlon), Chionis (races), Hipposthenes (wrestling), Milon (wrestling), Thysander (boxing), Dorieus (pankration), Theagenes (wrestling), Euthymenes (wrestling), and Chiron (wrestling). Some of them won not only the Olympic Games but also other festivals such as the Pythian Games. Various documents record that famous people such as Pythagoras, Herodotus, Thucydides, Plato, and Diogenes were among the many spectators. [Suzuki Yoshinori] The Beginnings of the Modern OlympicsThe origins of the modern Olympic Games date back to the Renaissance. The Renaissance reevaluated ancient physical education, and the Enlightenment further spurred this trend. Furthermore, the trend of classical thought from the 18th century spurred interest in ancient Greek and Roman culture. Winckelmann, an early promoter of this movement, actually aimed to excavate Olympia, but he collapsed before completing the excavation. In 1766, two years before his death, the Englishman Richard Chandler (1738-1810) discovered the ruins of Olympia, but was forced to abandon his excavation plans after receiving an order from the Turkish government to leave the country. This European passion for Greece was not only mediated by personal actions such as those of Byron, who participated in the independence army, but was also one of the driving forces behind the military support provided by nations such as Britain and France to the Greek War of Independence from 1821 to 1829. After the victory over the Turks, Otto I (1815-1867, reigned 1832-1862), who was made the King of Greece from a Bavarian prince, was inspired by the excavation of Olympia by a French team (1827-1829), the publication of the book Olympia by physical education historian JH Krauze (1838), and the travel report of the Peloponnese peninsula by Ernst Curtius (1814-1896) in Berlin (1852), and planned to revive the Olympic Games, holding the first games in 1859. However, due to a lack of knowledge of modern sports, it failed. The second games were held in 1870, but also ended in failure. The third games were held in 1875, when the Olympia excavation team led by Curtius, sponsored by the German imperial family, arrived in Greece, but only 24 people participated. The first events were running, long jump, triple jump, javelin, discus, wrestling, and pole climbing, but they were not very successful. The fourth Olympics was held in 1889 to coincide with the celebrations of King George I. These four Olympics marked the end of the Greek Independence Restoration Olympics. Afterwards, the outline of the ancient Olympias became clearer through excavations of buried ancient Greek ruins, and Coubertin, who was trying to implement an educational policy through physical education, first proposed the establishment of an Olympic Games to revive the Games in November 1892, but there was almost no response. In June 1894, in front of representatives from 12 countries who gathered at the Sorbonne lecture hall of the University of Paris, where the main topic was the issue of amateurs, Coubertin again proposed the revival of Olympic sports on the 23rd of that month. This time, perhaps due to the creation of a good mood at the venue, such as by having singers sing a melody to the Hymn to Apollo, discovered in Delphi in 1893, the previous year, the meeting was unanimously resolved to hold the Games, and the IOC was organized to run the Games, with the selection of the committee members left to Coubertin. It is said that Coubertin referred to the management of the ancient Olympics in the time of Pericles (c. 495-429 BC) in carrying out these procedures and selections. Coubertin recommended leading politicians and military figures from around the world, selecting 15 people from 13 countries to spur the movement. This was commemorated on June 23rd as "Olympic Day." [Yoshinori Suzuki] Modern Olympics1st Games (1896, Athens)The dates were April 6th (March 25th) to 15th (Greek calendar). 14 countries participated, and 241 athletes participated. The Greek people welcomed the decision made by Coubertin and others to hold the Olympic Games in Athens in 1896. However, the Greek government took a cold attitude, considering the financial situation was close to bankrupt. Therefore, Coubertin persuaded King Georg through Crown Prince Constantine (grandfather of Crown Prince Constantine (1940-), winner of the yachting category at the 1960 Rome Olympics) to hold the games. He then created a committee headed by the Crown Prince to take measures such as financial matters. The results were remarkable, such as the construction of the main stadium by George M. Averoff (1815-1899), a wealthy Greek man living in Alexandria, who donated 920,000 drachmas. The main stadium was a luxurious modern marble structure built on the site of an ancient stadium, capable of accommodating 50,000 people. The track was 400 meters long and curved clockwise, the opposite direction to the current one. Indoor events were held in the Zappeion, an indoor gymnasium donated in 1887 by Konstantinos Zappas (1814-1892), a cousin of Evangelos Zappas (1800-1865), who lived in Romania, in accordance with his will. 80,000 people flocked inside and outside the stadium to attend the opening ceremony, and after the King's opening declaration, the Olympic hymn, written by Kostis Palamas (1859-1943) and composed by Spiro Samara (1861-1917), was sung. The events announced for the tournament were 10 sports and 43 events, including athletics, gymnastics, weightlifting, fencing, rowing, swimming, cycling, wrestling, tennis, and shooting. However, the other scheduled events of water polo, equestrianism, and cricket were cancelled, and rowing was canceled due to bad weather. The content of these events was more heavily influenced by British sports, which Coubertin had studied enthusiastically, than by ancient Greece. Only the winners and runners-up received prizes in this tournament. The winners received a certificate, a silver medal, and an olive wreath, while the runners-up received a certificate, a bronze medal, and a laurel wreath. The Greeks were greatly disappointed when Americans and other foreign athletes won the land and water events, including the discus, which they believed to be a traditional event. However, in the 39.909 km marathon from Marathon to Athens, which was added to honor the glory of ancient Greece (the idea was conceived by Frenchman Michel Bréal (1832-1915) of the French Academy; such a long-distance race had never been held in ancient Greece), the Greek Spyridon Louis (1873-1940) ran a powerful sprint to victory, sending the whole of Greece into a frenzy. It can be said that Athens marked the start of the modern Olympic Games in a magnificent way. Winners: (1) USA 11, (2) Greece 10, (3) Germany 7. [Yoshinori Suzuki] 2nd Tournament (1900, Paris)May 14th to October 28th. 24 countries participated, 997 athletes. Coubertin's intention was to hold the event in collaboration with the World's Fair to be held in Paris that year. However, due to hostility with the French Athletics Association, lack of understanding from the fair's authorities, and lack of Olympic knowledge, the event began and ended in chaos. The IOC lacked operating funds, and in the end only held athletics events on the grass courts of the French Racing Club in the Bois de Boulogne. Other events were held as events associated with the World's Fair, with prize money ranging from 4,000 francs to 15 francs. There were some unclear points in the competition records, and the event did not conform to the true meaning of the Olympic Games. Charlotte Cooper (1870-1966) of Great Britain became the first woman to win the women's tennis singles in Olympic history. Number of victories: (1) USA 19, (2) France 13, (3) Great Britain 11. However, these figures are not clear. Also, from this Games, Coubertin became the second President of the IOC, replacing the first President, Demetrius Vikelas (1835-1908, Greece). [Yoshinori Suzuki] 3rd Tournament (1904, St. Louis)The Games ran from July 1st to November 23rd. However, the opening ceremony was held on August 29th, the day of the track and field events. 12 countries participated, with 651 athletes. The Games were held across the Atlantic to reward the United States for its success in the previous two Games. Chicago and St. Louis competed for the bid, but the latter was awarded by the ruling of the new president, T. Roosevelt. France did not participate because it could not raise the funds to send its athletes. Despite the failure of the previous Games, this one was treated as a side event at the Louisiana Purchase Centennial Exposition, and the Zeppelin airship and wireless telegraph became popular. In addition, interest was drawn to the American Track and Field Championships, which were being held at the time, so the Games were a lonely affair. However, America's advanced sports facilities and equipment were a great stimulus to Europe. The competitions were dominated by the United States again, but an unusual incident occurred in the marathon. American Fred Lorz (1884-1914) arrived at the stadium under the scorching sun and crossed the finish line to cheers. After a commemorative photograph was taken with the President's daughter and the results were announced, it was revealed that Loots had fallen behind at the 20km mark due to the intense heat, had been put back in the car of the escort, had recovered, and had resumed running while the car was stopped due to a breakdown, and had thus "won" the race. The real winner, American Thomas Hicks (1875-1963), was awarded the gold medal. This strange story remains famous to this day as the "Kiser Marathon." The main venue for this event was the University of Washington, and the Mississippi River was used for diving and other events under the guidance of German athletes. Forest Park, adjacent to the east of the university, was the exposition grounds, and a makeshift hotel was built there. Some of the athletes also stayed there, so it is said to be the origin of the Olympic Village. Number of winners: (1) USA 70, (2) Cuba 5, (3) Germany 4. [Yoshinori Suzuki] Athens International Games (1906, Athens)Before World War II, these were called intermediate Olympic Games, and were excluded from the official Games after the war. After the first Games, Coubertin had a hard time deciding on the location of the next Games, due to the enthusiastic atmosphere among Greeks that future Games should be held in Greece. As a measure to appease public opinion, he made a promise with the Crown Prince of Greece to hold a special Games in Athens in the middle of every four years, and this was the basis for the Games. Since the previous Games had been held in the United States, many European countries rallied to participate. 22 countries participated, with 883 athletes. [Yoshinori Suzuki] 4th Convention (1908, London)The event took place from April 27th to October 31st. 22 countries participated, and 2008 athletes participated. This event was held at the same time as the British-French Exposition, but was run only by borrowing funds from the exposition. The event was run by entrusting the management of the events to the relevant sports organizations, and the rules were well-established, so it is considered to be the event that laid the foundation for future event management, along with the next Stockholm event. The previous free entry system was abolished, and each country was given a national governing body for each sport, NOC, and only applications through the NOC were accepted. At the opening ceremony, the flags of each country marched in at the front. Also, for the first time, an OOC (Olympic Organizing Committee) was organized to manage the event. However, this event was a time when the emotional friction between the two major sports countries, Britain and America, since the War of Independence reached its peak, and many problems arose due to conflicts over issues such as amateur qualifications and competition rules. Unable to bear the sight of this, Bishop Etherert Talbot (1848-1928) of Pennsylvania at St. Paul's Cathedral preached to the athletes from various countries who had gathered for Sunday mass, "The important thing in the Olympics is not to win, but to participate." Moved by this, Coubertin later adopted these words as the ideal of the Olympics. The Olympic motto "Faster, citius, higher, altius, stronger, fortius" was proposed by Father Henri Didon (1840-1900) of the Dominican Order, and was adopted by Coubertin in 1897, but was not officially recognized by the IOC until 1926. This was the first time that a marathon course of 42.195 kilometers was run, but an incident known as the "Tragedy of Dorando" occurred. Dorando Pietri (1885-1942) of Italy collapsed when he arrived at the stadium and finished the race while being helped by officials, but this was deemed a foul and his victory was annulled. Empress Alexandra (1884-1925) of the United Kingdom took pity on him and presented him with a gold cup as a token of appreciation for his efforts. The marathon distance at this time became the official distance from the 8th Games onwards. Another notable event was the first appearance of figure skating in the winter sports. Number of winners: (1) Great Britain 56, (2) USA 23, (3) Sweden 7. [Yoshinori Suzuki] 5th Tournament (1912, Stockholm)The event took place from May 5th to July 27th. 28 countries participated, with 2,407 athletes. The Swedish royal family, who had been cooperating with the IOC since its founding, took the lead, and the nation and city also cooperated in the construction of the main stadium, and the Olympic Games finally began to be run in earnest, with the use of electric clocks for track and field events and photo finishers for the finals. As in the previous Games, various prizes were awarded by European emperors, royal families, and nobles. In addition, the pentathlon and decathlon were added to track and field, and new modern pentathlon and equestrian events, swimming for women, and artistic competitions such as a painting contest were added, modeled after the ancient Olympias. Boxing was not held due to a prohibition in Swedish domestic law. In the long-distance track and field events, Hannes Kolehmainen (1889-1966) of Finland, which was under the control of Imperial Russia, won three events: the 5,000-meter race, the 10,000-meter race, and the 8,000-meter cross-country race, drawing much attention. It was at this tournament that people of color began to stand out, with Hawaiian swimmer Duke Paoa Kahanamoku (1890-1968) winning the 100m swimming event with his freestyle swimming technique, and Native American Jim Thorpe (1888-1953) winning two mixed events. However, Thorpe was found to have been involved in professional baseball activities in the past, and was stripped of his amateur status at the IOC General Assembly the following year in 1913, and ordered to return his gold medal. He was the first swimmer to have his medal relinquished, but in October 1982, his disqualification was overturned thanks to a campaign by his sister and former President Ford to restore his status. Thanks to the efforts of Jigoro Kano, who was elected as an IOC member in 1909, Japan was able to participate from the 5th Olympics. At that time, the Japanese sports world was dominated by students and had no organization, so in 1911 (Meiji 44), the Dai-Nippon Taiiku Kyokai (known internationally as the Japanese Olympic Committee, or JOC) was founded and a qualifying tournament was held. As a result, it was decided to send Mishima Yahiko (Tokyo Imperial University) in the sprint and Kanaguri Shiso (Tokyo Higher Normal School) in the marathon. Kanaguri had set a great record in the qualifying tournament, breaking the world record at the time, and there were high hopes for him, but he suffered stomach pains during the marathon and withdrew from the race. Mishima also only passed the 400m qualifying and withdrew from the second qualifying round as he had no chance of winning. Number of wins: (1) Sweden 24, USA 24, (3) Great Britain 10. [Yoshinori Suzuki] 6th Congress (1916, Berlin)Coubertin designed the "Olympic Flag" when the IOC 20th anniversary ceremony was held in Paris from June 13, 1914. On June 28, the Sarajevo incident occurred, which led to the First World War, and the Berlin Games were finally canceled. In 1915 the IOC moved to its permanent headquarters in Lausanne, Switzerland. [Yoshinori Suzuki] 7th Tournament (1920, Antwerp)The event took place from April 20th to September 12th. 29 countries participated, with 2,626 athletes. The event was presented as a spiritual gift to the young people of Belgium, devastated by the war. Although the preparation period was short, the greatest efforts were made by organizing the event under the direction of Henri de Baillet-Latour (1876-1942), who later became the president of the IOC, including the construction of a 30,000-seat main stadium, a swimming pool that partitioned off a swamp, and the use of all-weather cranes for the tennis courts. Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkey were not allowed to participate in the event, as they were held responsible for the war, but the three Baltic states and Czechoslovakia, which had become independent as a result of World War I, participated. Finland also participated for the first time as a fully independent country. A newly designed Olympic flag was flown on the main pole, and the athletes took the oath modeled after the ancient Olympic Games, which became a worldwide trend. Nurmi, known as the "Flying Finn," won the 10,000 meter race and the 10,000 meter cross country race. The brave Kolehmainen won the marathon at the fifth tournament, which became a hot topic. Japan sent 15 athletes to compete in various events, but the Japan Athletic Association sent most of the delegation to the United States and Britain. The official reason was to inspect developed countries, but the actual purpose was to collect donations from Japanese residents in those countries. Tennis player Kumagai Kazuya won a silver medal in singles and in doubles with Kashiwao Seiichiro (1892-1962), becoming Japan's first medalist. Number of wins: (1) USA 41, (2) Sweden 17, (3) Finland 14. [Yoshinori Suzuki] 8th Convention (1924, Paris)The event was May 4th to July 27th. 44 participating countries and 3,089 athletes. The new stadium in Columbu, a suburb of Paris, was equipped with microphones for the first time, and an Olympic village was built nearby. It was a wooden barrack that accommodates four people per household, but it was a convenient facility for a small team. Prior to the event, the Winter Tournament, which could be considered a Zensho match, was held from January 25th to February 5th at Chamonix-Mont Blanc in South France. It was later recognized and became the first Winter Tournament. All of the events were heated, with Argentina defeating Western teams in Uruguay and Polo in soccer, and the unexpected country's performance in the tournament sparked the mood of the tournament. However, the championship for each sport was still secured by the United States. What is particularly noteworthy is Nurmi, Finland, who competed in the 5,000m race 30 minutes after winning the 1500m race and won the 5,000m race. This was also the case that American Weissmuller Johnny Weissmuller (1904-1984), who later became a film actor and became a famous film actor for his role as Tarzan, was active in swimming competitions. The marathon distance was constant at 42.195 kilometers, and tennis disappeared from the Olympics. Japan sent 19 athletes. In track and field, Oda Mikio (Oda Mikio) took sixth in the triple jump, while in swimming, Takaishi Katsuo (1906-1966) placed fifth in the 100-meter freestyle, fifth in the 1500-meter freestyle, Saito Ugiyo (1902-1944) placed sixth in the 100-meter backstroke, and fourth in the 800-meter relay. In wrestling, Naito Katsutoshi (1895-1969), a student at the University of Pennsylvania, finished third in the featherweight freestyle, and the Japanese sports world is now at its peak. Number of winners (1): 45 in the United States, (2): 14 in France and Finland. The following year, in 1925, the IOC officially promulgated the Olympic Charter, and took the opportunity to retire and become honorary chairman of life, with Belgium's Latour becoming the third president. [Suzuki Yoshinori] 9th Conference (1928, Amsterdam)になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Japan sent 43 athletes, including one female player (Hitomi Kinue), but Oda Mikio won the triple jump, while Nanbuchuhei finished fourth. Kimura Kazuo in the high vault, and Nakazawa Yonetaro (1903-1984) both took sixth in the pole vault, while Yamada Kanematsu (1903-1977) finished fourth in the marathon, and Tsuda Haruichiro (1906-1991) finished sixth. Hitomi Kinue, who was the first to participate, won second in the 800-meter race. However, the female athletes were considered to be too exhausting in this event, and the 17th tournament was not held until the 17th tournament. Meanwhile, Tsuruta Yoshiyuki (1903-1986) won the Olympic record in the 200-meter breaststroke, Takaishi Katsuo (1906-1966) placed third in the 100-meter freestyle, Irie Toshio (1911-1974) placed fourth in the 100-meter backstroke, and second in the 800-meter relay, making swimming Japan the world's most impressive. Number of winners (1) 22 in the US, 21 in the Germany, 3) 7 in the France. [Suzuki Yoshinori] 10th Tournament (1932, Los Angeles)になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In the pole vault where the US had monopolized the championship, Nishida Shuhei was a small runner up with American Miller William Waring Miller (1912-2008), finishing second by a small margin. In the equestrian, Nishi Takeichi rode the Uranus and became the winner of the Grand Shoten Showjutsu competition. Number of winners (1) America 44, (2) Italy 12, (3) France 11. [Suzuki Yoshinori] 11th Conference (1936, Berlin)になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In addition, Coubertin passed away in Geneva in 1937 after the tournament. [Suzuki Yoshinori] 12th Conference (1940, Tokyo-Helsinki)On July 15th, 1938, the Tokyo Conference was decided by a cabinet to repay the Tokyo Conference, citing the Sino-Japanese War. It was changed to Helsinki, but was cancelled due to World War II. The Winter Conference was also offered to be held in Sapporo, but was cancelled. Latour, chairman of the IOC, passed away in 1942, and Edström J. Sigfrid Edström (1870-1964), who worked hard to manage the Stockholm Conference, took over as vice-president, and officially became the fourth IOC president in 1946. [Suzuki Yoshinori] 13th Conference (London, 1944)It was cancelled due to World War II. [Suzuki Yoshinori] 14th Conference (London, 1948)になったんです。 English: The first thing you can do Number of winners (1): 38 in the United States, (2): 17 in the Sweden, (3): 10 in the Finland. The Soviet NOC was approved at the IOC General Assembly in 1951. [Suzuki Yoshinori] 15th Conference (1952, Helsinki)Opening ceremony July 19th - Closing ceremony August 3rd. 69 countries and 4,955 athletes. Finland, a small country in Northern Europe, lost its territory in the Soviet Union in World War II and lost territory in the Karelia region and paid compensation, but despite the long-standing aspirations, the Olympics were successfully bid. Using the facilities that had been prepared for a long time, combined with a sturdy national character, they held a well-organized tournament. Japan and Germany were invited to the tournament again, with 72 Japanese athletes (of which 11 female athletes) taking part. This tournament was the first time the Soviet Union participated since the Russian Revolution, but the level of the sport, including gymnastics, was high, and became a good rival to the United States. One athlete from the People's Republic of China, who was not a member of the IOC, was well-been allowed to compete in competitive swimming. China joined the IOC in 1953 and left in 1957. Nurmi, a local hero who played an active role in the pre-war Olympics, became the final runner on the torch relay and the tournament was livened up, and Zatopek won three events: the 5,000 meters, the 10,000 meters, and the marathon. Japan's promising Fujiyama Flying Fish Furuhashi Hironoshin did not do well, but in wrestling, Ishii Shohachi (1926-1980) won gold medal in freestyle bantamweight and achieved good gymnastics. Art competitions became an art exhibition from this tournament, and they stopped competing for superiority and inferiority. Number of winners (1) America 40, (2) Soviet 22, (3) Hungary 16. In addition, Brandage became the fifth IOC president in that year. [Suzuki Yoshinori] 16th Tournament (1956, Melbourne. Equestrian only Stockholm)になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Japan attracted attention, with 117 athletes (16 of which are female) participating, and gymnastics Ono Takashi (1931-) winning the gold medal with the iron bar. In wrestling, Sasahara Shozo (1929-) and Ikeda Mio (1935-2002) won the championship. The equestrian competition in Stockholm brought together the European royal family and recreated the glamorous era of medieval knighthood. The number of winners in equestrianism was (1) Sweden 3, (2) Germany 2, (3) England 1. Number of winners (1) Soviet 37, (2) America 32, (3) Australia 13. [Suzuki Yoshinori] 17th Conference (1960, Rome)になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The program was swapped at this tournament to leave the track and field after swimming, but this was due to the host city's intention that the event's star-studded track and field would be a lasting excitement. In the marathon, Abebe, an unknown newcomer from Ethiopia, ran barefoot and won a new record, giving a great inspiration to the sports world of emerging Africa. Japan sent 167 athletes (20 of which are women) and won 18 medals, including four gold medals. The main one was the gymnastics competition, the first to win the men's team overall championship. Number of winners (1) Soviet Union 43, (2) US 34, (3) Italy 13. [Suzuki Yoshinori] 18th Tournament (1964, Tokyo)Opening ceremony October 10th - Closing ceremony October 24th. 93 participating countries and 5,151 athletes. Tokyo, which gave up the 12th tournament in 1940, ran for the 17th tournament in 1952, failed. In 1959, representatives such as Governor Yasui Seiichiro and others were sent to the 55th IOC General Meeting in Munich, and finally successfully invited the bid. It was the first tournament in Asia and the first tournament run by people of color. The Tokyo Tournament's budget is said to be 1,080 trillion yen.になったんです。 English: The first thing you can do While the closing ceremony was cluttered, IOC President Brandage described the tournament as "not merely a success, but a monumental success." The designer of the indoor stadium, Tange Kenzo, and director Ichikawa Kon, who directed the film "Tokyo Olympics," were given an Olympic Diploma (certificate) and honored his achievements. There were six types of Olympic medals until 1972, but since then they were limited to two types: the Olympic Cup and the same diploma, and from 1975 they received the Olympic Order (gold, silver, and bronze). The competitions include track and field, boating, basketball, boxing, canoeing, cycling, fencing, soccer, gymnastics, weightlifting, hockey, wrestling, swimming and diving, modern pentaclasses, equestrians, shooting, water polo, yachts, and new volleyball and judo. The opening ceremony on October 10th stopped raining until the day before, and it was a good start. The Olympic Village was built in the wide forest of Meiji Jingu Gaien. Of the participating countries, 52 participating countries, and 16 newly participating countries were all nations of color, including Tanzania, which became independent this year. In addition to North Korea and Indonesia, North Korea and Indonesia visited Japan, but some athletes were ordered to be suspended by the International Federation after competing in Ganefo (Emerging Countries Competition), so both countries returned to Japan by the morning of the opening ceremony. The competition is also rich, with a world record of 47 and a new Olympic record of 111, and the teenagers were particularly prominent in swimming. Ethiopia's Abebe won the marathon for the second consecutive marathon, while Australia's Don Fraser Dawn Fraser (1937-) won the Olympics three times in a row in the women's 100-meter freestyle, and women's gymnastics Czechoslovakia's Chaslavska Věra Čáslavská (1942-2016) gained popularity. Japan's 355 players (61 of which were female) participated, winning 16 events after the US and Soviet Union. The breakdown includes five gymnastics, five wrestling, three judo, one boxing, one weightlifting, and one women's volleyball. The women's team, who was called the "witch of the Eastern" was a highlight of the tournament. As the tournament's slogan "One World is One", the opening ceremony was broadcast simultaneously to the US and Canada on the Sincom satellite, and was recorded and aired immediately to Europe. The opening ceremony had a TV viewership rating of 87.4%, and there is also an episode where Tokyo Telephone Bureau's out-of-city calls stopped perfectly during the women's volleyball final match between Japan and the Soviet Union. Number of winners (1): 36 America, (2): 30 Soviet Union, (3): 16 Japan. [Suzuki Yoshinori] 19th Conference (1968, Mexico City)になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Following on from last time, Czech Republic's Chaslavska, who won four gold medals in gymnastics, also attracted attention. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. This is also the first time that the final runner in the torch relay in a summer tournament has been a female active player. 183 people from Japan (30 of which are women) participated. Japan won six gymnastics, four wrestling, and one gold medal in weightlifting, and in the marathon, Kimihara Kenji (1941-) finished second in Ethiopia's Walde (1932-2002). Number of winners (1) America 45, (2) Soviet Union 29, (3) Japan 11. [Suzuki Yoshinori] 20th Tournament (1972, Munich)Opening ceremony from August 26th to September 11th. 121 participating countries and 7,134 athletes. The event was run to emphasize peace and freedom in order to alleviate the bad reputation that the 11th Conference under the Nazi rule was used to promote the nation's prestige. However, early on September 5th, a terrorist attack by a guerrilla organization called "Black September" occurred at the Israeli dormitory in the Olympic Village, killing 11 Israeli delegations. It was the biggest tragedy in the history of the Olympics. There were debates about whether to continue or cancel the conference, but after a day of condolence, the competition resumed, and the event was closed on the 11th. It was an impressive event that the Olympics have been filled with intense political, race and religion issues. Japan was marked the first feat in history, with 182 athletes (38 of whom, 38 women) taking part in Japan, winning four consecutive men's gymnastics team overall, and it was also impressive that the local East and West Germany were able to perform well. The US lost their unbeaten basketball and pole vault championships, but Spitz (1950-) participated in 13 swimming events alone, winning gold medals and a new world record seven. The dachshund, nicknamed Bardi, appeared for the first time as an Olympic mascot. Number of winners (1): 50 Soviet Union, (2): 33 US, (3): 20 East Germany. The demonstrations of the two events that were previously stipulated in the IOC regulations and were the authority of the Organizing Committee (also known as extra sports, martial arts and baseball were held at the Tokyo Games), were removed in 1973 due to the amendment to the regulations. However, although demonstrations can be conducted at the discretion of the host city, this is officially unrelated to the Olympics. [Suzuki Yoshinori] 21st Tournament (1976, Montreal)Opening ceremony from July 17th to August 1st. 92 participating countries and 6,084 athletes. The impact of the first oil shock caused the budget to jump four times the original, and political issues were also in danger of being cancelled several times, but the event was held. The lessons learned from Munich were also strict. The Taiwan and South Africa issues were in a state of confusion, and political issues were once again brought to the Olympics. The torch was lit by a laser beam from Greece, and then relayed to the venue, reflecting the times. Athletics were particularly impressive in the Caribbean countries, and there was a view that the Soviet Union's three consecutive Olympics wins in three consecutive Olympics, with the US as they moved from the stands to an era of dispersal of medals. In women's gymnastics, 14-year-old Romanian komaneci Nadia Comaneci (1961-), who was called the "white fairy," caught the hot topic seven times out of 10, while the women's swimming were the solo stage for East Germany's Ender (1958-), who was called the "white fairy." In boxing, Cuba's Steófilo Stevenson (1952-2012), won the second consecutive win in heavyweight history, the first time he won in a row. Japan has 213 players (61 of which are female) participating. Despite missing two talented athletes in the men's gymnastics team, the team made a comeback and won five consecutive Olympic games, and the women's volleyball championship was also a perfect victory, bringing back the "Oriental Witch" to the revival. Number of winners (1): 47 Soviet Union, (2): 40 East Germany, (3): 34 US. [Suzuki Yoshinori] 22nd Conference (1980, Moscow)Opening ceremony from July 19th to August 3rd. 80 participating countries and 5,179 athletes. The Olympics were the first in a socialist country to be the highest ever in both participating countries and participating personnel, but the Soviet invasion of Afghanistan at the end of 1979 boycotted the US, West Germany, Japan and other countries, and while the event was not as expected, the event attracted the attention of emerging countries. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [Suzuki Yoshinori] 23rd Tournament (1984, Los Angeles)Opening ceremony from July 28th to August 12th. 140 participating countries and 6,829 athletes. This is the second time in 52 years that the event was held in Los Angeles. Just before May 8th, the Soviet Union announced its participation in order to ensure the safety of its players. Several Eastern European countries such as East Germany and Poland, as well as 14 countries such as Cuba and North Korea also cancelled their participation, making it the so-called one-lung tournament, following the 1980 Moscow tournament. However, the number of participating countries and participating athletes reached the highest point. The US home country was overwhelming, and it was far ahead of Romania and West Germany. In fact, China, which participated for the first time, won a total of 32 medals, including 15 gold. 231 athletes from Japan (53 women) participated. Japan only achieved 10 gold, 8 silver and 14 bronze. American Carl Lewis (1961-) won gold medals in four events: the 100-meter, the 200-meter, the long jump, and the 400-meter relay. Japan's unbeaten men's gymnastics team overall, which Japan had unbeaten from the Rome Tournament to the Montreal Tournament, lost to the US and China, and finished third, but Gushiken Koji (1956-) won the individual overall championship, and finally retained his reputation as gymnastics Japan. In the judo indiscriminate class, Yamashita Yasuhiro won one match despite his leg strain, winning one match. The tournament was run as a tax-free "private competition" and was a profitable record due to the use of existing facilities, sponsorship money from sponsors, and labor costs through the massive recruitment of volunteers. Number of winners (1): 83 in the United States, (2): 20 in the Romania, (3): 17 in the West Germany. [Fukagawa Choro] 24th Tournament (1988, Seoul)開会式9月17日~閉会式10月2日。参加国159、選手数8391。東京大会に次いでアジアで2番目、第二次世界大戦後独立した国では初の開催となった。共同開催を主張した北朝鮮や、キューバなどが不参加であったものの、ソ連、東欧諸国が参加し、前回を上回る規模の祭典となった。各競技ではソ連、東欧勢が強さを発揮した。日本は259人(うち女子71)の選手が参加した。日本のメダル獲得は前回から半減した。 今大会はドーピング(薬物使用)問題で大きな波紋が生じ、男子陸上100メートル優勝のカナダのベン・ジョンソンBen Johnson(1961― )が筋肉増強剤使用で金メダルを剥奪(はくだつ)された。優勝数(1)ソ連55、(2)東ドイツ37、(3)アメリカ36。 オリンピックは巨大化し、都市や国家の負担の限度を超え始め、その継続のためにはコマーシャリズムの洗礼も受けざるをえない状態になってきた。 [深川長郎] 第25回大会(1992・バルセロナ)開会式7月25日~閉会式8月9日。参加国169、選手数9356。冷戦終結で政治的対立によるボイコットもなく、旧ソ連は合同チームEUN(Equipe Unie)の略称で参加し、ボスニア・ヘルツェゴビナ、南アフリカ共和国なども加わった。日本は263人(うち女子82)の選手を送り込み、オリンピック競泳史上最年少の14歳で金メダルを獲得した岩崎恭子(1978― )、けがを乗り越えて優勝した柔道の古賀稔彦(こがとしひこ)(1967―2021)、女子マラソン2位の有森裕子(1966― )らが話題を提供した。メダル獲得数の上位3国は、(1)旧ソ連112(うち金は45)、(2)アメリカ108(金は37)、(3)ドイツ82(金は33)。 [深川長郎] 第26回大会(1996・アトランタ)開会式7月19日~閉会式8月4日。参加国197、選手数1万0318。アメリカ・ジョージア州の州都で、近代オリンピック第1回アテネ大会(1896)以来、100周年大会となった。史上初めて全NOCが参加した。日本からは310人(うち女子150)が参加、金3、銀6、銅5の成績をあげた。アメリカのカール・ルイスが走幅跳びで8メートル50を跳び、35歳にして通算9個目の金メダルを手中にし世界的話題となった。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ101(うち金は44)、(2)ドイツ65(金は20)、(3)ロシア63(金は26)。 [深川長郎] 第27回大会(2000・シドニー)開会式9月15日~閉会式10月1日。参加国199、選手数1万0651。第16回メルボルン大会(1956)以来、2回目のオーストラリアでの開催であった。参加国・地域は前回を更新して199か国・地域に達し、さらに国連統治下の東チモールが個人資格での参加を特別に認められたため、実質的には200を数えた。開会式では、オリンピック史上初めて韓国と北朝鮮の合同入場行進が実現した。また陸上のフリーマンCathy Freeman(1973― )の聖火点火をはじめ、オーストラリアで古い歴史をもつ先住民(アボリジニー)の存在を随所に見せることを意識するなど、民族問題と平和的祭典を強く打ち出した演出が目だった。 競技種目は大幅に増えて28競技、300種目に及び、オリンピックの肥大化に拍車をかけた感ありの大会となった。競技としては、陸上競技や競泳での世界新記録も多く、プロ選手の参加も著しく増えるなどの話題があった。日本は268人(うち女子110)を送り、金5、銀8、銅5の成績をあげた。なかでも女子マラソンでは、高橋尚子(たかはしなおこ)が日本人女子として初めて陸上競技での金メダルを獲得。また、女子柔道48キログラム以下級では田村亮子(たむらりょうこ)(谷亮子)が優勝、女子競泳、ソフトボールの健闘など、女子選手の活躍が目だった。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ97(うち金は40)、(2)ロシア88(金は32)、(3)中国59(金は28)。 体操女子個人総合優勝のルーマニアのアンドレーア・ラドゥカンAndreea Rǎducan(1983― )が興奮剤使用で金メダルを剥奪(はくだつ)されるなど、近年問題となっているドーピングの発覚が多くみられ、大会の商業化、肥大化などの課題の解決も持ち越された。 [深川長郎] なお2007年、アメリカの陸上競技選手ジョーンズMarion Jones(1975― )はドーピングを認め、本大会で獲得した金メダル3個と銅メダル2個を剥奪されている。 [Editorial Department] 第28回大会(2004・アテネ)開会式8月13日~閉会式8月29日。参加国201、選手数1万0625。近代オリンピック第1回大会(1896)以来のギリシア・アテネで開催された。通常、開会式の入場行進はギリシアを先頭にしてアルファベット順に出場国が続き、最後に開催国の順となっているが、今大会では先頭はギリシア国旗のみで、以下、ギリシア語のアルファベット順に出場国が続き、最後にギリシア選手団が入場した。男子マラソンでは残り7キロメートルほどの地点で先頭を走っていたブラジルのデリマVanderlei de Lima(1969― )が乱入してきた男にコースから押し出されるというアクシデントにみまわれたが、3位でゴール。銅メダルとともに、オリンピック精神をたたえられピエール・ド・クーベルタン・メダルを授与された。 日本からは312人(うち女子171)が参加。女子マラソンの野口みずき(1978― )、水泳の北島康介らをはじめ体操男子団体総合、レスリング、柔道などで金メダルを16、銀を9、銅を12獲得した。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ103(うち金は35)、(2)ロシア92(金は27)、(3)中国63(金は32)。 [Editorial Department] 第29回大会(2008・北京(ペキン))開会式8月8日~閉会式8月24日。参加国204、選手数1万0942。1964年東京、1988年ソウルに続いて、アジアで開催されるのは3回目である。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ110(うち金は36)、(2)中国100(金は51)、(3)ロシア72(金は23)、メダル数ではアメリカに及ばなかったが、中国は金メダルの数で第1位となった。陸上男子100メートルと200メートルにおいて驚異的なタイムで世界新記録を更新したジャマイカのウサイン・ボルトUsain Bolt(1986― )や、男子水泳で8個の金メダルを獲得したアメリカのマイケル・フェルプスMichael Phelps(1985― )などが話題となった。日本は339人(うち女子169)が参加、北島康介が100メートル平泳ぎで世界新記録を出すなど、金9、銀6、銅10の成績をあげた。なお、開催前にチベット問題など中国の人権軽視問題が取り上げられ、欧米諸国で開催反対の動きがみられたが、大会は無事行われた。 [Editorial Department] 第30回大会(2012・ロンドン)開会式7月27日~閉会式8月12日。参加国・地域204、選手数約1万0500人。1908年、1948年に続く3回目で、同一都市では史上最多の開催となった。競技数は26、ボクシング女子が採用されたことにより、初めて男女とも全競技が実施された。メダル獲得数では、(1)アメリカ104(金は46)、(2)中国88(金は38)、(3)ロシア82(金は24)であるが、金メダルの数では29を獲得したイギリスが3位となった。日本は、レスリングフリースタイル女子55キログラム級の吉田沙保里(さおり)(1982― )と同63キログラム級の伊調馨(いちょうかおり)(1984― )がオリンピック3連覇を達成。さらにサッカー女子の「なでしこジャパン」が銀メダルを獲得するなど女子の活躍があり、金7、銀14、銅17の計38個で過去最多を記録した。しかし金メダルは男子柔道がゼロなど、伸び悩んだ。前回の北京大会に引き続き、陸上男子100メートル、200メートル、400メートルリレーでジャマイカのウサイン・ボルトが金メダルを獲得、また、競泳男子でアメリカのマイケル・フェルプスは4個の金メダルを獲得して、金メダル取得数を18と延ばし、史上最多記録を更新したあとに引退を表明した。なお、本大会では柔道やボクシングでの誤審が大きな問題となり、またバドミントンの女子ダブルスで、対戦の組み合わせを有利にするために、中国、韓国、インドネシアの選手が故意に負けようとしたとして失格になるという騒動があった。そのほか、男子サッカーの日本対韓国の対戦後、韓国の選手が竹島の領有問題に関するプラカードを掲げたため、オリンピックに政治問題を持ち込んだとして問題となった。 [Editorial Department] 第31回大会(2016・リオ・デ・ジャネイロ)開会式8月5日~閉会式8月21日。参加国・地域205と難民選手団、選手数約1万1000人。難民選手団は、紛争などのため母国から参加できない選手のために新設されたもので、10人が出場した。南米大陸初の開催となった。競技数はゴルフとラグビーフットボール(7人制ラグビー)が加わり28。メダル獲得数では、(1)アメリカ121(金は46)、(2)中国70(金は26)(3)イギリス67(金は27)であるが、金メダルの数では27を獲得したイギリスが2位となった。日本は、体操男子個人総合の内村航平(こうへい)(1989― )が連覇を果たし、レスリングフリースタイル女子で今回は58キログラム級となった伊調馨が個人種目4連覇、陸上男子400メートルリレーで銀メダルを獲得するなどの活躍があり、金12、銀8、銅21の計41個で歴代最多記録を更新した。ジャマイカのウサイン・ボルトは陸上男子100メートル、200メートル、400メートルリレーすべてで3連覇を達成、また、引退を撤回して臨んだ競泳男子、アメリカのマイケル・フェルプスは5個の金メダルを獲得し、金メダル取得数を23として、史上最多記録を更新したあと、ふたたび引退を表明した。なお、大会前にロシアの組織ぐるみのドーピングが発覚し、世界ドーピング防止機構(WADA)はロシア選手団の出場禁止を勧告したが、IOCは各種目の国際競技団体に十分な証拠を提示した選手のみを出場させることとし、当初予定された選手数の3分の2にあたる271人の出場を認めた。また、開会前は施設工事の遅れや治安面が懸念されたが、杞憂(きゆう)に終わった。 [Editorial Department] Winter Olympics冬の競技がオリンピック大会に加えられたのは第4回大会(1908・ロンドン)のフィギュアスケートが最初である。第一次世界大戦後の第7回大会(1920・アントワープ)でフィギュアのほかアイスホッケーが加えられた。翌1921年のIOC会議では本格的な冬季大会を開く提案があったが、北欧諸国は反対した。冬季大会は北欧のような地の利を得た所でなければ成功しないというのが表面上の理由であったが、すでに彼らが行っていた競技会、とくにノルウェーのホルメンコーレンでの大会で十分であるというのが本音であった。結局、テスト的にフランスで開くことになった。 [鈴木良徳] 第1回大会(1924・シャモニー・モンブラン)開会式1月25日~閉会式2月5日。参加国16、選手数258。アルプス登山の基地であったフランスの辺境シャモニーは当時まだ寒村であったが、村をあげて準備を進め、先進スポーツ都市の調査も行い、すばらしい大会を開いた。日本もスキーに参加を予定していたが、前年の関東大震災のため中止した。自然条件に恵まれ、当初は冬季オリンピック開催に反対した北欧諸国も参加し、冬季競技の先進国ぶりを発揮した。この年国際スキー連盟(FIS:International Ski Federation)が結成された。また、翌1925年のIOC総会で、この大会を第1回オリンピック冬季大会と呼称することになった。優勝数(1)ノルウェー4、フィンランド4、(2)オーストリア2。 [鈴木良徳] 第2回大会(1928・サン・モリッツ)開会式2月11日~閉会式2月19日。参加国25、選手数464。初参加の日本選手はスキー6人。夏の大会を開いたオランダは、平坦(へいたん)な国土ということもあり、冬季競技場がなかったので、スイスで開いた。会期中25℃が記録されるほど気温が高く、スピードスケートの1万メートルは中止したほどである。これ以後実に第10回大会まで冬季オリンピックは天候に災いされる。北欧諸国の活躍が目覚ましく、優勝数(1)ノルウェー6、(2)アメリカ・フィンランド・スウェーデン各2となった。 [鈴木良徳] 第3回大会(1932・レーク・プラシッド)開会式2月4日~閉会式2月15日。参加国17、選手数252。日本選手17。会場はニューヨーク州の交通不便な寒村であったが、アメリカは巨費を投じて施設をつくった。ただ50年来の暖冬異変で、スキーのコースなどは、レース前に80キロメートルも離れた場所に変更、カナダから雪を運んだ。スケートはアメリカ規則のオープンレース制で実施したので、ヨーロッパ選手との間に大きなトラブルが起こった。このためスピードスケートはアメリカが大勝したが、スキーは精鋭主義で参加した北欧の天下であった。優勝数(1)アメリカ6、(2)ノルウェー3、(3)フィンランド・スウェーデン・オーストリア・フランス各1。 [鈴木良徳] 第4回大会(1936・ガルミッシュ・パルテンキルヘン)開会式2月6日~閉会式2月16日。参加国28、選手数646。日本選手34(うち女子1)。この大会も気温に災いされたが、スキー、スケート会場ともナチス・ドイツの力で大きな仮設スタンドがつくられた。会場の周辺にまで反ユダヤスローガンがみられ、IOC会長ラトゥールHenri de Baillet-Lator(1876―1942)がヒトラーに厳重抗議して撤去させる一幕があった。スキーにアルペン競技が加えられたのはこの年が初めてである。女子種目としても初めてアルペン1種目が行われた。フィギュアスケートのソニア・ヘニーSonja Henie(1912―1969)は第1回大会に13歳で初参加し、その後この大会まで3回優勝、銀盤の女王といわれた。優勝数(1)ノルウェー7、(2)ドイツ3、(3)スウェーデン2。 [鈴木良徳] 第5回大会(1948・サン・モリッツ)開会式1月30日~閉会式2月8日。参加国28、選手数669。第二次世界大戦後の初大会。日本とドイツは招待されなかった。この大会も天候に恵まれなかった。アイスホッケーでアメリカから2チーム参加という珍しい事件が起きた。一つは国際アイスホッケー・リーグに加盟しているアメリカのアマチュア・ホッケー協会推薦のチームであったが、アメリカNOCはこれを認めず、独自のチームを編成した。しかしこのアメリカNOC編成のチームは国際リーグが承認しなかった。入場料目当てに2チームを認めた組織委員会は非難され、国際アイスホッケー・リーグが除名された。すぐリーグ側がIOCに陳謝し、アイスホッケーは正式競技として追認された。優勝数(1)スウェーデン4、ノルウェー4、(2)スイス3。 [鈴木良徳] 第6回大会(1952・オスロ)開会式2月14日~閉会式2月25日。参加国30、選手数694。日本選手13。ノルウェーの首都オスロの前名クリスティアニアがスキーの技術名称にあるように、初めて冬季競技の発祥地で開かれた。近代スキーの創始者の一人であるノルヘイムSondre Norheim(1825―1897)の生誕地モルゲダールからオスロまで冬季大会の最初のトーチリレーが行われた。首都を開催地としたのは冬季大会では初めてである。スピードスケートが室内リンクを使用したのも初めて。この大会から日本とドイツがふたたび招待された。北欧諸国はその面目にかけて活躍した。優勝数(1)ノルウェー7、(2)アメリカ4、(3)フィンランド・ドイツ各3。 [鈴木良徳] 第7回大会(1956・コルティーナ・ダンペッツォ)開会式1月26日~閉会式2月5日。参加国32、選手数821。日本選手10。イタリア北部の冬季競技の中心地だけに条件は良好であった。ソ連が初参加し、各競技に優れた成績をあげた。オーストリアのアントン(トニー)・ザイラーAnton Sailer(1935―2009)がスキー競技でアルペン三冠王に輝いた。ジャンプ競技では、フィンランド選手が手を腰につけるドロップスタイルで金・銀メダルを独占した。従来は両手を頭の前方に伸ばして飛ぶのが普通であった。日本チームとしては冬季大会初めての銀メダルを猪谷千春(いがやちはる)がスキー回転競技で手にした。優勝数(1)ソ連7、(2)オーストリア4、(3)フィンランド・スイス各3。 [鈴木良徳] 第8回大会(1960・スコー・バレー)開会式2月18日~閉会式2月28日。参加国30、選手数665。日本選手41(うち女子5)。アメリカの一企業家が、カリフォルニア州の雪崩(なだれ)で有名な「死の谷」の近くに巨費を投じて施設を設け、スケート・リンクはパイピング・リンクを採用するなどして大会を成功させた。競技ではソ連が圧倒的な強さを発揮した。女子スピードスケートが初めて正式種目として登場し、高見沢初枝(長久保初枝)(1935― )が3000メートルで4位となった。優勝数(1)ソ連7、(2)ドイツ4、(3)アメリカ3。 [鈴木良徳] 第9回大会(1964・インスブルック)開会式1月29日~閉会式2月9日。参加国36、選手数1091。日本選手48(うち女子6)。大会前ひどい雪不足で、練習中の選手2人が事故死したほどであった。ソ連が圧倒的な強さを発揮した。優勝数(1)ソ連11、(2)オーストリア4、(3)フィンランド・スウェーデン・ノルウェー・フランス・ドイツ各3。 [鈴木良徳] 第10回大会(1968・グルノーブル)開会式2月6日~閉会式2月18日。参加国37、選手数1158。日本選手62(うち女子9)。古い歴史をもち新興工業化に成功したフランスの都市が会場となり、大統領ドゴールの力の入れ方も大きなものであった。開会式が競技場でない大きな仮設スタジアムで行われたり、式典音楽に近代音楽を演奏するなどして、演出の新しさを示した。この大会から、これまで合同して参加していたドイツが東西二つに分かれて参加。また、セックス・チェックとドーピング検査も行われることになった。入賞者がメーカーの商標がはっきりわかるスキーを持って写真を撮ることは禁止された。 競技ではスキーでフランスのキリーJean-Claude Killy(1943― )が第7回大会のザイラーに次ぐ史上2人目のアルペン三冠王に輝いた。優勝数(1)ノルウェー6、(2)ソ連5、(3)フランス4、イタリア4。 [鈴木良徳] 第11回大会(1972・札幌)開会式2月3日~閉会式2月13日。参加国35、選手数1006。日本選手90(うち女子20)。1940年(昭和15)に開催が内定していたのを戦争のため返上した札幌が、今度は条件、成績とも良好な成果をあげた。冬季大会でいちばんたいせつなのは自然条件であるが、札幌は比較的天候に恵まれた。また支笏湖(しこつこ)を眼下に見下ろす恵庭岳(えにわだけ)の滑降コースと、冬季大会史上初めての海を望見できる手稲山(ていねやま)の回転コースは好評であった。日本チームとしては、冬では初めて、夏の大会も含めて3回目という同一種目金・銀・銅メダル独占の偉業を、スキーの70メートル級ジャンプで笠谷幸生(かさやゆきお)(1943― )、金野昭次(こんのあきつぐ)(1944―2019)、青地清二(1942―2008)が成し遂げた。ほかにもリュージュで大高優子(1950― )が5位、同じくリュージュ2人乗りBチームが4位と、国内で普及度の低い競技でも活躍した。冬季大会では初めて、オーストリアのシュランツKarl Schranz(1938― )がアマチュア違反で出場を拒否された。ドーピングで失格した選手も1人を出したが、冬季競技の非アマチュア化はIOCでも問題になった。優勝数(1)ソ連8、(2)東ドイツ・スイス・オランダ各4。 [鈴木良徳] 第12回大会(1976・インスブルック)開会式2月4日~閉会式2月15日。参加国37、選手数1123。日本選手57(うち女子6)。当初はアメリカのデンバーに決定していたが、環境破壊のおそれがあるとして市民投票で否決され、オーストリアのインスブルックが二度目の大会を引き受けることになった。できるだけ前回の施設を改善利用して、簡素な大会とすることをモットーとした。競技ではソ連が圧倒的な強さをみせて13種目に優勝、ついで東ドイツが7種目制覇と、社会主義国が優勢であった。日本チームの入賞者はゼロ。優勝数(1)ソ連13、(2)東ドイツ7、(3)アメリカ3、ノルウェー3。 [鈴木良徳] 第13回大会(1980・レーク・プラシッド)開会式2月13日~閉会式2月24日。参加国37、選手数1072。日本選手50(うち女子4)。第3回大会を開催したアメリカのレーク・プラシッドでふたたび開かれた。地元アメリカはハイデンEric Heiden(1958― )がスピードスケートで5個の金メダルをとり、アイスホッケーでソ連を押さえて優勝した。日本はスキーの70メートル級ジャンプで八木弘和(やぎひろかず)(1959― )が銀メダル、秋元正博(1956― )が4位。女子のスピードスケート500メートルで長屋真紀子(1955― )が5位、フィギュアスケートでは渡部絵美(1959― )が6位に入賞した。優勝数(1)ソ連10、(2)東ドイツ9、(3)アメリカ6。 [鈴木良徳] 第14回大会(1984・サラエボ/サライエボ)開会式2月8日~閉会式2月19日。参加国49、選手数1272。日本選手39(うち女子7)。共産圏国であるユーゴスラビアで初めて開催された。東ドイツはエンケKarin Enke(1961― )らの活躍で、スピードスケートの女子全4種目の金・銀メダルを独占した。フィギュアのペアではソ連が6連勝、アイスホッケーでも前回優勝のアメリカが初戦で敗退、ソ連が優勝。日本の北沢欣浩(きたざわよしひろ)(1962― )はスピードスケート男子500メートルで2位となり、スケート競技では日本初のメダリストとなった。スキーのノルディックではフィンランドのハマライネンMarja-Liisa Hämäläinen(1955― )が女子3種目に完全優勝した。優勝数(1)東ドイツ9、(2)ソ連6、(3)アメリカ・フィンランド・スウェーデン各4。 [鈴木良徳] 第15回大会(1988・カルガリー)開会式2月13日~閉会式2月28日。参加国57、選手数1423。日本選手48(うち女子11)。開催期間、参加国、選手数ともに前回を上回る大規模な大会となった。金メダル争いでは、ソ連が前回東ドイツに奪われた王座を奪回した。日本は黒岩彰(くろいわあきら)(1961― )(500メートル3位)、橋本聖子(1964― )(全5種目に入賞)らスピードスケート陣が健闘。橋本は同年開催されたソウル大会(夏季)で自転車競技にも出場した。優勝数(1)ソ連11、(2)東ドイツ9、(3)スイス5。 [鈴木良徳] 第16回大会(1992・アルベールビル)開会式2月8日~閉会式2月23日。参加国64、選手数1801。日本選手63(うち女子21)。冷戦終結後初めての大会で、旧ソ連がCIS(独立国家共同体)で、統一ドイツ、独立したバルト三国も参加した。アルベールビルを中心にフランスのサボア県全域で競技が行われた。日本は、ノルディック複合団体で金メダル、スピードスケートの黒岩敏幸(1969― )が銀メダルを獲得したほか、橋本聖子や、フィギュアスケートの伊藤みどりらの活躍で、7個のメダルを獲得、冬季大会としてはそれまでの最高の成績をあげた。橋本聖子は、この大会で、日本オリンピック委員会(JOC)が設けた報奨金制度の適用第一号となる。メダル獲得数の上位3国は、(1)ドイツ26(うち金は10)、(2)旧ソ連23(金は9)、(3)ノルウェー20(金は9)。 [深川長郎] 第17回大会(1994・リレハンメル)開会式2月12日~閉会式2月27日。参加国67、選手数1737。日本選手65(うち女子16)。従来の冬季大会と夏季大会の同一年開催を2年ごと交互開催に変更したため、この大会は前大会から2年後、ノルウェーの小都市リレハンメルでの開催となった。イスラエルがパレスチナ解放機構(PLO)と和解合意の成立で初参加し、南アフリカが34年ぶりに復帰した。日本はノルディック複合団体で金メダルを獲得し初の冬季オリンピック2連覇を達成した。同個人でも河野孝典(1969― )が銀メダルを獲得し、ほかの種目ではスキージャンプのラージヒル団体で銀メダル、スピードスケートで男子500メートルの堀井学(1972― )と女子5000メートルの山本宏美(1970― )がともに銅メダルを獲得したが、橋本聖子をはじめとして全体に低調な結果に終わった。メダル獲得数の上位3国は、(1)ノルウェー26(うち金は10)、(2)ドイツ24(金は9)、(3)ロシア23(金は11)。 [深川長郎] 第18回大会(1998・長野)開会式2月7日~閉会式2月22日。参加国72、選手数2176。日本選手166(うち女子66)。日本は金メダル5、銀メダル1、銅メダル4の成績をあげた。 [深川長郎] 第19回大会(2002・ソルト・レーク・シティ)開会式2月8日~閉会式2月24日。参加国77、選手数2399。日本選手109(うち女子48)。21世紀最初のオリンピックは、アメリカのロッキー山脈の西に位置するユタ州の州都ソルト・レーク・シティを中心にプロボー、オグデン等での開催となった。2001年9月に起きたアメリカ同時多発テロ事件後の大会とあって、厳戒態勢のなかで行われた。競技種目は7競技78種目で、日本はスピードスケート・男子500メートルで清水宏保(しみずひろやす)(1974― )が前回の長野大会金メダルに続いて銀メダルを、フリースタイルスキー・女子モーグルで里谷多英(さとやたえ)(1976― )が前回の金メダルに続いて銅メダルを獲得したが、メダルはこの二つにとどまった。しかし、8位以内の入賞数では長野大会の33に次ぐ27を数え、その点では成果をあげたといえる。メダル獲得数の上位3国は、(1)ドイツ35(うち金は12)、(2)アメリカ34(金は10)、(3)ノルウェー24(金は11)である。 開会式では、聖火の最終点火を、1980年レーク・プラシッド大会で当時無敵のソ連チームを破り金メダルを獲得したアメリカ・男子アイスホッケーチームのメンバーが務めた。また、テロにあった世界貿易センターの廃墟(はいきょ)から回収された星条旗が運び込まれるなど、話題の多い大会となった。 [深川長郎] 第20回大会(2006・トリノ)開会式2月10日~閉会式2月26日。参加国80、選手数2508。日本選手112(うち女子53)。イタリア北西部、ピエモンテ州の州都トリノを中心に、アルプスのセストリエール等での開催となった。イタリアでの冬季オリンピックは、1956年のコルティーナ・ダンペッツォ大会以来となる。競技種目は7競技84種目で、日本はフィギュアスケート女子シングルの荒川静香(あらかわしずか)が、日本人として史上初の金メダルを獲得。彼女の得意技イナバウアーが2006年の流行語大賞となるなど、広く話題となった。しかし、日本のメダルはこの一つにとどまった。8位以内の入賞数では42を数え、とくにスキーのアルペン回転競技での4位、カーリングの7位は健闘したといえる。メダル獲得数の上位3国は、(1)ドイツ29(うち金は11)、(2)アメリカ25(金は9)、(3)オーストリア23(金は9)である。 開会式は、仮面喜劇「コメディア・デラルテ」などを織り交ぜた幻想的なスペクタクル構成で、ヨーロッパの歴史をひも解く演目に続き、スカラ座のスターダンサー、イタリアのテクノロジーのシンボルとしてフェラーリF1チームが登場。女優のソフィア・ローレンら女性だけの8名が五輪旗を運んだのは史上初。 [深川長郎] 第21回大会(2010・バンクーバー)開会式2月12日~閉会式2月28日。参加国・地域82、選手数2566。日本選手94(うち女子45)。カナダ西部、太平洋側の都市バンクーバーで開催、カナダでの冬季オリンピックは1988年のカルガリー大会についで二度目である。競技種目は7競技86種目。開会式はオリンピック史上初となるスタジアム屋内で行われた。天候には恵まれず暖冬となり、ヘリコプターで雪を運び入れた会場もあった。また、リュージュの練習中に選手1名が死亡する事故が起きた。 日本選手では、スピードスケート男子500メートルの長島圭一郎(1982― )、スピードスケートの女子チームパシュート(団体追い抜き)、フィギュアスケート女子シングルの浅田真央が銀メダル、スピードスケート男子500メートルの加藤条治(かとうじょうじ)(1985― )、フィギュアスケート男子シングルの高橋大輔が銅メダルで、合計5個のメダルを獲得した。メダル獲得上位3国は、(1)アメリカ37(金は9)、(2)ドイツ30(金は10)、(3)カナダ26(金は14)。開催国カナダはメダル獲得数では第3位であったが、金メダルの獲得数は最多となった。 [Editorial Department] 第22回大会(2014・ソチ)開会式2月7日~閉会式2月23日。参加国・地域88、選手数2780。日本選手113(うち女子65)。ロシア連邦南西部、黒海北東岸に面する保養都市ソチで開催、旧ソ連邦で初の冬季オリンピック開催となった。競技種目は7競技98種目。比較的暖かい気候が続き、雪や氷のコンディションが思わしくないなかで競技が行われた。日本選手では、フィギュアスケート男子シングルの羽生結弦(はにゅうゆづる)(1994― )が金メダル、スキージャンプの男子ラージヒル個人で葛西紀明(1972― )、スキーノルディック複合のノーマルヒル個人で渡部暁斗(わたべあきと)(1988― )、スノーボードの男子ハーフパイプで平野歩夢(あゆむ)(1998― )、スノーボードの女子パラレル大回転で竹内智香(ともか)(1983― )が銀メダルなど、合計8個のメダルを獲得した。メダル獲得上位3国は、(1)ロシア33(金は13)、(2)ノルウェー26(金は11)、(3)カナダ25(金は10)。なお、大会終了後、ロシアの組織ぐるみのドーピングが明らかになり、IOCは金メダリスト2人を含む5選手を失格・オリンピックからの永久追放処分とし、計19人についてドーピングを認定、メダルも剥奪した。 [Editorial Department] 第23回大会(2018・平昌(ピョンチャン))開会式2月9日~閉会式2月25日。参加国・地域92、選手数2925。日本選手123(うち女子72)。なお、IOCは、前回大会で組織的なドーピング問題を起こしたロシア選手団の出場を認めず、ドーピングを行っていないことを証明できた選手のみ、個人資格、オリンピック旗のもとでの出場を認めた。韓国北東部、江原道(カンウォンド)の平昌で開催、フィギュアスケート、カーリング、アイスホッケーなどの氷上競技は、平昌から約20キロメートル離れ、日本海に面した都市、江陵(カンヌン)で実施された。アジアでの冬季オリンピックは札幌(1972)、長野(1998)に次いで三度目の開催。競技種目は7競技102種目。 日本選手では、フィギュアスケート男子シングルの羽生結弦が連覇を果たし、スピードスケートの女子チームパシュート、スピードスケート女子500メートルの小平奈緒(1986― )、スピードスケートのマススタートで高木菜那(なな)(1992― )が金メダルなど、金4、銀5、銅4と史上最多の計13個のメダルを獲得した。メダル獲得上位3国は、(1)ノルウェー39(金は14)、(2)ドイツ31(金は14)、(3)カナダ29(金は11)。なお、アイスホッケー女子で史上初めて韓国と北朝鮮の合同チームが結成された。 [Editorial Department] 『鈴木良徳著『オリンピック読本』改訂版(1952・旺文社)』 ▽ 『ピエール・ド・クベルタン著、カール・ディーム編、大島鎌吉訳『オリンピックの回想』(1962/新版・1976・ベースボール・マガジン社)』 ▽ 『M・アンドロニコス他著、成田十次郎他訳『古代オリンピック――その競技と文化』(1981・講談社)』 ▽ 『川本信正監修『オリンピックの事典――平和と青春の祭典』(1984・三省堂)』 ▽ 『日本オリンピック委員会監修『近代オリンピック100年の歩み』(1994・ベースボール・マガジン社)』 [参照項目] |||||Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
|
近代スポーツは19世紀のなかばごろからイギリスで組織され、施設に力を入れたアメリカの選手育成で発展普及してきたが、この各種類のスポーツを総合的に大成させたのがオリンピックであり、古代ギリシアに起源を有するスポーツの祭典を現代に復活させたものである。フランスの貴族クーベルタンはプロイセン・フランス戦争(1870~1871)に敗れた祖国を立て直すために、教育改革を主張しているうち、肉体と精神の調和を目ざす古代ギリシアの体育に魅せられるようになった。1894年IOC(国際オリンピック委員会、International Olympic Committee)を創設し、全世界の青年の平和の祭典としてオリンピックを4年ごとに定期的に開くことに成功した。IOCはすべての国にオリンピックへの参加を呼びかけることとし、また宗教・人種・政治によって差別待遇をすることを厳禁した。それに対し一部の国家からの抗議もあったが、それを克服したことがオリンピックを確固たるものにした。20世紀初頭を中心に各競技もそれぞれIF(国際競技連盟、International Sports Federation)を組織し、国際的に通用する競技規則を規定した。1980年代にはIOCに政治的な問題が持ち込まれ、その伝統が動揺した。1980年のモスクワ大会では、ソ連のアフガニスタン侵攻への抗議から諸大国の不参加という事態を招いた。それに対抗するかのように、1984年のロサンゼルス大会では、ソ連・東欧圏諸国を中心に不参加国が出た。また、各IFや各国NOC(国内オリンピック委員会、National Olympic Committee)の発言力も強くなっている。しかし、そのような状況下においても、IOCが公認する地域大会(アジア競技大会、パン・アメリカン競技大会など)を含め、世界のすべての競技会が、オリンピックを唯一の典型としているのは、その伝統的な実力を示すものである。1988年のソウル大会からは、この種の問題もなく開催されている。 [鈴木良徳] 古代オリンピア祭一般に古代オリンピックとよばれているが、古代ギリシアの祭典競技であり、定説によればおよそ1200年にわたり定期的に催された。 紀元前13世紀から始まったインド・ヨーロッパ語族の移動の第二陣がペロポネソス半島に定着したころから、オリンポス山の神々への奉納祭典に変化が生じてきた。トロヤ戦争を経た後に、英雄の葬礼や陣中の慰安のため軍技競技が行われ、これが祭典の行事に加えられるようになった。オリンピアで主神ゼウスを祭ったオリンピア祭は前776年に復活されたといわれるが、その起源は古くドーリス人の間で行われていた祭儀であるとするのが定説である。復活の年については、そのころフェニキアから文字が伝わって優勝者名が記録され始めたのが前776年の大会であり、それを第1回としたという説や、前1580年、前1195年、前884年を各創始年とする諸説がある。その後、デルフォイのアポロン神域で行われたピティアPythia祭(前582)、コリントスの海神ポセイドンを祭るイストミアIsthmia地峡祭(前582)、ゼウスのためのネメアNemea祭(前573)が始まり、これをギリシアの四大祭典競技という。オリンピアは半島の北西部の辺境にあったので内乱や興亡にあまり影響されず、オリンピア祭は紀元393年ローマの属州時代まで続いた。祭典は理由は明確でないが4年ごとに行われ、のちにシチリアのティーマイオス(前356?~前260?)などが、この4年を1オリンピアードOlympiadと名づけた。大会はその第1年に開かれ、記録のあるものとしては293回続いた。ただしJ・トインビーによると、非公式の「かくれオリンピア祭」が9世紀の終わりごろまでタイナロン岬で行われていたとしている。 他のギリシアの神域がそうであったようにオリンピアも狭かった(約2万5000平方メートル)ので、初めは短距離(1スタディオン、オリンピアでは191.27メートル)1種目で、前724年から、中距離競走、長距離競走、五種競技(幅跳び、円盤投げ、短距離競走、やり投げ、レスリング)、レスリング、ボクシングの順に徐々に加えられ、英雄時代から盛んであった戦車競走や競馬は前7世紀になってからであった。その後パンクラチオン(レスリングとボクシングを合成したような競技)、武装競走、ラッパ手競技、伝令競技が行われたが、戦車競走には二頭立て、四頭立てや駿馬(しゅんめ)、ラバなどの種別があり、競馬にも種別があったので、全大会を通じて行われたのは約19種目。ほかに、ほぼ満18歳以下の少年の競技が前7世紀から始まり、短距離競走、レスリング、五種競技、ボクシング、パンクラチオンの5種目があった。一つの大会で全競技行われたのではなく、全盛期でもだいたい十数競技といわれる。 祭典の時期は7月から9月(そのころのギリシアの1月から3月)の盛夏に開かれ、22回大会(前692)まで会期は1日のみであったが、前5世紀のなかばペルシアに勝ってギリシアの最盛期を迎え、オリンピア祭の会期も5日間と盛大になった。5日のうちには選手の宣誓式、祭儀、優勝者の招宴などが行われたが、その1日はかならず満月にあたっていた。豪華を極めるようになったオリンピア祭は政治家、軍人、文人の宣伝の場となり、参加各都市はその名誉のためには不正手段を使っても勝つことに熱中し、有望選手の引き抜き、審判(初め1人であったが、最盛期には12人となる)や相手選手を買収するなど、内部的には腐敗しきっていた。 参加資格は厳重で、純血のギリシア人で市民権を有すること、刑罰を受けたことがないこと、神に不敬の行いのないことのほか、最盛期には、自分の都市で訓練を受け、祭礼の前にはペロポネソス半島のエーリス地方で1か月の強化合宿を受け、その成績によって参加が判定された。市民権のない女子は参加できないばかりか、競技を見物することも厳禁されていた。参加者は戦車や馬の御者以外は全裸で試合をした。競技の規則も定められ、格闘競技で相手を殺すと判定負けとなり罰金が科せられ、目の中に指を突っ込むことや股間(こかん)を蹴(け)り上げることも禁じられていた。優勝者1人が決定され、それ以外の順位は認められなかった。優勝者の特権は、公式的にはオリーブの葉冠と大会の最後の日に神域の祝宴に招待されるだけであったが、実際には、自分の都市に帰ったときには社会的な地位と多額の賞金が贈られ、それが、スカウトされて他の都市に買われていく選手を生んで、大会を汚濁していった。また優勝者の記録の公認などはなかった。なお各都市は祭礼を高く評価していたため、ペルシア戦争に勝ったころまでは、祭典の前後3か月はいっさいの武力闘争を中止するという取り決めが各都市間でよく守られていた。しかしこれも第二次アッティカ海上同盟(前377)ごろから崩れ、会期中でさえオリンピアが兵火にみまわれた(前364)。ギリシア人一般に体育よりも弁説を尊ぶ風潮が出てきたことも見逃せない。アテネの体操場などで若者たちと哲学的会話を楽しんだソクラテスの罪状が、若者を肉体的鍛錬から離れさせ、好ましくない方向に導いたというものであったことは、この風潮が為政者にとって無視しえない影響力があったことを示している。マケドニアのフィリッポス2世が、彼による征服を恐れるギリシア人観衆の不興の視線のなかで競馬に優勝(前356)したのは、非ギリシア人として最初であった。その子アレクサンドロス大王は全ギリシアを統治下に置いたが、彼自身は競技に父ほどの興味を示さなかった。その後、ギリシアはローマに征服され、あるときは成年選手全部がローマに運ばれて、オリンピアでは少年競技だけが行われ(前80)、ネロの参加のために祭典が2年遅れる(後67)こともあり、祭典は名実ともに堕落した。 肉体を単なる魂の奴隷として軽視した初期キリスト教がローマ帝国内で着実に地歩を占め、紀元380年にテオドシウス帝はキリスト教を国教と定めて異教を弾圧した。最後に開かれた大会の翌年の394年にはオリンピア祭も禁止され、その後まもなく神殿は破壊された。フェイディアス作の金と象牙(ぞうげ)でできたゼウス像は運び去られ、オリンピアはまったくの廃墟(はいきょ)となり、さらに大地震や洪水で長く地中に埋没することとなった。19世紀の初めまでオリンピアの所在が不明であったのは、このあたりの地名が入植した人々の言語であるスラブ語に変わっていたためであった。 競技者として有名なのは、レオーニダス(競走)、ピロムプロトス(五種競技)、キオーニス(競走)、ヒッポステーネス(レスリング)、ミローン(レスリング)、ティーサンドロス(ボクシング)、ドリエウス(パンクラチオン)、テアゲネス(レスリング)、エウテューメネース(レスリング)、カイローン(レスリング)らがあげられる。彼らのなかには、オリンピア祭典だけでなく、ピティア祭など他の祭典競技で優勝した者もいる。また、数多い観覧者のなかにはピタゴラス、ヘロドトス、トゥキディデス、プラトン、ディオゲネスなどの著名人がいたことが種々の文献に記録されている。 [鈴木良徳] 近代オリンピックの胎動近代オリンピックの淵源(えんげん)はルネサンスに始まる。ルネサンスにより古代体育は再評価され、啓蒙(けいもう)主義がこれに拍車をかけた。さらに18世紀からの古典主義の思潮は、古代ギリシア・ローマ文化への関心を駆り立てた。その初期の鼓吹者ウィンケルマンは実際にオリンピアの発掘を志したが、中途で倒れた。彼の死の2年前の1766年には、イギリス人チャンドラーRichard Chandler(1738―1810)がオリンピア廃墟をみつけたが、トルコ政府の国外退去命令で発掘を断念しなければならなかった。このギリシアに対するヨーロッパ人の熱い思いは、独立軍に参加したバイロンなどの個人的行動だけでなく、1821~1829年のギリシア独立戦争に対するイギリス、フランスなどの国家的軍事援助の原動力の一つとなっていた。トルコに対する勝利ののち、バイエルンの王子からギリシア国王に迎えられたオットー1世Otto Ⅰ(1815―1867、在位1832~1862)は、フランス隊によるオリンピア発掘(1827~1829)、体育史家クラウゼJ. H. Krauzeの著書『オリンピア』の発刊(1838)、ベルリンにおけるクルティウスErnst Curtius(1814―1896)のペロポネソス半島旅行報告(1852)などに刺激されて、オリンピックの復活を計画し、1859年に第1回大会を開いた。しかし近代的スポーツの知識がなく失敗。第2回は1870年に開かれたが、これまた失敗に終わった。第3回はドイツ皇室が後援したクルティウス指揮のオリンピア発掘隊がギリシアに到着した1875年に開催されたが、参加者わずか24名。競走、幅跳び、三段跳び、やり投げ、円盤投げ、レスリング、棒登りが行われたが、成功とはいえなかった。ついで第4回は1889年、国王ゲオルグ1世の祝賀式典に時をあわせて行われた。この4回でギリシア独立記念復活オリンピックといわれる大会にピリオドが打たれた。 その後うずもれた古代ギリシアの遺跡発掘で古代オリンピア祭の輪郭がはっきりしてきたこともあり、体育による文教政策を実行しようとしていたクーベルタンは、1892年11月、これを復興させるためオリンピック競技大会を初めて提唱したが、ほとんど反響がなかった。1894年6月アマチュア問題を主要な議題として会場のパリ大学ソルボンヌ講堂に集まった12か国代表の前で、同月23日にクーベルタンはオリンピック競技復活を再度提案した。今回は、会場で、前年の1893年にデルフォイで発見されたアポロン讃歌にメロディをつけて歌手に歌わせるなどのムード作りが効を奏したのか、満場一致で大会の実施を決議、運営にあたるIOCを組織し、委員の選任はクーベルタンに一任された。これらの手順や選考にあたってクーベルタンは、ペリクレス(前495ころ―前429)時代の古代オリンピックの運営を参考にしたといわれる。クーベルタンは世界各国一流の政治家、軍人を推し、13か国15人を選んで推進に拍車をかけた。この6月23日を記念したのが「オリンピック・デー」である。 [鈴木良徳] 近代オリンピック第1回大会(1896・アテネ)会期ギリシア暦4月6日(太陽暦3月25日)~15日。参加国14、選手数241。ギリシア国民は、1896年にオリンピック大会をアテネで開催するというクーベルタンらの決定を歓迎した。しかし政府は、破産状態に近い財政などを考慮して冷淡な態度をとった。そのためクーベルタンはコンスタンティン皇太子(1960年ローマ大会ヨット部門の優勝者コンスタンティン皇太子(1940― )の祖父)を通してゲオルグ国王を動かし開催を決定させた。そして皇太子を長とする委員会をつくり、資金面などの対策をとることとなった。結果は、アレクサンドリア在住のギリシア人富豪アベロフGeorge M. Averoff(1815―1899)が92万ドラクマを寄付して主競技場を建設するなど目覚ましいものがあった。この主競技場は、古代競技場跡に大理石の近代造りとし、5万人を収容できる豪華なもので、走路は現在と逆の右回りの急カーブながら、1周400メートルのものであった。室内競技は、ルーマニア在住のE・ザッパスEvangelos Zappas(1800―1865)の遺志に従って従弟(いとこ)のK・ザッパスKonstantinos Zappas(1814―1892)が1887年に寄贈した室内体育館ザッペイオンで行われた。開会式には会場の内外に8万人が押しかけ、国王の開会の宣言のあと、パラマスKostis Palamas(1859―1943)が作詩、サマラスSpiro Samara(1861―1917)の作曲したオリンピック讃歌が歌われた。競技は陸上競技、体操、ウエイトリフティング、フェンシング、ボート、競泳、自転車、レスリング、テニス、射撃の10競技、43種目と発表されたが、ほかに予定していた水球、馬術、クリケットは取りやめ、ボートは荒天で中止となった。これら競技種目の内容については、古代ギリシアよりも、むしろクーベルタンが熱心に研究したイギリスのスポーツの影響が濃かった。本大会では優勝者と2位の者のみが賞を得た。優勝者は賞状、銀メダル、オリーブの冠、2位の者は賞状、ブロンズ(青銅)メダル、月桂樹(げっけいじゅ)の冠がその内容である。ギリシア人が伝統の競技と信じていた円盤投げをはじめ、水・陸競技の優勝はアメリカ人その他の外国勢に占められたので、彼らの落胆は大きかった。しかし古代ギリシアの栄光をたたえて加えられた、マラトンからアテネまでの距離39.909キロメートルのマラソン(フランス人でフランス学士院のブレアルMichel Bréal(1832―1915)の発案による。古代ギリシアではこのような長距離の競走はなかった)で、ギリシア人のスピリドン・ルイスSpyridon Louis(1873―1940)が力走して優勝、ギリシア全土を熱狂させた。アテネは近代オリンピックの出発をみごとに飾ったといってよい。優勝数(1)アメリカ11、(2)ギリシア10、(3)ドイツ7。 [鈴木良徳] 第2回大会(1900・パリ)5月14日~10月28日。参加国24、選手数997。この年パリで開かれる万国博覧会と共同主催で行うことがクーベルタンの意向であった。しかし、フランス陸上協会との反目、博覧会当局の無理解、オリンピック知識の欠如などから、混乱に始まり混乱に終わった大会であった。IOCは運営費にも事欠き、最後には、ブローニュの森のフランス・レーシング・クラブのグラス・コートを借りて陸上競技のみを行う始末であった。他の競技は万国博の付属競技会の名目で、最高4000フランから15フランの賞金が懸けられた。競技記録にも不明確な点があり、オリンピック大会の真意に沿わぬ大会であった。イギリスのクーパーCharlotte Cooper(1870―1966)が女子テニスのシングルスでオリンピック史上最初の女性優勝者となった。優勝数(1)アメリカ19、(2)フランス13、(3)イギリス11。しかし、この数字は明確とはいえない。 また、この大会から、初代会長のビケラスDemetrius Vikelas(1835―1908、ギリシア)にかわって、クーベルタンがIOC第2代会長となった。 [鈴木良徳] 第3回大会(1904・セントルイス)会期7月1日~11月23日。ただし、開会式は陸上競技開始の8月29日に行われた。参加国12、選手数651。前2回の大会で活躍したアメリカに報いるため大会は大西洋を渡った。シカゴとセントルイスが招致を争ったが、新大統領T・ルーズベルトの裁定で後者に決まった。フランスは派遣費の調達ができないという理由で参加しなかった。前大会の失敗にもかかわらず本大会もルイジアナ購入100年記念博覧会の余興的競技会として扱われ、飛行船ツェッペリンや無線電信が人気の的となった。加えて、おりから行われていたアメリカ陸上競技選手権大会に関心が集まった結果、寂しい大会となった。しかしアメリカの進んだスポーツ施設と用具は、ヨーロッパへの大きな刺激となった。競技はまたもアメリカの独壇場となったが、マラソンで珍事件が起こった。アメリカのローツFred Lorz(1884―1914)が炎天下のスタジアムに悠々と到着し歓呼のうちにゴールインした。大統領令嬢との記念撮影も済み、結果が発表されたあと、実はローツは20キロメートル地点で強い暑熱のため落後し伴走の自動車に収容されて元気回復、故障で自動車が止まっている間にまた走り出して「優勝」したことが判明。本物の1着であるアメリカのヒックスTomas Hicks(1875―1963)に金メダルが与えられた。これがいまに残る「きせるマラソン」として有名な珍話である。この大会の会場は主としてワシントン大学で、飛込などはドイツ選手の指導でミシシッピ川を使った。大学の東に接するフォレスト公園が博覧会場で、そこには急造のホテルがつくられた。一部の競技者も宿泊したのでオリンピック村の元祖といわれている。優勝数(1)アメリカ70、(2)キューバ5、(3)ドイツ4。 [鈴木良徳] アテネ国際競技会(1906・アテネ)第二次世界大戦前までは、オリンピック中間大会とよばれたもので、戦後は正式大会からは除外されている。第1回大会後、以後の大会もギリシアで開催すべきというギリシア人の熱狂的な雰囲気により、クーベルタンは次期大会開催地を容易には決定できなかった。彼は世論の緩和策として、4年ごとの中間年にアテネで特別大会を開催するという約束をギリシア皇太子と結び、それを受けて開かれたものである。前回の大会がアメリカだったので、多くのヨーロッパ諸国がこぞって参加した。参加国22、選手数883。 [鈴木良徳] 第4回大会(1908・ロンドン)会期4月27日~10月31日。参加国22、選手数2008。この大会も英仏博覧会と同時開催だったが、博覧会からは資金を借りただけで運営された。競技運営を関係競技団体に任せて行い、競技ルールもかなり整備されるなど、次回のストックホルム大会とともに、以後の大会運営の基礎をつくった大会として評価されている。それまでの自由な参加申込方式を廃し、各国に各競技の国内統轄団体NOCを組織し、そこを通した申込みだけを認めることとした。開会式には各国の国旗を先頭に入場行進が行われた。また、初めてOOC(大会組織委員会、Olympic Organizing Committee)が、大会運営のため組織されることになった。ただこの大会では二大スポーツ国であるイギリス、アメリカの独立戦争以来の感情的軋轢(あつれき)が最高潮に達した時期で、アマチュア資格問題、競技規則問題などで感情を対立させ、多くのトラブルを起こした。これを見かねたセント・ポール寺院のペンシルベニア司教タルボットEthelert Talbot(1848―1928)が日曜のミサに集まった各国選手に「オリンピックで重要なことは勝つことでなく参加することである」と説教した。これに感動したクーベルタンは、のちにこのことばをオリンピックの理想とした。なお、オリンピック・モットーとしての「より速くcitiusより高くaltiusより強くfortius」は、ドミニコ教団のディドン神父Henri Didon(1840―1900)が発案したもので、クーベルタンが1897年から採用したが、IOCで公認されたのは1926年である。マラソンはこの大会で初めて42.195キロメートルコースを走ったが、「ドランドの悲劇」とよばれる事件が起きた。競技場に到着したイタリアのドランドDorando Pietri(1885―1942)が倒れ、役員らに介抱されつつゴールインしたが、そのことが反則とされ、優勝が取り消された。イギリスのアレクサンドラ皇后Alexandra(1884―1925)がこれに同情し、彼に金カップを贈ってその労をねぎらったという。このときのマラソンの距離が第8回大会以後正規の距離となった。冬季競技のフィギュアスケートが初登場したのも一つの話題である。優勝数(1)イギリス56、(2)アメリカ23、(3)スウェーデン7。 [鈴木良徳] 第5回大会(1912・ストックホルム)会期5月5日~7月27日。参加国28、選手数2407。IOC創設以来協力したスウェーデン王室が先頭にたち、主競技場新設などにも国家や市の協力があり、陸上競技では電気時計での記録計測や、決勝の写真判定器採用などがあり、オリンピックもようやく本格的に運営され始めた。前大会に次いでヨーロッパの皇帝、王室、貴族などから各種の賞品も授与された。また、この大会から陸上競技に五種と十種の混成競技、新しく近代五種競技と馬術、女子種目としての水泳、さらに古代オリンピア祭に倣って絵画コンクールなどの芸術競技が追加された。ボクシングはスウェーデンの国内法の禁止規定により行われなかった。陸上競技の長距離で帝政ロシアの支配下にあったフィンランドのコーレマイネンHannes Kolehmainen(1889―1966)が5000メートル競走、1万メートル競走、8000メートルクロスカントリーの3種目に優勝、注目を浴びた。ハワイ出身のカハナモクDuke Paoa Kahanamoku(1890―1968)が水泳でクロール泳法をみせて100メートルに優勝、またアメリカ先住民出身のジム・ソープJim Thorpe(1888―1953)が混成2種目に優勝、有色人種の活躍が目だち始めたのもこの大会からであった。しかしソープは、かつて野球のプロ行為に関係していたと認定され、翌1913年のIOC総会でアマチュア資格を剥奪(はくだつ)され、金メダルの返還を命ぜられた。メダルを返上させられた第一号であったが、1982年10月になって彼の姉妹やフォード元大統領の復権運動が実り、失格が取り消された。 1909年にIOC委員に選ばれた嘉納治五郎(かのうじごろう)の努力で、日本はこの第5回大会から参加することになった。当時日本のスポーツ界は学生中心で組織もなかったので、1911年(明治44)に大日本体育協会(国際的には日本オリンピック委員会Japanese Olympic Committee略してJOCという)を創立し、予選会を開いた結果、短距離の三島弥彦(みしまやひこ)(東京帝大)とマラソンの金栗四三(かなくりしそう)(東京高師)を派遣することにした。金栗は予選会で当時の世界記録を破る大記録で走り大いに期待されたが、大会のマラソン走行中に腹痛をおこしレースを棄権、三島も400メートル予選を通過しただけで、第二次予選に出ても勝つ見込みがないとして棄権してしまった。優勝数(1)スウェーデン24、アメリカ24、(3)イギリス10。 [鈴木良徳] 第6回大会(1916・ベルリン)1914年6月13日からパリでIOC創設20周年記念式典が行われたとき、クーベルタンは「オリンピック旗」を考案した。6月28日にサライエボ事件(サラエボ事件)が突発、第一次世界大戦となり、ついにベルリン大会は中止となった。 1915年にIOCはスイスのローザンヌに移り恒久的な本部を置いた。 [鈴木良徳] 第7回大会(1920・アントワープ)会期4月20日~9月12日。参加国29、選手数2626。戦禍を被って荒廃したベルギーの青年たちへ心の糧(かて)として贈られた大会で、準備期間は短かったが、のちにIOC会長となるラトゥールHenri de Baillet-Latour(1876―1942)を組織委員長として3万人収容の主競技場や沼を仕切ったプールの築造、テニスコートには全天候型のアンツーカーを採用するなど最大の努力が払われた。この大会では、戦争責任を問う意味でドイツ、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、トルコの参加は許されなかったが、第一次世界大戦の結果独立したバルト三国、チェコスロバキアなどが参加した。フィンランドも完全な独立国として初めて参加した。メーンポールには新創案のオリンピック旗が翻り、古代オリンピア祭に倣う選手宣誓も行われ、以後選手宣誓は世界的流行となった。「飛ぶフィンランド人」といわれたヌルミが、1万メートル競走、1万メートルクロスカントリーで優勝。第5回大会の勇者コーレマイネンがマラソンを制覇したことなどが話題となった。日本は各種競技に15人の選手を送ったが、体育協会は代表団の大部分を米英回りで派遣した。名目は先進国の視察だったが、実は在留邦人から寄付を集めるのが目的だった。この大会ではテニスの熊谷一弥(くまがいいちや)がシングルスで、また柏尾誠一郎(かしわおせいいちろう)(1892―1962)とともにダブルスで銀メダルを獲得し日本初のメダリストとなった。優勝数(1)アメリカ41、(2)スウェーデン17、(3)フィンランド14。 [鈴木良徳] 第8回大会(1924・パリ)会期5月4日~7月27日。参加国44、選手数3089。パリ郊外コロンブの新設競技場には初めてマイクロホンが設備され、近くにオリンピック村が仮設された。1戸4人収容の木造バラックだったが、少数チームには便利な施設であった。大会に先だち、1月25日から2月5日まで南フランスのシャモニー・モンブランで、この大会の前哨(ぜんしょう)戦ともいえる冬季大会が催された。のちに公認されて第1回冬季大会となった。競技はいずれも熱を帯び、サッカーでウルグアイ、ポロでアルゼンチンが欧米チームを破り、予期しない国の活躍は大会のムードを盛り上げた。しかし、各競技の王座は依然アメリカが確保した。特筆されるのはフィンランドのヌルミで、1500メートル競走で優勝した30分後に5000メートル競走に出場して優勝した。のちに映画俳優となりターザン役で名を売ったアメリカのワイズミューラーJohnny Weissmuller(1904―1984)が水泳競技で活躍したのもこの大会であった。また、この大会からマラソンの距離が42.195キロメートルに一定され、テニスがオリンピック種目から姿を消した。日本は19人の選手を送った。陸上では織田幹雄(おだみきお)が三段跳びで6位に食い込み、水泳では高石勝男(1906―1966)が100メートル自由形で5位、1500メートル自由形で5位、斎藤魏洋(さいとうぎよう)(1902―1944)が100メートル背泳で6位、800メートルリレーは4位であった。レスリングではペンシルベニア大学学生の内藤克俊(1895―1969)がフェザー級のフリー・スタイルで3位入賞など、日本スポーツ界はここに萌芽(ほうが)期を迎えた。優勝数(1)アメリカ45、(2)フランス・フィンランド各14。 翌1925年、IOCはオリンピック憲章を正式に公布、それを機会にクーベルタンは引退して終身名誉会長となり、ベルギーのラトゥールが第3代会長となった。 [鈴木良徳] 第9回大会(1928・アムステルダム)会期5月17日~8月12日。参加国46、選手数2883。開催国オランダは準備の途中で、オリンピックが非キリスト教的であるとする反対意見のため、国の補助金支出ができなくなり、資金難で一時開催が危ぶまれたが、インドネシアなど植民地在住のオランダ人の援助が契機となり、施設が完備した。主競技場は全天候型のアンツーカー舗装であったが、会期中は多雨低温に悩まされ、開会式2日前に完成したこともあって軟弱であった。大会は、16年ぶりに敗戦国ドイツ、オーストリアなどが参加し、陸上競技で初めて女子競技も行われることになった。主競技場に建てられたマラソン塔には、会期中オリンピックの火が燃え続けた。本大会から、開会式の行進の先頭にギリシアがたつことになった。またインドがホッケーで初優勝(第16回大会まで優勝を続けることとなる)、サッカーではウルグアイが前回に引き続き優勝した。この大会は日本にとっても初の金メダル獲得者が出る画期的なものとなった。日本は女子1人(人見絹枝(ひとみきぬえ))を含む43人の選手を送ったが、織田幹雄が三段跳びで優勝、南部忠平(なんぶちゅうへい)は4位。走高跳びでは木村一夫が、棒高跳びでは中沢米太郎(1903―1984)がともに6位を占め、マラソンでは山田兼松(1903―1977)が4位、津田晴一郎(1906―1991)が6位となった。初めて出場した人見絹枝は800メートル競走で2位を獲得した。しかし、この種目は女子選手の消耗ぶりがあまりにも激しいとされ、第17回大会まで行われなかった。一方、水泳も鶴田義行(つるたよしゆき)(1903―1986)が200メートル平泳ぎにオリンピック新記録で優勝、高石勝男(1906―1966)が100メートル自由形で3位、入江稔夫(いりえとしお)(1911―1974)が100メートル背泳で4位、800メートルリレーでも2位を獲得した活躍ぶりは、水泳日本を世界に印象づけることとなった。優勝数(1)アメリカ22、(2)ドイツ11、(3)フランス7。 [鈴木良徳] 第10回大会(1932・ロサンゼルス)開会式7月30日~閉会式8月14日。参加国37、選手数1332。開催が決まってから9年間の準備期間を経て、大会3年前に完成していたオリンピック公園、10万5000人収容の大競技場(1984年の第23回大会もここが主競技場)、プール、それに美術館、オーディトリアムなど付属施設も当時最大のもので、民間の手で豪華な大会を運営した最初の大会ともいえた。またコテージ風のオリンピック村は男子の役員・選手を全員宿泊させるりっぱなものであった。しかしアメリカ大陸に渡るという資金難から、ヨーロッパからの参加国が少なかった。日本は131人(うち女子16)という大量の選手を派遣し、優勝7、メダル獲得数18という成果を収め、初参加から20年で初めてスポーツにおいて国際的な地位を得た。とくに競泳では男子6種目中5種目に優勝し、陸上では三段跳びで南部忠平が優勝。アメリカが優勝を独占していた棒高跳びでは、西田修平がアメリカのミラーWilliam Waring Miller(1912―2008)と一騎打ちを演じて少差で2位であった。また馬術では西竹一(にしたけいち)がウラヌス号に騎乗して、大賞典障害飛越競技の覇者となった。優勝数(1)アメリカ44、(2)イタリア12、(3)フランス11。 [鈴木良徳] 第11回大会(1936・ベルリン)開会式8月1日~閉会式8月16日。参加国49、選手数3963。ナチス総統である独裁者ヒトラーが国威宣揚を念頭に準備したこの大会は、オリンピック史上初めてすべての面に強い軍の協力があり、第10回大会をしのぐ豪壮な設備を整えた大祭典となった。反面、ナチ党旗のハーケンクロイツを初めてドイツ国旗として使用し、会場の内外に氾濫(はんらん)させるなど政治色の強い大会であった。古代ギリシアをしのぶように優勝者には金メダルのほかオリーブとカシの苗木を与えた。初めてトーチリレーが行われた。ギリシアの神殿跡で太陽の光線からとった火が、青年たちによって会場のベルリンまで運ばれた。本大会では、ドイツ軍参謀本部の兵要地誌調査に悪用されたとはいえ、のちにこのトーチリレーはオリンピックには欠くことのできない象徴的な儀式となった。競技内容も充実し、世界・オリンピック新記録が150以上も生まれ、世界記録の大会とよばれた。多くの英雄が生まれたが、短距離、走幅跳び、400メートルリレーに三つの世界記録を出し四つの金メダルを獲得したアメリカのオーエンスがとくに有名。経費を惜しまずにレニ・リーフェンシュタールが制作したオリンピック記録映画『民族の祭典』と『美の祭典』が知られる。日本も東京大会招致を目ざして179人(うち女子17)の選手が参加し、水陸とも大活躍をした。棒高跳びでは西田修平と大江季雄(おおえすえお)がアメリカのメドウスEarle Elmer Meadows(1913―1992)と延々5時間の熱闘を演じ、2、3位を分けあった。のち両選手は銀と銅のメダルを半分に切って継ぎ合わせ、各自が所持するという「友情のメダル」が生まれた。また、長距離2種目で村社講平(むらこそこうへい)はいずれも4位とはいえ、強豪の北欧選手に伍(ご)しての奮闘は国際的な反響をよんだ。マラソンでは、朝鮮出身の孫基禎(そんきてい/ソンキジョン)が金メダルを獲得した。さらに女子水泳の前畑秀子(のち、兵藤秀子)が200メートル平泳ぎで、ドイツのゲネンゲルMartha Genenger(1911―1995)と大接戦を展開、日本の女子選手として初の金メダルを獲得した。実況放送を担当したNHKアナウンサー河西三省(かさいみつみ)(1898―1970)の「前畑がんばれ」の絶叫は、競技が行われたのが日本時間の深夜であったにもかかわらず、日本国民の興奮をよんだ。優勝数(1)ドイツ38、(2)アメリカ24、(3)ハンガリー10。 なお、この大会後の1937年にクーベルタンがジュネーブで死去した。 [鈴木良徳] 第12回大会(1940・東京―ヘルシンキ)東京大会は1938年(昭和13)7月15日、日中戦争を理由に返上を閣議決定。ヘルシンキに変更されたが、第二次世界大戦が起こり中止。冬季大会も札幌開催が内定していたが、中止となった。 IOC会長ラトゥールが1942年死去し、ストックホルム大会で運営に尽力したエドストレームJ. Sigfrid Edström(1870―1964)が副会長のまま実権を握り、1946年正式に第4代IOC会長となった。 [鈴木良徳] 第13回大会(1944・ロンドン)第二次世界大戦のため中止となる。 [鈴木良徳] 第14回大会(1948・ロンドン)開会式7月29日~閉会式8月14日。参加国59、選手数4104。ドイツの爆撃で大きな被害を受けたロンドンでの開催は、運営も設備もかなり苦しかったが、各国の協力と新興国の参加でベルリン大会よりはるかに多数が集まった。日本はドイツとともに枢軸国であったという理由で参加できなかったが、いち早く降伏したイタリアは参加した。またトーチリレーはナチスのまねであるとして反対され、さらにオリンピック無用論まで飛び出したが、競技が進むにつれ、この極論は影を潜めた。競技内容は低調だったが、話題をまいたのはオランダのブランカース・クンとチェコスロバキアのザトペックであった。二児の母親クンは100メートル競走、200メートル競走、80メートル障害の3種目に優勝、400メートルリレーのアンカーも務め3人を抜いてゴールイン、4個の金メダルを得た。ザトペックは1万メートルに優勝、5000メートルで2位になった。優勝数(1)アメリカ38、(2)スウェーデン17、(3)フィンランド10。 1951年のIOC総会でソ連のNOCが承認された。 [鈴木良徳] 第15回大会(1952・ヘルシンキ)開会式7月19日~閉会式8月3日。参加国69、選手数4955。北ヨーロッパの小国であるフィンランドは、第二次世界大戦でソ連に敗れてカレリア地方などの領土を失い、賠償金を支払いながらも、十数年前からの熱望がかない、オリンピック招致に成功した。長い間準備していた施設を利用し、質実な国民性と相まって、よく組織された大会を開いた。日本とドイツもふたたび大会の招待を受け、日本から72人(うち女子11)の選手が参加した。この大会からソ連がロシア革命以来初めて参加したが、体操をはじめとしてその競技レベルは高く、アメリカの好敵手となった。またIOCに加盟していなかった中華人民共和国の選手1人が好意的に競泳に出場を許された。中国は翌1953年IOCに加盟、1957年に脱退した。戦前のオリンピックで活躍した地元の英雄ヌルミがトーチリレーの最終走者になって大会を盛り上げ、競技ではザトペックが5000メートル、1万メートル、マラソンの3種目で優勝した。 日本は期待の「フジヤマのトビウオ」古橋広之進が振るわなかったが、レスリングでは石井庄八(いしいしょうはち)(1926―1980)がフリースタイルバンタム級で金メダル、体操も好成績を収めた。芸術競技は、この大会から芸術展示となって、優劣を争うことをやめた。優勝数(1)アメリカ40、(2)ソ連22、(3)ハンガリー16。 また、この年ブランデージが第5代IOC会長となった。 [鈴木良徳] 第16回大会(1956・メルボルン。馬術のみストックホルム)開会式11月22日~閉会式12月8日。参加国72、選手数3314。南半球での初の大会であったが、IOCはこの決定のとき重大なミスを犯した。オーストラリアの法律では馬の移輸入に6か月の検疫期間があることに気づかなかったのである。そのため馬術競技だけが29か国チームを集め、6月10日から17日まで、ストックホルムで開かれるという、一都市開催を規定した憲章に違反する変則的な形となってしまった。メルボルンの準備も、一時放棄の段階にきたと思われるほど進捗(しんちょく)しなかった。大会直前スエズとハンガリーに動乱が起こり、大会出場のハンガリー選手のアメリカ亡命事件や、水球におけるハンガリー対ソ連戦での乱闘事件などが起きた。競技はソ連とアメリカの白熱戦に終始したが、水泳で地元オーストラリアが男女13種目中8種目に優勝した。日本は117人(うち女子16)の選手が参加、体操の小野喬(おのたかし)(1931― )が鉄棒で金メダルを獲得するなど、注目を集めた。レスリングでは笹原正三(ささはらしょうぞう)(1929― )、池田三男(1935―2002)が優勝。 ストックホルムでの馬術競技は、ヨーロッパ王室を一堂に集め、中世騎士道華やかな時代を再現した形であった。馬術だけの優勝数は(1)スウェーデン3、(2)ドイツ2、(3)イギリス1であった。優勝数(1)ソ連37、(2)アメリカ32、(3)オーストラリア13。 [鈴木良徳] 第17回大会(1960・ローマ)開会式8月25日~閉会式9月11日。参加国83、選手数5338。ローマはオリンピックが始まってから第4回大会にも立候補したが、国内事情で辞退、1940年の第12回大会は東京に譲るなど、ヘレニズム世界の中心都市としては恵まれない立場にいた。待望の機会到来に、ローマは施設整備に力を入れた。会場は、戦前のムッソリーニの構想どおり新旧市街に分散、その間にある古代ローマの遺跡カラカラ浴場やローマ市場などを利用して主競技場、近代風建築の円型体育館などを新設。聖火はかつてカエサルの凱旋(がいせん)した石畳のアッピア街道を走り、マラソンコースはカンピドリオ丘にある市庁舎前からアッピア街道を走ってコンスタンティヌス凱旋門をゴールとするなど歴史的舞台装置には事欠かなかった。この大会で水泳を先に、陸上を後にするプログラムの入れ換えが行われたが、大会の花形競技陸上によって最後に盛り上がりをもってくるという開催都市の思惑によるものであった。マラソンではエチオピアの無名の新人アベベが、はだしのまま走って新記録で優勝し、新興アフリカのスポーツ界に大きな刺激を与えた。日本は167人(うち女子20)の選手を送り、金メダル4個を含む18個のメダルを得た。そのおもなものは男子団体総合優勝を初めて獲得した体操競技であった。優勝数(1)ソ連43、(2)アメリカ34、(3)イタリア13。 [鈴木良徳] 第18回大会(1964・東京)開会式10月10日~閉会式10月24日。参加国93、選手数5151。1940年の第12回大会を返上した東京は、1952年、第17回大会に立候補したが失敗した。1959年、ミュンヘンで開かれた第55回IOC総会に安井誠一郎都知事などの代表を送り、ようやく招致に成功した。アジアで初めて開く、また有色人種の運営する最初の大会となった。東京大会の予算は1兆0800億円といわれる。これは、国費で建造した各種競技施設、国立屋内総合競技場、国立競技場拡張費、東京都が建造した駒沢(こまざわ)オリンピック公園、選手村、競技場と空港を結ぶ高架道路建設費、主要道路改良費、外国人宿泊施設拡充の補助金、東海道新幹線の建設費などだが、大会の直接運営費は98億5800万円で、そのうち国と東京都の補助金がそれぞれ16億8000万円、オリンピック資金財団を主とする寄付金28億5500万円、入場料16億0900万円を含む事業収入が30億5200万円となっている。ほかに選手強化費が約20億円。巨費を投じただけに各施設は高水準に仕上がった。競技の運営も、科学施設やそれまでの用具を改良して採用し、競技の進行と審判の正確さは高く評価された。IOC会長ブランデージは、閉会式を乱雑としつつも、本大会を「単なる成功ではない、記念碑的成功である」と評した。屋内総合競技場の設計者丹下健三(たんげけんぞう)と映画『東京オリンピック』の監督市川崑(いちかわこん)にはオリンピック・ディプロマ(賞状)が贈られ、その功績がたたえられた。なお、このオリンピックの栄章は1972年まで6種類あったが、その後オリンピック・カップと同ディプロマの2種類に制限され、1975年からはオリンピック・オーダー(金・銀・銅)が贈呈されている。 競技は陸上、ボート、バスケットボール、ボクシング、カヌー、自転車、フェンシング、サッカー、体操、ウエイトリフティング、ホッケー、レスリング、競泳と飛込、近代五種、馬術、射撃、水球、ヨットのほか、新しくバレーボールと柔道が加わって20競技。10月10日の開会式は前日までの雨もやんで快晴、幸運なスタートを切った。オリンピック村は明治神宮外苑(がいえん)の広い森林の中につくられた。参加国のうち、有色人種の参加国が52か国、新参加の16か国は、この年独立したタンザニアを含め全部有色人種国であった。このほかに北朝鮮とインドネシアが来日したが、ガネフォ(新興国競技大会)に出場して国際競技連盟から出場停止を命じられた選手がいたため、両国は開会式の朝までに帰国した。競技内容も充実、世界新記録47、オリンピック新記録111を出し、とくに競泳で十代選手が大活躍したのも特色といえよう。エチオピアのアベベがマラソンで2連覇を遂げ、オーストラリアのドン・フレーザーDawn Fraser(1937― )が水泳女子100メートル自由形でオリンピック3連勝し、女子体操のチェコスロバキアのチャスラフスカVěra Čáslavská(1942―2016)が人気を集めた。日本は355人(うち女子61)の選手が参加し、米ソに次いで16種目に優勝した。その内訳は、体操5、レスリング5、柔道3、ボクシング1、ウエイトリフティング1、女子バレーボール1である。とくにバレーボールで、「東洋の魔女」といわれた女子チームの勝利は本大会のハイライトであった。大会の標語「世界は一つ」のとおり、開会式はシンコム衛星でアメリカとカナダに同時中継され、ただちにヨーロッパへ録画放映された。開会式のテレビ視聴率は87.4%、女子バレーボール決勝戦の日本対ソ連の試合のときは東京電話局の市外通話がぴたりと止まったというエピソードも残されている。優勝数(1)アメリカ36、(2)ソ連30、(3)日本16。 [鈴木良徳] 第19回大会(1968・メキシコ市)開会式10月12日~閉会式10月27日。参加国112、選手数5516。メキシコ市は海抜2240メートルの高地のため、多くのスポーツ関係医師たちから会場として不適格であるとの反対があったが、IOCは強化合宿制限日数を2週間延ばして6週間に延長する方法をとった。しかし、参加国の準備が万全だったのか陸上競技では20人、競泳では15人が世界新記録を出し、世界タイ記録は19、オリンピック新記録114を数えた。とくに走幅跳びのアメリカのビーモンBob Beamon(1946― )による8メートル90の驚異的な記録が高地の希薄な大気との関係から論議された。一方、アフリカの国々が目覚ましい活躍をして、ケニア、エチオピア、チュニジア、ウガンダ、カメルーンの選手たちが16のメダルを受賞した。前回に引き続き、体操で4個の金メダルを獲得したチェコのチャスラフスカも注目を集めた。 世界有数の休養地アカプルコのヨット会場からメキシコ市への道を登ると、市内近くにオリンピック村、主競技場(初めての全天候トラック)があり、ボートとカヌー会場はソチミルコ運河を人工的に改築した豪華なものであった。既設のアステカ・サッカー場は、10万人の収容力があり、そこで3位に入賞した日本チームは、翌1969年パリでユネスコのクーベルタン賞を受賞した。一方、大会直前には激しい学生運動とそれに対する軍隊の苛烈(かれつ)な弾圧があった。市内には銃弾の跡も残っており、ものものしい警備ぶりであったが、大会の運営は異常がなかった。また、この大会には人種差別問題で南アフリカ共和国が招待されなかった。北朝鮮その他の正式国名の呼び方などでIOC総会で激しい論議がおこり、陸上競技の表彰式ではアメリカ黒人の入賞者2人が、アメリカの黒人差別に抗議の意を表し、オリンピック村から追放された事件なども起こった。また夏の大会でトーチリレーの最終走者が女子現役選手であったのは初めてである。日本からは183人(うち女子30)が参加した。日本は、体操で6個、レスリングで4個、ウエイトリフティングで1個の金メダルを獲得し、マラソンでは君原健二(1941― )がエチオピアのウォルデMamo Wolde(1932―2002)に次いで2位となった。優勝数(1)アメリカ45、(2)ソ連29、(3)日本11。 [鈴木良徳] 第20回大会(1972・ミュンヘン)開会式8月26日~閉会式9月11日。参加国121、選手数7134。ナチス治下の第11回大会が国威発揚に利用されたという悪評を和らげるために平和と自由を強調する運営であった。ところが、9月5日の早朝、オリンピック村のイスラエル宿舎で「黒い9月」と称するゲリラ組織によるテロ事件が起こって、11人のイスラエル代表団が犠牲となった。オリンピック史上最大の惨劇であった。大会を続行するか中止するかが論議されたが、1日哀悼の日を置いて競技は再開され、予定より1日後れ11日に閉会された。オリンピックに激しい政治、人種、宗教の問題が加わってきたことを印象づける大会となった。 日本は、182人(うち女子38)の選手が参加し、体操男子団体総合で4連続優勝という史上初めての偉業を樹立し、また、地元東西ドイツの健闘ぶりが目だった。アメリカは、いままで無敗だったバスケットボールと棒高跳びの優勝を奪われたが、スピッツMark Spitz(1950― )は1人で水泳13種目に参加し、金メダルと世界新記録7という前例のない活躍をした。バルディーという愛称のダックスフントが、オリンピックのマスコットとして初めて登場した。優勝数(1)ソ連50、(2)アメリカ33、(3)東ドイツ20。 これまでIOC規約に規定され、組織委員会の権限であった2種目のデモンストレーション(番外競技ともいわれ、東京大会では武道と野球が行われた)は、1973年の規約改正によって削除された。ただし、IOCとは関係なく、開催都市の判断でデモンストレーションは行えるが、それは公式的にはオリンピックと無縁である。 [鈴木良徳] 第21回大会(1976・モントリオール)開会式7月17日~閉会式8月1日。参加国92、選手数6084。第一次オイル・ショックの影響で予算が当初の4倍にも跳ね上がり、政治的問題も絡んで何度か中止の危機に追い込まれつつも開催の運びとなった。ミュンヘンの教訓から警備も厳重であった。開催間近に台湾・南アフリカ問題で混乱状態になり、またもオリンピックの場に政治問題が引き出されるという結果となった。聖火はギリシアから衛星中継によるレーザー光線で点火されてオタワにともり、そこから会場にリレーされるという、時代を反映するものであった。陸上競技にはカリブ諸国の活躍が目だち、またソ連のサネエフViktor Saneev(1945― )が三段跳びでオリンピック3連勝など、アメリカの独壇場からメダルの分散の時代へ移行の観があった。女子体操では「白い妖精(ようせい)」とよばれた、14歳のルーマニアのコマネチNadia Comaneci(1961― )が10点満点を7回も出して話題をさらい、水泳の女子は東ドイツのエンダーKornelia Ender(1958― )のひとり舞台であった。ボクシングではキューバのステベンソンTeófilo Stevenson(1952―2012)がKOの連続でヘビー級史上初の2連勝を果たした。 日本は213人(うち女子61)の選手が参加。体操男子団体総合で、有力2選手を欠きながら逆転でオリンピック5連勝、女子バレーボールも完全優勝を成し遂げて「東洋の魔女」が復活した。優勝数(1)ソ連47、(2)東ドイツ40、(3)アメリカ34。 [鈴木良徳] 第22回大会(1980・モスクワ)開会式7月19日~閉会式8月3日。参加国80、選手数5179。社会主義国で初めてのオリンピックは参加国、参加人員ともに史上最高を記録すると予想されたが、1979年暮れのソ連のアフガニスタン侵攻によりアメリカ、西ドイツ、日本などのボイコットがあり期待どおりとはいかなかった反面、新興国の参加が目だつ大会であった。 施設・運営は社会主義国のリーダーを自認するソ連の威信をかけたもので、資金と人手のかけ方はいままでにないものであった。しかし、モスクワの街中から子供や学生の姿が消え、大会関係者や旅行者のみが目だつ、市民と選手との交歓があまりみられぬ奇妙なオリンピック風景であった。主要国のボイコットにもかかわらず世界新記録39、オリンピック新記録95という数字は前回に劣らぬものであった。しかし全体としてソ連と東ドイツのメダル競争となった印象は否めない。アメリカの欠けた水泳で、男子1500メートル自由形に史上初の14分台の世界新記録を樹立したソ連のサルニコフVladimir Salnikov(1960― )はこの大会最大のヒーローであった。優勝数(1)ソ連80、(2)東ドイツ47、(3)イタリア・ブルガリア・カナダ・キューバ各8。 [鈴木良徳] 第23回大会(1984・ロサンゼルス)開会式7月28日~閉会式8月12日。参加国140、選手数6829。ロサンゼルスでの開催は52年ぶり二度目である。直前の5月8日になって、ソ連が選手の安全確保を理由に不参加を表明した。東ドイツ、ポーランドなどの東欧数か国とキューバ、北朝鮮などの14か国も参加を取りやめ、1980年のモスクワ大会に続いていわゆる片肺大会となった。しかし、参加国および参加選手数ではそれまでの最高を記録した。メダルの獲得数は地元アメリカが圧倒的で、ルーマニア、西ドイツを大きく引き離した。実質的には初めて参加した中国が金15を含めメダル合計32個を獲得した。日本からは231人(うち女子53)の選手が参加した。日本は金10、銀8、銅14の成績にとどまった。アメリカのカール・ルイスCarl Lewis(1961― )が、陸上100メートル、200メートル、走幅跳び、400メートルリレーの4種目で金メダルをとった。ローマ大会からモントリオール大会まで日本が不敗を誇った体操男子団体総合はアメリカ、中国に敗れ3位となったが、具志堅幸司(ぐしけんこうじ)(1956― )が個人総合で逆転優勝し、ようやく体操日本の面目を保った。柔道無差別級では、山下泰裕(やましたやすひろ)が足の肉離れにもかかわらず全試合を一本勝ちして優勝した。 本大会は、税金を使わない「民営大会」として運営され、既存施設の利用、スポンサーの協賛金、ボランティアの大動員による人件費の節約などで黒字決算となった。優勝数(1)アメリカ83、(2)ルーマニア20、(3)西ドイツ17。 [深川長郎] 第24回大会(1988・ソウル)開会式9月17日~閉会式10月2日。参加国159、選手数8391。東京大会に次いでアジアで2番目、第二次世界大戦後独立した国では初の開催となった。共同開催を主張した北朝鮮や、キューバなどが不参加であったものの、ソ連、東欧諸国が参加し、前回を上回る規模の祭典となった。各競技ではソ連、東欧勢が強さを発揮した。日本は259人(うち女子71)の選手が参加した。日本のメダル獲得は前回から半減した。 今大会はドーピング(薬物使用)問題で大きな波紋が生じ、男子陸上100メートル優勝のカナダのベン・ジョンソンBen Johnson(1961― )が筋肉増強剤使用で金メダルを剥奪(はくだつ)された。優勝数(1)ソ連55、(2)東ドイツ37、(3)アメリカ36。 オリンピックは巨大化し、都市や国家の負担の限度を超え始め、その継続のためにはコマーシャリズムの洗礼も受けざるをえない状態になってきた。 [深川長郎] 第25回大会(1992・バルセロナ)開会式7月25日~閉会式8月9日。参加国169、選手数9356。冷戦終結で政治的対立によるボイコットもなく、旧ソ連は合同チームEUN(Equipe Unie)の略称で参加し、ボスニア・ヘルツェゴビナ、南アフリカ共和国なども加わった。日本は263人(うち女子82)の選手を送り込み、オリンピック競泳史上最年少の14歳で金メダルを獲得した岩崎恭子(1978― )、けがを乗り越えて優勝した柔道の古賀稔彦(こがとしひこ)(1967―2021)、女子マラソン2位の有森裕子(1966― )らが話題を提供した。メダル獲得数の上位3国は、(1)旧ソ連112(うち金は45)、(2)アメリカ108(金は37)、(3)ドイツ82(金は33)。 [深川長郎] 第26回大会(1996・アトランタ)開会式7月19日~閉会式8月4日。参加国197、選手数1万0318。アメリカ・ジョージア州の州都で、近代オリンピック第1回アテネ大会(1896)以来、100周年大会となった。史上初めて全NOCが参加した。日本からは310人(うち女子150)が参加、金3、銀6、銅5の成績をあげた。アメリカのカール・ルイスが走幅跳びで8メートル50を跳び、35歳にして通算9個目の金メダルを手中にし世界的話題となった。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ101(うち金は44)、(2)ドイツ65(金は20)、(3)ロシア63(金は26)。 [深川長郎] 第27回大会(2000・シドニー)開会式9月15日~閉会式10月1日。参加国199、選手数1万0651。第16回メルボルン大会(1956)以来、2回目のオーストラリアでの開催であった。参加国・地域は前回を更新して199か国・地域に達し、さらに国連統治下の東チモールが個人資格での参加を特別に認められたため、実質的には200を数えた。開会式では、オリンピック史上初めて韓国と北朝鮮の合同入場行進が実現した。また陸上のフリーマンCathy Freeman(1973― )の聖火点火をはじめ、オーストラリアで古い歴史をもつ先住民(アボリジニー)の存在を随所に見せることを意識するなど、民族問題と平和的祭典を強く打ち出した演出が目だった。 競技種目は大幅に増えて28競技、300種目に及び、オリンピックの肥大化に拍車をかけた感ありの大会となった。競技としては、陸上競技や競泳での世界新記録も多く、プロ選手の参加も著しく増えるなどの話題があった。日本は268人(うち女子110)を送り、金5、銀8、銅5の成績をあげた。なかでも女子マラソンでは、高橋尚子(たかはしなおこ)が日本人女子として初めて陸上競技での金メダルを獲得。また、女子柔道48キログラム以下級では田村亮子(たむらりょうこ)(谷亮子)が優勝、女子競泳、ソフトボールの健闘など、女子選手の活躍が目だった。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ97(うち金は40)、(2)ロシア88(金は32)、(3)中国59(金は28)。 体操女子個人総合優勝のルーマニアのアンドレーア・ラドゥカンAndreea Rǎducan(1983― )が興奮剤使用で金メダルを剥奪(はくだつ)されるなど、近年問題となっているドーピングの発覚が多くみられ、大会の商業化、肥大化などの課題の解決も持ち越された。 [深川長郎] なお2007年、アメリカの陸上競技選手ジョーンズMarion Jones(1975― )はドーピングを認め、本大会で獲得した金メダル3個と銅メダル2個を剥奪されている。 [編集部] 第28回大会(2004・アテネ)開会式8月13日~閉会式8月29日。参加国201、選手数1万0625。近代オリンピック第1回大会(1896)以来のギリシア・アテネで開催された。通常、開会式の入場行進はギリシアを先頭にしてアルファベット順に出場国が続き、最後に開催国の順となっているが、今大会では先頭はギリシア国旗のみで、以下、ギリシア語のアルファベット順に出場国が続き、最後にギリシア選手団が入場した。男子マラソンでは残り7キロメートルほどの地点で先頭を走っていたブラジルのデリマVanderlei de Lima(1969― )が乱入してきた男にコースから押し出されるというアクシデントにみまわれたが、3位でゴール。銅メダルとともに、オリンピック精神をたたえられピエール・ド・クーベルタン・メダルを授与された。 日本からは312人(うち女子171)が参加。女子マラソンの野口みずき(1978― )、水泳の北島康介らをはじめ体操男子団体総合、レスリング、柔道などで金メダルを16、銀を9、銅を12獲得した。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ103(うち金は35)、(2)ロシア92(金は27)、(3)中国63(金は32)。 [編集部] 第29回大会(2008・北京(ペキン))開会式8月8日~閉会式8月24日。参加国204、選手数1万0942。1964年東京、1988年ソウルに続いて、アジアで開催されるのは3回目である。メダル獲得数の上位3国は、(1)アメリカ110(うち金は36)、(2)中国100(金は51)、(3)ロシア72(金は23)、メダル数ではアメリカに及ばなかったが、中国は金メダルの数で第1位となった。陸上男子100メートルと200メートルにおいて驚異的なタイムで世界新記録を更新したジャマイカのウサイン・ボルトUsain Bolt(1986― )や、男子水泳で8個の金メダルを獲得したアメリカのマイケル・フェルプスMichael Phelps(1985― )などが話題となった。日本は339人(うち女子169)が参加、北島康介が100メートル平泳ぎで世界新記録を出すなど、金9、銀6、銅10の成績をあげた。なお、開催前にチベット問題など中国の人権軽視問題が取り上げられ、欧米諸国で開催反対の動きがみられたが、大会は無事行われた。 [編集部] 第30回大会(2012・ロンドン)開会式7月27日~閉会式8月12日。参加国・地域204、選手数約1万0500人。1908年、1948年に続く3回目で、同一都市では史上最多の開催となった。競技数は26、ボクシング女子が採用されたことにより、初めて男女とも全競技が実施された。メダル獲得数では、(1)アメリカ104(金は46)、(2)中国88(金は38)、(3)ロシア82(金は24)であるが、金メダルの数では29を獲得したイギリスが3位となった。日本は、レスリングフリースタイル女子55キログラム級の吉田沙保里(さおり)(1982― )と同63キログラム級の伊調馨(いちょうかおり)(1984― )がオリンピック3連覇を達成。さらにサッカー女子の「なでしこジャパン」が銀メダルを獲得するなど女子の活躍があり、金7、銀14、銅17の計38個で過去最多を記録した。しかし金メダルは男子柔道がゼロなど、伸び悩んだ。前回の北京大会に引き続き、陸上男子100メートル、200メートル、400メートルリレーでジャマイカのウサイン・ボルトが金メダルを獲得、また、競泳男子でアメリカのマイケル・フェルプスは4個の金メダルを獲得して、金メダル取得数を18と延ばし、史上最多記録を更新したあとに引退を表明した。なお、本大会では柔道やボクシングでの誤審が大きな問題となり、またバドミントンの女子ダブルスで、対戦の組み合わせを有利にするために、中国、韓国、インドネシアの選手が故意に負けようとしたとして失格になるという騒動があった。そのほか、男子サッカーの日本対韓国の対戦後、韓国の選手が竹島の領有問題に関するプラカードを掲げたため、オリンピックに政治問題を持ち込んだとして問題となった。 [編集部] 第31回大会(2016・リオ・デ・ジャネイロ)開会式8月5日~閉会式8月21日。参加国・地域205と難民選手団、選手数約1万1000人。難民選手団は、紛争などのため母国から参加できない選手のために新設されたもので、10人が出場した。南米大陸初の開催となった。競技数はゴルフとラグビーフットボール(7人制ラグビー)が加わり28。メダル獲得数では、(1)アメリカ121(金は46)、(2)中国70(金は26)(3)イギリス67(金は27)であるが、金メダルの数では27を獲得したイギリスが2位となった。日本は、体操男子個人総合の内村航平(こうへい)(1989― )が連覇を果たし、レスリングフリースタイル女子で今回は58キログラム級となった伊調馨が個人種目4連覇、陸上男子400メートルリレーで銀メダルを獲得するなどの活躍があり、金12、銀8、銅21の計41個で歴代最多記録を更新した。ジャマイカのウサイン・ボルトは陸上男子100メートル、200メートル、400メートルリレーすべてで3連覇を達成、また、引退を撤回して臨んだ競泳男子、アメリカのマイケル・フェルプスは5個の金メダルを獲得し、金メダル取得数を23として、史上最多記録を更新したあと、ふたたび引退を表明した。なお、大会前にロシアの組織ぐるみのドーピングが発覚し、世界ドーピング防止機構(WADA)はロシア選手団の出場禁止を勧告したが、IOCは各種目の国際競技団体に十分な証拠を提示した選手のみを出場させることとし、当初予定された選手数の3分の2にあたる271人の出場を認めた。また、開会前は施設工事の遅れや治安面が懸念されたが、杞憂(きゆう)に終わった。 [編集部] 冬季オリンピック冬の競技がオリンピック大会に加えられたのは第4回大会(1908・ロンドン)のフィギュアスケートが最初である。第一次世界大戦後の第7回大会(1920・アントワープ)でフィギュアのほかアイスホッケーが加えられた。翌1921年のIOC会議では本格的な冬季大会を開く提案があったが、北欧諸国は反対した。冬季大会は北欧のような地の利を得た所でなければ成功しないというのが表面上の理由であったが、すでに彼らが行っていた競技会、とくにノルウェーのホルメンコーレンでの大会で十分であるというのが本音であった。結局、テスト的にフランスで開くことになった。 [鈴木良徳] 第1回大会(1924・シャモニー・モンブラン)開会式1月25日~閉会式2月5日。参加国16、選手数258。アルプス登山の基地であったフランスの辺境シャモニーは当時まだ寒村であったが、村をあげて準備を進め、先進スポーツ都市の調査も行い、すばらしい大会を開いた。日本もスキーに参加を予定していたが、前年の関東大震災のため中止した。自然条件に恵まれ、当初は冬季オリンピック開催に反対した北欧諸国も参加し、冬季競技の先進国ぶりを発揮した。この年国際スキー連盟(FIS:International Ski Federation)が結成された。また、翌1925年のIOC総会で、この大会を第1回オリンピック冬季大会と呼称することになった。優勝数(1)ノルウェー4、フィンランド4、(2)オーストリア2。 [鈴木良徳] 第2回大会(1928・サン・モリッツ)開会式2月11日~閉会式2月19日。参加国25、選手数464。初参加の日本選手はスキー6人。夏の大会を開いたオランダは、平坦(へいたん)な国土ということもあり、冬季競技場がなかったので、スイスで開いた。会期中25℃が記録されるほど気温が高く、スピードスケートの1万メートルは中止したほどである。これ以後実に第10回大会まで冬季オリンピックは天候に災いされる。北欧諸国の活躍が目覚ましく、優勝数(1)ノルウェー6、(2)アメリカ・フィンランド・スウェーデン各2となった。 [鈴木良徳] 第3回大会(1932・レーク・プラシッド)開会式2月4日~閉会式2月15日。参加国17、選手数252。日本選手17。会場はニューヨーク州の交通不便な寒村であったが、アメリカは巨費を投じて施設をつくった。ただ50年来の暖冬異変で、スキーのコースなどは、レース前に80キロメートルも離れた場所に変更、カナダから雪を運んだ。スケートはアメリカ規則のオープンレース制で実施したので、ヨーロッパ選手との間に大きなトラブルが起こった。このためスピードスケートはアメリカが大勝したが、スキーは精鋭主義で参加した北欧の天下であった。優勝数(1)アメリカ6、(2)ノルウェー3、(3)フィンランド・スウェーデン・オーストリア・フランス各1。 [鈴木良徳] 第4回大会(1936・ガルミッシュ・パルテンキルヘン)開会式2月6日~閉会式2月16日。参加国28、選手数646。日本選手34(うち女子1)。この大会も気温に災いされたが、スキー、スケート会場ともナチス・ドイツの力で大きな仮設スタンドがつくられた。会場の周辺にまで反ユダヤスローガンがみられ、IOC会長ラトゥールHenri de Baillet-Lator(1876―1942)がヒトラーに厳重抗議して撤去させる一幕があった。スキーにアルペン競技が加えられたのはこの年が初めてである。女子種目としても初めてアルペン1種目が行われた。フィギュアスケートのソニア・ヘニーSonja Henie(1912―1969)は第1回大会に13歳で初参加し、その後この大会まで3回優勝、銀盤の女王といわれた。優勝数(1)ノルウェー7、(2)ドイツ3、(3)スウェーデン2。 [鈴木良徳] 第5回大会(1948・サン・モリッツ)開会式1月30日~閉会式2月8日。参加国28、選手数669。第二次世界大戦後の初大会。日本とドイツは招待されなかった。この大会も天候に恵まれなかった。アイスホッケーでアメリカから2チーム参加という珍しい事件が起きた。一つは国際アイスホッケー・リーグに加盟しているアメリカのアマチュア・ホッケー協会推薦のチームであったが、アメリカNOCはこれを認めず、独自のチームを編成した。しかしこのアメリカNOC編成のチームは国際リーグが承認しなかった。入場料目当てに2チームを認めた組織委員会は非難され、国際アイスホッケー・リーグが除名された。すぐリーグ側がIOCに陳謝し、アイスホッケーは正式競技として追認された。優勝数(1)スウェーデン4、ノルウェー4、(2)スイス3。 [鈴木良徳] 第6回大会(1952・オスロ)開会式2月14日~閉会式2月25日。参加国30、選手数694。日本選手13。ノルウェーの首都オスロの前名クリスティアニアがスキーの技術名称にあるように、初めて冬季競技の発祥地で開かれた。近代スキーの創始者の一人であるノルヘイムSondre Norheim(1825―1897)の生誕地モルゲダールからオスロまで冬季大会の最初のトーチリレーが行われた。首都を開催地としたのは冬季大会では初めてである。スピードスケートが室内リンクを使用したのも初めて。この大会から日本とドイツがふたたび招待された。北欧諸国はその面目にかけて活躍した。優勝数(1)ノルウェー7、(2)アメリカ4、(3)フィンランド・ドイツ各3。 [鈴木良徳] 第7回大会(1956・コルティーナ・ダンペッツォ)開会式1月26日~閉会式2月5日。参加国32、選手数821。日本選手10。イタリア北部の冬季競技の中心地だけに条件は良好であった。ソ連が初参加し、各競技に優れた成績をあげた。オーストリアのアントン(トニー)・ザイラーAnton Sailer(1935―2009)がスキー競技でアルペン三冠王に輝いた。ジャンプ競技では、フィンランド選手が手を腰につけるドロップスタイルで金・銀メダルを独占した。従来は両手を頭の前方に伸ばして飛ぶのが普通であった。日本チームとしては冬季大会初めての銀メダルを猪谷千春(いがやちはる)がスキー回転競技で手にした。優勝数(1)ソ連7、(2)オーストリア4、(3)フィンランド・スイス各3。 [鈴木良徳] 第8回大会(1960・スコー・バレー)開会式2月18日~閉会式2月28日。参加国30、選手数665。日本選手41(うち女子5)。アメリカの一企業家が、カリフォルニア州の雪崩(なだれ)で有名な「死の谷」の近くに巨費を投じて施設を設け、スケート・リンクはパイピング・リンクを採用するなどして大会を成功させた。競技ではソ連が圧倒的な強さを発揮した。女子スピードスケートが初めて正式種目として登場し、高見沢初枝(長久保初枝)(1935― )が3000メートルで4位となった。優勝数(1)ソ連7、(2)ドイツ4、(3)アメリカ3。 [鈴木良徳] 第9回大会(1964・インスブルック)開会式1月29日~閉会式2月9日。参加国36、選手数1091。日本選手48(うち女子6)。大会前ひどい雪不足で、練習中の選手2人が事故死したほどであった。ソ連が圧倒的な強さを発揮した。優勝数(1)ソ連11、(2)オーストリア4、(3)フィンランド・スウェーデン・ノルウェー・フランス・ドイツ各3。 [鈴木良徳] 第10回大会(1968・グルノーブル)開会式2月6日~閉会式2月18日。参加国37、選手数1158。日本選手62(うち女子9)。古い歴史をもち新興工業化に成功したフランスの都市が会場となり、大統領ドゴールの力の入れ方も大きなものであった。開会式が競技場でない大きな仮設スタジアムで行われたり、式典音楽に近代音楽を演奏するなどして、演出の新しさを示した。この大会から、これまで合同して参加していたドイツが東西二つに分かれて参加。また、セックス・チェックとドーピング検査も行われることになった。入賞者がメーカーの商標がはっきりわかるスキーを持って写真を撮ることは禁止された。 競技ではスキーでフランスのキリーJean-Claude Killy(1943― )が第7回大会のザイラーに次ぐ史上2人目のアルペン三冠王に輝いた。優勝数(1)ノルウェー6、(2)ソ連5、(3)フランス4、イタリア4。 [鈴木良徳] 第11回大会(1972・札幌)開会式2月3日~閉会式2月13日。参加国35、選手数1006。日本選手90(うち女子20)。1940年(昭和15)に開催が内定していたのを戦争のため返上した札幌が、今度は条件、成績とも良好な成果をあげた。冬季大会でいちばんたいせつなのは自然条件であるが、札幌は比較的天候に恵まれた。また支笏湖(しこつこ)を眼下に見下ろす恵庭岳(えにわだけ)の滑降コースと、冬季大会史上初めての海を望見できる手稲山(ていねやま)の回転コースは好評であった。日本チームとしては、冬では初めて、夏の大会も含めて3回目という同一種目金・銀・銅メダル独占の偉業を、スキーの70メートル級ジャンプで笠谷幸生(かさやゆきお)(1943― )、金野昭次(こんのあきつぐ)(1944―2019)、青地清二(1942―2008)が成し遂げた。ほかにもリュージュで大高優子(1950― )が5位、同じくリュージュ2人乗りBチームが4位と、国内で普及度の低い競技でも活躍した。冬季大会では初めて、オーストリアのシュランツKarl Schranz(1938― )がアマチュア違反で出場を拒否された。ドーピングで失格した選手も1人を出したが、冬季競技の非アマチュア化はIOCでも問題になった。優勝数(1)ソ連8、(2)東ドイツ・スイス・オランダ各4。 [鈴木良徳] 第12回大会(1976・インスブルック)開会式2月4日~閉会式2月15日。参加国37、選手数1123。日本選手57(うち女子6)。当初はアメリカのデンバーに決定していたが、環境破壊のおそれがあるとして市民投票で否決され、オーストリアのインスブルックが二度目の大会を引き受けることになった。できるだけ前回の施設を改善利用して、簡素な大会とすることをモットーとした。競技ではソ連が圧倒的な強さをみせて13種目に優勝、ついで東ドイツが7種目制覇と、社会主義国が優勢であった。日本チームの入賞者はゼロ。優勝数(1)ソ連13、(2)東ドイツ7、(3)アメリカ3、ノルウェー3。 [鈴木良徳] 第13回大会(1980・レーク・プラシッド)開会式2月13日~閉会式2月24日。参加国37、選手数1072。日本選手50(うち女子4)。第3回大会を開催したアメリカのレーク・プラシッドでふたたび開かれた。地元アメリカはハイデンEric Heiden(1958― )がスピードスケートで5個の金メダルをとり、アイスホッケーでソ連を押さえて優勝した。日本はスキーの70メートル級ジャンプで八木弘和(やぎひろかず)(1959― )が銀メダル、秋元正博(1956― )が4位。女子のスピードスケート500メートルで長屋真紀子(1955― )が5位、フィギュアスケートでは渡部絵美(1959― )が6位に入賞した。優勝数(1)ソ連10、(2)東ドイツ9、(3)アメリカ6。 [鈴木良徳] 第14回大会(1984・サラエボ/サライエボ)開会式2月8日~閉会式2月19日。参加国49、選手数1272。日本選手39(うち女子7)。共産圏国であるユーゴスラビアで初めて開催された。東ドイツはエンケKarin Enke(1961― )らの活躍で、スピードスケートの女子全4種目の金・銀メダルを独占した。フィギュアのペアではソ連が6連勝、アイスホッケーでも前回優勝のアメリカが初戦で敗退、ソ連が優勝。日本の北沢欣浩(きたざわよしひろ)(1962― )はスピードスケート男子500メートルで2位となり、スケート競技では日本初のメダリストとなった。スキーのノルディックではフィンランドのハマライネンMarja-Liisa Hämäläinen(1955― )が女子3種目に完全優勝した。優勝数(1)東ドイツ9、(2)ソ連6、(3)アメリカ・フィンランド・スウェーデン各4。 [鈴木良徳] 第15回大会(1988・カルガリー)開会式2月13日~閉会式2月28日。参加国57、選手数1423。日本選手48(うち女子11)。開催期間、参加国、選手数ともに前回を上回る大規模な大会となった。金メダル争いでは、ソ連が前回東ドイツに奪われた王座を奪回した。日本は黒岩彰(くろいわあきら)(1961― )(500メートル3位)、橋本聖子(1964― )(全5種目に入賞)らスピードスケート陣が健闘。橋本は同年開催されたソウル大会(夏季)で自転車競技にも出場した。優勝数(1)ソ連11、(2)東ドイツ9、(3)スイス5。 [鈴木良徳] 第16回大会(1992・アルベールビル)開会式2月8日~閉会式2月23日。参加国64、選手数1801。日本選手63(うち女子21)。冷戦終結後初めての大会で、旧ソ連がCIS(独立国家共同体)で、統一ドイツ、独立したバルト三国も参加した。アルベールビルを中心にフランスのサボア県全域で競技が行われた。日本は、ノルディック複合団体で金メダル、スピードスケートの黒岩敏幸(1969― )が銀メダルを獲得したほか、橋本聖子や、フィギュアスケートの伊藤みどりらの活躍で、7個のメダルを獲得、冬季大会としてはそれまでの最高の成績をあげた。橋本聖子は、この大会で、日本オリンピック委員会(JOC)が設けた報奨金制度の適用第一号となる。メダル獲得数の上位3国は、(1)ドイツ26(うち金は10)、(2)旧ソ連23(金は9)、(3)ノルウェー20(金は9)。 [深川長郎] 第17回大会(1994・リレハンメル)開会式2月12日~閉会式2月27日。参加国67、選手数1737。日本選手65(うち女子16)。従来の冬季大会と夏季大会の同一年開催を2年ごと交互開催に変更したため、この大会は前大会から2年後、ノルウェーの小都市リレハンメルでの開催となった。イスラエルがパレスチナ解放機構(PLO)と和解合意の成立で初参加し、南アフリカが34年ぶりに復帰した。日本はノルディック複合団体で金メダルを獲得し初の冬季オリンピック2連覇を達成した。同個人でも河野孝典(1969― )が銀メダルを獲得し、ほかの種目ではスキージャンプのラージヒル団体で銀メダル、スピードスケートで男子500メートルの堀井学(1972― )と女子5000メートルの山本宏美(1970― )がともに銅メダルを獲得したが、橋本聖子をはじめとして全体に低調な結果に終わった。メダル獲得数の上位3国は、(1)ノルウェー26(うち金は10)、(2)ドイツ24(金は9)、(3)ロシア23(金は11)。 [深川長郎] 第18回大会(1998・長野)開会式2月7日~閉会式2月22日。参加国72、選手数2176。日本選手166(うち女子66)。日本は金メダル5、銀メダル1、銅メダル4の成績をあげた。 [深川長郎] 第19回大会(2002・ソルト・レーク・シティ)開会式2月8日~閉会式2月24日。参加国77、選手数2399。日本選手109(うち女子48)。21世紀最初のオリンピックは、アメリカのロッキー山脈の西に位置するユタ州の州都ソルト・レーク・シティを中心にプロボー、オグデン等での開催となった。2001年9月に起きたアメリカ同時多発テロ事件後の大会とあって、厳戒態勢のなかで行われた。競技種目は7競技78種目で、日本はスピードスケート・男子500メートルで清水宏保(しみずひろやす)(1974― )が前回の長野大会金メダルに続いて銀メダルを、フリースタイルスキー・女子モーグルで里谷多英(さとやたえ)(1976― )が前回の金メダルに続いて銅メダルを獲得したが、メダルはこの二つにとどまった。しかし、8位以内の入賞数では長野大会の33に次ぐ27を数え、その点では成果をあげたといえる。メダル獲得数の上位3国は、(1)ドイツ35(うち金は12)、(2)アメリカ34(金は10)、(3)ノルウェー24(金は11)である。 開会式では、聖火の最終点火を、1980年レーク・プラシッド大会で当時無敵のソ連チームを破り金メダルを獲得したアメリカ・男子アイスホッケーチームのメンバーが務めた。また、テロにあった世界貿易センターの廃墟(はいきょ)から回収された星条旗が運び込まれるなど、話題の多い大会となった。 [深川長郎] 第20回大会(2006・トリノ)開会式2月10日~閉会式2月26日。参加国80、選手数2508。日本選手112(うち女子53)。イタリア北西部、ピエモンテ州の州都トリノを中心に、アルプスのセストリエール等での開催となった。イタリアでの冬季オリンピックは、1956年のコルティーナ・ダンペッツォ大会以来となる。競技種目は7競技84種目で、日本はフィギュアスケート女子シングルの荒川静香(あらかわしずか)が、日本人として史上初の金メダルを獲得。彼女の得意技イナバウアーが2006年の流行語大賞となるなど、広く話題となった。しかし、日本のメダルはこの一つにとどまった。8位以内の入賞数では42を数え、とくにスキーのアルペン回転競技での4位、カーリングの7位は健闘したといえる。メダル獲得数の上位3国は、(1)ドイツ29(うち金は11)、(2)アメリカ25(金は9)、(3)オーストリア23(金は9)である。 開会式は、仮面喜劇「コメディア・デラルテ」などを織り交ぜた幻想的なスペクタクル構成で、ヨーロッパの歴史をひも解く演目に続き、スカラ座のスターダンサー、イタリアのテクノロジーのシンボルとしてフェラーリF1チームが登場。女優のソフィア・ローレンら女性だけの8名が五輪旗を運んだのは史上初。 [深川長郎] 第21回大会(2010・バンクーバー)開会式2月12日~閉会式2月28日。参加国・地域82、選手数2566。日本選手94(うち女子45)。カナダ西部、太平洋側の都市バンクーバーで開催、カナダでの冬季オリンピックは1988年のカルガリー大会についで二度目である。競技種目は7競技86種目。開会式はオリンピック史上初となるスタジアム屋内で行われた。天候には恵まれず暖冬となり、ヘリコプターで雪を運び入れた会場もあった。また、リュージュの練習中に選手1名が死亡する事故が起きた。 日本選手では、スピードスケート男子500メートルの長島圭一郎(1982― )、スピードスケートの女子チームパシュート(団体追い抜き)、フィギュアスケート女子シングルの浅田真央が銀メダル、スピードスケート男子500メートルの加藤条治(かとうじょうじ)(1985― )、フィギュアスケート男子シングルの高橋大輔が銅メダルで、合計5個のメダルを獲得した。メダル獲得上位3国は、(1)アメリカ37(金は9)、(2)ドイツ30(金は10)、(3)カナダ26(金は14)。開催国カナダはメダル獲得数では第3位であったが、金メダルの獲得数は最多となった。 [編集部] 第22回大会(2014・ソチ)開会式2月7日~閉会式2月23日。参加国・地域88、選手数2780。日本選手113(うち女子65)。ロシア連邦南西部、黒海北東岸に面する保養都市ソチで開催、旧ソ連邦で初の冬季オリンピック開催となった。競技種目は7競技98種目。比較的暖かい気候が続き、雪や氷のコンディションが思わしくないなかで競技が行われた。日本選手では、フィギュアスケート男子シングルの羽生結弦(はにゅうゆづる)(1994― )が金メダル、スキージャンプの男子ラージヒル個人で葛西紀明(1972― )、スキーノルディック複合のノーマルヒル個人で渡部暁斗(わたべあきと)(1988― )、スノーボードの男子ハーフパイプで平野歩夢(あゆむ)(1998― )、スノーボードの女子パラレル大回転で竹内智香(ともか)(1983― )が銀メダルなど、合計8個のメダルを獲得した。メダル獲得上位3国は、(1)ロシア33(金は13)、(2)ノルウェー26(金は11)、(3)カナダ25(金は10)。なお、大会終了後、ロシアの組織ぐるみのドーピングが明らかになり、IOCは金メダリスト2人を含む5選手を失格・オリンピックからの永久追放処分とし、計19人についてドーピングを認定、メダルも剥奪した。 [編集部] 第23回大会(2018・平昌(ピョンチャン))開会式2月9日~閉会式2月25日。参加国・地域92、選手数2925。日本選手123(うち女子72)。なお、IOCは、前回大会で組織的なドーピング問題を起こしたロシア選手団の出場を認めず、ドーピングを行っていないことを証明できた選手のみ、個人資格、オリンピック旗のもとでの出場を認めた。韓国北東部、江原道(カンウォンド)の平昌で開催、フィギュアスケート、カーリング、アイスホッケーなどの氷上競技は、平昌から約20キロメートル離れ、日本海に面した都市、江陵(カンヌン)で実施された。アジアでの冬季オリンピックは札幌(1972)、長野(1998)に次いで三度目の開催。競技種目は7競技102種目。 日本選手では、フィギュアスケート男子シングルの羽生結弦が連覇を果たし、スピードスケートの女子チームパシュート、スピードスケート女子500メートルの小平奈緒(1986― )、スピードスケートのマススタートで高木菜那(なな)(1992― )が金メダルなど、金4、銀5、銅4と史上最多の計13個のメダルを獲得した。メダル獲得上位3国は、(1)ノルウェー39(金は14)、(2)ドイツ31(金は14)、(3)カナダ29(金は11)。なお、アイスホッケー女子で史上初めて韓国と北朝鮮の合同チームが結成された。 [編集部] 『鈴木良徳著『オリンピック読本』改訂版(1952・旺文社)』▽『ピエール・ド・クベルタン著、カール・ディーム編、大島鎌吉訳『オリンピックの回想』(1962/新版・1976・ベースボール・マガジン社)』▽『M・アンドロニコス他著、成田十次郎他訳『古代オリンピック――その競技と文化』(1981・講談社)』▽『川本信正監修『オリンピックの事典――平和と青春の祭典』(1984・三省堂)』▽『日本オリンピック委員会監修『近代オリンピック100年の歩み』(1994・ベースボール・マガジン社)』 [参照項目] | | | | |出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
<<: Olympic Committee - Is the Olympics okay?
>>: Olympia (English spelling)
Recommend
Geomagnetic reference field
This model is determined to accurately represent t...
Ogaki Domain
During the Edo period, this domain ruled the west...
Sukunahikona no Mikoto - Sukunahikona no Mikoto
Also known as Sukunabikone, Sukunamikami, and Suk...
Monarda didyma (English spelling) Monardadidyma
… [Munemin Yanagi]. … *Some of the terminology th...
Ilbert, CP - Ilbert
…In 1883, during the reign of the Viceroy of Indi...
Cacajao calvus (English spelling) Cacajaocalvus
… [Kuroda Suehisa]. . . *Some of the terminology ...
Phoibē (English spelling) Phoibe
…She corresponds to Latona in Roman mythology. Sh...
Uchinada Sand Dunes
Sand dunes developed around Uchinada-cho, Kahoku-...
Doubs (English spelling)
A tributary of the Saône in eastern France. It is ...
Tourist guide - Kankou Gaido
...A person who uses his/her extensive knowledge ...
Movable partition - Movable partition
Also called movable partitions. A movable wall tha...
Dry phosphoric acid - Kanshikirinsan
...Many monohydrogen phosphates, M I 2 HPO 4 , an...
Mogannia hebes (English spelling)
…[Masami Hayashi]. . … *Some of the terminology t...
Warekara (split shell) - Warekara (English spelling) skeleton shrimp
A general term for crustaceans in the suborder Cap...
The Interconfessional Translation of the Bible
...The holy book of Judaism and Christianity. The...