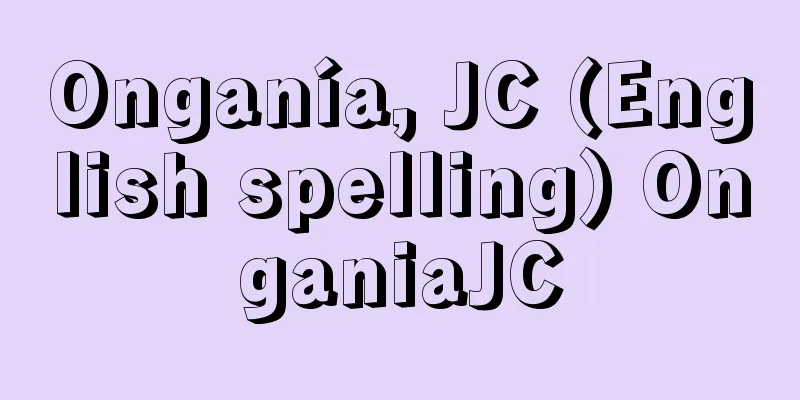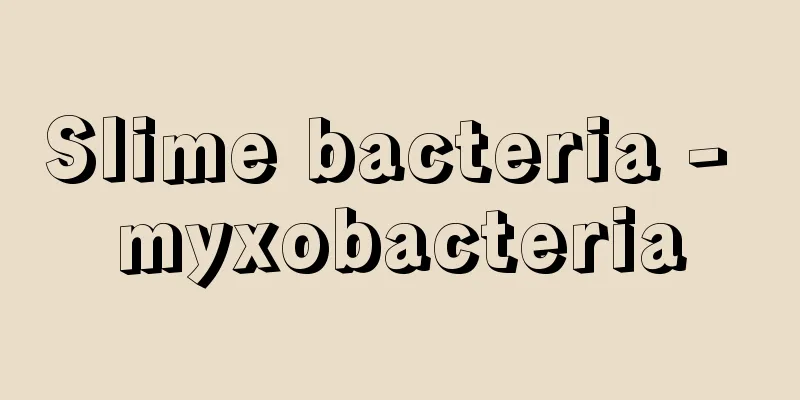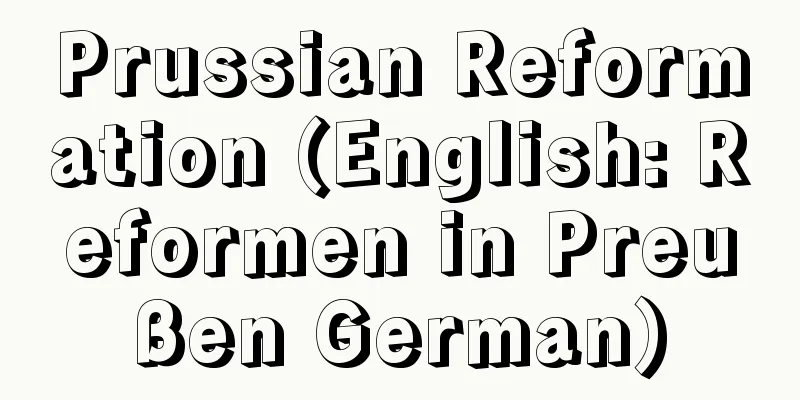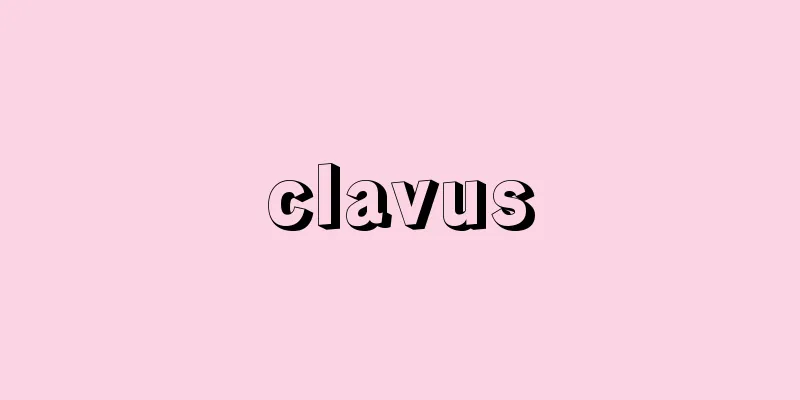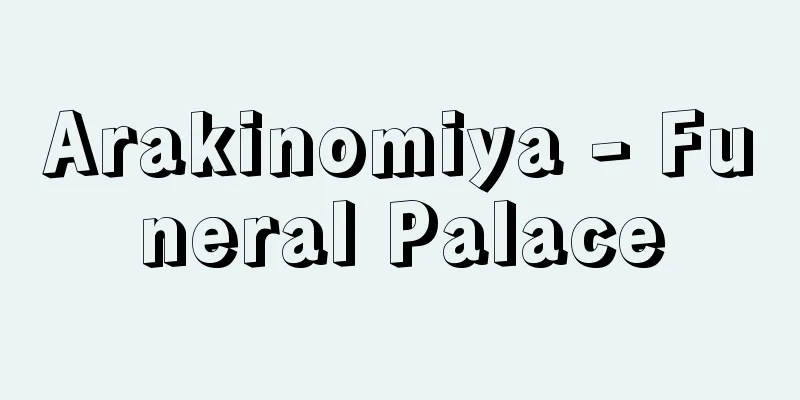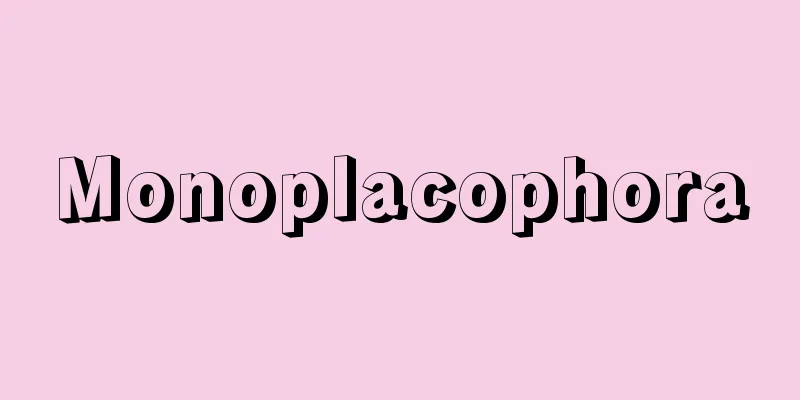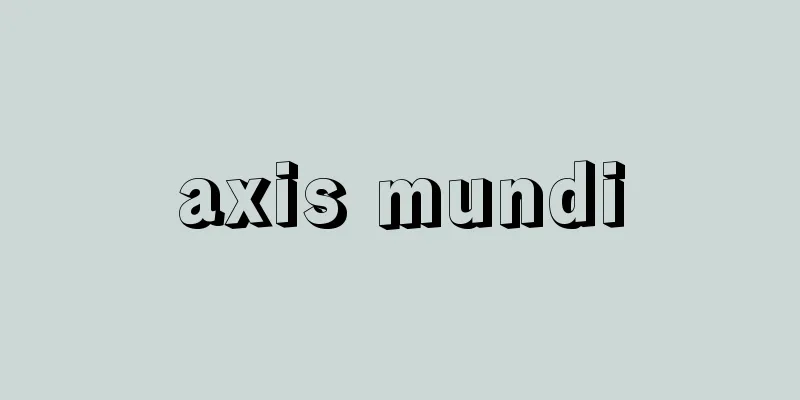Car - Car
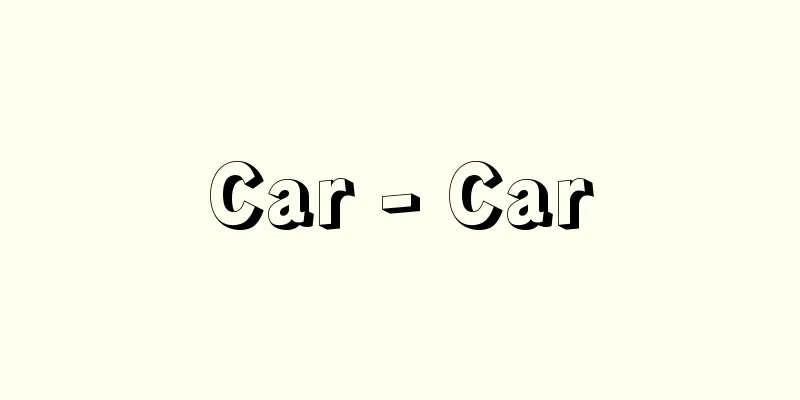
|
A general term for a machine that has a built-in prime mover and runs on land under its own power using wheels to transport people or goods or perform various tasks. It is called a motorcar in English, an automobile in American English, automobile in French, Kraftwagen in German, and kisha in Chinese. Automobiles were developed in the mid-1880s in the late 19th century, and gradually began to spread to the general public in the 20th century. The country that benefited most from automobiles was the United States. The rapid spread of automobiles from around 1910 dramatically increased the speed of people and goods transport on an individual basis, and the distance traveled also increased significantly, which is said to have caused the land area of the United States to shrink in relative terms. In just a little over 100 years, automobiles have made great strides, and since they have become widespread and widely used on a global scale, it is no exaggeration to say that the 20th century was the century defined by automobiles. On the other hand, the widespread use of automobiles has given rise to problems such as air pollution and other forms of pollution, traffic jams due to overcrowding, traffic accidents, oil crises due to regional conflicts, and the threat of oil depletion, and efforts are being made to resolve these problems. In particular, since the end of the 20th century, automobiles have been criticized as the largest source of carbon dioxide ( CO2 ), which causes global warming, and there is an urgent need to find a solution to this problem. From a national perspective, the automobile industry is the most important industry that forms the backbone of the economy, and at the same time, it is an important export industry. Since its production is possible only with a wide range of primary industrial products, the promotion of the automobile industry is a major stimulus to all other industries. In recent years, electronic control technology aimed at saving resources and improving safety has become indispensable for automobiles, and the scope of the automobile industry is expanding further. Until the second half of the 20th century, automobile production was almost monopolized by a handful of companies in developed industrial countries. However, driven by the strong demand for automobiles in developing countries, after local production by foreign companies and technical collaboration, companies in developing countries themselves have begun to develop and produce their own automobiles. The automobile industries of these newly industrialized countries are rapidly improving their technological capabilities, and with their high quality and low prices due to cheap labor, they are becoming a threat to the automobile industries of Europe and Japan. Furthermore, the map of the global automobile industry is being redrawn due to currency problems associated with exports and imports, and the hollowing out of domestic industries due to the relocation of factories to countries of demand. In addition, automobiles are durable consumer goods, and are sold through advertising, and are highly influenced by trends. On the other hand, automobiles are the things that are closest to humans and accompany them in their daily lives. As a result, automobiles often become the object of a kind of emotional empathy or a hobby, like pets. When viewed as a means of transportation, the automobile's greatest features are the freedom to go anywhere, anytime, along any route of your choice, regardless of time, destination, or route, and the convenience of door-to-door transportation. This article focuses on the history of the development of the automobile and its engineering aspects. For industrial and transportation policy aspects, please refer to the "Automobile Industry" and "Automobile Transportation" entries. [Takashima Shizuo and Ito Kazuhiko] Definition and types of automobilesDefinitionIn Japan, the Road Traffic Act, Chapter 1, Article 2, Paragraph 9, defines an automobile as "a vehicle that uses a motor and is driven without rails or overhead lines, other than a moped." Similarly, the Road Transport Vehicle Act, Chapter 1, Article 2, Paragraph 2, states, "In this Act, 'automobile' means a device manufactured for the purpose of moving on land with a motor, without rails or overhead lines, or a device manufactured for the purpose of moving on land by towing it, other than a moped as defined in the following paragraph." In other words, under Japanese law, two-wheeled vehicles other than mopeds, trailers, and vehicles with crawlers (endless tracks) are also automobiles. Also, since there is no provision for "something that runs on wheels," if a small road-use hovercraft were to be realized, it would be considered an automobile if it ran on the road alongside other means of transportation. Globally, a car is defined as a vehicle that supports its weight on wheels with pneumatic rubber tires (or, in rare cases, solid tires that are not inflated), turns the wheels with an internal prime mover, and moves due to friction with the road surface. [Takashima Shizuo] kindsVehicles are classified according to their structure and hardware, as well as their intended use and software. Structural classification will be discussed later. In terms of intended use, this section will only describe the classification of passenger cars that transport a small number of people. For various types of work vehicles, motorcycles, trucks, buses, racing cars, etc., please refer to the respective entries. Passenger cars are a wide variety of vehicles, ranging from small, practical cars that prioritize economy and are used by the general public, to large, luxury cars that prioritize comfort, to sports cars for enthusiasts that pursue high performance on a par with that of racing cars. A notable recent trend is that the characteristics of each vehicle overlap to a large extent, making the boundaries between them unclear. In the past, the vehicle's name could roughly tell what the vehicle was like, but today, even small, popular vehicles can be classified under a single name, ranging from models that prioritize economy to those equipped with DOHC engines or turbos that are used in touring car races and rallies. On the other hand, sports cars were limited to open-top two-seater cars until a long time ago, but after World War II, comfort became more important, and many of them took on a coupe shape under the name GT. GT is an abbreviation of the Italian word gran turismo, which means a car suitable for long-distance travel. This trend was spurred by American safety regulations, and although open-top cars have recently been making a comeback, they once completely disappeared. Furthermore, many GT coupes are equipped with two extra seats, making them a 2+2 model, or even a full 4-seater, so the line between them and coupe-type practical cars has virtually disappeared. A typical example of a coupe-type utility vehicle is the specialty car, which basically has a utility vehicle chassis, but has a low body, a long nose, a short rear, and sports car-like proportions. If the engine of this type of car is strengthened and the suspension is stiffened, it is no different from a sports car. This genre was developed in the United States by the Ford Mustang in 1964, and in Japan, examples include the Celica, Soarer, Silvia, Starion, Piazza, and Alcyone. The same kind of uncertainty exists between sedans and station wagons. Until a generation ago, sedans were dominated by three-box cars with trunks protruding from the rear, but today, mainly small, affordable cars, tend to be two-box wagons with tailgates (rear doors). This is the result of the pursuit of versatility in small cars with limited size, and is largely due to the front-wheel drive system with the drive system concentrated at the front. Starting from the mid-1990s, SUVs (Sports Utility Vehicles) became popular in Japan and Europe, starting with the minivan boom in the United States, and replaced the specialty cars mentioned above. These are slightly larger two-box or one-box cars that are basically multipurpose vehicles that can carry many people, but can also be used in a sporty manner for leisure. In Japan, Honda Motor Co.'s Odyssey, released in 1994, was a huge success, significantly improving the company's domestic sales, and other companies competed to follow suit, with the SUV catching up to sedan as a family car. Next, in terms of size, the range is almost perfect, from the smallest 50cc, one-seater, three- or four-wheeled vehicles found in France, Italy, and Japan, to the largest 6.3-meter long, 3.2-ton, 7000cc, eight-seater luxury car Zil from the former Soviet Union. The size of passenger cars in each country varies depending on the country's circumstances (economic power, national income, etc.) and national character. In short, European countries and Japan are centered on small cars, while American cars are far more oriented toward large cars. However, as a result of the two oil crises, strict Corporate Average Fuel Economy regulations (CAFE, 11.6 km/L since 1985, fines for violations) were imposed, and American cars are now rapidly shrinking and approaching European and Japanese cars. Even though Japan is said to be a European-type country, there are considerable differences between countries in Europe. In Italy, 77.1% of cars are 1500cc or less, in France 70.1%, and in the UK 87.8% are 1600cc or less. In Germany, on the other hand, only 30% are 1500cc or less, with the majority being in the 1501-2000cc range. Japan has 51.8% of cars under 1500cc, which means that there is clearly a preference for larger cars than Italy, France, and the UK, and is closer to Germany. Among the legal classifications in Japan, those based on the Road Transport Vehicle Act relate to inspection, maintenance, registration, statistics, compulsory insurance, taxation, etc., while those based on the Road Traffic Act apply to driving, licenses, traffic enforcement, etc. [Takashima Shizuo] Passenger car body type(1) Sedan The most common box-shaped car, available in two-door and four-door versions. The basic three-box type consists of three boxes: the bonnet where the engine is, the passenger compartment, and the luggage compartment, but recently there have been many station wagon-style two-box sedans with a tailgate at the rear. In these cases, they are sometimes called three-door sedans, five-door sedans, or hatchback sedans. The word originates from the sedan chair (a covered basket or palanquin) used by the nobility in medieval France, and is thought to have come from the place name sedan. The term sedan is American, and is called saloon (an archaic word for salon) in Britain, Berlin in France, and Berlina in Italy (both derived from the Berlin-type carriage). In Germany, it is called limousine. (2) Convertible Originally an adjective meaning "able to be converted," the correct terms are convertible coupe or convertible sedan. It refers to an open-top car that can be turned into a coupe or sedan by lifting the top and closing the side windows. In contrast, cars that do not have side windows that roll up and only have a simple top are called tourers (UK), touring cars (US), or phaeton (US) to distinguish them. Convertible is also an American term, and in the UK it is called a drophead coupe or drophead saloon, since the roof can be lowered. The word cabriolet in France, Italy, and Germany comes from a horse-drawn carriage with a top. (3) Hardtop The etymology of the word means "hard roof", and the correct name is hardtop convertible coupe (or sedan). It is a metalized convertible top (soft top), and the roof is lower, thinner, and lighter than coupes and sedans, and when the side windows are lowered, there is no pillar in the center, giving a feeling of openness similar to that of an open-top car. The French term "four cabriolet" (fake cabriolet) well describes its true nature. It was commercialized by General Motors (GM) in the United States in 1948, and it was very popular for a time. However, as a result of the intensifying safety debate, many of them came to have pillars to ensure strength, and the strange term "pillared hardtop" was born. As a result, although there are still pure hardtops today, most models have no sashes on the door windows, and the roof is slightly low and light, and is called a hardtop. Some sports cars and other vehicles are equipped with detachable hardtops that can be removed. (4) Roadster: A light, two-seater open-top car, which was once common among sports cars. It had only minimal protection against bad weather, with a simple top that could be raised and celluloid windows on the sides. More recent models have roll-up windows and a sturdy top, and should be called a convertible coupe. Those with sturdy roll bars and a removable top or plastic roof, or a removable roof and rear window, are generally called Targa tops. This is because the German sports car, the Porsche 911 Targa, set the trend. In Italy, the name Spider comes from the fact that the low-lying, crawling form of the car resembles a spider, and in France, Torpedo means sleek like a torpedo boat. (5) Coupe: A word derived from a light, two-seater, box-shaped carriage, a box-shaped vehicle with a low, small roof, often found in sports cars. Originally it had two seats, but in recent years, 2+2 and 4-seat coupes are not uncommon, and the difference between a 2-door sedan and a 2-door hardtop is becoming smaller. A fastback coupe is a streamlined coupe with no notch between the roof and the trunk, and if a tailgate is added, it becomes a hatchback coupe. (6) Limousine: A typical type of large, high-class car, with the passenger compartment and driver's cab separated by retractable glass. The passenger compartment is particularly spacious, and two extra seats can be pulled out if necessary. Limousines are used as official vehicles for heads of state, for transporting dignitaries, and for executives of large companies, and can also hold meetings while moving. (7) Station wagon It is a myth that it originated from a stage coach. It was a horse-drawn carriage used to pick up and drop off passengers at train stations in the horse-drawn carriage era, and was then turned into a car. The roof of the sedan was extended to the rear to create a large luggage compartment, and a tailgate was installed at the rear. There are three-door and five-door models, with two rows of seats for 4-6 people, and three rows for 6-9 people. The second and third rows of seats can be folded down to use as luggage compartments. There are purely passenger models and commercial models for transportation and work. The latter are called light vans in Japan and are registered as trucks, and are included in the truck category in statistics. Light vans are subject to restrictions on the number of passengers and the maximum load capacity, but wagons registered as passenger cars are limited only to the number of passengers and their luggage, and not to the load capacity. Recently, one-box models with more interior space have been registered as passenger cars, and are popular for leisure use. In England, they are called estate cars, referring to cars used on manors, while in France, dual-purpose vehicles are called breaks (horse-drawn carriages for hunting) and purely passenger vehicles are called familiars, referring to cars for family use. In Italy, they are also called familiare, but in Germany, the more common name is combi. (8) One Box Car: A car in which the driver's seat and passenger seat are positioned almost to the very tip of the body, making the whole car look like a single box. A long time ago, this type of car would have been called a light van, but today it is recognized as a type of passenger car. It is particularly used as a minivan or SUV, and also as a type of sports car. [Takashima Shizuo] History of the AutomobileSteps towards practical applicationIt is believed that humans first invented the wheel 6,000 years ago, but the era of using horses or oxen to pull vehicles continued for a long time, until just a few decades ago. In 1250, the medieval European theologian and philosopher R. Bacon predicted the emergence of the automobile, saying, "One day it will be possible to make a car that runs on its own power, without relying on horses or other animals." Among the various ideas for new inventions drawn by the 15th and 16th century artist and scientist Leonardo da Vinci was one that used power generated by bending wood to store energy, which was then extracted by gears to turn the wheels and run. In 1569, Simon Stevin of the Netherlands built a two-masted sailing cart, which carried 28 people and traveled at 24 kilometers per hour on the hard sand of the coast. However, since it was not possible to zigzag on land, it did not become widespread. In 1648, Hans Hautsch, a German clockmaker, prototyped a one-seater cart that was self-propelled by a spring, and traveled at a speed of 1.5 kilometers per hour. However, the capacity of the spring was limited, and it was not practical. In 1680, the British physicist and mathematician Newton successfully conducted a model experiment of a vehicle that ran on thrust generated by high-pressure steam produced in a boiler ejected from a thin tube at the rear. However, this was the first jet-propelled vehicle in history, and because it ejected high-temperature, high-pressure gas, it was too dangerous for use on the road, so in the end, an actual vehicle was never built. The invention of the steam engine made it possible for cars to run purely on mechanical power. The first person to try to run a car on a steam engine was Belgian artillery captain Cugnot of Louis XV's army. He designed a steam car to pull artillery carriages, which was completed in 1769 by an engineer named Bressens, and two years later, he built a larger car No. 2. This car was a tricycle with an additional front wheel added to a huge two-wheeled cart, 7.2 meters long and 2.3 meters wide, and had a 50-liter copper boiler in front of the front wheel. The steam generated there was sent alternately to vertical cylinders, one on each side of the front wheel, to rotate the front wheel. There was no crank yet, and the up and down movement of the pistons turned the front wheel with a ratchet. Cugnot's steam car was tested at Vincennes, where it ran at 9.5 kilometers per hour with four people on board, but it was virtually impossible to steer because of the heavy boiler and cylinders on the steering wheels, and it crashed into the castle walls. Research into steam cars was most active and produced the most results in England, the birthplace of the steam engine. In 1801, Trevithick completed a fairly practical steam car that ran at 14 kilometers per hour, but an explosion occurred due to the driver's carelessness. Two years later, Trevithick created a four-wheeled car with huge driving rear wheels measuring 3.2 meters in diameter. A single-cylinder steam engine was fitted to the rear of a tall carriage body, and it was driven by a driver in the front and a steam engine driver in the back. This car was successfully test-run through traffic-blocked London at a speed "faster than a carriage." In Britain, the Industrial Revolution created a need for the transportation of materials and products, and a network of highways, paved with tar, invented by Macadam, was built across the country. In 1831, one of these highways was used to start regular passenger service by steam coach. Sir Charles Dance started a regular service between Gloucester and Cheltenham using three 20-seater six-wheeled carriages made by Goldsworthy Gurney. It was a success, carrying 3,000 passengers in four months. In the same year, Walter Hancock also built ten steam coaches, which he operated on regular routes between London and its suburbs for ten years. By the 1840s, the average speed of such steam coaches had risen to 25 km per hour, and Hancock's automaton reached 32 km per hour. In the 1850s, steam coaches rapidly disappeared. One reason was the development of railways, which used the same steam engines and were more efficient at transport. However, the biggest reason was that carriage companies and horse suppliers, who were facing a business crisis due to the spread of steam coaches, lobbied Parliament. For example, on the turnpike between Liverpool and Prescott, the toll for a four-horse carriage was 4 shillings, but steam coaches were charged 2 pounds 8 shillings, 12 times as much, on the grounds that they damaged the road. In 1861, the British Parliament passed the Red Flag Act, which came into full effect in 1865. The law, properly called the Locomotives on Highways Act, was extremely strict, stipulating that "any road locomotive (as early steam cars were called) must be operated by three people, one of whom must hold a red flag 60 metres ahead during the day and a red light at night, and must operate at a speed not exceeding 3.2 kilometres per hour in towns and 6.4 kilometres per hour in rural areas," and it was not repealed until 1896. While the development of steam cars in the UK was halted by the Red Flag Law, steam cars continued to progress in continental Europe and America. In particular, the eight-seater minibus Robeisant (the faithful one), built in 1873 by Amédée Bollée the Elder, was a progressive car with independent front wheels that swung left and right when steered, and two V-shaped two-cylinder engines that drove the rear wheels separately. Steam cars, which were originally huge coaches, gradually became smaller, and their shortcomings, such as not being able to run immediately after being turned on and the need to frequently refuel with water, were solved by flash boilers and condensers. As a result, in America, where the Selden Patent for gasoline-powered cars was in place, steam cars were built until the mid-1930s. Electric cars were invented in the mid-19th century, and showed signs of becoming popular for a time. However, due to low battery capacity and low performance, and the short driving distance per charge, they did not become mainstream. However, due to the characteristics of the electric motor, they do not require a transmission, making them easy to drive, and they are quiet and odorless, so they were popular mainly with upper-class women, and were produced in America until the 1920s. Even after that, they continued to be used indoors where exhaust could not be emitted. Recently, electric vehicles have been attracting attention again due to the spread of gasoline and diesel vehicles, and major manufacturers around the world are conducting research into their practical use. In particular, the state of California in the United States, which is plagued by air pollution, mandated major manufacturers to make 10% of the cars sold in the state ZEVs (Zero Emission Vehicles) in 2003, which accelerated research into electric vehicles. At present, the state is at the stage of improving storage batteries, but companies are focusing on the development of fuel cells, which react hydrogen fuel with oxygen in the air to generate electricity using the reverse principle of electrolysis. DaimlerChrysler of Germany and the United States announced that they would put fuel cell-powered buses into practical use in 2002. Solar cells are still at the stage of being used to run ultra-lightweight racing cars. [Takashima Shizuo] Invention of the gasoline-powered automobileWith the invention of the gasoline engine, automobiles began to develop and become more widespread for the first time. The history of the internal combustion engine is long. The Dutch scientist Huygens suggested the possibility of a prime mover based on differences in air pressure, which helped invent the steam engine, but in 1680 he proposed an internal combustion engine (atmospheric engine) that used gunpowder. In 1858, Italians Eugenio Barsanti and Felice Matteucci created an internal combustion engine fueled by coal gas, and two years later, the Frenchman Renoir created a gas engine with a primitive ignition device. Moreover, in 1863, Renoir mounted a four-stroke engine that ran on liquid fuel (gasoline) on a wooden four-wheeled cart and successfully test-ran it. The Italian Enrico Bernardi also created a gas engine in 1864, and a gasoline engine the following year in 1865. The Austrian Siegfried Markus was also developing a gasoline engine, and twice, in 1864 and 1875, he built prototypes of cars that ran on it. Marx's car No. 2 is still housed in the Science Museum in Vienna, and in 1975, its 100th anniversary, it was demonstrated running at a speed of 8 kilometers per hour. However, there are many questions about Marx's car, such as its age. In 1884, Edouard Delamare-Deboutteville and others in France succeeded in building a prototype gasoline-powered automobile, and France used this as a basis for grandiose celebrations of the "Centenary of the French Automobile" in 1984, but all of these attempts ended with the inventor's generation, and no history has developed since. In 1862, France's Beau de Rochas (1815-1893) discovered the principle of the four-stroke engine, and in 1876 Germany's Otto succeeded in commercializing a stationary gas engine based on that principle. One of the young researchers at Otto's factory was Daimler, who later set up his own research laboratory and, with the help of his friend from his days with Otto, Wilhelm Maybach (1846-1929), began developing a new engine, completing a small, lightweight, high-speed gasoline engine in 1883 and obtaining a patent for it. In order to make the engine portable, Daimler chose gasoline as his fuel, a fuel that at the time had no other use than for cleaning, and used a method in which the gas evaporated from the heat of the atmosphere when it was placed in a wide, shallow dish, and collected the gas that was produced. The most difficult part was ignition. As the idea of using electric sparks had not yet been thought of, they came up with a method called hot tube ignition, in which a platinum rod was screwed into the cylinder and heated from the outside with a burner to ignite the gas inside. Daimler and Maybach attached a single-cylinder, 250cc, 0.4 horsepower engine to a wooden two-wheeled vehicle, and obtained a patent in 1885. The first practical gasoline-powered automobile in history was actually a motorcycle. Piloted by Daimler's eldest son Paul, this motorcycle successfully completed a test run of at least three kilometers near Stuttgart, recording a top speed of 12 kilometers per hour. The following year, in 1886, Daimler attached a steering wheel to a horse-drawn carriage that he had made as a birthday gift for his wife, drilled a hole in the floor of the rear seat, and attached a single-cylinder, 460cc, 1.1 horsepower engine to create a four-wheeled automobile. Meanwhile, Benz built a gasoline engine on his own, and used it to complete a three-wheeled automobile in 1886, for which he obtained a patent. Today, Daimler and Benz are known as the fathers of the gasoline-powered automobile, not only because they invented a practical gasoline-powered automobile, but also because they established a small-scale business that manufactured and sold the automobile, and granted the manufacturing rights for engines and automobiles to other companies, working to popularize them. Daimler (which changed its car name to Mercedes after 1900) and Benz grew as rival companies, before merging in 1926, and then merging with the American Chrysler Corporation in 1998 to become DaimlerChrysler. [Takashima Shizuo] Industrialization of productionになったんです。 English: The first thing you can do In 1894, just nine years after Daimler's first motorcycle, the first motorsport event was held in 1894, hosted by the French newspaper Petit Journal. It was held 126km between Paris and Rouen, and not only was its speed, but its reliability and convenience were also judged. At this event, the de Dion Bouton steam car driven by the de Dion Conte de Dion arrived first place at an average speed of 21km/h. However, the car was dropped to third prize because it lacked convenience, as it required a canter besides the driver, and the first prize was awarded to the second and third petrol cars, Panard et Lebassor and Peugeot. The advantage of the gasoline car was proven, and the de Dion Bouton soon switched to gasoline cars. Early cars, although expensive, were unknown when or where they would break down, were toys for young aristocrats and wealthy people. However, in America, a vast emerging country that was first developed by wagons and then by rail, they needed fast and long-distance vehicles. Moreover, in this country without aristocracy, cars were popularized from the beginning. For example, the Olds Mobile Curved Dash car of the Olds Ramson Eli Olds (1864-1950) produced 425 units in 1901, making it the first mass-produced car ever. The T-Ford, which was sent by H. Ford in 1908. Due to its simple and affordable design, it was easy for women and the elderly to handle, was not easily broken, and was relatively inexpensive, making it a hit selling 10,000 units in the first year. To meet the flooded orders, a new factory was built in 1913 in Highland Park, Michigan, where mass production was started using the first conveyor line in the automotive industry. Parts were kept waiting next to the conveyor line and assembled one after another on the chassis flowing over the line, resulting in a dramatic increase in productivity. As a result, in 1925, at its peak, its production was 1,990,950 units per year, reaching a 2 million mark. The T-Ford, which was $850 at the time of its release in 1908, was reduced to $260 for the cheapest roadster in 1925, and spread to the masses. Moreover, the T-Type Ford was made from expensive materials because of mass production, and the processing was uniform for the flow process, and the quality was dozens of times comparable to expensive luxury cars. However, Ford still, he made a good profit, gave workers a daily wage of $5, which is twice the average at the time, and in 1914 he paid a check to new buyers a rebate of $50, and in 1914 he was called a management magician. The T-Type Ford was produced in the UK and Germany outside the United States, and was assembled in various parts of the world, including Japan and Australia. From the announcement on October 1, 1908, by May 26, 1927, when production was discontinued to make way for the next A-Type, the T-Type Ford had reached 15,007,033 units, and at its peak, 68 of the 100 cars on earth were T-Type Fords. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In this year, Peugeot developed the 667cc Quadrilet into Type 172 in France, Renault released the 950cc Type KJ, and Austin released the 747cc Seven in the UK, which crossed Dover, and many small mass cars of less than 1,000cc were released. This was the first year of the popularization of automobiles in Europe. The Great Economic Depression that struck the whole world in 1929 had no choice but to have a major impact on the automotive world. First, pre-modern aristocracy and billionaires eclipsed the shadows, and the civil class became even stronger. As a result, countless super-luxury cars almost disappeared before World War II, and cars became more and more like mass-produced, mass-sale, mass-consuming goods, or durable goods. Autos became a product sold through advertising and trends, and were even considered to be the child of capitalist society. The prominent trends in automobiles in the 1930s were streamlined. Particularly, this was the desire to get closer to the smartness of faster planes. At the same time, the advancement of chassis designs made the passenger compartment in the most comfortable part between the front and rear axles, making it difficult to adopt the classic car shape. The parts that were independent of the headlights, radiators, bonnets, fenders, steps and trunks gradually absorbed into the body as an organic box, resulting in a wider interior space. Structurally, advanced cars and American cars on the continent of Europe became popular with independent front wheel suspensions that gave a better ride, and by the end of the 1930s, some small cars featured lighter, stronger monocoque bodies. [Takashima Shizuo] History of automobiles in JapanThe first automobile to be introduced to Japan was an electric car presented by the Japanese Association of Japanese Residents in San Francisco in 1899 (Meiji 32) to celebrate the marriage of the then Crown Prince (later Emperor Taisho). At this time, the steam locomotive driver was brought in from the Ministry of Railways to test run, but he failed to dodge the old woman among the spectators and jumped into the moat from Miyakezaka or Kinokunizaka. What is certain is that in 1900 (Meiji 33), an American trader Thomson, who lives in Yokohama, imported an American steam car Locomo building. Miyazaki Minetaro, who learned to drive with Thomson at this time, is considered to be the first Japanese person to drive a car in Japan. [Takashima Shizuo] The road to domestic productionIn 1902 (Meiji 35), Yoshida Shintaro, who ran a bicycle dealer in Ginza, made a prototype of a passenger car with the help of Uchiyama Komanosuke. However, the engine was brought back by Yoshida from the United States, so it cannot be considered a purely domestic car. However, the two founded the Automobile Shokai in the same year, and built a 12-seater bus chassis in response to orders from Hiroshima. However, the chassis was equipped with a heavy city tram body in Nagoya, so they were unable to drive well, and the tires were not able to bear. The two worked to absorb automobile technology and accumulate experience while repairing incoming imported cars, and established Tokyo Motor Corporation in 1904. However, they were unable to become the first manufacturer of purely domestic automobiles. This was because Yamaba Torao of Okayama made a steam bus on his own in 1905. However, this was because it was driven but far from practical use, and it was not developed in Japan's automobile technology. Therefore, it was the aforementioned Tokyo Motor Corporation that created the first Japanese-made gasoline passenger car in the true sense of the sense of the word, in 1907. This was the result of Arisugawa Miya, one of Japan's pioneer motorists who brought back Dalak cars from studying in France, strongly recommended the company to have the company feel uncomfortable about cars. Therefore, the first Yoshida-style passenger car was delivered to the Arisugawa Miya family, and the pilot of the shrine was successfully tested between Tokyo and Nikko. The car, which was 1,853cc, with a horizontally opposed two-cylinder, 12 horsepower engine, was named Takury by the driver, after it ran rattling and rattling along the unpaved road at the time. By the following year, 1908, 10 of the cars had been built (one of which was a truck), and was loved as a major figure in the political and business world of the time, including Hibiya Heizaemon, Nakagamigawa Jirokichi, Arima Yoritsumu, Fukuzawa Komakichi, and Inoue Kaoru. In 1911, Hashimoto Masujiro established the Kaishinsha Automobile Factory in Tokyo, and initially assembled it using imported parts, but in 1914 (Taisho 3), the company began manufacturing the DAT (relative to DAT) number, which has initials from its sponsors, Taden, Aoyama, and Takeuchi. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In 1933, the company was officially established as Nissan Motor, and built the largest mass production factory in the Toyo company in Koyasu, Yokohama. Datsun production at the factory reached 800 units per month in 1937 and 1938, at its peak. Although this may be a bit late, the Mitsubishi Shipbuilding Kobe Shipyard studied under the Italian Fiat Zero in 1917 and completed the Mitsubishi A-Type passenger car. By 1923, approximately 30 of the same car had been built, and it can be said to be the distant ancestor of today's Mitsubishi Motors products. In 1918, as a result of the recognition of the military importance of automobiles, the Military Automobile Protection Act, which grants subsidies to trucks that meet certain standards set by the Army. This is the first law in Japan to promote the development of the automobile industry. In response, Tokyo Gas Electric Industry began producing TGE (short for Tokyo Gas Electric) trucks, and Ishikawashima Shipyard also obtained the right to manufacture British Oosley vehicles and first made passenger cars domestically, but soon turned into trucks and later created buses. The two companies partnered in 1933, merged in 1937, and became Isuzu Motors after World War II. [Takashima Shizuo] Competition with foreign companiesになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. However, it is not possible to keep the Japanese market occupying Ford and Chevrolet. Nissan Motor Co., Ltd. bought the unrest production facilities of Graham cars in the United States, and began production of large passenger cars, trucks and buses in 1936. Around the time, Kiichiro, vice president of Toyoda Automatic Loom, made the first passenger car prototype in 1935, commercialized the truck in the same year, and began construction of a large factory in Koromo, Aichi Prefecture (now Toyota City). The factory was completed in 1938, and the following year, in 1939, the Toyota Automatic Loom Automobile Division became independent and became Toyota Motor Corporation (now Toyota Motor Corporation). [Takashima Shizuo] Post-war reconstructionThe Allied forces that occupied Japan after World War II overestimated the power of Japan's automobile industry, strictly restricted automobile production, and in particular passenger cars were effectively banned. The production restrictions were lifted in 1949 (Showa 24), but the gap between the wartime period when passenger cars were not being produced was large, and from around 1952 many manufacturers began technological partnerships with manufacturers from developed countries, knocking down foreign cars, and gradually turning them domestically to make them work to absorb technology. Nissan Motor Co., Ltd. created the A40 in the UK, while truck and bus manufacturer Isuzu Motor Co., Ltd. also joined with British Roots to make Hillman Minx domestically. Hino Motor Co., Ltd. (now Hino Motor Co., Ltd.), a heavy truck and bus manufacturer that was independent of Isuzu's tank factory, also planned to expand into small passenger cars, and converted Renault 4CVs from France and Renault Corporation into domestically produced Renault 4CVs. East Japan Heavy Industries, which was born from the former Mitsubishi Heavy Industries due to the dismantling of the zaibatsu, assembled the Henry J compact car from Kaiser Fraser, and the new Mitsubishi Heavy Industries also began to domestically produce Willis Jeep. Meanwhile, Toyota Motor Co., Ltd. and Fuji Precision Industries (later Prince Motor Co., Ltd., which was derived from the former Nakajima Aircraft and Tachikawa Aircraft, worked alone to accumulate technology while learning from overseas. During this period, Toyo Kogyo (now Mazda) and Daihatsu Kogyo were still specialized manufacturers of three-wheel trucks, and Suzuki Motor Co., Ltd. (now Suzuki) was planning to expand into light vehicles in addition to motorcycles, but Honda Motor Co., Ltd. was still a manufacturer of motorcycles exclusively. Similarly, Fuji Heavy Industries, the former Nakajima Aircraft, also made bus bodies, but it would still be a while before the minicar Subaru began expanding into four-wheeled vehicles. The national policy was to protect and nurture the domestic automobile industry, and due to a lack of foreign currency, the import of passenger cars was effectively banned from 1953 to 1958, except for press and tourism. After this economically difficult but ambitious learning period, the Datsun 110, Toyopet Crown and the master were announced in 1955, and finally the technically approached Western standards, and Japanese passenger cars were in an era of mass production and popularization. [Takashima Shizuo] Mass production and mass productionIn particular, since the 1960s, thanks to the policy of doubling income, four-wheel vehicle production continued to grow rapidly, increasing by 40-80% per year, and served as a core industry in Japan's industrial-based industry. Japan's four-wheel vehicle production surpassed the developed countries of Europe, including Italy in 1962 (Showa 37), France in 1964, the UK in 1966, and Germany in 1967. In 1980, it surpassed the long-standing top position of the United States, and finally became the world's number one spot, and since then it remained in its position until 1993 (Heisei 5). In response, demands for market opening and capital liberalization increased from other countries, and imports resumed under the allocation system in 1959, and imports of trucks and buses were liberalized in 1961, and imports of completed passenger cars were liberalized in 1964. In 1971, engine imports were liberalized, and in 1978, a bold policy was adopted to eliminate import duties on completed vehicles. Meanwhile, capital participation from foreign countries was first liberalized in 1967, and completely liberalized in 1973. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. This remarkable expansion of Japanese cars overseas proves that they have improved quality, and now Japanese cars are even symbols of high quality. In particular, the high production technology that makes full use of industrial robots does not allow other countries to follow suit. In terms of design technology, the world's strictest emissions regulations have led to research on combustion, and they have succeeded in achieving both performance and economics. In addition, it can be said that they will be at the cutting edge in terms of electronics applications to automobiles. This high-technical capabilities of the Japanese automobile industry are something that we would absolutely love for major Western manufacturers, and we continued to request for technical alliances and capital alliances. At the same time, the bubble burst in Japan, and despite its technical capabilities, its management strength was exposed, and many Japanese manufacturers accepted foreign capital. First, Mazda accepted Ford's capital, Isuzu Motors, Suzuki, and Fuji Heavy Industries, GM, Nissan Motors, Renault, and Mitsubishi Motors, Daimler Chrysler's capital. As a result, only Honda Motors, Toyota Motors, and Toyota's affiliates, Daihatsu Motors and Hino Motors, were all affiliated with Toyota. [Takashima Shizuo] Automotive structure
[Takashima Shizuo] engineになったんです。 English: The first thing you can do CNG-fueled vehicles, which began to become popular around 1998, are fueled by CNG (compressed natural gas) instead of gasoline, and the operating principle and structure of the engine are similar to that of gasoline engines. (1) 4-stroke engine Inline 4-cylinders are the standard for small cars up to around 2000cc, but in recent minicars and 1000cc-class popular cars, it is not uncommon to have inline 3-cylinders that can be easily mounted horizontally between the left and right front wheels using the FF system. Similarly, in the 2000cc class or above, the number of compact V-6s tends to increase. In addition, V-8, 12, horizontally opposed 4, 6, and 12, are also used. With the same displacement, the more cylinders the inertia mass of each piston and connecting rod, and the more rotation, and therefore the higher the output, but on the other hand, the more the structure is complicated, the higher the cost, and the more maintenance is cumbersome. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. There are also SOHCs (Single OHCs), which operate both the intake and exhaust valves with one camshaft, and DOHCs (Duble OHCs), which specialize in operating the intake and exhaust valves with two camshafts. DOHCs allow for a hemispherical shape with more combustion efficiency, and the intake and exhaust effect is also improved. High rotation speeds are possible in the order of OHVs, SOHCs, and DOHCs, and the output is increased, but the structure is complicated and cost is increased. Until a few years ago, DOHCs were only used in racing cars and some high-performance sports cars, but today's domestic cars are used in high-performance models even in the popular car class. Furthermore, it is not uncommon to have two intake and exhaust valves each in combination with DOHC, increasing the intake and exhaust efficiency. (3) Rotary Engines Today, along with four cycles, rotary engines are used in passenger cars. Around 1951, German Bankel Felix Wankel (1902-1988) established the principle of this. It was introduced in 1951 by the former West Germany NSU (NSU) in 1960. The NSU was used on two or three cars, but the expected results were not achieved, and many other manufacturers around the world studied its purpose, but none of them worked. Among these, Japan's Mazda has successfully put it into practical use with its own technology, and used it in high-performance models, and installed it in racing cars. Its weakness is that its fuel consumption is high, and as a result, the future was at stake during the oil crisis, but it has since improved considerably. There is also the possibility that rotary engines have a turbo, diesel, turbo diesel, etc. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Some ignition systems use transistors to strengthen the spark, while some use microcontrollers to adjust the ignition timing, while others have centralized the electronic control of fuel injection and ignition systems in other countries. Various new materials are being applied to engines and their auxiliary equipment, but some of the things that are likely to become popular in the near future include ceramics and plastics. In the United States, engines that use plastics, from cylinder blocks to pistons and connecting rods, have already been prototyped to produce plastics, and are only used in a limited number of parts of the engine, and are being tested in harsh races. (5)ディーゼルエンジン 爆発圧力が高いのでトルクが強く、また燃料消費が少ないうえに、燃料が低廉なので経済的である。反面、振動や騒音が大きいうえに、高回転が得られず、各部をじょうぶにつくらなければならないので重い。したがって長く大型トラック、バスに限られていたが、改良の結果、近年は乗用車にも用いられている。大型車用はシリンダー内に直接燃料を噴射する、より効率の高い直接噴射式が増えつつあるが、乗用車は騒音の小さい予燃焼室が依然中心である。ディーゼル乗用車はガソリン車に比べて出足が鈍く、最高速度も伸びないが、最近はターボの採用でガソリン車なみの性能をもつものも現れている。 日本では長く、産業振興の建前から、輸送の根幹をなす商用車への規制に消極的な傾向があった。その結果、ディーゼル車の排出するSPM(Suspended Particulate Matter、浮遊粒子状物質)やNO xにより、それらの濃度が環境基準を達成しない状況が続いた。石原慎太郎東京都政はこの状況を打開すべく、2000年に独自のディーゼル車の排出ガス規制を打ち出した。すでに使用中のディーゼル車に排ガスの後処理装置を取り付けるには多大の費用がかかるため、運輸業界は反対の立場を表明、自動車メーカーも消極的で、大きな論争が展開された。しかし規制が実施され、それが全国に波及することは必至である。これに対してメーカーはクリーンなディーゼルエンジンの開発を急ぐ一方、CNG(圧縮天然ガス)車の普及にも活路をみいだそうとしている。 (6)ターボチャージャーとスーパーチャージャー ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、近年普及の著しいのがターボチャージャーturbo chargerである。これは、通常そのまま大気中に捨てている排出ガスの圧力でタービンを回し、その力でポンプを働かせて、普通はエンジンが自然に吸い込む吸入気を積極的に押し込み、より高い爆発圧力を得るものである。エンジンにもよるが、出力は30~50%も向上する。いわば廃物利用の省エネルギー装置だが、現実には低速ではほとんど効果がないし、アクセルを踏んでも排気圧力が高まって効き始めるまでに時間的なずれがある、など弱点もある。そのためしだいに適用範囲が整理され、とくに高性能を売り物にする車だけに限られる傾向にある。 ターボにかわって、1980年代中ごろから注目され始めているのは、スーパーチャージャーsuper chargerである。これはポンプをエンジンで直接駆動するので、低速から効果を発揮し、いわゆるターボラグのような効きの遅れもない。もともと気圧の低い高空を高速で飛ぶ戦闘機用として発明されたものだが、1920年代初期から第二次世界大戦までは、レーシングカーや高性能スポーツカーに広く用いられた。戦後は有鉛高オクタン価ガソリンの普及などで使われなくなっていたが、無鉛ガソリン時代に入ってふたたびクローズアップされ始めたといえよう。 (7)出力とトルク エンジンの性能を表す方法には、出力(馬力ともいう。単位PSまたはkW)とトルク(回転力。単位kg・mまたはNt・m)の二つがある。出力は一定時間内に行うことのできる仕事の能率を表すから、出力の大きいほど速く走れるし、あるいは重い物を運べる。これに対しトルクは絶対的な回転力だから、トルクが強ければ出足がよく、あるいは登坂力に優れる。表記に際しては、最高出力、最大トルクともに、それを発生する回転数(単位、回転/分またはrpm)を併記する。出力は回転力に回転速度を掛け合わせた、仕事量を表すものだから、それを発生する回転数がわかれば、トルクの強いタイプか、回転数で出力を稼いだものか、そのエンジンの性質がわかる。一方トルクは絶対的な回転力だから、エンジンをつねに最大トルクを発生する回転に保てば、強い加速力と最良の燃費が得られる。高性能な自動車がタコメーター(エンジン回転計)を備えているのは、一つにはエンジンを回しすぎて壊さないためであるが、同時に、つねにエンジンを最大トルク発生回転域に保って、よりよい出足と、より少ない燃料消費を得るためである。 自動車のカタログなどにはよく、縦軸にトルク、横軸に回転数をとって、そのエンジンのトルク特性を表した線グラフが載っている。これが一般にトルクカーブとよばれるもので、レーシングカーのエンジンでは最大トルクは強いが、その前後では急速に落ち、険しい山の頂上のようになっており、しかも頂上は高回転側に寄っている。したがって、絶えず変速を繰り返して、その回転を保たなければ強い力が得られない。これに対し実用車のエンジンでは、最大トルクの数値こそ低いが、トルクカーブはなだらかな丘のような形をしており、しかも頂上は低回転側に寄っている。したがってどのギアに入っていても比較的強い力が得られ、そう頻繁に変速をしなくてもすむ。 (8)公害対策 自動車の排出ガス中には、燃料が未燃焼のままエンジンを通り抜けてしまう炭化水素(HC)、燃焼によって生じる一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NO x )など、人体に有害で大気汚染の原因になる成分が含まれている。ロサンゼルスのスモッグに悩むアメリカでは、カリフォルニア州がいち早くその規制に乗り出し、まもなくアメリカ連邦規制に発展した。日本でも、東京・牛込柳(うしごめやなぎ)町の鉛公害がきっかけとなって大気汚染公害が大きな社会問題となり、1966年(昭和41)から自動車の排出ガス規制が始められた。1978年には10(テン)モードでHCが許容限界0.39グラム/キロメートル(平均規制値0.25)、COが2.7グラム/キロメートル(同2.1)、NO xが0.48グラム/キロメートル(同0.25)という、世界一厳しい乗用車の規制が実施された。これに対し日本のメーカーは、シリンダー内での燃焼を研究して有害成分の発生を抑えるとともに、効率のよい後処理装置を開発、排出ガス浄化技術ではいまや世界の先端をいくといってよい。さらに燃焼についての研究が進んだ結果、副次的に性能と経済性も向上したことは特筆される。2000年(平成12)10月(継続生産車と輸入車では2002年9月)には、乗用車の10/15モード平均規制値でCOが0.67グラム/キロメートル、HCが0.08グラム/キロメートル、NO xが0.08%とさらに強化され、現実に規制実施前に先取りしてこの値をクリアする車も出た。 浄化技術として現在一般的なのは、シリンダーとピストンのわずかなすきまを通り抜けたブローバイガス(生ガス)をふたたび吸入させて燃焼させる(HCの減少)、不活性ガスとしての自身の排気を少量吸入気に混ぜて燃焼温度と速度を下げる(NO xの発生の抑制)、吸入バルブのほかに小さいバルブをつけるなどして吸入気に渦流をおこし完全燃焼を促す(HC,COの減少)などである。また、シリンダー内に直接燃料を噴射するDGIも普及しつつある。それでも排出ガス中には少量の有害成分が残るので、排気管の途中に三元触媒をつけて一挙に取り除く。さらにガソリンと電気を併用する、いわゆるハイブリッド方式もすでに実用化されている。将来は燃料から直接電気エネルギーを取り出す燃料電池が実用化されるであろう。 またガソリンには、オクタン価を高めてノッキングを防ぐために、長く鉛化合物(四塩化鉛)が混入されてきたが、日本では1972年4月以降の生産車は無鉛ガソリンの適合車とされ、1975年2月から無鉛ガソリンの生産が開始され、今日では完全に無鉛化された(一部の中古車や輸入車のために有鉛ガソリンも供給されている)。 また騒音規制も実施されており、日本では定常走行排気騒音は1971年4月以降の新型車から乗用車で70ホン、トラック、バスは車両総重量3.5トン以下が74ホン、同3.5トン超、最高出力200馬力以下が78ホン、同3.5トン超、200馬力超が80ホン以下とされている。加速走行騒音は年々強化され、1985年で乗用車と車両総重量3.5トン以下のトラック、バスが78ホン、同3.5トン超が83ホン以下とされた。2000年時点の規制値は加速走行騒音で大型トラック83デシベル(A)、大型バス81デシベル(A)、中型車83デシベル(A)、小型車76デシベル(A)、乗用車76デシベル(A)、二輪車73デシベル(A)、原動機付自転車71デシベル(A)となっている。 なおヨーロッパでは1980年代に入ってからドイツのシュワルツワルト(黒い森)の酸性雨による被害が表面化し、1984年ごろから排出ガス規制へ向けての動きが出始めている。しかし1985年からドイツでようやく無鉛ガソリンの供給が始まった程度で、各国の足並みはそろっていない。 [Takashima Shizuo] 駆動系統(1)変速装置 エンジンは一定の回転を保たないと強い力を出さないのに対して、自動車は自由に速度を調整できなければならないし、また重いので走り始めるときにはとくに大きなトルクを要する。そこで必要なのが変速装置である。通常のマニュアルトランスミッションmanual transmission(手動変速機)では、エンジンを出たトルクは、2枚の回転する摩擦円盤を圧着したり引き離したりして回転を断続するクラッチへ伝えられる。三つのペダルのうち左端を左足で踏むとクラッチが切れ、離すとスプリングでつながる。 次に回転はギヤボックスgear box(歯車式変速機)へ伝えられる。一つの箱の中に3組から6組の歯車の組合せを収め、外からシフトレバーで適宜組合せを選んで使えるようにしたのがギヤボックスである。エンジンの強力な大型車では3段のものもあるが、小型車では4段が普通で、高性能車ではエンジンの力を余すところなく使うために5段から6段のものも珍しくない。通常、最上段は1対1の直結だが、加速を終わって一定速度に達したのちは、大きい歯車から小さい歯車へ伝えて増速することもできる。そうすると、同じ速度で走ってもエンジン回転はその分だけ低くてもよいので、燃料消費は減り、エンジンの摩耗も少なくなって長もちするようになる。この1対1を超えた増速ギヤをオーバードライブギヤover-drive gear(OD)といい、5段変速機のトップをODにするものが少なくない。 ギヤはクラッチを切った状態で入れ替えるが、慣性で回ったままなので、ガリガリいってなかなかうまくかみ合わない。とくに上の段から下の段にシフトダウンする際が初心者にはたいへんむずかしいので、かみ合わせようとする二つのギヤの速度を、摩擦クラッチであらかじめ同じにし、スムーズに入るようにしたのがシンクロメッシュsynchro-mesh(同期かみ合い式)変速機である。今日のほとんどの乗用車は、すべての前進段数にシンクロメッシュを備えている。 アクセルペダルの踏み方一つでスムーズに走り始め、自動的に最高速まで加速できるようにし、クラッチペダルをなくしたのが自動変速機(オートマチックトランスミッションautomatic transmission)である。その心臓部は流体トルクコンバーターで、三つの羽根車が密閉容器に入り、オイルが満たされている。 ただし、これだけではトルク、速度ともに変換率が小さいので、油圧で自動的に制御される2段から4段の機械式変速機を併用して補う。初期には2段しかなかったが、最近では4段にしてエンジンパワーをよりよく生かしたものが多い。自動変速機はトルクコンバーターのスリップなどのため、どうしても加速力、最高速ともに手動式変速機に劣り、燃料消費率も悪い。そこで最近では、加速を終わって駆動側、被駆動側の2枚の羽根車の回転が1対1に近づいたときに、トルクコンバーターを機械的に、あるいは電磁石で直結させ、スリップによる性能低下を防いだものが増えつつある。これがトルクコンバーターのロックアップ装置で、トップだけにロックアップの効くものもあるが、進んだものでは全段に効くようになっている。またギヤボックスの場合と同様、自動変速機でもトップをオーバードライブにしたものがある。 これまでの自動変速機では、歯車変速機の変速点を調速機などで機械的ないしは物理的に探し出してきたが、最近ではそれをマイコンで行う電子制御自動変速機(EAT)もある。各種のセンサーでアクセル開度、エンジン回転、車速、エンジン温度などを感知し、マイコンで演算させて最適変速点を精密に割り出すので、加速や燃費が改善される。さらに進んだものでは、変速パターンを性能重視型と経済性重視型の2モードにし、運転者が必要に応じて選択できるようにしたものもある。このような自動変速機技術では、日本は世界の先端をいくといってよい。 しかしながらトルクコンバーター式自動変速機はコストも高く、1000cc以下の小型大衆車には向いていない。そこで現在注目を集めているのが、オランダのバン・ドールネ・トランミッシー社が特許をもっていた無段階変速機(continuously variable transmission、略称CVT)である。遠心力で径の変わるプーリーとベルトによる効率の高い方式である。しかも構造が簡単で比較的安価に供給でき、1986年には特許が切れたので、以後、ゴムベルトを金属ベルトにかえたものが急速に普及した。また、CVTを改良したECVT(electro CVT)も実用化されている。 (2)4WD 現在の一般的な乗用車は、四つの車輪のうち後ろまたは前の2輪だけを駆動して走っている。しかし悪路を走行する機会の多い車では、4輪全部を駆動する四輪駆動(4WD)としたものも少なくない。さらに最近ではとくに強力な高性能車において、エンジン出力を確実に路面に伝え、しかも高速での安全を確保するために四輪駆動とするものが増えつつある。前者は舗装路上では二輪駆動に切り替えるので、パートタイム4WDとよぶのに対し、後者は常時なのでフルタイム4WDないしはパーマネント4WDという。フルタイム4WDでは左右車輪間だけではなく、前後車軸間にもデフを備えるのが普通である。 (3)デフ デフはディファレンシャルギヤdifferential gear(差動歯車装置)の略で、カーブを曲がる際には内側の車輪はゆっくりと、外側の車輪は速く回らないとスムーズに走れないので、自動的に速度差をつける歯車装置のことである。しかしパワーの強い車では加速中に1輪が空転してハンドルをとられたり、出足が鈍ったりすることがあるので、急激に左右輪の回転差が大きくなった際には、機械式または電磁式のクラッチで左右の差動を抑制するようにしたものがある。これをリミテッド・スリップ・デフlimited slip differential(LSD)とよぶ。 [Takashima Shizuo] Chassis(1)モノコックボディー 一昔前の自動車は、はしごのような形をしたフレームにエンジン、駆動系統、サスペンション、操向装置などを組み付け、それに、別工程でつくったボディーを載せる、という方法でつくられていた。しかしいまやほとんどすべての乗用車が、車体を軽くじょうぶな一つの箱としてつくりあげ、これにエンジンその他の諸装置を取り付ける。このような構造様式をモノコックボディーmonocock bodyという。ボディーの主材料は鋼板だが、最近では軽量化のために軽くてじょうぶな高張力鋼板や軽合金なども多用されるようになった。同時に2枚の極薄の鋼板の間にプラスチックを挟んだラミネート鋼板や、プラスチックの使用も進みつつある。これらの新素材は軽くじょうぶなだけでなく、加工しやすく、しかも自動車ボディーにとって最大の敵である錆(さび)の発生の少ないものが選ばれている。 (2)サスペンション エンジンとともに自動車の性能を大きく左右するのはサスペンションsuspension(懸架装置。車輪と車体を結ぶばね装置)で、不断に変化する路面の不整を吸収して自動車を適応させるとともに、操向輪をつねに接地させてかじ取りを確保し、駆動輪をつねに接地させて推進力を確保する。同時に乗客や荷物、自動車自身の車体を路面のショックから守る役目を負っている。一昔前の自動車では、車輪は1本の車軸の左右についていたが、いまは1輪ずつ別々のばね装置で支持された独立懸架が多い。これは、自動車の車体をクレーンで吊(つ)り上げたときに、ばねの下にぶら下がる部分の重量(ばね下重量)が小さいほど、車輪の路面への追従性がよくなり、乗り心地、操向性、駆動力ともに高まるからである。 サスペンションに使われるばねには金属、ゴム、気体などがあり、金属ばねにもコイル(弦(つる)巻き)、リーフ(板)、トーションバー(ねじり棒)などがあり、それぞれに特質があるので必要に応じて使い分けている。独立懸架の方式で現在一般的なのはウィッシュボーン式、ストラット式、セミトレーリング式などである。ばねには固有振動数があり、路面の凹凸の周期や車体の固有振動に合致すると走行中揺れが止まらなくなるばかりでなく、増大して操向性や乗り心地を低下させる。そこで各輪には油圧の力でばねのむだな動きを吸収するショックアブソーバーshock absorber(ダンパーdamperともいう)が備えられている。車体の重量やその位置配分などに応じて、ばねの硬軟、ショックアブソーバーの効き方の最良の組合せを探し出すのは、設計、開発陣にとってはきわめて困難な作業である。まして乗り心地は人によって好みが分かれる。そこで最近ではショックアブソーバーの効き方を3段ほどに調節可能とし、運転者が好みと路面情況に応じて任意に選べるようにした車も少なくない。さらに進んだものでは、路面情況に応じて電子的に自動調節するものさえある。すなわち、単位時間内の車体の揺れをカウントし、揺れが多くなるとダンパーの効きを強めるものや、走行前方の路面の不整を超音波などで事前に察知し、即座に調節してしまうもの、などがある。 (3)ステアリング 現在一般的なステアリングは、アッカーマン方式といい、操向する左右前輪の中心線をかならず後車軸の延長線上で交わらせることにより、スムーズにコーナーを回らせるものである。ステアリングホイール(ハンドル)の回転を前車輪の首振りに変えるステアリングギヤは、軽くスムーズなリサーキュレーティングボールrecirculating ball(ボール循環)式と、より直接的で確実なラック・ピニオンrack and pinion式である。前者は一般の車に、後者はよりスポーティーな車に使われるが、最近の傾向としては旧来少数派であったラック・ピニオン式が増えつつある。さらに最近では直進付近の歯車比を遅くして、高速走行時には安全なようにハンドルの効きを鈍くし、低速では歯車比を速くしたバリアブル・レシオvariable ratioのステアリングギヤも普及している。 大型車や小型でもFF車ではハンドルが重くなりがちなので、パワーステアリングで操舵(そうだ)力を補う。これは、エンジンで駆動するポンプで油圧をつくって蓄えておき、ハンドルを切った際に、その切り方に応じてバルブを開き、シリンダーで車輪を曲げる力を補うものである。これも最近では、車の速度やエンジンの回転に応じて、高速ではパワーの効き方を弱く(ハンドルを重く)、低速では強く(軽く)なるように、電子制御するものが現れている。さらに油圧のかわりに電気モーターで補力するものも珍しくない。 これまでの通常の四輪車では、FRとFF、RR各方式を問わず、前2輪のみで操向を行ってきた。しかし最近では、四輪操向(4WS)の車も実用化されている。むろん主たる操向輪は前輪だが、後輪にもその何分の1かの操向角を与えて、スムーズなコーナリングを可能にしようとするものである。4WSには前輪と後輪に同方向の舵角を与える同位相操向と、前後を逆にする逆位相操向とがある。前者は高速道路上での車線変更や駐車時に有利であり、後者は曲がりくねった山道などに向く。この位相はドライバーが意図的に選択できるが、同時に前後の操向角のバランスとともに電子制御も行われる。4WSの最大のねらいは操向時の車輪のスリップをなくすことで、より安全な車への要求にこたえるものである。 ブレーキは右足のペダルで操作するが、ペダルと各車輪のブレーキは油圧で結ばれ、パスカルの法則を利用してペダル踏力を軽くしてある。それでも足らない車は、エンジンの吸気によって生じる負圧を利用したサーボ機構servo-mechanism(倍力装置)を備える。サーボを備えたブレーキをパワーブレーキという。油圧の配管は前後、あるいは右前輪と左後輪、左前輪と右後輪というぐあいに、2系統に分け、一方が故障してももう一方で安全が保てるようにすることが義務づけられている。 [Takashima Shizuo] Safety自動車は最大の安全性をもつよう設計され、実車による衝突実験で確認されたもののみが生産されている。車体は中央の客室部分が一段と強固に、前後の張り出し部分はやや柔構造になっており、衝突時にはその部分がショックを吸収しながらつぶれて客室を保護する。ドアの内部には側面衝突に備えてガードレールがつくり込まれている。燃料タンクは衝突時に燃料の漏れない構造のものが、もっとも安全な位置に備えられる。窓ガラスは安全ガラスが義務づけられているが、国産車はこれまで強化ガラスが大半を占めていた。しかし強化ガラスは鋭角に割れて乗員の目を傷つけたりするので、1986年型からは、2枚のガラスの間にビニルの薄膜を挟み込んだ、割れても飛散しない合わせガラスの使用が促進されている。 乗用車の室内では、ステアリングホイール(ハンドル)や計器板が衝撃吸収構造になっており、運転者席と助手席にはヘッドレスト(頭部後傾抑止装置)がついている。乗用車と小型トラック、軽トラックの車体側面には隣接する前向きの座席には3点式、その他の座席には2点式のシートベルトの装備が義務づけられている。1985年9月1日には道路交通法が改正され、高速道路、一般道路を問わず、運転者、前席同乗者は走行中シートベルトを着用することが義務づけられた。違反すると反則点1点を課せられる。 以上は、万が一衝突事故が起きた場合に乗員を保護するための「受動的(あるいは消極的)安全性」だが、それ以前に、事故を回避するための「能動的(あるいは積極的)安全性」も重要である。そのためには、たとえば操縦性をニュートラルに近い弱アンダーステアに保つとともに、ステアリングへの応答性をよくすることが必要である。また一部のとくに高性能な車に四輪駆動(4WD)が増えつつあるのも、高出力を2輪だけに与えることによっておこる横滑りなどの危険性を回避する目的によるものである。 同様に、一部の高性能車に使用されているのがABS(anti-skid brake systemの略)である。これは、片側がぬれたり凍った道で高速から急ブレーキをかけると、そちら側の車輪がロック(回転が止まる)して滑走し、反対側だけが効くので横滑りをおこし、道を外れたり、対向車や後続車と衝突する危険性が高い。そこで、ブレーキをかけたときに片側の1輪または2輪がロックすると、電気的にそれを検知し、コンピュータで左右の油圧を調節し、まっすぐ安全に止めるものである。4WDとABSを組み合わせた車は、自動車の安全性に新境地を開くものである。 [Takashima Shizuo] 居住性・快適性・装備現代の自動車は居住性、快適性を高めるためのさまざまな装備をもっている。ヒーターはいうに及ばず、いまや過半の車がエアコンを備えており、とくにマイコンによりつねに一定室温を維持するオートエアコンも多い。また開放感の得られる開閉式のサンルーフも広く普及している。よりよい運転姿勢が得られるよう、シートやステアリングホイールは高さや角度が調節でき、シートの内部に一種の風船をつくりこみ、空気圧を調節して好みのシート形状を得られるようにしたものもある。 カーライフをより楽しくするための装備の充実も目覚ましい。いわゆるカーオーディオは高度に発達しており、CD(コンパクトディスク)プレーヤーも普及している。国産車にはCRT(ブラウン管)ディスプレーを計器板に備え、車のさまざまな情報を映し出せるようにしたものもある。人工衛星からの電波により自身の現在地、進行方向などを割り出し、CRTや液晶ディスプレー上の地図や音声で道案内するカーナビゲーション・システムcar navigation systemは、現在急速に普及しつつある。CB(市民バンド)無線や自動車電話は携帯電話にとってかわられつつあり、道路と自動車との間のコミュニケーションも現実化しつつある。 [Takashima Shizuo] 自動車の開発と生産新型車の開発まったくの新型車の場合も、継続生産車のモデルチェンジの場合も、開発はまず市場の分析から始まる。市場が現行生産車をどう評価しているか、競合他車ではどんなモデルがよく売れているか、外国での新傾向はなにか、などを的確に把握したうえで、新型車の構想をつくりあげる。ほとんどのメーカーで、取締役クラスの技術者で主査とよばれる総括責任者の下に、車体設計、エンジン設計、外装デザイン、内装デザイン、生産、販売、宣伝などのエキスパートによる開発チームが編成される。 各社はそれぞれ大規模な研究・開発機関をもち、つねに将来の自動車のための基礎研究を行っている。それは新素材から、現在のガソリンエンジンにかわる新原動機、エレクトロニクス、デザインから、将来の交通体系、人間生活、はては社会、経済、政治にまで及ぶ。開発の初期、構想づくりの段階から、そうした基礎研究の成果が取り入れられることも少なくない。構想が1本にまとまらない場合は、競合する複数案が同時に進行されることもある。 新型車の開発でもっとも重要なものの一つはボディーデザインである。1台の新型車が市場に受け入れられるか否かは、発表会場での第一印象に大きく左右されるからである。まずデザイナーが何十枚、何百枚ものラフ・スケッチを書き、そのなかから優れた案を選んで、入念なレンダリング(意想図)に仕上げる。従来はそれを5分の1のクレイモデル(粘土模型)にして検討、修正を加えたうえで現寸大のクレイモデルをつくった。これはモデラーとよばれる人々の仕事で、ガラス部分や塗装面には特殊なフィルムを張り、本物そっくりにつくりあげる。しかし現在ではCAD(キャド)(computer-aided designの略。コンピュータによる設計のこと)が発達して、ごく簡単な図面だけで入力し、ブラウン管画面上に立体像をつくって、全体のフォルムや細部の造形を修正してゆく。こうして最終決定した案を別のコンピュータにかけると、粘土模型を自動的に削り出す。もちろん最後はモデラーが仕上げる。このころになるとシーティングバックとよばれる枠組みだけの模型がつくられ、内部空間の検討が行われ、同時に室内のデザインや塗色の検討も始まる。このようにして最終案のクレイモデルまたはプラスチックモデルが完成すると、広いスタジオに現行生産車、競合他車などとともに展示し、上層部を交えて評価が行われる。そこで許可が出れば、試作車の製作となる。技術部門はすでに、旧型車に新しいエンジンやトランスミッション、サスペンションなどを組み込んで走行テストを重ねているが、今度は手づくりの新しいボディーにその成果を組み入れて試作車をつくりあげる。試作車は外観を隠し、自社のテストコースで走行テストを重ね、不ぐあいな点を修正、操縦性や乗り心地の味つけを行う。ときには秘密が漏れるのを恐れて、外国へ出かけることもある。耐久テストと並行して、安全性を試す衝突実験も実施する。 最終生産型が決定すると、プレス型の製作や、組立てラインの更改、関連会社への外注など生産の準備が行われる。パイロット・モデルを流して各工程の所要時間を計り、生産計画の基礎資料をつくり、同時に工員に作業を習熟させる。パイロット・モデルがラインオフすると、カタログ用の写真撮影やCFの録画が行われ、発表会用の広報資料や、セールスマニュアルが製作される。 [Takashima Shizuo] production1台の自動車の部品は2000~4000種類、数万点にも達する。その素材も鉄や、アルミニウム、マグネシウム、銅などの非鉄金属、ガラス、セラミックス、各種プラスチック、ビニル、皮革、木材、紙、ゴム、各種接着材、塗料、油脂、そのほかきわめて多種に上り、ほとんどすべての一次工業産品が含まれるといってよい。したがって自動車メーカーがそのすべてを自製することは不可能で、多くの協力工場、部品会社、専門メーカーなどの協力を得なければならない。日本の自動車メーカーは、それぞれ系列化した有力な協力工場をもち、それが日本車の生産性の高さと、品質のよさ、低価格の理由の一つになっている。 自動車メーカー自身が行うのは、プレス、溶接、塗装などによるボディーの製作、鋳造、鍛造、焼入れ、切削加工などによるエンジン・変速機・サスペンション・ステアリングの組立てなどで、いずれにも社外製の部品が大量に使われる。ボディー内外の艤装(ぎそう)もメーカー自身が行うが、計器板、シート、内装、ガラス、ホイールとタイヤ、そのほか細かい部品はすべて協力工場から完成品として搬入されたものを組み付けるだけである。自動車メーカーが、しばしばアッセンブリーassembly(組立て)メーカーとよばれるのはそのためである。この協力工場からの膨大な部品を、生産ラインにあわせてちょうどよいタイミングで搬入させ、自社工場内の部品倉庫を廃止するために開発されたのが看板方式で、いまや世界的に普及し、「カンバン・システム」は国際語になりつつある。具体的にいえば、塗装が終わったボディーに、その車が最終的にどんな仕様になるかを詳細に書き込んだ看板(実際には用紙だが)をはり付け、ラインに沿って準備された看板どおりの部品を組み付けてゆくのである。 看板方式は、限られた生産ラインで多種のモデルを組み立てるための方法でもある。今日では1社が最大十数ものブランドをもち、それぞれにセダン、ハードトップ、ハッチバック、ワゴンなどのボディーバリエーションがあり、艤装や装備の違いによるグレードが数種はある。エンジンと変速機の組合せも多く、メーカーの生産ラインで組み付ける、いわゆるファクトリーオプションのアクセサリーもきわめて豊富である。これらをすべて数えると、1車で数百種類、1社では数千から1万に近い種類になる。現代の自動車は形のうえでは大量生産であるが、実際にはオーダーメイドに近い選択の自由を与えているのである。生産技術上は大いなる矛盾であるが、その解決策の一つが看板方式である。さらに最近では生産ラインと部品供給をコンピュータで連動させて、1ラインで複数の車を生産する工場もできている。 1913年にフォード社で始まったコンベヤーシステムは高品質と低価格をもたらしたが、同時に労働者に非人間的な単純反復作業を強いると批判された。しかし第二次世界大戦後にフランスのルノーあたりが始めたトランスファーマシンによるエンジンの機械加工などから、しだいに機械が人間にとってかわるようになった。最近ではロボットの採用により、自動車工場からは大幅に人影が減っている。まだまだ内装など人手によらざるをえない工程も残されているが、近い将来には100%自動化された工場が出現するかもしれない。 [Takashima Shizuo] 各種義務自動車の運転・保有については、各種の法令によって多くの事柄が義務づけられている。 driver licence自動車を運転する場合には、道路交通法(昭和35年法律第105号)によって、公安委員会が交付する運転免許を取得しなければならない。免許には、第一種免許と、バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客を運送する目的で運転しようとする者に交付される第二種免許がある。免許を取得しようとする者は、公安委員会の自動車運転免許試験に合格しなければならない。ただし、第一種免許の試験を受ける場合には、練習を目的とした運転のための仮運転免許を受け、一定の条件を備えた指導者が自動車に同乗し、その指導の下に自動車を運転しなければならない。試験は、自動車の運転について必要な適性・技能・知識について行われる。公安委員会の指定する自動車教習所で技能検定に合格すれば、技能試験は免除される。免許を受けた者は、自動車を運転する際に免許証を携帯しなければならない。免許(小型特殊免許などを除く)を現に受けている者が外国で自動車を運転しようとする場合には、自己の住所地を管轄する公安委員会に必要な書類を提出すれば、国外運転免許証が交付される。有効期間は発給された日から起算して1年である。 [木谷直俊] Registration自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除く)を購入し使用する際には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって、運輸大臣が管理する自動車登録ファイルに登録しなければならない。登録制度の目的は、個々の自動車に対する所有権を公証することにある。一部の自動車が登録の対象から除外されるのは、動産としての価値が低いため公証による権利移動の明確化をかならずしも必要としないという考え方に基づいている。登録制度は次に述べる検査制度と密接な関係をもち、新規登録(登録を受けていない自動車の登録)と新規検査は同時に申請しなければならない。登録を済ませた自動車には自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)の取付け、封印、表示が義務づけられる。二輪の小型自動車と軽自動車についても車両番号の指定を受け(検査の際に軽自動車検査協会が指定する)、車両番号標を表示しなければならない。 [木谷直俊] 検査(車検)自動車はその構造、装置、性能などが保安基準に適合しなければ使用してはならず、自動車(二輪の自動車など検査対象外軽自動車、小型特殊自動車を除く)は、新規登録の際に、新規検査を受けなければならない。保安基準に適合した自動車には、自動車検査証と検査標章(いわゆるステッカー)が交付される。運行中は、自動車検査証を自動車に備え付け、検査標章を自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼(は)り付けなければならない。その後、1年ないし2年ごとに継続検査を受けなければならない。ただし、自家用軽乗用車および自家用乗用自動車(乗車定員10人以下)は初回は3年後である。以降は2年ごととなっている。また、自家用貨物自動車(車両総重量8トン未満)については、初回は2年後、以降は1年ごとである。事業用自動車は1年ごとである。自動車の検査は運輸省地方運輸局陸運支局が行い、軽自動車については軽自動車検査協会が実施する。検査を受ける義務者は使用者である。通常の場合、自動車の所有者と使用者は同一人のケースが多いが、所有権留保付きの割賦販売の場合、所有者は販売業者であるのに対して、使用者は実際のユーザーであるなど、所有者と使用者が別人である場合も少なくない。 なお、車検の方法には、定期点検整備と検査をディーラーや整備事業者に任せる「整備車検」、定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」、検査を業者に代行してもらう「車検代行」などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多いとされている。厳密には定期点検整備と検査は別であり、現在では、車検を通した後に整備を行うこともある(前検査・後整備)。 [木谷直俊] Maintenance自動車の使用者は、次に示す(1)日常点検整備および(2)定期点検整備が義務づけられている。(1)自動車使用者は、自動車の走行距離、運行などの状態から判断した適切な時期(自家用乗用自動車および軽貨物自動車等以外の自動車にあっては1日1回運行前)に、自動車点検基準に従って目視などにより当該自動車を点検整備しなくてはならない(道路運送車両法47条の2)。(2)事業用自動車および自家用大型自動車等(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量8トン以上の自動車およびレンタカーであって乗用自動車および軽自動車を除く自動車)は3か月ごとに、自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車ならびに乗用自動車および軽自動車等のレンタカー等は6か月ごとに、その他の自動車については1年ごとに、自動車点検整備基準に従って当該自動車を点検・整備しなくてはならない(道路運送車両法48条)。 なお、1995年(平成7)7月から車齢が11年を超える自家用自動車について、自動車検査証の有効期間が1年から2年に延長された。また、自家用自動車の6か月点検の義務づけの廃止、「前整備・後検査」の義務づけの廃止、定期点検項目の簡素化が実施された。さらに、2007年(平成19)4月からは、自動車の安全確保・環境保全を前提に、ユーザーの負担軽減の観点から二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間を初回2年から初回3年に延長するとともに、二輪自動車の6か月点検の廃止が行われた。 [木谷直俊] storage自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型特殊自動車を除く)の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号、通称車庫法)によって、自動車の保管場所を確保しなければならず、道路を自動車の保管場所として使用することはできない。そのため、自動車を保有する者は、新規登録、変更登録(使用車の変更など)、移転登録(名義変更)に際して、保管場所の確保を証する書面(車庫証明)を作成するための申請をしなければならない。証明書の作成は、保管場所を管轄する警察署長が行う。警察署長は、申請を受理したときは、当該自動車の保有者に対して、当該自動車の付置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。保管場所標章の交付を受けた者は、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。軽自動車については新規の運用の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用地域)、保管場所の位置、その他政令で定める事項を届出しなければならない。ただし地域によってはその必要はない。 運送事業用自動車の車庫証明作成のための申請については道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法律に基づく命令に定めるところによる。 自動車を道路上の同一場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車した場合などには罰金に処せられる。 [木谷直俊] insurance自動車または原動機付自転車の保有者は、自動車損害賠償保障法(自賠法。昭和30年法律第97号)によって、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、責任保険)に加入しなければならない。これにより、人身事故を起こした場合、相手に対して最高3000万円までの損害賠償金が支払われる。この保険は、損害保険会社およびその代理店が取り扱う。自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行してはならない。農業協同組合、消費生活協同組合、事業協同組合で扱っている自動車損害賠償責任共済(責任共済)の内容、保険金などは、責任保険と同様である。以上の二つを通常、強制保険というのに対して、賠償額がきわめて高額化した現在、任意自動車保険への加入が一般的になっている。これには、一般自動車保険、対人賠償事故の際に損害保険会社の示談交渉サービスが得られる自家用自動車保険(ただし、保険に加入できる車種が限定されている)、運転免許証はもっているが、自動車は保有していない人が、他人から借用した自動車を運転中に起こした事故を担保するための自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)などがある。なお、強制保険に入っていない場合や、次に述べる自動車重量税の納付がない場合などには、新規検査が受けられない。そのほか、ひき逃げや自賠責無保険車による事故で、自賠責保険の補償が受けられない被害者は、自賠法に基づく国の保障事業により、自賠責保険と同様の保険が得られる。なお、最近は高齢者事故が多く、そのため国の自賠責会計が赤字となり、保険料率が引き上げられた。 [木谷直俊] tax自動車には自動車を取得した段階、保有段階、走行段階で各種の税金が課せられる。全体で消費税を除くと8種類のものがある。これらの税収は国および地方公共団体の一般財源にあてられている。 取得段階では自動車取得税、消費税が課せられる。自動車取得税は、新車、中古車に限らず購入したときの取得価格を基準として課税される。自家用車であれば取得価格の5%(営業用および軽自動車は3%)である。取得価格が50万円以下のものについては免除される。なお、2012年(平成24)4月から2015年3月までの間、別途、エコカーに対する自動車取得税の軽減措置が講じられている。 保有段階では自動車重量税、自動車税、軽自動車税が課税される。自動車重量税は、車検または届出のときに車の総重量に応じて課税される。税率は車種や車検の期間により異なる。かりに車検が3年間(新車)とすると、1.5トンの自家用車なら重量0.5トンまたはその端数ごとに1万2300円となっているので、その3倍の3万6900円となり、自家用軽自動車なら一律9900円である。なお、一定の環境対応車については税の減免措置がある。自動車重量税については車検証の交付または車両番号の指定を受けるときまでに、税額相当額の自動車重量税印紙を納付書に貼り付けて、運輸支局または軽自動車検査協会に提出することにより納税する。自動車税は毎年4月1日現在の持ち主に対して定額で課税される。税額は総排気量に応じて異なる。自家用乗用車であれば、たとえば、排気量が1リットル以下で2万9500円、1リットル超から1.5リットル以下で3万4500円、1.5リットル超から2リットル以下で3万9500円となっている。原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対する税金としての軽自動車税も毎年4月1日現在の持ち主に対して定額で課税される。軽自動車(自家用)は、乗用車で7200円、トラックで4000円である。二輪車は、たとえば50cc以下で1000円、51ccから90ccで1200円となっている。 走行段階では揮発油税、地方揮発油税(かつての地方道路税であるが、2009年度の道路特定財源制度廃止に伴い名称変更)、軽油引取税、石油ガス税、消費税がある。揮発油税、地方揮発油税は、ガソリンに課税されるもので、燃料価格に含まれ消費量に応じて負担する。揮発油税はリットル当り48.6円、地方揮発油税はリットル当り5.2円、合計で53.8円である。ディーゼルエンジンを搭載した自動車に対する税金としての軽油引取税も燃料価格に含まれ消費量に応じて負担する。軽油に課税され、リットル当り32.1円である。石油ガス税も同じく燃料の価格に含まれる。LPG(タクシーなどが利用している)に課税され、キログラム当り17.5円である。さらに消費税が燃料の購入価格に課税される。最後に、自動車関係税には多種多様な税が存在するだけでなく、ユーザーの負担額も大きいことから、こうした税金体系の根本的な見直しが必要であるといわれている。 [木谷直俊] 『日刊自動車新聞社編・刊『自動車産業ハンドブック 2001年版』(2000)』 ▽ 『大佐肇・齋藤淑人編『Q&Aくらしの税金知識』(2012・新日本法規出版)』 ▽ 『日本自動車工業会編・刊『自動車ガイドブック』各年版』 ▽ 『国土交通省自動車局監修『注解自動車六法』各年版(第一法規出版)』 ▽ 『国土交通省編『国土交通白書』各年版(ぎょうせい。平成12年度版までは運輸省編『運輸白書』)』 [参照項目] | || | | | | |||||||||| ||||||||||| |||||||||||||||| ||| |||©Shogakukan "> 乗用車の車体型式と各国における呼び名 ©Shogakukan "> エンジンの点火・冷却・潤滑系統 ©Shogakukan "> シリンダーのおもな配列型式 ©Shogakukan "> 自動車の公害対策 ©Shogakukan "> 後輪駆動と前輪駆動 ©Shogakukan "> ダイヤフラム型クラッチの作動原理 ©Shogakukan "> トランスミッションの作動原理 ©Shogakukan "> シンクロメッシュの作動原理 ©Shogakukan "> サスペンションのおもな方式 ©Shogakukan "> ステアリングの構造 ©Shogakukan "> ホイールアライメント(車輪整列) ©Shogakukan "> ブレーキ装置の構成 ©Shogakukan "> ブレーキの構造 ©Shogakukan "> 自動車の空調システム Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
|
原動機を内蔵して車輪により陸上を自力で走行し、人や物を運び、あるいは各種の作業を行う機械の総称。英語でmotorcar、アメリカ英語でautomobile、フランス語でautomobile、ドイツ語でKraftwagenといい、中国語では汽車と記す。 自動車が開発されたのは19世紀後半の1880年代中ごろで、20世紀に入ってから、徐々に一般市民へ普及が始まった。もっとも自動車の恩恵を受けたのはアメリカであった。1910年前後から急速に普及した自動車によって、個人単位の人と物流の速度が飛躍的に高まり、また移動距離が大幅に延びたことで、アメリカの国土は相対的に縮んだといわれている。 わずか100年そこそこのうちに、自動車は長足の進歩を遂げ、世界規模で自動車が普及、活躍したことから、20世紀は自動車がつくった世紀といっても過言ではない。 一方、自動車が広く普及したことによって、大気汚染などの公害、過密による交通渋滞、交通事故、地域紛争による石油危機、石油枯渇の危機などの問題が生じ、それらの解消のための努力が行われている。とりわけ20世紀末から、自動車が地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の最大の発生源として糾弾されるようになり、この解決が急がれている。 自動車産業は、国家という見地にたてば、経済の根幹となるもっとも重要な産業であり、同時に重要な輸出産業でもある。その生産は広範な一次工業産品があって初めて成り立つので、自動車産業の振興は他のすべての工業にとって大きな刺激となる。近年では、省資源化、安全性の向上を目的とした電子制御技術が自動車に欠かせないものとなり、さらに自動車産業の裾野(すその)は広がりをみせている。 20世紀後半まで、自動車生産は一握りの先進工業国の企業によってほぼ独占されていた。しかし、開発途上国における旺盛な自動車需要に背を押されるように、外国企業による現地生産や技術提携を経て、開発途上国の企業自身による独自開発と生産が始まっている。こうした新興工業国の自動車産業は急速に技術力を向上させており、その高い品質と安価な労働力による低価格を武器に、ヨーロッパや日本の自動車産業の脅威になりつつある。また輸出入に伴う為替(かわせ)問題や、需要国への工場移転によって国内産業の空洞化が生じるなど、世界的な自動車産業地図は塗り替えられつつある。 また、自動車は耐久消費財の一つで、宣伝で売る商品であり、流行に左右される度合いの強い商品でもある。反面、自動車は人間のもっとも身近にあって行動、生活をともにするものでもある。その結果、自動車はペットのように、一種の感情移入の対象になったり、趣味の対象となったりすることも少なくない。 交通の手段としてみた場合の自動車は、時と目的地と経路を選ばず、いつでも、どこへでも、好きなルートを通って行けるという自由さと、戸口から戸口までの輸送の利便性が最大の特徴といえる。 本項では、自動車の発達史と工学的な面を中心に記述する。産業面、交通政策面については、「自動車工業」「自動車交通」の項目を参照されたい。 [高島鎮雄・伊東和彦] 自動車の定義と種類定義日本では道路交通法第1章第2条9項で、自動車を「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車以外のものをいう」と定義している。同じく道路運送車両法第1章第2条2項では、「この法律で『自動車』とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引(けんいん)して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう」としている。すなわち、日本の法律では原付以外の二輪車や、トレーラー、クローラー(無限軌道)をもつ車両も自動車となる。また「車輪で走るもの」とは規定していないので、もし小型の路面用ホバークラフトが実現すれば、道路上を他の交通機関に伍(ご)して走る場合は自動車とされることになる。世界的にみて、空気入りゴムタイヤ(まれに空気を入れないソリッドタイヤのこともある)をつけた車輪で重量を支え、内蔵の原動機でその車輪を回し、路面との摩擦で走行するものを自動車としている。 [高島鎮雄] 種類構造、ハードウェアによる分類と、使用目的、ソフトウェアによる分類がある。構造上の分類については後述する。使用目的上も、ここでは少人数の人を輸送する乗用車の分類に限って記述する。各種の作業用自動車、モーターサイクル(「オートバイ」)、「トラック」「バス」「レーシングカー」などは、それぞれの項目を参照されたい。 ひと口に乗用車といっても、一般大衆が足として求める経済性重視の小型実用車から、乗り心地最優先の大型高級車、レーシングカーなみの高性能を追求した好事家(こうずか)向きのスポーツカーまで、その性格は千差万別である。最近の著しい傾向として、それぞれの性格が大幅に重なり合い、境界がはっきりしなくなっている。かつては車名でおおよその性格がわかったが、今日では小型大衆車でさえ一つの車名のもとに、経済性優先のモデルからDOHCエンジンやターボを備えてツーリングカー・レースやラリーに活躍するものまでが含まれている。反面スポーツカーといえば、一昔前まではオープン2座と決まっていたが、第二次世界大戦後しだいに居住性が重視され、GT(ジーティー)の名のもとにクーペ型をとるものが多くなった。GTはイタリア語のグラン・ツリスモgran turismoの略で、長距離旅行に適した車という意味である。この傾向に拍車をかけたのはアメリカの安全規準で、オープン車は最近ではふたたび復活しつつあるが、一時期完全に姿を消していた。さらにGTクーペでは2人分の補助席を設けた2(ツー)プラス2(ツー)座や完全な4座とするものも多く、実用車のクーペ型との境界線は事実上なくなっている。 実用車のクーペ型の一典型がスペシャルティーカーで、基本的には実用車のシャシー(車台)をもつが、ボディーは低く、鼻は長く、後部は短く、スポーツカー風なプロポーションをもつ。この種の車はエンジンを強化し、足回りを固めればもはやスポーツカーと変わりはない。1964年アメリカのフォード・ムスタングが開発したジャンルで、日本ではセリカ、ソアラ、シルビア、スタリオン、ピアッツァ、アルシオーネなどがその例である。 同じような境界線の不確かさは、セダンとステーション・ワゴンの間にもある。一昔前までセダンといえば後方にトランクの突き出た3(スリー)ボックス型が主流を占めていたが、今日では小型大衆車を中心に、ワゴン型でテールゲート(後部扉)をもった2(ツー)ボックス型をとるものが多くなっている。これは大きさの限られた小型車に多用途性を追求した結果で、駆動系統が前方に集まった前輪駆動によるところが大である。 1990年代中ごろからは、アメリカのミニバン・ブームに端を発して、日本やヨーロッパ諸国でもSUV(Sports Utility Vehicle)が大流行し、前述のスペシャルティーカーに取って代わった。これはやや大柄な2ボックスないしは1(ワン)ボックスカーで、基本的に多人数の乗れる多目的乗用車だが、レジャー用としてスポーティーな使い方もできるものである。日本では1994年に発売された本田技研工業のオデッセイが大成功を収め、同社の国内販売を大幅に改善した結果、各社が競って追従しており、ファミリーカーとしてセダンに迫る勢いとなった。 次に大きさによる分類だが、小は、フランス、イタリア、日本にみられる50cc、1人乗りの三輪ないしは四輪車から、大は、全長6.3メートル、重量3.2トン、排気量7000cc、8人乗りの旧ソ連の高級車ジルまで、ほとんど一分のすきもなく分布している。各国ごとの乗用車の大きさは、国情(経済力、国民所得、その他)や国民性によって違ってくる。ひと口にいってヨーロッパ諸国や日本は小型車中心で、アメリカ車は格段に大型車志向であった。しかし二度にわたる石油危機の結果、厳しい企業平均燃費規制(CAFE。1985年以後は11.6キロ/リットル、違反すると罰金)が敷かれ、現在アメリカ車は急速に縮小し、欧州車や日本車に近づきつつある。 日本はヨーロッパ型とはいっても、ヨーロッパでも国ごとにかなりの差がある。イタリアでは1500cc以下が77.1%を、フランスでも70.1%を占め、イギリスでも1600cc以下が87.8%を占める。これに対しドイツでは1500cc以下はわずか30%で、1501~2000cc級が過半を占める。日本は1500cc以下が51.8%で、明らかにイタリア、フランス、イギリスよりは大型車志向で、むしろドイツに近いといえる。 日本における法規上の分類のうち道路運送車両法による分類は検査、整備、登録、統計、強制保険、税制などに関係し、道路交通法による分類は運転、免許、交通取締りなどに適用される。 [高島鎮雄] 乗用車の車体型式(1)セダン もっとも一般的な箱型車で、2(ツー)ドアと4(フォー)ドアとがある。エンジンの入るボンネット部分、客室部分、荷物を入れる部分の三つの箱からなる3(スリー)ボックス型が基本だが、最近はステーション・ワゴン型で、後部にテールゲートをもつ2(ツー)ボックスのセダンも少なくない。この場合3(スリー)ドア・セダン、5(ファイブ)ドア・セダンとか、ハッチバック・セダンとよぶこともある。語源は中世フランスの貴族の乗り物セダン・チェア(屋根付きの籠(かご)または輿(こし))に由来し、地名のセダンから出ていると思われる。セダンという呼び方はアメリカ式で、イギリスではサルーン(サロンの古語)、フランスではベルリン、イタリアではベルリーナ(ともにベルリン型馬車から出ている)とよぶ。ドイツではリムジーネという。 (2)コンバーチブル もともと「変換しうる」という形容詞で、コンバーチブル・クーペまたはコンバーチブル・セダンというのが正しい。オープンだが幌(ほろ)を上げ、横の窓ガラスを閉めればクーペまたはセダンにかわるものをいう。これに対し、横に巻き上げ式の窓ガラスがなく簡単な幌しかもたないものはツアラー(イギリス)、ツーリングカー(アメリカ)、フェートン(アメリカ)などとよんで区別した。コンバーチブルもアメリカ式呼称で、イギリスでは屋根が下りるという意味でドロップヘッド・クーペまたはドロップヘッド・サルーンとよぶ。フランス、イタリア、ドイツのカブリオレは幌型馬車からきている。 (3)ハードトップ 語源は「固い屋根」の意味で、正しくはハードトップ・コンバーチブル・クーペ(ないしはセダン)という。コンバーチブルの幌(ソフトトップ)を金属化したもので、クーペやセダンより屋根を低く、薄く、軽快にし、かつ横の窓ガラスを前後とも下げると中央に柱がなく、オープンに近い開放感の得られる型式。フランス語のフォー・カブリオレ(偽のカブリオレ)という呼び方がその実体をよく表している。1948年にアメリカのゼネラル・モータース(GM)社が商品化し、一時大流行した。しかし安全論争が激しくなった結果、強度確保の必要から柱付きとするものが多くなり、ピラード(柱付き)ハードトップという奇妙な語も生まれた。その結果、今日でも純粋のハードトップがないではないが、多くはドア窓にサッシがなく、やや屋根が低く軽快なモデルをハードトップとよんでいる。なおスポーツカーなどに、脱着できるデタッチャブル・ハードトップを備えたものもある。 (4)ロードスター 2人乗りの軽快なオープン車で、かつてスポーツカーに多かった。悪天候に対する備えは最小限しかなく、簡単な幌を上げ、横にはセルロイドの窓を立てるようになっていた。最近のものは巻き上げ式の窓ガラスをもち、幌もしっかりとしており、コンバーチブル・クーペとよぶべきである。しっかりしたロールバーをもち、幌またはプラスチックの屋根、あるいは屋根と後ろの窓を外せるようにしたものは、一般にタルガ・トップという。ドイツのスポーツカー、ポルシェ911タルガが先鞭(せんべん)をつけたからである。イタリアでスパイダー(クモ)とよぶのは、低く地をはう姿がクモを思わせるところからきており、フランスでトルペードというのは、水雷艇のようにスマートだという意味である。 (5)クーペ 2人乗りの軽快な二輪箱型馬車から出た語で、低く小さな屋根をもつ箱型車でスポーツカーに多い。本来は2座だが、最近では2(ツー)プラス2(ツー)や4座のクーペも珍しくなく、2ドア・セダンや2ドア・ハードトップとの差はなくなってきている。なおファストバック・クーペというのは屋根とトランクの間にノッチ(段)がない流線型のクーペのことで、そこにテールゲートを設けるとハッチバック・クーペとなる。 (6)リムジン 大型の最高級車の典型的な型式で、客室と運転室とは開閉できるガラスで仕切られている。客室はとくに広く、必要に応じて2人分の補助席も引き出せる。国家元首の公式乗用車や、賓客の送迎、大会社の役員の乗用車などに使われ、走りながら会議もできる。 (7)ステーション・ワゴン 駅馬車(ステージ・コーチ)を起源とするのは俗説で、馬車時代に鉄道の駅へ人を送迎に行くときに使った、乗貨兼用の馬車を自動車に移したもの。セダンの屋根を後ろまで伸ばして広い荷物室を設け、後部にテールゲートを備える。3(スリー)ドアと5(ファイブ)ドアとがあり、座席が2列で4~6人乗りのものと、3列で6~9人乗りのものとがある。2、3列目のシートは折り畳んで荷物室として使えるようになっている。純粋に乗用のものと、輸送・作業のための業務用とがあり、後者は日本ではライトバンとよばれトラック登録となり、統計上もトラックに含まれる。ライトバンは定員と最大積載量が決められるが、乗用車登録のワゴンは定員とその手荷物だけで、積載量は決められていない。最近では、より室内空間の広い1(ワン)ボックスにも乗用車登録になるものがあり、レジャー用として人気がある。 イギリスでは荘園(しょうえん)で使う車という意味でエステート・カーとよび、フランスでは乗貨兼用型をブレーク(狩猟用の乗貨兼用馬車)、純乗用型を家族用という意味でファミリアールと呼び分けている。イタリアでもファミリアーレというが、ドイツではコンビという呼び方が一般的である。 (8)1ボックスカー(ワンぼっくすかー) 運転席と助手席がボディーのほぼ先端まで前進し、全体が一つの箱のような形になったもの。一昔前なら完全にライトバンとよばれた型式だが、今日では乗用車の一型式として認知されている。特にミニバンないしはSUVとして、またスポーツカーの一種としても用いられている。 [高島鎮雄] 自動車の歴史実用化への歩み人類がころから車輪を発明したのは6000年も前のこととされているが、それを馬や牛に引かせる時代は長く、つい数十年前まで続いた。中世ヨーロッパの神学者・哲学者のR・ベーコンは1250年に「いつの日か、馬あるいはその他の動物によらず、自身の力で走る車が可能になろう」と、自動車の出現を予言している。15、16世紀の芸術家・科学者のレオナルド・ダ・ビンチが描いたさまざまな新発明の意想図のなかにも、木をしなわせて力を蓄え、それを歯車で取り出して車輪を回して走る自走車がある。 1569年にはオランダのシモン・ステビンが2本マストの帆走車をつくり、28人を乗せて海岸の固い砂上を時速24キロメートルで走った。しかし陸上ではジグザグの帆走はできないので、普及には至らなかった。1648年にはドイツの時計職人ハンス・ハウチュがぜんまいで自走する1人乗りの車を試作、時速1.5キロメートルで走った。しかしぜんまいの能力に限界があって、実用にはならなかった。 イギリスの物理学者・数学者のニュートンは1680年に、ボイラーでつくった高圧蒸気を後方の細い管から噴射し、その推力で走る車両の模型実験に成功した。しかしこの史上初のジェット推進車は、高温・高圧のガスを噴射するので路上での使用には危険が大きすぎ、結局現物はつくられなかった。 純粋に機械力で走る車は、蒸気機関の発明によって初めて可能になった。最初に蒸気機関で車を走らせようとしたのは、ルイ15世軍の砲兵大尉で、ベルギー人のキュニョーであった。彼は砲車を牽引(けんいん)させる目的で蒸気車を設計、ブレザンという技術者により1769年に完成され、2年後、より大型の2号車をつくった。同車は長さ7.2メートル、幅2.3メートルという巨大な二輪荷車に前1輪を追加した三輪車で、前輪の前に50リットルの銅製のボイラーをもつ。そこでつくられた蒸気は前輪の左右に一つずつある垂直のシリンダーに交互に送られ、前輪を回転させた。まだクランクはなく、ピストンの上下動がラチェットで前輪を回すようになっていた。キュニョーの蒸気車はバンセンヌで実験され、4人を乗せて時速9.5キロメートルで走ったが、操向輪に重いボイラーやシリンダーが載っているため事実上操縦不能で、城壁に激突してしまった。 蒸気自動車の研究がもっとも盛んで実績があがったのは蒸気機関誕生の地、イギリスであった。1801年にはトレビシックがかなり実用的な蒸気自動車を完成、時速14キロメートルで走ったが、運転手の不注意で爆発事故を起こした。トレビシックは2年後、直径3.2メートルもある巨大な駆動用の後輪をもつ四輪車をつくる。高い馬車の車体の後部に1気筒の蒸気機関を備え、前に乗った操縦士と後ろの汽缶(きかん)士とで運転した。この車は交通を遮断したロンドン市中で「馬車より速い速度」で試走に成功した。 イギリスでは産業革命の結果、資材や製品の輸送の必要が生じ、マカダムの発明したタールを用いる簡易舗装のハイウェー網が全国に建設された。1831年にはその一つを用いて、スチーム・コーチ(蒸気馬車)による定期旅客輸送が始められた。ダンスSir Charles Danceが、ゴールズワージー・ガーニー製作の20人乗り六輪車3台により、グロスター―チェルトナム間の定期運行を開始したのである。4か月間に3000人の乗客を運んだというから、成功であった。同じ1831年、ハンコックWalter Hancockも10台のスチーム・コーチを建造し、10年間にわたってロンドン市中と近郊を結ぶ路線に定期運行させた。1840年代には、そうしたスチーム・コーチの平均時速は25キロメートルにもあがり、ハンコックのオートマトンのごときは32キロメートルにも達した。 1850年代に入ると、スチーム・コーチは急速に姿を消していった。一つには、同じ蒸気機関を用いて、より輸送効率の高い鉄道が発達したためである。しかし、最大の原因は、スチーム・コーチの普及で経営危機に陥った馬車業者や馬匹供給業者が議会に働きかけたためである。たとえばリバプール―プレスコット間のターンパイク(有料道路)では、四頭立ての馬車の通行料が4シリングであったのに、スチーム・コーチには道路を傷めるという理由で2ポンド8シリングと、12倍も課していた。1861年イギリス議会はレッド・フラッグ・アクト(赤旗法)を成立させ、1865年に全面的に施行した。正しくはロコモティブ・オン・ハイウェー・アクトという同法は、「いかなるロード・ロコモティブ(初期の蒸気自動車はこうよばれた)も、3人で運行し、うち1人は60メートル先を昼間は赤旗、夜間は赤ランプを持って走ること、速度は町中で時速3.2キロメートル以下、郊外では6.4キロメートル以下とする」というきわめて過酷なもので、1896年まで撤廃されなかった。 赤旗法でイギリスにおける発達が止まっている間にも、ヨーロッパ大陸やアメリカでは蒸気車はどんどん進歩していった。なかでもフランスのアメデー・ボレー(父)Amédée Bolléeが1873年につくった8人乗りの小型バス「ロベイザント」(忠実なるもの)は、操向に際して左右別々に首を振る独立懸架の前輪、二つのV形2気筒エンジンで別々に駆動する後輪などをもった進歩的なものであった。初めは巨大なコーチであった蒸気自動車も、しだいに小型化し、火を入れてもすぐ走れない、頻繁に水を補給しなければならない、といった欠点も、フラッシュ(瞬間)ボイラーやコンデンサー(復水器)などで解決されていった。その結果ガソリン自動車に関する特許のセルデン・パテントのあったアメリカでは、1930年代の中ごろまで蒸気自動車がつくられた。 19世紀の中ごろには電気自動車も発明され、一時普及の兆しをみせた。しかし蓄電池の容量が小さいので性能が低く、1回の充電当りの走行距離が短い、などのために、主流を占めるには至らなかった。ただ電気モーターの特性から変速機が不要で運転が容易なのと、音や臭(にお)いがしないので、主として上流階級の女性に愛用され、アメリカでは1920年代まで生産された。その後も排気を出せない屋内用などには使われている。 最近ではガソリン自動車やディーゼル自動車の普及に伴い、大気汚染や石油資源の枯渇などの面から、ふたたび電気自動車がクローズアップされ、世界の主要メーカーがその実用化に向けて研究中である。特に大気汚染に悩むアメリカのカリフォルニア州が、主要メーカーに2003年に同州で販売する車の10%をZEV(Zero Emission Vehicle、無公害車)にすることを義務づけた結果、電気自動車の研究は加速されることになった。現状ではこれまでの蓄電池の改良の段階にあるが、各社が開発に力を入れているのは燃料電池で、これは燃料の水素と大気中の酸素を反応させて、電気分解の逆の原理で電気を取り出すものである。独米のダイムラー・クライスラー社は、2002年には燃料電池を動力源とするバスを実用化すると発表した。なお太陽電池は、いまだ超軽量の競技車を走らせる段階にとどまっている。 [高島鎮雄] ガソリン自動車の発明ガソリンエンジンの発明により、自動車は初めて本格的な発達と普及の緒についた。 内燃機関の歴史は古い。オランダの科学者ホイヘンスは、気圧の差による原動機の可能性を示唆して蒸気機関の発明を助けたが、1680年には火薬を用いた内燃機関(大気圧機関)を提唱している。1858年イタリアのバルサンティEugenio BarsantiとマッテウッチFelice Matteucciが石炭ガスを燃料とする内燃機関を製作、2年後フランスのルノアールも原始的な点火装置をもったガスエンジンをつくった。そればかりかルノアールは1863年に液体燃料(ガソリン)で回る4ストローク・エンジンを木製の四輪車に積み、試走に成功している。イタリアのベルナルディEnrico Bernardiも1864年にガスエンジン、翌1865年にガソリンエンジンをつくった。オーストリアのマルクスSiegfried Markusもガソリンエンジンの開発を進めていたが、1864年と1875年の二度にわたって、それにより走る車を試作している。マルクスの2号車はいまもウィーンの科学博物館に収蔵され、100年目の1975年には時速8キロメートルで実際に走ってみせた。しかしマルクスの車は年代などに疑問点が少なくない。1884年にはフランスのドラマール・ドブットビルEdouard Delamare-Debouttevilleらがガソリン自動車試作に成功しており、フランスはそれを根拠に1984年に盛大に「フランス自動車百年祭」を祝ったが、これらの試みはいずれも発明者一代限りで終わって、そこから歴史が流れ出していない。 1862年フランスのボー・ド・ロシャBeau de Rochas(1815―1893)が4サイクル・エンジンの原理を発見、1876年ドイツのオットーがその原理による定置用ガスエンジンの製品化に成功した。そのオットーの工場の若い研究員の1人がダイムラーで、彼はのちに独立して研究所を開き、オットー時代からの友ウィルヘルム・マイバッハWilhelm Maybach(1846―1929)の助けを借りて新しいエンジンの開発に取り組み、1883年に小型・軽量の高速ガソリンエンジンを完成、特許を取得した。ダイムラーは、エンジンを可搬式にするために、当時はクリーニング以外には使い道のなかったガソリンを燃料に選び、広く浅い皿に入れたガソリンが大気の熱で蒸発してできるガスを集めて使う方法をとった。もっとも苦心したのは点火で、まだ電気火花を利用する考え方がなかったので、1本のプラチナの棒をシリンダー内にねじ込み、外からバーナーで熱して中でガスに点火するホットチューブ・イグニッションという方法を考案していた。ダイムラーとマイバッハは、1気筒250cc、0.4馬力のエンジンを木製の二輪車に取り付け、1885年に特許をとった。史上初の実用的なガソリン自動車は実はオートバイであった。このオートバイはダイムラーの長男パウルの操縦で、シュトゥットガルト近郊で少なくとも3キロメートルの試走に成功、最高時速12キロメートルを記録した。翌1886年ダイムラーは夫人の誕生祝いと称してつくらせた四輪馬車にハンドルをつけ、後席の床に穴をあけて1気筒460cc、1.1馬力のエンジンを取り付けて四輪自動車をつくった。 一方ベンツは独力でガソリンエンジンを製作、それを用いて1886年に三輪自動車を完成、特許を取得した。今日ダイムラーとベンツがガソリン自動車の父とよばれるのは、単に実用的なガソリン自動車を発明したからばかりでなく、小規模ながらその製造販売を企業化し、またエンジンや自動車の製造権を他社にも与え、その普及に努めたからである。ダイムラー(車名は1900年以後メルセデスと改める)とベンツはライバル会社として発展したのち1926年に合併、さらに1998年にはアメリカのクライスラー社と合併してダイムラー・クライスラーとなった。 [高島鎮雄] 生産の工業化ガソリン自動車を発明したのはドイツ人だが、その生産を工業化したのはフランス人であった。なかでもパナール・エ・ルバッソール社はダイムラー・エンジンの製造権を獲得、自ら自動車をつくるかたわら、プジョーなど他社にも供給した。同社の技術家ルバッソールEmile Levassorが1891年に設計した車は、それまで座席下の後部にあったエンジンを前方に移し、クラッチ、変速機と縦に直線に並べた。乗客とエンジンの位置関係が上下の積み重ねから、前後に水平に展開されたわけで、車は低く安定する方向へ一歩踏み出した。さらに、1900年から1901年にかけての冬、すでに死の床にあったダイムラーが、マイバッハの助けを借りて生み出した最初のメルセデス車は、車軸をよけてカーブした低い鋼製のフレーム、半楕円(だえん)板ばねの足回り、円ハンドル、蜂(はち)の巣状のラジエーターなどをもち、近代的な自動車の基本形を確立していた。 前後するが、ダイムラーの最初のオートバイからわずか9年後の1894年、フランスの新聞『プティ・ジュルナル』の主催で史上初のモータースポーツ・イベントが開かれている。パリ―ルーアン間126キロメートルで行われたもので、単なる速さばかりでなく、信頼性や簡便さも審査された。このイベントではド・ディオンConte de Dionの駆るド・ディオン・ブートン蒸気自動車が、6時間後、平均時速21キロメートルで1着で到着した。しかし同車は運転手のほかに汽缶士を必要としたために簡便さを欠くとして3等に落とされ、2、3位のガソリン車、パナール・エ・ルバッソールとプジョーに1等賞金が分け与えられた。ガソリン自動車の優位性が証明されたわけで、ド・ディオン・ブートンもまもなくガソリン車に転向した。 高価なくせに、いつ、どこで故障するかわからない初期の自動車は、いわば若い貴族や富豪のおもちゃであった。しかし、初め幌馬車で、ついで鉄道で西へ西へと開拓された広大な新興国アメリカでは、足が速く長距離用の乗り物を必要としていた。しかも貴族制度のないこの国では、自動車が初めから大衆化する素地があったといえる。たとえばオールズRamson Eli Olds(1864―1950)のオールズモビル・カーブド・ダッシュ車は、1901年に早くも425台を生産、史上初の量産車とされている。 それに輪をかけたのが1908年にH・フォードが送り出したT型フォードである。簡にして要を得た設計のために、女性や老人にも扱いやすく、壊れにくく、しかも比較的安価であったから、第1年目に1万台を売るヒットとなった。さらに殺到する注文にこたえるために、1913年にミシガン州ハイランド・パークに新工場を建設、そこで自動車産業初のコンベヤーラインによる大量生産を開始した。コンベヤーラインの横に部品を待たせておき、ライン上を流れてくるシャシーに次々と組み付けるので、生産性は飛躍的に向上した。この結果、最盛期の1925年には年産199万0950台と、200万の大台に迫った。1908年の発売時には850ドルであったT型フォードは、1925年の最廉価型ロードスターでは260ドルまで引き下げられ、大衆の間に浸透していった。 しかもT型フォードは、量産のゆえに高価な素材が使えたし、流れ作業のために加工も均一で、品質は何十倍も高価な高級車に匹敵した。それでもフォードは十分な利益をあげ、工員には当時の平均の2倍に相当する日給5ドルを与え、1914年には新規購入者に小切手で50ドルのリベートを支払うなど、思いきったことを行い、経営の魔術師といわれた。T型フォードはアメリカ以外でもイギリス、ドイツで生産され、日本やオーストラリアなど世界の各地で組み立てられた。1908年10月1日の発表から、次のA型に道を譲るために生産を終了した1927年5月26日までに実に1500万7033台に達し、最盛期には地球上を走る自動車100台のうち68台がT型フォードであった。 上流階級に独占されていたために、自動車の大衆への普及が遅れていたヨーロッパでも、第一次世界大戦後急速な大衆化が始まる。その原因はいくつかあるが、一つには、戦争で貴族階級が没落し、かわって中産階級が台頭してきた結果である。と同時に、大戦中航空機などの増産の必要から急速に規模を拡大された工場が、終戦と同時に自動車の大量生産に踏み切らざるをえなかったからである。たとえば、歯車会社として創業したフランスのシトロエン社は、大戦中砲弾の量産で急成長したが、戦争終結と同時に平和産業への転換を迫られ、シトロエンAndré-Gustave Citroën(1878―1935)は1919年、フォードに倣ってフランスのT型フォードともいうべきシトロエンA型の大量生産を開始する。ついでシトロエンは22年に855ccの小型大衆車「5CVトレフル」を出すが、それはドイツのオペル社によりコピーされ、「4/12PSラウプフロッシュ」として生産され、いずれも成功を収めた。この年には同じフランスで、プジョー社が667ccの「クァドリレット」をタイプ172へ発展させ、ルノー社が950ccのタイプKJを出し、ドーバーを渡ったイギリスでもオースチン社が747ccの「セブン」を出すなど、いずれも1000cc以下の小型大衆車が続出した。いわばヨーロッパにおける自動車大衆化元年であった。 1929年に全世界を襲った大経済恐慌は、自動車界にも大きな影響を与えずにはおかなかった。まず前近代的な貴族階級や大富豪が影を潜め、ますます市民階級が力を強めた。そのため、無数にあった超高級車は第二次世界大戦までの間にほとんど姿を消し、自動車は大量生産、大量販売、大量消費の商品、あるいは耐久消費財としての性格を強めていった。自動車は宣伝と流行で売る商品になり、資本主義社会の申し子とさえいわれるようになった。 1930年代の自動車の著しい流行は流線型であった。これは一つには、より速い飛行機のスマートさに近づきたいという願望であった。と同時に、シャシーの設計が進歩し、客室を前後車軸間のもっとも乗り心地のよい部分に収めたために、エンジンやラジエーターが前進し、もはや古典的な自動車の形態をとりにくくなった結果でもある。ヘッドライト、ラジエーター、ボンネット、フェンダー、ステップ、トランクとそれぞれ独立していた部分はしだいに一つの有機的な箱としてのボディーの中に吸収され、その分、室内空間は広くなっていった。構造的にみれば、ヨーロッパ大陸の進歩的な車やアメリカ車には、よりよい乗り心地を与える前輪独立懸架が普及し、1930年代末には小型車の一部に、より軽く、しかもより強度の高いモノコックボディーを採用するものも現れた。 [高島鎮雄] 日本における自動車の歴史日本に最初に渡来した自動車は、1899年(明治32)に、当時の皇太子(後の大正天皇)の御成婚を祝って、サンフランシスコの在留邦人会が献上した電気自動車である。このときは鉄道省から蒸気機関車の運転手を連れてきて試運転をさせたが、見物人のなかの老婆をよけ損ねて三宅(みやけ)坂か紀伊国(きのくに)坂から堀に飛び込んだという。 確かなのは1900年(明治33)に、横浜在住のアメリカ人貿易商トムソンが、アメリカ製の蒸気自動車ロコモビルを輸入したことである。このときトムソンといっしょに運転を習った宮崎峰太郎が、日本で自動車を運転した最初の日本人とされている。 [高島鎮雄] 国産化への道1902年(明治35)、銀座で自転車商を営んでいた吉田真太郎(しんたろう)が、内山駒之助(こまのすけ)の助けを借りて、乗用車を1台試作した。ただしエンジンは吉田がアメリカから持ち帰ったもので、純粋の国産車とはいえない。しかし、これに力を得た2人は、同年にオートモビル商会を設立、広島からの注文に応じて12人乗りのバスのシャシーを1台製作した。しかしそのシャシーには名古屋で重い市電の車体を架装したのでよく走らず、タイヤももたなかった。2人はぼつぼつと入ってくる輸入車の修理をしながら自動車技術の吸収と、経験の蓄積に努めた結果、1904年、東京自動車製作所を設立した。 しかし、彼らは純国産自動車製作者の第一号にはなれなかった。岡山の山羽虎夫(やまばとらお)が、1905年にまったく独力で蒸気バスをつくったからである。もっともそれは、走ることは走ったが実用からはほど遠く、またそれから日本の自動車技術が発展するということもなかった。したがって、真の意味での日本製ガソリン乗用車第一号をつくったのは、前述の東京自動車製作所で、1907年のことであった。これは、フランス留学からダラック車を持ち帰った日本のパイオニア・モータリストの一人、有栖川宮(ありすがわのみや)が、同社に車のめんどうをみさせていた縁で、強く勧めた結果であった。したがって吉田式乗用車の第1号は有栖川宮家に納入され、同宮の操縦で東京―日光間の試運転に成功した。水平対向2気筒1853cc、12馬力エンジンを備えた同車は、当時の舗装のない道をガタクリ、ガタクリと走ったところから、一運転手によってタクリー号と命名された。タクリー号は翌1908年までに10台がつくられ(うち1台はトラック)、日比谷平左衛門(ひびやへいざえもん)、中上川次郎吉(なかみがわじろきち)、有馬頼萬(よりつむ)、福沢駒吉、井上馨(かおる)など、当時の政財界の大立て物に愛用された。 1911年、橋本増次郎が東京に快進社自動車工場を設立、初めは輸入部品による組立てを行っていたが、1914年(大正3)に後援者田(でん)、青山、竹内のイニシャルを並べたダット(DAT、脱兎(だっと)に通じる)号の製造を開始した。 1919年には久保田鉄工(現、クボタ)社長の息子であった久保田篤次郎(とくじろう)が、大阪に実用自動車製造を設立、アメリカ人技術者ゴーハム(ゴルハム)William Gorhamを雇って、構造の簡単なゴルハム式三輪車(乗用と貨物用があった)をつくり始めた。途中から四輪車も加えてリラー号と改名、1923年までに合計約250台を製造した。快進社と実用自動車製造は、いずれも世界的な大経済恐慌の影響を受けて経営難に陥り、1926年に合併、ダット自動車製造となったが依然経営は困難であった。そこで戸畑鋳物の鮎川義介(あいかわよしすけ)が経営に乗り出し、同社の自動車部になる。同社は1931年に大阪で小型車を完成、ダットの息子という意味のダットソンと名づける。しかしソンは損に通じるというので太陽のサンに改め、ここにダットサンが生まれた。1933年(昭和8)同社は正式に日産自動車として発足、横浜の子安(こやす)に東洋一の大量産工場を建設した。同工場でのダットサンの生産は、最盛期の1937、1938年には月産800台にも達した。 前後するが、三菱(みつびし)造船神戸造船所は、1917年イタリアのフィアット・ゼーロに学んで三菱A型乗用車を完成した。同車は1923年までに約30台がつくられたが、今日の三菱自動車製品の遠い祖先といえる。 1918年、自動車の軍事上の重要性が認識された結果、陸軍が定めた一定の規格に合致するトラックに補助金を出す軍用自動車保護法が施行された。自動車工業の発達を促す日本で初めての法律である。それを受けて東京瓦斯(ガス)電気工業がTGE(Tokyo Gas Electricの略)トラックの生産を開始、石川島造船所もイギリスのウーズレー車の製造権を得て初め乗用車を国産化したが、まもなくトラックに転じ、のちバスもつくった。両社は1933年から提携、1937年に合併、第二次世界大戦後いすゞ自動車となった。 [高島鎮雄] 外国会社との競合1923年(大正12)、日本で自動車の有用性を大いに認識させるできごとが起こった。関東大震災である。東京市は、急遽(きゅうきょ)アメリカからT型フォードのトラック・シャシーを1000台輸入、簡単なバス・ボディーを載せて運行させ、人々の足を確保した。この大量発注に驚いたフォードは、極東地区への進出を企てて上海(シャンハイ)に計画していた組立て工場建設を横浜の子安に変更、1925年からT型のノックダウン生産を開始した。これに続いて大阪に日本ゼネラル・モータースも設立され、1927年(昭和2)からシボレーのノックダウン生産を開始した。1930年には別の会社によりクライスラー社のプリムス、ダッジのノックダウン生産も始められた。フォード、シボレーはタクシーに多用されたほか、トラックも生産、高品質の自動車を比較的安価に供給、結果として日本のモータリゼーションに大きく貢献した。 しかし日本の市場をフォード、シボレーに占領させておくわけにはいかない。日産自動車はアメリカのグラハム車の遊休生産施設をそっくり買い取って、1936年に大型乗用車とトラック、バスの生産を開始した。それと前後して、豊田(とよだ)自動織機の副社長豊田喜一郎(きいちろう)は、1935年に初の乗用車を試作し、同年トラックを製品化、1937年に愛知県挙母(ころも)(現、豊田(とよた)市)で大工場の建設に着手した。同工場は1938年に完成、翌1939年、豊田自動織機自動車部は独立して、トヨタ自動車工業(現、トヨタ自動車)となった。 [高島鎮雄] 戦後の復興第二次世界大戦後日本を占領した連合軍は日本の自動車産業の力を過大に評価し、自動車生産を厳しく制限、とくに乗用車は事実上禁止に等しかった。その生産制限は1949年(昭和24)に解かれたが、乗用車がつくられていなかった戦時中からの空白は大きく、1952年ごろから先進国のメーカーと技術提携し、外国車をノックダウン生産、しだいに国産化して技術の吸収に努めるメーカーが続出した。 日産自動車はイギリスのオースチン社と技術提携してA40をつくり、トラック・バスメーカーのいすゞ自動車は同じくイギリスのルーツ社と結んでヒルマン・ミンクスを国産化した。戦時中にいすゞの戦車工場から独立した大型トラック・バスメーカーの日野自動車工業(現、日野自動車)も小型乗用車への進出を企て、フランス、ルノー公団のルノー4CVを国産化した。財閥解体で旧三菱重工から生まれた東日本重工は、アメリカ、カイザー・フレーザー社のコンパクトカー、ヘンリーJを組み立て、同じく新三菱重工はウィリス・ジープの国産化に着手した。一方トヨタ自動車工業や、旧中島飛行機と立川飛行機から派生した富士精密工業(後のプリンス自動車工業。現、日産自動車)などは、外国に学びつつ独力で技術の蓄積に努めた。この時代、東洋工業(現、マツダ)とダイハツ工業はまだ三輪トラックの専門メーカーであったし、鈴木自動車工業(現、スズキ)はオートバイのほかに軽自動車への進出を企てていたが、本田技研工業はまだ二輪車専業メーカーであった。同様に、旧中島飛行機の富士重工業もバス・ボディーはつくっていたが、軽自動車スバルで四輪車に進出するのはまだ先のことである。 国の政策としても国内の自動車産業を保護育成する方針がとられ、外貨不足もあって1953年から1958年までは、報道用と観光用を除いては、乗用車の輸入は事実上禁止された。こうした経済的には苦しいが意欲的な学習の時期を経て、1955年にダットサン110とトヨペット・クラウン、同マスターが発表され、ようやく技術的に欧米の水準に一歩近づき、日本の乗用車は大量生産による大衆化の時代を迎えるのである。 [高島鎮雄] 大量生産と大衆化とくに1960年代に入ってからは所得倍増政策などに助けられ、四輪車生産は年間40~80%増という急成長を続け、日本の工業立国の基幹産業としての役目を果たした。日本の四輪車生産は1962年(昭和37)にはイタリア、1964年にフランス、1966年にイギリス、1967年にドイツと、ヨーロッパの先進国を次々に抜き、1980年には、長年トップの座にあったアメリカを抜いて、ついに世界一の座につき、以来1993年(平成5)までその地位を維持した。 これに対して、諸外国から市場開放と資本自由化の要求が高まり、1959年には割当て制度で輸入が再開され、さらに1961年にはトラック、バスの輸入自由化、1964年には完成乗用車の輸入自由化が実現された。1971年にはエンジンの輸入が自由化され、1978年には完成車の輸入関税をゼロにする思いきった施策がとられた。一方外国からの資本参加は、1967年に第一次自由化が行われ、1973年には完全に自由化された。 日本の自動車生産の驚異的な伸びを支えたのは、内需もさることながら、輸出であった。自動車輸出は1980年には生産の50%を超え、最大54%にも達しているが、そのうちの40%前後、すなわち全生産のほぼ20%はアメリカへの輸出である。その結果、自動車の輸出は日米間の著しい貿易不均衡の最大の原因とされている。1980年には日本製乗用車がアメリカの全乗用車販売の20%を超えたところから、主としてアメリカ側の要求により、日本は乗用車の対米輸出の自主規制を行うことになった。自主規制は当初1981~1983年の3年間に限り、年間168万台としてスタートしたが、1984年もアメリカ側の要求で185万台に枠を拡大して続行された。アメリカ側は1985年からは自主規制の要求を引っ込めたが、その後は日本政府の判断で230万台の自主規制が続行された。このほかイタリア、フランスは日本車に輸入制限を課し、イギリスとの間には自主規制の取り決めがなされた。しかし外貨に対する円高傾向が定着した結果、輸出は困難になり、各国内メーカーはしだいに輸出から現地生産に切り替えた。本田技研工業は1979年にイギリスの国有BL社と技術提携してホンダ車を現地で生産したし、トヨタ自動車は1983年にアメリカGM社と共同出資でNUMMI社を設立、1985年からカリフォルニア州フリーモント工場でスプリンターのアメリカ版、シボレー・ノーバの生産を開始した。本田技研工業、日産自動車もアメリカで乗用車を生産しており、マツダ、三菱自動車、トヨタ自動車、富士重工、いすゞ自動車もアメリカでの現地生産を行っている(いすゞ自動車は2002年末にアメリカ現地生産撤退)。その結果、輸出の自主規制は無意味となり、2000年末の日米自動車協議が決裂、自主規制は自然消滅した。対ヨーロッパ諸国とも同じ傾向にある。 このような日本車の著しい海外進出は、その品質の向上を証明するもので、いまや日本車は高品質の象徴とさえなっている。とくに産業用ロボットを駆使した生産技術の高さでは、他国の追従を許さない。設計技術面でも、世界一厳しい排出ガス規制のために燃焼の研究が進み、性能と経済性の両立に成功している。また自動車へのエレクトロニクスの応用という面でも、最先端をいくといってよい。 このような日本の自動車産業の高い技術力は、欧米の主要メーカーにとってはぜひとも欲しいもので、技術提携、さらには資本提携の申入れが続いた。時あたかも日本ではバブルが崩壊し、技術力とは裏腹に経営力の弱さが曝露され、外資を受け入れる日本メーカーが続出した。まずマツダがフォードの資本を受け入れ、いすゞ自動車、スズキ、富士重工業がGMの、日産自動車がルノーの、三菱自動車工業がダイムラー・クライスラーの資本を受け入れるというように続いた。その結果、資本的に外資から完全に独立を維持しているのは本田技研工業とトヨタ自動車、トヨタの系列のダイハツ工業と日野自動車工業だけとなった。 [高島鎮雄] 自動車の構造
[高島鎮雄] エンジン自動車の原動機としては電気(蓄電池、燃料電池、太陽電池)、蒸気、原子力まで考えられるが、現状では内燃機関が圧倒的で、ごく一部に蓄電池式電気自動車がみられる程度である。最近ではガソリンエンジンと発電機、蓄電池、モーターを組み合わせ、これらをコンピュータで最適制御し、排ガス対策と省資源を両立させたいわゆるハイブリッド方式も実用化されており、増える傾向にある。しかしハイブリッド方式も、完全無公害の燃料電池が実用化されるまでのつなぎとみることができる。もっとも実現性が高い燃料電池として世界の主要メーカーが開発を急いでいるのは、水素と酸素を反応させて電気を取り出す方式で、排出されるのは水だけというクリーンなものである。もっとも一般的な内燃機関は作動原理によって2サイクル、4サイクル、ロータリーの3種があり、別に使用燃料によりガソリンエンジンとディーゼルエンジンに分けられる。今日、乗用車用のエンジンとして大勢を占めているのは4サイクルガソリンエンジンで、それに少数の4サイクルディーゼルエンジンが用いられている。1998年ころから急速に普及し始めたCNG燃料車は、ガソリンのかわりにCNG(compressed natural gas、圧縮天然ガス)を燃料とするもので、エンジンの作動原理、構造はガソリンエンジンに準ずる。 (1)4サイクルエンジン 通常2000cc程度までの小型車用では直列4気筒が標準的だが、最近の軽自動車や1000cc級の大衆車では、FF方式で左右前輪の間に横向きに収めやすい直列3気筒も珍しくない。同様に2000cc級以上では、コンパクトなV型6気筒が増える傾向がある。このほかV型8気筒、同12気筒、水平対向4気筒、同6気筒、同12気筒なども用いられている。同じ排気量なら気筒数の多いほうが一つずつのピストン、コンロッドなどの慣性質量が小さく、回転があがり、したがって出力も高くなるが、反面、構造は複雑に、コストは高く、手入れもめんどうになる。 (2)バルブ機構 4サイクルエンジンは、排気を終わってピストンが下降する際に吸気バルブを開いて吸気し、圧縮(上昇)、燃焼(下降)が終わってピストンが上昇する際に排気バルブを開いて排気しなければならない。この吸気バルブと排気バルブは、クランクシャフトの半分の速度で回るカムシャフト(偏心輪軸)で開閉するが、カムシャフトをシリンダーブロック横の比較的低い位置に置き、長いプッシュロッド(押し棒)とロッカーアーム(てこ)で作動させる方式を、一般にOHV(overhead valveの略)という。実用本位の車ではOHVで十分だが、回転をあげて出力を高めようとすると、プッシュロッドの慣性のため、バルブの作動が不確実になる。そこでカムシャフトをシリンダーヘッド上の高い位置において、直接的にバルブを作動させるようにしたのがOHC(overhead camshaft engineの略)である。OHCにも、1本のカムシャフトで吸・排気両方のバルブを作動させるSOHC(single OHC)と、カムシャフトを2本にしてそれぞれ吸気バルブと排気バルブを専門に作動させるDOHC(double OHC、ツインカムともいう)とがある。DOHCでは燃焼室形状をより燃焼効率のよい半球形にでき、吸・排気効果も高められる。OHV、SOHC、DOHCの順で高回転が可能になり、出力は高まるが、構造は複雑でコストもあがる。一昔前まではDOHCはレーシングカーや一部の高性能スポーツカーにしか使われなかったが、現在の国産車では大衆車クラスでも高性能モデルには使用している。さらに、通常は1個ずつの吸・排気バルブを、DOHCとの組合せでそれぞれ2個ずつとし、吸・排気効率を高めたものも珍しくない。 (3)ロータリーエンジン 4サイクルとともに、今日乗用車に用いられているのはロータリーエンジンである。1951年ごろドイツのバンケルFelix Wankel(1902―1988)が回転式ポンプにヒントを得てその原理を確立、1960年に旧西ドイツのNSU(エヌエスウー)社によって製品化された。NSUは2、3の車に使用したが、所期の成果があげられず、ほかにも世界中の多くのメーカーが採用を前提に研究したが、いずれもうまくいかなかった。そのなかで日本のマツダが独自の技術で実用化に成功、高性能モデルに使用、レーシングカーにも搭載して活躍させている。能率が高いので燃料消費が大きいのが弱点で、そのため石油危機時には先行きが危ぶまれたが、その後かなり改善されている。なおロータリーエンジンにもターボ付きやディーゼル、ターボディーゼルなどの可能性がある。 (4)キャブレーション もっとも一般的なのは霧吹きの原理を応用したキャブレター(気化器)だが、最近では、ガソリンをポンプで加圧し、ノズルから噴射するフューエルインジェクションfuel injection(燃料噴射)も広く使われている。燃料噴射ではガソリンの霧化がよいので、わずかながら出力、トルクが向上するが、それ以上に、ガソリンの噴射量がより微妙に調節できるので排出ガスがよりきれいになり、燃料消費率も向上する。噴射量をマイクロコンピュータでより精密に調節するEFI(EGIともいう。電子制御燃料噴射)も広く普及している。これは、アクセル開度、エンジン回転、車速、気温などをセンサーで感知し、コンピュータで計算して噴射量を刻々と修正するものである。同様にキャブレターを電子的にコントロールするEFC(電子制御気化器)もある。燃料噴射は、通常は吸気バルブ直前の吸気管に行うが、最近では燃焼室内へ直接噴射するDGI(direct gasoline injection)も普及し始めている。燃費がよくなり、排気がクリーンになる特徴がある。 点火系統にもトランジスタを用いて火花を強くしたものや、点火時期の調節にマイコンを用いたものもあり、外国には燃料噴射と点火系の電子制御を一元化したものもある。エンジンやその補機類にはさまざまな新素材の応用が進んでいるが、近い将来普及すると思われるものには、セラミックスとプラスチックがある。アメリカではすでにシリンダーブロックからピストン、コンロッドまでプラスチックで、ごく限られた一部にしか金属を使わないエンジンが試作され、過酷なレースの場で試されている。 (5)ディーゼルエンジン 爆発圧力が高いのでトルクが強く、また燃料消費が少ないうえに、燃料が低廉なので経済的である。反面、振動や騒音が大きいうえに、高回転が得られず、各部をじょうぶにつくらなければならないので重い。したがって長く大型トラック、バスに限られていたが、改良の結果、近年は乗用車にも用いられている。大型車用はシリンダー内に直接燃料を噴射する、より効率の高い直接噴射式が増えつつあるが、乗用車は騒音の小さい予燃焼室が依然中心である。ディーゼル乗用車はガソリン車に比べて出足が鈍く、最高速度も伸びないが、最近はターボの採用でガソリン車なみの性能をもつものも現れている。 日本では長く、産業振興の建前から、輸送の根幹をなす商用車への規制に消極的な傾向があった。その結果、ディーゼル車の排出するSPM(Suspended Particulate Matter、浮遊粒子状物質)やNOxにより、それらの濃度が環境基準を達成しない状況が続いた。石原慎太郎東京都政はこの状況を打開すべく、2000年に独自のディーゼル車の排出ガス規制を打ち出した。すでに使用中のディーゼル車に排ガスの後処理装置を取り付けるには多大の費用がかかるため、運輸業界は反対の立場を表明、自動車メーカーも消極的で、大きな論争が展開された。しかし規制が実施され、それが全国に波及することは必至である。これに対してメーカーはクリーンなディーゼルエンジンの開発を急ぐ一方、CNG(圧縮天然ガス)車の普及にも活路をみいだそうとしている。 (6)ターボチャージャーとスーパーチャージャー ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、近年普及の著しいのがターボチャージャーturbo chargerである。これは、通常そのまま大気中に捨てている排出ガスの圧力でタービンを回し、その力でポンプを働かせて、普通はエンジンが自然に吸い込む吸入気を積極的に押し込み、より高い爆発圧力を得るものである。エンジンにもよるが、出力は30~50%も向上する。いわば廃物利用の省エネルギー装置だが、現実には低速ではほとんど効果がないし、アクセルを踏んでも排気圧力が高まって効き始めるまでに時間的なずれがある、など弱点もある。そのためしだいに適用範囲が整理され、とくに高性能を売り物にする車だけに限られる傾向にある。 ターボにかわって、1980年代中ごろから注目され始めているのは、スーパーチャージャーsuper chargerである。これはポンプをエンジンで直接駆動するので、低速から効果を発揮し、いわゆるターボラグのような効きの遅れもない。もともと気圧の低い高空を高速で飛ぶ戦闘機用として発明されたものだが、1920年代初期から第二次世界大戦までは、レーシングカーや高性能スポーツカーに広く用いられた。戦後は有鉛高オクタン価ガソリンの普及などで使われなくなっていたが、無鉛ガソリン時代に入ってふたたびクローズアップされ始めたといえよう。 (7)出力とトルク エンジンの性能を表す方法には、出力(馬力ともいう。単位PSまたはkW)とトルク(回転力。単位kg・mまたはNt・m)の二つがある。出力は一定時間内に行うことのできる仕事の能率を表すから、出力の大きいほど速く走れるし、あるいは重い物を運べる。これに対しトルクは絶対的な回転力だから、トルクが強ければ出足がよく、あるいは登坂力に優れる。表記に際しては、最高出力、最大トルクともに、それを発生する回転数(単位、回転/分またはrpm)を併記する。出力は回転力に回転速度を掛け合わせた、仕事量を表すものだから、それを発生する回転数がわかれば、トルクの強いタイプか、回転数で出力を稼いだものか、そのエンジンの性質がわかる。一方トルクは絶対的な回転力だから、エンジンをつねに最大トルクを発生する回転に保てば、強い加速力と最良の燃費が得られる。高性能な自動車がタコメーター(エンジン回転計)を備えているのは、一つにはエンジンを回しすぎて壊さないためであるが、同時に、つねにエンジンを最大トルク発生回転域に保って、よりよい出足と、より少ない燃料消費を得るためである。 自動車のカタログなどにはよく、縦軸にトルク、横軸に回転数をとって、そのエンジンのトルク特性を表した線グラフが載っている。これが一般にトルクカーブとよばれるもので、レーシングカーのエンジンでは最大トルクは強いが、その前後では急速に落ち、険しい山の頂上のようになっており、しかも頂上は高回転側に寄っている。したがって、絶えず変速を繰り返して、その回転を保たなければ強い力が得られない。これに対し実用車のエンジンでは、最大トルクの数値こそ低いが、トルクカーブはなだらかな丘のような形をしており、しかも頂上は低回転側に寄っている。したがってどのギアに入っていても比較的強い力が得られ、そう頻繁に変速をしなくてもすむ。 (8)公害対策 自動車の排出ガス中には、燃料が未燃焼のままエンジンを通り抜けてしまう炭化水素(HC)、燃焼によって生じる一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)など、人体に有害で大気汚染の原因になる成分が含まれている。ロサンゼルスのスモッグに悩むアメリカでは、カリフォルニア州がいち早くその規制に乗り出し、まもなくアメリカ連邦規制に発展した。日本でも、東京・牛込柳(うしごめやなぎ)町の鉛公害がきっかけとなって大気汚染公害が大きな社会問題となり、1966年(昭和41)から自動車の排出ガス規制が始められた。1978年には10(テン)モードでHCが許容限界0.39グラム/キロメートル(平均規制値0.25)、COが2.7グラム/キロメートル(同2.1)、NOxが0.48グラム/キロメートル(同0.25)という、世界一厳しい乗用車の規制が実施された。これに対し日本のメーカーは、シリンダー内での燃焼を研究して有害成分の発生を抑えるとともに、効率のよい後処理装置を開発、排出ガス浄化技術ではいまや世界の先端をいくといってよい。さらに燃焼についての研究が進んだ結果、副次的に性能と経済性も向上したことは特筆される。2000年(平成12)10月(継続生産車と輸入車では2002年9月)には、乗用車の10/15モード平均規制値でCOが0.67グラム/キロメートル、HCが0.08グラム/キロメートル、NOxが0.08%とさらに強化され、現実に規制実施前に先取りしてこの値をクリアする車も出た。 浄化技術として現在一般的なのは、シリンダーとピストンのわずかなすきまを通り抜けたブローバイガス(生ガス)をふたたび吸入させて燃焼させる(HCの減少)、不活性ガスとしての自身の排気を少量吸入気に混ぜて燃焼温度と速度を下げる(NOxの発生の抑制)、吸入バルブのほかに小さいバルブをつけるなどして吸入気に渦流をおこし完全燃焼を促す(HC,COの減少)などである。また、シリンダー内に直接燃料を噴射するDGIも普及しつつある。それでも排出ガス中には少量の有害成分が残るので、排気管の途中に三元触媒をつけて一挙に取り除く。さらにガソリンと電気を併用する、いわゆるハイブリッド方式もすでに実用化されている。将来は燃料から直接電気エネルギーを取り出す燃料電池が実用化されるであろう。 またガソリンには、オクタン価を高めてノッキングを防ぐために、長く鉛化合物(四塩化鉛)が混入されてきたが、日本では1972年4月以降の生産車は無鉛ガソリンの適合車とされ、1975年2月から無鉛ガソリンの生産が開始され、今日では完全に無鉛化された(一部の中古車や輸入車のために有鉛ガソリンも供給されている)。 また騒音規制も実施されており、日本では定常走行排気騒音は1971年4月以降の新型車から乗用車で70ホン、トラック、バスは車両総重量3.5トン以下が74ホン、同3.5トン超、最高出力200馬力以下が78ホン、同3.5トン超、200馬力超が80ホン以下とされている。加速走行騒音は年々強化され、1985年で乗用車と車両総重量3.5トン以下のトラック、バスが78ホン、同3.5トン超が83ホン以下とされた。2000年時点の規制値は加速走行騒音で大型トラック83デシベル(A)、大型バス81デシベル(A)、中型車83デシベル(A)、小型車76デシベル(A)、乗用車76デシベル(A)、二輪車73デシベル(A)、原動機付自転車71デシベル(A)となっている。 なおヨーロッパでは1980年代に入ってからドイツのシュワルツワルト(黒い森)の酸性雨による被害が表面化し、1984年ごろから排出ガス規制へ向けての動きが出始めている。しかし1985年からドイツでようやく無鉛ガソリンの供給が始まった程度で、各国の足並みはそろっていない。 [高島鎮雄] 駆動系統(1)変速装置 エンジンは一定の回転を保たないと強い力を出さないのに対して、自動車は自由に速度を調整できなければならないし、また重いので走り始めるときにはとくに大きなトルクを要する。そこで必要なのが変速装置である。通常のマニュアルトランスミッションmanual transmission(手動変速機)では、エンジンを出たトルクは、2枚の回転する摩擦円盤を圧着したり引き離したりして回転を断続するクラッチへ伝えられる。三つのペダルのうち左端を左足で踏むとクラッチが切れ、離すとスプリングでつながる。 次に回転はギヤボックスgear box(歯車式変速機)へ伝えられる。一つの箱の中に3組から6組の歯車の組合せを収め、外からシフトレバーで適宜組合せを選んで使えるようにしたのがギヤボックスである。エンジンの強力な大型車では3段のものもあるが、小型車では4段が普通で、高性能車ではエンジンの力を余すところなく使うために5段から6段のものも珍しくない。通常、最上段は1対1の直結だが、加速を終わって一定速度に達したのちは、大きい歯車から小さい歯車へ伝えて増速することもできる。そうすると、同じ速度で走ってもエンジン回転はその分だけ低くてもよいので、燃料消費は減り、エンジンの摩耗も少なくなって長もちするようになる。この1対1を超えた増速ギヤをオーバードライブギヤover-drive gear(OD)といい、5段変速機のトップをODにするものが少なくない。 ギヤはクラッチを切った状態で入れ替えるが、慣性で回ったままなので、ガリガリいってなかなかうまくかみ合わない。とくに上の段から下の段にシフトダウンする際が初心者にはたいへんむずかしいので、かみ合わせようとする二つのギヤの速度を、摩擦クラッチであらかじめ同じにし、スムーズに入るようにしたのがシンクロメッシュsynchro-mesh(同期かみ合い式)変速機である。今日のほとんどの乗用車は、すべての前進段数にシンクロメッシュを備えている。 アクセルペダルの踏み方一つでスムーズに走り始め、自動的に最高速まで加速できるようにし、クラッチペダルをなくしたのが自動変速機(オートマチックトランスミッションautomatic transmission)である。その心臓部は流体トルクコンバーターで、三つの羽根車が密閉容器に入り、オイルが満たされている。 ただし、これだけではトルク、速度ともに変換率が小さいので、油圧で自動的に制御される2段から4段の機械式変速機を併用して補う。初期には2段しかなかったが、最近では4段にしてエンジンパワーをよりよく生かしたものが多い。自動変速機はトルクコンバーターのスリップなどのため、どうしても加速力、最高速ともに手動式変速機に劣り、燃料消費率も悪い。そこで最近では、加速を終わって駆動側、被駆動側の2枚の羽根車の回転が1対1に近づいたときに、トルクコンバーターを機械的に、あるいは電磁石で直結させ、スリップによる性能低下を防いだものが増えつつある。これがトルクコンバーターのロックアップ装置で、トップだけにロックアップの効くものもあるが、進んだものでは全段に効くようになっている。またギヤボックスの場合と同様、自動変速機でもトップをオーバードライブにしたものがある。 これまでの自動変速機では、歯車変速機の変速点を調速機などで機械的ないしは物理的に探し出してきたが、最近ではそれをマイコンで行う電子制御自動変速機(EAT)もある。各種のセンサーでアクセル開度、エンジン回転、車速、エンジン温度などを感知し、マイコンで演算させて最適変速点を精密に割り出すので、加速や燃費が改善される。さらに進んだものでは、変速パターンを性能重視型と経済性重視型の2モードにし、運転者が必要に応じて選択できるようにしたものもある。このような自動変速機技術では、日本は世界の先端をいくといってよい。 しかしながらトルクコンバーター式自動変速機はコストも高く、1000cc以下の小型大衆車には向いていない。そこで現在注目を集めているのが、オランダのバン・ドールネ・トランミッシー社が特許をもっていた無段階変速機(continuously variable transmission、略称CVT)である。遠心力で径の変わるプーリーとベルトによる効率の高い方式である。しかも構造が簡単で比較的安価に供給でき、1986年には特許が切れたので、以後、ゴムベルトを金属ベルトにかえたものが急速に普及した。また、CVTを改良したECVT(electro CVT)も実用化されている。 (2)4WD 現在の一般的な乗用車は、四つの車輪のうち後ろまたは前の2輪だけを駆動して走っている。しかし悪路を走行する機会の多い車では、4輪全部を駆動する四輪駆動(4WD)としたものも少なくない。さらに最近ではとくに強力な高性能車において、エンジン出力を確実に路面に伝え、しかも高速での安全を確保するために四輪駆動とするものが増えつつある。前者は舗装路上では二輪駆動に切り替えるので、パートタイム4WDとよぶのに対し、後者は常時なのでフルタイム4WDないしはパーマネント4WDという。フルタイム4WDでは左右車輪間だけではなく、前後車軸間にもデフを備えるのが普通である。 (3)デフ デフはディファレンシャルギヤdifferential gear(差動歯車装置)の略で、カーブを曲がる際には内側の車輪はゆっくりと、外側の車輪は速く回らないとスムーズに走れないので、自動的に速度差をつける歯車装置のことである。しかしパワーの強い車では加速中に1輪が空転してハンドルをとられたり、出足が鈍ったりすることがあるので、急激に左右輪の回転差が大きくなった際には、機械式または電磁式のクラッチで左右の差動を抑制するようにしたものがある。これをリミテッド・スリップ・デフlimited slip differential(LSD)とよぶ。 [高島鎮雄] シャシー(1)モノコックボディー 一昔前の自動車は、はしごのような形をしたフレームにエンジン、駆動系統、サスペンション、操向装置などを組み付け、それに、別工程でつくったボディーを載せる、という方法でつくられていた。しかしいまやほとんどすべての乗用車が、車体を軽くじょうぶな一つの箱としてつくりあげ、これにエンジンその他の諸装置を取り付ける。このような構造様式をモノコックボディーmonocock bodyという。ボディーの主材料は鋼板だが、最近では軽量化のために軽くてじょうぶな高張力鋼板や軽合金なども多用されるようになった。同時に2枚の極薄の鋼板の間にプラスチックを挟んだラミネート鋼板や、プラスチックの使用も進みつつある。これらの新素材は軽くじょうぶなだけでなく、加工しやすく、しかも自動車ボディーにとって最大の敵である錆(さび)の発生の少ないものが選ばれている。 (2)サスペンション エンジンとともに自動車の性能を大きく左右するのはサスペンションsuspension(懸架装置。車輪と車体を結ぶばね装置)で、不断に変化する路面の不整を吸収して自動車を適応させるとともに、操向輪をつねに接地させてかじ取りを確保し、駆動輪をつねに接地させて推進力を確保する。同時に乗客や荷物、自動車自身の車体を路面のショックから守る役目を負っている。一昔前の自動車では、車輪は1本の車軸の左右についていたが、いまは1輪ずつ別々のばね装置で支持された独立懸架が多い。これは、自動車の車体をクレーンで吊(つ)り上げたときに、ばねの下にぶら下がる部分の重量(ばね下重量)が小さいほど、車輪の路面への追従性がよくなり、乗り心地、操向性、駆動力ともに高まるからである。 サスペンションに使われるばねには金属、ゴム、気体などがあり、金属ばねにもコイル(弦(つる)巻き)、リーフ(板)、トーションバー(ねじり棒)などがあり、それぞれに特質があるので必要に応じて使い分けている。独立懸架の方式で現在一般的なのはウィッシュボーン式、ストラット式、セミトレーリング式などである。ばねには固有振動数があり、路面の凹凸の周期や車体の固有振動に合致すると走行中揺れが止まらなくなるばかりでなく、増大して操向性や乗り心地を低下させる。そこで各輪には油圧の力でばねのむだな動きを吸収するショックアブソーバーshock absorber(ダンパーdamperともいう)が備えられている。車体の重量やその位置配分などに応じて、ばねの硬軟、ショックアブソーバーの効き方の最良の組合せを探し出すのは、設計、開発陣にとってはきわめて困難な作業である。まして乗り心地は人によって好みが分かれる。そこで最近ではショックアブソーバーの効き方を3段ほどに調節可能とし、運転者が好みと路面情況に応じて任意に選べるようにした車も少なくない。さらに進んだものでは、路面情況に応じて電子的に自動調節するものさえある。すなわち、単位時間内の車体の揺れをカウントし、揺れが多くなるとダンパーの効きを強めるものや、走行前方の路面の不整を超音波などで事前に察知し、即座に調節してしまうもの、などがある。 (3)ステアリング 現在一般的なステアリングは、アッカーマン方式といい、操向する左右前輪の中心線をかならず後車軸の延長線上で交わらせることにより、スムーズにコーナーを回らせるものである。ステアリングホイール(ハンドル)の回転を前車輪の首振りに変えるステアリングギヤは、軽くスムーズなリサーキュレーティングボールrecirculating ball(ボール循環)式と、より直接的で確実なラック・ピニオンrack and pinion式である。前者は一般の車に、後者はよりスポーティーな車に使われるが、最近の傾向としては旧来少数派であったラック・ピニオン式が増えつつある。さらに最近では直進付近の歯車比を遅くして、高速走行時には安全なようにハンドルの効きを鈍くし、低速では歯車比を速くしたバリアブル・レシオvariable ratioのステアリングギヤも普及している。 大型車や小型でもFF車ではハンドルが重くなりがちなので、パワーステアリングで操舵(そうだ)力を補う。これは、エンジンで駆動するポンプで油圧をつくって蓄えておき、ハンドルを切った際に、その切り方に応じてバルブを開き、シリンダーで車輪を曲げる力を補うものである。これも最近では、車の速度やエンジンの回転に応じて、高速ではパワーの効き方を弱く(ハンドルを重く)、低速では強く(軽く)なるように、電子制御するものが現れている。さらに油圧のかわりに電気モーターで補力するものも珍しくない。 これまでの通常の四輪車では、FRとFF、RR各方式を問わず、前2輪のみで操向を行ってきた。しかし最近では、四輪操向(4WS)の車も実用化されている。むろん主たる操向輪は前輪だが、後輪にもその何分の1かの操向角を与えて、スムーズなコーナリングを可能にしようとするものである。4WSには前輪と後輪に同方向の舵角を与える同位相操向と、前後を逆にする逆位相操向とがある。前者は高速道路上での車線変更や駐車時に有利であり、後者は曲がりくねった山道などに向く。この位相はドライバーが意図的に選択できるが、同時に前後の操向角のバランスとともに電子制御も行われる。4WSの最大のねらいは操向時の車輪のスリップをなくすことで、より安全な車への要求にこたえるものである。 ブレーキは右足のペダルで操作するが、ペダルと各車輪のブレーキは油圧で結ばれ、パスカルの法則を利用してペダル踏力を軽くしてある。それでも足らない車は、エンジンの吸気によって生じる負圧を利用したサーボ機構servo-mechanism(倍力装置)を備える。サーボを備えたブレーキをパワーブレーキという。油圧の配管は前後、あるいは右前輪と左後輪、左前輪と右後輪というぐあいに、2系統に分け、一方が故障してももう一方で安全が保てるようにすることが義務づけられている。 [高島鎮雄] 安全性自動車は最大の安全性をもつよう設計され、実車による衝突実験で確認されたもののみが生産されている。車体は中央の客室部分が一段と強固に、前後の張り出し部分はやや柔構造になっており、衝突時にはその部分がショックを吸収しながらつぶれて客室を保護する。ドアの内部には側面衝突に備えてガードレールがつくり込まれている。燃料タンクは衝突時に燃料の漏れない構造のものが、もっとも安全な位置に備えられる。窓ガラスは安全ガラスが義務づけられているが、国産車はこれまで強化ガラスが大半を占めていた。しかし強化ガラスは鋭角に割れて乗員の目を傷つけたりするので、1986年型からは、2枚のガラスの間にビニルの薄膜を挟み込んだ、割れても飛散しない合わせガラスの使用が促進されている。 乗用車の室内では、ステアリングホイール(ハンドル)や計器板が衝撃吸収構造になっており、運転者席と助手席にはヘッドレスト(頭部後傾抑止装置)がついている。乗用車と小型トラック、軽トラックの車体側面には隣接する前向きの座席には3点式、その他の座席には2点式のシートベルトの装備が義務づけられている。1985年9月1日には道路交通法が改正され、高速道路、一般道路を問わず、運転者、前席同乗者は走行中シートベルトを着用することが義務づけられた。違反すると反則点1点を課せられる。 以上は、万が一衝突事故が起きた場合に乗員を保護するための「受動的(あるいは消極的)安全性」だが、それ以前に、事故を回避するための「能動的(あるいは積極的)安全性」も重要である。そのためには、たとえば操縦性をニュートラルに近い弱アンダーステアに保つとともに、ステアリングへの応答性をよくすることが必要である。また一部のとくに高性能な車に四輪駆動(4WD)が増えつつあるのも、高出力を2輪だけに与えることによっておこる横滑りなどの危険性を回避する目的によるものである。 同様に、一部の高性能車に使用されているのがABS(anti-skid brake systemの略)である。これは、片側がぬれたり凍った道で高速から急ブレーキをかけると、そちら側の車輪がロック(回転が止まる)して滑走し、反対側だけが効くので横滑りをおこし、道を外れたり、対向車や後続車と衝突する危険性が高い。そこで、ブレーキをかけたときに片側の1輪または2輪がロックすると、電気的にそれを検知し、コンピュータで左右の油圧を調節し、まっすぐ安全に止めるものである。4WDとABSを組み合わせた車は、自動車の安全性に新境地を開くものである。 [高島鎮雄] 居住性・快適性・装備現代の自動車は居住性、快適性を高めるためのさまざまな装備をもっている。ヒーターはいうに及ばず、いまや過半の車がエアコンを備えており、とくにマイコンによりつねに一定室温を維持するオートエアコンも多い。また開放感の得られる開閉式のサンルーフも広く普及している。よりよい運転姿勢が得られるよう、シートやステアリングホイールは高さや角度が調節でき、シートの内部に一種の風船をつくりこみ、空気圧を調節して好みのシート形状を得られるようにしたものもある。 カーライフをより楽しくするための装備の充実も目覚ましい。いわゆるカーオーディオは高度に発達しており、CD(コンパクトディスク)プレーヤーも普及している。国産車にはCRT(ブラウン管)ディスプレーを計器板に備え、車のさまざまな情報を映し出せるようにしたものもある。人工衛星からの電波により自身の現在地、進行方向などを割り出し、CRTや液晶ディスプレー上の地図や音声で道案内するカーナビゲーション・システムcar navigation systemは、現在急速に普及しつつある。CB(市民バンド)無線や自動車電話は携帯電話にとってかわられつつあり、道路と自動車との間のコミュニケーションも現実化しつつある。 [高島鎮雄] 自動車の開発と生産新型車の開発まったくの新型車の場合も、継続生産車のモデルチェンジの場合も、開発はまず市場の分析から始まる。市場が現行生産車をどう評価しているか、競合他車ではどんなモデルがよく売れているか、外国での新傾向はなにか、などを的確に把握したうえで、新型車の構想をつくりあげる。ほとんどのメーカーで、取締役クラスの技術者で主査とよばれる総括責任者の下に、車体設計、エンジン設計、外装デザイン、内装デザイン、生産、販売、宣伝などのエキスパートによる開発チームが編成される。 各社はそれぞれ大規模な研究・開発機関をもち、つねに将来の自動車のための基礎研究を行っている。それは新素材から、現在のガソリンエンジンにかわる新原動機、エレクトロニクス、デザインから、将来の交通体系、人間生活、はては社会、経済、政治にまで及ぶ。開発の初期、構想づくりの段階から、そうした基礎研究の成果が取り入れられることも少なくない。構想が1本にまとまらない場合は、競合する複数案が同時に進行されることもある。 新型車の開発でもっとも重要なものの一つはボディーデザインである。1台の新型車が市場に受け入れられるか否かは、発表会場での第一印象に大きく左右されるからである。まずデザイナーが何十枚、何百枚ものラフ・スケッチを書き、そのなかから優れた案を選んで、入念なレンダリング(意想図)に仕上げる。従来はそれを5分の1のクレイモデル(粘土模型)にして検討、修正を加えたうえで現寸大のクレイモデルをつくった。これはモデラーとよばれる人々の仕事で、ガラス部分や塗装面には特殊なフィルムを張り、本物そっくりにつくりあげる。しかし現在ではCAD(キャド)(computer-aided designの略。コンピュータによる設計のこと)が発達して、ごく簡単な図面だけで入力し、ブラウン管画面上に立体像をつくって、全体のフォルムや細部の造形を修正してゆく。こうして最終決定した案を別のコンピュータにかけると、粘土模型を自動的に削り出す。もちろん最後はモデラーが仕上げる。このころになるとシーティングバックとよばれる枠組みだけの模型がつくられ、内部空間の検討が行われ、同時に室内のデザインや塗色の検討も始まる。このようにして最終案のクレイモデルまたはプラスチックモデルが完成すると、広いスタジオに現行生産車、競合他車などとともに展示し、上層部を交えて評価が行われる。そこで許可が出れば、試作車の製作となる。技術部門はすでに、旧型車に新しいエンジンやトランスミッション、サスペンションなどを組み込んで走行テストを重ねているが、今度は手づくりの新しいボディーにその成果を組み入れて試作車をつくりあげる。試作車は外観を隠し、自社のテストコースで走行テストを重ね、不ぐあいな点を修正、操縦性や乗り心地の味つけを行う。ときには秘密が漏れるのを恐れて、外国へ出かけることもある。耐久テストと並行して、安全性を試す衝突実験も実施する。 最終生産型が決定すると、プレス型の製作や、組立てラインの更改、関連会社への外注など生産の準備が行われる。パイロット・モデルを流して各工程の所要時間を計り、生産計画の基礎資料をつくり、同時に工員に作業を習熟させる。パイロット・モデルがラインオフすると、カタログ用の写真撮影やCFの録画が行われ、発表会用の広報資料や、セールスマニュアルが製作される。 [高島鎮雄] 生産1台の自動車の部品は2000~4000種類、数万点にも達する。その素材も鉄や、アルミニウム、マグネシウム、銅などの非鉄金属、ガラス、セラミックス、各種プラスチック、ビニル、皮革、木材、紙、ゴム、各種接着材、塗料、油脂、そのほかきわめて多種に上り、ほとんどすべての一次工業産品が含まれるといってよい。したがって自動車メーカーがそのすべてを自製することは不可能で、多くの協力工場、部品会社、専門メーカーなどの協力を得なければならない。日本の自動車メーカーは、それぞれ系列化した有力な協力工場をもち、それが日本車の生産性の高さと、品質のよさ、低価格の理由の一つになっている。 自動車メーカー自身が行うのは、プレス、溶接、塗装などによるボディーの製作、鋳造、鍛造、焼入れ、切削加工などによるエンジン・変速機・サスペンション・ステアリングの組立てなどで、いずれにも社外製の部品が大量に使われる。ボディー内外の艤装(ぎそう)もメーカー自身が行うが、計器板、シート、内装、ガラス、ホイールとタイヤ、そのほか細かい部品はすべて協力工場から完成品として搬入されたものを組み付けるだけである。自動車メーカーが、しばしばアッセンブリーassembly(組立て)メーカーとよばれるのはそのためである。この協力工場からの膨大な部品を、生産ラインにあわせてちょうどよいタイミングで搬入させ、自社工場内の部品倉庫を廃止するために開発されたのが看板方式で、いまや世界的に普及し、「カンバン・システム」は国際語になりつつある。具体的にいえば、塗装が終わったボディーに、その車が最終的にどんな仕様になるかを詳細に書き込んだ看板(実際には用紙だが)をはり付け、ラインに沿って準備された看板どおりの部品を組み付けてゆくのである。 看板方式は、限られた生産ラインで多種のモデルを組み立てるための方法でもある。今日では1社が最大十数ものブランドをもち、それぞれにセダン、ハードトップ、ハッチバック、ワゴンなどのボディーバリエーションがあり、艤装や装備の違いによるグレードが数種はある。エンジンと変速機の組合せも多く、メーカーの生産ラインで組み付ける、いわゆるファクトリーオプションのアクセサリーもきわめて豊富である。これらをすべて数えると、1車で数百種類、1社では数千から1万に近い種類になる。現代の自動車は形のうえでは大量生産であるが、実際にはオーダーメイドに近い選択の自由を与えているのである。生産技術上は大いなる矛盾であるが、その解決策の一つが看板方式である。さらに最近では生産ラインと部品供給をコンピュータで連動させて、1ラインで複数の車を生産する工場もできている。 1913年にフォード社で始まったコンベヤーシステムは高品質と低価格をもたらしたが、同時に労働者に非人間的な単純反復作業を強いると批判された。しかし第二次世界大戦後にフランスのルノーあたりが始めたトランスファーマシンによるエンジンの機械加工などから、しだいに機械が人間にとってかわるようになった。最近ではロボットの採用により、自動車工場からは大幅に人影が減っている。まだまだ内装など人手によらざるをえない工程も残されているが、近い将来には100%自動化された工場が出現するかもしれない。 [高島鎮雄] 各種義務自動車の運転・保有については、各種の法令によって多くの事柄が義務づけられている。 免許自動車を運転する場合には、道路交通法(昭和35年法律第105号)によって、公安委員会が交付する運転免許を取得しなければならない。免許には、第一種免許と、バス・タクシーなどの旅客自動車を旅客を運送する目的で運転しようとする者に交付される第二種免許がある。免許を取得しようとする者は、公安委員会の自動車運転免許試験に合格しなければならない。ただし、第一種免許の試験を受ける場合には、練習を目的とした運転のための仮運転免許を受け、一定の条件を備えた指導者が自動車に同乗し、その指導の下に自動車を運転しなければならない。試験は、自動車の運転について必要な適性・技能・知識について行われる。公安委員会の指定する自動車教習所で技能検定に合格すれば、技能試験は免除される。免許を受けた者は、自動車を運転する際に免許証を携帯しなければならない。免許(小型特殊免許などを除く)を現に受けている者が外国で自動車を運転しようとする場合には、自己の住所地を管轄する公安委員会に必要な書類を提出すれば、国外運転免許証が交付される。有効期間は発給された日から起算して1年である。 [木谷直俊] 登録自動車(軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を除く)を購入し使用する際には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって、運輸大臣が管理する自動車登録ファイルに登録しなければならない。登録制度の目的は、個々の自動車に対する所有権を公証することにある。一部の自動車が登録の対象から除外されるのは、動産としての価値が低いため公証による権利移動の明確化をかならずしも必要としないという考え方に基づいている。登録制度は次に述べる検査制度と密接な関係をもち、新規登録(登録を受けていない自動車の登録)と新規検査は同時に申請しなければならない。登録を済ませた自動車には自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)の取付け、封印、表示が義務づけられる。二輪の小型自動車と軽自動車についても車両番号の指定を受け(検査の際に軽自動車検査協会が指定する)、車両番号標を表示しなければならない。 [木谷直俊] 検査(車検)自動車はその構造、装置、性能などが保安基準に適合しなければ使用してはならず、自動車(二輪の自動車など検査対象外軽自動車、小型特殊自動車を除く)は、新規登録の際に、新規検査を受けなければならない。保安基準に適合した自動車には、自動車検査証と検査標章(いわゆるステッカー)が交付される。運行中は、自動車検査証を自動車に備え付け、検査標章を自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼(は)り付けなければならない。その後、1年ないし2年ごとに継続検査を受けなければならない。ただし、自家用軽乗用車および自家用乗用自動車(乗車定員10人以下)は初回は3年後である。以降は2年ごととなっている。また、自家用貨物自動車(車両総重量8トン未満)については、初回は2年後、以降は1年ごとである。事業用自動車は1年ごとである。自動車の検査は運輸省地方運輸局陸運支局が行い、軽自動車については軽自動車検査協会が実施する。検査を受ける義務者は使用者である。通常の場合、自動車の所有者と使用者は同一人のケースが多いが、所有権留保付きの割賦販売の場合、所有者は販売業者であるのに対して、使用者は実際のユーザーであるなど、所有者と使用者が別人である場合も少なくない。 なお、車検の方法には、定期点検整備と検査をディーラーや整備事業者に任せる「整備車検」、定期点検整備や検査を利用者自らが行う「ユーザー車検」、検査を業者に代行してもらう「車検代行」などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多いとされている。厳密には定期点検整備と検査は別であり、現在では、車検を通した後に整備を行うこともある(前検査・後整備)。 [木谷直俊] 整備自動車の使用者は、次に示す(1)日常点検整備および(2)定期点検整備が義務づけられている。(1)自動車使用者は、自動車の走行距離、運行などの状態から判断した適切な時期(自家用乗用自動車および軽貨物自動車等以外の自動車にあっては1日1回運行前)に、自動車点検基準に従って目視などにより当該自動車を点検整備しなくてはならない(道路運送車両法47条の2)。(2)事業用自動車および自家用大型自動車等(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量8トン以上の自動車およびレンタカーであって乗用自動車および軽自動車を除く自動車)は3か月ごとに、自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車ならびに乗用自動車および軽自動車等のレンタカー等は6か月ごとに、その他の自動車については1年ごとに、自動車点検整備基準に従って当該自動車を点検・整備しなくてはならない(道路運送車両法48条)。 なお、1995年(平成7)7月から車齢が11年を超える自家用自動車について、自動車検査証の有効期間が1年から2年に延長された。また、自家用自動車の6か月点検の義務づけの廃止、「前整備・後検査」の義務づけの廃止、定期点検項目の簡素化が実施された。さらに、2007年(平成19)4月からは、自動車の安全確保・環境保全を前提に、ユーザーの負担軽減の観点から二輪の小型自動車の自動車検査証の有効期間を初回2年から初回3年に延長するとともに、二輪自動車の6か月点検の廃止が行われた。 [木谷直俊] 保管自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型特殊自動車を除く)の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(昭和37年法律第145号、通称車庫法)によって、自動車の保管場所を確保しなければならず、道路を自動車の保管場所として使用することはできない。そのため、自動車を保有する者は、新規登録、変更登録(使用車の変更など)、移転登録(名義変更)に際して、保管場所の確保を証する書面(車庫証明)を作成するための申請をしなければならない。証明書の作成は、保管場所を管轄する警察署長が行う。警察署長は、申請を受理したときは、当該自動車の保有者に対して、当該自動車の付置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。保管場所標章の交付を受けた者は、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。軽自動車については新規の運用の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用地域)、保管場所の位置、その他政令で定める事項を届出しなければならない。ただし地域によってはその必要はない。 運送事業用自動車の車庫証明作成のための申請については道路運送法、貨物自動車運送事業法等の法律に基づく命令に定めるところによる。 自動車を道路上の同一場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車した場合などには罰金に処せられる。 [木谷直俊] 保険自動車または原動機付自転車の保有者は、自動車損害賠償保障法(自賠法。昭和30年法律第97号)によって、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険、責任保険)に加入しなければならない。これにより、人身事故を起こした場合、相手に対して最高3000万円までの損害賠償金が支払われる。この保険は、損害保険会社およびその代理店が取り扱う。自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行してはならない。農業協同組合、消費生活協同組合、事業協同組合で扱っている自動車損害賠償責任共済(責任共済)の内容、保険金などは、責任保険と同様である。以上の二つを通常、強制保険というのに対して、賠償額がきわめて高額化した現在、任意自動車保険への加入が一般的になっている。これには、一般自動車保険、対人賠償事故の際に損害保険会社の示談交渉サービスが得られる自家用自動車保険(ただし、保険に加入できる車種が限定されている)、運転免許証はもっているが、自動車は保有していない人が、他人から借用した自動車を運転中に起こした事故を担保するための自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)などがある。なお、強制保険に入っていない場合や、次に述べる自動車重量税の納付がない場合などには、新規検査が受けられない。そのほか、ひき逃げや自賠責無保険車による事故で、自賠責保険の補償が受けられない被害者は、自賠法に基づく国の保障事業により、自賠責保険と同様の保険が得られる。なお、最近は高齢者事故が多く、そのため国の自賠責会計が赤字となり、保険料率が引き上げられた。 [木谷直俊] 税金自動車には自動車を取得した段階、保有段階、走行段階で各種の税金が課せられる。全体で消費税を除くと8種類のものがある。これらの税収は国および地方公共団体の一般財源にあてられている。 取得段階では自動車取得税、消費税が課せられる。自動車取得税は、新車、中古車に限らず購入したときの取得価格を基準として課税される。自家用車であれば取得価格の5%(営業用および軽自動車は3%)である。取得価格が50万円以下のものについては免除される。なお、2012年(平成24)4月から2015年3月までの間、別途、エコカーに対する自動車取得税の軽減措置が講じられている。 保有段階では自動車重量税、自動車税、軽自動車税が課税される。自動車重量税は、車検または届出のときに車の総重量に応じて課税される。税率は車種や車検の期間により異なる。かりに車検が3年間(新車)とすると、1.5トンの自家用車なら重量0.5トンまたはその端数ごとに1万2300円となっているので、その3倍の3万6900円となり、自家用軽自動車なら一律9900円である。なお、一定の環境対応車については税の減免措置がある。自動車重量税については車検証の交付または車両番号の指定を受けるときまでに、税額相当額の自動車重量税印紙を納付書に貼り付けて、運輸支局または軽自動車検査協会に提出することにより納税する。自動車税は毎年4月1日現在の持ち主に対して定額で課税される。税額は総排気量に応じて異なる。自家用乗用車であれば、たとえば、排気量が1リットル以下で2万9500円、1リットル超から1.5リットル以下で3万4500円、1.5リットル超から2リットル以下で3万9500円となっている。原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車に対する税金としての軽自動車税も毎年4月1日現在の持ち主に対して定額で課税される。軽自動車(自家用)は、乗用車で7200円、トラックで4000円である。二輪車は、たとえば50cc以下で1000円、51ccから90ccで1200円となっている。 走行段階では揮発油税、地方揮発油税(かつての地方道路税であるが、2009年度の道路特定財源制度廃止に伴い名称変更)、軽油引取税、石油ガス税、消費税がある。揮発油税、地方揮発油税は、ガソリンに課税されるもので、燃料価格に含まれ消費量に応じて負担する。揮発油税はリットル当り48.6円、地方揮発油税はリットル当り5.2円、合計で53.8円である。ディーゼルエンジンを搭載した自動車に対する税金としての軽油引取税も燃料価格に含まれ消費量に応じて負担する。軽油に課税され、リットル当り32.1円である。石油ガス税も同じく燃料の価格に含まれる。LPG(タクシーなどが利用している)に課税され、キログラム当り17.5円である。さらに消費税が燃料の購入価格に課税される。最後に、自動車関係税には多種多様な税が存在するだけでなく、ユーザーの負担額も大きいことから、こうした税金体系の根本的な見直しが必要であるといわれている。 [木谷直俊] 『日刊自動車新聞社編・刊『自動車産業ハンドブック 2001年版』(2000)』▽『大佐肇・齋藤淑人編『Q&Aくらしの税金知識』(2012・新日本法規出版)』▽『日本自動車工業会編・刊『自動車ガイドブック』各年版』▽『国土交通省自動車局監修『注解自動車六法』各年版(第一法規出版)』▽『国土交通省編『国土交通白書』各年版(ぎょうせい。平成12年度版までは運輸省編『運輸白書』)』 [参照項目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |©Shogakukan"> 乗用車の車体型式と各国における呼び名 ©Shogakukan"> エンジンの点火・冷却・潤滑系統 ©Shogakukan"> シリンダーのおもな配列型式 ©Shogakukan"> 自動車の公害対策 ©Shogakukan"> 後輪駆動と前輪駆動 ©Shogakukan"> ダイヤフラム型クラッチの作動原理 ©Shogakukan"> トランスミッションの作動原理 ©Shogakukan"> シンクロメッシュの作動原理 ©Shogakukan"> サスペンションのおもな方式 ©Shogakukan"> ステアリングの構造 ©Shogakukan"> ホイールアライメント(車輪整列) ©Shogakukan"> ブレーキ装置の構成 ©Shogakukan"> ブレーキの構造 ©Shogakukan"> 自動車の空調システム 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
<<: Automobile transport business - Automobile transport business
>>: Children's magazine - Jidou Zasshi
Recommend
James-Lange theory
This is a classical theory on the experience and e...
Cousin - Cousin
... refers to marriage between cousins. Cousin ma...
ballet slipper
…In the 18th century, mules became independent an...
Onagawa [town] - Onagawa
A town in Oshika County in eastern Miyagi Prefectu...
Takayama [city] - Takayama
A city in northern Gifu Prefecture. It was incorpo...
Equation - equation
An equation is an equation that contains variable...
Suomenlahti
…Official name: Republic of FinlandSuomen Tasaval...
General jurisdiction - Ippankankatsuken
…Civil jurisdiction is the power to determine or ...
Ethyl alcohol
Also called ethanol. Chemical formula: C 2 H 5 OH....
Foz do Iguaçu (English spelling)
A city on the Parana River in the western part of ...
Pinel, Philippe
Born: April 20, 1745 in Saint-André Died October 2...
Shinchosha Co., Ltd. - Confidence
Founded by Sato Yoshiaki in 1904, Shincho is a lon...
Abū al‐'Atāhiya
748 to 750 - 825 to 828 A poet of the Abbasid peri...
Zesen, P.von (English spelling)
...His fame was due entirely to the explosive suc...
Lavender oil - lavender oil
This essential oil is obtained by steam distillat...