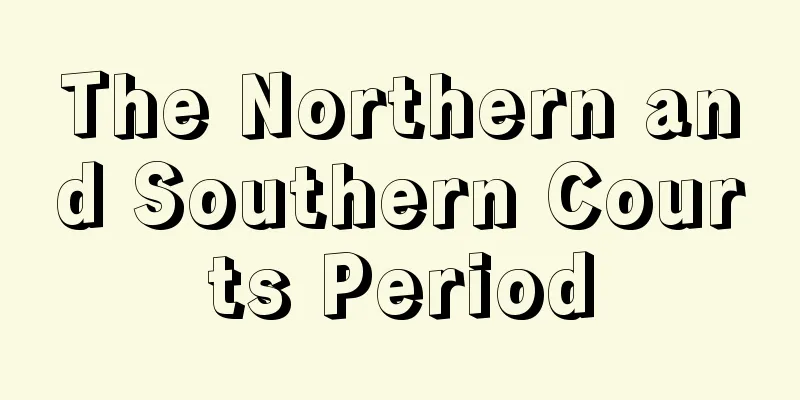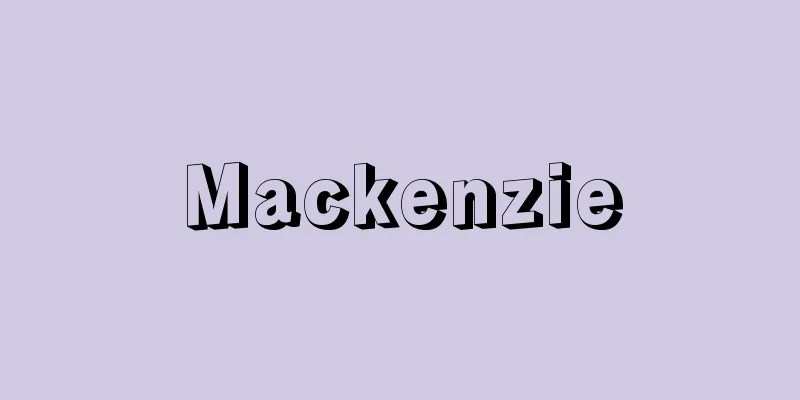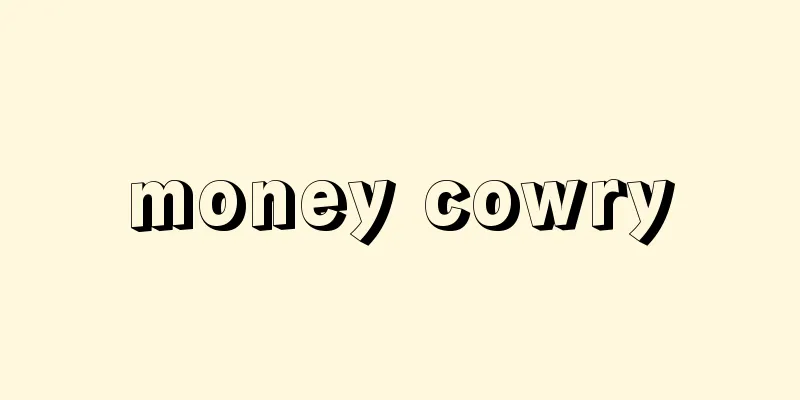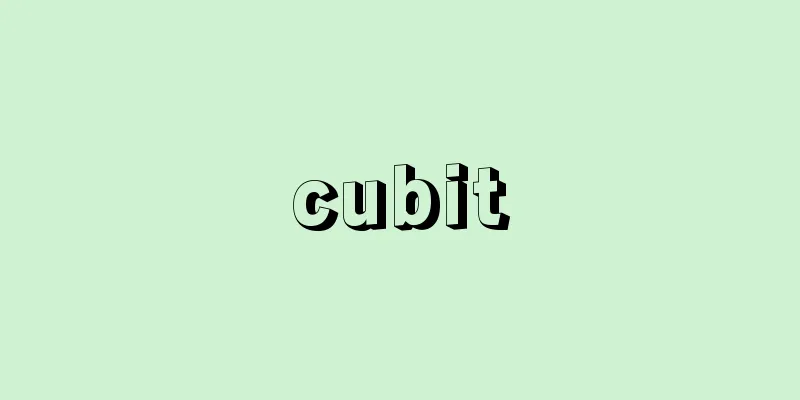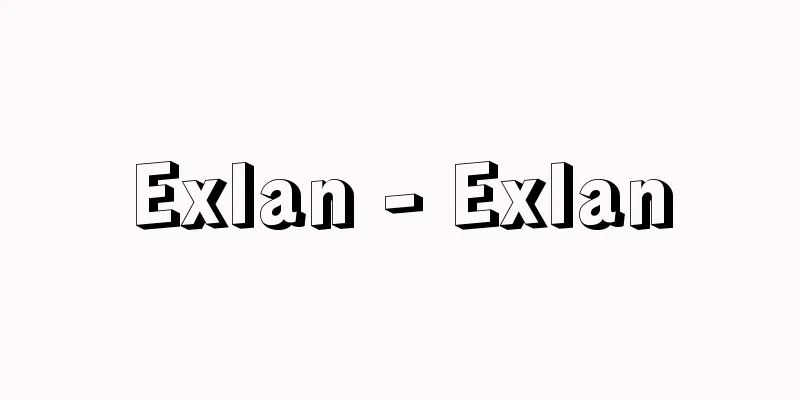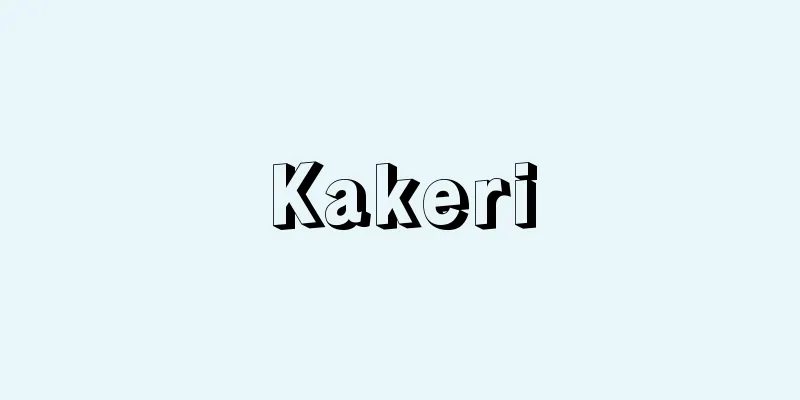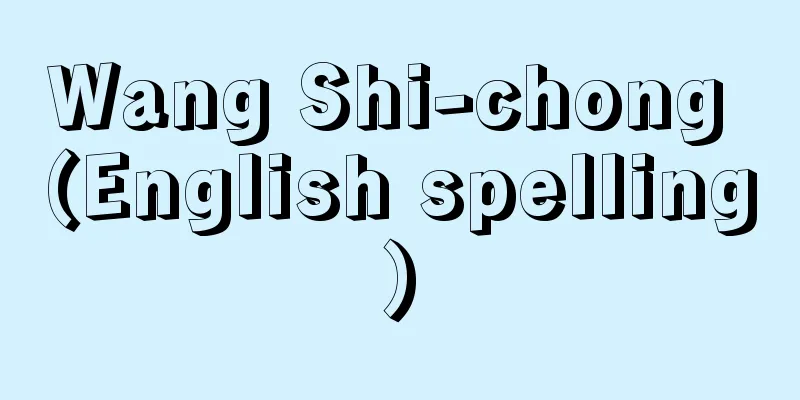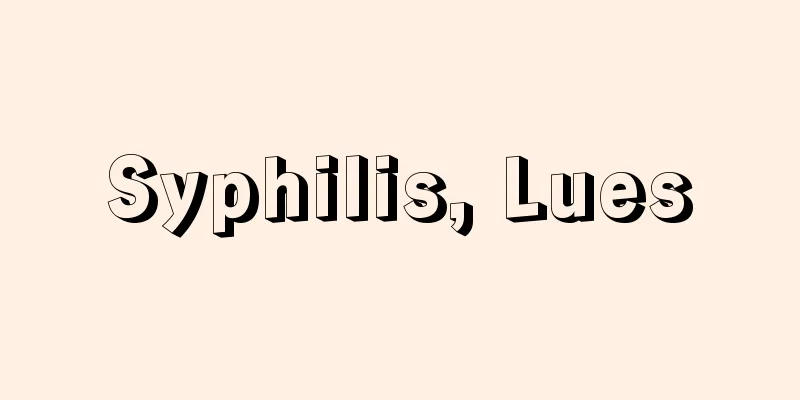India - Indo (English spelling) India English
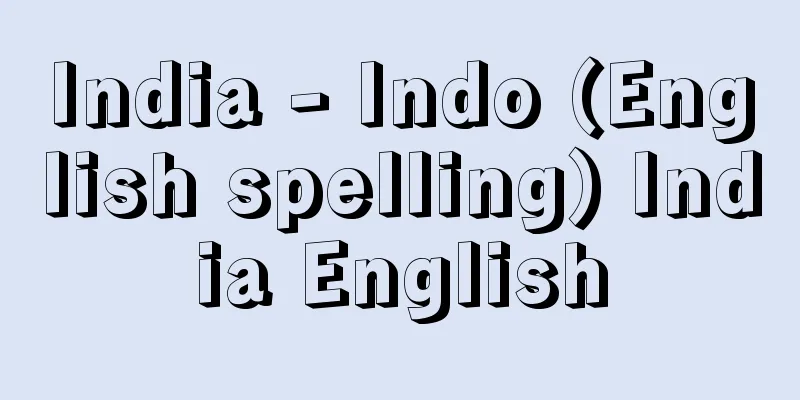
OverviewIndia is a constitutional democratic republic that gained independence on August 15, 1947, from two centuries of British colonial rule. It is also called Bharat. It occupies the center of South Asia, has a vast land area of 3,287,263 square kilometers, which is slightly less than nine times the size of Japan, and has a population of 1,117,734,000 (estimated in 2006), the second largest in the world after China. After independence, under the leadership of the excellent leader Nehru, India has played an important role in the international community as a leader of non-aligned countries. The name of the country, "India," comes from the fact that the Greeks once called the Indus River basin Indos. The Aryans, who advanced into the Indus River basin in waves from around 2000 BC, called this region Sindhu. It is believed that this was called Hindu in the Iranian region, and then became Indos in Greek. Bharat also comes from "the country that opens to the south" (Bhāratvarsa) mentioned in the Brahmanic scriptures around the 6th century BC, and is the name of an ideal holy king who is said to have unified India in ancient times. More than one billion people live in this country, which is bounded by the Himalayas, the roof of the world, to the north, the Bay of Bengal to the east, and the Arabian Sea to the west. The mainland is made up of the Andaman and Nicobar Islands, which float in the sea south of Myanmar, and the Lakshadweep Islands, which are off the west coast of the southern tip of the mainland. The mainland stretches across the northern hemisphere from 8°4′ to 37°6′ north latitude and 68°7′ to 97°25′ east longitude. The longest stretch of the country is 3,214 km from north to south and 2,933 km from east to west, with a border of 15,200 km and a coastline of 6,100 km. The northern half of the country borders Myanmar and China in the east and encompasses Bangladesh. The north borders China across Nepal, and the west borders Pakistan. The peaceful maintenance of borders with so many countries is deeply related to the development of the national economy and is a major challenge for the government and the people. A nation with the current land area first emerged on the Indian subcontinent with India's independence in 1947, but the history that unfolded on this stage dates back to the Indus civilization, one of the world's four great ancient civilizations. Around 2000 BC, the Aryans crossed the Khyber Pass and advanced into the Indus River basin, where they encountered the indigenous Indus civilization and destroyed it. They then expanded their living space to the Ganges River basin and the Deccan Plateau. This process saw the nomadic Aryans invading and integrating with the indigenous settled agricultural people, and Brahmanism was established as a philosophy to legitimize this. The indigenous agricultural people rebelled against this, systematizing their own indigenous philosophy and giving birth to Buddhism and Jainism. However, over the long history of history, the ideas of the two were fused and integrated, resulting in the formation of Indian culture. Islam, which was born in the desert countries in the early 7th century, quickly spread its sphere of influence to Western Asia, and in the 8th century, various dynasties sent numerous expeditionary forces to the fertile Indian subcontinent and repeatedly plundered it. Finally, in the early 13th century, Qutb-ud-din Aibak, an aggressive Muslim warlord of the Ghorid dynasty, established an Islamic dynasty in Delhi, a strategically important location in the subcontinent. From then until the Mughal dynasty (Mughal Empire) was destroyed by the British in 1858, the subcontinent was a place of rise and fall of various Muslim dynasties, and during that time, it was a period of conflict between Islamic and Hindu cultures. On the other hand, from the 17th century onwards, the colonization of India by the British East India Company continued to expand, and after the Indian Mutiny (Sepoy Mutiny) of 1857-1858, it became a direct British colony. Until independence in 1947, India suffered under colonial rule, but actively developed local administrative systems, education systems, railways, road networks, and other systems. The history of India is by no means glorious, but rather is a history of cultural reorganization due to wave-like invasions by different ethnic groups, beginning with the advance of the Aryans. Thus, the people of each era suffered from the friction of different cultures, and from that struggle they created new philosophies and religions. In the longest history of civilization in the world, modern India has become a multilingual, multiethnic society, and has acquired unique characteristics such as the caste system, which is a social restriction on life, and the discriminated people, which has led to it being characterized as "unity in diversity." [Shuichi Nakayama] NatureterrainThe Indian mainland is divided into four major geographical regions: the Himalayas, which are covered with glaciers; the Hindustan plain formed by the upper reaches of the sacred rivers Ganges and Indus; the Thar Desert, an arid region that does not allow development; and the semi-arid Deccan Plateau. The Himalayas were under the sea 600 million years ago, and began to rise by large-scale folding and faulting movements about 70 million years ago, forming the huge mountain body we see today. It is a neo-orogenic belt that stretches about 2,500 kilometers from east to west and 240 kilometers wide, and is home to many of the world's highest peaks, including Mount Everest (8,848 meters). The name Himalayas is a compound word of Hima (snow) and Ālaya (palace), meaning "snow palace." The area of the snowy plains covered with perpetual snow is 40,000 square kilometers, making it the largest in the world. The Hindustan Plain is formed by the drainage basins of three major rivers, the Ganges River at its center, the lower Brahmaputra River to the east, and the upper Indus River to the west. It stretches for about 2,400 km from east to west and 240 to 320 km from north to south, and is a very low-lying plain as a whole. Even near the capital city of Delhi on the banks of the Jamuna River, about 1,600 km west of the Bay of Bengal at the mouth of the Ganges River, the elevation is only about 200 meters. Its area is about 770,000 square kilometers, more than twice the size of Japan. The Hindustan Plain was under the sea during the Pleistocene (Pleistocene) Epoch, and is believed to have been filled in by large amounts of sediment carried from the Himalayas to the north and the Deccan Plateau to the south, with the sedimentary layer reaching a depth of over 6,000 meters at its deepest point. The soil that forms the Hindustan Plain is called Bhangar, which is an older layer dating back to the Middle Pleistocene. The relatively new soil that accumulates in the floodplains of rivers is called Khadar in Uttar Pradesh and Bet in Punjab. The Deccan Plateau is the world's oldest Gondwana landmass. In a broad sense, it is a collective term for the plateaus and mountain ranges located in the peninsula south of the Ganges River. In a narrow sense, it refers to the plateau areas included in the states of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh, and is characterized by table-like hills and undulating topography. Its area is about 700,000 square kilometers, about 1.9 times the size of Japan. On the western border of the Deccan Plateau, the Western Ghats run north to south for about 1,600 kilometers, with an average elevation of 1,200 meters, and on the eastern border, the Eastern Ghats run with an average elevation of 600 meters. These mountains prevent the movement of monsoon rain clouds, and the western part of the plateau is a semi-arid region with an annual rainfall of around 600 mm. The plateau as a whole is 1,200 to 300 meters above sea level, and the altitude drops stepwise from west to east. Therefore, with the exception of the Narmada and Tapti in the north, all major rivers originate in the Western Ghats and flow eastward into the Bay of Bengal. Soils are generally poor, red soil or laterite, except for the black soil in the Deccan lava flow area in the northwest. [Shuichi Nakayama] climateLocated at the southern end of the Asian continent, India occupies a vast area in the Northern Hemisphere and is surrounded by the Himalayas, the "roof of the world," and the Indian Ocean. Due to this topography, India's climate generally exhibits typical monsoonal characteristics. The country has four seasons: winter, summer, rainy season, and autumn. In winter (December to February), a high pressure belt stretching from the Western Mediterranean to Central Asia and northeastern China causes cold air to flow eastward at high altitudes, resulting in clear skies, low temperatures, and large daily temperature differences. However, low pressure systems that occur in the Iranian Plateau four or five times a month move eastward across the Hindustan Plain accompanied by a winter rain front, bringing rain and sometimes causing a cold air mass to pass through and drop the temperature to around 0°C. This rain is an important factor that greatly affects the yield of winter wheat crops in northern India. As the sun moves north toward the Tropic of Cancer, the temperature begins to rise and summer (March to May) arrives. The temperature rise begins in southern India (average 38°C in March), then in central India it reaches 38-43°C in April, and in northern India it reaches 45°C or higher in May, a horrific heat wave. In the Hindustan plain, the high temperatures cause strong updrafts, creating a low-pressure zone overall. A strong hot wind called Lu blows in from the south from the Deccan Plateau, sometimes bringing thunderstorms accompanied by sandstorms and hail. This results in a dry, hot summer that crushes life. At the end of May, the temperature rise and low pressure zone in the Hindustan plains reach their limit, and trade winds from the southwest, loaded with moisture from the Indian Ocean, begin to blow in toward them. This is the arrival of the southwest monsoon, or rainy season (June to September). The rainy season begins in the southern tip of India in early June, and the rainy area moves northward day by day. By mid-June, the rainy season reaches all of India, and it rains and rains every day. This season brings 90% of the annual rainfall to northern India. In the second week of September, the trade winds begin to weaken, and the low pressure that had covered India widely begins to retreat to the Bay of Bengal, and in October, high pressure extends out. Then comes autumn (October to December). Northern India enjoys dry and refreshing days, but on the eastern coast of southern India, cyclones (typhoons) occur due to the activity of the low pressure that has moved south of the Bay of Bengal. On average, once every three years, a fully developed cyclone makes landfall on the southeastern coast, causing great damage to people and livestock. Sometimes, it travels westward from the east coast, crosses the Deccan Plateau, and causes great damage in the Kerala region on the west coast before passing into the Arabian Sea and disappearing. Monsoon rains in India are a crucial factor in controlling agricultural development. However, areas with an average annual rainfall of more than 1000 mm are limited to the western coastal plain of the Western Ghats, the eastern coastal plain of the Eastern Ghats, and eastern India. The remaining major part of the Deccan Plateau and northwestern India are semi-arid regions, which are a major obstacle to agricultural development. [Shuichi Nakayama] BiotaBlessed with a vast land area, diverse topography, and climates ranging from temperate to tropical, India boasts a rich vegetation of 30,000 species. By region, it has four distinct vegetation zones: (1) dry tropical deciduous forest, (2) dry thorny scrub forest, (3) moist tropical deciduous forest, and (4) temperate highland forest. The dry tropical deciduous forest occupies the largest area in India, spreading from the Punjab plain to the Ganges River basin and the northwestern and southern ends of the Deccan Plateau. The main tree species are linden and sal in the Hindustan plain, and teak, rosewood, and bay laurel in the Deccan Plateau. The dry thorny scrub forest is widely distributed in the states of Haryana, Rajasthan, and Gujarat, as well as in the central part of the Deccan Plateau. Acacia, neem (a roadside tree that grows to over 10 meters tall), and Chinese ash are common in western India, while sandalwood and neem are typical species that are widespread in the central Deccan Plateau. The humid tropical deciduous forests are found in the Terai region along the Nepal border, the Assam Hills, the eastern Deccan Plateau, and the Western Ghats. These forests are characteristic of areas with an annual rainfall of 1000-2000 mm, and lose their leaves during the dry and hot season of 6-8 weeks. Representative tree species include teak, bay laurel, rosewood, and sal. The temperate highland forests are widespread in the western Himalayas, and are dominated by Himalayan cedar, black pine, spruce, and fir, with white birch and juniper found at higher altitudes. Furthermore, tree species that are commonly seen around cities and settlements throughout the country include the Indian linden, banyan and neem in northern India, and palm species, particularly coconut palms, in southern India. Since independence, the government has been enthusiastically promoting eucalyptus afforestation projects across a wide area in semi-arid regions with an annual rainfall of 400-800 mm. As India has a large area of cultivated land, forests account for only a small area of about 17%, but of this, over 90% is government-owned, and afforestation projects are considered an important issue for the government. India is blessed with a rich natural environment and is known to have many animals, including about 500 species of mammals, about 21,000 species of birds, and 30,000 species of insects. Excluding livestock, India is famous for being home to many large animals, such as elephants, wild buffaloes, one-horned rhinos, tigers, lions, and various deer. However, since ancient times, kings and local lords have loved hunting (called shikar in India), and during the colonial period, the British also enjoyed hunting, so the numbers of large animals have decreased, and in recent years, the habitats of large animals have been limited to national parks and wildlife sanctuaries. Looking at the regional habitats of major animals, the Himalayan mountains in Kashmir are home to many wild goats, bears, Kashmir deer, and leopards. Antelopes remain in some areas of the Punjab plains. In eastern India, wild buffaloes, deer, and the world's only one-horned rhinoceros live in the forest areas of the Assam hills. The famous Bengal tiger still sometimes threatens villagers in the dense forests at the mouth of the Ganges River. Crocodiles are also known to live in the Mahanaji River. The Gir Sanctuary in Gujarat, western India, is famous as the only lion habitat in Asia. The forests of Belgaum district in northern Karnataka are home to elephants, tigers, wild buffalo, leopards, bears, deer, and more. Elephants and wild buffalo also live in the forests on the eastern foot of the Western Ghats in the southern part of the state, and warning signs warning "Watch out for elephants" are posted on the national highways. Further south, wild goats called "Nilgiri yagi" also live in the Nilgiri Mountains. The tiger is India's national animal and the peacock its national bird. Under the Wildlife Protection Act (enacted in 1972), a breeding program for tigers has been implemented in 11 protected areas nationwide with the goal of increasing the population to over 2,500, and a breeding program for crocodiles has been underway in 12 protected areas since 1974 with the assistance of UN agencies with the goal of increasing the population to 3,000. In this way, animals and birds are given thorough protection in over 450 national parks and wildlife sanctuaries across the country. [Shuichi Nakayama] GeographyTo look at the regional characteristics of India, if we divide it into regions based on its topographical features, we can see that it can be divided into four major regions: the Himalayas, the Hindustan Plains, the Deccan Plateau, and the coasts and islands. [Shuichi Nakayama] HimalayasThe Himalayan Mountains in India are divided into the Western Himalayan Region and the Eastern Himalayan Region, with Nepal in between. The Western Himalayan Region includes the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and the northern part of Uttar Pradesh. The Eastern Himalayan Region is centered on the states of Arunachal Pradesh and Sikkim. Both regions share the commonality of being dominated by the steep mountainous terrain of the Himalayas, but show significant differences in precipitation and historical development. While the Western Himalayan Region is relatively well developed, centered around the Kashmir Basin, the Eastern Himalayan Region is one of the least developed regions in India. In agriculture, rice, corn, and millet are the main crops in both regions, but slash-and-burn cultivation still remains in the Eastern Himalayan Region. Apple production in the Western Himalayan Region has also been growing rapidly in recent years, thanks to its cool climate. The Western Himalayan Mountains attract the hearts of the people with two faces. The first is as a summer resort centered on the Kashmir Valley, and the second is as a holy place for Hinduism. The Kashmir Valley has scenic mountain areas such as the state capital Srinagar, Pahalgam, Amarnath, and Sonamark, and is described as a "paradise of clear streams and lakes studded with pearls and emeralds." The number of tourists who come to escape the heat from the scorching heat of the Hindustan Plain and the Deccan Plateau is steadily increasing year by year. For the residents of the plains and plateaus, who suffer from scorching heat of over 40 degrees Celsius, the Kashmir Valley in the deep mountains and valleys, where the temperature is just over 20 degrees Celsius even in midsummer, is truly a "paradise on earth." Kashmir carpets, produced by cottage industries, are a specialty product known not only in the country but also around the world. Mount Kamet (7,756 meters) in the Western Himalayas is the source of the holy Ganges River, and is revered as the seat of Shiva (the god of destruction), one of the three Hindu gods. Holy sites such as Badrinath and Kedarnath have been established at altitudes of over 6,000 meters since ancient times, and many pilgrims visit the area even outside of the rainy season. The border between Pakistan and China in the Western Himalayas and between China in the Eastern Himalayas has not been determined, and border disputes have continued even after independence. [Shuichi Nakayama] Hindustan PlainThe Hindustan Plain is sandwiched between the Himalayas to the north and the Deccan Plateau to the south, and is approximately 2,400 km wide from east to west and 240 km wide from north to south. It occupies approximately 33% of the country's land area, but is home to approximately 45% of the population (2001), making it one of the most densely populated plains in the world (population density: 488 people per square kilometer). The plain includes the states of Punjab, Rajasthan, and Haryana to the west, Uttar Pradesh and Bihar in the center, and West Bengal and Assam to the east. The Hindustan Plain is formed by the world's great rivers, with the upper reaches of the Ganges River in the center, the upper reaches of the Indus River to the west, and the lower reaches of the Brahmaputra River to the east, and its fertile soil forms a grain-producing region for rice, wheat, and millet. Latitude-wise, it is located about 30 degrees north of the Tropic of Cancer, but because it stretches from east to west along the Himalayas and is dominated by an inland climate, it exhibits a wide variety of climates, from the tropical rainy areas of Assam to the dry, scorching heat of the Thar Desert. It can be said that this diversity of climate gave birth to Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, and other religions that originated in India, in the Hindustan Plain. The Muslim rule of the Indian subcontinent, which greatly determined the history of India, began in Delhi, located in the western part of the plain, in the 13th century, and British colonization in the 17th century began in Calcutta (now Kolkata) in the east. The first war of independence against the British, the Indian Mutiny (Sepoy Mutiny), was fought on this plain from 1857 to 1858, and the partition of India and Pakistan in 1947 was the political division of this densely populated and productive, rich plain. The Hindustan Plain shows notable regional characteristics even in modern economic activity. The western state of Rajasthan is known as a producer of gypsum, silver, and asbestos, while Punjab is known for its wheat, rice, and machinery and equipment industries. In the central region, Uttar Pradesh is rich in sugarcane, while Bihar is rich in coal, iron ore, copper, mica, and other mineral resources, producing 40% of India's total mining production. In the eastern region, West Bengal is home to rice, jute, and tea, as well as steel and chemical industries. Assam is the center of black tea production, and also produces 50% of the country's oil and natural gas, making each of these major production areas in India. [Shuichi Nakayama] Deccan PlateauThe Deccan Plateau is a vast region that occupies most of the peninsula of the Indian subcontinent. The plateau is characterized by an undulating topography with numerous mountains and hills scattered in a mosaic pattern, and an elevation of 300 to 1,200 meters. With the Western Ghats on its western edge and the Eastern Ghats on its eastern edge, the area receives little monsoon rainfall, with the western region receiving around 600 millimeters of annual rainfall, making it a semi-arid region, and the overall area receiving less than 1,000 millimeters of rainfall, which is a major obstacle to agricultural development. The Deccan Plateau divides the cultural sphere into two, the north and the south, and the south is further divided into three sub-regions with their own characteristics. The northern states of Madhya Pradesh and Maharashtra are Aryan-speaking cultural spheres, and the Marathas in particular retain a strong Hindu nationalist character that strongly resisted Muslim rule in the Middle Ages. The southern states of Andhra Pradesh, Karnataka, and Tamil Nadu constitute the indigenous Dravidian-speaking region. However, the people of Andhra Pradesh, who have been strongly dominated by Muslims since the Middle Ages, the Tamils who have strong Tamil nationalist colors, and the people of Karnataka, which has the most arid land of the three states and is enterprising, each show their own characteristics in terms of political and economic behavior. Andhra Pradesh, with its strong Islamic coloration, is anti-central government, and is not blessed with natural resources, so it has been left behind in economic development after independence. Tamil Nadu, located at the southern tip of the peninsula, has tended to be alienated from the central government. However, since ancient times, the state has been internationally conscious, having sent many immigrants to various parts of Southeast Asia, and has acquired a character that shows off the superiority of Tamil culture and the unity of the Tamil people. This has led to a stronger sense of autonomy in relation to the central government, and a strong spirit of self-reliance and independence is deeply rooted in the state. On the other hand, Karnataka has had the advantage of being located in the central southern part of the Deccan Plateau since ancient times, and was able to keep a close eye on both the eastern and western coastal regions. However, due to the semi-arid climate, investment in agriculture was stagnant, so the state focused on the development of commerce and industry. In the modern era, the famous general Tipu Sultan resisted British colonization to the end and became an Indian hero, and in the early 20th century, the state produced the great entrepreneur and politician Vishbeth Walaya. He is a great man who built the first hydroelectric power plant in South India, constructed Lake Krishna Raj, and completed a large-scale irrigation canal network in the southern part of the state, making a great contribution to agricultural development. [Shuichi Nakayama] Coastal and IslandThe country, which juts out from the Asian continent into the Indian Ocean, has a long coastline of about 6,100 km, divided into east and west coasts by Cape Comorin at the southern tip of the peninsula. In addition, the Andaman and Nicobar Islands are located in the southern ocean of Myanmar, about 1,500 km west of Chennai (Madras), and the Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea, about 350 km west of Kozhikode (Calicut) in Kerala. Both islands are under the direct control of the central government, with the former having its seat in Port Blair and the latter on Kavaratti Island. The islanders focus on fishing and coconut production, and are dedicated to growing rice for their own consumption. Looking at the coastal areas, the east coast is an elevated coastal plain, and the further south you go, the wider it becomes, reaching 100 kilometers. This area has been called the Coromandel Coast since ancient times, and flourished as a rice-producing region. The west coast is a submerged coast where the Western Ghats have fallen into the Arabian Sea due to a fault, and is called the Malabar Coast, a narrow strip of plain with an average width of 25 kilometers. As the southwest monsoon hits this mountain range, it becomes a rainy area with an annual rainfall of 2,000 to 6,000 mm, and rice and coconut cultivation is thriving. The coastal areas have been in contact with foreign countries through the sea since ancient times, and have played an extremely important role in building India's unique history. From ancient times to the Middle Ages, the gateway for maritime traffic connecting India with West Asia and Arabia was the coast of Gujarat state in northwest India, and Surat in particular was the largest port city on the west coast. At the end of the 15th century, after Vasco da Gama discovered a sea route around the Cape of Good Hope when he arrived in Calicut, Portuguese power arrived on the west coast and opened port cities such as Bombay (now Mumbai), Goa, Daman, and Diu. France, which arrived on the east coast, established trading posts in Pondicherry, and Britain in Madras (now Chennai) and Calcutta (now Kolkata), and began trading with Indian merchants. Currently, the main port cities that have developed on the east coast are, from the north, Kolkata, Haldia, Paradeep, Visakhapatnam, Chennai, and Tuticorin, and Visakhapatnam in particular has been developed as a port for the purpose of shipping iron ore to Japan. On the west coast, important ports such as Mumbai, Marmagao, New Mangalore, and Cochin are lined up from the north. [Shuichi Nakayama] PoliticsGeneral characteristics of politicsIndia achieved independence from Britain in 1947, while separating from Pakistan. This brought about important changes, such as the transfer of sovereignty from British hands to Indian hands. On the other hand, many things, such as the bureaucracy and military system, have been inherited without much change to this day. For about two and a half years after independence, India was a dominion within the British Commonwealth, like Canada and Australia, and formally the British monarch was the head of state, with a governor-general appointed by him. However, unlike before independence, real political power had already moved away from the governor-general and into the central government's cabinet members. With the constitution that came into force in 1950, India abolished the British monarch as head of state and adopted a presidential system, but it remains a member of the Commonwealth. The first universal suffrage based on equal rights for men and women was held from 1951 to 1952. From this time, a parliamentary cabinet system like that seen in the UK was established at the centre and in each state, which continues to this day. Generally speaking, free elections are held fairly regularly. India is almost the only country in Asia where the central government can change through general elections, and it is extremely rare in the third world. This did not come about by itself, but is the result of the fact that many Indians believe that free elections are necessary for the unity and improvement of India, and have made great efforts to maintain them. There were some who believed that democracy does not bring about economic development, as opposed to the dictatorships that were common in many other Asian countries, or that, conversely, India should set an example of how democracy and development can coexist, but since the liberalization policy of 1991, such voices have died down. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Indira Gandhi showed more reformist poses than his father, splitting the ruling Congressional faction and expelling many elder politicians (1969). However, both of them differentiated themselves from the left-wing parties in the country and tried to contain them. This characteristic was particularly strong in Indira. Another characteristic that was seen in Indira was that he strengthened his personal dictatorship while taking a lot of emphasis on his relatives and aides. These characteristics were even more pronounced during the emergency period of 1975-1977, bringing extremely uniqueness to Indian politics. The main challenges faced by India when it gained independence in 1947 can be summarised into three: changing colonial economic structures and raising standards of living, democratizing all areas of political and economic society, and overcoming the unfortunate history of people conflicting and resulting in the separation of Pakistan from Pakistan. Indian politics have moved around these major challenges. [Yamaguchi Hiroichi] Constitutional system and realityThe head of India is the president, but this is a nominal position and has no real political power. The president is elected by members of both federal and state parliament, with a term of five years. The nine presidents by religion up to 1997 are six Hindus, two Muslims (Muslims) and one Sikh, and up to four of the six Hindus are from South India. It can be seen that the presidential elections are being held while taking into consideration the complexity of the social structure. The reason why the majority of Hindus people are from the North, with the large population is that the 12 prime ministers up to 1997 are all Hindus, and with the exception of the two, all of them are from North India. Compared to the case of the President, the constitutional provisions regarding the Prime Minister and Ministerial Conference are very simple, but in reality, the Prime Minister and Ministerial Conference are the central part of the executive power. There are a large number of ministers, but the main members of these are all unofficially referred to as Cabinets. The Prime Minister is appointed by the President, and the other ministers are appointed by the President based on the advice of the Prime Minister. The Ministerial Conference is jointly and responsible for the House of Representatives, and no ministers are allowed to be left unaffiliated with the Congress for six months in a row. In principle, Congress controls the government. Although the Congress is a two-house system, the House, which is made up of direct elections, is overwhelmingly important. The House of Representatives has been held 14 times until 2004. In line with the Congress faction, the first three times were fought under Nehru's leadership and the next four times under Indira Gandhi's leadership, but in the sixth time (1977), Indira resigned as prime minister, and in the seventh time she has been revenge and has returned to Prime Minister. The nearly three years of those years were the first time the Congress faction was not in the ruling party position in the central position. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. During this time, Rajiv was killed by Tamil terrorists, due to his own intervention in Sri Lanka's ethnic conflict as prime minister (sponsored Indian troops to Sri Lanka from 1987 to 1990). In this general election, perhaps in the sense that Rajiv's mourning, the Conference faction won and the government of Narasimha Rao (1921-2004) was formed, and a series of major economic reforms centered on liberalization was promoted under the hands of Manmohan Singh, who became finance minister. Economic activity became more active than ever before, foreign capital was influxed, and many people were eager to seize the opportunities they had obtained in this way. However, on the other hand, there are signs that the gap between rich and poor is actually growing. Reflecting this, the Conference faction, which had been promoting liberalization policies, was defeated in the 11th General Election in 1996. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The party, a Hindu supremacy force and boasting of its great power, carried out five nuclear tests in Rajasthan over two days on May 11th and 13th, 1998. This was followed by Pakistan's nuclear tests, shaking the world heading towards nuclear abolition. After that, in April 1999, the All India Anna Dravidad Progressive Federation broke out from the Indian People's Party, and the ruling coalition led by Vajpai was no longer convinced by one vote, the House of Representatives was dissolved, and the 13th general election was held in September 1999. This led to the Indian People's Party winning 182 of the 545 seats, while the ruling coalition led by Vajpai secured a majority of 296 seats, and the Vajpai administration continued. In the 14th general election in May 2004, the Indian People's Party led by Vajpayee was defeated, and the National Assembly faction became the ruling party, and Manmohan Singh became prime minister. He was India's first Sikh prime minister, and in the past he served many important positions in the economic field, including finance minister during the Rao cabinet. He announced that he would continue his economic reforms, poverty countermeasures, and dialogue with Pakistan, and the National Assembly faction won in 2009, and the Second Singh administration was established. However, in January 2014 he announced his retirement this term, and after the general election in May of the same year, he resigned. The Indian People's Party won a big victory, surpassing the sole majority, and Narendra Modi (1950-) became prime minister. Elections in the House of Representatives are carried out by a single-member district system where one constituency is one. The term of office is five years. As a result of the adjustment of the districts by the decade-old census, the number of voters in each district is almost equal. The number of constituencies is reserved for the designated castes and designated tribes (see the "Society" section below) is reserved for the number of constituencies that are roughly proportional to their population ratio. The electoral districts revised in 2008, out of the 543 constituencies across the country are reserved for the designated castes and designated tribes, and only those who belong to these groups cannot run for office. This is a system that guarantees the improvement of designated castes and designated tribes, but there are very few cases in which they have been elected from other general districts throughout the period after independence. In addition, two seats are nominated by the president. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. A major force behind central and state politics is the group of approximately 5,000 senior bureaucrats known as the IAS (Indian Administrative Service). The existence of a group of senior bureaucrats under the jurisdiction of central government, such as the IAS (Indian Police Service (IPS) helps to strengthen our position on central states. The judicial system has inherited the colonial era in many ways. At the top of this is the Supreme Court located in Delhi, under which there are 18 High Courts across the country. All of these are under federal jurisdiction in personnel matters and other respects. Under the High Court there are courts under the state's jurisdiction. The judgments of the Supreme Court and the High Court are considered precedent. The jurisdiction is independent, and the courts are given the right to unconstitutional review. [Yamaguchi Hiroichi] Foreign PolicyThe direct result of Pakistan's invasion of Kashmir immediately after independence led to a war between the new nations of India and Pakistan (1947-1949). The relations between the two countries did not improve after that, and wars also took place in 1965 and 1971. The war in 1971 was an expansion of the Bangladesh War of Independence, and as a result of East Pakistan's independence as Bangladesh, India's gravity in the Indian subcontinent increased dramatically. The fact that India remained in the British Commonwealth after the republic (1950) was important in connecting these to the British Commonwealth when British colonies in Africa and other countries became independent. With the accession of India, Pakistan in 1947 and Ceylon (now Sri Lanka) in 1948, the nature of the British Commonwealth as a group exclusively for white countries was somewhat disrupted, but the appearance of the British Commonwealth changed completely with the mass accession of African countries in the early 1960s. The non-alignmentalism, known as Nehru diplomacy, and a policy of friendship with Asian, Arab and African countries, was most shining before and after the announcement of the Five Principles of Peace by Nehru and China's Zhou Enlai in 1954, and the Asia-African Conference in Bandung in 1955. In Nehru's later years, this was shattered by the strengthening of his dependence on economic aid against the US from 1957, the dissent from China from 1959, in which the Dalai Lama's exile in India, and especially the defeat in the border war with China in 1962. However, the role India played in the non-aligned movements after 1961 cannot be ignored. In 1983, the 7th Non-aligned Conference was held in New Delhi. India under Gandhi regime was seen as pro-Soviet, and the 20-year effectiveness Treaty of Friendship and Peace Cooperation in India, which was concluded in 1971, was the most important axis of India's external relations, but it was not closed to the West either. It supported Vietnam's liberation struggle, and in 1980 it approved Cambodia's Hen Samlin regime. During the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, a massive amount of Western weapons flowed through Pakistan to the anti-Soviet and rebels in Afghanistan further strained relations between India and Pakistan. For India, the "end of the Cold War" was the disappearance of the cause of the US-Soviet counter-counter over Afghanistan, and the disappearance of the China-Soviet conflict in the Indian subcontinent. As a result, the conditions for dialogue with Pakistan and China regarding territorial issues were created, but the belonging of the Kashmir region with Pakistan is still a major concern (Kashmir issue), and the issue of border line with China developed into war in 1962. It is likely that it will take more time to resolve these issues, but economic relations continue to be strengthened, and joint training with China is also being carried out with the navy and army. The first seven South Asian summit was held in Dhaka, Bangladesh in December 1985, and the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) was formed. Since then, SAARC has held a summit almost every year (the secretariat is Kathmandu, Nepal). India has also expressed interest in promoting economic cooperation between coastal Indian Ocean countries. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [Yamaguchi Hiroichi] National DefenseColonial Indian troops, like bureaucracy, were divided between India and Pakistan in 1947. The Indian military was based on this, and the rank system was the same as that of Britain. Under the constitution, the president has the highest command of the military, but in reality it is the prime minister and the minister of defense. The minister of defense is a civilian, and civilian control and military neutrality have been well protected so far. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [Yamaguchi Hiroichi] Economy and IndustryOverviewになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. However, since the 1990s, the proportion of people below the poverty line has fallen from 36% (1993) to 28% (2004), while the average life expectancy has steadily improved from 58 years (1991) to 64 years (2006), and the literacy rate has also steadily improved from 52% (1991) to 65% (2001). As economic expansion continues to steadily progress, it is expected that poverty issues and basic human rights will further improve. [Kojima Makoto] Economic reformAfter independence in 1947, the two major goals that were carried out in India's economic development were to eliminate poverty and economic independence. Since the East India Company entered the country in the early 17th century, India has been forced to experience the bitter experience of long-term colonial rule. As a result, India has had a strong desire to economic independence, and national capital had already emerged before independence, and the movement to use domestic products (Swadeshi movement) was called for. After independence, the mixed economic system established during the Nehru period (1947-1964) largely stipulated India's economic development. The backbone of this was the principle of prioritizing expansion of the public sector, wide economic control over the private sector, centered on the industrial licensing system, and even closed foreign policy. From the 1950s to the early 1960s, India focused on creating an industrial base, and public sector-led heavy industrialization was promoted. During the same period, the industrial sector expanded relatively smoothly, but the agricultural sector revealed its fragility, and the Indian economy eventually entered a period of stagnation (1965-1980) due to the Second India-Pacific War in 1965 and the two years of drought in 1965 and 1966. During this period, India's industrial growth slowed for a long time, coinciding with the period when closed and controllist economic management was strengthened under the First Indira Gandhi regime (1965-1977). Meanwhile, the agriculture-focused attitude was actively promoted and the green revolution had made it possible to achieve self-sufficiency in grains such as rice and wheat by the time the 1980s. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Meanwhile, the government of the National Assembly faction, Narasinha Rao, was established in the general elections from April to May 1991, and economic reforms were introduced in July of the same year. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In terms of foreign capital, many industrial sectors were opened to foreign capital, and the inflow of foreign direct investment was increased through the increase in the foreign investment ratio. The introduction of the principle of competition led to a decline in prices and quality improvements, making a major contribution to the expansion of the domestic market and, ultimately, to strengthen the competitiveness of Indian industry. During the centre-left coalition government (1996-1998), economic reforms were temporarily reluctant, but further progress was made under the BJP coalition government (National Democratic Union), led by Vajpayee, during the period from 1998 to 2004. The 1999 New Communications Policy paved the way for the spread of mobile phones through subsequent competition between businesses, and the 2003 Electric Power Act showed the necessary path for reforming the electricity sector. Furthermore, with the passage of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (2003), steady activities began to be undertaken to ensure fiscal soundness. Later, the National Assembly coalition government led by Manmohan Singh (Unified Progressive Alliance, 2004-2014) was established in the 2004 general election. The administration proposed an inclusive growth in which all people can participate in the economic growth process and benefit from it, and in 2004, a nationwide rural employment security scheme aimed at providing 100 days of employment for farmers below the poverty line. The economic reforms aimed at by the administration were generally progressive, leaving behind issues such as rigid revisions to labor laws, entry into foreign capital in retail, and an increase in the proportion of foreign capital in the insurance sector. [Kojima Makoto] Service-driven developmentSince the 1990s, it has been the service sector that has driven the high level of economic growth in India. In fact, the service industry has grown from 6% in the 1980s to 7% in the 1990s, and from 9% in the 2000 to 2007. The service sector consists of many sectors, including commercial, finance, transportation and warehouse, real estate, and administrative services, and since the 1990s, the sectors of communications, insurance, business services (including IT services), and hotels and restaurants have achieved particularly significant growth. Looking at the sectoral composition of GDP, the service sector's share has expanded from 43.8% in 1990 to 50.6% in 2000, and to 52.4% in 2007. The IT industry has emerged as the new face of the Indian economy as the central figure of the service sector's leading development. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The characteristic of the Indian IT industry is that it is more inclined to software than hardware, and even exports than domestic markets. The majority of export destinations are English-speaking countries, with the US accounting for 60% of the total, with the UK accounting for 19%. Initially, IT services delivery was overwhelmingly overwhelming insights, in which IT engineers go to clients and provide services, but the offshore system, which uses satellite communications to provide services directly from India, where labor costs are low, has gradually become dominant. What is attracting attention as trends in the Indian IT industry is that they are rapidly evolving and expanding each year, and are moving towards areas with higher added value in each field. The incomes enjoyed by IT engineers are significantly higher than in other industries, and the number of jobs they have been increasing rapidly each year. The number of IT engineers employed in 2009 was 2.3 million, and indirect employment for transportation, catering, construction, security, and miscellaneous tasks reached 8.2 million. In India, the IT industry has produced many middle class members with purchasing power, and plays an important role in increasing demand for various goods and services across secondary and tertiary industries, and has also contributed greatly to improving the efficiency of other industries such as manufacturing and finance through IT, which is progressing across industries. [Kojima Makoto] The new rise of manufacturing1991年の経済改革の実施に伴い、インド経済は新たな段階を迎えたが、経済成長を牽引する主役はサービス部門であり、工業部門は脇役的存在にとどまっていた。しかしながら2002年以降、工業部門は新たな拡大を示し、サービス部門と並んで、経済成長のエンジンとしての役割を果たすようになった。実際、2004~2007年の4年間、工業部門は年平均8.8%の高レベルで成長し、2006年には11.0%の成長率を記録した。とくに注目されるのは、経済全体への波及効果の大きい自動車、鉄鋼の両産業である。1980年代前半におけるスズキのインド進出は、インドに日本的経営や生産方式をもたらし、自動車産業に新風を吹き込む結果となった。1991年以降、経済自由化が本格化するなかで、国内市場の潜在的規模に対する期待が高まり、日米欧韓の大手自動車メーカー(そして大手部品メーカー)のインド進出が活発化するようになった。1998年には民族系商用車メーカーとして豊富な経験を生かしてタタ・モーターズが新たに乗用車部門に進出し、企業間競争が激しさを増すようになった。2001年以降、インドの自動車生産は2けた成長を遂げており、四輪車の生産台数は2003年に126万5000台と初めて100万台を突破し、2007年には232万7000台に達した。2008年には金融・経済危機の影響によって生産台数が一時的に225万5000台に低下したが、2009年には291万8000台へと力強い回復を示すようになった。現在、インドは小型車生産の国際拠点、さらには自動車部品の輸出国として、その地位を着々と固めつつある。また自動二輪の分野ではインドは中国に次ぐ世界第2位の地位にあり、2009年には、その生産台数は1051万3000台に及んだ。 また鉄鋼業の場合、経済自由化と対外開放の進展は、鉄鋼生産の拡大を刺激するとともに、生産性向上、品質改善に向けて大きな刺激を与えることになった。独立後、インド鉄鋼業の最大手は、公共部門のインド鉄鋼公社(SAIL)であったが、1990年代以降、鉄鋼生産拡大の主役を担ったのは民間部門である。大手鉄鋼メーカーのタタ・スチール以外にも、JSWスチール、エッサール・スチール、イスパット・インダストリーズ、ジンダル・スチール&パワーといった中堅鉄鋼メーカーが大きく台頭するようになった。粗鋼生産は1992年の1520万トンから2008年には5452万トンへと拡大し、世界第5位の鉄鋼生産国になっている。2009年時点で、各鉄鋼メーカーが新規製鉄所の建設のために州政府と取り交わした合意書は222件(2億7600万トン)に及んでおり、インドの鉄鋼生産能力は2011年ころには1億2000万トンに達することが期待されている。 [小島 眞] 拡大する中間層近年、インドでは一定の購買力をもった中間層が大きく台頭し、消費財市場の拡大に弾みを与えている。中間層を一義的にとらえることは必ずしも容易ではないが、インド応用経済研究協議会(NCAER)によれば、世帯年収20万~100万ルピー(2001価格)の所得階層である。こうした中間層は、家電や自動二輪は容易に購入でき、また自動車購入にも手が届く所得階層であり、かつては高所得世帯に該当していた所得階層である。実際、中間層の人口規模は1995年には2500万人、2001年には5800万人程度でしかなかったが、その後、2007年には1億2300万人、さらに2009年には1億5300万人に増加している。実際、インドの中間層は21世紀に入ってから、きわめて高いペースで増え続けている。2001年から2009年までの期間中、その年平均成長率は12.9%に及んでおり、世帯別シェアも5.7%から12.8%に拡大している。また新中間層(世帯年収9万~20万ルピー)の場合、世帯別シェアは21.9%から33.9%に増えている。2007年時点で、中間層の自動車所有世帯は、都市では40%以上、農村でも24%に及んでいる。また中間層のテレビ所有世帯は、都市では96%、農村では62%に及んでいる。 インド国内市場拡大にかかわる新たな動向として、とくに注目されるのは次の2点である。第一に、低コスト・モデルの活用が広がり、中間層のみならず、後続の新中間層(2009年時点で4億人強)も新たな有力な購買層として登場し、国内市場の裾野(すその)が確実に広がりつつあるということである。実際、携帯電話の場合、その加入件数は2004年3月の3369万件から、2010年3月末には5億8432万件に拡大しており、インドは中国について2番目に大きい携帯電話の市場になっている。第二に、インドでは購買力をもつ人々が必ずしも都市のみに集中しているのではなく、農村にも広く分布しているということである。2009年時点での中間層、新中間層に占める農村のシェアをみても、それぞれ33.4%、61.2%と推計されており、マーケットとしての農村の重要性はきわめて大きいものがある。 [小島 眞] 産業の担い手独立後、インドでは基幹産業の中枢を担うべく、新規設立ないしは民間企業の国有化を通じて多くの公企業が誕生し、経済の管制高地(中心的役割)を占めることが期待されてきた。1991年以降、公共部門拡大優先の原則が撤回されたことに伴い、インド経済のなかでの公企業の相対的地位は低下するようになったが、石炭、石油、電力、通信(固定電話)の分野では依然として公企業は支配的な地位を保っている。インドの売上高ベスト10の企業には、インド石油、バーラート石油、ヒンドゥスターン石油、インド・ステイト銀行(SBI)、石油天然ガス、インド鉄鋼公社の6公企業が含まれている。公企業は中央政府公企業と州営企業から構成される。2008年3月時点で、中央政府企業は242社存在し、その売上高はGDPの23%に相当するレベルにある。また州営企業の場合、実働中の州営企業は837社存在するが、その多くは慢性的赤字に陥っている。 インドでは独立以前からタタ(1868設立)やビルラ(1857設立)などの有力な老舗財閥が存在していたが、混合経済体制下では産業許認可制度、さらには「独占・制限的商慣行法」(1969)に基づいて、一定規模以上の民間企業、とりわけ財閥系企業の活動は厳しく抑圧されていた。1991年以降、上記の規制が解除され、民間部門の活動範囲が広がるなかで、既存の財閥に加えてリライアンス(1966設立)などの新興財閥が多数台頭し、インド経済拡大の牽引役として重要な役割を果たすようになった。リライアンスは石油化学事業を通じて1990年代以降に急成長した財閥であり、21世紀に入って以降、タタと並んでインドを代表する財閥に成長した。ちなみにインドの財閥は後継者問題で分裂するケースが多く、1990年代にビルラが複数のグループに分裂し、またリライアンスについても、創立者であるディルバイ・アンバニの死去に伴い、2人の息子の対立が表面化し、2005年には兄ムケシュ率いるリライアンス・グループ(石油化学、石油・ガス採掘、石油精製)と弟アニル率いるリライアンス・ADAグループ(通信・電力・金融)の二つに分割された。 上記の三大企業グループ以外にも、エッサール(鉄鋼・電力)、ラーセン&トウブロ(重機械)、ITC(タバコ・食品・ホテル・IT)、マヒンドラ(自動車・IT・金融)、アヴァンタ(旧タパール、パルプ・食品・電力)、バジャージ(二輪車・三輪車)、キルロスカ(機械・トラクター)、ヒーロー(二輪車)、ゴドレージ(機械・食品・日用品)、シュリラム(金融)、バールティ(通信・小売業)、JSW(鉄鋼・電力)など有力な企業グループが多数台頭し、しのぎを削る競争をしているのがインドの現状である。ちなみにタタの場合、2008年度の売上高はGDPの6.1%に相当する708億ドルに及んでおり、その64.7%は海外事業によるものである。同グループの活動はエンジニアリング、鉄鋼、電力、IT、ホテル、紅茶など幅広い分野に及んでいる。旗艦企業としてのタタ・スチール、タタ・モーターズ、タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)の3社の場合、グループ全体の売上高の76%(2008)を占めるとともに、それぞれ鉄鋼、自動車、ITの分野でインドを代表する最有力企業である。 [小島 眞] Infrastructureインド経済が高レベル経済成長を着実な拡大を続けていくうえで、そのかぎを握っているのがインフラ部門(道路、鉄道、空港、電力、通信、上下水道、灌漑、倉庫など)である。近年、民間部門の参入によって通信設備は急速に整備されつつあるが、大きな課題として残しているのが電力部門、それに鉄道、道路、港湾の物流部門である。道路は鉄道にかわってすでに輸送面での主役の座にあるが、総じてインドの道路事情は劣悪である。都市部では交通混雑が深刻さを増す一方、農村部では全天候型の道路が整備されていないため、雨期には外部との物流面で支障をきたす地域が少なくない。総額3兆ルピーをかける大規模な全国ハイウェー開発計画が進行中であり、その象徴的存在として注目されているのが、「黄金の四辺形」(デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルコタを結ぶ総延長距離5546キロメートル)、「東西・南北回廊」(東西・南北の両端を貫く総延長距離7300キロメートル)である。2010年6月末時点で、前者は99%、後者は71%の工事が完了しており、一部の箇所はBOT方式に基づいて、シンガポール、マレーシアなど外資を含めた民間部門が参入している。 インドの鉄道については、すでに飽和状態に達し、安全性や輸送能力の面で多くの問題を抱えているとの見方が支配的であったが、コンテナ輸送において民間参入が認められるなど、急速ピッチで効率性向上が図られるようになってきた。第十一次五か年計画中には、本邦技術活用条件(STEP。日本の技術、ノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて「顔の見える援助」を促進する目的で創設されたタイド円借款)方式に基づいて、デリー・ムンバイ、デリー・ハウラー(コルカタ)間で高速貨物専用鉄道の建設が着手される見込みである。インドの港湾についても、外国貿易に伴う物流コストが高くつき、産業全般の国際競争力を損ねているという見方が一般的であったが、中央政府管轄下の12の主要港、その他の港を含め、PPP(官民パートナーシップ)方式に基づいて、専用港建設、さらには港湾施設の増強や取扱処理能力の向上が図られている。また需要増大に対応できず、施設増強が急務とされている空港についても、バンガロール、ハイデラバードでは新空港が建設されるとともに、デリー、ムンバイ両空港ではPPP方式に基づく改良工事が行われた。 インフラ分野で改革が容易に進まず、工業成長に対する最大の制約要因として作用しているのが電力部門である。2009年時点で、ピーク時の電力不足は12.7%に達している。日常的に停電など、不安定な電力供給にみまわれ、そのため工場・事業所の多くは自家発電・UPS(無停電電源装置)の設置を余儀なくされている。また2008年時点で、各家計への電気の普及を示す電化率はいまだ60%(農村では45%)にとどまっている。電力不足解消という観点から、石炭火力に基づいた4000メガワット級の9件のウルトラメガ・パワー・プロジェクト(入札に基づいてすでに4件が決定)が予定されるとともに、2008年に原子力供給国グループの了承を経て米印民生用原子力協定が正式に成立したことに伴い、今後、原子力発電所の増設に弾みがつくことが予想される。留意されるべきことは、電力部門の主要事業体である州電力庁(SEB)が軒並み深刻な経営赤字に直面しており、そうした構造上の問題にメスを入れない限り、問題の本質的解決にならないという点である。SEB改革の最大の焦点は、配電ネットワークのオープンアクセスや配電部門の民営化を含む配電部門の改革にある。利用者負担の原則の徹底を図りつつ、SEBの配電部門改革を軌道に乗せることができるのか、大きな課題が横たわっている。 [小島 眞] 対外経済関係独立後、インドは長年にわたって先進国、国際機関からの大口の経済援助を受け入れる一方、自給色の強い保護主義的な対外政策が採用されてきたが、1991年以降、グローバリゼーションの時代に即した対外志向型の経済開発が目ざされるようになった。その結果、インドの輸出依存度(商品輸出/GDP)は1980年代には4.5%であったのが、1990年代には7.7%、さらに2007年には15.3%に上昇するに至った。また貿易相手先としては、長らくEU、アメリカ、旧ソ連、それに日本が上位を占めていた。1990年代以降、全方位外交を基調としつつも、ルックイースト政策が唱えられ、近年、ASEAN、中国、韓国との貿易が急速に拡大しており、また2010年よりインドASEAN・FTA(自由貿易)協定、インド韓国CEPA(包括的経済連携協定)が発効している。 2008年時点で、インドの商品輸出は1853億ドルに及んでおり、その品目別構成をみると、宝石・宝飾品、石油製品がそれぞれ全体の15.1%、14.9%を占め、以下、輸送機器(6.0%)、アパレル(5.9%)、機械類・器具(5.9%)、医薬品・化学品(4.7%)となっている。また商品輸入は3037億ドルに及び、原油・石油製品がトップで全体の30.1%を占め、以下、一般機械(8.7%)、エレクトロニクス製品(7.7%)、金銀(7.2%)、真珠・貴石・貴金属(5.5%)、輸送機器(4.4%)となっている。インドの主要貿易相手国は、輸出先ではアラブ首長国連邦(UAE)がトップで13.2%を占め、以下、アメリカ(11.4%)、中国(5.0%)、シンガポール(4.6%)、香港(ホンコン)(3.6%)となっており、輸入先では中国がトップで10.7%を占め、以下、UAE(7.8%)、サウジアラビア(6.6%)、アメリカ(6.1%)、イラン(4.1%)となっている。 インドの貿易収支(商品貿易)は慢性的に大幅な赤字を計上している一方、貿易外収支(サービス、投資所得、経常移転)は顕著な黒字を計上しており、経常収支全体の赤字幅がかなり軽減されている。世界輸出におけるインドの存在感が強まっているのは、商品輸出よりもサービス輸出のほうである。1995年当時、世界輸出に占めるインドのシェアは商品輸出、サービス輸出のいずれとも0.6%程度であったのが、2007年時点で、商品輸出では1.1%、サービス輸出では2.6%に拡大している。2008年、サービス輸出(ソフトウェア・サービス、ビジネス・サービス、運輸、旅行、金融サービスなど)は1020億ドルに及んでおり、その半分近くを占めているのがソフトウェア・サービスである。またインド人が海外で多数活躍していることは、在外インド人による国内送金、およびNRI(非居住インド人)口座への預金などで、多額な経常移転収入をもたらしており、2008年には435億ドルに及んでいる。2009年時点で、アメリカ、中東など世界各国に約2500万人の在外インド人が存在しているといわれる。 外国投資に目を転じると、従来、投資先としてインドはそれほど注目される存在ではなかったが、巨大な国内市場、生産拠点としての重要性が高まるなかで、新たな展開がみられるようになった。対内直接投資は2002年の50億ドルから2006年に236億ドル、さらに2007年には368億ドルに拡大し、リーマン・ショックに伴う世界同時不況の影響を受けた2008年の場合でも363億ドルを記録した。またポートフォリオ投資は2002年の10億ドルから2003年には114億ドル、さらに2007年には236億ドルに拡大した。2008年には世界同時不況の影響を受け、ポートフォリオ投資の海外からの引揚げがみられたが、2009年には回復傾向を示している。 対内直接投資と並んで注目されるのは、対外直接投資の拡大である。インド企業の活発なグローバル事業展開を反映して、インドの対外直接投資は2004年には18億ドルであったのが、2007年には135億ドル、さらに2008年に179億ドルへと拡大した。インド企業の海外進出は、とりわけIT産業、鉄鋼業、それにエネルギーの分野において顕著である。実際、タタ・グループはグローバル事業の拡大を成長戦略の重要な柱の一つに位置づけ、2000年のタタ・ティーによるイギリス紅茶メーカーのテトリー買収を手始めとして、2007年にはタタ・スチールによる129億ドルでのヨーロッパ第2位のイギリス・オランダ鉄鋼メーカーのコーラスの買収、さらに2008年にはタタ・モーターズによる23億ドルでのイギリス高級車ブランドのジャガー、ランドローバーの買収を手がけ、インド企業のグローバル展開を世界に強く印象づけるできごととなった。 [小島 眞] society社会構造の全般的特徴インドの社会を彩る大きな特徴は、その構成要素の多様さということである。それを宗教、カースト、民族の三つの面から考えることができる。 [山口博一] religionインド人の約75%はヒンドゥー教徒である(指定部族は除く)。パキスタンがまだインドから分かれていなかった植民地時代には、その比率はこれほど高くはなかった。ムスリム(イスラム教徒)が全体の25%を占めていたからである。1870年代以後に発展したインドの民族運動は、ヒンドゥーの中産階級をおもな担い手としていた。マハトマ・ガンディーに代表されるその指導者たちは、従来のヒンドゥー教の教義をそのまま信奉したのではなく、これを解釈し直して新しい時代の要求に合致させようとした。しかしそれはムスリムや不可触民の反発を招いた。ムスリムは人口の12%で、絶対数ではインドネシア、パキスタン、バングラデシュに次ぐ世界第4位である。独立のときに旧インドのムスリムの約3分の2が東西両パキスタンに属することになったが、約3分の1はインドに残された。つまり、植民地インドの両端のムスリム多数派地域をパキスタンとして独立させたのである。1971年には東パキスタンが独立してバングラデシュとなった。 これらのことは、宗教と民族を同一視しそれによって国家をつくろうとする試みが無理であったことを示している。パキスタン(とくに東パキスタン)に残されたヒンドゥーと、インドに残されたムスリムはともすれば疎んぜられ、スケープゴートにされることが多い。ヒンドゥーとムスリムに次いで多いのは人口の8%を占める指定部族である。これは、奥地の丘陵地帯などに住む人々を政府がこのように認定したものだが、宗教的にはヒンドゥー化が進んでおり、経済生活のうえでもその他のインド社会とあまり区別がなくなっている。このほかにキリスト教徒、シク教徒、ジャイナ教徒などがいる。仏教徒は1956年から不可触民の改宗者が増えている。 最近の注目すべき動きはヒンドゥー至上主義勢力の台頭である。これはインドの当面する困難をムスリムの存在のせいにし、インドをヒンドゥー的に純化することを要求するもので、多様性に富む社会に単一の尺度をもち込み、宗派間に緊張をもたらし、上位カーストの立場を強化する意味をもっている。1992年12月6日にこの勢力はウッタル・プラデシュ州アヨーディヤーにあるイスラム寺院の破壊を強行した。 [山口博一] casteバラモン(ブラーマン)、クシャトリア、バイシャ、シュードラの四つに不可触民を加えた五つがカーストであると普通に考えられている。これは間違いではないが、カーストの理念を示しているだけであり、現実のカーストははるかに複雑で、サブカーストがほとんど無数に存在する。人々の接触と結婚の範囲を決めているのはサブカーストであり、職業とサブカーストの結び付きもまだ強く残っている。農村では地主あるいは有力な農民のサブカーストを中心として生産活動が営まれている。バラモンなど上位のサブカーストは一般に肉食を忌み嫌い、肉体労働をしないなど特定の生活様式をもっている。そこでそれ以外のサブカーストの人々が集団で肉食をやめるなど上位カーストの生活様式を採用し、そのうえで自分たちは上位のカーストに属すると主張するということが始終起こっている。つまり個々人にとっては、その所属するサブカーストは生涯変えることはできないが、サブカーストが集団として上位あるいは下位に移動することは可能であった。最近は中位の有力な農民のサブカーストが上位カーストの行動様式を模倣するのではなく、逆に自分たちはバラモンなどによって低い地位に追いやられていたとして、指定カースト(SC)や指定部族(ST)並みの保護を要求する動きもみられる。 憲法では特定の人々を不可触民として差別することは処罰の対象であるとされている。つまりカーストの廃止は規定されてないが、不可触民は公式には存在しないことになっている。しかし彼らへの偏見と差別はまだ根強くみられる。政府は、人口の約16%にあたる範囲の人々を、従来不可触民として差別されてきたとして指定カーストに認定し、指定部族と同じくさまざまな保護を与えている。しかしこれはヒンドゥーとシクだけについてであって、他の宗教に属する不可触民を含んでいない。カーストは理念上はヒンドゥーだけのものであるが、多かれ少なかれほかの宗教にも類似のものがみられる。 指定カーストと指定部族には、議会選挙、公務員採用、公立学校入学などで一定の割合が留保されているが、中間諸カーストからも同様の優先措置を求める声が高まり、1990年にV・P・シン政権によってそのための方策がとられた。指定カースト、指定部族以外のいわゆる「その他の後進諸階級(OBC)」への保護である。ヒンドゥー至上主義の動きはこれへの対抗という面をもっている。OBCは人口の半数を占める大勢力であるが、その内部は一様ではなく、上位カーストに対立する面をもつ一方で、下位カースト、SC、STを抑圧する面ももっている。 1997年7月に10人目の大統領に副大統領であったナーラーヤナンが選出された。彼は南インドの指定カースト出身である。 [山口博一] 民族・言語インドの各州は1950年代からは言語別に構成されそれぞれの公用語をもっている。ヒンディー語だけは六つの州で用いられている。言語が違うそれぞれの集団を民族と考えることができる。つまりインドは多民族社会、多民族国家である。 28の州間の人口規模の差は非常に大きく、1億を超えるウッタル・プラデシュ州をはじめ、1000万人以上の州が18ある反面で、200万人未満が5州ある(2001)。憲法には、1000万人以上の州の公用語となっている11の言語、すなわちヒンディー語、マラーティー語、ベンガル語、テルグ語、タミル語、カンナダ語、グジャラート語、オーリヤー語、マラヤーラム語、アッサム語、パンジャーブ語に、広くムスリムの間で用いられるウルドゥー語、ジャム・カシミール州の公用語カシミール語、現在パキスタンに属するシンド州からのヒンドゥー難民が用いるシンド語、古典語のサンスクリット語を加えた15語の尊重がうたわれている。1992年の第七十一次憲法改正によりあらたにコンカン語、マニプル語、ネパール語が付け加えられた。インドの紙幣にはマニプル語とシンド語を除くこれらのすべての言語および英語の計17語で金額が記されている。州が言語別に構成されているといっても、州の区画と住民の言語的な区分はかならずしも一致しないので、各州はそれぞれ少数言語集団をいくつも含み、それぞれが多かれ少なかれ多民族的構成になっている。したがって、州の人口とその州の公用語である言語の実際の話者人口とは一致しない。ヒンディー語は連邦の公用語であるが、これを公用語とする六つの州(ヒンディー・ベルトとよばれる)の人口の比率は42%、実際の話者人口は39%前後である。 インドは一国でヨーロッパ並みの広さをもっているから、主要な言語が18あるといっても不思議ではない。それにサンスクリットの影響が強いから、多くの言語の間にはある程度の共通性がある。しかし各民族がそれぞれの言語に強い誇りをもっているので、中央政府がヒンディー語を単に連邦の公用語から、より国語に近づけようとする方向に動くと、かならず反発が起きてきた。当分は英語が共通語として重要な役割を果たし続けると思われる。他方で各州が言語的な閉鎖状況に陥ると、民族間の通婚や州間の人口移動がそれだけむずかしくなる。 インド社会を構成する要素はこのように複雑であるが、その中身は政治的、経済的な動きを反映して変化しつつあるのであり、これを固定的なものとみてはならない。このような複雑さをもつインドの社会が一つにまとまりうるものであるかどうかは大きな問題であるが、政治と宗教の分離、諸民族と諸言語の平等、政治・経済・社会の各分野にわたる民主的発展によって可能になると思われるし、インド国内でも多くの人々がそれを望んでいる。 [山口博一] National lifeインドは10年ごとに国勢調査を行っている。1991年のそれによると人口は8億4393万で、前回の1981年に比べて23%、1億6000万人増えている(2001年には10億2701万5247、2007年推計では11億6901万)。増加の絶対数は非常に大きい。しかし増加の年率は1990年代に入って2%を切るようになり、2000年代前半(2000~2006)では1.6まで落ちている。人口の動態からは、今後に人口増緩和の期待をかけられる面がでてきている。乳児死亡率は2006年には57まで低下し、これを反映して同年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に何人の子供を生むかの予測指数)も2.5に下がっている。 人口動態では州間の差が大きい。乳児死亡率はケララが最低で17であるのに対し、最大の人口をもつウッタル・プラデシュ州では98、最高のオリッサでは120であった。 死亡率の低下は天然痘の絶滅(1977年4月)など保健衛生状態の改善によるところが大きい。しかし平均寿命はまだ60歳に達したばかりで課題も多い。2006年の平均寿命は男63歳、女66歳である。1986年に当時の首相ラジブが発表した20項目の政策(20ポイント政策)にも、清潔な飲料水の確保と、ハンセン病、結核、マラリア、甲状腺腫(こうじょうせんしゅ)、視力喪失その他の主要な病気の克服があげられていた。最近はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者の増加も指摘されている。 これだけの人口をまかなうための食糧(穀物および豆類)の生産は1980年代末からモンスーン(季節風)に恵まれて順調に伸びている。しかし人口増加が続いた場合の不安は残るうえ、1人当りの消費量にも目だった増加はみられない。 より重要な課題は雇用である。1980年代だけをみても、14歳までの人口比は4%減少し、その分だけ15~59歳人口比が増加した。しかし、これに見合うだけの雇用の創出がなされたとは信じがたい。1976~1991年の15年間をとると、新規雇用の大部分は公共部門(政府部門)でなされている。この傾向は長続きしないであろうし、好ましいことでもない。同時に農村でも農業への基礎的投資と雇用拡大とを結びつけることが望まれる。 識字率は1981年の36%から1995年の52%、2007年の66%へと上昇したが、男子が76.9%であるのに対し女子は54.5%で、その差が縮まっていない。識字率は州間の差が大きくビハール、マディヤ・プラデシュ、ラージャスターン、ウッタル・プラデシュなどのヒンディー・ベルトの大きな州で低い。頭文字をとって「BIMARU(ビマル)」とよばれるこの4州はいろいろな意味で問題が多く、合計特殊出生率が高く、女性の識字率が極端に低いのもこの4州である。 男女の差に関して一つ奇妙なことは、国勢調査のたびに男子人口に対する女子人口の比率が減少していることである。これは女子を意図的に少なく数えるからだという説もある。 国連の人間開発指標でインドは世界のなかでかなり下位に位置づけられている。世界の貧困層の3分の1近くを抱えているといわれ、1991年からの経済改革もその効果を膨大な人口のうえに及ぼすに至っていない。その意味で大きな社会経済格差を残したままの自由化には問題が多い。土地の劣化など環境の悪化も進んでいる。BIMARU諸州などの現状は指定カーストや指定部族の問題を含めて、カーストを基盤とする身分制度的な状況の存続をうかがわせる。その反面で経済の活性化と絡み合って、インド人によるNGO(非政府組織)活動が目だつようになっている。 都市人口と農村人口の比は1990年代なかばで27対73であった。100万人以上の都市が1981年の12に対し1991年の国勢調査では23あり、都市化の傾向が早まっていることを示した。しかも1981年から1991年のこれら23都市の人口増加率は36.5%に達し、予想を上回った。10万人以上の都市は約300あったが、そのなかには10年間で人口が2倍以上となった都市も少なくない。2001年には人口100万人以上の都市は35を数えるようになった。多くの都市が過剰人口を抱え、なかばスラム的な様子をみせている。ムンバイ(ボンベイ)、コルカタ(カルカッタ)、デリー、チェンナイ(マドラス)の四大都市を通常メトロポリスといっている。 [山口博一] educationインドの学校制度は、大学を別にすれば、5年の初等教育、5年の前期中等教育、2年の後期中等教育となっている。最初の8年間が義務教育で、入学者は増加しているが、強制就学ではなく、登校しなくなる児童も多い。しかしこの12年間をあわせて「10プラス2」といわれるようになったのは、一定の年数の教育が必要であるという考えに基づくものである。 そのあとの高等教育機関はカレッジとユニバーシティである。カレッジの数は1950年の542から急増して8000を超えている。その大部分はそれぞれユニバーシティの管轄下にある。前者が学部教育を行い、後者が大学院教育を受け持つ関係にあるといってよい。ユニバーシティは222ある。独立後の就学率と就学者数の増加は上級の学校になるほど大きく、カレッジの場合にもっとも顕著である。植民地時代の教育の欠陥がこのようにして是正されているのである。しかし義務教育も十分に普及していない状況では、このこと自体が格差拡大の一面となりかねない。また、カレッジやユニバーシティを卒業しても適当な職が得られない者が非常に多い。これは、経済発展の速度が遅いためもあるが、同時に高等教育が文科に偏っていて、当面インドでもっとも必要とされる中小企業や農村での働き手の養成に適していないことも一因である。 [山口博一] 出版とマスコミインドは出版活動が盛んな国で、毎年の書籍の刊行点数も多い。文学作品はそれぞれの言語で書かれることが多いが、学術書は主として英語で書かれている。これは、全国の高等教育機関で教科書や参考書として用いられるには、英語で書かれていることが望ましいし、国際的な流通も保証されるからである。 インドでは日刊紙2130(2006)をはじめ多くの新聞が発行されている。日刊紙を言語別にみると、ヒンディー紙がもっとも多く、ついでウルドゥー紙、タミル紙、英語紙の順となっている。日刊紙の発行部数の合計は8886万3000部(2006)で、約12人につき1部の割合である。有力な新聞のなかには民間の財閥の所有になるものが多い。 新聞の発行や書籍の出版は都市の高等教育を受けた住民をおもな対象としている。これに対しラジオあるいはテレビは識字を前提にしないため、より普及する可能性をもっている。これらはいずれも国営で、テレビはDDI(Doordarshan India)、ラジオはAIR(All India Radio)が、独占的に運営している。中央政府の情報放送省が管轄しているが、1997年9月、DDI、AIRを政府から切り離して、独立の放送機関とするための「インド放送協会法」が発効した。テレビは人口の85%が住む地域をカバーしている。しかし、DDIの調査によると、1998年には6500万世帯にテレビがあり、テレビを見ることのできる人は2億9600万人であった。テレビのない家庭が圧倒的に多かった。1990年代に入ってケーブルテレビもスタートした。ケーブルテレビ事業者数は約6万、1998年末で加入世帯数は2160万であった。2006年のテレビ保有世帯数は8807万、ケーブルテレビ加入世帯数は6800万となっている。 [山口博一] cultureインド文化の特質インドの自然が寒冷と猛暑、乾燥と湿潤の両極端をあわせもった多様性を示すと同様に、インド文化にもさまざまなレベルにおける多様性がみてとれる。それは生態系に見合った生活文化の多様性とも対応するが、端的にいって、車で1時間も行くとことばが異なるという言語や民族文化の圧倒的な多様性にもみてとることができる。しばしば人は、インド国民としての意識よりも、自らの属する母語集団ないしは民族集団に強い帰属意識をもつが、各集団がそれぞれ数千、数百年の独自の歴史をもつことを考えれば、それはあまりに当然のことといえよう。しかも東西ヨーロッパをあわせたに等しい広大なインド亜大陸の広がりを考慮するとき、そこに単一の「インド文化」や「インド人の国民性、民族性」を求めることは至難である。 しかしインドの人々は、自らのよりどころたる各地方ごとの自民族文化に固執する一方で、北方の二辺を山に囲まれ、南方の二辺を海によって限定されたこの広大な大地を、一つの「母なるインド」(バーラト・マーター)として古くから意識してきた。いかに広大ではあれ、この巨大な菱(ひし)形をなす文化地理的単位は、るつぼのように、さまざまに異質な文化を受容しつつ、独自の文化的枠組みを醸成、確立していった。西方からは古くは先史時代の先進農耕・牧畜文化、抽象的な思考を特徴とするアーリア文化、さらにはグレコ・ローマン、ペルシア、中央アジア、イスラムなどの諸文化、より近年はイギリスをはじめとするヨーロッパ文化を次々と受け入れ、また東方からはチベットや東南アジア北西山地などからの文化要素をも受容しつつ、インド独自の文化的枠組みは、崩れるどころか、ますますそのしなやかな構造を複雑にしつつ、内容を豊富にし、しかもインド的な発展を新たに遂げていったのである。 その際、インドの枠組みにあわぬものは、結局は受容されずに終わるか、もしくは原型をとどめぬほどにインド化した形においてのみ、そしゃくされた。インドはいかなる異質の文化にも積極的な受容の態度をとった一方、その枠組みのもつ同化力はきわめて強靭(きょうじん)である。ことにインドでは、衣食住や思想、芸術などのうえで、異種の文化要素をそのままの形で共存させることをほとんど許すことがない。音楽を例にとれば、インドの音階にそぐわないピアノのような鍵盤(けんばん)楽器はかならずしも定着せず、かえって自在に音をつくれるバイオリンがインド楽曲の演奏用に受け入れられた。女性たちがサリーに固執し、また料理はいわゆる「カリー」に限定されていることも、よく知られている事実である。インド文化の特質の一つによく「寛容性」があげられるが、実はそのオープンな構造は、かならずしもすべてをそのまま受容するというよりも、自らの枠組みにあわせたうえで積極的にそしゃくするというその強靭性にこそ特徴があるといえる。 またこのしなやかな構造は、外からの異文化に対してのみならず、本来インドがそのうちにあわせもった多種の文化諸類型に対してもその力を発揮する。すなわちそれは、一見両極端にみえるような事象をも、同じ一つのことの両局面とみて許容するからである。たとえば、不殺生、非暴力(アヒンサー)はインドの宗教、思想を通じてよく強調される特徴であるが、一方ではヒンドゥー教シャクティ派寺院などにみられるように、祭時には日に数十頭のヤギが首をはねられ、かつては人身御供(ひとみごくう)まで行われることがあった。無私無欲、徹底した苦行すらが強調される一方では、『カーマスートラ』に典型的にみられるように、徹底した愛欲の追求が是とされた。高度に抽象的な哲学教理は現世利益を願う呪術(じゅじゅつ)的儀礼と共存し、現世は幻であると同時に真であり、色と空、動と静なども結局は不二なる存在としてとらえられることが多かった。 このようにインドでは、善悪、光陰、正邪のような明確な二元的対比論は概して退けられた。光あっての陰であり、創造あっての死、男あっての女、というように、両者は相補的な関係にあるか、一つのものの両面にすぎないものと考えられ、多様は一元へと収斂(しゅうれん)した。ヒンドゥー教が一元的多神教とよばれるのもこのゆえんである。そしてかかる思潮は、生と死の輪廻(りんね)観、永劫(えいごう)の時間観念、浄・不浄観などとともに、宗教や哲学のみならず、社会、文化、衣食住などの生活のあらゆる局面においても意識され、インド独自の風習を形成しているのをみてとることができる。いわゆるカースト制の原理も、食事慣習、衣服の着用法、家屋敷の配置なども、すべてがこれらの観念によって分かちがたく、一つの生活文化を渾然(こんぜん)と形成している。芸術においても同様であり、かならずしもそれは、文芸、美術、芸能などに、もしくは彫刻、絵画、建築、あるいは音楽、舞踊、演劇などに分かちがたい。ただし一方では、これら一つ一つのジャンルにおける極端なまで微細にわたる分類、細分を行うのもインド文化の特色であるが、それもこの大きな枠組みあってのことであることを忘れてはならない。 [Masaaki Konishi] Relations with Japan明治以降の日印関係を文化交流に重点を置いて振り返る場合に、大まかにいって第二次世界大戦以前とそれ以後との2段階に区分しておくのが重要である。 [中村平治] 第二次世界大戦前の日印関係明治期から太平洋戦争の終わる1945年(昭和20)までは、日本は主として経済面で英領インドから綿花、鉄鉱石を輸入してきた。とくに綿花輸入は1893年(明治26)にボンベイ航路が開設されてから急上昇し、1930年代末、太平洋戦争が始まるまで続けられた。文化交流の面ではベンガルの民族的詩人でノーベル文学賞を得たラビンドラナート・タゴールが来日し、大正末と昭和初期の右傾化が進む日本の思想・文化界に衝撃を与えた。 そのタゴールは日中戦争の開始とともに日本の「知識人」と絶交するが、その深い意味を受け止めるべき条件は、当時の日本の政界やアカデミズム、言論界には欠落していた。「アジアの指導者である日本」といった軍国主義日本と、植民地的な地位からの脱却を目ざすインドとの間に対話の場は存在しなかった。太平洋戦争期、日本のインド侵略が目前に迫った1943年(昭和18)、インドの風俗・資源の紹介を中心に50冊を超える書物が刊行されたが、インドの民衆が提起する本源的な要求に目を向けていないという点で、すべて紙屑(くず)同然のものでしかなかった。その意味では、文化交流以前の段階に日印関係は置かれ、わずかに矢内原忠雄(やないはらただお)『帝国主義下の印度』(1937)が科学的なインド認識の礎石となっているにすぎない。 [中村平治] 第二次世界大戦後の日印関係太平洋戦争での日本の敗北と新生インドの誕生とは、日印関係をまったく新しい段階に導いた。経済関係では鉄鉱石輸入が主軸となり、それは日本の高度経済成長を下から支えた。他方で文化・学術面での交流は飛躍的な発展をみせるに至った。 とくにインドを含めたアジア・アフリカ諸国の独立と革命は、日本の文化・学術のあり方に対しても少なからぬ影響を及ぼした。それは、ヨーロッパ中心主義の日本の文化・学術に対して、内容的にも体制的にも一種の自己批判を迫るものであり、アジア諸国への停滞的な視点の克服を求めるものであった。インドに即していえば、在来の文献学的インド研究、とくに印度学、仏教学の研究分野に加えて、広く人類・考古学、歴史学、経済学の分野からするインド研究の必要性が強調され、事実、その方向での研究蓄積が1960年代以降において日本でなされつつある。 こうした研究蓄積の背景には、日印双方による学術・文化交流の努力があった事実を見逃すわけにはいかない。すなわち、独立して数年後の1951年からインド政府留学生制度が導入され、日本の研究者はインドで直接学習する条件を確保するに至った。この制度は今日まで継続されているが、国家建設途上のインド政府の払った努力は高く評価されよう。日本側は1950年代末から、インド人留学生を迎える体制を組み、それが続行されて今日に及んでいる。こうした状況に加えて、日印間には学術交流も盛んであり、歴史・考古学、地理学、経済学の諸分野からする学術調査団がインドに派遣され、その業績はインドの学界でも注目されている。これらの調査活動は、インド側の当局者、とくに大学・研究所などの協力なしには不可能の事柄であり、その面で、じかにインド側研究者との交流も大きく発展する時期にきている。 1970年代の後半以後、タゴールの著作集の刊行を含め、インド音楽、舞踊、映画などの諸領域での交流は一段とその幅を拡大し、厚みを増していることも付言しなければならない。とくに日本の一部には、こうした面で積極的に交流を促進する努力があり、欧米一辺倒の思想・文化状況のなかで注目すべき流れを準備しつつあるといえよう。 経済関係では、1986年以降日本は最大の援助国である(以下イギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、デンマークなど)。1997年までの累計でみると、有償援助が1兆8772億円、無償援助は699億円である。1998年以降は、1998年5月のインド核実験の実施を受け、緊急、人道などを除く新規案件に対する無償資金協力と、新規円借款を停止した。1998年の援助実績は、有償が115億3700万円、無償が3億9800万円であった。2008年は有償2360億4700万円、無償4億2400万円となっている。 日本にとっては、インドとのバランスのとれた多面的な交流の促進が望まれている。 [中村平治] 『『文化誌世界の国5 インド・南アジア諸国』(1973・講談社)』 ▽ 『織田武雄編『世界地理4 南アジア』(1978・朝倉書店)』 ▽ 『石田寛・中山晴美訳『世界の教科書シリーズ11 インド その国土と人々』(1978・帝国書院)』 ▽ 『中村平治著『南アジア現代史 Ⅰ』(1977・山川出版社)』 ▽ 『大内穂編『インド憲法の基本問題』(1978・アジア経済研究所)』 ▽ 『大内穂編『危機管理国家体制――非常事態下のインド』(1980・アジア経済研究所)』 ▽ 『中村平治著『現代インド政治史研究』(1981・東京大学出版会)』 ▽ 『山口博一編『現代インド政治経済論』(1982・アジア経済研究所)』 ▽ 『佐藤宏ほか編『もっと知りたいインドⅠ』(1989・弘文堂)』 ▽ 『近藤則夫編『現代南アジアの国際関係』(1997・アジア経済研究所)』 ▽ 『堀本武功著『インド現代政治史』(1997・刀水書房)』 ▽ 『近藤則夫編『インド民主主義体制のゆくえ』(2009・アジア経済研究所)』 ▽ 『佐藤宏編『南アジア――経済』(1991・アジア経済研究所)』 ▽ 『伊藤正二・絵所秀紀著『立ち上るインド経済』(1995・日本経済新聞社)』 ▽ 『小島眞著『インド経済がアジアを変える』(1995・PHP研究所)』 ▽ 『小島眞著『インドのソフトウェア産業』(2004・東洋経済新報社)』 ▽ 『小島眞著『タタ財閥』(2008・東洋経済新報社)』 ▽ 『絵所秀紀著『離陸したインド経済』(2008・ミネルヴァ書房)』 ▽ 『三上喜貴著『インドの科学者 頭脳大国への道』(2009・岩波書店)』 ▽ 『辛島昇・奈良康明著『生活の世界歴史5 インドの顔』(1975・河出書房新社)』 ▽ 『山崎元一著『インド社会と新仏教』(1979・刀水書房)』 ▽ 『山折哲雄著『インド・人間』(1980・平河出版社)』 ▽ 『山際素男著『不可触民の道』(1982・三一書房)』 ▽ 『山口博一編『現代インド政治経済論』(1982・アジア経済研究所)』 ▽ 『臼田雅之ほか編『もっと知りたいインドⅡ』(1989・弘文堂)』 ▽ 『佐藤正哲・山崎元一編著『歴史・思想・構造』(1994・明石書店)』 ▽ 『小谷汪之編著『西欧近代との出会い』(1994・明石書店)』 ▽ 『内藤雅雄編著『解放の思想と運動』(1994・明石書店)』 ▽ 『柳沢悠編著『暮らしと経済』(1995・明石書店)』 ▽ 『押川文子編著『フィールドからの現状報告』(1995・明石書店)』 ▽ 『押川文子編著『南アジアの社会変容と女性』(1997・アジア経済研究所)』 ▽ 『田辺明生著『カーストと平等性インド社会の歴史人類学』(2010・東京大学出版会)』 ▽ 『辛島昇編『インド入門』(1977・東京大学出版会)』 ▽ 『小西正捷著『多様のインド世界』(1980・三省堂)』 ▽ 『奈良康明・山折哲雄監修『神と仏の大地インド』(1982・佼成出版社)』 ▽ 『辛島昇編『ドラヴィダの世界――インド入門2』(1994・東京大学出版会)』 ▽ 『小西正捷編『アジア読本・インド』(1997・河出書房新社)』 ▽ 『大形孝平編『日本とインド』(1978・三省堂)』 ▽ 『大形孝平編『日中戦争とインド医療使節団』(1982・三省堂)』 [参照項目] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[補完資料] |"> India flag ©Shogakukan Illustration/Shogakukan Creative "> インド位置図 ©Shogakukan "> インドの地形 インドとパキスタンの国境に広がる砂漠。降水量が多く、農村風景も見られる。近くのワジ(涸れ川)から砂丘が始まっている。インド ラージャスターン州ジョドプル近郊©赤木祥彦"> タール砂漠(大インド砂漠) インド西部、マハラシュトラ州の州都。17世紀末からイギリスのインド経営における西の根拠地として発展し、独立後も順調に経済的成長を遂げてきた。写真はバック湾から望む高層ビル群。インド ムンバイ©Shogakukan "> ムンバイ市街 一帯に残る総数100を超える石窟寺院のなかの代表的寺院。多くがグプタ朝期以後のものであるが、第3窟はそれよりも前のものである。インド ムンバイ近郊©Shogakukan "> カーンヘリー石窟第3窟 ムンバイ湾、エレファンタ島にあるヒンドゥー教の石窟寺院。七つの石窟があるが、第1窟以外は未完成である。世界文化遺産「エレファンタ石窟群」(インド・1987年登録) インド エレファンタ島©Shogakukan "> エレファンタの石窟寺院 全石窟中で建築的にもっとも興味深い第16窟の「カイラーサナータ」。岩山から巨大な岩塊を切り離して彫刻的につくりだした単一石の建築。世界文化遺産「エローラ石窟群」(インド・1983年登録) インド オーランガーバード©Shogakukan "> エローラの石窟寺院 ムガル朝第5代シャー・ジャハーンが、若くして亡くなった愛妃ムムターズ・マハルのために建てた廟墓。22年の歳月をかけて1654年に完成。インド・イスラム建築の白眉で、「大理石の夢幻」といわれた。中央ドームの高さ58m。世界文化遺産「タージ・マハル」(インド・1983年登録) インド アグラ郊外©Shogakukan "> Taj Mahal ヒンドゥー教徒たちの聖地ワーラーナシのガンジス川沿い、5kmにわたって連なるガート(沐浴場)。信徒は聖河ガンジスで身を清め、太陽に向かって祈り、潔斎や消罪の功徳を願う。インド ワーラーナシ©Shogakukan "> ガンジス川での沐浴 Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
総論インドは1947年8月15日、2世紀に及んだイギリスの植民地支配から独立した立憲民主共和国である。バーラトBhāratともよぶ。南アジア地域の中心を占め、総面積328万7263平方キロメートル、日本の9倍弱の広大な国土をもち、11億1773万4000(2006推計)と、中国に次ぐ世界第二の人口を擁する。独立後優れた指導者ネルーのもとに、非同盟主義諸国のリーダーとして、国際社会で重要な役割を演じてきた。国名の「インド」は、かつてギリシア人が、インダス川流域地方をインドスIndosとよんだことに由来する。紀元前2000年ごろより波状的にインダス川流域に進出したアーリア人(アーリアン)は、この地方をシンドゥーSindhuとよんだ。これをイラン地方でヒンドゥーHinduとよび、さらにギリシア語ではインドスになったものとされる。またバーラトは、前6世紀ごろのバラモン教聖典に記された「南に開けた国」(バーラトワルサBhāratvarsa)に由来し、太古にインドを統一したとされる理想的聖王の名である。 10億人を超える人々が生活を営む国土は、北に世界の屋根ヒマラヤ山脈を、東にベンガル湾、西にアラビア海を従え、インド洋に逆三角形の型で突き出した本土と、ミャンマーの南海上に浮かぶアンダマン・ニコバル諸島、および本土南端の西岸沖合いのラクシャドウィープ諸島で構成される。本土は北緯8度4分から37度6分、東経68度7分から97度25分の北半球に広がる。国土の最長距離は、南北3214キロメートル、東西2933キロメートルもあり、国境線は1万5200キロメートル、海岸線は6100キロメートルにも及ぶ。国土の北半のうち、東はミャンマーおよび中国と国境を接し、バングラデシュを包み込む。北はネパールを挟み中国と接し、西はパキスタンと国境を接する。このように多くの国と接する国境線の平和的維持は、国民経済の発展に深くかかわっており、政府と国民にとって大きな課題となっている。 現在の国土領域をもつ国家は、1947年インドの独立によってインド亜大陸に初めて出現したものであるが、この領域を舞台に繰り広げられた歴史は、世界の四大古代文明の一つ、インダス文明を起源とする。前2000年ごろより、カイバー峠を越えてインダス川流域へ進出したアーリア人は、先住民のインダス文明と遭遇し、これを滅ぼした。その後、ガンジス川流域やデカン高原へと生活圏を広げていった。この過程は、遊牧民アーリア人が先住の定着農耕民を侵略し、融合する形となり、これを正統化するための哲学としてバラモン教が成立した。これに反発した先住の農耕民は、自らの土着的哲学を体系化し、仏教やジャイナ教を誕生させた。しかし、長い歴史のなかで両者の思想は融合・統合され、インド文化の形成をみたのである。7世紀初め、砂漠の国に生まれたイスラム教はまたたくまに勢力圏を西アジアに広げ、8世紀には諸王朝が豊饒(ほうじょう)なインド亜大陸に幾多の遠征軍を送り、略奪を繰り返した。ついに13世紀初頭に、攻撃的イスラム教徒であるゴール朝の武将クトゥブッディーン・アイバクが、亜大陸の戦略上要衝の地デリーにイスラム勢力の王朝を確立した。これ以降、1858年にムガル王朝(ムガル帝国)がイギリスによって滅ぼされるまで、亜大陸はイスラム教徒諸王朝の興亡の場となり、その間は、イスラム文化とヒンドゥー文化の葛藤(かっとう)の時代であった。他方、17世紀以降、イギリスの東インド会社によるインドの植民地化は拡大の一途をたどり、1857~1858年のインドの大反乱(セポイの反乱)後は、イギリス直轄植民地とされた。そして、1947年に独立を迎えるまで、植民地支配に苦しめられながらも、地方行政制度、教育制度、および鉄道、道路網などの整備が積極的に進められていった。インド史はけっして栄光に彩られたものではなく、アーリア人の進出を皮切りに、異民族の波状的侵攻による文化の再編成の歴史であった。こうして、それぞれの時代を生きた民衆は、異文化の軋轢(あつれき)に苦しみ、そのなかから新しい哲学や宗教を創造してきたといえる。この世界でもっとも長い文明史のなかで、現代のインドは、多言語、多民族の社会となり、それに起因する社会的生活規制であるカースト制度や被差別民を生み出すなど固有の性格を備えることになり、「多様性のなかの統一性」と特徴づけられている。 [中山修一] 自然地形インドの本土は四つの大地形区に分けられる。すなわち、氷河を抱くヒマラヤ山脈、聖なる大河ガンジス川とインダス川の上流に形づくられたヒンドスタン平野、開発を許さない乾燥地帯であるタール砂漠、および半乾燥のデカン高原である。ヒマラヤ山脈は、6億年の昔には海底にあったもので、およそ7000万年前ごろから、大規模な褶曲(しゅうきょく)運動と断層運動によって隆起を始め、現在の巨大な山体をなした新期造山帯である。その規模は、東西に約2500キロメートル、幅240キロメートルの広がりのなかに、エベレスト山(8848メートル)をはじめ多くの世界の高峰をもつ。ヒマラヤの名は、ヒマHima(雪)とアーラヤĀlaya(館(やかた))の合成語で、「雪の館」の意であり、万年雪に覆われた雪原の面積は4万平方キロメートルで、世界一の規模をもつ。ヒンドスタン平野は、ガンジス川を中心に、東にブラマプトラ川下流、西にインダス川上流を従え、これら三大河川の流域により形成される。東西に長く約2400キロメートル、南北には240~320キロメートルの幅で広がり、全体としてきわめて低平な平野をなす。ガンジス川河口のベンガル湾岸から西に約1600キロメートルも離れた、ジャムナ川河畔の首都デリー付近でも、標高は約200メートルにすぎない。その面積は約77万平方キロメートルに及び、日本の2倍強という規模である。ヒンドスタン平野地域は、更新世(洪積世)のころには海底にあったもので、それ以降、北側のヒマラヤ山脈と南のデカン高原から運ばれる大量の土砂により埋め立てられたものとされ、堆積(たいせき)層は最深部で6000メートルを超えている。ヒンドスタン平野を形づくる土壌は、更新世中期以降の古い地層をバーンガルとよぶ。また、河岸の氾濫原(はんらんげん)などに堆積する比較的新しい土壌を、ウッタル・プラデシュ州ではカダールとよび、パンジャーブ州ではベートとよばれる。デカン高原は、世界最古のゴンドワナ陸塊である。広義には、ガンジス川以南の半島部に位置する高原群と山脈群の総称である。狭義には、マハラシュトラ州、カルナータカ州およびアンドラ・プラデシュ州に含まれる高原部分をさし、テーブル状の残丘と波状地形に特徴づけられる。その面積は約70万平方キロメートルで日本の約1.9倍の広さがある。デカン高原の西境には、約1600キロメートルにわたって平均標高1200メートルの西ガーツ山脈が南北に走り、東境には平均標高600メートルの東ガーツ山脈がある。これらの山脈がモンスーンの雨雲の動きを妨げ、とりわけ高原西部は年降水量600ミリメートル前後の半乾燥地帯となる。また高原は全体として標高1200~300メートルで、西から東にかけて高度を階段状に下げる。したがって、北部のナルマダ川やタプティ川を除くと、主要河川はすべて西ガーツ山脈に源を発し、東流してベンガル湾に注ぐ。土壌は、北西部のデカン溶岩流地帯の黒色土を除くと、地味のやせた赤色土やラテライト(紅土)土壌が一般的である。 [中山修一] 気候アジア大陸の南端にあって北半球の広大な面積を占め、「世界の屋根」ヒマラヤ山脈とインド洋によって取り囲まれたインドの気候は、こうした地形によって全体としてモンスーン気候(季節風気候)の典型的な特徴を示す。季節は、冬、夏、雨期、秋の四季に分かれる。冬(12~2月)は、西地中海から中央アジアを経て中国東北地区に至る高圧帯の影響で、高層を冷気が東に向かって流れ、快晴、低温でしかも1日の較差が大きい毎日となる。しかし、月に4~5回の割合でイラン高原方面に発生する低気圧が、冬雨前線を伴ってヒンドスタン平野を東進するため、雨をもたらすとともに、その後に寒気団が通り抜け、気温が0℃前後に落ち込むこともある。この雨は、北インドの冬小麦作のできばえに大きな影響を与える重要な要素である。やがて太陽が北回帰線へ向かって北上するに伴い、気温の上昇が始まって夏(3~5月)が訪れる。気温の上昇は南インド(3月に平均38℃)から始まり、4月には中部インドで38~43℃となり、5月には北インドで45℃以上と恐るべき酷暑となる。ヒンドスタン平野では高温のため激しい上昇気流が発生し、全体として低圧帯となる。そこにデカン高原方面より強い南寄りのルーとよぶ熱風が吹き込み、ときには砂嵐(すなあらし)や雹(ひょう)を伴う雷雨も襲う。これが生活を押しつぶすような乾燥熱暑の夏である。 5月末にはヒンドスタン平野での気温上昇と低圧帯は極限状態に達し、これに向かってインド洋の湿気をたっぷりと含んだ南西からの貿易風が吹き込み始める。これが南西モンスーン、つまり雨期(6~9月)の到来である。6月初旬にインド南端地域から雨期に入り、雨域は日を追って北上する。6月中旬には全インドが雨期に入り、雨また雨のうっとうしい毎日が続く。この季節に北インドでは、年降水量の90%がもたらされる。9月の2週目に入るころ、貿易風が弱まり始め、インドを広く覆っていた低気圧が、ベンガル湾へと後退し始め、10月には高気圧が張り出してくる。そして秋(10~12月)が訪れる。北インドは乾燥したさわやかな毎日を迎えるが、南インドの東岸では、ベンガル湾の南に下がった低気圧の活動によってサイクロン(台風)が発生する。平均して3年に一度は、発達したサイクロンが南東部沿岸に上陸し人畜に多大の被害を与える。ときには、東海岸から西に向かいデカン高原を横断し、西海岸のケララ地方に大被害をもたらしたのち、アラビア海に抜けて消滅することもある。インドのモンスーンによる雨は、農業発展を規制する決定的要因である。しかし、年平均1000ミリメートル以上の多雨地域は、西ガーツ山脈の西側海岸平野、東ガーツ山脈の東側海岸平野および東インドに限られる。残るデカン高原の主要部と北西インドには半乾燥地域が広がり、農業開発の大きな妨げとなっている。 [中山修一] 生物相広い国土と多様な地形、温帯から熱帯までの気候に恵まれ、インドの植生は3万種の豊かさを誇る。地域別にみると、(1)乾燥熱帯落葉樹林地域、(2)乾燥地有刺低木樹林地域、(3)湿潤熱帯落葉樹林地域、(4)温帯高地林地域の4区の特徴ある植生区を生み出している。乾燥熱帯落葉樹林地域は、インドで最大の面積を占め、パンジャーブ平原からガンジス川流域、デカン高原の北西部と南端部に広がる。おもな樹種は、ヒンドスタン平野でインドボダイジュ、サラソウジュ、デカン高原では、チーク、シタン、ゲッケイジュなどである。乾燥地有刺低木樹林地域は、ハリアナ、ラージャスターン、グジャラートの各州とデカン高原中央部に広く分布する。アカシア、ニーム(樹高10メートル以上になる街路樹)、カエンジュなどはインド西部に多く、ビャクダンやニームがデカン高原中央部で広くみられる代表的な樹種である。湿潤熱帯落葉樹林地域は、ネパール国境に沿うテライ地方、アッサム丘陵、デカン高原東部、西ガーツ山脈にみられる。この樹林は、年降水量1000~2000ミリメートルの地域に特徴的に現れ、乾暑期の6~8週間に落葉する。樹種はチーク、ゲッケイジュ、シタン、サラソウジュなどに代表される。温帯高地林地域は、西ヒマラヤ地域に広く分布し、ヒマラヤスギ、クロマツ、エゾマツ、モミなどが多く、さらに高くなると、シラカンバ、ネズなどがみられる。また、市街地や集落の周辺で全国的に広くみられる樹種として、北インドでは、インドボダイジュ、バンヤンおよびニーム、南インドではヤシ科の樹種、とりわけココヤシがあげられる。独立後、政府は年降水量400~800ミリメートルの半乾燥地域で、広域にわたってユーカリの造林事業を意欲的に進めている。インドの国土は耕地面積が広いため、森林面積は17%程度と少ないが、そのうち90%強が官有林であり、造林事業は政府の重要課題とされている。 自然環境に恵まれるインドでは、哺乳(ほにゅう)動物約500種、鳥類約2万1000種、昆虫3万種もの多くの動物が知られる。哺乳動物のうち家畜を除くと、ゾウ、野生スイギュウ、イッカクサイ、トラ、ライオン、各種のシカなど、大型獣が多く生息することで有名である。しかし、古来、王侯や地方領主が狩猟(インドではシカールとよぶ)を好み、さらに植民地時代にはイギリス人も狩猟を楽しんだため数が減少し、近年では大型獣の生息地も、ほとんどが国立公園や自然動物保護区に限られてきた。主要動物の地域別生息地をみると、カシミール地方のヒマラヤ山脈には、野生ヤギ、クマ、カシミールシカ、ヒョウなどが多い。パンジャーブ平原には一部でカモシカ類が残っている。東インドでは、アッサム丘陵の森林地帯に、野生スイギュウ、シカ、それに世界唯一のイッカクサイが生息する。有名なベンガルトラは、ガンジス川河口の密林でいまもときおり村人を脅かす。また、マハナージ川ではワニの生息が知られる。アジア唯一のライオン生息地として西インドのグジャラート州のギル保護区は有名である。カルナータカ州北部ベルガム県の森林は、ゾウ、トラ、野生スイギュウ、ヒョウ、クマ、シカなどが生息する。また、同州南部の西ガーツ山脈東麓(とうろく)の森林にゾウや野生スイギュウが生息し、国道には「ゾウに注意」の警告板が出されている。さらに南のニルギリ山地には「ニルギリヤギ」とよばれる野生ヤギも生息する。なおインドでは、トラが国民獣に、クジャクが国民鳥に指定されている。自然動物保護法(1972施行)のもとに、トラは2500頭以上の生息を目標に、全国11の保護区で増殖事業が実施され、ワニについても1974年より3000頭を目標に国連機関の援助を受け、12保護区で増殖事業が進んでいる。こうして動物や鳥類は、全国の450を超える国立公園、自然動物保護区において手厚い保護が加えられている。 [中山修一] 地誌インドの地域別特徴をみるのに、地形の形態を指標として地域区分すると、ヒマラヤ山脈、ヒンドスタン平野、デカン高原、および沿岸・島嶼(とうしょ)の四大地域に分けられる。 [中山修一] ヒマラヤ山脈インドのヒマラヤ山脈は、ネパールを挟んで西ヒマラヤ地方と東ヒマラヤ地方とに分かれる。西ヒマラヤ地方は、ジャム・カシミール州、ヒマチャル・プラデシュ州およびウッタル・プラデシュ州の北部を含む地域をさす。東ヒマラヤ地方は、アルナーチャル・プラデシュ州とシッキム州を中心とする。両地方ともヒマラヤの急峻(きゅうしゅん)な山岳地形に支配される共通性をもつものの、降水量や歴史的開発過程に大きな違いを示す。西ヒマラヤ地方がカシミール盆地を中心に比較的開発が進んでいるのに対し、東ヒマラヤ地方はインドでもっとも低開発地域の一つとなっている。農業では、米、トウモロコシおよびキビ類が両地域の主作物であるが、東ヒマラヤ地方ではいまでも焼畑耕作が残っている。また西ヒマラヤ地方のリンゴ生産は、その冷涼な気候に恵まれ近年ますます発達しつつある。西ヒマラヤ山地は二つの顔で国民の心をひきつける。その第一は、カシミール盆地を中心とした避暑地としての顔であり、第二はヒンドゥー教の聖地としての顔である。カシミール盆地は、州都スリナガルをはじめ近郊のパハルガム、アマルナート、ソナマルクなどの山岳景勝地をもち、「真珠にエメラルドをちりばめた清流と湖の楽園」と評され、酷暑のヒンドスタン平野やデカン高原から避暑に訪れる観光客は年々増加の一途をたどっている。40℃を超える酷暑にみまわれる平野と高原の住民にとって、真夏でも20℃強の深山幽谷のカシミール盆地は、まさしく「地上の楽園」である。また、家内工業で生産されるカシミールじゅうたんは、国内のみならず世界に知れわたる特産品である。西ヒマラヤのカメート山(7756メートル)は、聖なるガンジス川の発源地であり、そこはヒンドゥー教三神の一神であるシバ神(破壊の神)の御座所として崇(あが)められ、6000メートル以上の高地にバドリナートやケダルナートといった聖地が古くから開かれ、雨期を除いて訪れる巡礼も多い。なお、西ヒマラヤ地方ではパキスタンと中国、東ヒマラヤ地方では中国との間で国境線が確定しておらず、国境紛争は独立以降も絶えることがない。 [中山修一] ヒンドスタン平野北のヒマラヤ山脈と南のデカン高原に挟まれ、東西に約2400キロメートル、南北に240キロメートル以上の幅をもつ広大なヒンドスタン平野は、国土の約33%を占めるが、ここに人口の約45%(2001)が居住し、世界でもっとも人口の稠密(ちゅうみつ)な平野地域の一つとなっている(人口密度1平方キロメートル当り488人)。この平野は、西にパンジャーブ、ラージャスターン、ハリアナの各州を、中央にウッタル・プラデシュおよびビハール両州を、東に西ベンガル、アッサムの諸州を含む。ヒンドスタン平野は、世界の大河によって形づくられ、中央部をガンジス川上流、西をインダス川の上流、東をブラマプトラ川の下流流域が占め、恵まれた肥沃(ひよく)な土壌にイネ、小麦、キビ類の穀倉地帯を形成する。緯度的には北回帰線から北緯30度ほどに位置するが、ヒマラヤ山脈を北に東西に長いことと内陸性気候に支配されるため、アッサム地方の熱帯多雨地から、タール砂漠の乾燥酷暑の地域まで、多様な変化をみせる。この気候の多様性が、インド起源のヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、シク教などをこのヒンドスタン平野の地から生み出したといえる。インド史を大きく決定づけたイスラム教徒のインド亜大陸支配は、13世紀にこの平野の西部に位置するデリーから始まり、17世紀に入ってのイギリスの植民地化は東のカルカッタ(現、コルカタ)から起こった。第1回の反英独立戦争であるインドの大反乱(セポイの反乱)は、1857~1858年この平野を舞台に戦われ、1947年の印パ分離独立は、人口稠密でそのうえ生産力の高い豊かなこの平野の政治的分割であった。 ヒンドスタン平野は現代の経済活動でも顕著な地域的特徴を示す。西部のラージャスターン州は石膏(せっこう)、銀、石綿の生産地として、また、パンジャーブ州は小麦とイネ、それに機械器具工業の生産地として知られる。中央部では、ウッタル・プラデシュ州のサトウキビ、ビハール州は石炭および鉄鉱石、銅、雲母(うんも)など各種鉱物資源の宝庫で、全インド鉱業生産の40%を生産する。東部では、西ベンガル州のイネ、ジュート(黄麻(こうま))および茶、加えて製鉄、化学工業などが盛んである。また、アッサム州は紅茶生産の中心地であり、さらに石油と天然ガスで国産の50%を産出するなど、いずれもインドの代表的生産地を形成する。 [中山修一] デカン高原デカン高原は、インド亜大陸の半島部のほとんどを占める広大な地域である。高原は多くの山地や残丘をモザイク状にちりばめ、標高300~1200メートルの波状地形に特徴づけられる。西縁に西ガーツ山脈を、東縁に東ガーツ山脈を配しているため、モンスーンによる降水が少なく、年降水量が西部で600ミリメートル前後の半乾燥地となるほか、全体として1000ミリメートル以下の少雨地域となり、農業発展の大きな障害となっている。 デカン高原は北と南で文化圏を二分し、さらに南部でそれぞれ特徴ある3亜区に分かれる。北のマディヤ・プラデシュ州とマハラシュトラ州はアーリア語文化圏で、とりわけマラータ人は、中世のイスラム教徒支配に強く抵抗したヒンドゥー教民族主義の性格を強く残している。南部のアンドラ・プラデシュ州、カルナータカ州およびタミル・ナド州は、先住民族系のドラビダ語族圏を構成する。しかし、中世以降イスラム教徒の強い支配が続いたアンドラ・プラデシュ州民とタミル民族主義の色彩が強いタミル人、加えて3州のうちではもっとも乾燥地が広く、進取の気性に富むカルナータカ州民とは、それぞれ政治・経済行動に特徴を示す。アンドラ・プラデシュ州はイスラム色が強いため、反中央政府的であり、資源にも恵まれないことから、独立後の経済発展から取り残されてしまった。タミル・ナド州は半島南端部に位置することから、これまで中央政府から疎外されがちであった。しかし古来、東南アジア各地に多くの移民を送り出したことによって国際感覚に優れ、タミル文化の優越性とタミル人の団結を誇示する性格を備えた。そのために中央政府に対していっそう強い自治意識をもち、自主独立の気風が根強く浸透している。他方カルナータカ州は古来デカン高原の南部中央という地の利を得て、東と西の両沿岸地方ににらみをきかせることができた。しかし、半乾燥気候のもとで農業への投資が進まず、商工業の発達に力を入れた。近世には、名将ティプー・スルタンが、イギリスによる植民地化に最後まで抵抗し、インドの英雄となったし、20世紀初頭には偉大な企業家で政治家でもあるウィシュベス・ワラヤを輩出した。彼は南インド初の水力発電所を建設し、またクリシュナ・ラージ湖を築造して、同州南部に大規模な灌漑(かんがい)用水路網を完成させ、農業発展に大きく貢献した偉人である。 [中山修一] 沿岸・島嶼アジア大陸からインド洋へ突き出した形の国土は、約6100キロメートルの長い海岸線をもち、半島南端のコモリン岬を境に東海岸と西海岸に分かれる。また、チェンナイ(マドラス)の西方約1500キロメートル、ミャンマーの南海上にアンダマン・ニコバル諸島があり、ケララ州のコジコーデ(カリカット)西方の沖合い約350キロメートルのアラビア海にはラクシャドウィープ諸島がある。両諸島とも中央政府直轄地区とされ、前者はポート・ブレアに、後者はカバラティ島に政庁を置く。島民は漁業とココヤシ生産に力を入れ、自給用米作りに励んでいる。 沿岸地域をみると、東海岸は隆起海岸平野で、南に行くほど幅が広く100キロメートルに達する。この地域は、古くからコロマンデル海岸とよばれ、米の穀倉地帯として栄えてきた。西海岸は、西ガーツ山脈が断層によってアラビア海に落ち込んだ沈水海岸で、マラバル海岸とよばれ、平均の幅は25キロメートルと狭い帯状の平野である。南西モンスーンがこの山脈にぶつかるため、年降水量が2000~6000ミリメートルの多雨地帯となり、イネとココヤシの栽培が盛んである。沿岸地域は海洋を介して古来外国と接し、インド固有の歴史を築くことに果たした役割はきわめて大きかった。古代から中世にかけてインドと西アジア、アラビア方面とを結ぶ海上交通の門戸は、北西インドのグジャラート州沿岸であり、とりわけスーラトは西海岸で最大の港町であった。15世紀末には、カリカットに来航したバスコ・ダ・ガマの喜望峰回り航路の発見ののち、ポルトガル勢力が西海岸に来航し、ボンベイ(現、ムンバイ)、ゴアをはじめ、ダマン、ディウなどの港町を開いた。また、東海岸に来航したフランスはポンディシェリに、イギリスはマドラス(現、チェンナイ)やカルカッタ(現、コルカタ)に商館を設けて、インド商人と交易を始めた。現在、東海岸に発達するおもな港湾都市は、北からコルカタ、ハルディア、パラディープ、ビシャカパトナム、チェンナイ、ツチコリンなどで、とりわけビシャカパトナムは、日本への鉄鉱石積み出しを目的に港湾整備が進められた。また西海岸では、北からムンバイ、マルマガオ、ニュー・マンガロール、コーチンなどの重要港湾が並んでいる。 [中山修一] 政治政治の全般的特徴インドは1947年にパキスタンと分離しながらイギリスからの独立を達成した。これによって主権がイギリス人の手からインド人の手に移るなど重要な変化がもたらされた。その一方で、官僚機構や軍隊の制度など多くのものはあまり変更を受けずに引き継がれて今日に至っている。独立当初の2年半ほどは、インドはカナダ、オーストラリアなどと同じくイギリス連邦内の自治領で、形式上はイギリス国王が元首であり、その任命する総督を頂いていた。しかし独立以前とは違って政治の実権はすでに総督を離れて中央政府の閣僚たちに移っていた。1950年に施行された憲法によって、インドはイギリス国王を元首とすることをやめ、大統領制をとることになったが、イギリス連邦には加盟国としてとどまっている。1951年から1952年にかけて男女同権に基づいた最初の普通選挙が行われた。このときから中央と各州とに、イギリスにおいてみられるような議院内閣制が成立し現在に至っている。 概して自由な選挙がほぼ定期的に実施されている。総選挙によって中央政府がかわることがあるということは、アジアでもインドがほとんど唯一の例であり、第三世界のなかできわめてまれである。これはひとりでにもたらされたものではなく、インド国民の多くが、自由な選挙がインドの統一と向上のために必要であると考え、大きな努力によってそれを維持してきた結果である。ほかのアジア諸国に多くみられた独裁国家と比べて、民主主義では経済発展をもたらさない、あるいは、逆に民主主義と発展とが両立する例をインドに示してほしいという見解もみられたが、1991年の自由化政策以来、このような声はいずれも下火になっている。 イギリス式の議院内閣制であるということは、元首である大統領ではなく首相が政治の中心に位置するということであるが、独立後50年間の8割近くにあたる期間を通じて、首相の座はわずか3人によって占められていた。すなわち、マハトマ・ガンディーとともに独立運動で大きな役割を果たしたジャワハルラール・ネルー(在任1947~1964、1964年病没)、そのひとり娘インディラ・ガンディー(在任1966~1977、1980~1984、1984年10月31日暗殺)、インディラの長男ラジブ・ガンディー(在任1984~1989、1991年5月21日暗殺)である。これが「ネルー王朝」ということばの由来である。ネルーのもとで国民会議派(以下会議派と略す)を与党とする政府は「社会主義型社会」の目標を打ち出し、五か年計画の実施にとりかかった。インディラ・ガンディーは、与党である会議派を分裂させて多くの長老政治家を追放するなど(1969)、父よりもさらに現状改革派的ポーズをみせた。しかし両者ともに国内の左翼諸政党とは一線を画し、これらを封じ込めようとした。この特徴はとくにインディラの場合に強くみられた。同じくインディラにみられた特徴は、縁故者や側近を重用しながら個人的独裁の傾向を強めたことである。1975~1977年の非常事態の期間にはこれらの特徴が一段と顕著にみられ、インド政治にきわめて大きな特異性をもたらした。 1947年に独立を獲得したときインドが直面したおもな課題は、植民地的な経済構造を変え生活水準を引き上げる、政治経済社会の全分野において民主化を行う、宗教によって人々が対立しその結果パキスタンと国が分かれたという不幸な歴史を克服する、の三つに要約することができる。インドの政治はこれらの主要な課題をめぐって動いてきたのである。 [山口博一] 憲法体制と実態インドの元首は大統領であるが、これは名目的な地位で、政治の実権はない。大統領は、連邦と州の両方の議会の議員によって選挙され、任期は5年である。1997年までの9人の大統領の宗教別の内訳は、ヒンドゥー6人、ムスリム(イスラム教徒)2人、シク教徒1人で、6人のヒンドゥーのうち4人までが南インド出身である。大統領選挙が社会構成の複雑さに配慮しながら行われていることがわかる。多数派のヒンドゥーのなかで人口の多い北部出身者が少ないのは、1997年までの12人の首相がいずれもヒンドゥーで、2人を除きいずれも北インドの出身であることを考えあわせる必要がある。 大統領の場合に比べると首相および首相を長とする閣僚会議に関する憲法の規定は非常に簡単なものであるが、実際には首相と閣僚会議が執行権力の中心である。閣僚の数は非常に多いが、そのなかのおもな顔ぶれを一括して非公式に内閣とよんでいる。首相は大統領が任命し、その他の閣僚は首相の助言に基づいて大統領が任命する。閣僚会議は連邦下院に対して連帯責任を負い、またどの閣僚も6か月続けて連邦議会に籍をもたないことを許されない。つまり原則上は、議会が政府をコントロールするということである。 連邦議会は両院制であるが、直接選挙によって構成される下院の重要性が圧倒的に大きい。連邦下院の総選挙は2004年まで14回実施されている。会議派に即してみると、最初の3回はネルーの指導下に、次の4回はインディラ・ガンディーの指導下に戦われたが、6回目(1977)には敗れてインディラが首相を辞任し、7回目には雪辱を遂げて彼女が首相に復帰している。その間の3年近くの期間は、会議派が中央で与党の地位になかった最初の時期である。 首相に復帰したインディラ・ガンディーは、パンジャーブ州に多いシク教徒のなかの一部過激派への対策を誤り、アムリッツァルにあるその黄金寺院を軍隊で攻撃した(ブルースター作戦)ことが直接のきっかけとなって、首相官邸で自らの護衛であるシク教徒に暗殺される。その後を継いだ長男のラジブ・ガンディーは5年の任期をまっとうしはしたが、政権が安泰であったのはその前半だけであった。1989年の総選挙では北インドの中間諸カーストをおもな基盤とするV・P・シンVishwanath Pratap Singh(1931―2008)の勢力にとってかわられた。このころからインドの政局は目だって流動性を増す。V・P・シン、チャンドラ・シェカールChandra Shekhar(1927―2007)の両政権はいずれも短命で、政党間の関係も変化が激しく、1991年にふたたび総選挙となった。その最中に、ラジブはかつて自らが首相としてスリランカの民族対立に介入したことが原因となって(1987年から1990年までインド軍をスリランカに派遣)、タミルのテロリストによって殺害された。 この総選挙では、ラジブの弔いという意味もあってか、会議派が勝利してナラシンハ(ナラシマ)・ラオP. V. Narasimha Rao(1921―2004)政権が誕生し、財務相に就任したマンモハン・シンの手で自由化を中心とする一連の大幅な経済改革が推進された。経済活動はこれまでになく活発になり、外資が流入し、多くの人々がこのようにして得られた機会をつかむことに熱心となった。しかしその反面、貧富の差はむしろ拡大している兆候がある。このことを反映して1996年の第11回総選挙では自由化政策を進めてきた当の会議派が敗北した。 1991年の総選挙のときに生まれた、会議派、インド人民党(BJP、ヒンドゥー至上主義の勢力)、統一戦線(中間諸カーストを代表する有力地方政党やCPIM=インド共産党マルクス主義派を中心とする左翼諸政党が提携したもので反会議派・反ヒンドゥー主義を旗印とする)の三大勢力という政治地図は1996年にも変わらなかった。第一党となったBJPが、A・B・バジパイを首相としていったんは政権についたが、13日間で辞任し統一戦線の政権が続いていた(首相はデーベ・ゴウダDeve Gowda(1933― )を経てI・K・グジラールInder Kumar Gujral(1919―2012))。1998年の第12回総選挙によって、インド人民党が第一党の地位についたが、過半数に達しなかったため、地域政党との連立で政権を握った(首相はバジパイ)。ヒンドゥー至上主義の勢力であり、大国主義を誇示する同党は、1998年5月11日、13日の2日間で5種類の核実験をラージャスターン州で実行した。これに続いてパキスタンが核実験を行い、核廃止の方向に向かう世界を揺るがすこととなった。 その後、1999年4月に全インド・アンナ・ドラビダ進歩連盟がインド人民党から離反したことにより、バジパイ率いる連立与党は1票差で不信任され、下院は解散、1999年9月に第13回総選挙が行われた。これによって定数545議席のうちインド人民党が182議席を獲得、バジパイ率いる与党連合が過半数の296議席を確保し、バジパイ政権が続投することとなった。 2004年5月の第14回総選挙では、バジパイ率いるインド人民党は敗北、国民会議派が与党第一党となり、マンモハン・シンが首相に就任した。インド初のシク教徒の首相であり、過去にラオ内閣時代の財務相など経済分野の要職を多く務めた。経済改革、貧困対策、パキスタンとの対話路線の継続を表明、2009年に行われた第15回総選挙では国民会議派が勝利し、第二次シン政権が発足した。しかし2014年1月に今期での首相退任を表明し、同年5月の総選挙後、退任した。選挙はインド人民党が単独過半数を超えて大勝し、ナレンドラ・モディNarendra Modi(1950― )が首相に就任した。 連邦下院の選挙は、1選挙区の議員定数が1人という小選挙区制によって行われる。任期は5年。10年ごとの国勢調査によって選挙区の調整がなされる結果、各選挙区の有権者数はほぼ均等になっている。指定カースト、指定部族(後述の「社会」の項参照)のためにその人口比にほぼ比例した数の選挙区が留保されている。2008年に改正された選挙区割りでは全国543選挙区のうち84が指定カーストに、54が指定部族に留保され、これらのグループに属する人々でなければ立候補することができない。これは指定カーストや指定部族の向上を保障するための制度であるが、独立後の期間を通じて彼らがその他の一般選挙区から当選した例は非常に少ない。また、2議席は大統領が指名する。 連邦を構成する政治単位は州と中央政府直轄地区で、28州と7直轄地区がある。ただし後者のなかのデリー首都圏の地位は州にほぼ等しい。州は言語別に構成されているが、ヒンディー語だけは特別で、これを用いる州が6ある。州には名目上の長官である州知事の下に、州議会に対して連帯責任を負う州閣僚会議(その長は州首相)があって、州における執行権力の中心をなす。州議会はやはり小選挙区制に基づいて選出される。指定カースト、指定部族への議席留保はここでもなされている。要するに中央での制度を小型にしたものであるが、州知事は中央政府の意向に沿って大統領が任命するのであるから、州政府の政策が中央政府と異なる場合には、州政府を監視し、場合によってはこれを解任する機能を果たす。また州議会の立法権には制約があり、州の財政基盤の弱さと相まって、連邦制ではあるが中央の立場は非常に強力である。州の下には県Districtがあり、その数は全国で約520である。 中央と州の政治を支える大きな力になっているのは、IAS(Indian Administrative Service、インド行政職)とよばれる約5000人の高級官僚群である。IASあるいはIPS(Indian Police Service、インド警察職)のような中央政府が管轄する高級官僚群の存在は、中央の州に対する立場を強くするのに役だっている。 司法制度は多くの面で植民地時代のそれを継承している。その頂点にあるのは、デリーに置かれている最高裁判所で、その下に全国18の高等裁判所がある。これらはいずれも人事その他の点で連邦の管轄下にある。高等裁判所の下に州が管轄する諸裁判所がある。最高裁判所と高等裁判所の判決は判例とみなされる。司法権は独立しており、裁判所には違憲審査権が与えられている。 [山口博一] 外交政策独立直後にパキスタンがカシミールに侵入したことが直接の原因で、インド、パキスタン両新生国家の間に戦争が起こった(1947~1949)。その後も両国の関係は改善されず、1965年と1971年にも戦争が起きている。1971年の戦争はバングラデシュ独立戦争が拡大したもので、東パキスタンがバングラデシュとして独立した結果、インド亜大陸におけるインドの比重は非常に増大した。 インドが共和国となった(1950)のちもイギリス連邦にとどまったことは、のちにアフリカなどでのイギリス領植民地が独立した際に、これらをイギリス連邦につなぎとめるうえで重要な意味をもった。1947年のインド、パキスタン、1948年のセイロン(現、スリランカ)の加盟によって、白人諸国だけの集団としてのイギリス連邦の性格はある程度崩れたが、1960年代前半のアフリカ諸国の大量加盟によってイギリス連邦の様相は一変した。 ネルー外交とよばれた非同盟主義、アジア・アラブ・アフリカ諸国との友好重視の政策は、1954年のネルーと中国の周恩来による平和五原則の発表、1955年のバンドンでのアジア・アフリカ会議の前後にもっとも光彩を放った。ネルーの晩年にはそれは、1957年からの対アメリカ経済援助依存の強化と、ダライ・ラマのインド亡命がからむ1959年からの中国との不和、とくに1962年の中国との国境戦争における敗北によって陰りをみせた。しかし1961年以降の非同盟運動でインドが果たした役割は無視できない。1983年には第7回非同盟諸国会議がニュー・デリーで開かれた。 ガンディー政権下のインドはソ連寄りとみられていて、1971年に締結された有効期間20年の印ソ友好平和協力条約は、インドの対外関係におけるもっとも重要な軸となっていたが、西側に対しても閉鎖的ではなかった。ベトナムの解放闘争を支持し、1980年にはカンボジアのヘン・サムリン政権を承認した。 1979年のソ連のアフガニスタン侵攻の際に大量の西側の武器がパキスタン経由でアフガニスタンの反ソ・反政府勢力に流れたことは、インドとパキスタンの関係をさらに緊張させた。インドにとって「冷戦の終結」とはアフガニスタンをめぐる米ソの対抗という要因の消滅であり、またインド亜大陸における中ソ対立の消滅であった。これらの結果、パキスタンおよび中国との領土問題についての対話の条件が生まれたが、パキスタンとの間ではカシミール地方の帰属がいまなおおもな懸案であり(カシミール問題)、中国との間では国境線の問題が1962年には戦争にまで発展した。これらの解決にはさらに時間を要すると思われるが、経済面での関係強化が続いており、中国とは海軍や陸軍の共同訓練も行われている。 1985年12月にバングラデシュのダッカで最初の南アジア7か国首脳会議が開かれ、南アジア地域協力連合(SAARC(サールク):South Asian Association for Regional Cooperation)が結成された。以来、SAARCはほぼ毎年首脳会議を開催している(事務局はネパールのカトマンズ)。また、インドはインド洋沿岸諸国間の経済協力の促進にも関心を示している。 インドは国連安保理事会の非常任理事国にはこれまで6回当選し、1992年からは常任理事国となる希望を表明している。しかし1996年には非常任理事国の席を日本と争って142票対40票という大差で落選した。これは包括的核実験禁止条約(CTBT)に反対し、孤立したことが響いていると思われる。このCTBTに対するインドの反対は核保有国である中国の脅威に対するもので、核実験の禁止は期限を明確にした核兵器廃絶と結びつけるべきであり、それができなければインドは核兵器をもつという選択権を放棄しないというものであった。そして1998年5月、インド人民党を第一党とする連立政権(首相はA・B・バジパイ)のもと、ラージャスターン州で核実験を行い、続いてパキスタンが核実験を行った。両国ともに同年9月にCTBTへの署名を表明したが、同時に進めているミサイル開発の停止は両国とも拒否している。 [山口博一] 国防植民地時代のインド軍は、官僚機構と同じく、1947年にインドとパキスタンの間で分割された。インドの軍隊はこれを母体としており、階級制度もイギリスのそれと同一である。 憲法上は大統領が軍隊の最高指揮権をもつが、実際は首相と国防相がこれを管轄している。国防相は文民で、文民統制と軍隊の中立性はこれまでのところよく守られている。 兵役の義務はなく志願制で、三軍の総兵力は128万8000人、内訳は陸軍110万人、海軍5万5000人、空軍12万5000人などである。陸軍は機甲師団3、緊急展開師団4、歩兵師団17、山岳師団10などからなり、戦車約3660台をもつ。海軍はイギリス製の航空母艦1隻を中心とし、空軍は作戦機565機、ヘリコプター20機で、ミグ、スホイ、ミラージュなどを含む(2006年)。兵器の国産化はかなり進んでいる。軍事費は、1962年の中国との戦争および1965年のパキスタンとの戦争によって急激に増大した。その後パキスタンや中国との関係がそれほど改善されていないので、軍事費を削減する可能性はあまりない。この点では、国内の見解にも大きな対立はない。 [山口博一] 経済・産業概論かつてインドといえば、混合経済体制の殻に閉じこもり、閉鎖的で停滞的なイメージの強い国であった。しかし1980年代の規制緩和(部分的経済自由化)を経て、1991年に経済改革を導入して以来、従来の面目を一新する変貌(へんぼう)を遂げるようになった。独立後、インドの国内総生産(GDP)は年平均3.5%(ヒンドゥー成長率)の成長レベルに甘んじていたが、1980年代、1990年代を通じて5%台に上昇し、21世紀を迎えてさらに加速するようになった。2003年から2007年までの5年間、インドは年間8.8%の高レベルの経済成長を記録しており、21世紀の世界経済を牽引(けんいん)する勢力として、中国、ブラジル、ロシアとともにBRICs(ブリックス。2011年からは南アフリカ共和国が加わりBRICS)の有力な一角を形成している。 2008年時点で、人口11億5400万人のインドのGDPは1兆1217億ドルであり、世界第12位(購買力平価換算では世界第4位)の大きさにある。他方、その1人当り所得をみれば、インドは中国の3分の1強に相当する1070ドル(購買力平価換算では2960ドル)のレベルにとどまっており、貧困線(収入が、生活に必要な最低限の物を購入することができる最低限の水準にあることを表す指標)以下の約3億人の絶対的貧困層を抱える世界最大の貧困国でもある。成人の36%は栄養失調であり、3歳以下の幼児の46%は標準以下の体重しかない状況にある。また雇用人口のうち、組織部門(従業員10人以上の事業所)に所属する人々の割合は14.7%、さらに年金・社会保障が提供される公式部門に所属する人々の割合は7.6%にすぎない(2004)。しかしながら1990年代以降、貧困線以下の人々の割合は36%(1993)から28%(2004)に低下する一方、平均寿命は58歳(1991)から64歳(2006)、識字率も52%(1991)から65%(2001)へと確実に向上してきており、今後とも経済的拡大が順調に進展するなかで、貧困問題や基本的人権がさらに改善されることが期待される。 [小島 眞] 経済改革1947年の独立後、インドの経済開発において貫かれた二大目標は、貧困の解消と経済自立であった。17世紀初めに東インド会社が進出して以来、インドは長期にわたる植民地支配の苦い経験を余儀なくされてきた。そのためインドでは経済自立への志向がきわめて強く、すでに独立以前の段階で民族資本が台頭し、国産品愛用運動(スワデーシ運動)が叫ばれた。独立後、インドの経済開発を大きく規定したのが、ネルー時代(1947~1964)に確立された混合経済体制であった。そのバックボーンをなしていたのが、公共部門拡大優先の原則、産業許認可制度を軸とした民間部門に対する広範な経済統制、さらには閉鎖的な対外政策であった。1950年代から1960年代前半にかけて、インドでは産業基盤の形成に力が注がれ、公共部門主導型の重工業化が推進された。同期間中、工業部門は比較的順調に拡大したが、農業部門はその脆弱(ぜいじゃく)性を露呈する結果となり、1965年の第二次印パ戦争、さらには1965年、1966年の2年続きの旱魃(かんばつ)が原因となって、インド経済はやがて停滞期(1965~1980)に突入した。この間、インドの工業成長は長期にわたって減速したが、それは第一次インディラ・ガンディー政権(1965~1977)の下で閉鎖的で統制主義的な経済運営が強化された時期と重なっている。その一方で、農業重視の姿勢が積極的に打ち出され、緑の革命が着実に進展したことによって、1980年代を迎えるころまでには、米、小麦などの穀物自給を達成している。 1980年代を迎えて、インドではもはや従来の行きすぎた統制主義のもとでは生産性向上や生産拡大を図ることが困難であるとの認識が強まり、第二次インディラ・ガンディー政権(1980~1984)、それに続くラジブ・ガンディー政権(1984~1989)のもとで産業政策や外資・貿易政策において規制緩和措置が導入されるようになった。しかしながら混合経済体制の枠組みが引き続き温存されたため、経済自由化はアドホック(限定的)な形でしか導入されず、また財政支出の拡大や汚職の蔓延(まんえん)など経済運営における規律も緩みがちになった。さらには主要貿易相手先であった旧ソ連の崩壊、湾岸戦争に伴う中東からの海外送金の激減など国内外の要因が重なり、財政赤字や経常収支赤字といったマクロ経済不均衡が拡大する結果となり、インド経済は1990年代を迎えて大きな岐路に立たされた。そうした最中、1991年4~5月の総選挙で国民会議派のナラシンハ・ラオ政権が成立し、同年7月に経済改革が導入された。 経済改革のねらいは、マクロ経済不均衡の是正を図りつつ、既存の混合経済体制の政策的枠組みの変更を促して大胆な経済自由化を後戻りすることなく実施することにあった。それによってインド経済は従来の閉鎖的な殻を打ち破り、世界経済と密接にかかわりながら大きく前進するという新たな段階を迎えるようになった。公共部門に留保されていた分野への民間部門の参入がほぼ全面的に認められ、公共部門優位の政策が撤回されるとともに、民間企業の活動を大きく束縛していた産業許認可制度が事実上撤廃されるに至った。また対外政策も従来の閉鎖的、内向型から開放的、外向型へと転換され、貿易自由化や外資自由化が着実に進行するようになった。貿易面についていえば、平均関税率は1991年の77.2%から1997年には30.6%、さらに2007年には9.2%に低下するとともに、輸入数量制限は2001年に事実上撤回された。外資面では、多くの産業分野が外資に開放されるとともに、外資出資比率の引上げを通じて外国直接投資の流入拡大が図られた。競争原理の導入は価格低下、品質向上をもたらし、国内市場の拡大、ひいてはインド産業の競争力強化に大きく貢献するようになった。 中道左派連立政権(1996~1998)の期間中、経済改革は一時的に逡巡(しゅんじゅん)をみせた時期もあったが、その後1998~2004年の期間中、バジパイを首班とするBJP連立政権(国民民主同盟)のもとでさらなる前進が図られた。「1999年新通信政策」はその後の企業間競争による携帯電話普及の道を開き、「2003年電力法」は電力部門改革に必要な道筋を示した。さらには「財政責任・予算管理法」(2003)の成立に伴い、財政健全化に向けて着実な営みが開始されるようになった。 その後、2004年の総選挙でマンモハン・シンを首班とする国民会議派連立政権(統一進歩同盟、2004~2014)が成立した。同政権では貧困層の底上げを目ざして、すべての人々が経済成長の過程に参加し、その恩恵にあずかることができるような包括的成長inclusive growthが提唱され、2004年には貧困線以下の農民を対象に100日分の雇用提供を目ざす全国農村雇用保障スキームが導入された。同政権が目ざした経済改革は概して漸進的なものであり、硬直的な労働法の改正、小売業への外資参入、保険分野での外資出資比率の引上げといった懸案事項が残された。 [小島 眞] サービス主導型発展1990年代以降、インドでの高レベルの経済成長を牽引してきたのはサービス部門であった。実際、サービス産業の成長率は1980年代の6%台から1990年代には7%台、さらに2000年から2007年にかけて9%台の高レベルの成長を示すに至っている。サービス部門は商業、金融、運輸・倉庫、不動産、行政サービスなど多くの分野から構成されており、1990年代以降、とりわけ顕著な成長を遂げているのが通信、保険、ビジネス・サービス(ITサービスを含む)、ホテル・レストランといった分野である。GDPの部門別構成をみても、サービス部門のシェアは1990年の43.8%から2000年には50.6%、さらに2007年には52.4%に拡大している。サービス部門主導発展の中心的存在として、インド経済の新しい顔として一躍台頭したのがIT産業である。 インドは世界でも屈指の高等教育人口を抱える国である。ネルー時代にインド工科大学(IITs)が創設され、理工系人材の育成に力が注がれた。自らの才能を発揮できる有利な雇用機会を求めて、1980年代以降、多くの優秀なインド人学生がアメリカに留学するようになり、やがて彼らは1990年代におけるアメリカでのIT革命に遭遇し、存分に活躍する機会を得た。IT革命が進行したアメリカでは、海外アウトソーシング先としてインドが注目されるようになり、アメリカ在住のインド系住民をパイプ役として、人材大国としてのインドはその本領を発揮するようになったのである。1990年代を通じてIT産業は年間50%の成長を示し、21世紀を迎えてからも2007年までの期間中、年間約30%の成長を続けた。インドIT産業の売上高は2009年に731億ドルに達し、GDPの6.1%に達するとともに、輸出は501億ドルを記録し、インド最大の外貨獲得源になっている。 インドIT産業の特徴はハードウェアよりもソフトウェア、さらには国内市場よりも輸出に大きく傾斜していることにある。輸出先の大半は英語圏であり、アメリカが全体の60%を占め、第2位のイギリスが19%を占めている。ITサービスのデリバリーとして、当初、IT技術者が顧客先に赴き、サービス提供を行うインサイト方式が圧倒的であったが、衛星通信を活用して人件費の安いインドから直接サービス提供を行うオフショア方式のほうがしだいに優勢になってきた。 インドIT産業の動向として注目されるのは、年々急速に進化・拡大を遂げているとともに、それぞれの分野でより付加価値の高い分野へと移行している点である。IT技術者が享受する所得は他業種に比べて格段に高く、しかもその雇用数は年々急激に拡大しつつある。IT技術者の雇用数は2009年には230万人、さらに輸送、ケータリング、建設、警備、雑務などの間接雇用は820万人に及んでいる。インド国内においてIT産業は購買力をもつ中間層の多くの担い手を輩出し、第二次・第三次産業にまたがる各種財・サービスに対する需要拡大においても重要な役割を果たすとともに、産業横断的に進行するIT化を通じて製造業、金融など他産業の業務効率化にも大きく貢献する結果になっている。 [小島 眞] 製造業の新たな台頭1991年の経済改革の実施に伴い、インド経済は新たな段階を迎えたが、経済成長を牽引する主役はサービス部門であり、工業部門は脇役的存在にとどまっていた。しかしながら2002年以降、工業部門は新たな拡大を示し、サービス部門と並んで、経済成長のエンジンとしての役割を果たすようになった。実際、2004~2007年の4年間、工業部門は年平均8.8%の高レベルで成長し、2006年には11.0%の成長率を記録した。とくに注目されるのは、経済全体への波及効果の大きい自動車、鉄鋼の両産業である。1980年代前半におけるスズキのインド進出は、インドに日本的経営や生産方式をもたらし、自動車産業に新風を吹き込む結果となった。1991年以降、経済自由化が本格化するなかで、国内市場の潜在的規模に対する期待が高まり、日米欧韓の大手自動車メーカー(そして大手部品メーカー)のインド進出が活発化するようになった。1998年には民族系商用車メーカーとして豊富な経験を生かしてタタ・モーターズが新たに乗用車部門に進出し、企業間競争が激しさを増すようになった。2001年以降、インドの自動車生産は2けた成長を遂げており、四輪車の生産台数は2003年に126万5000台と初めて100万台を突破し、2007年には232万7000台に達した。2008年には金融・経済危機の影響によって生産台数が一時的に225万5000台に低下したが、2009年には291万8000台へと力強い回復を示すようになった。現在、インドは小型車生産の国際拠点、さらには自動車部品の輸出国として、その地位を着々と固めつつある。また自動二輪の分野ではインドは中国に次ぐ世界第2位の地位にあり、2009年には、その生産台数は1051万3000台に及んだ。 また鉄鋼業の場合、経済自由化と対外開放の進展は、鉄鋼生産の拡大を刺激するとともに、生産性向上、品質改善に向けて大きな刺激を与えることになった。独立後、インド鉄鋼業の最大手は、公共部門のインド鉄鋼公社(SAIL)であったが、1990年代以降、鉄鋼生産拡大の主役を担ったのは民間部門である。大手鉄鋼メーカーのタタ・スチール以外にも、JSWスチール、エッサール・スチール、イスパット・インダストリーズ、ジンダル・スチール&パワーといった中堅鉄鋼メーカーが大きく台頭するようになった。粗鋼生産は1992年の1520万トンから2008年には5452万トンへと拡大し、世界第5位の鉄鋼生産国になっている。2009年時点で、各鉄鋼メーカーが新規製鉄所の建設のために州政府と取り交わした合意書は222件(2億7600万トン)に及んでおり、インドの鉄鋼生産能力は2011年ころには1億2000万トンに達することが期待されている。 [小島 眞] 拡大する中間層近年、インドでは一定の購買力をもった中間層が大きく台頭し、消費財市場の拡大に弾みを与えている。中間層を一義的にとらえることは必ずしも容易ではないが、インド応用経済研究協議会(NCAER)によれば、世帯年収20万~100万ルピー(2001価格)の所得階層である。こうした中間層は、家電や自動二輪は容易に購入でき、また自動車購入にも手が届く所得階層であり、かつては高所得世帯に該当していた所得階層である。実際、中間層の人口規模は1995年には2500万人、2001年には5800万人程度でしかなかったが、その後、2007年には1億2300万人、さらに2009年には1億5300万人に増加している。実際、インドの中間層は21世紀に入ってから、きわめて高いペースで増え続けている。2001年から2009年までの期間中、その年平均成長率は12.9%に及んでおり、世帯別シェアも5.7%から12.8%に拡大している。また新中間層(世帯年収9万~20万ルピー)の場合、世帯別シェアは21.9%から33.9%に増えている。2007年時点で、中間層の自動車所有世帯は、都市では40%以上、農村でも24%に及んでいる。また中間層のテレビ所有世帯は、都市では96%、農村では62%に及んでいる。 インド国内市場拡大にかかわる新たな動向として、とくに注目されるのは次の2点である。第一に、低コスト・モデルの活用が広がり、中間層のみならず、後続の新中間層(2009年時点で4億人強)も新たな有力な購買層として登場し、国内市場の裾野(すその)が確実に広がりつつあるということである。実際、携帯電話の場合、その加入件数は2004年3月の3369万件から、2010年3月末には5億8432万件に拡大しており、インドは中国について2番目に大きい携帯電話の市場になっている。第二に、インドでは購買力をもつ人々が必ずしも都市のみに集中しているのではなく、農村にも広く分布しているということである。2009年時点での中間層、新中間層に占める農村のシェアをみても、それぞれ33.4%、61.2%と推計されており、マーケットとしての農村の重要性はきわめて大きいものがある。 [小島 眞] 産業の担い手独立後、インドでは基幹産業の中枢を担うべく、新規設立ないしは民間企業の国有化を通じて多くの公企業が誕生し、経済の管制高地(中心的役割)を占めることが期待されてきた。1991年以降、公共部門拡大優先の原則が撤回されたことに伴い、インド経済のなかでの公企業の相対的地位は低下するようになったが、石炭、石油、電力、通信(固定電話)の分野では依然として公企業は支配的な地位を保っている。インドの売上高ベスト10の企業には、インド石油、バーラート石油、ヒンドゥスターン石油、インド・ステイト銀行(SBI)、石油天然ガス、インド鉄鋼公社の6公企業が含まれている。公企業は中央政府公企業と州営企業から構成される。2008年3月時点で、中央政府企業は242社存在し、その売上高はGDPの23%に相当するレベルにある。また州営企業の場合、実働中の州営企業は837社存在するが、その多くは慢性的赤字に陥っている。 インドでは独立以前からタタ(1868設立)やビルラ(1857設立)などの有力な老舗財閥が存在していたが、混合経済体制下では産業許認可制度、さらには「独占・制限的商慣行法」(1969)に基づいて、一定規模以上の民間企業、とりわけ財閥系企業の活動は厳しく抑圧されていた。1991年以降、上記の規制が解除され、民間部門の活動範囲が広がるなかで、既存の財閥に加えてリライアンス(1966設立)などの新興財閥が多数台頭し、インド経済拡大の牽引役として重要な役割を果たすようになった。リライアンスは石油化学事業を通じて1990年代以降に急成長した財閥であり、21世紀に入って以降、タタと並んでインドを代表する財閥に成長した。ちなみにインドの財閥は後継者問題で分裂するケースが多く、1990年代にビルラが複数のグループに分裂し、またリライアンスについても、創立者であるディルバイ・アンバニの死去に伴い、2人の息子の対立が表面化し、2005年には兄ムケシュ率いるリライアンス・グループ(石油化学、石油・ガス採掘、石油精製)と弟アニル率いるリライアンス・ADAグループ(通信・電力・金融)の二つに分割された。 上記の三大企業グループ以外にも、エッサール(鉄鋼・電力)、ラーセン&トウブロ(重機械)、ITC(タバコ・食品・ホテル・IT)、マヒンドラ(自動車・IT・金融)、アヴァンタ(旧タパール、パルプ・食品・電力)、バジャージ(二輪車・三輪車)、キルロスカ(機械・トラクター)、ヒーロー(二輪車)、ゴドレージ(機械・食品・日用品)、シュリラム(金融)、バールティ(通信・小売業)、JSW(鉄鋼・電力)など有力な企業グループが多数台頭し、しのぎを削る競争をしているのがインドの現状である。ちなみにタタの場合、2008年度の売上高はGDPの6.1%に相当する708億ドルに及んでおり、その64.7%は海外事業によるものである。同グループの活動はエンジニアリング、鉄鋼、電力、IT、ホテル、紅茶など幅広い分野に及んでいる。旗艦企業としてのタタ・スチール、タタ・モーターズ、タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)の3社の場合、グループ全体の売上高の76%(2008)を占めるとともに、それぞれ鉄鋼、自動車、ITの分野でインドを代表する最有力企業である。 [小島 眞] インフラストラクチャーインド経済が高レベル経済成長を着実な拡大を続けていくうえで、そのかぎを握っているのがインフラ部門(道路、鉄道、空港、電力、通信、上下水道、灌漑、倉庫など)である。近年、民間部門の参入によって通信設備は急速に整備されつつあるが、大きな課題として残しているのが電力部門、それに鉄道、道路、港湾の物流部門である。道路は鉄道にかわってすでに輸送面での主役の座にあるが、総じてインドの道路事情は劣悪である。都市部では交通混雑が深刻さを増す一方、農村部では全天候型の道路が整備されていないため、雨期には外部との物流面で支障をきたす地域が少なくない。総額3兆ルピーをかける大規模な全国ハイウェー開発計画が進行中であり、その象徴的存在として注目されているのが、「黄金の四辺形」(デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルコタを結ぶ総延長距離5546キロメートル)、「東西・南北回廊」(東西・南北の両端を貫く総延長距離7300キロメートル)である。2010年6月末時点で、前者は99%、後者は71%の工事が完了しており、一部の箇所はBOT方式に基づいて、シンガポール、マレーシアなど外資を含めた民間部門が参入している。 インドの鉄道については、すでに飽和状態に達し、安全性や輸送能力の面で多くの問題を抱えているとの見方が支配的であったが、コンテナ輸送において民間参入が認められるなど、急速ピッチで効率性向上が図られるようになってきた。第十一次五か年計画中には、本邦技術活用条件(STEP。日本の技術、ノウハウを活用し、途上国への技術移転を通じて「顔の見える援助」を促進する目的で創設されたタイド円借款)方式に基づいて、デリー・ムンバイ、デリー・ハウラー(コルカタ)間で高速貨物専用鉄道の建設が着手される見込みである。インドの港湾についても、外国貿易に伴う物流コストが高くつき、産業全般の国際競争力を損ねているという見方が一般的であったが、中央政府管轄下の12の主要港、その他の港を含め、PPP(官民パートナーシップ)方式に基づいて、専用港建設、さらには港湾施設の増強や取扱処理能力の向上が図られている。また需要増大に対応できず、施設増強が急務とされている空港についても、バンガロール、ハイデラバードでは新空港が建設されるとともに、デリー、ムンバイ両空港ではPPP方式に基づく改良工事が行われた。 インフラ分野で改革が容易に進まず、工業成長に対する最大の制約要因として作用しているのが電力部門である。2009年時点で、ピーク時の電力不足は12.7%に達している。日常的に停電など、不安定な電力供給にみまわれ、そのため工場・事業所の多くは自家発電・UPS(無停電電源装置)の設置を余儀なくされている。また2008年時点で、各家計への電気の普及を示す電化率はいまだ60%(農村では45%)にとどまっている。電力不足解消という観点から、石炭火力に基づいた4000メガワット級の9件のウルトラメガ・パワー・プロジェクト(入札に基づいてすでに4件が決定)が予定されるとともに、2008年に原子力供給国グループの了承を経て米印民生用原子力協定が正式に成立したことに伴い、今後、原子力発電所の増設に弾みがつくことが予想される。留意されるべきことは、電力部門の主要事業体である州電力庁(SEB)が軒並み深刻な経営赤字に直面しており、そうした構造上の問題にメスを入れない限り、問題の本質的解決にならないという点である。SEB改革の最大の焦点は、配電ネットワークのオープンアクセスや配電部門の民営化を含む配電部門の改革にある。利用者負担の原則の徹底を図りつつ、SEBの配電部門改革を軌道に乗せることができるのか、大きな課題が横たわっている。 [小島 眞] 対外経済関係独立後、インドは長年にわたって先進国、国際機関からの大口の経済援助を受け入れる一方、自給色の強い保護主義的な対外政策が採用されてきたが、1991年以降、グローバリゼーションの時代に即した対外志向型の経済開発が目ざされるようになった。その結果、インドの輸出依存度(商品輸出/GDP)は1980年代には4.5%であったのが、1990年代には7.7%、さらに2007年には15.3%に上昇するに至った。また貿易相手先としては、長らくEU、アメリカ、旧ソ連、それに日本が上位を占めていた。1990年代以降、全方位外交を基調としつつも、ルックイースト政策が唱えられ、近年、ASEAN、中国、韓国との貿易が急速に拡大しており、また2010年よりインドASEAN・FTA(自由貿易)協定、インド韓国CEPA(包括的経済連携協定)が発効している。 2008年時点で、インドの商品輸出は1853億ドルに及んでおり、その品目別構成をみると、宝石・宝飾品、石油製品がそれぞれ全体の15.1%、14.9%を占め、以下、輸送機器(6.0%)、アパレル(5.9%)、機械類・器具(5.9%)、医薬品・化学品(4.7%)となっている。また商品輸入は3037億ドルに及び、原油・石油製品がトップで全体の30.1%を占め、以下、一般機械(8.7%)、エレクトロニクス製品(7.7%)、金銀(7.2%)、真珠・貴石・貴金属(5.5%)、輸送機器(4.4%)となっている。インドの主要貿易相手国は、輸出先ではアラブ首長国連邦(UAE)がトップで13.2%を占め、以下、アメリカ(11.4%)、中国(5.0%)、シンガポール(4.6%)、香港(ホンコン)(3.6%)となっており、輸入先では中国がトップで10.7%を占め、以下、UAE(7.8%)、サウジアラビア(6.6%)、アメリカ(6.1%)、イラン(4.1%)となっている。 インドの貿易収支(商品貿易)は慢性的に大幅な赤字を計上している一方、貿易外収支(サービス、投資所得、経常移転)は顕著な黒字を計上しており、経常収支全体の赤字幅がかなり軽減されている。世界輸出におけるインドの存在感が強まっているのは、商品輸出よりもサービス輸出のほうである。1995年当時、世界輸出に占めるインドのシェアは商品輸出、サービス輸出のいずれとも0.6%程度であったのが、2007年時点で、商品輸出では1.1%、サービス輸出では2.6%に拡大している。2008年、サービス輸出(ソフトウェア・サービス、ビジネス・サービス、運輸、旅行、金融サービスなど)は1020億ドルに及んでおり、その半分近くを占めているのがソフトウェア・サービスである。またインド人が海外で多数活躍していることは、在外インド人による国内送金、およびNRI(非居住インド人)口座への預金などで、多額な経常移転収入をもたらしており、2008年には435億ドルに及んでいる。2009年時点で、アメリカ、中東など世界各国に約2500万人の在外インド人が存在しているといわれる。 外国投資に目を転じると、従来、投資先としてインドはそれほど注目される存在ではなかったが、巨大な国内市場、生産拠点としての重要性が高まるなかで、新たな展開がみられるようになった。対内直接投資は2002年の50億ドルから2006年に236億ドル、さらに2007年には368億ドルに拡大し、リーマン・ショックに伴う世界同時不況の影響を受けた2008年の場合でも363億ドルを記録した。またポートフォリオ投資は2002年の10億ドルから2003年には114億ドル、さらに2007年には236億ドルに拡大した。2008年には世界同時不況の影響を受け、ポートフォリオ投資の海外からの引揚げがみられたが、2009年には回復傾向を示している。 対内直接投資と並んで注目されるのは、対外直接投資の拡大である。インド企業の活発なグローバル事業展開を反映して、インドの対外直接投資は2004年には18億ドルであったのが、2007年には135億ドル、さらに2008年に179億ドルへと拡大した。インド企業の海外進出は、とりわけIT産業、鉄鋼業、それにエネルギーの分野において顕著である。実際、タタ・グループはグローバル事業の拡大を成長戦略の重要な柱の一つに位置づけ、2000年のタタ・ティーによるイギリス紅茶メーカーのテトリー買収を手始めとして、2007年にはタタ・スチールによる129億ドルでのヨーロッパ第2位のイギリス・オランダ鉄鋼メーカーのコーラスの買収、さらに2008年にはタタ・モーターズによる23億ドルでのイギリス高級車ブランドのジャガー、ランドローバーの買収を手がけ、インド企業のグローバル展開を世界に強く印象づけるできごととなった。 [小島 眞] 社会社会構造の全般的特徴インドの社会を彩る大きな特徴は、その構成要素の多様さということである。それを宗教、カースト、民族の三つの面から考えることができる。 [山口博一] 宗教インド人の約75%はヒンドゥー教徒である(指定部族は除く)。パキスタンがまだインドから分かれていなかった植民地時代には、その比率はこれほど高くはなかった。ムスリム(イスラム教徒)が全体の25%を占めていたからである。1870年代以後に発展したインドの民族運動は、ヒンドゥーの中産階級をおもな担い手としていた。マハトマ・ガンディーに代表されるその指導者たちは、従来のヒンドゥー教の教義をそのまま信奉したのではなく、これを解釈し直して新しい時代の要求に合致させようとした。しかしそれはムスリムや不可触民の反発を招いた。ムスリムは人口の12%で、絶対数ではインドネシア、パキスタン、バングラデシュに次ぐ世界第4位である。独立のときに旧インドのムスリムの約3分の2が東西両パキスタンに属することになったが、約3分の1はインドに残された。つまり、植民地インドの両端のムスリム多数派地域をパキスタンとして独立させたのである。1971年には東パキスタンが独立してバングラデシュとなった。 これらのことは、宗教と民族を同一視しそれによって国家をつくろうとする試みが無理であったことを示している。パキスタン(とくに東パキスタン)に残されたヒンドゥーと、インドに残されたムスリムはともすれば疎んぜられ、スケープゴートにされることが多い。ヒンドゥーとムスリムに次いで多いのは人口の8%を占める指定部族である。これは、奥地の丘陵地帯などに住む人々を政府がこのように認定したものだが、宗教的にはヒンドゥー化が進んでおり、経済生活のうえでもその他のインド社会とあまり区別がなくなっている。このほかにキリスト教徒、シク教徒、ジャイナ教徒などがいる。仏教徒は1956年から不可触民の改宗者が増えている。 最近の注目すべき動きはヒンドゥー至上主義勢力の台頭である。これはインドの当面する困難をムスリムの存在のせいにし、インドをヒンドゥー的に純化することを要求するもので、多様性に富む社会に単一の尺度をもち込み、宗派間に緊張をもたらし、上位カーストの立場を強化する意味をもっている。1992年12月6日にこの勢力はウッタル・プラデシュ州アヨーディヤーにあるイスラム寺院の破壊を強行した。 [山口博一] カーストバラモン(ブラーマン)、クシャトリア、バイシャ、シュードラの四つに不可触民を加えた五つがカーストであると普通に考えられている。これは間違いではないが、カーストの理念を示しているだけであり、現実のカーストははるかに複雑で、サブカーストがほとんど無数に存在する。人々の接触と結婚の範囲を決めているのはサブカーストであり、職業とサブカーストの結び付きもまだ強く残っている。農村では地主あるいは有力な農民のサブカーストを中心として生産活動が営まれている。バラモンなど上位のサブカーストは一般に肉食を忌み嫌い、肉体労働をしないなど特定の生活様式をもっている。そこでそれ以外のサブカーストの人々が集団で肉食をやめるなど上位カーストの生活様式を採用し、そのうえで自分たちは上位のカーストに属すると主張するということが始終起こっている。つまり個々人にとっては、その所属するサブカーストは生涯変えることはできないが、サブカーストが集団として上位あるいは下位に移動することは可能であった。最近は中位の有力な農民のサブカーストが上位カーストの行動様式を模倣するのではなく、逆に自分たちはバラモンなどによって低い地位に追いやられていたとして、指定カースト(SC)や指定部族(ST)並みの保護を要求する動きもみられる。 憲法では特定の人々を不可触民として差別することは処罰の対象であるとされている。つまりカーストの廃止は規定されてないが、不可触民は公式には存在しないことになっている。しかし彼らへの偏見と差別はまだ根強くみられる。政府は、人口の約16%にあたる範囲の人々を、従来不可触民として差別されてきたとして指定カーストに認定し、指定部族と同じくさまざまな保護を与えている。しかしこれはヒンドゥーとシクだけについてであって、他の宗教に属する不可触民を含んでいない。カーストは理念上はヒンドゥーだけのものであるが、多かれ少なかれほかの宗教にも類似のものがみられる。 指定カーストと指定部族には、議会選挙、公務員採用、公立学校入学などで一定の割合が留保されているが、中間諸カーストからも同様の優先措置を求める声が高まり、1990年にV・P・シン政権によってそのための方策がとられた。指定カースト、指定部族以外のいわゆる「その他の後進諸階級(OBC)」への保護である。ヒンドゥー至上主義の動きはこれへの対抗という面をもっている。OBCは人口の半数を占める大勢力であるが、その内部は一様ではなく、上位カーストに対立する面をもつ一方で、下位カースト、SC、STを抑圧する面ももっている。 1997年7月に10人目の大統領に副大統領であったナーラーヤナンが選出された。彼は南インドの指定カースト出身である。 [山口博一] 民族・言語インドの各州は1950年代からは言語別に構成されそれぞれの公用語をもっている。ヒンディー語だけは六つの州で用いられている。言語が違うそれぞれの集団を民族と考えることができる。つまりインドは多民族社会、多民族国家である。 28の州間の人口規模の差は非常に大きく、1億を超えるウッタル・プラデシュ州をはじめ、1000万人以上の州が18ある反面で、200万人未満が5州ある(2001)。憲法には、1000万人以上の州の公用語となっている11の言語、すなわちヒンディー語、マラーティー語、ベンガル語、テルグ語、タミル語、カンナダ語、グジャラート語、オーリヤー語、マラヤーラム語、アッサム語、パンジャーブ語に、広くムスリムの間で用いられるウルドゥー語、ジャム・カシミール州の公用語カシミール語、現在パキスタンに属するシンド州からのヒンドゥー難民が用いるシンド語、古典語のサンスクリット語を加えた15語の尊重がうたわれている。1992年の第七十一次憲法改正によりあらたにコンカン語、マニプル語、ネパール語が付け加えられた。インドの紙幣にはマニプル語とシンド語を除くこれらのすべての言語および英語の計17語で金額が記されている。州が言語別に構成されているといっても、州の区画と住民の言語的な区分はかならずしも一致しないので、各州はそれぞれ少数言語集団をいくつも含み、それぞれが多かれ少なかれ多民族的構成になっている。したがって、州の人口とその州の公用語である言語の実際の話者人口とは一致しない。ヒンディー語は連邦の公用語であるが、これを公用語とする六つの州(ヒンディー・ベルトとよばれる)の人口の比率は42%、実際の話者人口は39%前後である。 インドは一国でヨーロッパ並みの広さをもっているから、主要な言語が18あるといっても不思議ではない。それにサンスクリットの影響が強いから、多くの言語の間にはある程度の共通性がある。しかし各民族がそれぞれの言語に強い誇りをもっているので、中央政府がヒンディー語を単に連邦の公用語から、より国語に近づけようとする方向に動くと、かならず反発が起きてきた。当分は英語が共通語として重要な役割を果たし続けると思われる。他方で各州が言語的な閉鎖状況に陥ると、民族間の通婚や州間の人口移動がそれだけむずかしくなる。 インド社会を構成する要素はこのように複雑であるが、その中身は政治的、経済的な動きを反映して変化しつつあるのであり、これを固定的なものとみてはならない。このような複雑さをもつインドの社会が一つにまとまりうるものであるかどうかは大きな問題であるが、政治と宗教の分離、諸民族と諸言語の平等、政治・経済・社会の各分野にわたる民主的発展によって可能になると思われるし、インド国内でも多くの人々がそれを望んでいる。 [山口博一] 国民生活インドは10年ごとに国勢調査を行っている。1991年のそれによると人口は8億4393万で、前回の1981年に比べて23%、1億6000万人増えている(2001年には10億2701万5247、2007年推計では11億6901万)。増加の絶対数は非常に大きい。しかし増加の年率は1990年代に入って2%を切るようになり、2000年代前半(2000~2006)では1.6まで落ちている。人口の動態からは、今後に人口増緩和の期待をかけられる面がでてきている。乳児死亡率は2006年には57まで低下し、これを反映して同年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に何人の子供を生むかの予測指数)も2.5に下がっている。 人口動態では州間の差が大きい。乳児死亡率はケララが最低で17であるのに対し、最大の人口をもつウッタル・プラデシュ州では98、最高のオリッサでは120であった。 死亡率の低下は天然痘の絶滅(1977年4月)など保健衛生状態の改善によるところが大きい。しかし平均寿命はまだ60歳に達したばかりで課題も多い。2006年の平均寿命は男63歳、女66歳である。1986年に当時の首相ラジブが発表した20項目の政策(20ポイント政策)にも、清潔な飲料水の確保と、ハンセン病、結核、マラリア、甲状腺腫(こうじょうせんしゅ)、視力喪失その他の主要な病気の克服があげられていた。最近はHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者の増加も指摘されている。 これだけの人口をまかなうための食糧(穀物および豆類)の生産は1980年代末からモンスーン(季節風)に恵まれて順調に伸びている。しかし人口増加が続いた場合の不安は残るうえ、1人当りの消費量にも目だった増加はみられない。 より重要な課題は雇用である。1980年代だけをみても、14歳までの人口比は4%減少し、その分だけ15~59歳人口比が増加した。しかし、これに見合うだけの雇用の創出がなされたとは信じがたい。1976~1991年の15年間をとると、新規雇用の大部分は公共部門(政府部門)でなされている。この傾向は長続きしないであろうし、好ましいことでもない。同時に農村でも農業への基礎的投資と雇用拡大とを結びつけることが望まれる。 識字率は1981年の36%から1995年の52%、2007年の66%へと上昇したが、男子が76.9%であるのに対し女子は54.5%で、その差が縮まっていない。識字率は州間の差が大きくビハール、マディヤ・プラデシュ、ラージャスターン、ウッタル・プラデシュなどのヒンディー・ベルトの大きな州で低い。頭文字をとって「BIMARU(ビマル)」とよばれるこの4州はいろいろな意味で問題が多く、合計特殊出生率が高く、女性の識字率が極端に低いのもこの4州である。 男女の差に関して一つ奇妙なことは、国勢調査のたびに男子人口に対する女子人口の比率が減少していることである。これは女子を意図的に少なく数えるからだという説もある。 国連の人間開発指標でインドは世界のなかでかなり下位に位置づけられている。世界の貧困層の3分の1近くを抱えているといわれ、1991年からの経済改革もその効果を膨大な人口のうえに及ぼすに至っていない。その意味で大きな社会経済格差を残したままの自由化には問題が多い。土地の劣化など環境の悪化も進んでいる。BIMARU諸州などの現状は指定カーストや指定部族の問題を含めて、カーストを基盤とする身分制度的な状況の存続をうかがわせる。その反面で経済の活性化と絡み合って、インド人によるNGO(非政府組織)活動が目だつようになっている。 都市人口と農村人口の比は1990年代なかばで27対73であった。100万人以上の都市が1981年の12に対し1991年の国勢調査では23あり、都市化の傾向が早まっていることを示した。しかも1981年から1991年のこれら23都市の人口増加率は36.5%に達し、予想を上回った。10万人以上の都市は約300あったが、そのなかには10年間で人口が2倍以上となった都市も少なくない。2001年には人口100万人以上の都市は35を数えるようになった。多くの都市が過剰人口を抱え、なかばスラム的な様子をみせている。ムンバイ(ボンベイ)、コルカタ(カルカッタ)、デリー、チェンナイ(マドラス)の四大都市を通常メトロポリスといっている。 [山口博一] 教育インドの学校制度は、大学を別にすれば、5年の初等教育、5年の前期中等教育、2年の後期中等教育となっている。最初の8年間が義務教育で、入学者は増加しているが、強制就学ではなく、登校しなくなる児童も多い。しかしこの12年間をあわせて「10プラス2」といわれるようになったのは、一定の年数の教育が必要であるという考えに基づくものである。 そのあとの高等教育機関はカレッジとユニバーシティである。カレッジの数は1950年の542から急増して8000を超えている。その大部分はそれぞれユニバーシティの管轄下にある。前者が学部教育を行い、後者が大学院教育を受け持つ関係にあるといってよい。ユニバーシティは222ある。独立後の就学率と就学者数の増加は上級の学校になるほど大きく、カレッジの場合にもっとも顕著である。植民地時代の教育の欠陥がこのようにして是正されているのである。しかし義務教育も十分に普及していない状況では、このこと自体が格差拡大の一面となりかねない。また、カレッジやユニバーシティを卒業しても適当な職が得られない者が非常に多い。これは、経済発展の速度が遅いためもあるが、同時に高等教育が文科に偏っていて、当面インドでもっとも必要とされる中小企業や農村での働き手の養成に適していないことも一因である。 [山口博一] 出版とマスコミインドは出版活動が盛んな国で、毎年の書籍の刊行点数も多い。文学作品はそれぞれの言語で書かれることが多いが、学術書は主として英語で書かれている。これは、全国の高等教育機関で教科書や参考書として用いられるには、英語で書かれていることが望ましいし、国際的な流通も保証されるからである。 インドでは日刊紙2130(2006)をはじめ多くの新聞が発行されている。日刊紙を言語別にみると、ヒンディー紙がもっとも多く、ついでウルドゥー紙、タミル紙、英語紙の順となっている。日刊紙の発行部数の合計は8886万3000部(2006)で、約12人につき1部の割合である。有力な新聞のなかには民間の財閥の所有になるものが多い。 新聞の発行や書籍の出版は都市の高等教育を受けた住民をおもな対象としている。これに対しラジオあるいはテレビは識字を前提にしないため、より普及する可能性をもっている。これらはいずれも国営で、テレビはDDI(Doordarshan India)、ラジオはAIR(All India Radio)が、独占的に運営している。中央政府の情報放送省が管轄しているが、1997年9月、DDI、AIRを政府から切り離して、独立の放送機関とするための「インド放送協会法」が発効した。テレビは人口の85%が住む地域をカバーしている。しかし、DDIの調査によると、1998年には6500万世帯にテレビがあり、テレビを見ることのできる人は2億9600万人であった。テレビのない家庭が圧倒的に多かった。1990年代に入ってケーブルテレビもスタートした。ケーブルテレビ事業者数は約6万、1998年末で加入世帯数は2160万であった。2006年のテレビ保有世帯数は8807万、ケーブルテレビ加入世帯数は6800万となっている。 [山口博一] 文化インド文化の特質インドの自然が寒冷と猛暑、乾燥と湿潤の両極端をあわせもった多様性を示すと同様に、インド文化にもさまざまなレベルにおける多様性がみてとれる。それは生態系に見合った生活文化の多様性とも対応するが、端的にいって、車で1時間も行くとことばが異なるという言語や民族文化の圧倒的な多様性にもみてとることができる。しばしば人は、インド国民としての意識よりも、自らの属する母語集団ないしは民族集団に強い帰属意識をもつが、各集団がそれぞれ数千、数百年の独自の歴史をもつことを考えれば、それはあまりに当然のことといえよう。しかも東西ヨーロッパをあわせたに等しい広大なインド亜大陸の広がりを考慮するとき、そこに単一の「インド文化」や「インド人の国民性、民族性」を求めることは至難である。 しかしインドの人々は、自らのよりどころたる各地方ごとの自民族文化に固執する一方で、北方の二辺を山に囲まれ、南方の二辺を海によって限定されたこの広大な大地を、一つの「母なるインド」(バーラト・マーター)として古くから意識してきた。いかに広大ではあれ、この巨大な菱(ひし)形をなす文化地理的単位は、るつぼのように、さまざまに異質な文化を受容しつつ、独自の文化的枠組みを醸成、確立していった。西方からは古くは先史時代の先進農耕・牧畜文化、抽象的な思考を特徴とするアーリア文化、さらにはグレコ・ローマン、ペルシア、中央アジア、イスラムなどの諸文化、より近年はイギリスをはじめとするヨーロッパ文化を次々と受け入れ、また東方からはチベットや東南アジア北西山地などからの文化要素をも受容しつつ、インド独自の文化的枠組みは、崩れるどころか、ますますそのしなやかな構造を複雑にしつつ、内容を豊富にし、しかもインド的な発展を新たに遂げていったのである。 その際、インドの枠組みにあわぬものは、結局は受容されずに終わるか、もしくは原型をとどめぬほどにインド化した形においてのみ、そしゃくされた。インドはいかなる異質の文化にも積極的な受容の態度をとった一方、その枠組みのもつ同化力はきわめて強靭(きょうじん)である。ことにインドでは、衣食住や思想、芸術などのうえで、異種の文化要素をそのままの形で共存させることをほとんど許すことがない。音楽を例にとれば、インドの音階にそぐわないピアノのような鍵盤(けんばん)楽器はかならずしも定着せず、かえって自在に音をつくれるバイオリンがインド楽曲の演奏用に受け入れられた。女性たちがサリーに固執し、また料理はいわゆる「カリー」に限定されていることも、よく知られている事実である。インド文化の特質の一つによく「寛容性」があげられるが、実はそのオープンな構造は、かならずしもすべてをそのまま受容するというよりも、自らの枠組みにあわせたうえで積極的にそしゃくするというその強靭性にこそ特徴があるといえる。 またこのしなやかな構造は、外からの異文化に対してのみならず、本来インドがそのうちにあわせもった多種の文化諸類型に対してもその力を発揮する。すなわちそれは、一見両極端にみえるような事象をも、同じ一つのことの両局面とみて許容するからである。たとえば、不殺生、非暴力(アヒンサー)はインドの宗教、思想を通じてよく強調される特徴であるが、一方ではヒンドゥー教シャクティ派寺院などにみられるように、祭時には日に数十頭のヤギが首をはねられ、かつては人身御供(ひとみごくう)まで行われることがあった。無私無欲、徹底した苦行すらが強調される一方では、『カーマスートラ』に典型的にみられるように、徹底した愛欲の追求が是とされた。高度に抽象的な哲学教理は現世利益を願う呪術(じゅじゅつ)的儀礼と共存し、現世は幻であると同時に真であり、色と空、動と静なども結局は不二なる存在としてとらえられることが多かった。 このようにインドでは、善悪、光陰、正邪のような明確な二元的対比論は概して退けられた。光あっての陰であり、創造あっての死、男あっての女、というように、両者は相補的な関係にあるか、一つのものの両面にすぎないものと考えられ、多様は一元へと収斂(しゅうれん)した。ヒンドゥー教が一元的多神教とよばれるのもこのゆえんである。そしてかかる思潮は、生と死の輪廻(りんね)観、永劫(えいごう)の時間観念、浄・不浄観などとともに、宗教や哲学のみならず、社会、文化、衣食住などの生活のあらゆる局面においても意識され、インド独自の風習を形成しているのをみてとることができる。いわゆるカースト制の原理も、食事慣習、衣服の着用法、家屋敷の配置なども、すべてがこれらの観念によって分かちがたく、一つの生活文化を渾然(こんぜん)と形成している。芸術においても同様であり、かならずしもそれは、文芸、美術、芸能などに、もしくは彫刻、絵画、建築、あるいは音楽、舞踊、演劇などに分かちがたい。ただし一方では、これら一つ一つのジャンルにおける極端なまで微細にわたる分類、細分を行うのもインド文化の特色であるが、それもこの大きな枠組みあってのことであることを忘れてはならない。 [小西正捷] 日本との関係明治以降の日印関係を文化交流に重点を置いて振り返る場合に、大まかにいって第二次世界大戦以前とそれ以後との2段階に区分しておくのが重要である。 [中村平治] 第二次世界大戦前の日印関係明治期から太平洋戦争の終わる1945年(昭和20)までは、日本は主として経済面で英領インドから綿花、鉄鉱石を輸入してきた。とくに綿花輸入は1893年(明治26)にボンベイ航路が開設されてから急上昇し、1930年代末、太平洋戦争が始まるまで続けられた。文化交流の面ではベンガルの民族的詩人でノーベル文学賞を得たラビンドラナート・タゴールが来日し、大正末と昭和初期の右傾化が進む日本の思想・文化界に衝撃を与えた。 そのタゴールは日中戦争の開始とともに日本の「知識人」と絶交するが、その深い意味を受け止めるべき条件は、当時の日本の政界やアカデミズム、言論界には欠落していた。「アジアの指導者である日本」といった軍国主義日本と、植民地的な地位からの脱却を目ざすインドとの間に対話の場は存在しなかった。太平洋戦争期、日本のインド侵略が目前に迫った1943年(昭和18)、インドの風俗・資源の紹介を中心に50冊を超える書物が刊行されたが、インドの民衆が提起する本源的な要求に目を向けていないという点で、すべて紙屑(くず)同然のものでしかなかった。その意味では、文化交流以前の段階に日印関係は置かれ、わずかに矢内原忠雄(やないはらただお)『帝国主義下の印度』(1937)が科学的なインド認識の礎石となっているにすぎない。 [中村平治] 第二次世界大戦後の日印関係太平洋戦争での日本の敗北と新生インドの誕生とは、日印関係をまったく新しい段階に導いた。経済関係では鉄鉱石輸入が主軸となり、それは日本の高度経済成長を下から支えた。他方で文化・学術面での交流は飛躍的な発展をみせるに至った。 とくにインドを含めたアジア・アフリカ諸国の独立と革命は、日本の文化・学術のあり方に対しても少なからぬ影響を及ぼした。それは、ヨーロッパ中心主義の日本の文化・学術に対して、内容的にも体制的にも一種の自己批判を迫るものであり、アジア諸国への停滞的な視点の克服を求めるものであった。インドに即していえば、在来の文献学的インド研究、とくに印度学、仏教学の研究分野に加えて、広く人類・考古学、歴史学、経済学の分野からするインド研究の必要性が強調され、事実、その方向での研究蓄積が1960年代以降において日本でなされつつある。 こうした研究蓄積の背景には、日印双方による学術・文化交流の努力があった事実を見逃すわけにはいかない。すなわち、独立して数年後の1951年からインド政府留学生制度が導入され、日本の研究者はインドで直接学習する条件を確保するに至った。この制度は今日まで継続されているが、国家建設途上のインド政府の払った努力は高く評価されよう。日本側は1950年代末から、インド人留学生を迎える体制を組み、それが続行されて今日に及んでいる。こうした状況に加えて、日印間には学術交流も盛んであり、歴史・考古学、地理学、経済学の諸分野からする学術調査団がインドに派遣され、その業績はインドの学界でも注目されている。これらの調査活動は、インド側の当局者、とくに大学・研究所などの協力なしには不可能の事柄であり、その面で、じかにインド側研究者との交流も大きく発展する時期にきている。 1970年代の後半以後、タゴールの著作集の刊行を含め、インド音楽、舞踊、映画などの諸領域での交流は一段とその幅を拡大し、厚みを増していることも付言しなければならない。とくに日本の一部には、こうした面で積極的に交流を促進する努力があり、欧米一辺倒の思想・文化状況のなかで注目すべき流れを準備しつつあるといえよう。 経済関係では、1986年以降日本は最大の援助国である(以下イギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、デンマークなど)。1997年までの累計でみると、有償援助が1兆8772億円、無償援助は699億円である。1998年以降は、1998年5月のインド核実験の実施を受け、緊急、人道などを除く新規案件に対する無償資金協力と、新規円借款を停止した。1998年の援助実績は、有償が115億3700万円、無償が3億9800万円であった。2008年は有償2360億4700万円、無償4億2400万円となっている。 日本にとっては、インドとのバランスのとれた多面的な交流の促進が望まれている。 [中村平治] 『『文化誌世界の国5 インド・南アジア諸国』(1973・講談社)』▽『織田武雄編『世界地理4 南アジア』(1978・朝倉書店)』▽『石田寛・中山晴美訳『世界の教科書シリーズ11 インド その国土と人々』(1978・帝国書院)』▽『中村平治著『南アジア現代史 Ⅰ』(1977・山川出版社)』▽『大内穂編『インド憲法の基本問題』(1978・アジア経済研究所)』▽『大内穂編『危機管理国家体制――非常事態下のインド』(1980・アジア経済研究所)』▽『中村平治著『現代インド政治史研究』(1981・東京大学出版会)』▽『山口博一編『現代インド政治経済論』(1982・アジア経済研究所)』▽『佐藤宏ほか編『もっと知りたいインドⅠ』(1989・弘文堂)』▽『近藤則夫編『現代南アジアの国際関係』(1997・アジア経済研究所)』▽『堀本武功著『インド現代政治史』(1997・刀水書房)』▽『近藤則夫編『インド民主主義体制のゆくえ』(2009・アジア経済研究所)』▽『佐藤宏編『南アジア――経済』(1991・アジア経済研究所)』▽『伊藤正二・絵所秀紀著『立ち上るインド経済』(1995・日本経済新聞社)』▽『小島眞著『インド経済がアジアを変える』(1995・PHP研究所)』▽『小島眞著『インドのソフトウェア産業』(2004・東洋経済新報社)』▽『小島眞著『タタ財閥』(2008・東洋経済新報社)』▽『絵所秀紀著『離陸したインド経済』(2008・ミネルヴァ書房)』▽『三上喜貴著『インドの科学者 頭脳大国への道』(2009・岩波書店)』▽『辛島昇・奈良康明著『生活の世界歴史5 インドの顔』(1975・河出書房新社)』▽『山崎元一著『インド社会と新仏教』(1979・刀水書房)』▽『山折哲雄著『インド・人間』(1980・平河出版社)』▽『山際素男著『不可触民の道』(1982・三一書房)』▽『山口博一編『現代インド政治経済論』(1982・アジア経済研究所)』▽『臼田雅之ほか編『もっと知りたいインドⅡ』(1989・弘文堂)』▽『佐藤正哲・山崎元一編著『歴史・思想・構造』(1994・明石書店)』▽『小谷汪之編著『西欧近代との出会い』(1994・明石書店)』▽『内藤雅雄編著『解放の思想と運動』(1994・明石書店)』▽『柳沢悠編著『暮らしと経済』(1995・明石書店)』▽『押川文子編著『フィールドからの現状報告』(1995・明石書店)』▽『押川文子編著『南アジアの社会変容と女性』(1997・アジア経済研究所)』▽『田辺明生著『カーストと平等性インド社会の歴史人類学』(2010・東京大学出版会)』▽『辛島昇編『インド入門』(1977・東京大学出版会)』▽『小西正捷著『多様のインド世界』(1980・三省堂)』▽『奈良康明・山折哲雄監修『神と仏の大地インド』(1982・佼成出版社)』▽『辛島昇編『ドラヴィダの世界――インド入門2』(1994・東京大学出版会)』▽『小西正捷編『アジア読本・インド』(1997・河出書房新社)』▽『大形孝平編『日本とインド』(1978・三省堂)』▽『大形孝平編『日中戦争とインド医療使節団』(1982・三省堂)』 [参照項目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [補完資料] |"> インドの国旗 ©Shogakukan 作図/小学館クリエイティブ"> インド位置図 ©Shogakukan"> インドの地形 インドとパキスタンの国境に広がる砂漠。降水量が多く、農村風景も見られる。近くのワジ(涸れ川)から砂丘が始まっている。インド ラージャスターン州ジョドプル近郊©赤木祥彦"> タール砂漠(大インド砂漠) インド西部、マハラシュトラ州の州都。17世紀末からイギリスのインド経営における西の根拠地として発展し、独立後も順調に経済的成長を遂げてきた。写真はバック湾から望む高層ビル群。インド ムンバイ©Shogakukan"> ムンバイ市街 一帯に残る総数100を超える石窟寺院のなかの代表的寺院。多くがグプタ朝期以後のものであるが、第3窟はそれよりも前のものである。インド ムンバイ近郊©Shogakukan"> カーンヘリー石窟第3窟 ムンバイ湾、エレファンタ島にあるヒンドゥー教の石窟寺院。七つの石窟があるが、第1窟以外は未完成である。世界文化遺産「エレファンタ石窟群」(インド・1987年登録) インド エレファンタ島©Shogakukan"> エレファンタの石窟寺院 全石窟中で建築的にもっとも興味深い第16窟の「カイラーサナータ」。岩山から巨大な岩塊を切り離して彫刻的につくりだした単一石の建築。世界文化遺産「エローラ石窟群」(インド・1983年登録) インド オーランガーバード©Shogakukan"> エローラの石窟寺院 ムガル朝第5代シャー・ジャハーンが、若くして亡くなった愛妃ムムターズ・マハルのために建てた廟墓。22年の歳月をかけて1654年に完成。インド・イスラム建築の白眉で、「大理石の夢幻」といわれた。中央ドームの高さ58m。世界文化遺産「タージ・マハル」(インド・1983年登録) インド アグラ郊外©Shogakukan"> タージ・マハル ヒンドゥー教徒たちの聖地ワーラーナシのガンジス川沿い、5kmにわたって連なるガート(沐浴場)。信徒は聖河ガンジスで身を清め、太陽に向かって祈り、潔斎や消罪の功徳を願う。インド ワーラーナシ©Shogakukan"> ガンジス川での沐浴 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
<<: India [Country] (English spelling) India
>>: Intendencia (English spelling)
Recommend
Muskrat - Maskuratto (English spelling) Musk rat
A member of the mammalian class, rodent order, fa...
Reaction diffusion system
In a chemical reaction system in which reactants a...
Carlo [VII] - Carlo
…In Naples, rebellions by the lower classes occur...
Essais - Zuisouroku (English)
This is a work by the French thinker Montaigne. I...
Borah, William Edgar
Born June 29, 1865 in Fairfield, Illinois Died: Ja...
Manis longicaudata (English spelling) Manislongicaudata
…[Yoshiharu Imaizumi]. … *Some of the terminology...
Councillor - Gishin
〘 noun 〙 One of the six rikugi (decrees) in the ri...
Sedum ishidae (English spelling) Sedumishidae
… [Hiroshi Yuasa]. … *Some of the terminology tha...
Abuse of rights - Kenriranyou
It refers to a state in which the exercise of righ...
Bethune - Norman Bethune
A Canadian doctor born in Toronto. He served as a...
Strategic Defense Initiative
...The United States detects ICBM and SLBM launch...
Yen-denominated foreign bonds
⇒ Yen-denominated bonds Source: About Shogakukan D...
Takamure Itsue - Takamure Itsue
A researcher of women's history. After being ...
Nihon-daira
This refers to the flat land at the summit of Mt....
Colchester
A city in Essex, southeast England. It was the fir...