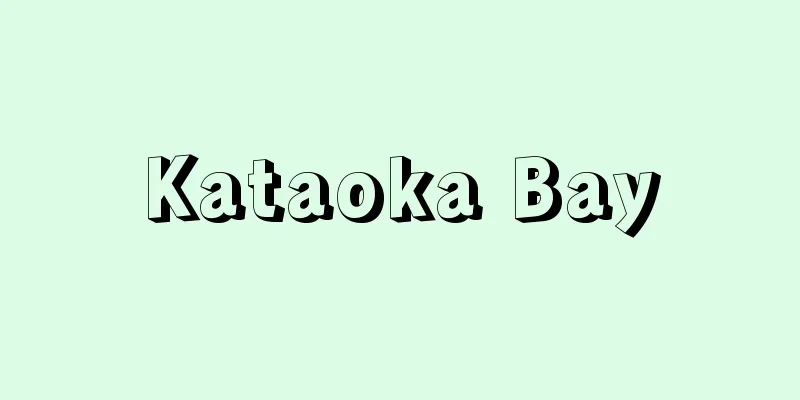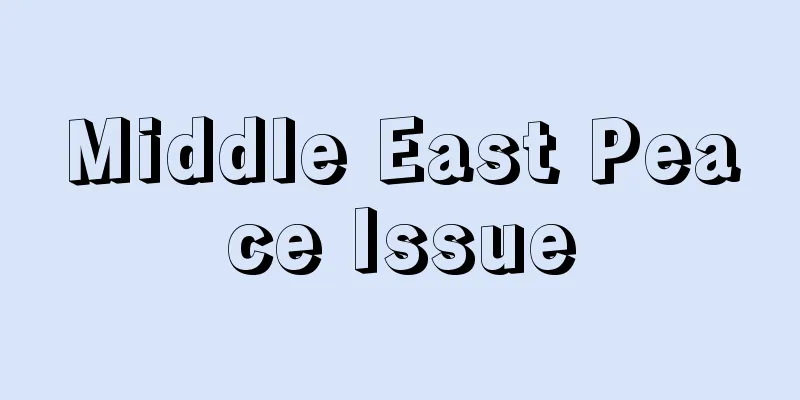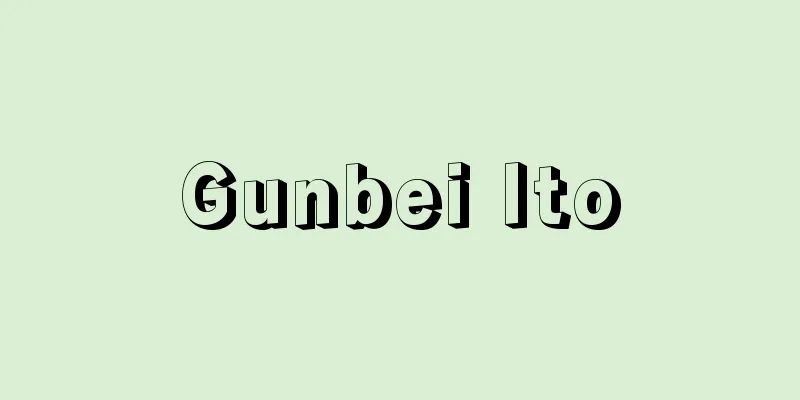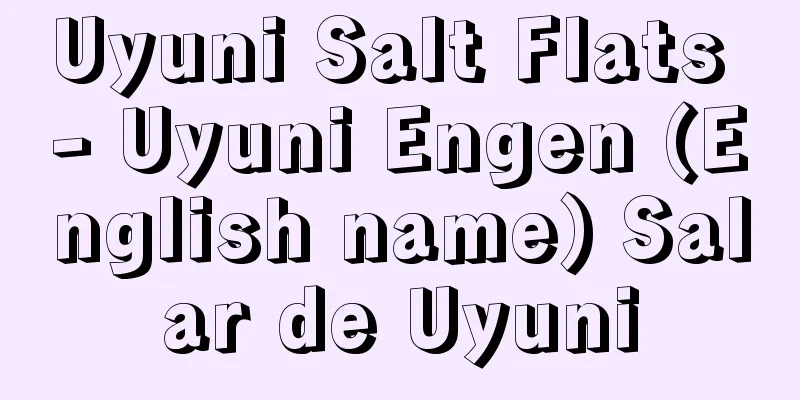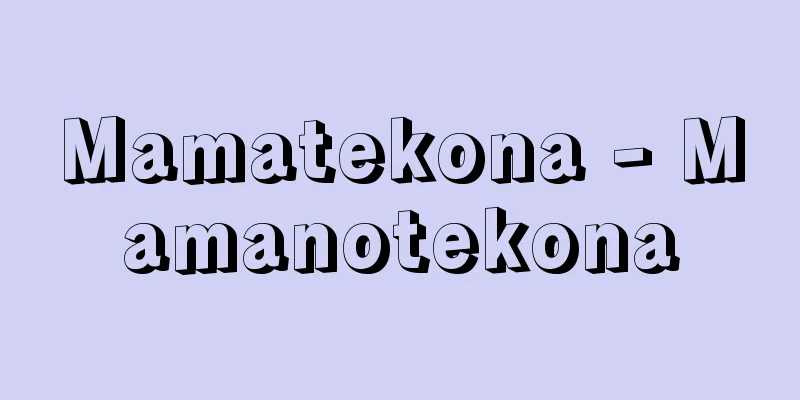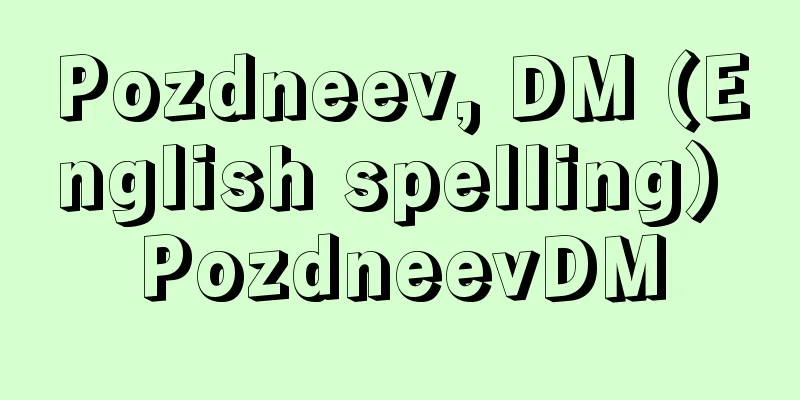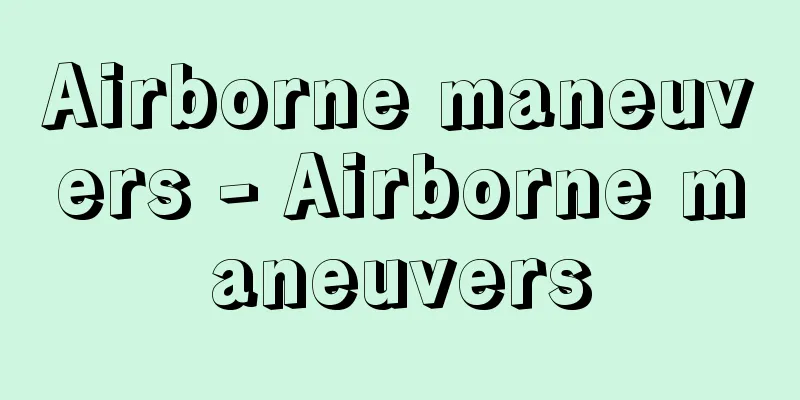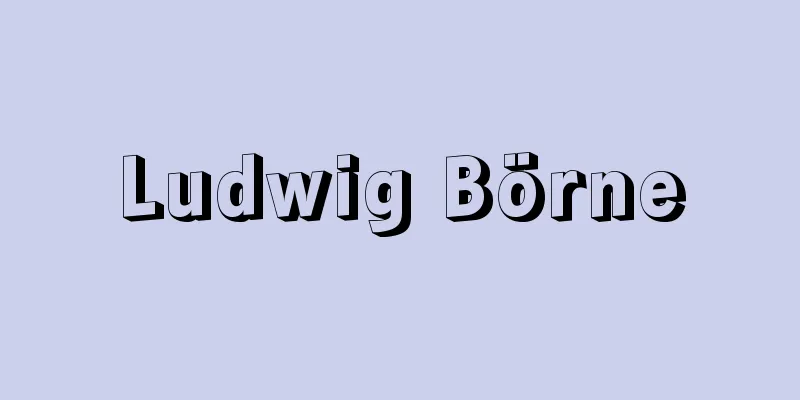Golf - gorufu (English spelling) golf
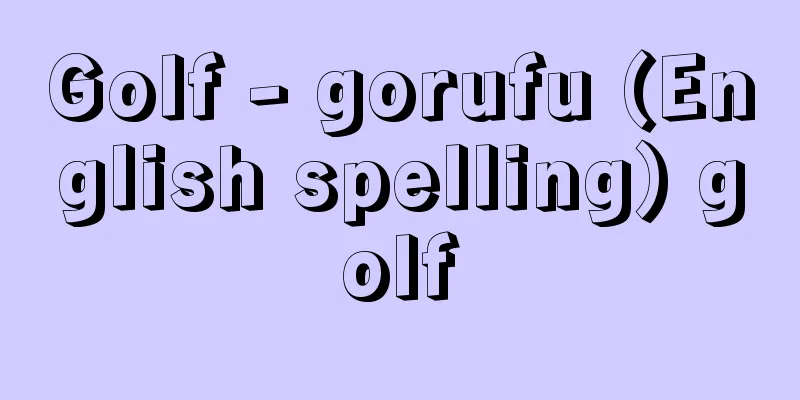
|
A sport in which players hit a ball that is stationary on the course with a cane-shaped club and send it into a designated hole, with the winner being determined by the number of strokes required to get there. [Jun Mizutani and Tadashi Shiota April 17, 2020] HistoryThere are two theories about the origin of golf: one that it is unique to Scotland, and another that it was introduced from the Netherlands. Although there is still no conclusive proof, it is known that in the 14th century, golf was played in its current form and style by the common people of Scotland. In the 15th century, it became so popular that it was considered to be an obstacle to the martial arts and religious faith of the people, and was completely banned by royal decree, or even on the Sabbath. However, the fact is that the game spread to the nobility, and even the king became enthusiastic about it. This is why the game is called the "Royal and Ancient Game." From the 16th century onwards, it developed into a game that could be played by people of all social classes, and eventually spread to England. The small Scottish city of St. Andrews is home to a course of the same name that is said to be the oldest in the world. In the mid-18th century, a club organization (now the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, or R&A) was formed and so-called championship competitions began. At first, a competition was held for a life-size silver club called the Silver Club, and as fair regulations were necessary for official competitions, a set of 13 rules was created. These form the basis of the current General Rules of Golf. Currently, major revisions are made every four years in consultation with the R&A and the United States Golf Association (USGA). In Japan, the Japan Golf Association (JGA) translates these rules and disseminates the rules of golf. As golf became more popular, people began to specialize in making the clubs and balls used in the game, and because they were also skilled in golf techniques, they also began to teach the game. Eventually, golf was recognized as a professional sport, and momentum began to build for open championship tournaments to be held jointly with amateurs. In other sports, open competitions are often only meaningful for socializing, but in golf, the fact that it is recognized as the highest tournament is due to a long-standing tradition. Golf was introduced to the American continent across the Atlantic Ocean from the UK in the late 19th century. Golf courses in the US were first established in 1888, and within just 20 years, the US had acquired a level of prowess rivaling that of the UK. In the 20th century, the US caught up with the UK, and eventually even took the throne. World War I played a major role in this. The UK's national power was exhausted from winning the war, and the golf world also stagnated. In contrast, the US suffered almost no damage from the war, and even during the war it showed enough leeway to try to raise funds for the Red Cross by holding a golf tournament. The post-war economic boom led to the popularization of golf, and the US came to overwhelm the UK in every aspect. [Jun Mizutani and Tadashi Shiota April 17, 2020] History of Golf in JapanMeanwhile, golf spread from the Old Continent to the Orient, using British colonies around the world as a base, and was introduced to Japan in 1901 (Meiji 34) by Arthur H. Groom (1846-1918), an Englishman living in Kobe. A four-hole golf course was built in the villa area on Mount Rokko, and opened in 1903 as Kobe Golf Club. In response to this, the Nippon Race Club Golfing Association, organized by the British Expatriates, was established at Negishi Racecourse in Yokohama in 1906, and in 1914 (Taisho 3), the Tokyo Golf Club, which had its first Japanese members, was opened in Komazawa Village, on the outskirts of Tokyo. At first, golfers in Japan were limited to the upper class, but the sport was popularized in 1924 by the Musashino Country Club. The Japan Golf Association was founded that same year, and amateur Akaboshi Rokuro (1901-1944) won the first Japan Open Championship in 1927 (Showa 2). In the Showa period, golf courses were built one after another all over the country. However, when the Second Sino-Japanese War in 1937 led to the Pacific War, golf was considered an enemy sport, and even vast courses were requisitioned for military use, leading to a state of decline as the war intensified. Eventually, with the end of the war, golf became prominent as a recreational activity for the occupying forces, and there was an opportunity for golf courses that had been converted into military use to return to their original form. At the same time, new golf courses were built all over the country, and the golf world in Japan surpassed its prewar status. [Jun Mizutani and Tadashi Shiota April 17, 2020] Greatest players in golf historyThe first golf pro in history was Allan Robertson (1815-1857) from England. He was a golf ball manufacturer in St. Andrews, but he also excelled in playing technique, and was the first player in the world to record a score in the 70s, winning many followers. Robertson's successor, Thomas (Old Tom) Morris (1821-1908), is known as the "father of the professional golfer." He excelled in both skill and personality, and devoted himself to the development of golf. He teamed up with his son, Young Tom Morris (1851-1875), and achieved an undefeated record. Britain's golden age reached its peak from the late 19th century to the early 20th century, but it owes much to Harry Vardon, James Braid (1870-1950), and Henry Taylor (1871-1963). These three men almost exclusively won the British Open for 20 years from 1894 to 1914 during World War I. Vardon in particular is known as the "father of modern golf" and is known for inventing the overlapping grip (described below). In the 20th century, America caught up with Britain, first Walter Travis (1862-1927) won the British Amateur Championship in 1904 during a tour of Britain, then nine years later, in 1913, Francis Ouimet (1893-1967), an unknown young amateur, won the U.S. Open after a playoff against Vardon. During the blank period caused by World War I, American golf grew significantly, and when Walter Hagen (1892-1969) won the British Open Championship, Britain's Golden Age ended, and America's first Golden Age began. The three players who represent this period are Walter Hagen, Gene Sarazen, and Bobby Jones. Jones, in particular, is known for the immortal feat of winning the world's leading competitions (the U.S. Open and British Open, and the British and American Amateurs) in the same year at the young age of 28, despite being an amateur. After World War II, the United States held an unshakable position, supported by three players: Byron Nelson (1912-2006), Sam Snead (1912-2002), and Ben Hogan. Although we have mentioned three representative players so far, the term "Big Three" was given to Arnold Palmer, Jack Nicklaus, and Gary Player (1935- ), who were active from the 1960s to the 1970s. Subsequent greats include Lee Trevino (1939- ), Tom Watson (1949- , both America), Severiano Ballesteros (1957-2011, Spain), Bernhard Langer (1957- , Germany), Greg Norman (1955- , Australia), Nick Faldo (1957- , Great Britain) and Eldrick (Tiger) Woods (1975- , America). [Jun Mizutani and Tadashi Shiota April 17, 2020] From the early Showa period onwards, Japan began to produce many professionals, and the successive tours to the United States by such players as Miyamoto Tomekichi (1902-1985), Yasuda Kokichi (1905-2003), Asami Rokuzo (1908-1984), Nakamura Kanekichi (1911-1974), and Toda Toichiro (1914-1984) earned them recognition for their abilities and helped them to improve their techniques. Furthermore, in 1957 (Showa 32), at the Canada Cup (now the World Cup), an international competition held at Japan's Kasumigaseki Country Club (also the golf venue for the 2020 Tokyo Olympic Games, postponed to 2021), Torakichi Nakamura (1915-2008) won the team championship as well as the individual championship in a pair with Koichi Ono (1919-2000), proving that Japanese golf had reached world standards, and thus sparked the first golf boom. In 1960, the first private golf tournament in Japan was held, and Hideyo Sugimoto (1938-), Takaaki Kono (1940-2010), Haruo Yasuda (1943-) and others played there. With the success of Isao Aoki, Masashi Ozaki (1947-, also known as Jumbo Ozaki), Tsuneyuki Nakajima (1954-), and Masahiro Kuramoto (1955-), Japanese golf tournaments reached their heyday in the late 1980s. After that, Shigeki Maruyama (1969-), Hidemichi Tanaka (1971-), Ryo Ishikawa (1991-), Hideki Matsuyama (1992-) and others have played mainly on the PGA Tour (US men's professional golf tour). [Masaki Iida April 17, 2020] Golf CourseGolf course Golf first developed as a game in the sand dune areas of the Scottish coast, so the playing fields were originally called links. Eventually, golf courses began to be established in inland areas, and golf courses came to be broadly divided into seaside courses and inland courses. The typical seaside course is the St. Andrews (old) course in Scotland, which is said to be a divine model in that it perfectly meets all the conditions required for golf. The course was created by converting natural sand dunes that had turned into pastureland, and the combination of the changing winds blowing in from the North Sea and the subtle undulations of the sand has resulted in endless excitement when playing. The distinctive feature of seaside courses is that they are designed in closer accordance with nature, and in this we can see the most basic design concept of golf courses. In contrast, inland courses have complex topography, including hills, forests, streams, and ponds, and are characterized by designs with a strong artificial feel. A typical example is the Augusta National course in Georgia, USA. This course, where the Masters Tournament is held every April, has succeeded in creating a completely different kind of appeal from links-type (seaside) courses by using forests, water, undulating terrain, and curves. [Jun Mizutani and Tadashi Shiota April 17, 2020] Course StructureOriginally, there were no specific standards for the size or shape of golf courses, and the game was played using the natural environment, but over the years standards have been established. The course is based on 18 holes, with a total length of around 6000 to 7000 yards (1 yard = 0.91 meters), and the standard par (standard number of strokes) is 72. It takes about 4 hours to play a round. In Japanese courses, the clubhouse is often located in the center for meals and rest, and players naturally return to the house after completing the 9 holes (half). The first 9 holes are called the outer course and the latter 9 holes are called the inner course, and each course consists of 2 long holes, 5 middle holes, and 2 short holes, for a total of 18 holes. The standards are short holes under 250 yards, middle holes between 251 and 470 yards, and long holes over 471 yards, with a par of 3 for short holes, 4 for middle holes, and 5 for long holes, for a total par of 72. For women, the distance is shorter, and the par for long holes over 576 yards is 6. Hole distances are measured horizontally from the center of the tee to the center of the green, or on curved (dogleg) holes, through the center of the fairway as intended by the designer. In addition, courses have course ratings. Par is simply calculated from distance, but natural conditions vary from course to course, which inevitably makes the course more difficult to play on. Therefore, the course rating is done to determine a more scientific standard number of strokes by taking into account the terrain, obstacles, and climatic characteristics in addition to the distance. For example, a flat, wide course may have a total par of 72, but its course rating may be 69, while a well-designed, difficult course may be 74. In Japan, these evaluations are carried out by the Japan Golf Association. [Jun Mizutani and Tadashi Shiota April 17, 2020] Basic Rules and EtiquetteBasic rulesGolf consists of hitting one ball with one club and playing 18 holes on a course. Compared to other sports such as baseball and soccer, which have relatively large playing fields, golf is played in a vast area and is a sport that involves nature, so various things can happen, and the rules are more complicated than other sports. Another characteristic of golf is that many people can participate in the same competition at the same time, so the rules are complicated so that all participants can compete fairly. Another major feature is that there is no referee present. This is because the players themselves are the referees, and the rules are created on the premise that the players must play by following the rules at their own discretion. It does not take into account players who intentionally violate the rules or deceive others to gain an advantage for themselves. The rules of golf have been observed in this way for hundreds of years. [Masaki Iida April 17, 2020] Revision of the Golf RulesThe golf rules were changed on January 1, 2019. The golf rules have been revised every four years, but the 2019 change is not just a revision, but a transition to the new golf rules. The current playing format is mostly stroke play, which allows many players to compete at the same time. However, because it is played on a vast area called a golf course, the golf rules have become too complicated. This is unavoidable in order to maintain fairness, but the transition to the new golf rules was made to change the current situation where rounds take too long and new golfers are prevented from joining the game. Originally, the golf rules were based on the honesty of the players and each player plays in accordance with the golf rules, but the new golf rules require more honesty from players than ever before. Many players who have been playing golf for many years seem to have been confused at first, but they seem to have realized that the rules as a whole have become easier to understand and that playing time has become shorter. What has remained the same is that golfers should always be considerate of other players, protect the course and ensure safety, and behave in a refined manner while demonstrating good manners and sportsmanship. [Masaki Iida April 17, 2020] Etiquette and MannersIt is generally said that etiquette and manners are important in golf. So, what is the difference between etiquette and manners? Manners are not rules but are things that must be followed, while etiquette is consideration for others. For example, it is good manners to smooth a bunker after leaving it. Not smoothing it is not a violation of the rules, but it is something that must be followed. So, what is etiquette? It refers to the consideration of leaving the bunker rake (a tool placed to smooth the sand in a bunker) used when smoothing the sand in an easy-to-reach place for the next person to use. Players should also be considerate of other players on the course. When other players have addressed the ball, they should not move, talk or make unnecessary noise to disturb other players. Players should also be careful not to bring electronic devices onto the course that may distract other players. Players should not tee up in the teeing area until it is their turn to play. Players should not stand near or directly behind another player's ball or directly behind the hole when another player is about to play. On the putting green, players should not walk on another player's line of play or cast a shadow on the line of play when another player is making a stroke. Players in a group should wait on or near the putting green until all players in their group have played that hole. Players should also be aware of safety, not practice swings near people, and not start playing until the player in front of them is out of reach of the ball. And players must be ready to play as soon as their turn comes, and leave the putting green as soon as they finish playing a hole, so as not to cause trouble to the group behind them. It is also important to maintain a fast pace of play, so as not to leave too much space between the group in front of you. [Masaki Iida April 17, 2020] Course Area RulesGolf is played in five areas of the course. Depending on which area of the course your ball is in, different rules apply when playing or taking relief. [1] Teeing area [2] General area [3] Bunker [4] Penalty area [5] Putting green [Masaki Iida April 17, 2020] Teeing AreaThe order of the starting holes is decided by drawing lots. From the next hole, the person who plays first is called the honor, and the order is based on the best (worst) score on the previous hole. The order does not change between players with the same score. The ball must be within a rectangular area that connects the front of the two tee marks (artificial landmarks that have various shapes depending on the golf course) and is two club lengths behind the outside of the tee marks. If the ball is within the area, the stance can be outside the area. If you are within the teeing area of the hole you are playing, you can play with the ball teed up, regardless of how many strokes you are on. When playing from within this area, the tee markers that are set up cannot be moved, regardless of how many strokes you are on. If a teed ball accidentally falls off the tee (by being hit by a club, for example), there is no penalty, and you can tee it up and play again. Because many players play from within this small area, even if you fix unevenness in the ground within the area or tear off any grass or grass that is in the way, this does not improve the lie (the state in which the ball is placed) and no penalty is incurred (penalties are incurred in other areas). [Masaki Iida April 17, 2020] General AreaAny place other than the teeing area, bunkers, penalty areas, and putting green of the hole being played. The so-called fairways (areas where the grass is kept trimmed to make it easier to hit the ball) and roughs (areas other than the fairways that are not intentionally maintained and consist of weeds, shrubs, trees, etc.) are representative. Therefore, for players using the back tees (teeing areas for advanced players located at the back of each hole on the course), the front tees (teeing areas for general players located in front of the back tees) are the general area. Also, since a ball played from the teeing area is in play, it is basically not possible to touch or replace the ball. However, if a local rule called a preferred lie is issued by the committee, it may be permitted to wipe the ball in the general area or place it in a different place. In other cases where free relief is permitted due to abnormal course conditions (such as ground under repair) or immovable obstructions, the ball can also be picked up and wiped. Basically, when a ball is lifted to take relief with or without penalty, the player is allowed to clean the ball or substitute a different ball. [Masaki Iida April 17, 2020] bunkerThere are some restrictions on the area of sand defined as a bunker, as it is an area specially created to test the player's ability to play a ball from the sand. The first and most typical restriction is that players are prohibited from testing the condition of the sand. Therefore, players cannot touch the sand with their hands or clubs. This means that players must be prepared not to touch the sand from the address position, since accidental touching during the address or backswing to hit the ball will be penalized. Also, players are allowed to firmly plant both feet when taking their stance, but are not allowed to excessively dig their feet in or use their feet to remove sand from the side of the bunker to create a level area to create a stance. However, players are allowed to move movable obstacles in the bunker, as well as stones and leaves defined as loose impediments. [Masaki Iida April 17, 2020] Penalty AreaA penalty area is any body of water on the course from which, if the ball comes to rest, the player may either play the ball or take relief under a one-stroke penalty. There are two types of penalty areas, and the procedures for taking relief are different. A yellow penalty area is an area marked by yellow stakes or a yellow line by the Committee, and a red penalty area is an area marked by red stakes or a red line. If an area has not been marked or identified by the Committee, it is treated as a red penalty area. The procedures for taking relief are as follows: [1] Yellow Penalty Area (2) Back-On-the-Line Relief. The player drops the original ball or another ball, under one penalty stroke, in a relief area defined by a back line between the hole and the reference point, which is taken as the point where the player's original ball last crossed the edge of the penalty area (there is no limit on the distance behind that line). [2] Red Penalty Area (3) Lateral Relief (for red penalty areas only) [Masaki Iida April 17, 2020] Putting GreenA ball on the putting green can be marked (a small artificial object that indicates the location of a ball at rest) and picked up and cleaned at any time. When a ball is picked up, it is no longer in play, and when it is replaced, it is back in play. Sand and loose soil on the putting green can be removed without penalty (it is also permitted in the teeing area, but not in other areas). Also, damage caused by external influences such as people and animals on the putting green can be repaired. For example, ball marks (traces of balls dropped on the putting green), marks of replaced turf, marks of old holes (holes), damage caused by shoes (spike marks, etc.), scuffs caused by maintenance work, and indentations caused by animal footprints and hooves. Also, unlike other areas, if a player's ball in play is accidentally moved by the player or caddie, it must be replaced in its original position without penalty. There is no penalty if the ball hits the flagstick, so the player must decide before playing whether to play with the flagstick in place or to remove it and then play. [Masaki Iida April 17, 2020] Main forms of competitionGolf is primarily played in the form of match play or stroke play. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. If a player has told an opponent the number of strokes wrong and fails to correct the error within the specified time, the player will be punished by the public (losing the hole). If stroke play is a battle with all players participating in the competition, then match play is a battle with the opponent. [2] Stroke play A common type of stroke play is stroke play. This is because many players can compete at once at the same time. There is also a special rule that matches play does not have. It is that you must always fill out a score card and hole out. Because each player competes with all players participating in the sport, and all players must be treated equally according to the rules. Once a round is over, the player and marker (who records a player's score) must record the score for each hole of that player and prove that the score is correct, and the player must submit the scorecard to the committee. The player who completes all rounds with the lowest total number of strokes becomes the winner. [3] Other play formats (2) Foursome (commonly known as Alternate Shot) (3) Four-ball [飯田雅樹 2020年4月17日] Relief with punishmentUnplayableThis is the right of a player to pay a single penalty to escape difficult situations in any location other than the penalty area on the course and play from another location. For example, this is also an effective measure when a player's ball is on a tree or stuck in the base of a tree, making it difficult to play. Only the player can declare unplayable, and the procedure is as follows: [1] Relief for strokes and distance (see "Relief based on punishment of strokes and distance" below) [飯田雅樹 2020年4月17日] Relief based on stroke and distance punishmentIf a player's ball cannot be found within three minutes, cannot be identified as a player's ball, or if the ball stops out of bounds, the player must receive stroke and distance relief under one penalty hit. The procedure is to drop the original or another ball into a relief area within one club length that is not approaching the hole from the location where the previous stroke was made, and then tee up from the teeing area and re-hit it) to resume play. If the first hit is out of bounds, the first hit is counted and one penalty hit is added. Then the second hit will be re-hit, so the next one will be the third hit. [飯田雅樹 2020年4月17日] Temporary ballIf a ball that was just played by a player flies to a location where it is likely to be lost, or out of bounds, it takes time for them to search for the ball and then return to the place where they were originally played, so to save time, it is permitted to play another ball tentatively. If the original ball is found after playing a temporary ball, the ball that was played must be abandoned. Furthermore, as long as you continue to play the provisional ball from a location where you estimate that the first ball is present, or from a distance away from the hole, you can play the ball as a provisional ball as long as you continue to play as a provisional ball, but if you stroke from a location closer to the hole than the place where you estimate that there is a ball, the provisional ball will be in play under the punishment of stroke and distance. Even if the first ball is found, the first ball will be lost, so if you play with this ball, you will have played the wrong ball. [飯田雅樹 2020年4月17日] Droping a ball into the relief areaBy rules, when dropping a ball into the relief area, the original or another ball can always be dropped. The player must drop the drop itself, and the ball must be dropped directly below the height of the knee so that it does not touch the player or equipment. It must also be dropped directly below without throwing, spinning or rolling the ball. The dropped ball must fall into the relief area, and if the ball falls into the relief area has left the rescue area, it must be re-dropped. If the re-dropped ball also stops outside the relief area, the procedure for dropping into the relief area by replacing it at the point where it fell on the course when it was dropped for the second time, and the player's ball has returned to its in-play state when the ball stays there. [飯田雅樹 2020年4月17日] Local RulesMaximum ScoreThe principle of stroke play is to hole out, so the maximum score is adopted in the local rule. The maximum score is one form of stroke play, and the player's score on each hole is limited to the maximum number of strokes set by the committee. For example, if the committee determines the maximum score of a score twice the par (specified number of hits), a given score, or a net double bogey (double bogey minus the number of handicaps), even if the actual score exceeds the maximum score, the player's score will be the score of that player. Furthermore, even if the player does not hole out, the maximum score will be the score of that hole. [飯田雅樹 2020年4月17日] Special local rules for lost or out of bounds ballsになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [飯田雅樹 2020年4月17日] Handicaphandicap. Golf is a game where children and adults can compete simultaneously, from beginners to advanced players. This is because there is handicap. In the case of "18 holes par 72", if a handicap 20 person makes a round with 95 strokes, the net score of 75 when a handicap 20 person makes a round with 95 strokes, the net score of 75 when a handicap 30 person makes a round with 95 strokes, and if a handicap 30 person makes a round with 95 strokes, the net score of 65 strokes is minus 30 handicap from 95. In other words, having a handicap allows you to compete at the same time even if there is a difference in skill level. [1] Official handicap [2] Private handicaps [飯田雅樹 2020年4月17日] Amateurs and professionalsになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. PGA and LPGA members are offering official golf lessons at golf courses and driving ranges in Japan. [飯田雅樹 2020年4月17日] ToolsUse of toolsAlthough players can use tools to assist their play during the round (for example, gloves or sunglasses), they cannot artificially eliminate the need for techniques and judgment that are essential to the challenge of the game (for example, using tools that secure the wrist, anemometer, or tilt measurement tools), mitigating tools (other than clubs and balls), or using tools (including clubs and balls) in unusual ways when making strokes. "Anomalous Method" means a method that is fundamentally different from intended use, or methods that are not normally acceptable to play the game (for example, by placing a towel on the side so that the sides are tightened while swinging). Some tools are permitted and not permitted during the round, but these are as follows: [1] Distance and direction information It is permitted to obtain distance and direction information using a distance measuring device or a compass. However, it is not permitted to measure not only distance but also height differences using a distance measuring device. [2] Information on wind and other weather conditions It is permitted to use electrical equipment to obtain weather conditions (including wind speed) and to measure the temperature and humidity of the course, but it is not permitted to directly measure wind speed on the course or use artificial objects to check the direction of the wind. For example, check the powder or handkerchief of an artificial object in the wind by waving it in the wind. However, it is permitted to tear off natural grass and other objects to check the direction of the wind. [3] Gloves and Grip Aids It is permitted to use simple gloves that conform to the tool rules, to apply rosin (on the eyelashes), powder, or wrap a towel or handkerchief around the grip, but not to use gloves that do not conform to the tool rules, or to use tools that provide unfair aid to the position or grip of the hand. [4] Stretching Equipment and Training or Swing Aids Although it is permitted to perform stretching only with general stretching equipment, stretching methods related to golf swings are not permitted. Also, practice equipment and swing aids (alignment rods and weighted head covers for checking position and orientation) designed for golf are not permitted to be used during rounds. [5] Equipment used for medical reasons Although supporters, tapes, bandages, etc. can be used to alleviate medical conditions, it is not permitted to use them for the purpose of assisting golf swings. For example, supporters and tapes can be used because wrist pain, but these tools cannot be used by fixing the wrist to make the golf swings advantageous. [6] Modification of equipment rules for players with disabilities This is a direct way to modify the rules so that players with disabilities can play fairs with other players with no disabilities, or with players with the same or different types of disabilities. These rules can be viewed in the Official Guide to the Rules of Golf. [飯田雅樹 2020年4月17日] clubになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [飯田雅樹 2020年4月17日] The evolution of the clubになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. Club settings have also changed over time, with fairway wood and long irons gradually disappearing, and utility clubs are becoming the mainstream. [飯田雅樹 2020年4月17日] Club FeaturesDivided by type are wood, iron, utility club, and putter. Woods include Wood 1 (driver), Wood 2 (brussy, fairway wood), Wood 3 (spoon, fairway wood), Wood 4 (buffy, fairway wood), and Wood 5 (creek), and in recent years, Wood 7, 9, and Wood 11 have also become the mainstream. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The medium tone type is said to be a shaft type that is easy to get timing, while the double kick type is said to be a shaft type that is easy to create handles and makes it easy to hold the ball. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. However, recently, it has tended to be based on the loft angle rather than approach wedges or sand wedges. Depending on the manufacturer, approach wedges generally refer to lofts of 50 to 54 degrees, while sand wedges are 55 to 60 degrees. Iron sets are mainly sold in pitching wedges, so the lower ranks are paired with single wedges. There are also ways to combine them with 50 degrees, 54 degrees, and 58 degrees, or 52 degrees, 56 degrees, or 60 degrees. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [飯田雅樹 2020年4月17日] ballBalls used in round play must be one that conforms to the equipment rules. The ball must weigh less than 1.620 ounces (45.93 grams) and the diameter of the ball must be at least 1.680 inches (42.67 mm). Also, the ball must not be designed, manufactured or intentionally modified to have characteristics that differ from the characteristics of balls that are symmetrical (when rotated, they must have the same shape when viewed from any angle). There are many regulations, such as the initial velocity of the ball must not exceed the specified value, and the distance of the ball must not exceed the specified distance when tested with equipment approved by R & A and USGA. The ball that has passed these will be a ball that conforms to the equipment rules and can be used in round play. [飯田雅樹 2020年4月17日] The evolution of the ballゴルフで使用される球は最初、堅い木を丸く削られてつくられたものを使用していたが、15世紀中ごろからフェザーボール(革の中へ羽毛を詰めたもの)が使われるようになり、19世紀中ごろからガッタパーチャ球gutta-perchaballが出現した。これは、熱帯植物の樹脂からとったゴム様のグタペルカ(ガッタパーチャー)を丸めたものであった。さらに、球の表面に刻み目をつけることによって、高く、まっすぐに飛ぶことが発見されたのが現在のディンプル(くぼみ)の始まりである。1898年、現在の球の前身ともなるハスケル球が現れ、飛距離が著しく増大した。これは、固いゴム芯をインドゴムの細糸で巻き、グタぺルカの皮膜でくるんだものである。1990年代は糸巻ボールが主流になり、2000年代に入るとウレタンカバーの多層構造(ソリッドコア)タイプが出現し、飛距離と耐久性に劣る糸巻ボールは衰退していった。現在では、カバーが硬く中身が柔らかい飛距離重視のディスタンス系とカバーが柔らかく中身が硬いスピン系の球が主流となってきて、昔から比べてもゴルフ用具のなかでもっとも進化したのがゴルフボールではないかといわれている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] Spikesゴルフ場は天然の芝でつくられているので、ゴルフをプレーするのに非常に滑りやすくなっている。そこで滑らないように靴底に鋼製スパイクをつけたスパイクシューズが誕生し、長い間メタルスパイクが使われていた。しかし、現在はグリーンを傷つけてしまうためほとんどのゴルフコースで禁止されている。現在多く使用されているのがソフトスパイクであり、プラスチックや樹脂でつくられている。以前と違い鋲(びょう)が爪のような形をしているため、鋲が芝をしっかりつかめるようになり滑りにくくなっている。スパイクレスシューズは鋲がついていないタイプで、底の部分は滑りにくい加工がされている。鋲がついていないので普段から履けるようになっている。また、現在では以前から使われている靴ひもタイプに加え、ダイヤル式タイプも使用されるようになっている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 基本技術地上に静止しているゴルフボールをヒットするにはどんな打ち方をしても自由であるが、距離と方向の両方を正しく決めるには、クラブを一定した軌道に沿ってスウィングswingするのがもっとも効果的であるから、スウィングの基本的な原則はほとんど定石化されている。ただしプレーヤーの体格や力量は千差万別なので、その相違によって枝葉的調整が加味される。したがって、一流プロたちが一見異質のスウィングをしているようでも、その肝要なポイント、とくにインパクト(クラブが球に当たる瞬間)ではまったく符節があっている。要するに、ゴルフ・スウィングは、腕とクラブによる円運動であって、その軌道上にあるボールがクラブヘッドによって打ち出される受動作用にすぎないと理解すべきであろう。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] gripgrip クラブと人体を結合させるには両手でクラブを握る必要があるが、この握り方がグリップであって、正しいグリップはもっとも基本的なものである。グリップには次の3種があるが、いずれの場合も、右利きの者は右手が左手よりも下方のヘッドに近くなるから、そのために右肩がすこし下がるのが自然な形となる。 〔1〕ナチュラル・グリップnatural grip 野球のバットを握るときのように10本の指全部でシャフトを握るので、ベースボール・グリップの別称もある。 〔2〕インターロッキング・グリップinterlocking grip 右小指と左人差し指とを絡み合わせて握る方式で、手が小さく指の短い人が用いると両手の締まりがよくなり、スウィング中に緩まない効果がある。 〔3〕オーバーラッピング・グリップoverlapping grip 右の小指を左の人差し指の上に重ねて握る方式で、右利きの人は左利きに比べて右手が強力なのでそれを制約し、両手の一体化に有効である。イギリスのハリー・バードンがこのグリップを広めたためにバードン・グリップとも称され、もっとも多用されている。 なお、以上のグリップに共通するものとして、指を主体にして握る方法をフィンガー・グリップfinger gripといい、親指の付け根のたなごころで握るのをパーム・グリップpalm gripという。また、標準グリップをスクエア・グリップ、右手を開き左手をかぶせた握り方をストロング・グリップ、逆に右手をかぶせぎみにした握り方をウィーク・グリップという。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] アドレスとスタンススウィングは飛球線と平行の形をとり、それを行うために足場を固める構えをスタンスstanceという。バランスを保つためには、スウィングが大きいほど足幅を広げる必要があるが、自由なスウィングとバランスの保全は、「ドライバーのアドレスでほぼ肩幅の広さ」が定説である。スタンスには次の3種がある。 〔1〕スクエア・スタンスsquare stance 両足のつまさきを結んだ線が飛球線と平行になっている標準型で、左のつまさきを右よりもやや開いてセットすることで腰の回転を助成する。 〔2〕クローズド・スタンスclosed stance 右足をわずかに手前に引き、両つまさきを結んだ線が飛球線に対して右から左へクロスするようになる立ち方で、ボールに左回転を与えてフックhookさせる打ち方を容易にする。 〔3〕オープン・スタンスopen stance 左足をわずかに手前へ引き、両つまさきを結んだ線が飛球線に対して左から右へクロスする立ち方で、ボールに右回転を与えてスライスsliceさせる打ち方が容易となる。 どのスタンスをとるにしても、体重は両足の内側後半にかかっている感じで、両足に均分され、両膝(ひざ)をわずかに曲げる程度に緩め、しっかりと地面に定着されている感じが望ましい。ボールの位置は、左かかとの内側から飛球線と直角に交わる地点が標準で、クラブをボールの直後にあてがい、スウィングをおこすアドレスaddress(準備体勢)がとられる。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] バック・スウィング、ダウン・スウィングback-swing、down-swing スウィングは、後方への振り上げ(バック・スウィング)と前方への振り下ろし(ダウン・スウィング)の二つの部分で構成されるが、切れ目のない単一動作(ワンピース・スウィング)と理解すべきである。スウィングは、地面に対して傾斜した平面を形成するが、長身の者ほどその角度が直立し、これをアップライトuprightといい、短躯(たんく)または肥満の者は水平に近くなり、これをフラットflatという。いずれもスウィングは適正なタイミングによってコントロールされていなくてはならない。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] ドライバーショットdriver shot ドライバーは長打のティーショット用であるが、ティーアップの高さとボールの位置によって弾道の高低を変化させたり、またキャリー(滞空距離)をも変えることができる。スウィングの弧を大きくするほどクラブヘッドの速度が増して距離も増大する。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] フェアウェーウッドショットfairway wood shot 比較的ボールのライがよい場合の長打用で、ドライバーと異なり、ややダウンブロー(打ち下ろし)ぎみのスウィングでボールをとらえないと上昇力がつかない。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] ウッド型ユーティリティクラブによるショットウッド型ユーティリティクラブは、基本的にフェアウェイウッドが短くなったものであり、フェアウェイウッドの打ち方とあまり変わらないが、打ち込まずに滑らすように打つのがこつである。 [飯田雅樹 2020年4月17日] アイアン型ユーティリティクラブによるショットアイアン型ユーティリティクラブは、アイアンに比べて、ソールが幅広になっているため、無理せずに球があがるので、滑らすように払い打ちをするのがこつである。 [飯田雅樹 2020年4月17日] アイアンショットアイアンは、標的をねらうための正確さと、ライの悪いボールをたたき出すために発案されたもので、打ち方は、ウッドが箒(ほうき)とすれば、アイアンははたきと考えると、その性能を理解しやすい。 〔1〕ロングアイアンlong iron 1~4番までをロングアイアンと称しているが、ユーティリティクラブと比べても球が上がりづらく、スウィングにばらつきがあると使いこなせないためセット売りからは外れている。 〔2〕ミドルアイアンmiddle iron 5~7番のアイアンをさし、一般的に130~160ヤードの距離に用い、より正確なショットが要求される。ショットの特徴は、ダウンブローにショットすることによってボールにバックスピンをかけてグリーン上で止まる球を打つことである。 〔3〕ショートアイアンshort iron 8、9番アイアンとピッチング・ウェッジをさし、通常130ヤード以下の距離に用いられる。ショートアイアンの目標は旗(ピン)そのものであり、そのためにはいっそうボールにバックスピンをかけて、着地後ただちに停止できるショットが要求される。ダウンブローが有効で、クラブ自体もその作用を助ける構造となっている。 〔4〕ショート・アプローチshort approach グリーンから80ヤード以内のショットは多彩で、バラエティーがあるが、そのためのクラブとしてアプローチ・ウェッジとサンド・ウェッジがある。メーカーによっては52度とか58度といったように度数だけで表示しているものもある。 (1)ランニングショットrunning shot 3分の2以上を転がして旗まで寄せる打法で、方向の正確さという点でもっとも安全であり、使用クラブは普通ミドルアイアンやショートアイアンが多用される。 (2)ピッチショットpitch shot ボールを高くあげてボールを止めるショット。立ち木やバンカーを越して旗(ピン)をねらう場合に用いられるが、熟練の技が要求される。 (3)ピッチ・エンド・ランpitch and run ピッチとランニングとを併用したショットで、効果も両者の特質を兼備している。練習によって使用クラブ(通常ショートアイアン)のキャリーとランの割合を知っておくことが必要である。 (4)チップ・ショットchip shot ごく短い距離をランニングで寄せる打法をいう。 〔5〕パッティングputting 「パットに定型なし」というのが定説となっているのは、ボールをカップに沈めるのが究極目的だからである。しかし正しいパットの原則は、パターフェースが直角を保って、距離に応じて必要な速度で動くことであって、それをいかなる場合も実行できるようにするには独自の型をもつ必要がある。それらを大別すると三つの型となる。手首型(タップ式)は、フォロースルー(インパクトからフィニッシュまでの間)を小さくして手首の屈折でボールをピシッと打つので、必然的にヒット性が強くなる。腕型(ストローク式)は、両腕をラインに平行に動かしながらパターヘッドを振り子のように移動させる。肩型は、肩の回転に多く依存し、距離の大小をその回転度で決める。パットはフィーリング(感覚)が大きな要素を占め、さらにグリーンの傾斜と芝目を読んでその変化に適応したパッティングをしないと、単に打ち方が正しいだけでは成功率を高められない。 〔6〕特殊なライからのショット (2)下り坂(ダウンヒルdown-hill) 右足が左足よりも高くなるライでは、体重が左荷重になり、スウィング中に左へよろけ、トップボールになりやすい。それを避けるために右足寄りにボールを置く。スライスがかかりやすい。 (3)前上り(ハイ・ライhigh lie) ボールが両足よりも高い(たとえば土手の斜面など)場合には、ボールと体との間隔が近くなり、スウィングもフラットにならざるをえないので、体重のバランスに注意し、クラブを短めに持ち、コンパクトなスウィングを心がける。フックがかかりやすいので目標を右側に設定する。 (4)前下り(ロー・ライlow lie) ボールが両足よりも低い場合には、ボールとの間隔が遠くなるので、広めのスタンスをとって低い姿勢をとり、その姿勢を崩さずにボールをとらえる。(2)と同様に打球はスライスぎみになる。 (5)草深いヘビー・ラフheavy rough ボールが長い雑草の中に沈んでいるときは、ボールとクラブフェースの間に草の葉が挟まるから、飛距離は極端に短縮され、ボールも低くなる。ロフトの大きいクラブで脱出を優先させる。 (6)林間・樹木の交錯したなかから脱出する場合 梢(こずえ)を越すにはクラブフェースを極端にオープンに構えてカットショットし、木の枝下を低く抜くにはロフトの少ないロングアイアンを短く持ってコンパクト・スウィングに努め、脱出することに重点を置く。 〔7〕バンカーショットbunker shot ボールの手前の砂へクラブを打ち込み、砂といっしょにボールを飛ばす打法が使われ、これをエクスプロージョンexplosion(爆打)という。ボールの飛距離は削りとる砂の量とスウィングの大きさで決まる。それにはまず砂質を見分けることと、砂の状態を測知することが必要であるが、クラブを砂に触れてはいけないから、しっかり足場を固めると同時に、砂の状態を察知する。砂は産地によって礫(こいし)状のものから粉状のものまでいろいろあり、クラブヘッドへの抵抗を異にし、また乾湿によって砂の締まりぐあいが変わってくるので、いっそう複雑さを増す。エクスプロージョンにはサンド・ウェッジが使用されるが、固く締まった砂ではフランジ(輪ぶち)の厚いサンド・ウェッジははね返りが強すぎて危険の度合いも多く、この場合には9番アイアンなどで、砂を浅くとる。 〔8〕天候の影響下にあるショット (2)雨 地面湿潤でショットのランが殺され、またダフのミスを誘発しやすいので、できるだけボールをクリーンに打つ。 [水谷 準・塩田 正・飯田雅樹 2020年4月17日] 球質とミスショット打たれたボールはスウィングの独自な型によって、それぞれの球質をもつ。厳密にはストレート・ボール(まっすぐ飛ぶボール)はなく、通常どちらかに曲がる。右打ちの場合、まっすぐ飛んで、ボールが落ちぎわにすこし右にカーブするものをフェード・ボールfade ball、左にカーブするものをドロー・ボールdraw ballという。いずれも正しいボールで、球質に応じてコース戦略を考える。しかし、スウィングの軌道が飛球線をクロスしたり、クラブフェースがボールにスクェア(まっすぐ)に当たらないと、ボールは方向が狂ったり、右・左に大きくカーブしたりする。意識的(インテンショナル)に行うものを除いて、この曲がり方が著しい場合にはミスショットで、次のようなものがある。 〔1〕スライスslice 右へカーブするショットで、スウィングの軌道がアウトサイド・イン(ボールと目標を結んだ線の外側からクラブがボールに当たること)に入り、クラブフェースがオープン(右向き)でボールに接し、カットするからである。 〔2〕フックhook インサイド・アウト(ボールと目標を結んだ線の内側からクラブがボールに当たること)に入り、クラブフェースがクローズ(閉じて左向き)に当たると左カーブのショットとなる。 〔3〕プルpull(ひっかけ) スウィングの軌道が飛球線の外側から内側へクロスし、ボールは左へ直行する。著しいものをスマザーという。 〔4〕プッシュpush(押し出し) スウィングの軌道が飛球線の内側から外側へクロスし、ボールは右へ直行する。 〔5〕ダフduff ボールを直接打たず手前の地面をヒットしたため必要な距離が得られないミスで、しばしば犯す者をダッファーという。 〔6〕トップtopping ボールの赤道から上部へクラブのブレードが当たるとボールは上がらずにゴロになる。腕が縮むのと、上体が左へ流れる(スウェイ)のが原因であることが多い。 〔7〕スカイングskying(俗称、てんぷら) クラブヘッドがボールの底部を打つために高い球となる。スウィングを力むと上体が沈むし、手首の使用が過多になっておこる例が多い。 〔8〕シャンクshank ソケットsocketともいう。ボールがフェースの中心を大きく外れ、あるいはシャフトの挿入部(ソケット)に当たり、ボールは極端に右へ飛び出す。原因のうちもっとも多いのは、手だけでクラブを送り出す「手打ち」スウィングになることである。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] Competitionメジャートーナメント世界四大メジャートーナメントとよばれているのは、開催月順に並べると次の通りである。 (1)マスターズトーナメントMasters Tournament(4月開催) (2)全米プロゴルフ選手権 PGA Championship(5月開催) (3)全米オープン選手権 US National Open Championship(6月開催) (4)全英オープン選手権 The Open Championship/British Open(7月開催) [飯田雅樹 2020年4月17日] Grand SlamGrand Slam。スポーツ界で初めてグランドスラムということばが用いられたのは、1930年に当時28歳でアマチュアであったボビー・ジョーンズが、当時の世界四大タイトル、全英アマチュア、全米アマチュア、全英オープン、全米オープンを1年間ですべて制覇したことから使われるようになった。現在の四大メジャートーナメントは前述のように変わっているが、1年間でグランドスラムを達成したのはボビー・ジョーンズただ一人である。複数年を要してメジャートーナメントを制覇した者をキャリア・グランドスラムとよび、ボビー・ジョーンズ(アメリカ)、ジーン・サラゼン(アメリカ)、ベン・ホーガン(アメリカ)、ゲーリー・プレーヤー(南アフリカ)、ジャック・ニクラウス(アメリカ)、タイガー・ウッズ(アメリカ)らが達成している。女子のメジャートーナメントは現在、ANAインスピレーション、全米女子プロゴルフ選手権、全米女子オープン、全英女子オープン、エビアン選手権と五大トーナメントで、キャリア・グランドスラムの達成者はルイーズ・サックスLouise Suggs(1923―2015。アメリカ)、ミッキー・ライトMickey Wright(1935―2020。アメリカ)、パット・ブラッドリーPat Bradley(1951― 。アメリカ)、ジュリ・インクスターJuli Inkster(1960― 。アメリカ)、カリー・ウェブKarrie Webb(1974― 。オーストラリア)、アニカ・ソレンスタムAnnika Sorenstam(1970― 。スウェーデン)の6名がいる。シニアのメジャートーナメントはシニア・プレーヤーズ選手権、全米プロシニアゴルフ選手権、全米シニアオープン、全英シニアオープン、リージョンズ・トラディションの五大トーナメントで、キャリア・グランドスラムの達成者はベルンハルト・ランガーBernhard Langer(1957― 。ドイツ)ただ一人である。日本人で海外メジャーの優勝者は、1977年に全米女子プロを制した樋口久子(ひさこ)(1945― )、2013年全米プロシニアを制した井戸木鴻樹(いどきこうき)(1961― )、2019年全英女子オープンを制した渋野日向子(しぶのひなこ)(1998― )、2021年にマスターズ・トーナメントを制した松山英樹の4名である。 [飯田雅樹 2021年4月16日] 日本のメジャートーナメント代表的な二大競技会が日本オープン(ジャパンオープン、1927年創設)と日本最古のゴルフトーナメントでもある日本プロゴルフ選手権(ジャパンプロ、1926年創設)であり、ほかに日本ゴルフシリーズ(1963年創設)、日本プロゴルフマッチプレー(1975年創設、現在休止中)と日本ゴルフツアー選手権(2000年創設)がある。女子ゴルフのメジャートーナメントは日本女子オープン(1968年創設)、日本女子プロゴルフ選手権(1968年創設)、ワールドレディスチャンピオンシップ(1973年創設)、LPGAツアーチャンピオンシップ(1979年創設)がある。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 日本のゴルフの現状日本は狭い国土でありながらアメリカ、イギリスに次いで現在世界第3位のゴルフ場数を誇っている。第二次世界大戦前の1940年(昭和15)には64コースまで増え、2002年(平成14)の2460コースをピークに2018年時点で2248コースまで減少している。ゴルフ場の多い都道府県は多い順番に北海道、兵庫県、千葉県である。北海道は減少傾向にあるが千葉県などは逆に増加傾向にある。 ゴルフ人口もバブル時代に最高潮を迎え、時代とともに減少傾向にある。とくに20代から30代の男性が減少している。それは自家用車をもたない若者が増えたのも原因の一つと考えられているが、逆に女性や時間とお金に余裕がある60代以上のゴルファーが増えているという統計もある。また、バブル期と比べてもプレーフィー(ゴルフコースの使用料)も低くなってきている。地方のコースなどはかなりの低料金となっているが、オリンピック正式種目にもかかわらず、1回プレーするだけで300円~1200円と、高額なゴルフ場利用税がいまだに残っているため、廃業せざるを得ないゴルフ場も増えており、ゴルフ人口の減少にもつながっている。 また、1926年に日本最古のゴルフトーナメントである日本プロゴルフ選手権が開催されてから多くの企業がスポンサーとなり、多くのゴルフトーナメントが開催されてきた。ゴルフトーナメントは他のプロスポーツに比べても賞金が高く、これによって多くの若者がプロゴルファーを目ざし、バブル期には青木功、尾崎将司、中嶋常幸、倉本昌弘などスター選手が活躍し、40試合近くのトーナメントが開催された。バブルの崩壊とともに徐々に衰退したが、最近では石川遼(プロトーナメント初優勝時、高校生)や池田勇太(ゆうた)(1985― )、アメリカPGAツアーで優勝している松山英樹などの活躍で盛り返し始めている。女子プロゴルフは歴史が少し浅く、全米女子プロに優勝した樋口久子、1987年アメリカLPGAツアーの賞金女王岡本綾子(あやこ)、1993年アメリカLPGAツアーでの優勝を果たした小林浩美(ひろみ)(1963― )などの活躍で人気も出始め、横峯(よこみね)さくら(1985― )、宮里藍(みやざとあい)(1985― )(プロトーナメント初優勝時、高校生)などの出現でブレークした。現在では鈴木愛(1994― )や、2019年全英女子オープンで優勝した渋野日向子をはじめ黄金世代、プラチナ世代とよばれる20歳前後の女子プロゴルファーの活躍で、男子トーナメントよりも人気が出ている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 代表的な日本のゴルフ団体(1)公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA:Japan Golf Association) (2)公益社団法人日本プロゴルフ協会(PGA:The Professional Golfers' Association of Japan) (3)一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA:The Ladies Professional Golfers' Association of Japan) (4)一般社団法人日本ゴルフツアー機構(JGTO:Japan Golf Tour Organization) [飯田雅樹 2020年4月17日] [参照項目] ||||||||||[補完資料] |©Masazumi Fujita "> ゴルフコース(レイアウトの例) ©Shogakukan "> ゴルフクラブの各部名称 ©Shogakukan "> ゴルフクラブのロフトと飛距離の例 ©Shogakukan "> スタンスとグリップ ©Shogakukan "> ショート・アプローチ ©Shogakukan "> ショットの球質の名称 Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
|
コース上に静止しているボールを杖(つえ)状のクラブで打ち継ぎ、定められたホール(球孔(きゅうこう))へ入れ、それまでに要したストローク(打数)の多寡によって優劣を競う競技。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] 沿革ゴルフの起源については、スコットランド固有のものとする説と、オランダから渡来したものとする2説があって、いまだに決定的な実証はないが、14世紀に現行の形式と方法による競技としてスコットランドの庶民間に親しまれた事実が明らかにされている。15世紀にはそれが盛んになりすぎて、国民の武道と信仰の妨げとなるものとされ、勅令による全面禁止、あるいは安息日のプレー禁止などもあったが、事実は、この競技が貴族階級にも蔓延(まんえん)し、ついには王も熱中する風潮となった。これが、この競技の「王の、そして、いにしえなる競技」Royal and Ancient Gameと称されるゆえんである。16世紀以降、身分の上下を問わない競技にまで発展し、やがてイングランドにまで波及していった。 スコットランドの小都市セント・アンドリューズSt. Andrewsには世界最古といわれる同名のコースが現存しているが、18世紀中ごろにクラブ組織(現、全英ゴルフ協会=R & A:Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews)ができ、いわゆる選手権競技も始められた。最初はシルバー・クラブSilver Clubと称して実物大の銀製クラブの争奪戦が催され、公式競技には公平な規約が必要とあって、13か条からなる規則がつくられた。これが現行のゴルフ総則の基盤となっている。現在はR & Aと全米ゴルフ協会(USGA:United States Golf Association)との協議のもとに、4年ごとに大幅改正が行われる。日本では、これを日本ゴルフ協会(JGA:Japan Golf Association)が翻訳してゴルフルールを普及している。 ゴルフが盛んになるにつれて、使用するクラブやボールを専門につくる者ができ、彼らはゴルフ技にも長じていたので実技教習にも携わるようになった。やがて、プロフェッショナルとして認められ、アマチュアと合同のオープン選手権競技会も開催される機運となった。ほかのスポーツでは、オープン競技には懇親的な意義しかない場合が多いが、ゴルフでは最高の大会と認められているのは、遠く当時からの伝統による。 ゴルフは19世紀後半にイギリス本土から大西洋を渡ってアメリカ大陸に移入された。アメリカ合衆国におけるゴルフコースの誕生は1888年のことであるが、その後わずか20年もたたないうちに、イギリスに迫るほどの実力を備えるようになった。20世紀に入るやアメリカはイギリスに追いつき、ついにその王座さえ奪った。それには第一次世界大戦が大きな役割を占めている。イギリスは大戦を勝ち抜くため国力も疲弊し、ゴルフ界も沈滞した。これに反してアメリカは大戦による被害はほとんどなく、戦時中もゴルフ大会で赤十字義援を試みたほどの余裕を示し、戦後の好景気によってゴルフの大衆化はすさまじく、あらゆる面でイギリスを圧倒するようになった。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] 日本のゴルフ史一方ゴルフ競技は世界各地のイギリス植民地を拠点として旧大陸から東洋へも浸透し、日本へは1901年(明治34)に神戸在住のイギリス人アーサー・グルームArthur H. Groom(1846―1918)によって導入された。ゴルフコースが六甲(ろっこう)山上の別荘地帯に建設(4ホール)され、神戸ゴルフ倶楽部(くらぶ)として1903年オープンの運びとなった。これに呼応して1906年には、横浜の根岸競馬場内にイギリス居留民主体のニッポン・レース・クラブ・ゴルフィング・アソシエーションが設立され、1914年(大正3)には初めて日本人を会員とする東京ゴルフ倶楽部が東京郊外駒沢(こまざわ)村に発足した。 日本におけるゴルファーは、初め上流階級だけに限られていたが、その大衆化は1924年、武蔵野(むさしの)カントリー倶楽部が口火を切った。同年日本ゴルフ協会が設立され、1927年(昭和2)の第1回日本オープン選手権競技で、アマチュアの赤星六郎(1901―1944)が優勝した。昭和期に入ると各地に続々とゴルフ場が建設された。しかし1937年日中戦争から太平洋戦争を迎えるに及んで、ゴルフは敵性スポーツとみなされ、さらには広大なコースが軍用地として接収され、戦争激化とともに逼塞(ひっそく)状態となった。やがて終戦を迎えて、ゴルフが駐留軍のレクリエーションとして大きく浮かび上がり、軍用地に転用されたゴルフ場はふたたび初めの姿に返る機運が生まれた。同時に新設のゴルフ場が各地につくられ、日本ゴルフ界は戦前をしのぐ状態となった。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] ゴルフ史に残る名手史上ゴルフ・プロ第一号はイギリスのアラン・ロバートソンAllan Robertson(1815―1857)である。彼はセント・アンドリューズでボール製造を業としていたが、プレー技術にも優れ、世界で初めて70台のスコアを記録し、多くの帰依(きえ)者を得た。ロバートソンの後継者トム・モリスThomas (Old Tom) Morris(1821―1908)は「プロの父」といわれ、技量・人格ともに優れ、ゴルフの発展に尽くし、息子のヤング・トムYoung Tom Morris(1851―1875)とペアを組んでは無敗の戦績をあげた。イギリスの黄金期は19世紀末から20世紀初頭にかけて最高に達するが、ハリー・バードン、ジェームス・ブレードJames Braid(1870―1950)、ヘンリー・テイラーHenry Taylor(1871―1963)の三者に負うところが大きい。1894年から第一次世界大戦の1914年までの20年間の全英オープンはほとんどこの三者のみで優勝を独占している。とくにバードンは「近代ゴルフの父」とよばれ、オーバーラッピング・グリップ(後述)を創案したことで知られる。 20世紀を迎えてからアメリカはイギリスに肉薄し、まずウォルター・トラビスWalter Travis(1862―1927)がイギリス遠征によって1904年度イギリス・アマチュア選手権を制覇、それから9年後の1913年に、全米オープン奪取のため渡米したバードンを迎えて、無名の若きアマチュアであったフランシス・ウイメットFrancis Ouimet(1893―1967)がバードンとのプレーオフのすえ優勝した。第一次世界大戦による空白時代にアメリカ・ゴルフ界は著しく成長し、ウォルター・ヘーゲンWalter Hagen(1892―1969)が全英オープン選手権のタイトルをとることによって事実上イギリスの黄金時代は去り、アメリカの第一期の黄金時代を迎えることになる。この期を代表するのがウォルター・ヘーゲン、ジーン・サラゼンおよびボビー・ジョーンズの3名である。とくにジョーンズはアマチュアでありながら当時28歳の若さで世界の代表的競技会(全米・全英両オープンと英・米両アマチュア)の優勝を1年間で成就するという不滅の偉業(グランドスラム)によって知られている。 第二次世界大戦後はアメリカが不動の地位を占め、バイロン・ネルソンByron Nelson(1912―2006)、サム・スニードSam Snead(1912―2002)、ベン・ホーガンの3名がそれを支えた。これまで代表的名手を3名ずつあげてきたが、いわゆるビッグ・スリーの呼称は、1960年代から1970年代にかけて活躍したアーノルド・パーマー、ジャック・ニクラウスおよびゲーリー・プレーヤーGary Player(1935― )に対して与えられたものである。そして、リー・トレビノLee Trevino(1939― )、トム・ワトソンTom Watson(1949― 。いずれもアメリカ)、セベリアーノ・バレステロスSeveriano Ballesteros(1957―2011。スペイン)、ベルンハルト・ランガーBernhard Langer(1957― 。ドイツ)、グレッグ・ノーマンGreg Norman(1955― 。オーストラリア)、ニック・ファルドNick Faldo(1957― 。イギリス)、タイガー・ウッズEldrick(Tiger)Woods(1975― 。アメリカ)らがその後の名手として名を連ねた。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] 日本では昭和初期に入って多くのプロを輩出しているが、宮本留吉(とめきち)(1902―1985)、安田幸吉(こうきち)(1905―2003)、浅見緑蔵(あさみろくぞう)(1908―1984)、中村兼吉(かねきち)(1911―1974)、戸田藤一郎(とういちろう)(1914―1984)らの相次ぐ渡米遠征の善戦によってその実力が十分に認められ、また、技術向上の助けともなった。さらに、1957年(昭和32)日本の霞ヶ関(かすみがせき)カンツリー倶楽部(2020年オリンピック東京大会<2021年に延期>のゴルフ会場でもある)で開催された国際競技であるカナダカップ(現、ワールドカップ)で、中村寅吉(とらきち)(1915―2008)が小野光一(1919―2000)とペアで団体優勝するとともに個人優勝するに至って、日本のゴルフが世界水準に達していることを証明し、沸き起こったのが第一次ゴルフブームである。1960年には日本初の民間ゴルフトーナメントが開催され、杉本英世(ひでよ)(1938― )、河野高明(1940―2010)、安田春雄(1943― )らが活躍し、青木功(いさお)や尾崎将司(まさし)(1947― 、別名ジャンボ尾崎)、中島常幸(つねゆき)(1954― )、倉本昌弘(まさひろ)(1955― )らの活躍で日本のゴルフトーナメントは1980年代後半に全盛期を迎えた。その後、丸山茂樹(しげき)(1969― )、田中秀道(ひでみち)(1971― )、石川遼(りょう)(1991― )、松山英樹(ひでき)(1992― )らがPGAツアー(アメリカ男子プロゴルフツアー)を主戦場とし活躍している。 [飯田雅樹 2020年4月17日] ゴルフコースgolf course ゴルフがゲームとして育ったのは、スコットランド海岸の砂丘地帯であるため、競技場は当初リンクスlinks(砂原)とよばれた。やがて内陸地方にもゴルフ場が設けられるに至って、ゴルフコースは、シーサイド・コースとインランド・コースとに大別されてよばれるようになった。 シーサイド・コースの典型は、スコットランドにあるセント・アンドリューズ・(オールド)コースSt. Andrews (old) courseで、ゴルフが必要とするあらゆる条件を完全に具備している点で、天与のモデルであるとされる。同コースは自然の砂丘が牧草地帯となったところをコース化したもので、北海から吹き寄せる風の変化と、砂地の微妙な起伏とが複合して、プレーに無限の興趣を与える結果となった。シーサイド・コースの特徴は、より自然に即して設計されており、ここにゴルフコースのもっとも基本的な設計理念をみることができる。 これに比べて、インランド・コースは地形的に複雑で、丘陵、森林、細流、池沼などを内包するので、人工的な色彩の強い設計となるのが特徴である。その典型的なものとしてアメリカ、ジョージア州のオーガスタ・ナショナル・コースAugusta National courseをあげることができる。毎春4月にマスターズ・トーナメントが開催される同コースは、森と水、起伏と曲線とによってリンクス型(シーサイド・コース)とはまったく別種の興趣を盛ることに成功した。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] コースの構成ゴルフコースは、当初はその規模・形態に特定の規格が設けられていたわけではなく、自然そのものを利用して競技が行われていたが、長い年月の間にその標準ができあがった。 コースは18ホールを基本として全長6000~7000ヤード(1ヤード=0.91メートル)前後の距離をもち、パーpar(基準打数)72が標準のタイプである。これを一巡(ラウンド)するのに約4時間を要する。日本のコース設計では、食事や休憩のためにクラブハウスを中央に配して、9ホール(ハーフ)を終えると自然にハウスに戻れるデザインが多い。前半の9ホールをアウトコース、後半の9ホールをインコースといい、各コースはロングホール2、ミドルホール5、ショートホール2の計9ホール、全体で18ホールからなっている。その基準は、ショートは250ヤード以下、ミドルは251~470ヤード、ロングは471ヤード以上で、ショートのパーを3、ミドルを4、ロングを5とし、合計パー72を標準とする。女子の場合は距離が短く、576ヤード以上のロングホールのパーは6になっている。ホールの距離は、ティーの中心からグリーン中心まで水平に計測し、曲がっている(ドッグレッグ)ホールでは、設計者の意図するフェアウェイの中心を通じて計測する。 さらに、コースにはコース・レーティングcourse ratingがある。パーは単に距離から割り出されたもので、コースによって自然の条件はいろいろ異なり、必然的にプレーの難易が生ずるから、地形、障害物、風土的特徴を距離に加えて、より科学的な標準打数を決めるために行われるコースの評価がコース・レーティングである。たとえば平坦(へいたん)・広闊(こうかつ)なコースはパー総計が72であっても、コース・レートは69であったり、優れた設計のむずかしいコースでは74になったりする。これらの評価は日本では日本ゴルフ協会が担当している。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] 基本的ルールとエチケット基本的ルールゴルフは一つの球を一つのクラブで打ち、コース上の18ホールをプレーすることによって成り立っている。また、野球やサッカーなど他の競技フィールドが比較的広いスポーツと比べてもゴルフは広大な場所で行われ、自然を相手にするスポーツなので、さまざまなことが起こる可能性もあり、他のスポーツに比べて規則が複雑になっている。そして、同時に大勢の人たちが一つの競技会に参加できるという特徴ももっているので、すべての参加者が公平性をもって競えるよう規則が複雑になっている。それと、もう一つの大きな特徴はレフェリーが立ち会わないことである。これは、プレーヤー自身がレフェリーであり、プレーヤー自身の判断で規則を守ってプレーしないといけないということを前提につくられているからである。自分だけが有利になるように、わざと違反をしたり、他人をだましたりするようなプレーヤーがいることは考慮していない。そのゴルフ規則が何百年もの間、こうして守られ続けている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] ゴルフ規則の改正について2019年1月1日からゴルフ規則は変更された。これまでもゴルフ規則は4年ごとの改正を行ってきたが、2019年の変更は単なる改正ではなく新しいゴルフ規則への移行となっている。現在のプレー形式はほとんどの場合ストロークプレー方式を採用しており、多くのプレーヤーが同時に競えるようになっている。しかし、ゴルフコースという広大なエリアでプレーされるため、ゴルフ規則も複雑になりすぎていた。公平性を保つには致し方ないが、そのためにラウンド時間がかかりすぎたり、新しいゴルファーの参入を妨げてしまったりという現状を改めるために、新しいゴルフ規則へと移行された。もともと、ゴルフ規則とはプレーヤーの誠実さに頼り、プレーヤーひとりひとりがゴルフ規則を守ってプレーするということから成り立っているが、新しいゴルフ規則ではいままで以上にプレーヤーの誠実さを求める内容となった。長年ゴルフをしてきたプレーヤーの多くは、最初のうちはとまどいもあったようだが、規則全体がわかりやすくなった、プレーの時間が短くなった、と実感しているようである。ただ、変わっていないのはゴルファーはつねに他のプレーヤーに心配りをし、コースを保護して安全確認を怠らず、礼儀正しさとスポーツマンシップを示しながら洗練されたマナーでふるまうべきであるということである。 [飯田雅樹 2020年4月17日] エチケットとマナー一般的にゴルフはエチケットとマナーがたいせつだといわれている。では、エチケットとマナーでは何が違うのかというと、マナーは規則ではないが守らなければならないもの、エチケットは他人に対しての気配りである。たとえばバンカーから出た後、そのバンカーをきれいにならすのがマナーである。ならさなかったからといって規則違反になるわけではないが守らなければならないことである。では、エチケットは何かというと、ならすときに使ったバンカーレーキ(バンカーの砂をならすために置かれているもの)を次に使う人のために取りやすい場所に置いておく気配りなどをいう。 プレーヤーはコース上の他のプレーヤーたちにも心配りをしなければならない。他のプレーヤーがアドレスに入ったら、むやみに動いたり、話したり、不必要に音をたてたりして、他のプレーヤーのじゃまになるようなことをしてはならない。また、プレーヤーはコース内に持ち込んだ電子機器が他のプレーヤーの集中を乱すことがないように留意すべきであり、ティーイングエリアでは自分の打順になるまでティーアップ(ティーイングエリアで球をティーペグにのせること)してはならない。そして、他のプレーヤーがプレーを始めようとしているときに、そのプレーヤーの球の近くや真後ろ、あるいはホールの真後ろに立ったりしてはならない。パッティンググリーン上では他のプレーヤーのプレーの線の上を歩いたり、他のプレーヤーがストロークしているときにプレーの線上に影をおとしてはならず、同じ組のプレーヤー全員がそのホールのプレーを終えるまで、その組のプレーヤーはパッティンググリーン上かその近くで待っているべきである。また、安全面の確認も怠らず、人の近くでは素振りをしないようにし、前の組のプレーヤーが球の届く範囲外に出るまではプレーを始めてはならない。そして、プレーヤーは自分の順番になったらすぐにプレーできるように準備し、ホールのプレーが終わったらすぐにそのパッティンググリーンから離れ、後ろの組に迷惑をかけないようにしなければならない。また、プレーのペースを保つことも重要で前の組との間隔をあけすぎないように速やかなプレーのペースを維持することが重要である。 [飯田雅樹 2020年4月17日] コースエリアの規則ゴルフは次の五つのコースエリアでプレーを行う。球がどのコースエリアにあるかによって、プレーや救済を受けるときに適用される規則は異なる。 〔1〕ティーイングエリア teeing area 〔2〕ジェネラルエリア general area 〔3〕バンカー bunker 〔4〕ペナルティーエリア penalty area 〔5〕パッティンググリーン putting green [飯田雅樹 2020年4月17日] ティーイングエリアスタートホールの順番はくじ引きなどで決められる。次のホールからは最初にプレーする人をオナーhonorといい、前のホールのスコアがよかった(少なかった)順となる。同じスコアの人同士の順番は変わらない。二つのティーマーク(ゴルフコースによってさまざまな形があるが目印となる人工物)の前方を結び、ティーマークの外側から後方2クラブレングスからなる長方形のエリア内に球がなければならず、球がエリア内であればスタンスはエリア外でもかまわない。プレーしているホールのティーイングエリア内であれば何打目であろうとティーアップした状態でプレーすることができる。このエリア内からプレーするときは何打目であるかを問わず、設置されているティーマーカーは動かすことはできない。ティーアップしている球が(クラブが当たるなどして)ティーから偶然落ちても罰はなく、ふたたびティーアップしてプレーすることができる。大勢のプレーヤーがこの狭いエリア内からプレーするため、エリア内の地面の凹凸を直したり、じゃまな芝や草をちぎってもライ(球の置かれている状態)の改善とはならず罰はつかない(他のエリアでは罰がつく)。 [飯田雅樹 2020年4月17日] ジェネラルエリアプレーしているホールのティーイングエリア、バンカー、ペナルティーエリア、プレーしているホールのパッティンググリーン以外の場所。いわゆる、フェアウェイfairway(芝地を刈り込み、球を打ちやすい状態に保つよう配慮されている地域)とラフrough(フェアウェイ以外の、意図的な非整備地帯で、雑草、低木、樹林などからなる)がその代表となる。そのため、バックティー(コースの各ホール最後方に配置される上級者用のティーイングエリア)を使用しているプレーヤーにはフロントティー(バックティーより前に位置する一般的プレーヤー用のティーイングエリア)はジェネラルエリアとなる。また、ティーイングエリアからプレーされた球はインプレーの状態となるので、基本的には球に触ったり球を取り替えたりすることはできない。ただ、委員会によってプリファードライとよばれるローカルルールが出されている場合、ジェネラルエリアで球をふいたり、違う場所にプレースすることが許されているケースもある。他に異常なコース状態(修理地など)や動かせない障害物による無罰での救済が許されるケースでも、球を拾いあげてふくことができる。基本的に罰ありの救済、罰なしの救済を受けるために球が拾いあげられたときは、その球をふくこともできるし、違う球にかえることも許されている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] バンカーバンカーとして定義されている砂のエリアで、砂地から球をプレーするプレーヤーの能力をテストするために特別につくられた区域であるため、いくつかの制限がある。まず代表的なものは、プレーヤーに砂の状態をテストすることを禁止していることである。このため、手やクラブなどで砂に触れることはできない。これは球を打つためのアドレス時やバックスウィングのときに偶然触れても罰がつくので、アドレス時からクラブを砂につけないように構えなければならないということである。また、スタンスをとるときに自分の両足をしっかりと据えることは認められているが、過度に足を潜り込ませたり、水平な区域をつくるために足でバンカーの側面の砂を落としたりしてスタンスの場所をつくることは認められていない。ただ、バンカー内の動かせる障害物や、ルース・インペディメントとして定義されている石や葉っぱなどを動かすことは許されている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] ペナルティーエリアペナルティーエリアとはコース上のすべての水域であり、球がそこに止まったらそのまま打つこともできるし、1打の罰によって救済を受けることも認められているエリアである。ペナルティーエリアには二つの種類があり、救済を受ける際の処置にも違いがある。イエローペナルティーエリアは委員会によって黄杭(くい)や黄線によってマークされているエリアであり、レッドペナルティーエリアは赤杭や赤線でマークされているエリアである。委員会によってマーキングされていないか、特定されていなかった場合は、レッドペナルティーエリアとして扱われる。救済を受ける際の処置の仕方は次の通りである。 〔1〕イエローペナルティーエリア (2)後方線上の救済 〔2〕レッドペナルティーエリア (3)ラテラル救済(レッドペナルティーエリアに対してのみ) [飯田雅樹 2020年4月17日] パッティンググリーンパッティンググリーンの上にある球はいつでもマーク(止まっている球の箇所を示す小さな人工物)して拾いあげふくことができる場所で、球が拾いあげられているときはインプレーではなくなり、球をリプレースしたときにふたたびインプレーの状態となる。パッティンググリーン上の砂やバラバラの土は罰なしに取り除くことができる(ティーイングエリアでも認められるが、それ以外のエリアでは取り除けない)。また、パッティンググリーン上で人や動物などの外的影響によってつくられた損傷は修復することができる。たとえば、ボールマーク(パッティンググリーン上にある打球の落下跡)や芝の張り替え跡、古いホール(穴)の埋め跡や靴による損傷(スパイクマークなど)、メンテナンス作業によって傷つけられた擦り傷や、動物の足跡や蹄(ひづめ)によるくぼみも含まれる。また、他のエリアと違い、プレーヤーのインプレーの球が偶然にプレーヤーやキャディによって動かされてしまっても、無罰で元の位置にリプレースしなければならない。プレーした球が旗竿(はたざお)に当たっても無罰なので、旗竿をそのままにした状態でプレーするのか取り除いてからプレーするのかを、プレーヤーはプレーする前に決めなければならない。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 競技のおもな形式ゴルフ競技は、おもにマッチプレーmatch playかストロークプレーstroke playの形式で行われる。 〔1〕マッチプレー 〔2〕ストロークプレー 〔3〕その他のプレー形式 (2)フォアサム foursome(通称、オルタネートショット) (3)フォアボール four-ball [飯田雅樹 2020年4月17日] 罰ありの救済アンプレヤブルコース上のペナルティーエリア以外のすべての場所で、プレーヤーの球がむずかしい状況から脱出するために1打の罰を払い、別の場所からプレーすることができるプレーヤーの権利である。たとえば、プレーヤーの球が木の上にのっていたり、木の根元にはまり込んでいて、プレーすることが困難な場合に有効な処置でもある。アンプレヤブルを宣言できるのはプレーヤーのみで処置の仕方は次の通りである。 〔1〕ストロークと距離の救済(後述の「ストロークと距離の罰に基づく救済」参照) [飯田雅樹 2020年4月17日] ストロークと距離の罰に基づく救済プレーヤーの球を3分以内にみつけられなかったり、プレーヤーの球と確認できなかったとき、または、球がアウト・オブ・バウンズに止まったとき、プレーヤーは1罰打のもとストロークと距離の救済を受けなければならない。処置の仕方は、直前のストロークを行った場所からホールに近づかない1クラブレングス以内の救済エリアに、元の球か別の球をドロップ(ティーイングエリアからプレーされていた場合はティーイングエリアからティーアップして打ち直し)してプレーを再開しなければならない。第1打目がアウト・オブ・バウンズであった場合は、1打目をカウントして1罰打を加える。そして、打ち直しとなるので次は3打目となる。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 暫定球プレーヤーによってプレーされたばかりの球が紛失する可能性のある場所に飛んでいったり、アウト・オブ・バウンズである可能性がある場合に、球を探してから元のプレーした場所に戻るのは時間がかかるため、時間節約のため暫定的に別の球をプレーすることが許されている。暫定球をプレーした後に元の球がみつかった場合は、プレーされた暫定球は放棄されなければならない。また、最初の球があると推定する場所とホールから等距離、または、ホールから遠い所から暫定球を続けてプレーする限りにおいては、暫定球としての状態のままでその球をプレーすることができるが、球があると推定する場所よりもホールに近づいた場所からストロークを行ってしまうと、その暫定球がストロークと距離の罰のもとにインプレーとなる。その後に最初の球がみつかっても最初の球は紛失球となるので、この球でプレーしてしまうと誤球をプレーしたことになる。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 救済エリアに球をドロップすること規則により救済エリアに球をドロップするときは、つねに元の球か別の球をドロップすることができる。ドロップはプレーヤー自身がドロップしなければならず、球は膝(ひざ)の高さからプレーヤーや用具に触れないように真下にドロップされなければならない。また、球を投げたり回転をかけたり転がすことなく真下にドロップされなければならない。ドロップされた球は救済エリアに落ちなくてはならず、救済エリアに落ちた球が救済エリアから外に出た場合は再ドロップをしなければならない。再ドロップした球も救済エリアの外に止まった場合は、2度目にドロップしたときのコース上に落ちた場所にリプレースすることによって救済エリアにドロップする処置は終了したことになり、球がそこに留まった時点でプレーヤーの球はインプレーの状態に戻ったことになる。 [飯田雅樹 2020年4月17日] ローカルルール最大スコアストロークプレーの原則はホールアウトすることなので、最大スコアがローカルルールでの採用となる。最大スコアがストロークプレーの一つの形式であり、プレーヤーの各ホールでのスコアを委員会が設定した最大のストローク数に制限する形式である。たとえば、パー(規定打数)の2倍のスコア、決められたスコア、または、ネットダブルボギー(ハンデ数を差し引いたダブルボギー)を委員会が最大スコアと決定した場合、実際のスコアが最大スコアを超えたとしても、決められた最大スコアがそのプレーヤーのスコアとなる。また、ホールアウトしなくてもそのプレーヤーには最大スコアがそのホールのスコアとなる。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 紛失球やアウト・オブ・バウンズの球についての特別なローカルルール暫定球をプレーしなかった場合で、球がみつからなかったとき、またはアウト・オブ・バウンズであった場合、規則ではストロークと距離の罰のもとに元の場所に戻り、球を打ち直さなければならないが、一般的なラウンドではプレーのペースに著しく問題が生じるケースもあるため、このローカルルールがつくられている。その目的は直前のストロークを行った場所に戻らずにプレーヤーがプレーを続けることができるように、追加の救済の選択肢を委員会が規定することを認めることである。また、このローカルルールはゴルファーがカジュアルにラウンドするときや、仲間内のコンペでプレーする一般的なプレーにだけ適しており、このローカルルールを高い技量のレベルの競技会などで使うのは妥当ではない。これは、暫定球でプレーしなかった場合の規定で、自分の球をみつけることができなかった場合やアウト・オブ・バウンズとなっていたときに、決められたルールのなかで、その球を紛失した近辺やアウト・オブ・バウンズとなった場所近辺から、2打の罰を払い別の球を定められたエリアからプレーできるというものである。 [飯田雅樹 2020年4月17日] ハンディキャップhandicap。ゴルフは子供から大人まで、初心者から上級者まで同時に競えるゲームである。それはハンディキャップがあるからである。「18ホール・パー72」という場合、ハンディキャップ20の人が95ストロークでラウンドしたら、95からハンディキャップ20を引いたネットスコアは75で、ハンディキャップ30の人が95ストロークでラウンドしたら、95からハンディキャップ30を引いたネットスコアは65ストロークとなる。つまり、ハンディキャップがあることで技量に差があっても同時に競うことができるのである。 〔1〕オフィシャルハンディキャップofficial handicap 〔2〕プライベート・ハンディキャップprivate handicap [飯田雅樹 2020年4月17日] アマチュアとプロフェッショナルアマチュアゴルファーとは一般的ゴルファーのことをいい、ゴルフで報酬や営利を目的としない一般的なプレーヤーである。日本ゴルフ協会(JGA)のJGA競技や各地区で行われているゴルフ競技に参加することができる。プロフェッショナルゴルファーは営利や報酬を目的とし、日本プロゴルフ協会(PGA)のプロテストに合格したトーナメントプレーヤーズと、ティーチングプロ実技審査に合格し、ティーチング実技講習に合格した者と、日本女子プロゴルフ協会(LPGA)のプロテスト、ティーチングプロ実技審査に合格し、PGA主催のティーチングプロの実技講習に合格した者をいう。これらの者にはライセンスカードが発行され、海外でもプロフェッショナルとして活動ができる。男子プロは日本ゴルフツアー機構(JGTO)のクオリファイングトーナメントを通過した者がジャパンゴルフツアーJAPAN GOLF TOURに出場することができ、女子はLPGA会員でクオリファイングトーナメントを通過した者がLPGAツアーに出場できる。アマチュアゴルファーはプロのオープントーナメントに参加できるが、賞金はもらえない。プロはアマチュアのゴルフ競技に参加することはできない。日本のゴルフ場やゴルフ練習場で正式なゴルフレッスンを行っているのはPGA会員とLPGA会員である。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 用具用具の使用プレーヤーはラウンド中に自分のプレーを援助する用具(たとえば、手袋やサングラス)を使用することができるが、ゲームの挑戦に不可欠である技術や判断の必要性を人工的になくしたり(たとえば、手首などを固定させる用具や風速計、傾斜を測定する用具を使用すること)、軽減する用具(クラブと球以外)を使用したり、ストロークを行うときに異常な方法で用具(クラブと球を含む)を使用することはできない。「異常な方法」とは、意図された使用方法とは根本的に異なる方法や、ゲームをプレーすることとは通常受け入れられない方法を意味する(たとえば、脇(わき)にタオル等をはさんでスウィング中に脇が締められるようにするなど)。用具の使用についてはラウンド中に認められるものと認められないものがあるが、それは次の通りである。 〔1〕距離や方向の情報 〔2〕風や他の気象条件に関する情報 〔3〕手袋やグリップ補助具 〔4〕ストレッチ機器とトレーニングまたはスウィング補助器具 〔5〕医療上の理由のために使用する用具 〔6〕障がいをもつプレーヤーのための用具規則の修正 [飯田雅樹 2020年4月17日] クラブプレーヤーはストロークを行うとき、用具規則に適合しているクラブを使用しなければならない。また、クラブを改造したり、偶然に変えられたときであっても、規則に適合するものでなければならない。しかし、適合していたクラブが通常の使用で摩耗して変わったとしても、そのクラブは適合クラブのままである。また、ラウンド中にクラブが損傷した場合は、その損傷したクラブを続けて使うこと、そして、可能であれば修理して使うこともできる(プレーを不当に遅らせないことが条件)。ただ、ラウンド中にクラブの性能特性を故意に変えることは許されていない。たとえば鉛を貼(は)ったりはがしたり、専用レンジを使い、ロフト角度(クラブフェースの傾斜角)を変えたり、クラブフェース(ヘッドの打撃面)の向きを変えたりすることはできない。そして、プレーヤーがラウンドで持ち運べるクラブの本数は14本までと制限されており、14本に達していない状態でラウンドを始めた場合は14本に達するまで追加することはできるが、14本に達したとき、それ以上追加することはできない。 [飯田雅樹 2020年4月17日] クラブの進化ゴルフクラブは1本のシャフトと一つのクラブヘッドからなっている。ゴルフクラブは大きく分けて、ウッドwood、アイアンiron、ユーティリティクラブutility clubがある。昔のゴルフクラブではシャフトにヒッコリー材が使われていたが、1900年代前半にスチールシャフトが出現し、1928年にはジーン・サラゼンによってサンド・ウェッジsand wedgeが開発され、バンカーからのショットの難易度が劇的に変わった。また、1960年代にはゴム製のグリップも登場し、キャビティー・バック・アイアンcavity back ironも出現した。ウッドでは長年パーシモン・ヘッドpersimmon headが使われていたが、1970年代にはメタルウッドも現れ、1990年代に登場したチタンヘッドドライバーが現在の主流となっている。チタンヘッドは素材が軽いため、大きなクラブヘッドがつくられるようになり、長いシャフトでも楽に振れるようになり、飛距離を稼げるようになった。また、クラブセッティングも時代とともに変わってきていて、フェアウェイウッドfairway woodやロングアイアンlong ironがだんだん姿を消し、ユーティリティクラブが主流となってきている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] クラブの特徴種類別に分けると、ウッド、アイアン、ユーティリティクラブ、パターである。 ウッドには、1番ウッド(ドライバー)、2番ウッド(ブラッシー、フェアウェイウッド)、3番ウッド(スプーン、フェアウェイウッド)、4番ウッド(バフィー、フェアウェイウッド)、5番ウッド(クリーク)があり、近年では、7番、9番、11番ウッドも主流になりつつある。 1番ウッド(ドライバー)はゴルフをプレーするなかで、もっとも飛距離がでるクラブであり、ロフト(角度)が小さいので、ティーアップできるティーショットで使われるのが一般的である。ロフトにはメーカーにもよるが、9度、10度、11度といろいろあり、ロフトが小さいほど球があがりにくく、初心者にはロフトが大きいものがやさしく打てるため向いている。現在のドライバーはロフト調整ができたり、クラブヘッドの向きを調整できるクラブも多くあるので、これらのクラブで自分にあったクラブを選ぶことが重要である。また、クラブ選びで重要なのがシャフト選びである。シャフトにもいろいろ種類があり、長いシャフトもあるし短いシャフトのものもある。クラブの長さは18インチ(0.457メートル)以上で、パターを除いて48インチ(1.219メートル)以下と規則で決められている。一般的には短いほうがやさしいが飛距離が出にくいといわれている。また、シャフトの重量は重すぎると振り切れなくなり、軽すぎるとスウィングが不安定になりやすい。シャフトはフレックス(硬さ)が重要であり、メーカーによって多少の違いもあるが、一般的にフレックスの種類は6種類ある。シャフトが柔らかい順番に、L(レディス)、A(アベレージ)、R(レギュラー)、SR(スティッフレギュラー)、S(スティッフ)、X(エキストラ)である。ドライバーのヘッドスピードにあったフレックスを選ぶのが重要である。シャフトのトルク(シャフトのねじれ)は球が曲がりづらいのが3.5以下であり、少し曲がっても飛距離を重視する場合には3.5以上のトルクのシャフトが選ばれる。また、シャフトにはキックポイント(シャフトが一番しなるポイント)にも種類があり、グリップ側が硬くクラブヘッド側が柔らかい先調子タイプ、グリップ側が柔らかくクラブヘッド側が硬い元調子タイプ、グリップ側とクラブヘッド側が硬い中調子タイプ、グリップ側とクラブヘッド側が柔らかいダブルキックタイプの4種類のタイプがある。先調子タイプは球があがりやすく初心者向きであり、元調子タイプは球があがりすぎるのを嫌う上級者タイプである。中調子タイプはタイミングがとりやすく、ダブルキックタイプはタメがつくりやすく、球のつかまりやすさに優れているシャフトタイプといわれている。 フェアウェイウッドはドライバー以外のウッドであり、2番ウッドはほとんど出回っておらず、一般的には3番ウッド(スプーン)から下のクラブをさす。形はドライバーに似ているがクラブヘッドは番手(数字)が大きいほど小さくなっている。芝の上から直接打てるクラブで飛距離が出しやすい。ロフトが大きいほど球があがりやすいが、シャフトが長く重心も深いため、むずかしいクラブといえる。最近の傾向としてはフェアウェイウッドが少なくなってきていて、かわりに多くなってきているのがウッド型ユーティリティクラブである。フェアウェイウッドよりもやさしく打てるので多く使われるようになっている。フェアウェイウッドよりもシャフトが短い分簡単に打てるが球があがりづらく、飛距離も出しづらい。次にアイアン型ユーティリティクラブがあり、アイアンに似たつくりになっている。ロングアイアンよりも球があがりやすいが、ウッド型ユーティリティクラブより球があがりづらい。 アイアンはロングアイアン、ミドルアイアン、ショートアイアンとある。ロングアイアンは1番アイアンから4番アイアンまでのクラブであり、ミドルアイアンは5番アイアンから7番アイアンまでのクラブである。8番アイアン、9番アイアン、ピッチング・ウェッジをショートアイアンとよび、ロングアイアンは球があがりづらくむずかしいクラブであるため、ロングアイアンを使う人はほとんどいなく、ユーティリティクラブが主流となっている。メーカーのアイアン販売も6番アイアンからの販売が主流となってきている。アイアンは番手が大きい数字のクラブほどロフトが大きく球もあがりやすいので、グリーンを直接ねらうクラブである。次にロフトが大きいのがアプローチ・ウェッジであり、もっともロフトが大きいクラブはサンド・ウェッジである。ロフトが大きいアプローチ・ウェッジやサンド・ウェッジはグリーンの近くからのアプローチで多く使われている。とくにサンド・ウェッジはバンカーショットのために開発されたクラブであり、バンカーから打つときに適していて球がもっともあがりやすいクラブである。ただ、最近はアプローチ・ウェッジ、サンド・ウェッジとはよばずにロフト角度でよぶ傾向にある。メーカーにもよるが一般的にアプローチ・ウェッジはロフトが50度から54度、サンド・ウェッジは55度から60度までのものをいう。アイアンセットはピッチング・ウェッジまでがセット売りの主流となっているのでそれより下の番手は単品のウェッジを組み合わせるのが主流となっている。50度、54度、58度と組み合わせたり52度、56度、60度と組み合わせる組み方もある。 パターは絶対に必要なクラブである。パターにもさまざまな種類があるが、代表的なタイプとしてまずあげられるのがピンタイプである。パターの前後が細長く、前後に重量があるため芯(しん)を外して打ってもまっすぐ転がりやすく初心者向きといえる。また、スイートエリア(芯)が広くて目標に対して構えやすい特徴をもっている。次にL字タイプでシャフトとヘッドを見ると、名前の通りLの字に似ていてL字タイプといわれている。アイアンの形にも似ているのでショットの感覚で打ちたい人に向いている。マレットタイプは重心距離が深いためまっすぐ打ち出しやすいといわれていて、ヘッドが大きく重いためヘッドの重さで距離を出しやすくなってもいる。ネオマレットタイプはマレットタイプに似て、ヘッドの重さで距離が出しやすく、まっすぐに打ち出しやすい。形状もスクエア(正方形)に近いため、目標に構えやすく、ヘッドが大きいためミスヒットしてもまっすぐ転がりやすい。センターシャフトタイプのパターは、名前の通りシャフトがヘッドのセンターにあり、シャフトとクラブフェースが一直線に見えて引っかけづらいという特徴をもっている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 球ラウンドのプレーで使用される球は用具規則に適合する球を使用しなければならない。球の重量は1.620オンス(45.93グラム)以下でなければならず、球の直径は1.680インチ(42.67ミリメートル)以上でなければならない。また、球は球対称(回転させても同じ形で、どの角度から見ても同じ形状であること)な球の特性とは異なる特性をもたせるようにデザインされたり、製造されたり意図的に手を加えられたものであってはならない。球の初速も決められた数値を超えてはならず、球の飛距離もR & AとUSGAによって承認された機器でテストされたときに、その規定された距離を超えてはならないなど多くの規定があり、それらをクリアした球が用具規則に適合された球となり、ラウンドのプレーで使用できる球となる。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 球の進化ゴルフで使用される球は最初、堅い木を丸く削られてつくられたものを使用していたが、15世紀中ごろからフェザーボール(革の中へ羽毛を詰めたもの)が使われるようになり、19世紀中ごろからガッタパーチャ球gutta-perchaballが出現した。これは、熱帯植物の樹脂からとったゴム様のグタペルカ(ガッタパーチャー)を丸めたものであった。さらに、球の表面に刻み目をつけることによって、高く、まっすぐに飛ぶことが発見されたのが現在のディンプル(くぼみ)の始まりである。1898年、現在の球の前身ともなるハスケル球が現れ、飛距離が著しく増大した。これは、固いゴム芯をインドゴムの細糸で巻き、グタぺルカの皮膜でくるんだものである。1990年代は糸巻ボールが主流になり、2000年代に入るとウレタンカバーの多層構造(ソリッドコア)タイプが出現し、飛距離と耐久性に劣る糸巻ボールは衰退していった。現在では、カバーが硬く中身が柔らかい飛距離重視のディスタンス系とカバーが柔らかく中身が硬いスピン系の球が主流となってきて、昔から比べてもゴルフ用具のなかでもっとも進化したのがゴルフボールではないかといわれている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] スパイクシューズゴルフ場は天然の芝でつくられているので、ゴルフをプレーするのに非常に滑りやすくなっている。そこで滑らないように靴底に鋼製スパイクをつけたスパイクシューズが誕生し、長い間メタルスパイクが使われていた。しかし、現在はグリーンを傷つけてしまうためほとんどのゴルフコースで禁止されている。現在多く使用されているのがソフトスパイクであり、プラスチックや樹脂でつくられている。以前と違い鋲(びょう)が爪のような形をしているため、鋲が芝をしっかりつかめるようになり滑りにくくなっている。スパイクレスシューズは鋲がついていないタイプで、底の部分は滑りにくい加工がされている。鋲がついていないので普段から履けるようになっている。また、現在では以前から使われている靴ひもタイプに加え、ダイヤル式タイプも使用されるようになっている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 基本技術地上に静止しているゴルフボールをヒットするにはどんな打ち方をしても自由であるが、距離と方向の両方を正しく決めるには、クラブを一定した軌道に沿ってスウィングswingするのがもっとも効果的であるから、スウィングの基本的な原則はほとんど定石化されている。ただしプレーヤーの体格や力量は千差万別なので、その相違によって枝葉的調整が加味される。したがって、一流プロたちが一見異質のスウィングをしているようでも、その肝要なポイント、とくにインパクト(クラブが球に当たる瞬間)ではまったく符節があっている。要するに、ゴルフ・スウィングは、腕とクラブによる円運動であって、その軌道上にあるボールがクラブヘッドによって打ち出される受動作用にすぎないと理解すべきであろう。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] グリップgrip クラブと人体を結合させるには両手でクラブを握る必要があるが、この握り方がグリップであって、正しいグリップはもっとも基本的なものである。グリップには次の3種があるが、いずれの場合も、右利きの者は右手が左手よりも下方のヘッドに近くなるから、そのために右肩がすこし下がるのが自然な形となる。 〔1〕ナチュラル・グリップnatural grip 野球のバットを握るときのように10本の指全部でシャフトを握るので、ベースボール・グリップの別称もある。 〔2〕インターロッキング・グリップinterlocking grip 右小指と左人差し指とを絡み合わせて握る方式で、手が小さく指の短い人が用いると両手の締まりがよくなり、スウィング中に緩まない効果がある。 〔3〕オーバーラッピング・グリップoverlapping grip 右の小指を左の人差し指の上に重ねて握る方式で、右利きの人は左利きに比べて右手が強力なのでそれを制約し、両手の一体化に有効である。イギリスのハリー・バードンがこのグリップを広めたためにバードン・グリップとも称され、もっとも多用されている。 なお、以上のグリップに共通するものとして、指を主体にして握る方法をフィンガー・グリップfinger gripといい、親指の付け根のたなごころで握るのをパーム・グリップpalm gripという。また、標準グリップをスクエア・グリップ、右手を開き左手をかぶせた握り方をストロング・グリップ、逆に右手をかぶせぎみにした握り方をウィーク・グリップという。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] アドレスとスタンススウィングは飛球線と平行の形をとり、それを行うために足場を固める構えをスタンスstanceという。バランスを保つためには、スウィングが大きいほど足幅を広げる必要があるが、自由なスウィングとバランスの保全は、「ドライバーのアドレスでほぼ肩幅の広さ」が定説である。スタンスには次の3種がある。 〔1〕スクエア・スタンスsquare stance 両足のつまさきを結んだ線が飛球線と平行になっている標準型で、左のつまさきを右よりもやや開いてセットすることで腰の回転を助成する。 〔2〕クローズド・スタンスclosed stance 右足をわずかに手前に引き、両つまさきを結んだ線が飛球線に対して右から左へクロスするようになる立ち方で、ボールに左回転を与えてフックhookさせる打ち方を容易にする。 〔3〕オープン・スタンスopen stance 左足をわずかに手前へ引き、両つまさきを結んだ線が飛球線に対して左から右へクロスする立ち方で、ボールに右回転を与えてスライスsliceさせる打ち方が容易となる。 どのスタンスをとるにしても、体重は両足の内側後半にかかっている感じで、両足に均分され、両膝(ひざ)をわずかに曲げる程度に緩め、しっかりと地面に定着されている感じが望ましい。ボールの位置は、左かかとの内側から飛球線と直角に交わる地点が標準で、クラブをボールの直後にあてがい、スウィングをおこすアドレスaddress(準備体勢)がとられる。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] バック・スウィング、ダウン・スウィングback-swing、down-swing スウィングは、後方への振り上げ(バック・スウィング)と前方への振り下ろし(ダウン・スウィング)の二つの部分で構成されるが、切れ目のない単一動作(ワンピース・スウィング)と理解すべきである。スウィングは、地面に対して傾斜した平面を形成するが、長身の者ほどその角度が直立し、これをアップライトuprightといい、短躯(たんく)または肥満の者は水平に近くなり、これをフラットflatという。いずれもスウィングは適正なタイミングによってコントロールされていなくてはならない。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] ドライバーショットdriver shot ドライバーは長打のティーショット用であるが、ティーアップの高さとボールの位置によって弾道の高低を変化させたり、またキャリー(滞空距離)をも変えることができる。スウィングの弧を大きくするほどクラブヘッドの速度が増して距離も増大する。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] フェアウェーウッドショットfairway wood shot 比較的ボールのライがよい場合の長打用で、ドライバーと異なり、ややダウンブロー(打ち下ろし)ぎみのスウィングでボールをとらえないと上昇力がつかない。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] ウッド型ユーティリティクラブによるショットウッド型ユーティリティクラブは、基本的にフェアウェイウッドが短くなったものであり、フェアウェイウッドの打ち方とあまり変わらないが、打ち込まずに滑らすように打つのがこつである。 [飯田雅樹 2020年4月17日] アイアン型ユーティリティクラブによるショットアイアン型ユーティリティクラブは、アイアンに比べて、ソールが幅広になっているため、無理せずに球があがるので、滑らすように払い打ちをするのがこつである。 [飯田雅樹 2020年4月17日] アイアンショットアイアンは、標的をねらうための正確さと、ライの悪いボールをたたき出すために発案されたもので、打ち方は、ウッドが箒(ほうき)とすれば、アイアンははたきと考えると、その性能を理解しやすい。 〔1〕ロングアイアンlong iron 1~4番までをロングアイアンと称しているが、ユーティリティクラブと比べても球が上がりづらく、スウィングにばらつきがあると使いこなせないためセット売りからは外れている。 〔2〕ミドルアイアンmiddle iron 5~7番のアイアンをさし、一般的に130~160ヤードの距離に用い、より正確なショットが要求される。ショットの特徴は、ダウンブローにショットすることによってボールにバックスピンをかけてグリーン上で止まる球を打つことである。 〔3〕ショートアイアンshort iron 8、9番アイアンとピッチング・ウェッジをさし、通常130ヤード以下の距離に用いられる。ショートアイアンの目標は旗(ピン)そのものであり、そのためにはいっそうボールにバックスピンをかけて、着地後ただちに停止できるショットが要求される。ダウンブローが有効で、クラブ自体もその作用を助ける構造となっている。 〔4〕ショート・アプローチshort approach グリーンから80ヤード以内のショットは多彩で、バラエティーがあるが、そのためのクラブとしてアプローチ・ウェッジとサンド・ウェッジがある。メーカーによっては52度とか58度といったように度数だけで表示しているものもある。 (1)ランニングショットrunning shot 3分の2以上を転がして旗まで寄せる打法で、方向の正確さという点でもっとも安全であり、使用クラブは普通ミドルアイアンやショートアイアンが多用される。 (2)ピッチショットpitch shot ボールを高くあげてボールを止めるショット。立ち木やバンカーを越して旗(ピン)をねらう場合に用いられるが、熟練の技が要求される。 (3)ピッチ・エンド・ランpitch and run ピッチとランニングとを併用したショットで、効果も両者の特質を兼備している。練習によって使用クラブ(通常ショートアイアン)のキャリーとランの割合を知っておくことが必要である。 (4)チップ・ショットchip shot ごく短い距離をランニングで寄せる打法をいう。 〔5〕パッティングputting 「パットに定型なし」というのが定説となっているのは、ボールをカップに沈めるのが究極目的だからである。しかし正しいパットの原則は、パターフェースが直角を保って、距離に応じて必要な速度で動くことであって、それをいかなる場合も実行できるようにするには独自の型をもつ必要がある。それらを大別すると三つの型となる。手首型(タップ式)は、フォロースルー(インパクトからフィニッシュまでの間)を小さくして手首の屈折でボールをピシッと打つので、必然的にヒット性が強くなる。腕型(ストローク式)は、両腕をラインに平行に動かしながらパターヘッドを振り子のように移動させる。肩型は、肩の回転に多く依存し、距離の大小をその回転度で決める。パットはフィーリング(感覚)が大きな要素を占め、さらにグリーンの傾斜と芝目を読んでその変化に適応したパッティングをしないと、単に打ち方が正しいだけでは成功率を高められない。 〔6〕特殊なライからのショット (2)下り坂(ダウンヒルdown-hill) 右足が左足よりも高くなるライでは、体重が左荷重になり、スウィング中に左へよろけ、トップボールになりやすい。それを避けるために右足寄りにボールを置く。スライスがかかりやすい。 (3)前上り(ハイ・ライhigh lie) ボールが両足よりも高い(たとえば土手の斜面など)場合には、ボールと体との間隔が近くなり、スウィングもフラットにならざるをえないので、体重のバランスに注意し、クラブを短めに持ち、コンパクトなスウィングを心がける。フックがかかりやすいので目標を右側に設定する。 (4)前下り(ロー・ライlow lie) ボールが両足よりも低い場合には、ボールとの間隔が遠くなるので、広めのスタンスをとって低い姿勢をとり、その姿勢を崩さずにボールをとらえる。(2)と同様に打球はスライスぎみになる。 (5)草深いヘビー・ラフheavy rough ボールが長い雑草の中に沈んでいるときは、ボールとクラブフェースの間に草の葉が挟まるから、飛距離は極端に短縮され、ボールも低くなる。ロフトの大きいクラブで脱出を優先させる。 (6)林間・樹木の交錯したなかから脱出する場合 梢(こずえ)を越すにはクラブフェースを極端にオープンに構えてカットショットし、木の枝下を低く抜くにはロフトの少ないロングアイアンを短く持ってコンパクト・スウィングに努め、脱出することに重点を置く。 〔7〕バンカーショットbunker shot ボールの手前の砂へクラブを打ち込み、砂といっしょにボールを飛ばす打法が使われ、これをエクスプロージョンexplosion(爆打)という。ボールの飛距離は削りとる砂の量とスウィングの大きさで決まる。それにはまず砂質を見分けることと、砂の状態を測知することが必要であるが、クラブを砂に触れてはいけないから、しっかり足場を固めると同時に、砂の状態を察知する。砂は産地によって礫(こいし)状のものから粉状のものまでいろいろあり、クラブヘッドへの抵抗を異にし、また乾湿によって砂の締まりぐあいが変わってくるので、いっそう複雑さを増す。エクスプロージョンにはサンド・ウェッジが使用されるが、固く締まった砂ではフランジ(輪ぶち)の厚いサンド・ウェッジははね返りが強すぎて危険の度合いも多く、この場合には9番アイアンなどで、砂を浅くとる。 〔8〕天候の影響下にあるショット (2)雨 地面湿潤でショットのランが殺され、またダフのミスを誘発しやすいので、できるだけボールをクリーンに打つ。 [水谷 準・塩田 正・飯田雅樹 2020年4月17日] 球質とミスショット打たれたボールはスウィングの独自な型によって、それぞれの球質をもつ。厳密にはストレート・ボール(まっすぐ飛ぶボール)はなく、通常どちらかに曲がる。右打ちの場合、まっすぐ飛んで、ボールが落ちぎわにすこし右にカーブするものをフェード・ボールfade ball、左にカーブするものをドロー・ボールdraw ballという。いずれも正しいボールで、球質に応じてコース戦略を考える。しかし、スウィングの軌道が飛球線をクロスしたり、クラブフェースがボールにスクェア(まっすぐ)に当たらないと、ボールは方向が狂ったり、右・左に大きくカーブしたりする。意識的(インテンショナル)に行うものを除いて、この曲がり方が著しい場合にはミスショットで、次のようなものがある。 〔1〕スライスslice 右へカーブするショットで、スウィングの軌道がアウトサイド・イン(ボールと目標を結んだ線の外側からクラブがボールに当たること)に入り、クラブフェースがオープン(右向き)でボールに接し、カットするからである。 〔2〕フックhook インサイド・アウト(ボールと目標を結んだ線の内側からクラブがボールに当たること)に入り、クラブフェースがクローズ(閉じて左向き)に当たると左カーブのショットとなる。 〔3〕プルpull(ひっかけ) スウィングの軌道が飛球線の外側から内側へクロスし、ボールは左へ直行する。著しいものをスマザーという。 〔4〕プッシュpush(押し出し) スウィングの軌道が飛球線の内側から外側へクロスし、ボールは右へ直行する。 〔5〕ダフduff ボールを直接打たず手前の地面をヒットしたため必要な距離が得られないミスで、しばしば犯す者をダッファーという。 〔6〕トップtopping ボールの赤道から上部へクラブのブレードが当たるとボールは上がらずにゴロになる。腕が縮むのと、上体が左へ流れる(スウェイ)のが原因であることが多い。 〔7〕スカイングskying(俗称、てんぷら) クラブヘッドがボールの底部を打つために高い球となる。スウィングを力むと上体が沈むし、手首の使用が過多になっておこる例が多い。 〔8〕シャンクshank ソケットsocketともいう。ボールがフェースの中心を大きく外れ、あるいはシャフトの挿入部(ソケット)に当たり、ボールは極端に右へ飛び出す。原因のうちもっとも多いのは、手だけでクラブを送り出す「手打ち」スウィングになることである。 [水谷 準・塩田 正 2020年4月17日] 競技会メジャートーナメント世界四大メジャートーナメントとよばれているのは、開催月順に並べると次の通りである。 (1)マスターズトーナメントMasters Tournament(4月開催) (2)全米プロゴルフ選手権 PGA Championship(5月開催) (3)全米オープン選手権 U. S. National Open Championship(6月開催) (4)全英オープン選手権 The Open Championship/British Open(7月開催) [飯田雅樹 2020年4月17日] グランドスラムGrand Slam。スポーツ界で初めてグランドスラムということばが用いられたのは、1930年に当時28歳でアマチュアであったボビー・ジョーンズが、当時の世界四大タイトル、全英アマチュア、全米アマチュア、全英オープン、全米オープンを1年間ですべて制覇したことから使われるようになった。現在の四大メジャートーナメントは前述のように変わっているが、1年間でグランドスラムを達成したのはボビー・ジョーンズただ一人である。複数年を要してメジャートーナメントを制覇した者をキャリア・グランドスラムとよび、ボビー・ジョーンズ(アメリカ)、ジーン・サラゼン(アメリカ)、ベン・ホーガン(アメリカ)、ゲーリー・プレーヤー(南アフリカ)、ジャック・ニクラウス(アメリカ)、タイガー・ウッズ(アメリカ)らが達成している。女子のメジャートーナメントは現在、ANAインスピレーション、全米女子プロゴルフ選手権、全米女子オープン、全英女子オープン、エビアン選手権と五大トーナメントで、キャリア・グランドスラムの達成者はルイーズ・サックスLouise Suggs(1923―2015。アメリカ)、ミッキー・ライトMickey Wright(1935―2020。アメリカ)、パット・ブラッドリーPat Bradley(1951― 。アメリカ)、ジュリ・インクスターJuli Inkster(1960― 。アメリカ)、カリー・ウェブKarrie Webb(1974― 。オーストラリア)、アニカ・ソレンスタムAnnika Sorenstam(1970― 。スウェーデン)の6名がいる。シニアのメジャートーナメントはシニア・プレーヤーズ選手権、全米プロシニアゴルフ選手権、全米シニアオープン、全英シニアオープン、リージョンズ・トラディションの五大トーナメントで、キャリア・グランドスラムの達成者はベルンハルト・ランガーBernhard Langer(1957― 。ドイツ)ただ一人である。日本人で海外メジャーの優勝者は、1977年に全米女子プロを制した樋口久子(ひさこ)(1945― )、2013年全米プロシニアを制した井戸木鴻樹(いどきこうき)(1961― )、2019年全英女子オープンを制した渋野日向子(しぶのひなこ)(1998― )、2021年にマスターズ・トーナメントを制した松山英樹の4名である。 [飯田雅樹 2021年4月16日] 日本のメジャートーナメント代表的な二大競技会が日本オープン(ジャパンオープン、1927年創設)と日本最古のゴルフトーナメントでもある日本プロゴルフ選手権(ジャパンプロ、1926年創設)であり、ほかに日本ゴルフシリーズ(1963年創設)、日本プロゴルフマッチプレー(1975年創設、現在休止中)と日本ゴルフツアー選手権(2000年創設)がある。女子ゴルフのメジャートーナメントは日本女子オープン(1968年創設)、日本女子プロゴルフ選手権(1968年創設)、ワールドレディスチャンピオンシップ(1973年創設)、LPGAツアーチャンピオンシップ(1979年創設)がある。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 日本のゴルフの現状日本は狭い国土でありながらアメリカ、イギリスに次いで現在世界第3位のゴルフ場数を誇っている。第二次世界大戦前の1940年(昭和15)には64コースまで増え、2002年(平成14)の2460コースをピークに2018年時点で2248コースまで減少している。ゴルフ場の多い都道府県は多い順番に北海道、兵庫県、千葉県である。北海道は減少傾向にあるが千葉県などは逆に増加傾向にある。 ゴルフ人口もバブル時代に最高潮を迎え、時代とともに減少傾向にある。とくに20代から30代の男性が減少している。それは自家用車をもたない若者が増えたのも原因の一つと考えられているが、逆に女性や時間とお金に余裕がある60代以上のゴルファーが増えているという統計もある。また、バブル期と比べてもプレーフィー(ゴルフコースの使用料)も低くなってきている。地方のコースなどはかなりの低料金となっているが、オリンピック正式種目にもかかわらず、1回プレーするだけで300円~1200円と、高額なゴルフ場利用税がいまだに残っているため、廃業せざるを得ないゴルフ場も増えており、ゴルフ人口の減少にもつながっている。 また、1926年に日本最古のゴルフトーナメントである日本プロゴルフ選手権が開催されてから多くの企業がスポンサーとなり、多くのゴルフトーナメントが開催されてきた。ゴルフトーナメントは他のプロスポーツに比べても賞金が高く、これによって多くの若者がプロゴルファーを目ざし、バブル期には青木功、尾崎将司、中嶋常幸、倉本昌弘などスター選手が活躍し、40試合近くのトーナメントが開催された。バブルの崩壊とともに徐々に衰退したが、最近では石川遼(プロトーナメント初優勝時、高校生)や池田勇太(ゆうた)(1985― )、アメリカPGAツアーで優勝している松山英樹などの活躍で盛り返し始めている。女子プロゴルフは歴史が少し浅く、全米女子プロに優勝した樋口久子、1987年アメリカLPGAツアーの賞金女王岡本綾子(あやこ)、1993年アメリカLPGAツアーでの優勝を果たした小林浩美(ひろみ)(1963― )などの活躍で人気も出始め、横峯(よこみね)さくら(1985― )、宮里藍(みやざとあい)(1985― )(プロトーナメント初優勝時、高校生)などの出現でブレークした。現在では鈴木愛(1994― )や、2019年全英女子オープンで優勝した渋野日向子をはじめ黄金世代、プラチナ世代とよばれる20歳前後の女子プロゴルファーの活躍で、男子トーナメントよりも人気が出ている。 [飯田雅樹 2020年4月17日] 代表的な日本のゴルフ団体(1)公益財団法人日本ゴルフ協会(JGA:Japan Golf Association) (2)公益社団法人日本プロゴルフ協会(PGA:The Professional Golfers' Association of Japan) (3)一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(LPGA:The Ladies Professional Golfers' Association of Japan) (4)一般社団法人日本ゴルフツアー機構(JGTO:Japan Golf Tour Organization) [飯田雅樹 2020年4月17日] [参照項目] | | | | | | | | | | [補完資料] |©藤田正純"> ゴルフコース(レイアウトの例) ©Shogakukan"> ゴルフクラブの各部名称 ©Shogakukan"> ゴルフクラブのロフトと飛距離の例 ©Shogakukan"> スタンスとグリップ ©Shogakukan"> ショート・アプローチ ©Shogakukan"> ショットの球質の名称 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
Recommend
United Nations Convention on the Law of the Sea
⇒ United Nations Convention on the Law of the Sea ...
《Oiwa Inari》 - Festive
… [Hirosue Tamotsu] [movie] There is a genre of J...
Plate fuse - Itafuse
…Low melting point alloys include cellulose (Sn, ...
Echis carinatus (English spelling)
…When excited, it inflates its body and makes a l...
Holometaboly
… [insect] The metamorphosis of terrestrial inver...
birdie
…An 18-hole course is usually designed with 4 sho...
Markgrafschaft
...A century later, Austria became a place of mig...
Near East
A regional concept centered on Western Europe, me...
Bretton Woods Agreements
The Bretton Woods Agreements were signed in 1944 ...
Koya version - Koyaban
These are Buddhist scriptures published at Mount ...
Eumenides
…The Erinyes and Apollo argued over the importanc...
Husband seed loan - Fujikitanekashi
In the Edo period, this meant that feudal lords wo...
Sanskrit Worterbuch (English spelling)
…In 1816, F. Bopp (1791-1867), who studied under ...
Okabe [town] - Okabe
Located in northwest Saitama Prefecture, between F...
Faysal I (English spelling)
In 1824, Muhammad ibn Saud's grandson Turki (...