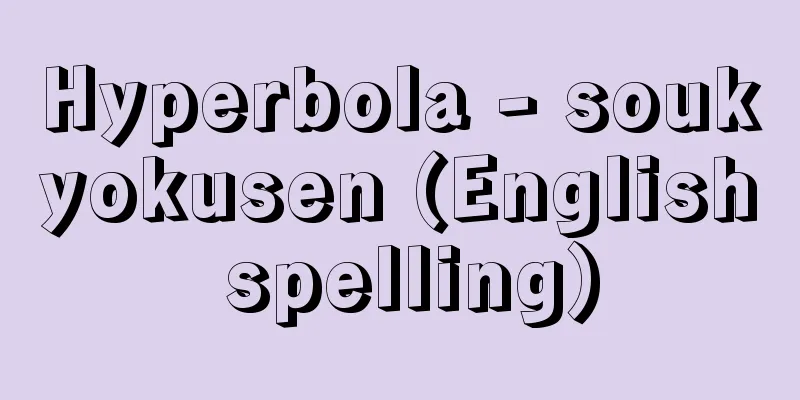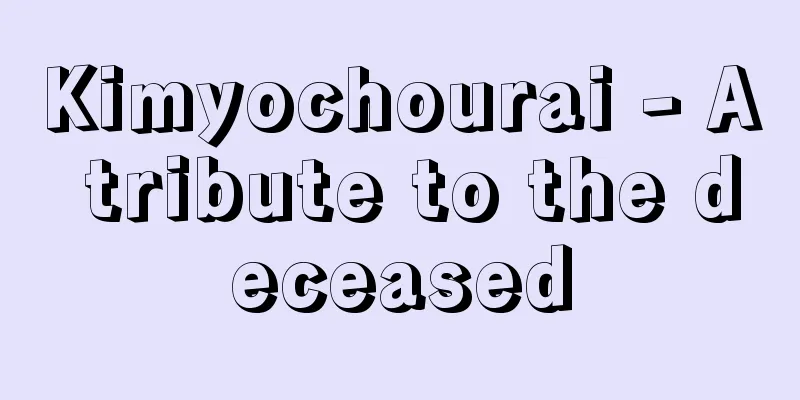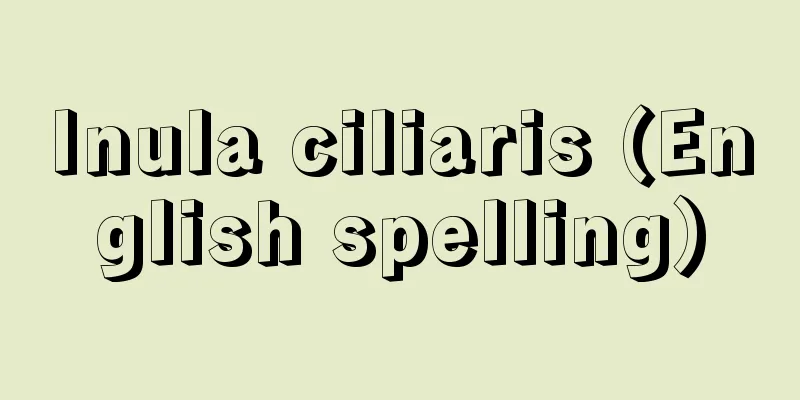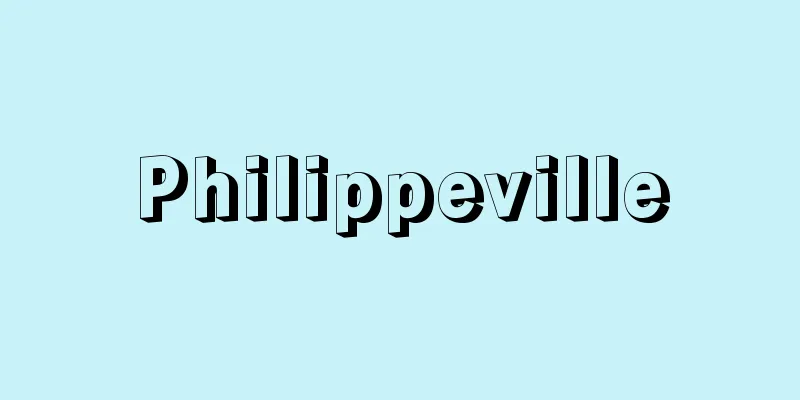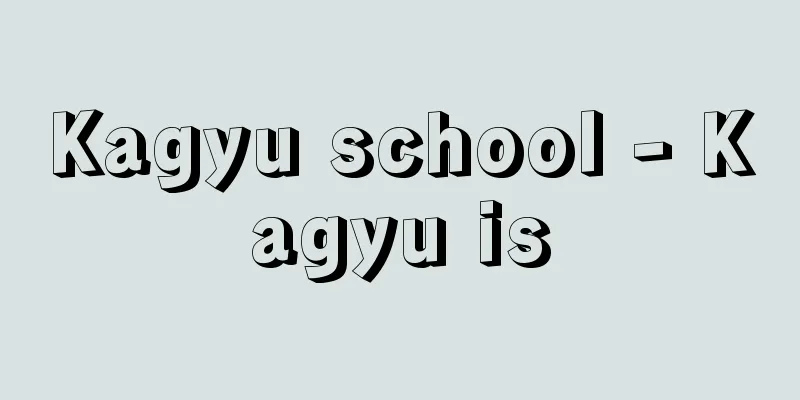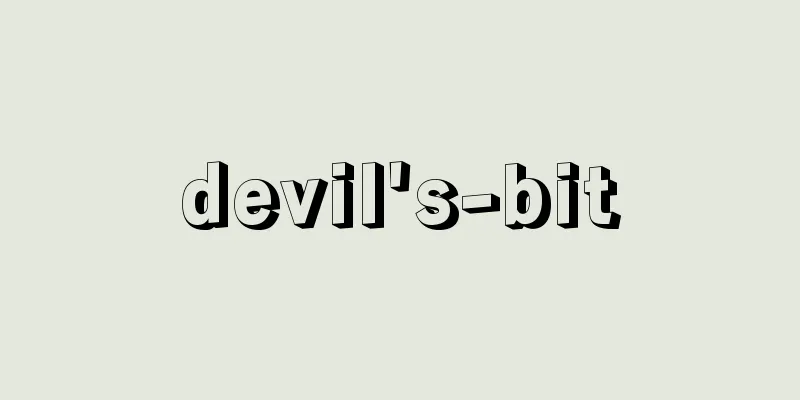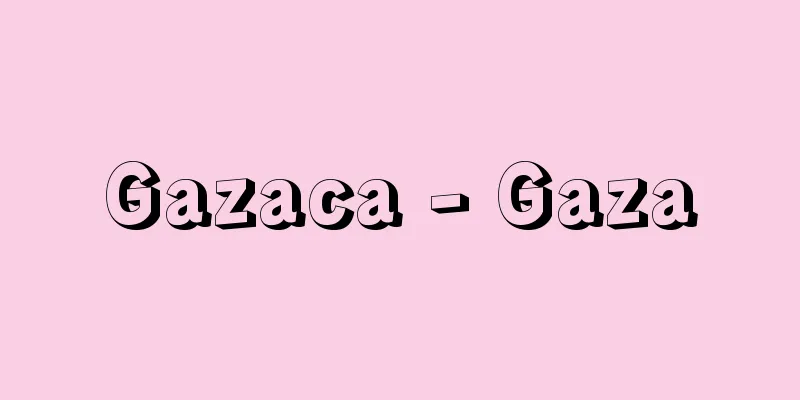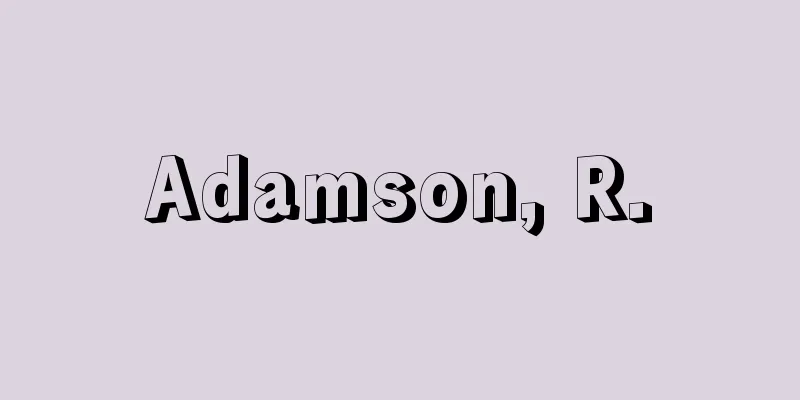Money - Kahei (English spelling) money English
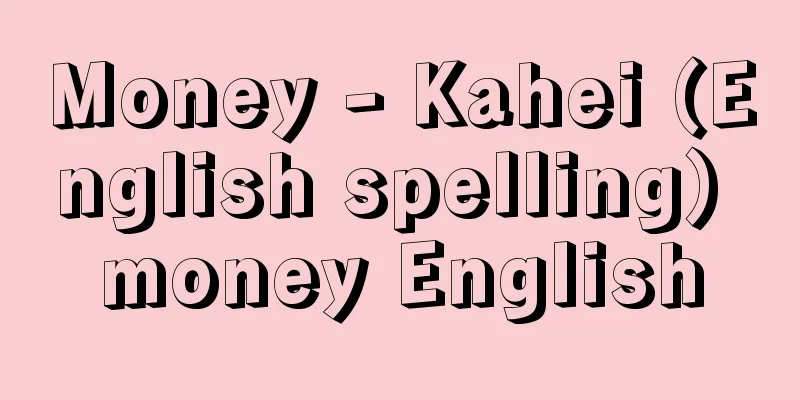
|
Modern capitalist economy is based on the division of labor and private property, and as a result, it is divided into countless individual economies (economic entities, unit economies). Therefore, the modern economy can be said to be one comprehensive economy composed of these countless divided individual economies. Economic entities include production entities and consumption entities, which are mutually dependent and connected to form a distribution economy and a market economy. Money is involved in this. In this way, money in the modern economy is a chain that connects each individual economy together with goods = commodities, but in this case, money can be either an intermediary or an objective entity. The former is the flow of money paid in exchange for the purchase of goods, and money functions as a means of purchase or distribution. In the latter, only money flows in one direction, and it is expected that more money will flow back (with interest). Here, money itself is the subject of demand and supply, that is, trading, as if it were a commodity. [Hara Shiro] Theories and theories on moneyMetallism and NominalismToday, there are two theories regarding the nature of money that has this role: metallurgy and nominalism. In a broad sense, the former includes the commodity theory and materialism, while the latter includes the state theory, the direct securities theory, the occupational theory, and the abstract theory. According to metallurgy, money is the most widely and generally accepted commodity. As a result, money, like other commodities, must have material value in itself. In other words, in the process of exchanging goods for goods, money is exchanged for goods that have value in themselves as a commodity that has value in itself. Thus, the essence of money is a valuable material, and money must be a commodity or valuable property, especially a precious metal. According to this theory, the existence of money without material value is not recognized, so paper money cannot be money. Even if paper money is in circulation, as long as it is government paper money, it is a symbol of value that arises from the function of money as a means of circulation. In other words, paper money is merely a substitute that saves on the use of money. Metallism explains that money has value as a commodity itself, and therefore can function as a unit of value to measure the value of other commodities. Therefore, the essential function of money is to be the unit of value, from which its functions as a means of circulation, a store of value, a means of payment, and a world currency are derived. This theory has been developed by British classical economics and Marxian economics. The main scholars of this theory include Ricardo, Knies, Hildebrand, and Marx, and it was Marx in particular who established it as a monetary theory based on the labor theory of value. This is also called the commodity theory. In contrast, nominalism denies the general value measure function based on commodity value, which is the material value asserted by metallurgy, and seeks the essence of money in its abstract function - a general exchange or means of circulation. A representative theory that takes the nominalist position is F. Knapp's state theory. This theory holds that money has legal validity only through the legal system of a nation, regardless of its material, and seeks the essence of money in its means of circulation. Nominalism has further developed into the ticket theory (indicative instrument theory) of F. Bendiksen and K. Elster, which holds that money is a general participation ticket for goods, the professional theory of L. F. Mises and K. Helfferich, which holds that money is everything that performs the function of money, and the abstract theory of R. Liefmann, which holds that money is an abstract unit of calculation that expresses the ratio of commodity values. In this way, nominalism can be said to have become popular mainly in Germany since the beginning of the 20th century. Keynes, a leading modern economist in the first half of the 20th century, also adopted the nominalist position in his Treatise on Money (1930), regarding money as merely a means of purchasing, and used the concept of money of account. Keynes' money of account is the one in which debts, prices, and general purchasing power are expressed, and corresponds to the function of money as a measure of value in metallurgy. Below, I would like to explain the monetary theory in modern economics, which follows the nominalist tradition, and the monetary theory in Marxian economics, which represents metallism. [Hara Shiro] Money in Modern EconomicsTwo types of money: money of account and real moneyMoney is a means or a social institution used to settle credit and debt relationships that arise when completing a transaction. There are two types of money: money of account and real money. Money of account is a unit generally used to count and compare economic values, such as when expressing the size of national income or comparing the value of 1 kilogram of iron with the value of 1 kilogram of cotton. It is called the yen, dollar, euro, etc., and generally varies from country to country. Many money of account are also units of weight, but this is merely a vestige of the past when most settlements were made by measuring the weight of the metal used. As can be seen from the fact that the Japanese money of account, the yen, simply represents a round shape and has nothing to do with weight, money of account is an abstract unit that is separate from units of weights and measures, time, etc. and is used solely for economic calculations, and has no substance. "Money" is something whose price (expressed value) is fixed and unchanging when measured in such money of account. To clarify its relationship with currency of account, currency is sometimes called "real currency," and the relationship between the two is made even clearer by the fact that a "currency," such as a 10,000 yen note, is represented by 10,000 units of "currency of account, yen," and remains the same yesterday, today, and tomorrow. Of course, even though the value of currency expressed as currency of account remains constant, the value of currency measured in terms of non-currency goods and services fluctuates daily. However, people generally would not say that the value of currency (measured in terms of canned coffee) has fallen by one tenth when, for example, a 100 yen can of coffee becomes 1,000 yen, even though the price of the can of coffee measured in currency has risen tenfold. In this way, currency of account and currency are the standards of economic life. However, while currency of account is an abstract unit, currency is also an entity that acts as the final means of settlement for debts that arise from real economic transactions. [Horiie Bunkichirō] Two types of currency: national currency (or cash currency) and bank currency (or deposit currency)The power to declare something of a certain substance and form to be money is called "monetary supererogation," and it came to be held by the state with the establishment of the modern nation-state. The state solidified its monetary supererogation by imposing heavy penalties on counterfeiting currency, requiring tax payments to be made in currency, and officially recognizing transactions settled in private currency as final. This was the establishment of legal tender. Subsequently, as coin manufacturing technology developed and counterfeiting became more difficult, the face value stamped on the coin and the material value of the coin when it was crushed became increasingly separated. This is because coins were circulated without questioning the value of the materials used as goods. Coins became an asset called money, completely separate from goods and services, with no intention of using their materials as goods. Over the years, the material value of the minted coins has decreased relative to their face value, until today's subsidiaries and government bills are at the limit. This type of currency is called state currency because it functions based on the power of the state, and is also called "cash currency" because it is circulated through actual delivery. Apart from state currency, bank currency was later created. This is a self-paying debt in which a private financial institution, a bank, promises to immediately deliver cash (state currency) upon demand. Bank currency was initially in the form of banknotes (bank-issued promissory notes payable on bearer demand), but the issuance of various banknotes caused confusion, so the issuance of banknotes was monopolized by the central bank. Even in this case, the central bank was initially obligated to convert banknotes into gold (under the gold standard system in which the exchange rate between banknotes and gold, i.e. gold parity, was legally set by the state), and people trusted banknotes as something that could be exchanged for gold (convertible banknotes), and therefore the central bank had to hold a certain amount of gold reserves (guaranteed reserves) against the outstanding balance of banknotes issued. In this sense, banknotes were credit currency (currency that circulated based on trust in banks) under the gold standard system, but when the managed currency system was established and gold convertibility was suspended (becoming inconvertible banknotes), the basis of trust in banknotes was that the state granted them mandatory legal tender. At this stage, banknotes were incorporated into state currency and ceased to be bank currency. Bank of Japan notes in Japan are state currency. Banks that could no longer issue banknotes turned demand deposits into bank money. Unlike banknotes, these have no physical form and can be instantly converted into cash, but they are not cash; they are simply numbers on the bank's books and are the bank's debt that can be moved by depositors' checks (demand bills issued to the bank) or account transfer instructions and used to settle debts. Unlike state currency, which legally settles debts in the end, bank money is established on the basis of social confidence in the debts of private institutions such as banks, and there is some debate as to whether it can be called money in the strict sense. However, demand deposits were originally accepted by the public as a way to conserve and replenish the use of state currency, which was prone to shortages, and because there are strict self-imposed sanctions and administrative regulations in cases where the parties involved (including the issuer of a check) are unable to immediately exchange them for state currency, they are actually used to settle debts without being converted into cash. Therefore, regardless of the system, it can be said that functionally they function fully as currency. In this way, because banks' demand deposits can be moved around as deposits and function as currency, deposits at other financial institutions that function in the same way as described above are collectively called "deposit currency," and statistically they come to form part of a country's monetary supply alongside cash currency (national currency). [Horiie Bunkichirō] The Functions of Money: Medium of Exchange and Store of ValueWhether it is state currency or bank currency, when it functions as currency, it first functions as an economic "measure of value." However, because the value of currency measured with currency of account is constant, it appears as if currency is a measure of value, and this should be said to be the function of currency of account, rather than the function of actual currency. Secondly, money is used to buy goods and services. And since money is obtained by selling goods and services, it ultimately serves as a "medium of exchange" for goods and services. However, exchange mediated by money consists of two stages: the stage of exchanging goods and services for money, and the stage of exchanging money for goods and services, and there is usually a time gap between the two stages. Between these two points, money does not move and remains in one place, and during that time, money functions as a "store of value." However, the two functions of medium of exchange and store of value cannot be separated. That is, those who give up money do so because they know that the other party can use it to store value, and those who receive money hold it because they know that it can be used as a medium of exchange in the future. People arrived at money in an attempt to minimize the time and trouble (i.e., information cost) it takes to find someone who can provide the right goods or services under the right conditions, and the loss (transaction cost) such as depreciation incurred when the received money is used for payment next time. However, in order to minimize these two costs as much as possible and for money to fully fulfill its two functions of medium of exchange and store of value, the price of money measured in terms of goods and services in general, that is, the power that money has over other goods, that is, its "purchasing power," must remain constant (or at least be thought to remain constant). Fortunately, the price of money measured in units of currency remains constant, so while something that can be bought with a 1,000 yen note today may not be able to be bought with a 1,000 yen note tomorrow, you can certainly buy something with a 1,000 yen note today and tomorrow. As a result, it is easy to develop a "money illusion" that makes people believe that the purchasing power of money remains constant, and it is true that this has been a major support for the idea. [Horiie Bunkichirō] Demand and motivation for moneyIt is difficult to see money moving. With cash, it is only for an instant, and money has an intangible quality. Therefore, the amount of money is measured by its balance (the amount at a given point in time). With a balance, the entire amount is always in someone's hands. There are three possible motives for holding money. First, even if the cumulative amount of money received and paid by a person during a certain period is equal, this does not mean that the amount received and paid is equal at all times during the period. On the other hand, there is a principle of good faith that requires that debts be fulfilled at the time they are promised, which entails some penalties, so debts must be settled at the time they are promised. For this reason, it is necessary to hold a small balance (transaction motive). Second, expectations are not always realized as expected. There may be unexpected goods or services that you want to use money for. The principle of good faith also applies in that case. For this reason, a small balance is held (precautionary motive). Third, since anyone can receive money at any time, people hold money on hand in order to take advantage of the opportunity to buy and sell things that they have no intention of using now or in the future and make a profit from the difference (speculative motive). As mentioned above, there are three motives for holding money, but it is not possible to specifically show which part of the money balance is due to which motive. However, it is possible to call them all "liquidity preference." Generally, there are two elements to the liquidity of an asset. One is the property of being easily convertible into other goods and services, in other words, marketability, and the other is the property of having a stable price measured in monetary terms, in other words, the stability of market value. All assets have these two elements to a greater or lesser extent. However, money is superior to any other asset in these two elements (though money does have the drawback that its price measured in terms of other goods and services (purchasing power) fluctuates. However, this is covered up by the money illusion). [Horiie Bunkichirō] Money Supply – AbstractionAt the turn of the 19th and 20th centuries, the debate over the nature of money, which asked why money could be money, was fought between metallurgy, which was based on the value of the material, and nominalism, which opposed it. However, since then, even cash (national currency) has come to be made from paper, a material that is almost completely worthless, and deposits (bank currency) have become overwhelmingly more common in terms of balance, so today the idea that something that functions as money is money (professionalism) has become dominant. In this process of money becoming intangible, the scope of those who can use money as money has gradually expanded from governments and central banks to private financial institutions in general (such as credit unions). Furthermore, nowadays, non-financial companies and individuals are given credit lines in advance (in the form of deposit collateral or overdrafts), which they can use as purchasing power at any time, so the available supply of money in a country cannot be considered as a balance. In addition, the speed at which money changes hands has increased significantly as a result of recent advances in electronic technology, making it difficult to grasp the true amount of purchasing power that has moved or will move during a period (total amount). For this reason, despite various attempts by governments and central banks, it is becoming increasingly difficult to grasp the effects of fluctuations in the money supply. Nevertheless, the monetary authorities (the government and the Bank of Japan) must always have an accurate grasp of the overall money supply as a means to achieve such goals as price stability and employment stability. However, this is completely impossible. [Horiie Bunkichirō] Money in Electronic CommerceAlthough electronic commerce on the Internet is a virtual or digital society, it has become extremely popular and important in recent years. However, what functions in this case is the currency of account, not real currency. In this case, in a virtual society between parties that are essentially stateless, the unit of account currency does not have to be the unit commonly used in the country, and it can be a foreign unit, or even a simple "sound" that is completely unrelated to them, as long as there is an agreement between the parties. However, in order for transactions of goods and services to be settled as transactions, a national legal system is currently necessary. For this reason, if an organization equivalent to a real world state in the future is able to establish taxation rights like current countries and maintain public order, then until then, there will be no real currency comparable to that currently in countries in the virtual society. As a result of globalization that transcends national borders, in order to have a currency that can be used to settle transactions that also encompass the Internet society, a world state (or at least a world union) must be established and functioning, and in this sense, currency is currently supported by the "monetary sovereignty" held by each country. [Horiie Bunkichirō] Money in Marxian EconomicsThe nature of moneyThe substance of the value of a commodity is abstract human labor, and the magnitude of its value is measured by the labor time socially necessary to produce the commodity. However, the value of a commodity is social and cannot be expressed in itself, but can only be expressed in a value relationship with other commodities. This form in which value manifests itself is called the value form. The simplest form of this value form is " x amount of commodity A = y amount of commodity B." In this value equation, the two commodities play completely different roles. That is, only the value of commodity A is expressed, and commodity B only serves as a material for the expression of the value of commodity A. The value of commodity A is expressed by the use value (commodity object) of commodity B itself. In this value equation, commodity A offers to exchange for commodity B by being equal to x amount of commodity A for y amount of commodity B, and thus commodity B is given the possibility of direct exchange with commodity A. A commodity that serves as a material for the expression of the value of another commodity is called an equivalent form. When the above simple value forms are developed so that all commodities are placed on the left side and only one commodity, gold, is excluded from the commodity world and placed on the right side (equivalent form), and this gold becomes the general equivalent form expressing the value of all commodities and being directly exchangeable with all other commodities, then gold becomes money. This money performs three functions: [Nihei Satoshi] Value ScaleThe first function of money (gold) is to provide the material for expressing value to the commodity world. By expressing the value of various commodities in the same commodity, gold, the values of the various commodities are qualitatively equal, and therefore it is possible to quantitatively compare the values of the various commodities. While labor time is the intrinsic measure of value, money can be said to be its extrinsic measure of value. Price is the expression of the value of a commodity in a certain amount of gold, such as "10 kilograms of rice = 0.75 grams of gold." In order to express all commodity values in various amounts of gold, a standard for measuring the amount of gold itself must be established. This is called the price standard. The price standard was fundamentally the same as the weight standard, but since general validity is necessary, it will eventually be adjusted by law. In Japan, Article 2 of the Currency Act of 1897 (Meiji 30) stipulated that the unit of price was 2 bu (750 milligrams) of pure gold, and that this was called the yen. This allows the price of a commodity to be expressed in a legally valid monetary term such as "10 kilograms of rice = 1 yen in gold." When such a monetary term is given to a commodity, actual money does not need to exist, and in its function as a measure of value, money is merely an idea. However, in the process of exchange, the commodity is transformed into actual money. [Nihei Satoshi] Distribution MethodA commodity that has been given a price and thrown into the circulation process moves as follows: W (commodity) - G (money) - W (commodity). This is the transformation of the commodity. Of these, W - G is sales, and G - W is purchases. Of the transformation of the commodity's form W - G - W, the difficult part is the sale W - G of the commodity. This is because in anarchic commodity production, the success of a sale is entirely contingent. Once a commodity has been sold and successfully transformed into money, money is exchangeable with all commodities, so there is no difficulty in the next purchase.
While goods are produced and put into circulation, they are consumed after changing hands and fall out of circulation, while money remains in circulation all the time, moving away from its starting point. The amount of money M required to mediate the circulation of goods in a certain period of time can be calculated as M = PT / V ( P = price of goods, T = total amount of goods, V = average velocity of money in circulation). This is the law of circulating money, and the gist of this law is that the amount of money required for circulation M is determined by the total price ( PT ) of circulating goods when the average velocity of money in circulation V is constant. Since the function of money as a medium of circulation is temporary and momentary, which mediates the circulation of goods, subsidiary currency minted from silver or copper and relatively worthless government paper money can also fulfill this function as a substitute for gold. Since government paper money is legally given binding tender power by the government, it can be issued in excess of the amount of gold needed for circulation, but in this case the amount of gold represented by the paper money decreases and commodity prices rise nominally. This is inflation. [Nihei Satoshi] Money as currencyIn its function as a measure of value, money is an abstract entity, and in its function as a means of circulation, it can be represented by symbols. In contrast, when gold appears physically and is fixed as an independent entity of value, it is called money as money. It has three forms of existence: hoard money, means of payment, and world money. (1) Hoard money is money that was withdrawn from circulation when the circulation of goods was interrupted by W-G, and its function as a means of circulation was denied. Most of the hoard money is accumulated in banks and functions to regulate the amount of money in circulation. (2) A means of payment is money when goods are sold on credit and the credit-debt relationship that was established there is settled independently by money later. (3) Money leaves the domestic circulation area and appears on the world market, transforming into world money. There, it appears in the form of gold bullion. World money functions as a general means of payment for settling the balance of payments, etc., a general means of purchase, and also functions as the absolute materialization of wealth in general when wealth is transferred to other countries, such as in the payment of reparations. [Nihei Satoshi] History of MoneyCreation of primitive currencyWhen bartering became common in primitive societies, commodity money (natural money) came to be used as a medium of exchange to eliminate the inconveniences associated with exchanging goods. This is called primitive money, and it was made of objects that were relatively easy to dispose of. Typical examples include grain (Middle America, the Philippines, China, Japan), cloth (China, Japan), livestock (Greece, Rome, South Africa), farm tools (China), salt (Ethiopia), weapons (ancient Britain), and furs (Siberia). In addition, there are also ornamental, ceremonial, and magical objects such as cowrie shells, ark shells, feathers, tortoise shells, and whale teeth, and their creation often has religious significance. Later, when metals came to be used, minted coins that imitated primitive currency appeared. This was because metals were able to meet the necessary conditions for currency, such as preservation, uniformity, divisibility, and transportability. China's cloth coins, sword coins, and fish coins are typical examples. According to the Old Testament, gold and silver were already being used as currency by weight in Egypt and Babylonia around 2000 B.C. Other similar materials included gold and silver in Assyria, iron in Persia and Sparta, copper in Arabia, and tin in Mexico. [Yotaro Sakudo] European CoinsGreek coinsThe oldest coins in Europe are said to be electron coins minted in the 7th century BC in the kingdom of Lydia. The electron was a natural alloy of gold and silver, with about 30% silver. It was the first coin to be minted with a fixed shape, fineness, and weight. The Lydian prince Gyges stamped the electron coins to guarantee their value, and used them as small pieces of metal with a uniform value. Later, Gyges' successor Croesus stamped the Lydian seal on the electron coins and had them minted as staters. These circulated throughout the Near East. The Kingdom of Lydia was conquered by Persia in the 6th century BC, but the Persians followed the use of money. Darius I (522-486 BC) of the Persian Empire used gold shekels and silver drachmas as monetary units, and adopted a gold-silver dual-based system, minted Dareikos gold and Siglos silver coins. The gold-silver ratio was set at 1:13 1/3 . This ratio was used around the world for about 2,000 years. Greece minted Aeginan silver coins in the 6th century BC, and later silver coins were made in Athens. The latter coins featured a picture of Goddess Athena and the back of the coins are engraved with owls and olives. These are high-quality silver coins, and became international coins on the Mediterranean coast. In the 5th century BC, in addition to Athens, most Greek city-states created their own coins, which gradually spread to cities in southern Italy, Asia Minor and Sicily, and during the Hellenistic era it spread to Orient. Around the 3rd century BC, ancient India was also influenced by Greeks, and coins that featured statues of kings and Apollo. [Sakudō Yotaro] Roman coinsになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. During the era of Caesar (Caesar, 100-44 BC), coins were engraved with the letters CAESAR and the paintings of the elephant, the Caesar family crest. After Caesar's death, Antonius (around 82 BC - 30 BC) first made coins in Gaul and later at the Orient mint, but some of the coins minted in Asia Minor were engraved with the portraits of Cleopatra and Antonius, and some of the designs of warships and flags. Emperor Augustus (27-14 BC) adopted the Aureus gold coin as the main coin. This gold coin was considered equivalent to 25 Denarius silver coins, and 1 Denarius was considered equivalent to 16 Aese bronze coins. Until Emperor Augustus, the design of the coins was not consistent, but after the Emperor, the coins were included with the portrait of the emperor, and by emphasizing the emperor's personality, the coins were sacred and the unity of the monetary system was achieved. However, between Emperor Nero (reigned 54-68) and Emperor Caracalal (reigned 211-217), the Roman Empire's finances became poor, and both gold and silver coins were renouncing several times, with a low level of dignity and quantity. Constantine the Great (reigned 306-337) strived to improve the monetary system and minted Solidus gold coins in place of Aureus gold coins, which were high quality coins and later spread to the West, and were valid for over 1,000 years. [Sakudō Yotaro] Byzantine Empire currencyになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [Sakudō Yotaro] Medieval European currencyThe Germanic monetary system was built on the heritage of ancient Mediterranean civilization. At the time, Roman coins were common in the Germanic countries, and for political reasons, the Germanic rulers ruled the occupied areas in the name of the Roman emperor, Germanic chiefs minted coins with portraits of the Roman emperor. However, gradually the Germanic rulers switched to coins with their own name engraved in place of the Roman emperor. In the Roman Empire, the right to coins were the emperor or state, but in the Germanic states, the right to coins were no longer monopoly by the state. In the Mellobing dynasty, in addition to coins minted at royal mints, there were also coins created in the names of churches, bishops, and lords of manors. There were also some called wandering coins made by mints in various places, but the quality was poor and it was unauthorized. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In the 12th century, the influence of the Crusades brought Orient gold to Europe, and in the 13th century gold coins were minted everywhere. Florin gold coins, made in Florence in 1251, were particularly famous, and were distributed throughout Europe and were used as models for new gold coins to be minted in various countries. Florin gold coins are engraved with a standing statue of St. John and the lily flower, the coat of arms of Florence. During the Roman era, England used the Roman gold coin Solidus, but it became the first home currency with a penny coin minted by Henry III (reigned 1216-72) in 1257. In 1344, Florin gold coin was introduced by Edward III (reigned 1327-77), and later in 1487, under the reign of Henry VII (reigned 1485-1509), a sovereign gold coin was minted. The gold coin is engraved with a seated statue of the king wearing a crown on the front, and on the back is an army shield and a rose coat of arms of the Tudor family. [Sakudō Yotaro] Early modern currencyIn the 16th century, a large amount of silver was flowing from the Americas into European countries, causing a sharp fluctuation in the gold and silver ratio of each country, causing a price revolution. As a result, the European monetary system also changed dramatically, and Spanish peso coins became internationally popular currency. In Germany, large Tarrel silver coins were minted from 1520. Tarrel silver coins were monetized. The Tarrel silver coins were painted with portraits on the front and coat of arms on the back, and eventually they were made at the mints of European countries under various names such as the Crown, Dollar, Ducaton, Ecu d'Argent, Patacon, Piastle, and Louvre. In addition to the sovereign gold coins that had been reigned up until then, shilling and penny coins showing the usual prices were minted on the side of the coins that were following the Roman monetary system. In the early modern era, when minting coins, a centralized state took the money away from feudal lords, trying to unify them by breaking the monetary system. The pattern of money was often adopted in place of Christ, churches, castles, cities, feudal lords, and other such as the portrait of an absolute lord. [Sakudō Yotaro] Modern currencyAs a result of the Industrial Revolution, the introduction of minting machines led to the creation of large quantities of uniform coins, and the production costs of currency became low. From the end of the 18th century to the beginning of the 19th century, monetary units such as the Mark, Franc, Lila, and Pesetas emerged. Also, from around the 19th century, banknotes began to become common alongside coins. Furthermore, from the second half of the 19th century to the 20th century, gold standard systems were adopted in various countries, shaping the unified foundation of the monetary financial system on a global scale. In England, which first undertook the Industrial Revolution, in 1662, under the reign of King Charles II (reigned 1660-85), the guinea gold coins of modern coins were manufactured at a factory newly established at the Mint, replacing them with conventional gold coins, and then silver and copper coins. Later, in 1848 under the reign of Queen Victoria (reigned 1837-1901), two shilling gold coins (Florin), which became popular among people. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The origin of banknotes around the world was the Goldsmith Note, a gold and silver deposit certificate issued by the Goldsmith Notes, which was established in London in 1392. The Bank of England was established in 1694 in the UK and the first banknotes were issued. This system gradually spread across countries around the world. The first banknotes in America were issued in Massachusetts in 1690 during the colonial period, and by the early 18th century it was published in states such as Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, New York, and New Jersey. In addition, during periods of national fluctuations such as wars and revolutions, government bills were once issued to cover immediate expenses. The most famous ones are Assinian banknotes issued by the revolutionary government during the French Revolution in 1789, and government bills called greenbacks (green backs) issued in the United States during the Civil War (1861-65). The Daijokansatsu (Dajokansatsu) issued by the Meiji Restoration in May 1868 (Keio 4) can also be said to belong to this series. [Sakudō Yotaro] Chinese currencyFrom the Yin to the beginning of the Zhou dynasty, shells, tortoise shells, pearls, and jewels were used as exchange methods. During the Zhou dynasty, cloth coins (cloth), sword coins (sword coins), and fish coins (fish coins). These were used to preserve the remnants of goods coins, and are believed to have been a type of coin that was before the appearance of circular coins. Cloth coins evolved from the prototype of hoes and suki suki, which were used as agricultural tools, and were classified as empty neck cloth, pointed foot cloth, hooded foot cloth, and rounded foot cloth. Sword coins developed from small swords for household use, and can be broadly divided into tip swords, rounded foot swords, and anti-neck swords. Fish coins began when dried fish, a necessity in the inland region, were used as goods coins, and these coins became exchange coins. Next to these fabric, sword and fish coins, the coins were made in Zhou's period, circular coins called encyclopedia or encyclopedia coins were produced. These coins were also called kanpei, and round holes were drilled into round coins. When it becomes Zhou's rendezvous, the hole of the coins is squared. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In Japan, the coins were created by Fuhonsen, a copper coin minted in the late 7th century, and Wado Kaisen (also known as "Wado Kaihou") in the early 8th century. Furthermore, copper coins from Song, Gen, and Ming Ming also flowed into Japan, and they accounted for a large portion of Japanese coins from the Kamakura period to the Muromachi period. In particular, Yongra Tangbao, the Ming Dynasty Emperor Yongle (reigned 1402-24), were representative of this, and were well-established until the early Edo period. The banknotes were issued during the Song Dynasty and were passed down to the Gold, Yuan, Ming and Qing Dynasties. Marco Polo's The Eastern Book of Records shows that during the reign of the Yuan Sezu Kublai (reigned 1260-94), coins were abolished and banknotes were used, as shown in Marco Polo's The Touhou Journal. Spanish silver was inflowing into China during the Ming Dynasty, and Mexican silver and European western silver in the Qing Dynasty, spreading throughout the country. To counter this, new mints were established in the late Qing Dynasty, and a large number of European-style silver and copper coins were minted. As a result of the Xinhai Revolution, when the Republic of China was established in 1912, the national currency ordinance stipulated that the silver yuan was the main currency, and coins engraved with portraits of Sun Yat-Yen and Yuan Shikai were issued. However, major countries had already moved to the gold standard system one after another since the second half of the 19th century, and the silver price fluctuations had become increasingly high. China remained as a silver standard country until the end, but in 1935 it finally shifted to the gold exchange system, one of the gold standard systems. [Sakudō Yotaro] Japanese currencyAncient coinsになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The Wado Kaisen contained silver coins and copper coins, but all other Imperial monies were copper coins. In addition to Imperial monies, the first Japanese money, the Founder Shoten, was created in 760 (Tenpei Hoji 4), and in the same year the Taihei Genho was also minted. [Sakudō Yotaro] Medieval currencyDue to the weakening of political power in the Ritsuryo state, coin business was suspended with Qian Yuan Daiho as the last, and at the end of the Heian period, Tang coins were inflowing into Japan, Song coins were imported in the Kamakura period and Ming coins were imported in the Muromachi period, and they were also used in Japan. Hongwu Tangbao, Yongle Tangbao, and Xundeok Tangbao were representative Ming coins. In addition to the official coins in China, imitation coins made in Japan and private coins were also found in medieval coins, and seisen and skeleton coins were used side by side, resulting in the phenomenon of Erizeni. In addition to coins in the Muromachi period, gold coins and silver coins were also minted, and during the Warring States period, gold and silver coins were developed, and gold and silver coins were actively produced by the warring state lords. This was not the coins needed in the secondary markets within the territory, but rather as military gold. [Sakudō Yotaro] Early modern currencyDuring the Azuchi Momoyama period, Toyotomi Hideyoshi minted various gold and silver coins, which were used as the funds. The Tensho large format, which is said to be the largest gold coin in the world, is particularly famous. Tensho large formats are the Tensho Hishi large format and the Tensho Long-term format, and the diamond size was reportedly made by ordering Goto Tokujo in 1588 (Tensho 16). During the Edo period, the monetary system was unified, and three coins were minted in Kinza, Ginza and Zeniza, gold coins, silver coins, and coins were minted in the shogunate, making them the national standard coins. Gold coins were large (juryo), five ryo, oxen (one ryo), two kin, one kin, two kin, two kin, two kin, two kin, two kin, two kin, and one kin, and silver coins were made in the hyoryo coins, as well as the 5 momme, one kin, two kin, and one kin, one kin, and one kin, as well as the localized silver coins. The coins included Keicho Tsuho, Genna Tsuho, Kanei Tsuho, Hoei Tsuho, Tenpo Tsuho, and Bunkyu Ei Hoei. Of the three coins, gold and silver coins are often re-cashed, and the shogunate often collects re-cashed money to overcome fiscal poverty.になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The shogunate recalls of silver coins, almost like the koban, were repeatedly recalled by the shogunate, reaching 11 types: Keichocho Silver and Kodama Silver (1601), Genroku Silver and Kodama Silver (1695), Hoei Futsuho Silver and Kodama Silver (1706), Hoei Futsuho Silver and Kodama Silver (1710), Hoei Mitsuho Silver and Kodama Silver (1710), Hoei Futsuho Silver and Kodama Silver (1711), Shotoku Silver and Kodama Silver (1714), Genbuncho Silver and Kodama Silver (1736), Bunsho Silver and Kodama Silver (1820), Tenpo Silver and Kodama Silver (1837), Ansei Shinsho Silver and Kodama Silver (1859). The exchange rate of these three coins was determined by the shogunate in 1609 (Keicho 14) to 1 ryo gold = 50 silver = 4 kanmon, but in 1700 (Genroku 13) to 1 ryo gold = 60 silver = 4 kanmon. This statutory market price is constantly changing throughout the market, and in reality the floating exchange system was maintained for a long time. In addition to the three coins of the Shogunate coins, banknotes called domain cards were issued in Daimyo's territory. The first domain card was the Fukui domain card issued in 1661 (Kanbun 1). According to a survey in 1871 (Meiji 4), when an order to dispose of domain cards was issued by the Meiji government, 244 domain cards had been issued. [Sakudō Yotaro] Modern currencyになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The most important thing when maintaining this system of dual gold and silver is that the gold and silver ratio is always constant. However, the gold and silver ratio under the New Coin Ordinance was 1 to 16, but as the silver value continued to fall after that, the gold and silver ratio rose, and Gresham's law took effect, and gold coins soon disappeared from the circulation. In other words, the system of silver was essentially replaced by a silver ratio. The Meiji government established a modern monetary system by establishing the New Coin Ordinance, but before and after this, in order to cover the current expenses, it issued Daijokan (gold bills), Ministry of Finance's bills, converted securities for the Ministry of Finance, and converted securities for the development of pioneering services. However, since printing technology was childish and often forged, the government decided to unite them into new banknotes, and in February 1872 the new banknotes were issued. This bill is officially called Meiji Tsuboho, but since it was printed in Germany, it was generally called Germanic banknotes. From 1881, modified banknotes of the statue of Empress Jingu were printed and issued domestically in place of this new banknote. In addition to these government banknotes, as part of the policy for promoting and industrial development, foreign currency companies established in 8 locations, including Tokyo in 1869, issued bills, and the National Bank, which was established in 1873 under the National Bank Ordinance, initially issued large amounts of gold coins converted banknotes, and after the revision of the ordinance in 1876, the government's banknotes were reprinted in large quantities. になったんです。 English: The first thing you can do In addition, most of the paperbacks and original printings created by this time were made by Edoardo Kiyosone, an Italian man who had been invited to the printing office at the time. In the second half of the 19th century, the advanced countries of Europe and the United States, including Britain, moved to the gold standard system one after another, and as a result, silver prices fell more and more, putting pressure on the economy of silver standard countries. Japan also reached 1897 and finally enacted and promulgated the Money Act, which was based on the gold standard system. This was the reserve that included compensation for the Sino-Japanese War (1894-95), and the value of the yen was halved from the previous 1.5 grams of pure gold to 0.75 grams, and the value of the yen was halved, from 20 yen, 10 yen, 5 yen gold coins as the main currency, and 50 yen, 20 yen, 10 yen, 10 yen, 10 yen, 10 yen, 5 yen gold coins as subsidy coins, 50 yen, 20 yen, 10 yen, 10 yen, 5 yen silver coins, 5 yen white copper coins, 1 yen, 5 rin bronze coins. In addition, the Bank of Japan's convertible silver coins were revised to convertible gold coins bank notes. [Sakudō Yotaro] Modern currencyWhen World War I broke out, Japan was also affected by the war and banned gold exports in 1917 (Taisho 6) and suspended the gold standard system. After the war, major countries immediately returned to the gold standard system, but Japan's return was delayed due to the postwar depression (1920), the Great Kanto Earthquake (1923), and the financial depression (1927), and finally, gold exports were lifted in January 1930 (Showa 5). However, when the Great Depression that happened to be in America was on the way, the ban was lifted at the old parity, resulting in the leak of gold. In addition, austerity policy to maintain the gold standard system, coupled with the impact from overseas caused by the Great Depression, had a serious impact on the lives of the people, and the following year, December 1931 was implemented. This was where the gold standard system in Japan ended and shifted to a controlled currency system. After the Manchurian Incident in September 1931, Japan's wartime regime was strengthened each day, and at the same time, monetary materials gradually deteriorated and lighter. In other words, in 1933, 10 or 5 sen subsidized coins were replaced by nickel coins from white copper coins, and when the Sino-Japanese War broke out in July 1937, the following year, in May 1938, the Special Currency Act was enacted, with nickel coins being aluminum coins, and the silver coins, popularly known as "50 sen Giza", switched to 50 sen government banknotes with plum blossoms on Mount Fuji. After that, when World War II began, in March 1944, 10 sen, 5 sen, tin coins were made into tin zinc coins, and in August of the same year, 10 sen and 5 sen tin coins were issued in place of the 10 sen and 5 sen tin coins, and 5 sen Bank of Japan notes, a statue of Kusunoki Masashige, was issued in place of the 10 and 5 sen tin coins. Furthermore, in 1945, at the end of the war, 10 sen, 5 sen, and 1 sen coins were even produced, but the war ended before it was issued. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In September of the same year, a five-yen brass coin from the Diet Building and a one-yen brass coin with a pattern of Tachibana was issued. In addition, in May 1946, the Allied High Command (GHQ) issued a memorandum ban on the use of postal stamps and designs that advocate militaristic or supernationalistic in money, and was regulated by GHQ when deciding on the design of these new coins. 1949年には1ドル=360円の単一為替レートが設定され、翌1950年からの民間貿易の全面再開への体制が整えられた。1949年には稲穂の模様の穴あきの5円黄銅貨が発行され、翌1950年にはアメリカのドル紙幣に似た横長の1000円券がつくられた。これには聖徳太子の肖像が用いられた。翌1951年には岩倉具視(ともみ)の500円券、高橋是清(これきよ)の50円券、宇治平等院の鳳凰(ほうおう)堂の10円青銅貨が発行された。 1953年7月には「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」が制定され、1円未満の小額通貨の廃止・整理が行われることになった。戦後のインフレによって銭や厘は通貨としても取引の額としてもすでに無意味になっていたのである。同年には新たに板垣退助(たいすけ)像の100円券が発行された。1955年には戦後初の図案公募による若木の1円アルミニウム貨、横から見た菊花の50円ニッケル貨が発行された。 インフレの進行とともに高額紙幣の発行が問題とされていたが、1957年には5000円券が、翌1958年には1万円券が発行され、ともに聖徳太子の肖像が取り入れられた。また、1957年には20年ぶりに銀貨が鋳造されることとなり、鳳凰の模様の100円銀貨がつくられた。しかし、この銀貨は先につくられた50円ニッケル貨と形や色が似ていて紛らわしかったため、図案を公募してつくりかえることとなり、1959年に稲穂の100円銀貨、大輪の菊花の穴あき50円ニッケル貨がつくられた。さらに1963年には伊藤博文(ひろぶみ)の1000円券、1967年には桜花の100円白銅貨、菊花三輪を配した穴あき50円白銅貨がつくられた。 その後の日本の高度成長に伴い、円安傾向の交換レートは是正されることになり、1971年12月に1ドル=308円の新為替レートが実施されたが、さらに1973年2月からは変動為替相場制へと移行することになった。 1982年4月には、15年ぶりに新しい貨幣として桐(きり)の模様の500円白銅貨がつくられた(1999年に韓国の500ウォン硬貨を変造した偽500円硬貨が出回ったため、2000年改鋳された新しい500円ニッケル黄銅貨が発行された)。1984年11月には、紙幣のデザインを一新することとなり、形を従来のものより一回り小さくするとともに、1万円券には福沢諭吉、5000円券には新渡戸稲造(にとべいなぞう)、1000円券には夏目漱石(そうせき)の肖像を採用したものが発行された。さらに、2000年(平成12)7月には九州・沖縄サミット(先進国首脳会議)と西暦2000年を記念して、新紙幣2000円券が発行された。表面に沖縄の首里城の守礼門(しゅれいもん)、裏面には国宝『源氏物語絵巻』の一部と紫式部(むらさきしきぶ)の肖像を採用した。2004年には偽造防止をおもな目的とした新紙幣が発行された。うち5000円券は樋口一葉(いちよう)、1000円券は野口英世(ひでよ)に肖像を変更した。 なお、第二次世界大戦後にはこのほかに記念貨幣として、1964年に東京オリンピック記念貨幣(1000円銀貨、100円銀貨)、1970年に日本万国博覧会記念貨幣(100円白銅貨)、1972年に札幌オリンピック記念貨幣(100円白銅貨)、1975年に沖縄国際海洋博覧会記念貨幣(100円白銅貨)、1976年に天皇陛下御在位50年記念貨幣(100円白銅貨)、1985年に国際科学技術博覧会記念貨幣(500円白銅貨)、内閣制度創始100周年記念貨幣(500円白銅貨)、1986年に天皇陛下御在位60年記念貨幣(10万円金貨、1万円銀貨、500円白銅貨)が発行された。 その後、1988年に新貨幣法の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行され、記念貨幣を政令で随時発行する体制がつくられた。以後、1988年に青函(せいかん)トンネル開通記念貨幣(500円白銅貨)、瀬戸大橋開通記念貨幣(500円白銅貨)、1990年に国際花と緑の博覧会記念貨幣(5000円銀貨)、天皇陛下御即位記念貨幣(10万円金貨、500円白銅貨)、裁判所制度100周年記念貨幣(5000円銀貨)、議会開設100周年記念貨幣(5000円銀貨)、1992年に沖縄復帰20周年記念貨幣(500円白銅貨)、1993年に皇太子殿下御成婚記念貨幣(5万円金貨、5000円銀貨、500円白銅貨)、1994年に関西国際空港開港記念貨幣(500円白銅貨)、第12回アジア競技大会記念貨幣3種(いずれも500円白銅貨)、1997年に長野オリンピック記念貨幣(第1~2次)(1万円金貨、5000円銀貨、500円白銅貨)、1998年に同じ記念貨幣(第3次)(第1~2次と同額の金貨、銀貨、白銅貨)、1999年に天皇陛下御在位10年記念貨幣(1万円金貨、500円白銅貨)、2002年FIFAワールドカップ記念貨幣(1万円金貨、1000円銀貨、500円ニッケル黄銅貨3種)が相次いで発行された。2003年発行の第5回アジア冬季競技大会記念貨幣(1000円銀貨)は日本で初めての彩色を施した硬貨(カラーコイン)であった。同年に奄美(あまみ)群島復帰50周年記念貨幣(1000円銀貨)が発行された。 また、1998年4月には、戦時立法の日本銀行法(1942年2月公布)が改正・施行となり、日本銀行は開かれた独立性と政策決定の透明性を確保し、アカウンタビリティ(説明責任)を果たしていくことが重要となった。 [作道洋太郎] 『カール・マルクス著、長谷部文雄訳『資本論』第1巻第1篇第3章(1954・青木書店)』 ▽ 『J・G・ガーレイ、E・S・ショウ著、桜井欣一郎訳『貨幣と金融』(1967・至誠堂)』 ▽ 『D・パティンキン著、貞木展生訳『貨幣・利子および価格』(1971・勁草書房)』 ▽ 『久留間鮫造著『貨幣論』(1979・大月書店)』 ▽ 『J・M・ケインズ著、長沢惟恭訳『貨幣論』(1980・東洋経済新報社)』 ▽ 『J・ニーハンス著、石川経夫訳『貨幣の理論』(1982・東京大学出版会)』 ▽ 『前田拓生著『銀行システムの仕組みと理論――地域を支える中小企業金融の理解のために』(2008・大学教育出版)』 ▽ 『カール・マルクス著、武田隆夫他訳『経済学批判』(岩波文庫)』 ▽ 『三島四郎・作道洋太郎著『貨幣』(1963・創元社)』 ▽ 『造幣局泉友会編『原色日本のコイン』(1967・朝日新聞社)』 ▽ 『平木啓一著『コイン』(1968・文芸春秋)』 ▽ 『日本銀行調査局編『図録日本の貨幣』全11巻(1972~76・東洋経済新報社)』 ▽ 『郡司勇夫編『日本貨幣図鑑』(1981・東洋経済新報社)』 ▽ 『小川浩著『日本古貨幣変遷史』(1983・日本古銭研究会)』 ▽ 『山口和雄著『日本の紙幣』(1984・保育社)』 ▽ 『E・ビクター・モーガン著、小竹豊治監訳『改訂増補 貨幣金融史』(1989・慶応通信)』 ▽ 『東野治之著『貨幣の日本史』(1997・朝日新聞社)』 ▽ 『山田喜志夫著『現代貨幣論――信用創造・ドル体制・為替相場』(1999・青木書店)』 ▽ 『山田勝芳著『貨幣の中国古代史』(2000・朝日新聞社)』 ▽ 『パルメーシュワリ・ラール・グプタ著、山崎元一・鬼生田顕英・古井龍介・吉田幹子訳『インド貨幣史――古代から現代まで』(2001・刀水書房)』 ▽ 『黒田明伸著『貨幣システムの世界史――「非対称性」をよむ』(2003・岩波書店)』 ▽ 『マーク・シェル著、小沢博訳『芸術と貨幣』(2004・みすず書房)』 ▽ 『ピエール・クロソウスキー著、ピエール・ズッカ写真、兼子正勝訳『生きた貨幣』新装版(2004・青土社)』 ▽ 『矢部倉吉著『古銭と紙幣――収集と鑑賞 無文銀銭から現行貨幣まで』改訂新版(2004・金園社)』 ▽ 『中村佐伝治著『日本のコイン』(保育社・カラーブックス)』 ▽ 『藤沢優著『世界のコイン』(保育社・カラーブックス)』 ▽ 『岩井克人著『貨幣論』(ちくま学芸文庫)』 [参照項目] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
|
近代資本主義経済は、分業と私有財産制とを基礎とする結果、無数の個別経済(経済主体、単位経済)に分裂している。したがって近代経済は、この分裂した無数の個別経済をもって構成される一つの総合経済であるといえる。経済主体には生産の主体と消費の主体とがあり、相互に依存しあい、結び付いて、流通経済、市場経済を形成する。そしてそこに貨幣が介在する。このように近代経済における貨幣は、財貨=商品とともに各個別経済を結び付ける連鎖であるが、この場合の貨幣には、媒介的存在のものと目的的存在のものとがある。前者は商品を購入した対価として支払われる貨幣の流れで、貨幣は購買手段あるいは流通手段として機能する。後者では貨幣だけが一方的に流れ、より多くの貨幣となって(利子を付して)ふたたび還流してくることが期待されている。ここでは貨幣それ自体があたかも商品のごとく、需要供給、すなわち取引の対象となっているのである。 [原 司郎] 貨幣に関する学説・理論金属主義と名目主義このような役割をもつ貨幣の本質がなんであるかに関する学説には、今日、金属主義と名目主義の二つがある。広義では、前者に商品学説、素材主義が含まれ、後者には国定学説、指図証券説、職能学説、抽象学説などが入れられる。 金属主義によれば、貨幣はもっとも広く一般的に受領される商品となる。この結果、貨幣は他の商品と同じく、それ自体が素材価値をもたなくてはならない。すなわち、商品と貨幣との交換過程において、貨幣はそれ自身が価値ある商品としてそれ自体価値ある商品と交換されることとなる。かくて貨幣の本質は価値をもった素材に求められ、貨幣は商品あるいは価値ある財貨、とくに貴金属でなくてはならないと考える。この理論に従えば、素材価値をもたない貨幣の存在は認められないから、紙幣は貨幣たりえぬこととなる。紙幣が流通している場合でも、それが政府紙幣を意味している限り、流通手段としての貨幣の機能から生じた価値章標である。つまり紙幣は貨幣の使用を節約する代用物にすぎないこととなる。 金属主義においては、貨幣がそれ自身一つの商品として価値をもっていることから、価値尺度として他の商品の価値を測定しうる機能を果たしうるものと説明されている。そこで貨幣の本質的機能を価値尺度に求め、そこから流通手段、価値保蔵、支払い手段、世界貨幣といった諸機能を導いてくるのである。この学説は、イギリスの古典派経済学やマルクス経済学によって展開されてきた。主たる学者としては、リカード、クニース、ヒルデブラント、マルクスなどがあげられるが、とくにマルクスによって労働価値説に立脚した貨幣学説として確立されるに至った。これは商品学説ともいわれている。 これに対して名目主義では、金属主義の主張する素材価値たる商品性による一般的価値尺度機能を否定して、貨幣の本質を抽象的機能――一般的交換ないし流通手段――に求める。名目主義の立場をとる代表的学説にF・クナップの国定学説がある。貨幣は素材には関係なく国家の法制だけによって通用力を有するとし、貨幣の本質を流通手段に求めるのがこれである。名目主義は、さらに、貨幣は商品に対する一般的参加票券であるとするF・ベンディクセン、K・エルスターの票券説(指図証券説)、貨幣は貨幣としての機能を営むいっさいのものであるとするL・F・ミーゼス、K・ヘルフェリッヒの職能学説、さらに貨幣は商品価値の比率を表す抽象的計算単位であるとするR・リーフマンの抽象学説に発展した。このように名目主義は、20世紀に入ってからドイツを中心に盛んになったものであるといえる。 20世紀前半を代表する近代経済学者ケインズも、『貨幣論』(1930)において名目主義の立場にたって、貨幣を単なる購買手段の機能をもつものと考えて、計算貨幣という概念を使っている。ケインズの計算貨幣は、債務、諸価格、一般購買力がそれにおいて表現されるもので、金属主義でいう価値尺度としての貨幣の機能に相当するものである。 以下、名目主義の流れをくむ近代経済学における貨幣理論と金属主義を代表しているマルクス経済学における貨幣理論について解説することとしたい。 [原 司郎] 近代経済学における貨幣2種の貨幣――計算貨幣と現実の貨幣貨幣とは、取引の完結に際し生ずる債権・債務関係の決済のために用いられる手段、もしくは社会制度をいう。計算貨幣と現実の貨幣の2種がある。 計算貨幣は、国民所得の大きさを示したり、鉄1キログラムの値うちと綿(わた)1キログラムの値うちを比べたりする場合のように、経済的価値の集計や比較を行う際に一般に用いられる単位である。円、ドル、ユーロなどの称呼(となえ)がそれにあたり、おおむね国ごとに異なる。計算貨幣の多くは重量の単位でもあるが、これはかつて決済の多くが、それに使用する金属の重量をそのつど量る習慣があったことの名残(なごり)にすぎない。日本の計算貨幣である「円」が単に丸いことを表して、重量とはまったく無関係であることからもわかるように、計算貨幣は度量衡や時間などの単位とは切り離され、もっぱら経済計算のためにのみ用いられる抽象的単位であって、実体をもたない。「貨幣」とは、こうした計算貨幣で計ったとき、その価格(表された値)が固定かつ不変のものである。計算貨幣との関係をより明確にするために、貨幣を「現実の貨幣」とよぶこともあるが、両者の関係は、たとえば1万円札という「通貨」は、昨日も今日も明日も、「計算貨幣・円」の1万単位によって表されて変わらないという事実によっていっそう明らかになるであろう。 もっとも、通貨を計算貨幣で表した値は不変でも、通貨を通貨以外の財やサービスによって計った値は日々変動する。しかし一般に人は、たとえば100円の缶コーヒーが1000円になったとき、通貨で計った缶コーヒーの価格が10倍に上がったとはいっても、通貨の(缶コーヒーで計った)値うちが10分の1に下がったとはいわない。このように計算貨幣と通貨は経済生活の基準になっている。ただし通貨は、計算貨幣が抽象的単位であるのに対して、現実の経済的取引に伴って生ずる債務の最終的決済手段として働く実体でもある。 [堀家文吉郎] 2種の通貨――国家貨幣(あるいは現金通貨)と銀行貨幣(あるいは預金通貨)特定の実質・形式のものを貨幣であると宣言する力を「貨幣高権(こうけん)」とよぶが、これを近代国家の確立とともに国家がもつことになった。国家は通貨の偽造に重刑を科し、納税を通貨によるべきものとし、また民間の通貨による取引決済を最終的なものと公認することで、貨幣高権を確実なものとした。法貨の成立である。その後、鋳貨の製造技術が発達し、偽造がむずかしくなるにつれて、鋳貨に打ってある額面価値と鋳貨をつぶしたときの素材価値とは離れていった。素材の財としての価値を問うことなく、鋳貨が流通したからである。鋳貨は財・サービスとはまったく別の、その素材を財として利用することを予定しない、貨幣という一つの資産となった。 その後、鋳貨は年を経るにつれて額面価値に対して素材価値を低下させていき、その極限に今日の補助貨や政府紙幣が位置するまでになっている。この系列の貨幣は、国家の権力が根拠となって機能する貨幣なので国家貨幣といわれ、それの現実の受け渡しによって流通する貨幣なので「現金通貨」ともよばれる。 国家貨幣とは別に、のちに銀行貨幣が生まれた。これは、民間の金融機関である銀行が、要求がありしだい即時に現金(国家貨幣)を引き渡すと約束した自己あて債務のことである。銀行貨幣は初め銀行券(銀行振出しの持参人要求払いの約束手形)の形をとっていたが、各種の銀行券が発行されて混乱を招いたので、銀行券の発行は中央銀行が独占することとなった。この場合でも、初めは中央銀行は銀行券の金兌換(だかん)を義務づけられ(銀行券と金の交換比率、すなわち金平価を国家が法定する金本位制度の下で)、人々は銀行券を金に交換できるもの(兌換銀行券)として信頼し、中央銀行はそのゆえに銀行券発行残高に対して一定の金準備(保証準備)を保有しなくてはならなかった。この意味で銀行券は金本位制度の下では信用貨幣(銀行に対する信用によって流通する貨幣)であったが、管理通貨制度となって金兌換が停止されるに至って(不換銀行券化)、国家が銀行券に強制通用力を与えることが、銀行券に対する信頼の基礎となった。この段階で銀行券は国家貨幣に編入され、銀行貨幣であることをやめた。日本の日本銀行券は国家貨幣である。 銀行券の発行ができなくなった銀行は、要求払預金を銀行貨幣とした。これは銀行券と違って形がなく、即時に現金にかえうるが現金ではなく、単なる銀行の帳簿上の数字で、預金者の小切手(銀行あてに振り出した要求払いの為替(かわせ)手形)や口座振替の指図によっても移動して債務の決済に用いうる銀行の債務である。銀行貨幣は、法的に債務を最終的に決済する国家貨幣とは異なり、銀行という民間の機関の債務への社会的信認を成立の根拠とするから、厳密な意味でこれを貨幣といえるかということについては議論がある。 しかし、要求払預金は、もともと不足がちの国家貨幣の使用を節約し、補充する意味で世に受け入れられたもので、(小切手の振出人を含めた)関係者がそれを即時に国家貨幣に取り替えることができないような状態にした場合については、厳しい自主的な制裁があり、また行政上の規制も厳重であるために、実際には現金化されないままに債務の決済に用いられているものである。したがって、制度的にはともかく、機能的には十分に貨幣の働きをしているといってよい。 このように、銀行の要求払預金は、預金のままに移動して貨幣として機能するために、他の金融機関の預貯金で前記と同じ性質の働きをするものをあわせて「預金通貨」とよばれ、統計的には現金通貨(国家貨幣)と並んで一国の貨幣量を構成する部分をなすこととなった。 [堀家文吉郎] 貨幣の機能――交換媒介と価値貯蔵国家貨幣にせよ銀行貨幣にせよ、それが貨幣として働くということは、第一に経済的「価値の尺度」として働くということである。しかし、貨幣を計算貨幣で計った値が不変であるために、あたかも貨幣が価値尺度のようにみえるのであるから、これはむしろ現実の貨幣の機能ではなく、計算貨幣の機能というべきであろう。第二に貨幣は財やサービスを買うのに使われる。そしてその貨幣は財やサービスを売って得るのであるから、結局は貨幣は財やサービスの「交換の媒介」をしていることになる。しかし、貨幣が媒介をする交換は、財・サービスと貨幣を交換する段階と、貨幣と財・サービスを交換する段階の二つからなっており、二つの段階の間には通常時間的な隔たりがある。この二つの時点の間、貨幣は動くことがなく、1か所にとどまっているのであるが、その間貨幣は「価値貯蔵」の働きをしているのである。 しかし、交換の媒介と価値貯蔵の二つの機能は切り離すことができない。というのは、貨幣を手放す者は相手が価値貯蔵に役だてることを知るから手放すのであるし、貨幣を受け取る者は将来交換の媒介に用いうることを知るから保有するのである。人は、しかるべき財やサービスをしかるべき条件で提供する者に巡り会うまでの時間と煩労(すなわち情報コスト)と、受け取った貨幣を次に支払いに用いるときに被る減価などの損失(取引コスト)が、できるだけ少なくなるように試みて貨幣にたどり着いたのであった。けれども、これら二つのコストを可能な限り小さくし、交換媒介と価値貯蔵の二つの機能を貨幣が十分に果たすためには、貨幣を財・サービス一般で計った価格、すなわち貨幣が他財を支配する力、つまり「購買力」が不変で(あると少なくとも思われてい)なければならない。 幸いにして、貨幣を計算貨幣で計った価格が不変なので、今日1000円札で買えたものは明日は1000円札で買えないかもしれないが、今日も明日も1000円の正札がついたものは確実に買えるために、あたかも貨幣の購買力は不変だと思い込む「貨幣錯覚」が生じやすく、それが大きな支えとなってきたことは事実である。 [堀家文吉郎] 貨幣の需要と動機貨幣が動く姿をみることはむずかしい。現金ならどうかというと、それも一瞬のことであるし、そのうえに貨幣には形のないものがある。それで、貨幣の量をとらえるには残高(ある一時点の量)によることになった。残高ならば、いつにせよ、すべてがだれかの手中にあるわけである。 貨幣を保有する動機には次の三つが考えられる。第一に、たとえだれにしてもある人の、ある期間中の貨幣の受け払いの累計額が等しくなっていても、期間中のすべての時点において受け払いの額が等しいということではない。他方で、債務には約束した時点でかならず債務を履行するという、若干の罰則を伴う誠実の原則があるので、債務は約束された時点でかならず決済されなければならない。このために若干の残高の保有が必要である(取引動機)。第二に、期待がそのとおりに実現するとは限らない。貨幣を使いたい財・サービスが思いがけず出てくることもあろう。その場合でも誠実の原則は働く。このためにも若干の残高が保有される(予備的動機)。第三に、貨幣はだれにでもいつでも受け取れるので、いまも将来も使う気はないものを売買してその差益を手にする機会をねらう目的でも、人は貨幣を手元に保有する(投機的動機)。このように貨幣保有の動機は三つあるけれども、その貨幣残高のどの部分がどの動機によるものかは具体的には示せない。しかし、一括して「流動性選好」ということはできる。 一般に資産の流動性には二つの要素がある。一つは他の財・サービスにかえやすいという性質、つまり市場性で、他は貨幣で計った価格が安定しているという性質、すなわち市場価値の安定性である。これら二つの要素は、どの資産にも多かれ少なかれある。しかし貨幣はこれら二つの要素において、他のどの資産よりも優れている(もっとも、貨幣にも他の財・サービスで計った価格(購買力)が変動するという難点はある。しかしそれは貨幣錯覚によって覆われている)。 [堀家文吉郎] 貨幣の供給――抽象化19世紀と20世紀の変わり目ごろに、貨幣がなにゆえに貨幣たりうるかを問う貨幣本質論争が、素材の価値に根拠を置く金属主義と、それに反対する名目主義との間で争われた。しかしその後、現金(国家貨幣)さえも、紙というほとんどまったく無価値に近い素材でつくられるようになり、預金(銀行貨幣)が残高においても圧倒的に多くなったので、今日では結局、貨幣の働きをするものが貨幣だという考え(職能主義)が支配的になってきている。 このように貨幣が素材を問題としなくなる無体化の過程のなかで、貨幣を貨幣として使用させうる者の範囲が政府・中央銀行のほかに、民間金融機関一般(たとえば信用組合)へとしだいに広がってきた。そのうえ現今では、金融機関ではない企業・個人にも(預金担保や当座貸越の形で)あらかじめ信用枠が与えられていて、彼らはその枠を随時購買力となしうるから、一国の貨幣の供給可能量を残高としてはとらええない。それに、貨幣が人手をかえる早さは、近年の電子的な技術進歩の結果、著しく増大してきているので、一期間中に動いた、あるいは動くであろう本当の購買力の大きさ(延べ量)はとらえにくくなった。このため、政府・中央銀行の各種の試みにもかかわらず、貨幣供給量変動の効果の把握はますます困難になってきている。 それにもかかわらず、通貨当局(政府・日本銀行)は、物価安定・雇用安定などの目標達成の手段としての貨幣供給量全体を、常時正確に把握していなければならない。ところがこれはまったく不可能である。 [堀家文吉郎] 電子商取引における貨幣インターネットによる電子商取引はバーチャル(仮想的)、ないしデジタル社会のものであるが、近年では著しく流行し、その重みを増してきている。ただし、この場合に機能しているのは計算貨幣であって、現実の貨幣ではない。この場合、計算貨幣の単位は、本来無国籍である当事者間の仮想的社会においては、取引当事者間の合意さえあれば、自国内で一般に広く使われている単位にとらわれる必要はまったくなく、外国の単位でも、あるいはそれらとさえまったく無関係な単なる「音」でもよい。しかし、財・サービスの取引が、取引として決済されるためには、現在では国家の法制が必要である。このことから将来、現実に世界国家に相応する組織が、現在の各国のように徴税権を確立し、治安の維持をまっとうしうるに至るのであればとにかく、それまでの間は仮想社会に、現在諸国にあるものに匹敵する現実の貨幣は存在しえない。 世界が国境を越えたグローバリゼーションの結果、インターネット社会をも包括する取引決済に用いうる貨幣をもつためには、世界国家(少なくとも世界連合)が成立し、それが機能していなければならず、この意味で貨幣は、現在のところ各国がもつ「貨幣高権」に支えられているのである。 [堀家文吉郎] マルクス経済学における貨幣貨幣の本質商品の価値の実体は抽象的・人間的労働であり、価値の大きさは商品を生産するのに社会的に必要な労働時間によって度量されるが、商品価値は社会的なものであり、それ自体では表現されず、他の商品との価値関係においてのみ現象しうる。この価値の現象形態を価値形態という。この価値形態のもっとも単純な形態は、「x量の商品A=y量の商品B」である。この価値等式においては、両商品はまったく異なった役割を演じている。すなわち、A商品の価値だけが表現されており、B商品はA商品の価値表現の材料として役だっているにすぎない。A商品の価値はB商品の使用価値(商品体)そのものによって表現されているのである。この価値等式においては、x量のA商品はy量のB商品に等しいということによって、A商品はB商品に交換を申し出ているのであり、これによってB商品はA商品との直接的交換可能性を与えられる。他の商品の価値表現の材料として役だっている商品を等価形態という。上記の単純な価値形態が発展して、すべての商品が左辺に立ち、ただ一つの商品金(きん)が商品世界から排除されて右辺(等価形態)に置かれ、この金がすべての商品の価値を表現する一般的等価形態となり、すべての商品との直接的交換可能性をもつようになったとき、金は貨幣となる。この貨幣は次の3機能を果たしている。 [二瓶 敏] 価値尺度貨幣=金の第一の機能である価値尺度機能は、商品世界に対して価値表現の材料を提供するということである。諸商品の価値が金という同一商品で表現されることによって、諸商品が価値としては質的に均等であり、したがって、諸商品の価値を量的に比較することが可能となる。労働時間が価値の内在的価値尺度であるのに対して、貨幣はその外在的価値尺度ということができる。「米10キログラム=金0.75グラム」というように、商品の価値を金の一定量で表現したものが価格である。すべての商品価値をさまざまな金分量で表現するためには、金そのものの分量を度量する基準を確定しておかねばならない。これを価格の度量基準という。価格の度量基準は根源的には重量の度量基準と一致していたが、一般的妥当性が必要なので、やがて法律によって調整される。日本の場合、1897年(明治30)の貨幣法第2条で、純金2分(750ミリグラム)をもって価格の単位となし、これを円と称すると定められていた。これによって商品の価格は、「米10キログラム=金1円」という法律上有効な貨幣称呼で表現されるようになる。商品にこのような貨幣称呼を付与する場合、現実の貨幣がそこに存在する必要はなく、価値尺度機能においては貨幣は観念的な存在にすぎない。しかし交換過程では商品は現実の貨幣に転化される。 [二瓶 敏] 流通手段価格を付与されて流通過程に投ぜられた商品は次のような運動を行う。W(商品)―G(貨幣)―W(商品)である。これが商品の姿態変換である。このうちW―Gが販売であり、G―Wが購買である。商品の姿態変換W―G―Wのうち、困難なのは商品の販売W―Gである。というのは、無政府性的な商品生産のもとでは販売の成功はまったく偶然的だからである。商品の販売が行われて貨幣に転化することに成功したならば、貨幣はすべての商品との交換可能性を有しているので、次の購買に困難は存在しない。
商品は、生産されて流通に投ぜられ、そこでの持ち手変換ののち消費されて流通から脱落していくのに対して、貨幣は、出発点から遠ざかりながら絶えず流通にとどまっている。ある一定期間における商品流通を媒介するのに必要な貨幣量Mは、M=PT/V(P=商品の価格、T=商品総量、V=貨幣の平均流通速度)で求めることができる。これが流通貨幣量に関する法則であり、この法則の眼目は、流通必要貨幣量Mは、貨幣の平均流通速度Vを一定とした場合、流通諸商品の価格総額(PT)によって規定されるということである。貨幣の流通手段機能は、商品流通を媒介する一時的、瞬間的なものであるから、この機能に限って、銀や銅で鋳造された補助貨幣や、相対的に無価値な政府紙幣も、金の代理としてこの機能を果たすことができる。政府紙幣は政府が法的に強制通用力を与えるものであるから、流通必要金量を超えて発行しうるが、この場合には紙幣の代表する金量は低下し、商品価格は名目的に騰貴する。これがインフレーションである。 [二瓶 敏] 貨幣としての貨幣価値尺度機能においては貨幣は観念的な存在であり、流通手段機能においては象徴によって代表可能であるのに対して、金が現身で現れ、価値の自立的存在として固定化される場合の機能を貨幣としての貨幣という。これは蓄蔵貨幣、支払い手段、世界貨幣という三つの存在形態をもつ。(1)蓄蔵貨幣は、商品流通がW―Gで中断されて流通から引き上げられ、流通手段としての機能が否定された貨幣である。蓄蔵貨幣の大部分は銀行に集積され、流通貨幣量を調節する機能を果たす。(2)支払い手段は、商品が信用で販売され、そこで取り結ばれた債権債務関係を、あとで貨幣が自立的に決済する場合の貨幣である。(3)貨幣は国内流通部面から歩み出て、世界市場に登場するとともに世界貨幣に転化する。貨幣はそこでは金の地金形態で表れる。世界貨幣は、国際収支の決済等の一般的支払い手段、一般的な購買手段として機能し、賠償金支払いのように富を他国に移譲する場合、富一般の絶対的物質化としても機能する。 [二瓶 敏] 貨幣の歴史原始貨幣の生成原始社会において物々交換が盛んに行われるようになると、物資の交換に伴う不便を取り除くために、交換の媒介物として物品貨幣(自然貨幣)が用いられるに至った。これが原始貨幣とよばれるもので、比較的処分の容易な物が利用された。その代表的なものとして、穀物(中部アメリカ、フィリピン、中国、日本)、布帛(ふはく)(中国、日本)、家畜(ギリシア、ローマ、南アフリカ)、農具(中国)、塩(エチオピア)、武器(古代イギリス)、毛皮(シベリア)などがあげられる。そのほか、子安貝、赤貝、羽毛、亀甲(きっこう)、鯨歯など、装飾品や儀礼的、呪術(じゅじゅつ)的な物もみられ、その生成には宗教的意義をもつ場合が少なくない。 その後、金属が用いられるようになると、原始貨幣をかたどった鋳造貨幣(鋳貨coin)が現れるに至った。金属は、保存性、等質性、分割性、運搬性など、貨幣の必要な条件をよく満たすことができたからである。中国の布貨、刀貨、魚貨などはその典型的な例である。 また、『旧約聖書』によれば、すでに紀元前2000年ごろに、エジプトやバビロニアにおいて金銀が秤量(ひょうりょう)貨幣として使用されていたとある。このようなものにはほかに、アッシリアの金銀、ペルシアやスパルタの鉄、アラビアの銅、メキシコの錫(すず)などがあった。 [作道洋太郎] ヨーロッパの貨幣ギリシアの貨幣ヨーロッパにおける最古の鋳貨は、前7世紀にリディア王国で鋳造されたエレクトロン貨とされている。エレクトロン貨は金と銀との天然の合金であって、銀がおよそ30%含まれていた。これは鋳貨として一定の形状、品位、量目が定められてつくられた最初の貨幣であった。リディア王国の王侯ギゲスはエレクトロン貨にその価値を保証する刻印を打ち、価値の一様な金属の小片として使用した。その後、ギゲスの後継者クロイソスは、エレクトロン貨にリディア王国の証印を打ち、スタテル貨を鋳造させた。これは近東の各地において流通した。 リディア王国は前6世紀にペルシアによって征服されたが、ペルシア人は貨幣の使用を踏襲した。ペルシア帝国のダリウス(ダレイオス)1世(在位前522~前486)は金シェケルと銀ドラクマとを貨幣単位となし、金銀複本位制度を採用し、ダレイコス金貨ならびにシグロス銀貨を鋳造した。金銀比価は1:131/3と定められた。この比率は以後約2000年にわたって世界各地において用いられるところとなった。 ギリシアでは前6世紀にアイギナ銀貨を鋳造し、のちにアテネにおいても銀貨をつくった。後者の貨幣表面にはアテナ女神の顔、裏面にフクロウとオリーブの絵が刻み込まれている。これは良質の銀貨で、地中海沿岸の国際貨幣となった。前5世紀には、アテネのほかギリシアの都市国家はほとんど独自の貨幣をつくり、それがしだいに南イタリア、小アジア、シチリアの諸都市に及び、ヘレニズム時代にはオリエントにも波及した。前3世紀ごろには古代インドもギリシアの影響を受け、王やアポロンの像を取り入れた貨幣を鋳造した。 [作道洋太郎] ローマの貨幣ローマでは前3世紀に大型の青銅貨(アエス・グラウェ)および銀貨(デナリウス)が鋳造され、さらに前1世紀には金貨(アウレウス)がつくられた。アエス青銅貨には貨幣単位(アス)が刻印されており、その表面には両面神のヤヌスの神、裏面には船首の絵が取り入れられている。デナリウス銀貨にも青銅貨10アエスに相当する貨幣単位が刻印されており、その表面にはローマの神、裏面には通商の神であるカストルとポリデウケスの双生神の像とROMAという文字が刻まれている。デナリウス銀貨はローマの造幣所のほか各地で多量につくられ、地中海の西部から中部にかけて主要な通貨となった。また、アウレウス金貨はオリエントの造幣所において鋳造され、その表面にビーナスの像、裏面にインペラトールimperator(軍司令官)という文言や戦利品の模様などが配されている。カエサル(シーザー、前100―前44)の時代には、貨幣にCAESARの文字やカエサルの家紋であるゾウの絵などが刻み込まれている。 カエサルの死後、アントニウス(前82ころ―前30)は、初めガリアで、のちにはオリエントの造幣所で貨幣をつくったが、そのうち小アジアで鋳造された貨幣のなかには、クレオパトラとアントニウスの肖像をいっしょに刻印したものや、軍艦および軍旗のデザインを取り入れたものがみられる。また、アウグストゥス皇帝(在位前27~後14)は本位貨幣としてアウレウス金貨を採用した。この金貨は25デナリウス銀貨と等価とされ、1デナリウスは16アエス青銅貨と等価とされた。アウグストゥス皇帝までは、貨幣のデザインは一定していなかったが、同皇帝以後、貨幣には皇帝の肖像が入れられることになり、皇帝の人格を強調することによって貨幣を神聖なものとし、幣制の統一を実現しようとした。しかし、ネロ皇帝(在位54~68)からカラカラ皇帝(在位211~217)にかけて、ローマ帝国の財政は窮乏化し、金・銀貨ともに数度にわたって、品位、量目を落として改鋳された。コンスタンティヌス大帝(在位306~337)は幣制の改善に努め、アウレウス金貨にかえてソリドゥス金貨を鋳造したが、これは良質の貨幣で、のちに西方にも流布し、1000年以上にわたって通用した。 [作道洋太郎] ビザンティン帝国の貨幣ローマ帝国の再建を図り、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)を建設したユスティニアヌス皇帝(在位527~565)は、皇帝の肖像を配したソリドゥス金貨をつくり、これを本位貨幣とした。ビザンティン時代には、金貨のほかに銀貨、銅貨も鋳造された。銀貨、銅貨には皇帝の肖像、キリストの胸像、十字架などの模様が取り入れられている。これらの金・銀・銅貨はビザンティン帝国の首都コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)でつくられたが、ローマ、カルタゴ、ラベンナ、アレクサンドリアなどにおいても鋳造された。ビザンティン貨幣のうち、とくに金貨は地中海沿岸諸国において広く用いられ、6世紀から7世紀にかけて現在のフランス、ドイツ、ベルギー、オランダ、スカンジナビア、ロシア、バルカン、レバント、北アフリカなどにおいても通用した。 [作道洋太郎] 中世ヨーロッパの貨幣ゲルマン諸国の幣制は古代地中海文明の遺産のうえに成り立っていた。当時、ゲルマン諸国ではローマ時代の貨幣が一般に慣れ親しまれており、ゲルマン人が占領地域をローマ皇帝の名において支配していた政治的理由もあり、ゲルマン人の首長たちはローマ皇帝の肖像を配した貨幣を鋳造した。しかし、その後しだいにゲルマンの支配者は、ローマ皇帝の名にかえて自分の名を刻印した貨幣に切り替えていった。 ローマ帝国では造幣権は皇帝すなわち国家にあったが、ゲルマン国家の場合、造幣権は国家の独占ではなくなっていた。メロビング朝時代には、王室の造幣所で鋳造された貨幣のほかに、教会、司教、荘園(しょうえん)領主の名においてつくられた貨幣もみられる。また各地の鋳造師によってつくられた放浪貨幣とよばれたものがあったが、品質は粗悪で、権威をもたぬ貨幣であった。 ゲルマン諸国のなかで、フランク系のサリ人だけはメロビング朝時代に独自の幣制を設け、サリカ法典のなかで1ソリドゥス(金貨)=40デナリウス(銀貨)と定め、ローマ時代に実体貨幣であったデナリウス銀貨を計算貨幣としてとらえた。しかし、この新しい体系は不便であったため、カロリング朝時代にはふたたび実体貨幣としてデナリウス銀貨が鋳造された。これはカロリング家の宮宰カール・マルテルの子ピピン3世(在位751~768)とその子カール大帝(在位768~814)によって行われ、新デナリウス銀貨は中世ヨーロッパの本位貨幣となるに至った。カール大帝の子ルイ(ルードウィヒ)1世(敬虔(けいけん)王、在位813~840)はソリドゥス金貨を鋳造したが、これには十字架と「神への贈り物」という文字とが刻印されている。 12世紀になると、十字軍の影響によってオリエントの金がヨーロッパにもたらされ、13世紀には各地で金貨が鋳造された。1251年にフィレンツェでつくられたフロリン金貨はとくに有名で、ヨーロッパの各地に流布し、各国において金貨を新鋳する場合のモデルとなった。フロリン金貨には聖ヨハネの立像とフィレンツェの紋章であるユリの花が刻印されている。 イギリスは、ローマに支配されていた時代にはローマ金貨のソリドゥスを用いていたが、ヘンリー3世(在位1216~72)が1257年に鋳造したペニー金貨によって最初の自国通貨をもつようになった。1344年にはエドワード3世(在位1327~77)によってフロリン金貨が導入され、その後ヘンリー7世(在位1485~1509)治下の1487年にはソブリン金貨が鋳造された。この金貨は、表面には王冠をかぶった国王の坐像(ざぞう)、裏面には軍隊の盾とチューダー家のバラの紋章が刻印されている。 [作道洋太郎] 近世の貨幣16世紀に入って、アメリカ大陸から多量の銀がヨーロッパ諸国に流入し、そのため各国の金銀比価は激しく変動し、価格革命を引き起こした。これに伴ってヨーロッパの貨幣制度も大きな変化を示し、スペインのペソ貨は国際的に有力な貿易用の貨幣となった。ドイツでは1520年から大型のターレル銀貨が鋳造された。ターレル銀貨は、表面には肖像、裏面には紋章が配されており、やがてクラウン、ドル、ドゥカートン、エキュ・ダルジャン、パタコン、ピアストル、ルーブルといった各種の名称でヨーロッパ諸国の造幣所においてつくられるようになった。またイギリスでは、チューダー家のエドワード6世(在位1547~53)のとき、それまでのソブリン金貨のほかに、ローマの幣制に倣った貨幣面に通用価格を表示したシリング貨やペニー貨が鋳造された。 近世になると、貨幣の鋳造に際して中央集権国家が造幣権を封建諸侯から奪い取り、幣制の割拠体制を打破して統一を図ろうとした点に特徴がみられる。貨幣の模様もキリスト、教会、城、都市、封建領主などにかわって絶対君主の肖像が取り入れられることが多くなった。 [作道洋太郎] 近代の貨幣産業革命の結果、造幣機械の導入によって、均一な貨幣が大量に製造されるようになり、貨幣の製造費も低廉となった。18世紀の末期から19世紀の初めにかけて、マルク、フラン、リラ、ペセタなどの貨幣単位が現れるに至った。また19世紀のなかばごろから鋳貨と並んで紙幣が一般化するようになった。さらに19世紀後半から20世紀にかけて各国において金本位制度が採用され、世界的な規模で貨幣金融制度の統一基盤が形づくられた。 産業革命を最初に行ったイギリスでは、チャールズ2世(在位1660~85)治下の1662年に造幣局に新設された工場で近代貨幣のギニー金貨を製造し、従来の金貨と取り替え、ついで銀貨と銅貨も製造した。その後ビクトリア女王(在位1837~1901)治下の1848年には2シリング金貨(フロリン)がつくられ、人々の人気をよんだ。 アメリカにおける最初の貨幣は、ボストン造幣局で1652年から1682年にかけてつくられたシリング銀貨、6ペンス銀貨、3ペンス銀貨であった。それまでにイギリス、スペインなどの貨幣が流入していたが、その数量は少なかった。独立戦争が終結し、アメリカの独立が承認された1783年には銅貨がつくられ、初代大統領ワシントンの肖像が刻印された。1785年には連邦会議において新しい幣制が採用され、ドルは正式にアメリカの貨幣単位となった。さらに1792年には通貨法と貨幣製造法が制定され、金銀複本位制度を採用することとなり、フィラデルフィア造幣局が開設された。同年10月に5セント貨幣、翌1793年に1セント、1/2セントの貨幣が製造され、1794年には有名な彫金家のロバート・スコットにより銀貨がつくられ、ついで1795年から金貨が製造された。 世界における紙幣の始まりは、1392年ロンドンに設立された金匠会社発行の金銀預り証「ゴールドスミス・ノート」であった。その後、イギリスでは1694年にイングランド銀行が創設され、最初の銀行券が発行された。この制度は、その後しだいに世界諸国に広がっていった。アメリカで最初の紙幣は、植民地時代の1690年にマサチューセッツで発行されたもので、その後18世紀初めまでにコネティカット、ニュー・ハンプシャー、ロード・アイランド、ニューヨーク、ニュー・ジャージーなどの諸州で相次いで発行された。 なお、戦争や革命など国家の変動期には、当面の経費をまかなうために政府紙幣が発行されたことがある。もっとも有名なものは、1789年のフランス革命に際して革命政府が発行したアッシニア紙幣と、アメリカで南北戦争(1861~65)当時に発行されたグリーン・バック(緑背紙幣)とよばれる政府紙幣である。明治維新に際して維新政府が1868年(慶応4)5月に発行した太政官札(だじょうかんさつ)もこの系列に属するものといえよう。 [作道洋太郎] 中国の貨幣殷(いん)から周時代の初めにかけては、貝殻、亀甲(きっこう)、真珠、宝石などが交換手段として用いられた。周の時代にはやがて布貨(布幣)、刀貨(刀幣)、魚貨(魚幣)が用いられるようになった。これらは物品貨幣の名残(なごり)をとどめたもので、円形の鋳貨が出現する以前における鋳貨の一種であったとみられる。布貨は農具として使われてきた鍬(くわ)や鋤(すき)の原型である鎛(ふ)から進化したもので、その形状から空首布(くうしゅふ)、尖足布(せんそくふ)、方足布(ほうそくふ)、円足布などに類別される。刀貨は家庭用の小刀から発展したもので、形態のうえから尖首刀、円首刀、反首刀に大別される。魚貨は内陸地方の生活必需品であった干魚が物品貨幣として用いられていたことに端を発して、これが交換用の鋳貨となるに至った。これらの布貨、刀貨、魚貨に次いで、周の時代には、垣銭(えんせん)または垣字銭(えんじせん)とよばれた円形の鋳貨がつくられた。これは環幣(かんぺい)ともとなえられ、丸い鋳貨に丸い穴があけられている。それが周の両甾銭(りょうしせん)になると、鋳貨の穴が四角になっている。 秦(しん)の始皇帝(在位前247~前210)は円形方孔銭(ほうこうせん)をつくり、銅銭による貨幣の統一を図り、旧来の布貨、刀貨などの使用を禁止し、造幣権を国家の手に収めた。これは漢代にも引き継がれ、漢の武帝(在位前141~前87)は五銖銭(ごしゅせん)を発行した。これはその後約800年にわたり中国の貨幣として存続した。漢を滅亡させた新(しん)の王莽(おうもう)(在位9~23)は大泉五十、契刀(けいとう)、貨布などの王莽銭を鋳造したが、新は15年で崩壊したので、王莽銭も一時的なものにすぎなかった。唐の高祖(在位618~626)は開元通宝を新鋳した。これは国内のみならず広くアジアの諸国において使用された。日本においては、7世紀後半に鋳造された銅貨である富本銭(ふほんせん)と8世紀初頭の和同開珎(わどうかいちん)(「わどうかいほう」ともよぶ)が、これをモデルとしてつくられたものである。さらに宋(そう)、元(げん)、明(みん)の銅銭も日本に流入し、鎌倉時代から室町時代にかけて、日本の貨幣の大部分を占めた。とくに明の成祖永楽帝(在位1402~24)の永楽通宝はその代表的なもので、江戸初期まで通用した。 紙幣は宋代から発行され、金、元、明、清(しん)代へと引き継がれていった。元の世祖フビライ(在位1260~94)の治世下には鋳貨を廃して紙幣を使用させたことが、マルコ・ポーロの『東方見聞録』にみられる。 明代にはスペイン銀、清代にはメキシコ銀やヨーロッパの洋銀が中国に流入し、全土に広まっていった。これに対抗するために、清代後期には新しい造幣所が設立され、ヨーロッパ型の銀貨や銅貨が大量に鋳造されるようになった。 辛亥(しんがい)革命の結果、1912年に中華民国が成立すると、国幣条例によって銀元が本位貨幣と定められ、孫文や袁世凱(えんせいがい)の肖像を刻印した貨幣が発行された。しかし、主要国はすでに19世紀後半から相次いで金本位制度に移行しており、銀価の変動は激しくなっていた。中国は最後まで銀本位国として残っていたが、1935年にはついに金本位制度の一つである金為替(かわせ)本位制度へと移行した。 [作道洋太郎] 日本の貨幣古代の貨幣日本における最初の官銭は、7世紀後半に鋳造された富本銭とされ、唐の制度を模倣して鋳銭事業が開始された。その後、奈良・平安時代には、708年(和銅1)に鋳造された和同開珎、万年通宝(760創鋳)、神功(じんぐう)開宝(765)、隆平永宝(796)、富寿神宝(818)、承和昌宝(じょうわしょうほう)(835)、長年大宝(848)、饒益(じょうえき/にょうやく)神宝(859)、貞観(じょうがん)永宝(870)、寛平(かんぴょう)大宝(890)、延喜(えんぎ)通宝(907)、乾元(けんげん)大宝(958)が引き続いて発行された。これらのうち富本銭を除く12の官銭を総称して皇朝十二銭または本朝十二銭と呼び習わしてきた。和同開珎には銀銭と銅銭とがあったが、そのほかの皇朝銭はすべて銅銭であった。皇朝銭のほかに760年(天平宝字4)には日本で最初の金銭である開基勝宝がつくられ、また同年に銀銭の太平元宝も鋳造された。 [作道洋太郎] 中世の貨幣律令(りつりょう)国家における政治力の弱体化により、乾元大宝を最後として鋳銭事業は停止され、平安末期には唐の銭貨が日本に流入し、鎌倉時代には宋銭、室町時代には明銭が輸入され、日本においても通用した。洪武通宝、永楽通宝、宣徳通宝などは代表的な明銭であった。中世の貨幣には、このような中国における官鋳制銭のほかに、日本製の模造銭や私鋳銭がみられ、精銭(せいせん)と鐚銭(びたせん)とが並んで用いられたので、撰銭(えりぜに)の現象が発生した。室町時代には銭貨のほかに金貨や銀貨も鋳造され、さらに戦国時代になると諸国の金山、銀山が開発され、戦国諸侯により金・銀貨が盛んにつくられるようになった。これは領内の流通市場において必要とした貨幣というよりも、軍用金としてつくられたものであった。 [作道洋太郎] 近世の貨幣安土(あづち)桃山時代には、豊臣(とよとみ)秀吉が各種の金・銀貨を鋳造し、これを軍資金とした。とくに、世界最大の金貨とさえいわれる天正(てんしょう)大判は有名である。天正大判には天正菱(ひし)大判と天正長大判とがあり、菱大判は1588年(天正16)に後藤徳乗に命じてつくらせたものと伝えられている。 江戸時代には幣制が統一され、金座、銀座、銭座(ぜにざ)において金貨、銀貨、銭貨の三貨を鋳造し、幕府は全国通用の正貨とした。金貨には大判(十両)、五両判、小判(一両)、二分判、一分判、二朱判、一朱判があり、銀貨には秤量(ひょうりょう)貨幣の丁銀、小玉銀(小粒(こつぶ)銀、豆板銀ともいう)のほか、定位銀貨として五匁銀、一分銀、二朱銀、一朱銀がつくられた。銭貨には慶長(けいちょう)通宝、元和(げんな)通宝、寛永(かんえい)通宝、宝永(ほうえい)通宝、天保(てんぽう)通宝、文久(ぶんきゅう)永宝があった。三貨のうち金貨と銀貨はしばしば改鋳され、幕府は財政窮乏を打開するために改鋳益金を収得した場合が多い。金貨のうち大判には、慶長大判(1601創鋳)、元禄(げんろく)大判(1695)、享保(きょうほう)大判(1725)、天保大判(1838)、万延(まんえん)大判(1860)の5種類があり、また小判には、慶長小判(1601)、元禄小判(1695)、宝永小判(1710)、正徳(しょうとく)小判(1714)、享保小判(1716)、元文(げんぶん)小判(1736)、文政(ぶんせい)小判(1819)、天保小判(1837)、安政(あんせい)小判(1859)、万延小判(1860)の10種類があった。小判は大判に比べて改鋳の機会が多く、それだけ小判には日常的な通貨の性格が比較的強かったとみられている。銀貨の丁銀および小玉銀は小判とほとんど同じように幕府によって改鋳が繰り返され、慶長丁銀・小玉銀(1601)、元禄丁銀・小玉銀(1695)、宝永二ツ宝丁銀・小玉銀(1706)、宝永永字丁銀・小玉銀(1710)、宝永三ツ宝丁銀・小玉銀(1710)、宝永四ツ宝丁銀・小玉銀(1711)、正徳丁銀・小玉銀(1714)、元文丁銀・小玉銀(1736)、文政丁銀・小玉銀(1820)、天保丁銀・小玉銀(1837)、安政丁銀・小玉銀(1859)の11種類に達した。これらの三貨の交換割合は幕府により1609年(慶長14)に金1両=銀50匁=銭4貫文と定められたが、1700年(元禄13)には金1両=銀60匁=銭4貫文と改定された。この法定相場は市中では絶えず変動しており、実際には変動相場制が長く維持された。 幕府貨幣の三貨のほかに、大名領国では藩札とよばれる紙幣が発行された。最初の藩札は1661年(寛文1)発行の福井藩札であった。明治政府により藩札処分令が発せられた1871年(明治4)の調査によれば244藩で藩札が発行されていた。 [作道洋太郎] 近代の貨幣明治新政府は、1871年に新貨条例を制定するとともに、幣制改革のために造幣寮(現在の独立行政法人造幣局)と紙幣寮(現在の独立行政法人国立印刷局)を開設した。新貨条例において、日本の貨幣の単位は正式に円とされ、円の価値は純金1.5グラムと定められた。また、補助単位として銭、厘が設けられ、十進法が採用された。本位貨幣として20円、10円、5円、2円、1円の金貨、補助貨幣として50銭、20銭、10銭、5銭の銀貨、2銭、1銭、半銭、1厘の銅貨が鋳造されることとなったが、銀本位国に囲まれた日本の実情から、貿易の便宜上、1円銀貨の発行を定め、事実上無制限の通貨として認めた。そのため、新貨条例が金本位制度をとったとはいえ、現実には金銀複本位制度の性格をもつものとなった。このような金銀複本位制度を維持するにあたってもっとも重要なことは、金銀比価がつねに一定していることである。しかし、新貨条例による金銀比価は1対16であったが、その後銀価が低落を続けたため、金銀比価は上昇し、グレシャムの法則が働いて、金貨はまもなく流通界から姿を消してしまった。すなわち、実質的には銀本位制度になってしまったわけである。 明治政府は、このように新貨条例を定めて近代的貨幣制度を確立したが、これに前後して、当面の経費をまかなうために、太政官札(金札)、民部省札、大蔵省兌換(だかん)証券、開拓使兌換証券などを発行した。しかし、これらの紙幣は印刷技術が幼稚で、偽造されることも多かったため、政府は新紙幣に統一することとし、1872年2月から新紙幣を発行した。この紙幣は正式には明治通宝というが、ドイツで印刷されたため、一般にはゲルマン紙幣とよばれた。1881年からは、この新紙幣にかわって神功(じんぐう)皇后像の改造紙幣が国内で印刷され、発行された。 このような政府紙幣のほかに、殖産興業政策の一環として1869年に東京など8か所に設置された為替(かわせ)会社も紙幣を発行し、また、国立銀行条例に基づいて1873年から設立された国立銀行も、当初は金貨兌換紙幣を、1876年の同条例改定後は政府紙幣との兌換紙幣を大量に発行した。 これら各種の紙幣の整理は、1881年に大蔵卿(きょう)に就任した松方正義(まつかたまさよし)によって推進されることになった。1882年には中央銀行として日本銀行が設立され、国立銀行紙幣を新たに発行することは禁止された。1884年には兌換銀行券条例が制定され、翌1885年から日本銀行の銀貨兌換銀行券が発行された。この最初の日本銀行券には大黒天の像が印刷されており、100円、10円、5円、1円の4種類があった。1888年からはこれにかわって改造券が発行されることとなり、100円券には藤原鎌足(ふじわらのかまたり)、10円券には和気清麻呂(わけのきよまろ)、5円券には菅原道真(すがわらのみちざね)、1円券には武内宿禰(たけしうちのすくね)の肖像が採用された。なお、このころまでにつくられた紙幣の下絵および原版製作は、当時印刷局に招聘(しょうへい)されていたイタリア人エドアルド・キヨソーネによるものがほとんどである。 19世紀の後半に入ると、イギリスをはじめとして、欧米の先進諸国は相次いで金本位制度に移行し、その影響もあって銀価はますます低落の度を強め、銀本位国の経済を圧迫していた。日本も1897年に至り、ようやく金本位制度を基幹とする貨幣法を制定、公布した。これは日清(にっしん)戦争(1894~95)の賠償金を準備金に設定したもので、円の価値を従前の純金1.5グラムから0.75グラムへと平価の半減を行い、本位貨幣として20円、10円、5円の金貨、補助貨幣として50銭、20銭、10銭の銀貨、5銭の白銅貨、1銭、5厘の青銅貨を鋳造するというものであった。また、日本銀行の銀貨兌換銀行券は金貨兌換銀行券に改定された。 [作道洋太郎] 現代の貨幣第一次世界大戦が勃発(ぼっぱつ)すると、日本も大戦の影響を受けて1917年(大正6)に金輸出を禁止し、金本位制度を停止した。大戦後、主要国はただちに金本位制度に復帰したが、日本は戦後恐慌(1920)、関東大震災(1923)、金融恐慌(1927)などのため復帰が遅れ、ようやく1930年(昭和5)1月に金輸出を解禁した。しかし、たまたまアメリカに端を発した大恐慌が進行していた時期に旧平価で解禁したため、金の流出をもたらし、また、金本位制度維持のための緊縮政策は、大恐慌による海外からの打撃と相まって、国民生活に深刻な影響を及ぼし、翌1931年12月には金輸出再禁止が実施された。ここに日本における金本位制度は終わりを告げ、管理通貨制度へと移行したのである。 1931年9月の満州事変勃発後、日本では日増しに戦時体制が強化され、それとともに貨幣素材はしだいに悪化と軽量化の道をたどっていった。すなわち、1933年には補助貨幣の10銭、5銭が白銅貨からニッケル貨にかわり、1937年7月に日中戦争が勃発すると、翌1938年5月には臨時通貨法が制定され、ニッケル貨はアルミニウム貨に、「50銭ギザ」として親しまれていた銀貨は、富士山に梅花を配した50銭政府紙幣に切り替えられた。その後第二次世界大戦に入ると、1944年3月には10銭、5銭は錫(すず)貨に、1銭は錫亜鉛貨になり、同年8月には10銭と5銭の錫貨にかわって八紘一宇(はっこういちう)の塔のデザインのある10銭、楠木正成(くすのきまさしげ)像の5銭の日本銀行券が発行された。さらに戦争末期の1945年になると陶器製の10銭、5銭、1銭貨幣の製造さえ進められていたが、発行されないうちに終戦を迎えた。 第二次世界大戦後、インフレの異常な高進に対処するために、1946年(昭和21)2月には金融緊急措置令に基づいて旧円から新円への切り替えが行われ、新円として聖徳太子の肖像の100円券、国会議事堂の10円券、唐草(からくさ)模様を配した5円券、二宮尊徳の1円券が発行された。また、新しく菊紋と稲穂の10銭アルミニウム貨、菊紋と鳩(はと)の5銭錫貨、および産業立国を象徴する鍬(くわ)、つるはし、稲、麦、魚、歯車を配した50銭黄銅貨が発行された。このうち50銭黄銅貨は翌1947年には直径・量目を縮小し、図案も菊紋と桜花に改められた。1948年5月には小額紙幣整理法が制定されて、50銭以下の紙幣は同年8月末日をもって通用禁止とされ、回収が進められた。また同年9月には国会議事堂の5円黄銅貨、橘(たちばな)の模様のある1円黄銅貨が発行された。なお、1946年5月に連合国最高司令部(GHQ)から郵便切手ならびに貨幣に軍国主義的なものや超国家主義的なものを標榜(ひょうぼう)する図案を使用することを禁止する旨の覚書が出され、これらの新しい貨幣の図案を決定するに際してはGHQの規制を受けた。 1949年には1ドル=360円の単一為替レートが設定され、翌1950年からの民間貿易の全面再開への体制が整えられた。1949年には稲穂の模様の穴あきの5円黄銅貨が発行され、翌1950年にはアメリカのドル紙幣に似た横長の1000円券がつくられた。これには聖徳太子の肖像が用いられた。翌1951年には岩倉具視(ともみ)の500円券、高橋是清(これきよ)の50円券、宇治平等院の鳳凰(ほうおう)堂の10円青銅貨が発行された。 1953年7月には「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」が制定され、1円未満の小額通貨の廃止・整理が行われることになった。戦後のインフレによって銭や厘は通貨としても取引の額としてもすでに無意味になっていたのである。同年には新たに板垣退助(たいすけ)像の100円券が発行された。1955年には戦後初の図案公募による若木の1円アルミニウム貨、横から見た菊花の50円ニッケル貨が発行された。 インフレの進行とともに高額紙幣の発行が問題とされていたが、1957年には5000円券が、翌1958年には1万円券が発行され、ともに聖徳太子の肖像が取り入れられた。また、1957年には20年ぶりに銀貨が鋳造されることとなり、鳳凰の模様の100円銀貨がつくられた。しかし、この銀貨は先につくられた50円ニッケル貨と形や色が似ていて紛らわしかったため、図案を公募してつくりかえることとなり、1959年に稲穂の100円銀貨、大輪の菊花の穴あき50円ニッケル貨がつくられた。さらに1963年には伊藤博文(ひろぶみ)の1000円券、1967年には桜花の100円白銅貨、菊花三輪を配した穴あき50円白銅貨がつくられた。 その後の日本の高度成長に伴い、円安傾向の交換レートは是正されることになり、1971年12月に1ドル=308円の新為替レートが実施されたが、さらに1973年2月からは変動為替相場制へと移行することになった。 1982年4月には、15年ぶりに新しい貨幣として桐(きり)の模様の500円白銅貨がつくられた(1999年に韓国の500ウォン硬貨を変造した偽500円硬貨が出回ったため、2000年改鋳された新しい500円ニッケル黄銅貨が発行された)。1984年11月には、紙幣のデザインを一新することとなり、形を従来のものより一回り小さくするとともに、1万円券には福沢諭吉、5000円券には新渡戸稲造(にとべいなぞう)、1000円券には夏目漱石(そうせき)の肖像を採用したものが発行された。さらに、2000年(平成12)7月には九州・沖縄サミット(先進国首脳会議)と西暦2000年を記念して、新紙幣2000円券が発行された。表面に沖縄の首里城の守礼門(しゅれいもん)、裏面には国宝『源氏物語絵巻』の一部と紫式部(むらさきしきぶ)の肖像を採用した。2004年には偽造防止をおもな目的とした新紙幣が発行された。うち5000円券は樋口一葉(いちよう)、1000円券は野口英世(ひでよ)に肖像を変更した。 なお、第二次世界大戦後にはこのほかに記念貨幣として、1964年に東京オリンピック記念貨幣(1000円銀貨、100円銀貨)、1970年に日本万国博覧会記念貨幣(100円白銅貨)、1972年に札幌オリンピック記念貨幣(100円白銅貨)、1975年に沖縄国際海洋博覧会記念貨幣(100円白銅貨)、1976年に天皇陛下御在位50年記念貨幣(100円白銅貨)、1985年に国際科学技術博覧会記念貨幣(500円白銅貨)、内閣制度創始100周年記念貨幣(500円白銅貨)、1986年に天皇陛下御在位60年記念貨幣(10万円金貨、1万円銀貨、500円白銅貨)が発行された。 その後、1988年に新貨幣法の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が施行され、記念貨幣を政令で随時発行する体制がつくられた。以後、1988年に青函(せいかん)トンネル開通記念貨幣(500円白銅貨)、瀬戸大橋開通記念貨幣(500円白銅貨)、1990年に国際花と緑の博覧会記念貨幣(5000円銀貨)、天皇陛下御即位記念貨幣(10万円金貨、500円白銅貨)、裁判所制度100周年記念貨幣(5000円銀貨)、議会開設100周年記念貨幣(5000円銀貨)、1992年に沖縄復帰20周年記念貨幣(500円白銅貨)、1993年に皇太子殿下御成婚記念貨幣(5万円金貨、5000円銀貨、500円白銅貨)、1994年に関西国際空港開港記念貨幣(500円白銅貨)、第12回アジア競技大会記念貨幣3種(いずれも500円白銅貨)、1997年に長野オリンピック記念貨幣(第1~2次)(1万円金貨、5000円銀貨、500円白銅貨)、1998年に同じ記念貨幣(第3次)(第1~2次と同額の金貨、銀貨、白銅貨)、1999年に天皇陛下御在位10年記念貨幣(1万円金貨、500円白銅貨)、2002年FIFAワールドカップ記念貨幣(1万円金貨、1000円銀貨、500円ニッケル黄銅貨3種)が相次いで発行された。2003年発行の第5回アジア冬季競技大会記念貨幣(1000円銀貨)は日本で初めての彩色を施した硬貨(カラーコイン)であった。同年に奄美(あまみ)群島復帰50周年記念貨幣(1000円銀貨)が発行された。 また、1998年4月には、戦時立法の日本銀行法(1942年2月公布)が改正・施行となり、日本銀行は開かれた独立性と政策決定の透明性を確保し、アカウンタビリティ(説明責任)を果たしていくことが重要となった。 [作道洋太郎] 『カール・マルクス著、長谷部文雄訳『資本論』第1巻第1篇第3章(1954・青木書店)』▽『J・G・ガーレイ、E・S・ショウ著、桜井欣一郎訳『貨幣と金融』(1967・至誠堂)』▽『D・パティンキン著、貞木展生訳『貨幣・利子および価格』(1971・勁草書房)』▽『久留間鮫造著『貨幣論』(1979・大月書店)』▽『J・M・ケインズ著、長沢惟恭訳『貨幣論』(1980・東洋経済新報社)』▽『J・ニーハンス著、石川経夫訳『貨幣の理論』(1982・東京大学出版会)』▽『前田拓生著『銀行システムの仕組みと理論――地域を支える中小企業金融の理解のために』(2008・大学教育出版)』▽『カール・マルクス著、武田隆夫他訳『経済学批判』(岩波文庫)』▽『三島四郎・作道洋太郎著『貨幣』(1963・創元社)』▽『造幣局泉友会編『原色日本のコイン』(1967・朝日新聞社)』▽『平木啓一著『コイン』(1968・文芸春秋)』▽『日本銀行調査局編『図録日本の貨幣』全11巻(1972~76・東洋経済新報社)』▽『郡司勇夫編『日本貨幣図鑑』(1981・東洋経済新報社)』▽『小川浩著『日本古貨幣変遷史』(1983・日本古銭研究会)』▽『山口和雄著『日本の紙幣』(1984・保育社)』▽『E・ビクター・モーガン著、小竹豊治監訳『改訂増補 貨幣金融史』(1989・慶応通信)』▽『東野治之著『貨幣の日本史』(1997・朝日新聞社)』▽『山田喜志夫著『現代貨幣論――信用創造・ドル体制・為替相場』(1999・青木書店)』▽『山田勝芳著『貨幣の中国古代史』(2000・朝日新聞社)』▽『パルメーシュワリ・ラール・グプタ著、山崎元一・鬼生田顕英・古井龍介・吉田幹子訳『インド貨幣史――古代から現代まで』(2001・刀水書房)』▽『黒田明伸著『貨幣システムの世界史――「非対称性」をよむ』(2003・岩波書店)』▽『マーク・シェル著、小沢博訳『芸術と貨幣』(2004・みすず書房)』▽『ピエール・クロソウスキー著、ピエール・ズッカ写真、兼子正勝訳『生きた貨幣』新装版(2004・青土社)』▽『矢部倉吉著『古銭と紙幣――収集と鑑賞 無文銀銭から現行貨幣まで』改訂新版(2004・金園社)』▽『中村佐伝治著『日本のコイン』(保育社・カラーブックス)』▽『藤沢優著『世界のコイン』(保育社・カラーブックス)』▽『岩井克人著『貨幣論』(ちくま学芸文庫)』 [参照項目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
<<: Geldkapital; money capital
>>: Wall - Kabe (English spelling) wall
Recommend
Pulmonata
…It can refer to all land mollusks, but more prec...
Post-modernism
...After World War II, reflecting the unprecedent...
Pajajaran (English spelling)
The last Hindu kingdom in West Java (Sunda region)...
nevus sebaceus (English spelling) nevussebaceus
...There are usually no symptoms, but some people...
Program (English spelling) program; computer program
A program is a set of instructions written in a pr...
Kasumi stone
A silicate mineral. An ore of potash and aluminum....
Woodwardia orientalis Sw.
A large fern of the family Lycoraceae whose leaves...
Ghost
…There are also creatures that appear as giants o...
Guo Ruosi - Peacock
…An astronomer, mathematician, and hydraulic engi...
Dishwasher book - Kinsobon
A small Chinese book written in fine print. A pock...
system oil
…JIS (Japanese Industrial Standards) classifies l...
Improvement method
...In addition to the limitations of such project...
Loyalty (English spelling)
Generally speaking, it refers to an emotion or at...
Anderson, D.
...Therefore, when referring to the country's...
Celebration dish - Iwai Fish
...Singing, dancing and hidden performances also ...