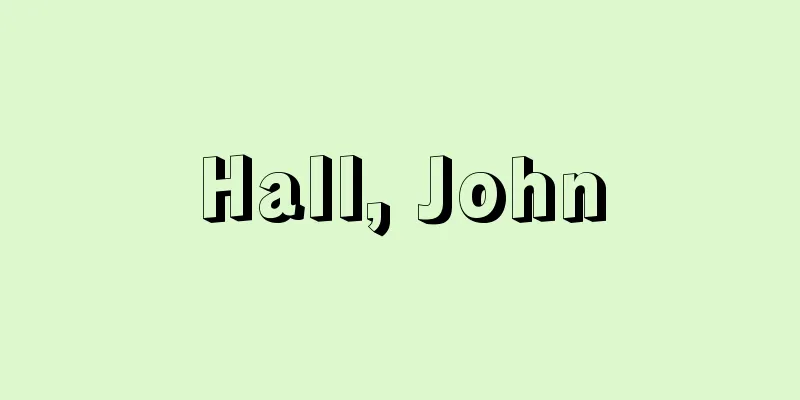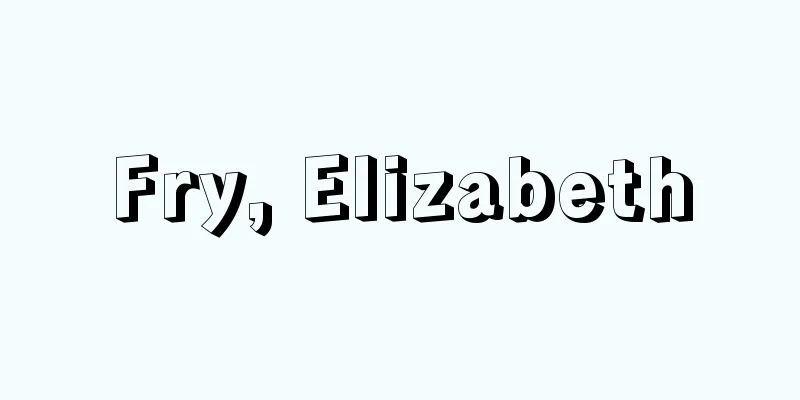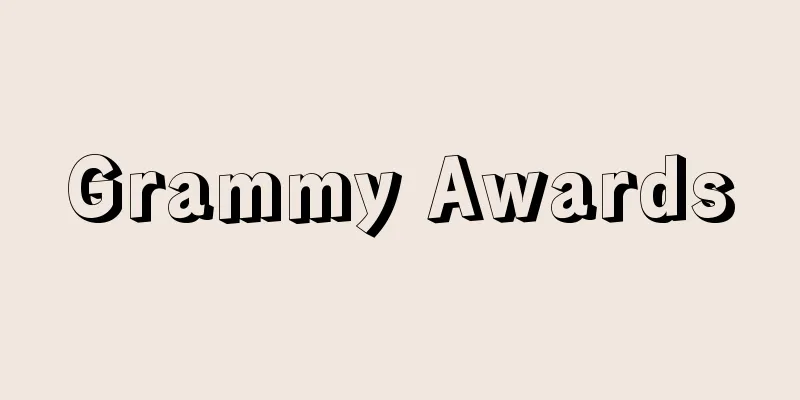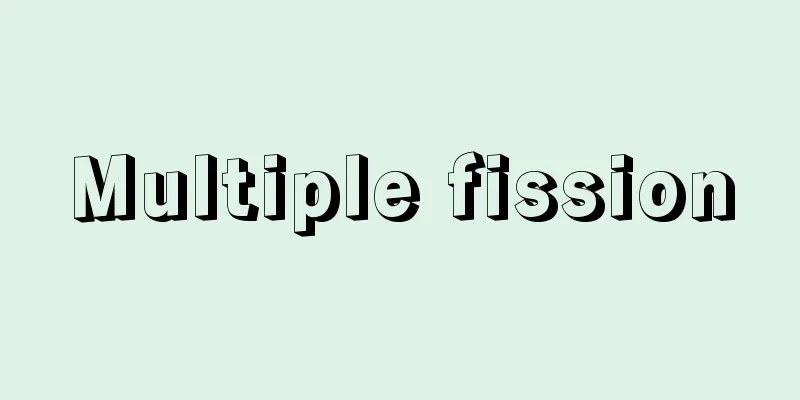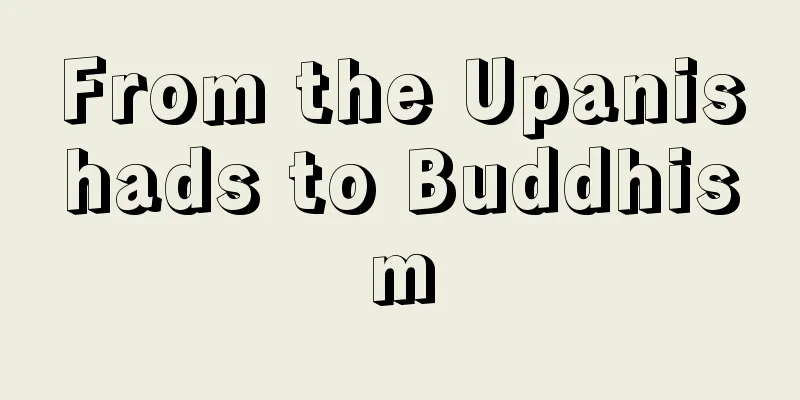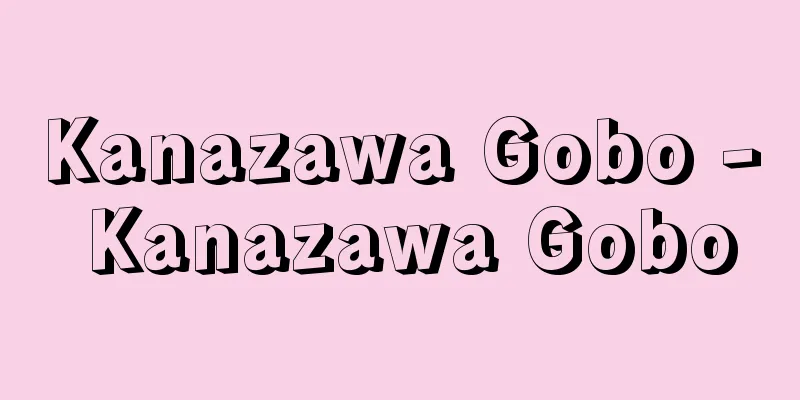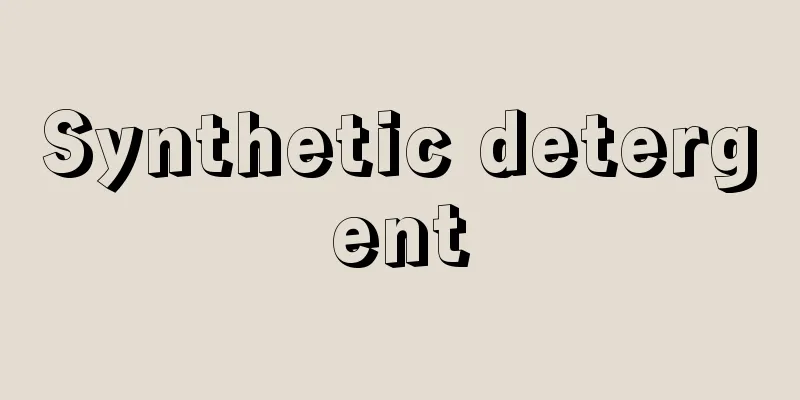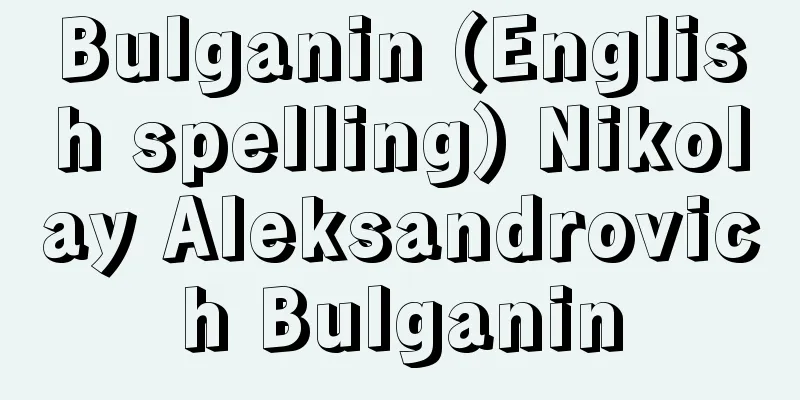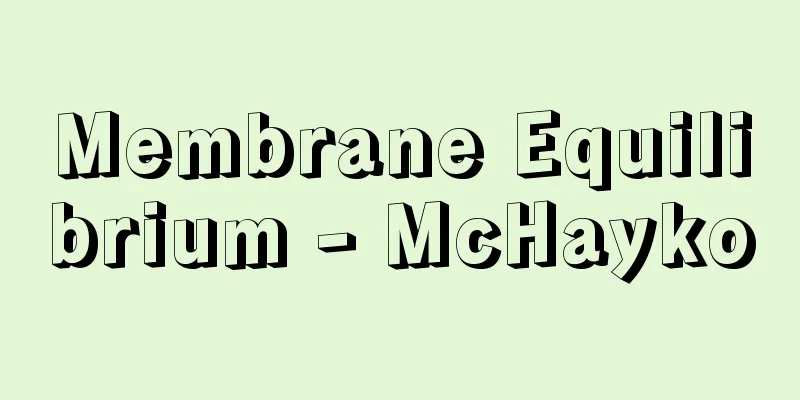Publishing - shuuppan (English spelling)
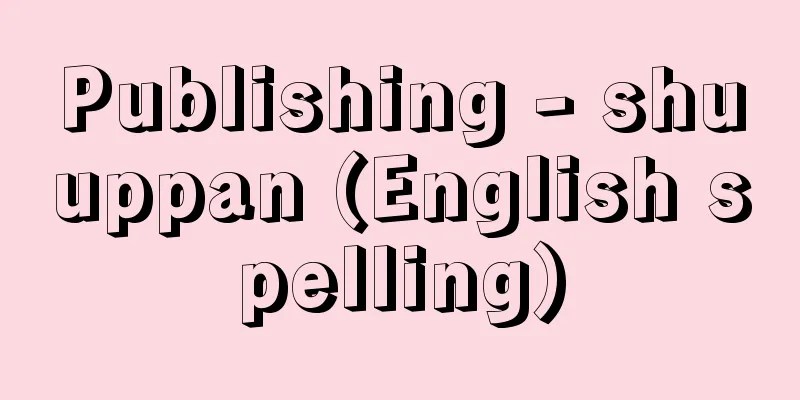
|
Publishing refers to the reproduction and publication of copyrighted works such as documents, photographs, and paintings for the purpose of sale and distribution. Before letterpress printing became widespread, printing was mainly done on wooden boards, so words such as kaiban, joshi, hango, and hatsuda were used. In a broad sense, it includes all publication of printed matter such as newspapers, but it usually means the publication of books and magazines. The modern era is one in which we are rapidly moving from printing with type to computerized electronic printing, and then to electronic publishing. [Hideo Shimizu] Publishing FeaturesPublishing has long been used as a tool for communication in human society, and after the advent of movable type printing, it gradually became a mass medium. However, compared to newspapers, radio, television, and other media, publishing is inferior in terms of speed, simultaneity, and wide-rangingness of information transmission, but it can still be said to be the most superior communication medium in terms of accuracy, logic, and accumulation. In other words, newspapers, which place importance on news, have limitations in the systematic and analytical nature of their messages, and audiovisual media, which place emphasis on entertainment and visual quality, tend to sacrifice diversity of thought and logic. In general, mass media are characterized by a passive and reluctant attitude toward receiving information, which leads to the standardization of the tastes and thoughts of the recipients. In this regard, publishing is centered on communication through letters and can transmit extremely diverse and dense information, making it possible to transmit the diversity of thought that is essential to democracy, as well as advanced academic and literary works to a small number of recipients. On the other hand, publishing often lacks dynamism and comprehensive expressiveness, and has weaknesses that make it difficult to fully adapt to modern conditions and needs. This is particularly true of book publishing, but at the same time, this weakness plays a role in preventing people's perspectives from becoming extremely microscopic or conformist. This is a characteristic that cannot be ignored in the development of opinion journalism and social sciences. However, mass communication is undergoing major changes due to the remarkable development of electronic technology. This is particularly dramatic in the fields of broadcasting and communications, but it is also bringing about major changes in the editing, production, and sales (transmission) processes in publishing, marking a new era in the history of reproduction culture since Gutenberg. The academic field that aims to scientifically study and investigate publishing is called publishing science, and in Japan the Japan Society for Publishing Studies was formed in 1969 (Showa 44). [Hideo Shimizu] Characteristics of the publishing industryPublishing is a business that can be done with relatively little capital, even among the mass media industries. In this respect, it is relatively easy for new businesses to enter the market, compared to newspapers and broadcasting, which require huge amounts of capital, and the number of publishers in Japan has continued to increase. Therefore, while publishing enjoys free competition not seen in other media industries, it cannot be denied that there are many companies with small capital and small number of employees, making them vulnerable as companies. The publishing business has been made unstable by the large amount of liquid capital compared to fixed capital, the high proportion of labor costs and advertising expenses, the lack of objectivity in product value, and the lack of internationality in Japanese publishing in particular. However, some major publishers have a large market share, stable products such as mass magazines, and huge advertising revenues, so they have been breaking away from the small-scale image they once had. However, the publishing business as a whole is becoming increasingly difficult due to the phenomenon of young people turning away from print and the overflow of media information. [Hideo Shimizu] Publishing HistoryThe history of publishing is also the history of books. Although it depends on how you define a book, many bibliographers cite the Sumerian clay tablets (clay tablets, around 3100 BCE) from Mesopotamia, where cuneiform writing was invented, as the oldest book remaining today. Starting from this point, the history of publishing around the world can be roughly divided into the following five periods. [Hideo Shimizu] The emergence of the bookLetters and pictures engraved on materials such as wood, bamboo, clay, metal, and wax gradually changed to use lighter and more flexible materials. That is, letters written on papyrus (around 3000 BC), silk (around 1200 BC), and leather (around 30 BC) gradually took on the form of scrolls (Latin: volūmen) and booklets (codex), which gradually took on the form of modern books. In ancient Greece, scriptors appeared in the 5th century BC, and in Rome, a guild of scribes was formed in 207 BC. Priests and slaves were responsible for copying, but as the work shifted to wage labor, the price of books also rose. Since it is not possible to write many characters on a single sheet of papyrus, which is only 30 centimeters square, 20 to 30 sheets of papyrus were glued together to form a scroll, which became a volūmen. Parchment first appeared in Asia Minor around 170 BC, and until the 6th century, this volume dominated books in the cultural sphere centered around Rome. In China, books made from wooden or bamboo strips appeared during the Qin dynasty in the 3rd century BC, but stone scriptures, in which the text of Buddhist scriptures was carved into stone and then rubbed, were also used. This could be said to be the beginning of printing. Paper was first invented by a man named Cai Lun around 105 AD during the Eastern Han dynasty. This, combined with woodblock printing technology invented in the early Tang dynasty in the 7th century, marked the beginning of the long era of woodblock printing. In 932, a large-scale printing project was carried out in Luoyang for the purpose of civil service examinations. [Hideo Shimizu] The Age of ManuscriptsParchment, which was cruder than papyrus but much stronger and cheaper, was widely used by Christians and eventually became the mainstream of books in the Middle Ages. By cutting each sheet of parchment and binding them together, the paginated booklet (codex), which is characteristic of modern books, was created. This format was particularly suitable for long Bibles and legal documents, and the word codex was born from codex. For more than 1,000 years after the 4th century AD, parchment manuscripts by clergymen were the main publishing culture in Medieval Europe. Manuscripts gradually became more beautiful, and manuscripts of the late Middle Ages in particular were works of art with highly colored miniatures, and the refined alphabet characters directly influenced the typefaces of the next generation. During this period, romances, which are chivalrous tales, were written and published in the Romance languages (French, Spanish, Italian, etc.) that branched off from Latin. In other words, they are the roots of the novel. [Hideo Shimizu] The invention of movable type printingThere are differing opinions as to whether Johann Gutenberg was the true inventor of movable type printing, but there is no doubt that the printing technique developed by Gutenberg was passed down to later generations and had a direct influence. It is said that movable type itself was invented by a man named Bi Sheng in the Song Dynasty in the mid-11th century, who made unglazed clay movable type, and by the mid-13th century, metal movable type in Goryeo. However, in early modern Europe, which had alphabet characters suitable for metal movable type and soon entered the Protestant Reformation and the Age of Discovery, this invention became a reality and had a major impact on history itself. This technique, which applies pressure to movable type to print on paper, was far more efficient than any previous publishing technique, and made it possible to print a large amount of clear print in a short time. Within a century, this printing technique had spread throughout the European world at that time, crossing the Alps and the English Channel. Books printed before the 15th century are called incunabula (early published books, books in their infancy), but the average number of copies printed was no more than a few hundred, mainly religious books. However, the total number of incunabula is estimated to be about 20 million, which is an astonishing spread considering that the population of Europe at the time was less than 100 million, most of whom were illiterate. The Roman Catholic Church was concerned by the emergence of movable type printing, and in the 1470s and 1480s it established a publishing license system, and in 1559 it created the famous Index of Prohibited Books to restrict reading. Printers who wanted to monopolize the profits from their business also formed guilds, so books remained expensive products available only to a small portion of the wealthy class. It is estimated that the centers of publishing activity in 15th-century Europe were Italy and Germany, accounting for 42% and 30%, respectively, followed by France at 16% and the Netherlands at 8%. From the 16th to the 18th centuries, publishing gradually expanded from a religious focus to literature and practical books, and at the same time, magazines appeared. The origin of today's magazines is said to be the catalogs published by French booksellers in the 17th century to introduce new publications, but independent periodical publications include the Journal des Sabins, first published in Paris in 1665, and the Bulletin of the British Academy, published in London in the same year. The world's first weekly newspaper, Aviso, was published in Germany in 1609. Thus, publishers emerged as entrepreneurs, replacing the printing and bookselling industries, which had previously accounted for a large proportion of the market. [Hideo Shimizu] Modern PublishingThe French Revolution and the American Independence in the latter half of the 18th century were also landmark events for publishing. The Bill of Rights and the Declaration of the Rights of Man, which are components of modern constitutions, set out freedom of speech and the press as the most basic human rights, and opportunities for citizens to be involved in publishing activities increased. At the same time, publishing finally took off from the printing industry and entered the era of modern publishing. The average number of copies printed per issue also became more than 2,000, and it is said that Thomas Paine's Common Sense, published in Pennsylvania in 1776, actually reached hundreds of thousands of copies. In addition, Byron's The Corsair, published in 1814, sold 10,000 copies on the day of its release. Printing technology also became more efficient, and before the end of Napoleon's reign, the amount of printing in one hour was greater than the amount of printing in one day 15 years earlier. Following in the footsteps of the Netherlands and Germany, publishing activities in England and then America rapidly flourished. The first daily newspaper, the Daily Courant, was published in England in 1702, and popular newspapers appeared in Europe and the United States in the middle of the 19th century. Seeing their rapid spread, French socialist Jean-Louis Blanc declared that "the age of the book is over, and the age of the newspaper has begun," but this was a premature judgment, as publishing began to become more popular around this time. Then, as the 19th century drew to a close, low-priced books were being published in various countries with the intention of selling them on mass sales. The radio appeared soon after the start of the 20th century, ushering in the age of mass communication, and the spread of books and magazines also progressed at a rapid pace. [Hideo Shimizu] Modern PublishingA political and cultural characteristic of the post-World War II era is the phenomenon of mass socialization. In publishing, the phenomenon of massification, symbolized by the so-called paperback revolution, has been remarkable, and book publication is rapidly developing and increasing not only in developed countries but also in developing countries. According to statistics from UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), the total number of books published worldwide in the 45 years from 1952 to 1996 increased 3.3 times from 250,000 to 836,550. Furthermore, consumption of printing and writing paper, excluding newsprint, increased 11.7 times between 1950 and 1997. This clearly shows that publications, which were previously the exclusive domain of a small literate and intellectual class, have become mainstream. However, a few notable phenomena have emerged amid this massification of publishing. The first is the domination of the publishing market by huge media and non-media capital. In the United States in particular, the best-seller syndrome, known as the "blockbuster era," is eroding healthy publishing activity, but similar phenomena are also emerging in other developed countries. The second is the remarkable progress of electronic technology. The publishing industry is undergoing major changes, including the generalization of computer editing, the sale of CD-ROMs, DVDs, and e-books via download (transferring data from a host computer), and the entry of Internet bookstores. The third is the widening publishing gap between developed and developing countries. It is true that publishing in emerging countries has developed in both quality and quantity compared to the colonial era before World War II, but the disparity in economic and technological power has further widened the gap in the level of enjoyment of reading culture among the people. UNESCO designated 1972 as the International Year of the Book and called for the promotion of books in developing countries under the slogan "Books for All." However, to date, with the exception of a few countries, progress has been slow. [Hideo Shimizu] Japanese PublishingBefore the Edo periodIt is generally believed that the history of publishing in Japan began with the oldest surviving printed work, the Hyakumanto Dharani. This is a set of four Dharani sutras that were completed over a period of about five years, from 764 (Tenpyo Hoji 8) to 770 (Hōki 1), and many believe that they were printed by woodblock printing. Woodblock printing became more active at the end of the Heian period, and many temples produced so-called Nanto editions (Nara editions) such as the Kasuga edition and the Hōryū-ji edition. The Gozan editions were published mainly in the five mountains of Kyoto from the Kamakura period to the Muromachi period. Many of the Gozan editions were reprints of Chinese Song editions and Yuan editions, and were influenced by their printing style, but they came to cover not only Buddhist scriptures but also other books (apocrypha). At the end of the same period, private publishers also appeared, and publications called "bokokubon" and "machiban" began to be published for the general public. Meanwhile, movable type printing, which was invented in Europe in the mid-15th century, was brought to Japan by the Tensho Embassy to Europe and Jesuit priest Alessandro Valignano, who returned to Japan in 1590 (Tensho 18). From the following year, 1591, for about 20 years, movable type publications (about 30 titles) were printed in either Roman or Japanese characters, mainly in Kyushu, and are known as "Kirishitan (Christian, Christian) editions." However, the policy of persecuting Christianity that began soon afterwards led to the Kirishitan editions disappearing. Separately, metal movable type was brought to Japan by Toyotomi's expeditionary force, which dispatched troops to Korea, and later the "Keicho Imperial Edition" was published using wood movable type imitating these movable types. [Hideo Shimizu] Edo periodThe "Fushimi" edition, created by order of Tokugawa Ieyasu, used wood type, while the "Suruga" edition used copper type. However, European-style movable type printing did not become widespread due to the complexity of Chinese characters and Japanese characters, and did not see the light of day until the Meiji era. Private publishing in Japan got its start in Kyoto in the early Edo period, but it flourished during the Genroku period (1688-1704). The "Zoueki Shoseki Mokuroku Daizen" (Complete Catalog of All Books), published by Kawachiya Rihee in 1696 (Genroku 9), contains approximately 7,800 books. In 1721 (Kyoho 6), Echizen no Kami Ooka ordered book wholesalers and paper dealers to create a catalog that included 7,446 types of books. In other words, nearly 10,000 books had already been published during this period, but by this time the center of publishing had shifted from Kyoto to Edo. Meanwhile, restrictions on publishing, which began around 1657 (Meireki 3), were not fully implemented until 1722, but after that, although the restrictions were sometimes more frequent, there was a succession of literary scandals for reasons of political criticism and the corruption of public morals. These included the imprisonment and execution of Santo Kyoden, Hayashi Shihei, Watanabe Kazan, and Takano Choei. Famous Edo publishers included Shokai Sanshiro, Urokogataya Sanzaemon, Tsuruya Yoshiemon, Suharaya Mohee, and Tsutaya Juzaburo. [Hideo Shimizu] Meiji and Taisho PeriodsDespite successive crackdowns, Edo publishing expanded its readership through kusazoshi, sharebon, ninjyobon, and kokkeibon, but the rapid development of modern publishing that unfolded after the Meiji period cannot be discussed without considering the accumulation of knowledge during the Edo period. However, the numbered type developed by Motoki Shozo in 1870 (Meiji 3) modernized Japanese publishing in one fell swoop. While encouraging publishing, the government also cracked down on free speech through the Publishing Law and the Libel Law. Publishing began to take off as a business in the 1880s, with Hakubunkan and Shunyodo being representative of the Meiji period. Kodansha and Iwanami Shoten, founded between the end of the Meiji period and the beginning of the Taisho period, both grew significantly and became symbols of prewar Japanese publishing. The contrast between "Kodansha culture" and "Iwanami culture" well represents the prewar publishing situation, which was divided between publications aimed at the masses and those aimed at intellectuals. After the diverse publication of magazines flourished during the Taisho era, the so-called "100 yen book boom" occurred. This was a complete collection battle triggered by Kaizosha's "Complete Works of Modern Japanese Literature," and heralded the beginning of the era of mass production and mass sales. However, with the onset of excessive competition and recession, this quickly turned into a boom in bankruptcies, but by this time Japanese publishing had already grown to the point where it could stand shoulder to shoulder with the world's developed countries. [Hideo Shimizu] Showa PeriodHowever, with the advent of the so-called emergency, publishing control was gradually strengthened, and by the time of the Pacific War, freedom of publishing had been almost completely taken away. The Emperor Organ Theory Incident, the Kawai Eijiro Incident, and the Tsuda Sokichi Incident also had a detrimental effect on publishers, and in the Yokohama Incident of 1944 (Showa 19), many editors were imprisoned. As a result of the defeat, freedom of publishing activities was restored except for those related to the occupying forces, and the public, hungry for print, rushed to buy cheap books and magazines. The full-scale publication of the postwar period began around 1955 (Showa 30), which, together with television, signified the arrival of mass culture. Publishing as an industry had continued to grow at a high rate almost in line with GDP (gross domestic product) since the 1960s, but sales began to decline from the mid-1990s, and have been in negative growth since 1996. Meanwhile, publishing is at a major turning point due to the remarkable progress of electronic technology. [Hideo Shimizu] Current state of publishingJapanPublications can be broadly categorized into books, magazines, textbooks, e-books, and others. Others include educational materials and tapes for educational equipment. Publications can be divided into commercial and non-commercial, depending on the purpose of publication, but it is difficult to distinguish commercial publications conducted by publishers as a business activity from non-commercial publications conducted by universities, research institutes, government agencies, companies, organizations, or individuals. Publications can also be divided into academic/specialized book publishing and general book publishing, but the boundaries between these categories are also unclear. According to the "Japan Book Catalog" (2000 edition), there were 7,150 publishers as of June 2000, but it is believed that only about half of these publishers use the wholesaler-bookstore route to sell their books. The rest are distributed and sold directly. There are 575,000 books in circulation on the market as "new books." This is more than three times the number of companies (entities) and items listed in the inaugural edition of the catalog (1977-78). Looking back at trends in publishing since the 1970s, we can see that Japan's publishing industry has been undergoing rapid change. When the 1970s arrived, Japan loudly proclaimed the "age of the educational information industry" and the "information age." It was around 1970 (Showa 45) that the term "publishing industry" began to spread in the publishing world. Until then, the publishing world had not referred to itself as an "industry" but as the "publishing business," so the 1970s marked the beginning of a change in the publishing world's attitude. A notable movement in the publishing world in 1970 was the phenomenon of magazine segmentation. Magazines that adopted a new approach of segmenting and narrowing down readership rather than targeting all readers began to appear one after another. In 1971, the four women's magazines, Shufu no Tomo, Shufu to Seikatsu, Fujin Club (Club), and Fujin Seikatsu, set a new sales record of 5.57 million copies for the New Year's issue, and women's magazines began to decline (as of 2000, Fujin Club and Fujin Seikatsu were discontinued, and Shufu to Seikatsu was replaced by Suteki na Okusan). In 1971, Kodansha entered the paperback market, and the third paperback boom occurred. In 1973, the first oil crisis caused a shortage of publishing paper, which caused confusion in the publishing world. In 1977, New Family Magazine and Kadokawa's business method of media mix with movies were publicized. In July 1978, Chikuma Shobo, whose business situation had deteriorated, went bankrupt (it was re-launched as a reorganized company in October 1980). In October, the publishing world became even more confused with the sudden announcement by the Fair Trade Commission that it would "reconsider the resale system (resale price maintenance contract system)." When word processors were introduced in 1978 (Showa 53) and advertised as "business document creation machines," there was little interest in them in the publishing and printing industries. However, in the 1980s, the printing industry began to switch to computerized typesetters (CTS), and the electronics and communications equipment industry developed and introduced video discs, laser discs, personal computers, home game consoles, CD-ROMs, and other devices one after another. Around 1985, the publishing industry also became active in DTP (desktop publishing) with the introduction of the Macintosh personal computer developed by Apple. These various new electronic and information devices completely transformed the way publications were produced, edited, and printed, and at the same time, dramatically changed the publishing distribution situation. Following the new media boom of the 1980s, the publishing industry also rapidly went electronic in the 1990s, and in the latter half of the 1990s, Internet-related publishing formats became the main interest of those involved. Meanwhile, the late 1980s saw the collapse of the Soviet Union, the Tiananmen Square incident and German unification, and the collapse of Japan's economic bubble in the 1990s. These sudden changes in political, economic and social situations prompted changes in people's values and consumer behavior. At the same time, the development of computers and other electronic technologies led to the rapid development of communication technologies and devices, networking the world and bringing about an electronic technology revolution for individuals and homes. This momentum shows no signs of stopping, and the media world is in the midst of it all. Printing on paper was once seen as the most stable form of expression for storing and transmitting knowledge, but the publishing world, which was at the core of this, is also being swept away by waves of sudden change. The printing technique using lead type, which was invented by Gutenberg in Mainz, Germany in 1450 and has contributed the most to the development of academic culture and the spread of religion around the world since then, is now considered to have fulfilled its role. In the 1960s and 1970s, many people would not have expected that the printing method using lead type would disappear. That is how rapid the change has been. As the technology of media production and transmission changes, the attitude of those who receive and use it will also change, and so will the way they interpret it. In particular, when media, which were primarily one-way, become capable of two-way, simultaneous transmission and reception in multiple directions, this will inevitably have an impact on the techniques and methods of expression, as well as the content of what is expressed. People who previously only received information but did not have the means to send it can now become senders at any time, calling into question the very nature of the media itself. Copyright laws to accommodate new media have not yet been established. [Kobayashi Kazuhiro] BooksAccording to the Publishing Science Institute's Annual Report on book publishing, the number of new releases was 19,226 in 1970, 27,709 in 1980, and 38,680 in 1990. In 1995, the statistical standards were changed to include new releases other than those distributed in large quantities by distributors (so-called new releases on order), and the number suddenly rose to 61,302, peaking at 65,513 in 1998, but dropping slightly to 65,026 in 1999. Estimated circulation numbers rose from 606,920,000 copies in 1970 to 1,013,170,000 copies for the first time in 1977, peaking at 1,506,320,000 copies in 1996 and 1,508,300,000 copies in 1997, but fell to 1,368,310,000 copies in 1999. Estimated sales figures rose from 471.59 million copies in 1970 to 764.5 million copies in 1980, peaking at 943.79 million copies in 1988. Since then, there have been slight increases and decreases, but since 1996, there has been a steady decline, reaching 791.86 million copies in 1999. This is roughly the same level as the 796.97 million copies in 1982. Sales revenue was 224.6 billion yen in 1970, 672.4 billion yen in 1980, and 866 billion yen in 1990, peaking at 1,093.1 billion yen in 1996, before falling to 993.5 billion yen in 1999, returning to the 1992 level (statistics for e-books and other items are unknown). Looking at the number of new books by subject area in 1999, the social sciences led the way with 13,365 titles (20.6% share), followed by literature with 11,367 titles (17.5%) and arts and lifestyle including comics with 10,998 titles (16.9%). All other subjects had numbers in the single digits. As the trend towards an information society grows stronger, people are constantly seeking new information. On the information source side, the distribution situation is becoming increasingly cramped due to a number of problems in the distribution of publications, but the publishers (people) disseminating new information continue to increase year by year. However, information-based books quickly become outdated and disposable. This cycle is the main cause of the high rate of returns. According to the million-seller list from 1946 onwards, the number of hits has been increasing rapidly since the 1970s. Also, since the 1980s, entertainment-related books such as those featuring celebrities have become more prominent. There are many cases where books sell 1 or 2 million copies in a short period of time, but are no longer available in stores within a few years. Looking at the categories, we can see a decline in the market share of children's books and study guides, but there has been no major change in the market share of literary and specialized books by genre. Although there have been major changes in the content of literary and specialized books, these do not show up in the statistics by genre. The category that has been steady, or rather, has shown a notable increase, is practical books, but even here the range is widening, and the rise and fall of practical books seems to be severe. [Kobayashi Kazuhiro] magazineThe number of magazines, including academic journals, government journals, company/organization magazines, doujinshi, etc., exceeds 20,000, but the trends of magazines distributed in the publishing market since 1970 (from the Annual Report above) are as follows (from the previous Annual Report). Monthly magazines 1,722 (1970), 2,498 (1980), 2,721 (1990), 3,305 (1999). Weekly magazines 49 (1970), 59 (1980), 81 (1990), and 89 (1999). The circulation of monthly magazines was 841.33 million and weekly magazines 1.100.77 million (1970), but in 1997, the total number of monthly magazines was 3.310.56 million and weekly magazines 1.879.23 million, totaling 5.189.79 million, but in 1999, the monthly magazines 3.091.16 million and weekly magazines 1.723.94 million, totaling 4.815.1 million. The number of monthly magazines reversed from weekly magazines in 1974. The peak of the estimated number of copies sold was 3.910.6 million in 1995 (2.275.87 million, weekly magazines 1.634.73 million), and the estimated sales amount was 1.564.4 billion yen in 1997 (1.169.9 trillion yen in monthly magazines, 394.5 billion yen in weekly magazines). In 1999, the total sales amount was 1.4672 trillion yen (1.096.5 trillion yen in monthly magazines and 370.7 billion yen in weekly magazines), indicating a downward trend. Since magazines reversed the sales amount of books in 1976 (Showa 51), the magazine has been dominated by magazines. However, since 1997, sales for both books and magazines have been down for the fourth consecutive year. Since 1980, the number of magazines first published annually was 235 in 1980, 244 in 1983, 238 in 1984, 245 in 1985, 245 in 1985, 202 in 1995, and 200 in 1996, and over 200 in 17 years. As of 1999, the number of magazines was published was 3,305 monthly magazines and 89 weekly magazines. It is believed that magazines that respond to information more than books will continue to dominate. However, some people believe that information-providing magazines will no longer be necessary due to the widespread use of the Internet. [Kobayashi Kazuhiro] ComicsAlthough it is seen as a phenomenon common to developed countries in publishing countries, the popularization of publication is also noticeable in Japan. The number of paperbacks and new book formats continues to increase, as well as the number of magazines in magazines. In particular, comics, which had been rapidly expanding since the 1980s, fell to 252 billion yen in 1994, with an estimated sales amount of 335.7 billion yen in comic magazines, which have peaked at 335.7 billion yen in 1995, and have continued to decline since then. As of 1999, comic magazines have increased by 230.2 billion yen and comic magazines, and 304.1 billion yen, totaling 534.3 billion yen. The circulation of the volume was 631.46 million comic books in 1999 and 1.382.54 million comic magazines (according to the Institute of Publication Science). Although comic books have sold at a plateau, they still hold a large proportion of the publishing market. [Kobayashi Kazuhiro] Import/Exportになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The largest importer is also the United States, with books of 10,137,180,000 yen and magazines of 6,555,660,000 yen, both of which are well ahead of second place or below. [Kobayashi Kazuhiro] Increase in bookstoresAccording to a survey conducted by the Ministry of International Trade and Industry (now the Ministry of Economy, Trade and Industry), the total sales area of bookstores nationwide was 798,423 square meters. As of the end of June 1994, it had expanded to 2,651,473 square meters, and by 1997 it exceeded 3.15 million square meters, and the number of floors continued to increase. Meanwhile, in 1999, the number of convenience stores was 39,754, and the sales of books and magazines was estimated to be 507.1 billion yen (total sales of major convenience stores were 6,9116 trillion yen). [Kobayashi Kazuhiro] Information and logisticsWhen looking at the publishing world as a whole, bibliographic information preparation and real-time information provision are delayed. Furthermore, reader services that link this information to logistics have been significantly delayed. Individually, major contractors and major publishers are keen to improve information provision and logistics improvements, and we can see how progress is progressing every year. However, from the reader's perspective, the delay in handling orders remains old. While information is circulating around the world in real time on the Internet, the publishing industry is finally experiencing rapid developments, such as providing information via the Internet and online bookstores led by intermediaries, but the industry as a whole is improving slowly. There are many voices that rapid reforms are needed. Furthermore, the Japan Federation of Shoten Commercial Associations (Nichishoren) began to turn bookstores into SA (store automation) in 1983 (Showa 58), and it was also in 1983 that Tohsen (now Tohan) and Nihon Shoten all announced a publishing information search system. [Kobayashi Kazuhiro] Resale issues and moreになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. If the resale system is abolished, it is expected that the way publication sales will change completely. The consumption tax was confused twice, when it was first introduced in March 1989 (Heisei 1) and the tax rate increase in April 1997. In 1989, both books and magazines adopted the tax includ-only display method, and in 1997, the book only displayed the tax from the tax includ-only display method to the tax exclud-only display method. Moreover, the industry's inability to establish a uniform standard under the Consumption Tax Act, also likely amplified the confusion. The publishing world has been stagnant and confused since the 1990s, but there are also new movements. A total of 5,000 people participated in the Daisen Midori Yin Symposium, which was held five times in a row by the Yonago Imai Shoten Group, and the publishing industry discussed various issues facing the issue for three days each, and a collection of records was published. In addition, inspired by Funabashi Gakuen Reading Research Group's "Morning Reading Born a Miracle" (1993, Takabunken), a 10-minute morning reading campaign was launched at approximately 4,000 elementary, junior high and high schools across the country by the summer of 2000. These were great stimulations, and the book of reading promotion campaigns that have been active throughout the publishing world. Currently, these reading campaigns do not have the strength to influence the sales of publications, but there is hope that in the future, it will become a huge underground vein. With the estimated that the Internet, e-books, and mobile phones are decreasing the sales of traditional publications, the publishing industry is continuing to explore positively, even though the future is uncertain. [Kobayashi Kazuhiro] worldになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In the United States, there have been a series of mergers and acquisitions across borders and industries, with the merger between internet-related giant American Online (AOL) and media giant Time Warner merged in 2000. になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. [Kobayashi Kazuhiro] From publishing plans to reach readersPublishing usually outsources manufacturing processes such as paper, printing, and binding to external sources. There is almost no example of directly manufacturing them in-house with a factory. In terms of sales, most publishers rarely sell directly to readers, and use distributors, bookstores, and sales companies. Publishers mainly engage in planning, editing, advertising, and other duties. Related tasks such as planning, editing, production, and sales differ depending on the content, such as books, magazines, and textbooks, so here we will focus on books. [Kobayashi Kazuhiro] planBook publications are planned based on each company's own publishing policy and editorial policy. In planning, subject matter, writing guidelines, author, writing guidelines, author, book-making court, number of copies, distribution method, and preliminary prices are set, and materials such as printing companies, bindings, paper and other materials are selected. Manuscripts are often brought in by the author. Newly founded publishers do not plan after the company's founding, but instead decide on publishing policies and authors in advance, and manuscripts are prepared in advance. [Kobayashi Kazuhiro] editになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. In addition, there are increasing numbers of publishers who also perform tasks such as layout and page-up (making the appearance of each page in a state that is involved in the printing process) using DTP. Each publisher has rules that have been customarily made for the order of composition of books, such as doors, prefaces, table of contents, text, indexes, chronology, and afterwords. [Kobayashi Kazuhiro] Printing and bindingになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. になったんです。 English: The first thing you can do The work style of the author, editor, and printing company has changed dramatically. After printing, the printed book is taken by the bookbinding shop, turned into folded books based on 16 pages, and is organized into a single volume with the door, frontispiece, and the book is collected in one volume (collected), and if it is a book bound (book bound), it is bound with thread, bound with a cover, boxed or covered, and completed. In the case of temporary binding (parallel binding), it is wire bound instead of thread bound, or wirelessly bound with adhesive. There are many cases where the book is omitted. Furthermore, as a new method and technology for On-Demand Publishing was developed in the United States in the late 1990s. This is a system that prints, binds, and sells only the required number of copies according to the orders of books accumulated on computers, based on the original data of books stored on computers. It was introduced in Japan at the end of the 1990s, and in 2000, On-Demand Publishing was launched under the leadership of distributors and major printing companies such as Tohan, Nihon Shoten, Dai Nippon Printing, and Toppan Printing. Currently, On-Demand Publishing is slow to come into play, but it is said that in the future, as with academic publishing in the United States, there will be an increasing number of cases where specialized books and academic literature are published in the on-demand format. [Kobayashi Kazuhiro] Distribution and salesになったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. New publications are commissioned for six months between publishers and distributors and bookstores, and four months between publishers and bookstores, but due to the small size of bookstores and the increased volume of publication, it is not uncommon for them to be returned within a week. The excessive return rate became a problem within the industry in the 1960s, but despite various measures to reduce returns, the rate of book returns continued to rise since the 1980s, reaching 41% in 1998. In addition, these returns have been attracting attention from the Fair Trade Commission for some time, and as mentioned above, the chairman of the Fair Trade Commission made a statement to review the resale system (resale price maintenance contract system) in October 1978. The resale system that had been implemented since June 1956 was partially revised in October 1980, making it possible to publish "non-resale books." になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do. The "Nihon Tosho Code" is being implemented to promote smooth distribution and to centralize bibliographic information. This is a system that mainly uses the International Standard Book Number (ISBN) that represents books from around the world as 10 digits (digits), and includes classification codes, price codes, etc., and it seems that barcodes are now almost in place. There are also some who point out that further publication information needs to be prepared in order to adapt to electronic commerce in the Internet age. [Kobayashi Kazuhiro] になったんです。 English: The first thing you can do is to find the best one to do . ▽ Koide Takeo's Theory of Modern Publishing Industry: The Structure of Competition and Collaboration (1992, Japan Editor School Publishing Department) ▽ Shimizu Hideo's Freedom of Publishing Studies and Publication: Selection of Publication Papers (1995, Japan Editor School Publishing Department) ▽ "Compiled by the Japan Publishing Society, "Verification of Publication - From Defeat to the Present" (1996, Bunka Tsushinsha)" ▽ Minowa Naruo's Introduction to Publishing Studies (1997, Japan Editor School Publishing Department) ▽ Takamiya Toshiyuki and Harada Noriko's "Illustrated Books and the History of People" (1997, Kashiwa Shobo) ▽ "Shinbun" Editorial Department, "Archipelago Bookstore Map - Going through the Battlefields" (1998, Yuyu Publishing)" ▽ "How Publishers and Bookstores Disappear" (1999, Paru Publishing)" ▽ "Iegami Takayuki, Nagae Akira, Yasuhara Akira, "Super Severe Hilarious Discussion: Is there a Future for "Publishing"?" (1999, Seiunsha)" [Reference items] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Source: Shogakukan Encyclopedia Nipponica About Encyclopedia Nipponica Information | Legend |
|
出版とは、販売、配布の目的で文書や写真、絵画などの著作物を複製、刊行することをいう。活版印刷が普及されるまでの印刷は木板が中心であったので、開板(かいばん)、上梓(じょうし)、板行(はんこう)、発兌(はつだ)などのことばが用いられた。広義では新聞など印刷物の刊行をすべて含むが、普通は書籍、雑誌の刊行を意味する。現代は活字による印刷からコンピュータ電子印刷へ、さらには電子出版へと急速に移りつつある時代である。 [清水英夫] 出版の機能長い間、人間社会のコミュニケーションの道具として用いられてきた出版は、活版印刷の出現後、しだいにマス・メディア化するに至った。しかし、新聞やさらにラジオ、テレビなどと比べると、情報伝達の速報性、同時性、広域性などの点で劣るかわりに、正確性、論理性、蓄積性などにおいて、依然、出版はもっとも優れたコミュニケーション・メディアということができる。すなわち、ニュース性を重んじる新聞は、メッセージの系統性や分析性に限界があるし、視聴覚メディアは娯楽性や映像性などに重点が置かれるため、思想の多様性、論理性が犠牲となる傾向がある。一般的にマス・メディアは、情報の受容態度を受動的、消極的とする特徴をもっており、この特性が受け手の趣向や思想を画一化させることになる。この点、出版は、文字による伝達を中心とし、またきわめて多様で濃密な情報を送ることができるので、民主主義にとって不可欠な思想の多様性であるとか、少数の受け手を対象とする高度な学術や文芸の伝達を可能とさせている。 他方、出版は往々ダイナミズムや総合的表現力に欠け、現代的状況やニーズにかならずしも十分に適応できない弱点をもっている。とくにそれは書籍出版にみられるところであるが、この弱点は同時に、人々の観点が著しく微視的になったり、大勢順応的になったりするのを防ぐ役割を演ずることになる。そのことは、オピニオン・ジャーナリズムや社会科学の発展のうえで無視できない特質といえよう。しかしながら、マス・コミュニケーションは電子技術の著しい発達によって、大きく変化しつつある。それは、ことに放送や通信の分野で激しいが、出版においても編集、製作、販売(伝達)の諸過程に大きな変革をもたらしており、グーテンベルク以来の複製文化の歴史に一紀元を画しつつある。なお、出版を科学的に研究、調査することを目ざす学問を出版学editologyといい、日本では1969年(昭和44)に日本出版学会が結成された。 [清水英夫] 出版業の特色出版は、マスコミ産業のなかでも比較的小資本でも可能な事業である。その点、巨額な資本を必要とする新聞や放送に比べて、新規事業の市場参入が比較的容易であり、日本の出版社数は増大を続けてきた。したがって、他のメディア産業にみられない自由競争が出版では行われている反面、資本金、従業員数が少ない会社が多いなど、企業としての脆弱(ぜいじゃく)性が存在することは否定できない。固定資本に比べて流動資本が大きく、人件費や宣伝費の比重が高いことや、商品価値に客観性が乏しいこと、またとくに日本の出版は国際性が薄いことも、出版事業を不安定なものとさせてきた。しかし、一部の大手出版社は市場占有率も大きく、マス・マガジンなど安定商品をもち、広告収入も巨額に上っているので、ひところの零細イメージから脱却してきている。しかし、若者たちを中心にみられる「活字離れ」現象やメディア情報の氾濫(はんらん)などにより、業界全体としては出版事業はしだいに困難なものになってきている。 [清水英夫] 出版の歴史出版の歴史は本の歴史でもある。本の定義にもよるが、多くの書誌学者は、今日に残る最古の本として、楔形(くさびがた)文字を案出したメソポタミア・シュメールの粘土板(クレー・タブレット、前3100年ごろ)をあげている。ここを出発点として、世界の出版史はほぼ次の5期に分かつことができる。 [清水英夫] 本の登場木、竹、粘土、金属、蝋(ろう)などの材料に刻み込まれた文字や絵は、しだいにより軽くて柔軟な物質の利用を求めて変化する。すなわち、パピルス(前3000年ごろ)、絹(前1200年ごろ)、皮(前30年ごろ)などに書き込まれた文字は、巻物(ラテン語でボルーメンvolūmen)、冊子(コーデックスcodex)などの形態により、しだいに今日的な書籍の体裁を整えていった。古代ギリシアでは紀元前5世紀から書肆(しょし)が現れ、ローマでは前207年に写字生の同業組合がつくられている。筆写にあたったのは僧侶(そうりょ)や奴隷であるが、賃労働に移行するとともに、本の値段も上がっていった。30センチメートル四方しかない1枚のパピルスには、いくらも字が書けないので、20~30枚のパピルスを糊(のり)で継ぎ合わせ、巻物としたのがボルーメンである。羊皮紙(パーチメント)が登場するのは前170年ごろの小アジアであるが、6世紀ごろまで、このボルーメンがローマを中心とする文化圏の本の主流を占めた。中国では、前3世紀の秦(しん)の時代に木簡や竹簡を用いた書物が現れているが、経典の文を石に彫って拓本とする石経(せっけい)も用いられている。印刷の始まりといってよいであろう。紀元後105年ごろ後漢(ごかん)の時代に蔡倫(さいりん)という人物によって初めて紙が発明される。そして、7世紀の唐時代初期に発明された木版技術とあわさって木版印刷の長い時代が始まるのである。洛陽(らくよう/ルオヤン)で、官吏登用試験のため大規模な印刷事業が行われたのは932年のことである。 [清水英夫] 写本の時代パピルスよりも粗末だが、ずっと頑丈で安価な羊皮紙は、キリスト教徒によって大いに用いられ、やがて中世における書籍の主流を形成することになる。羊皮紙は1枚ごとに切って綴(と)じることにより、現代の書籍の特徴であるページ編成の冊子(コーデックス)がくふうされた。この形式は長文の聖書や法律文書にとくに向いており、コーデックスからコードcode(法典)ということばも生まれた。紀元4世紀以後1000年以上にわたって、聖職者たちにより羊皮紙の写本が中世ヨーロッパの出版文化を担った。写本はしだいに美しいものになり、とくに中世後期の写本は極彩色の細密画を有する美術品でもあり、また洗練されたアルファベット文字は、次代の活字(タイプ・フェース)に直接影響を与えている。この時代、ラテン語から分かれたロマンス諸言語(フランス語、スペイン語、イタリア語など)で騎士物語であるロマンスが書かれ出版された。すなわち小説novelのルーツである。 [清水英夫] 活版印刷の発明活版印刷の真の発明者がヨハン・グーテンベルクであるかどうかは説の分かれるところであるが、後世に伝わり直接の影響を与えたのがグーテンベルクの開発した印刷術であることは疑いない。もっとも活字そのものは、すでに11世紀なかばの宋(そう)の時代に畢昇(ひっしょう)という人物が粘土を素焼きした陶活字を、また13世紀のなかばごろ高麗(こうらい)で金属活字が発明された、といわれている。しかし、金属活字にふさわしいアルファベット文字をもち、またまもなく宗教改革と大航海時代を迎えた近世ヨーロッパは、この発明を現実のものとし、歴史そのものを大きく左右させたのであった。活字に圧力(プレス)を加えて用紙に印刷するこの技術は、これまでのいかなる出版技術よりもはるかに能率的で、短時間に多量で鮮明な印刷を可能にした。この印刷術は1世紀たらずのうちに、アルプスを越え、ドーバー海峡を渡って、当時のヨーロッパ世界にくまなく普及した。 15世紀以前に印刷された書籍をインキュナブラincunabula(初期刊行本・揺籃期本)とよんでいるが、宗教書を中心とするその平均印刷部数は数百部以内にすぎなかった。しかしインキュナブラの総部数は約2000万部と推定されており、当時のヨーロッパ人口が1億に満たず、その大半が非識字者であったことを考えると、驚くべき普及ぶりであったといえよう。活版印刷の出現に危惧(きぐ)を抱いたのはローマ教会で、1470年代から80年代にかけて出版免許制度を敷き、1559年には有名な禁書目録をつくって読書規制を行っている。また、事業の利益を独占しようとする印刷業者たちはギルドをつくったので、書籍は依然として一部富裕階級のみが利用できる高価な商品であった。 15世紀ヨーロッパにおける出版活動の中心はイタリアおよびドイツで、それぞれ42%、30%を占め、続いてフランス16%、オランダ8%であったと推定されている。16世紀から18世紀にかけて、出版は宗教中心からしだいに文学や実用書へと拡大していったが、同時に雑誌が姿を現してくる。今日の雑誌の起源は、17世紀フランスの書籍業者が新刊紹介のため発行したカタログだといわれるが、独立した定期刊行物としては、1665年にパリで創刊された『ジュルナール・デ・サバン』および同年ロンドンで刊行されたイギリス学士院の会報とされている。また、世界最初の週刊新聞『アビソ』が1609年にドイツで発行されている。こうして、これまで大きな比重を占めていた印刷業や書籍販売業にかわって、出版業者が企業家として登場することになる。 [清水英夫] 近代出版18世紀後半におけるフランス革命やアメリカの独立は、出版にとっても画期的なできごとであった。近代憲法の構成要素としての権利章典や人権宣言は、もっとも基本的な人権として言論・出版の自由を掲げ、市民が出版活動に携わる機会は増大した。それとともに、出版業はようやく印刷業から離陸して近代出版の時代を迎えることになる。1点当りの平均発行部数も2000部以上となり、1776年にペンシルベニアで発行されたトマス・ペインの『コモン・センス』は実に数十万部に達したといわれる。また、1814年に発行されたバイロンの『海賊』は発売当日で1万部を売り切った。印刷技術も高能率化し、ナポレオンの治世が終わるより早く、1時間の印刷量は15年前の1日分よりも多くなっていた。オランダやドイツの後を追ってイギリス、さらにはアメリカの出版活動が急速に隆盛となった。 イギリスで最初の日刊新聞『デーリー・クーラント』が1702年に発行されたが、19世紀のなかばには欧米で大衆新聞が出現している。その急速な普及を目前にみて、フランスの社会主義者ジャン・ルイ・ブランは「本の時代は終わり、新聞の時代が始まった」と述べたが、その判断は早計で、このころから出版の大衆化が始まっている。そして、19世紀も終わりに近づくころには、マス・セールを前提とした低定価本の出版が各国で行われるようになった。20世紀に入ってまもなくラジオが出現し、マス・コミュニケーションの時代に入るが、書籍、雑誌の普及も急ピッチで進んだ。 [清水英夫] 現代出版第二次世界大戦後の政治的・文化的特徴はその大衆社会化現象にある。出版においても、いわゆるペーパーバック革命に象徴される大量化現象が著しく、先進国はもとより開発途上国においても、書籍の発行は急速に発展・増大しつつある。ユネスコ(国連教育科学文化機関)の統計によれば、1952年から96年までの45年間に世界で出版された書籍の年間総発行点数は、25万点から83万6550点と3.3倍に増大している。また、新聞用紙を除く印刷・筆記用紙の消費量は、1950~97年の間に11.7倍に伸びている。従来は、一部の識字・知識層の独占物であった出版物が一般化したことを如実に示しているといえよう。 しかし、このような出版の大量化のなかで目だった現象がいくつかある。その第一は、巨大なメディア資本、メディア外資本による出版市場の制覇である。とくにアメリカでは「ブロックバスターblockbuster時代」とよばれるベストセラー症候群が健全な出版活動を侵食しつつあるが、その他の先進国においても似たような現象が現れている。第二は、電子技術の著しい進歩である。コンピュータ編集作業の一般化をはじめ、CD-ROM、DVD、電子書籍のダウンロード(ホストコンピュータからデータを転送すること)販売、インターネット書店の参入など、出版事業に大きな変革が訪れている。第三は、先進国と開発途上国との間の出版ギャップがますます拡大していることである。確かに、新興諸国の出版が第二次世界大戦以前の植民地時代に比べて質・量ともに発達していることは事実であるが、経済力や技術力の格差により、読み物文化のうえでも国民の享受度の開きがさらに大きくなっている。ユネスコは1972年を国際図書年とし、「ブックス・フォア・オール」(みんなに本を!)のスローガンにより、開発途上国における図書普及を訴えたが、今日までのところ、一部の国を除いて、成果は遅々としているのが現実である。 [清水英夫] 日本の出版江戸時代以前日本の出版の歴史は、現存最古の印刷物『百万塔陀羅尼(だらに)』に始まるとするのが通説である。これは764年(天平宝字8)から770年(宝亀1)まで約5年をかけて完成した4種の陀羅尼経であり、木版により印刷されたとみる説が多い。木版印刷が活発化するのは平安末期からで、「春日(かすが)版」「法隆寺版」などのいわゆる南都版(奈良版)が多くの寺院でつくられた。また、鎌倉時代から室町時代にかけて京都五山を中心に出版されたのが「五山版」である。五山版は中国の宋(そう)版、元版の復刻が多く、またその版式の影響を受けているが、従来の仏典からそれ以外の書籍(外典(げてん))にも及ぶようになった。そして同時代末期には民間の出版業者も現れ、「坊刻(ぼうこく)本」とか「町版(まちばん)」とよばれる出版が一般人を対象に行われるようになった。 一方、15世紀中葉にヨーロッパで発明された活版印刷術は、1590年(天正18)に帰国した天正(てんしょう)遣欧使節とイエズス会神父アレサンドロ・バリニャーノによって日本にもたらされた。翌91年から約20年間にわたって九州を中心にローマ字または日本字で印刷された活字出版物(約30点)を「キリシタン(切支丹、吉利支丹)版」とよんでいる。しかし、まもなく始まったキリスト教弾圧政策によりキリシタン版も姿を消すことになる。これとは別に日本に金属活字をもたらしたのは朝鮮に出兵した豊臣(とよとみ)遠征軍で、のちにこの活字を模した木活字を用いて「慶長(けいちょう)勅版」が出版された。 [清水英夫] 江戸時代徳川家康の命でつくられた「伏見(ふしみ)版」は木活字、「駿河(するが)版」は銅活字を用いたものである。しかしながら、ヨーロッパ流の活版印刷は漢字・和字の複雑さから普及するに至らず、明治を迎えるまで日の目をみることはなかった。日本の民間出版が緒につくのは江戸時代初期の京都であるが、それは元禄(げんろく)時代(1688~1704)になって開花する。1696年(元禄9)河内屋利兵衛(かわちやりへえ)が刊行した『増益書籍目録大全』には、約7800点に上る書籍が収録されている。また1721年(享保6)、大岡越前守(えちぜんのかみ)が書物問屋、草紙(そうし)屋に命じて作成させた書物目録には7446種の書籍が掲載されている。すなわち、この時代すでに1万点近い本が発行されていたわけであるが、このころまでに出版の中心は京都から江戸へ移ることになる。 一方、1657年(明暦3)ごろから始まった出版規制は、1722年になって本格的な取締条目が発布されるが、その後はときに緩急はあれ、政治批判と風俗壊乱の理由で筆禍事件が相次ぐことになる。山東京伝(さんとうきょうでん)、林子平(しへい)、渡辺崋山(かざん)、高野長英らの投獄、処刑がそれである。江戸の版元として有名なのは松会(しょうかい)三四郎、鱗形屋三左衛門(うろこがたやさんざえもん)、鶴屋喜右衛門(つるやよしえもん)、須原屋茂兵衛(すはらやもへえ)、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)らである。 [清水英夫] 明治・大正期相次ぐ取締りにもかかわらず、江戸の出版は草双紙、洒落(しゃれ)本、人情本、滑稽(こっけい)本などを通じて読者層を拡大していったが、明治以降に展開された近代出版の急速な発達も、江戸時代の蓄積を除いては語りえない。しかし、1870年(明治3)本木昌造(もときしょうぞう)によって開発された号数活字は、日本の出版を一挙に近代化させることになった。政府は一方で出版を奨励するとともに、出版法や讒謗律(ざんぼうりつ)によって言論活動を取り締まった。出版事業が企業として軌道に乗り出すのは明治20年代からで、博文館、春陽堂などが明治期を代表して活躍した。明治末期から大正初期に創立された講談社と岩波書店は、ともに大きく発展して、戦前日本の出版を象徴する存在となった。「講談社文化」と「岩波文化」という対比は、大衆向けと知識人向けとに分断されていた戦前の出版状況をよく表している。 大正時代に開花した多様な雑誌出版のあと、いわゆる「円本ブーム」がおこった。これは改造社の『現代日本文学全集』が引き金となった全集合戦で、マス・プロ、マス・セール時代の開幕を告げるものであった。しかし、過当競争や不況の到来で、それはたちまち倒産ブームに転化したが、このころ、すでに日本の出版は世界の先進国と肩を並べるまでに成長していた。 [清水英夫] 昭和期しかし、いわゆる非常時の到来とともに出版統制はしだいに強化され、太平洋戦争を迎えるころには、ほとんど出版の自由は奪われていた。天皇機関説事件、河合(かわい)栄治郎事件、津田左右吉(そうきち)事件は出版人にも累を及ぼしたが、1944年(昭和19)に起きた横浜事件で多数の編集者が投獄された。敗戦の結果、出版活動の自由は占領軍関係を除いて回復され、活字に飢えた大衆は粗末な本や雑誌にも殺到した。戦後出版の本格化は55年(昭和30)ごろから始まるが、それはテレビとともにマス文化の到来を意味した。産業としての出版は、1960年代からGDP(国内総生産)とほぼ軌を一にして高度成長を続けてきたが、90年代なかばから売上高がダウンし、96年以降は連続してマイナス成長に入った。一方、電子技術の著しい進歩によって出版は大きな転機にたたされている。 [清水英夫] 出版の現状日本出版物の種類は、書籍、雑誌、教科書、電子書籍、その他に大別することができる。その他には、教育用教材、教育機器用テープなどが含まれる。発行の目的別には、営利的出版と非営利的出版に分けることができるが、出版社が企業活動として行う営利的出版と、大学、研究機関、官公庁、企業、団体、あるいは個人が行う非営利的出版は、その出版物から識別することは困難である。また、内容別には、学術・専門書出版と一般書出版に分けられるが、この境界もあいまいである。出版社(者)の数は、『日本書籍総目録』(2000年版)によると、2000年6月現在7150社となっているが、取次―書店ルートを利用して市販している出版社はその約半数とみられている。そのほかは直接配布、直接販売である。「新刊本」として市場に流通している書籍は57万5000点である。同目録の創刊版(1977~78年版)では2156社(者)、18万7668点だから、3倍強となっている。 1970年代以降の出版物の動向について流れを追って振り返ってみると、わが国の出版界はめまぐるしい変化を続けていることがわかる。70年代を迎えたとき、日本では「教育情報産業の時代」とか「情報化時代」が声高に唱えられた。出版界に「出版産業」という用語が浸透してゆくのも、この70年(昭和45)前後のことであった。それまで出版界は自らを「産業」とはいわず「出版業」と称していたので、70年代になって出版界の意識改革が始まったことになる。70年、出版界に起きた顕著な動きは、雑誌のセグメント化(細分化)現象であった。すべての読者を網羅的に対象にするような雑誌ではなく、読者対象を細分化して絞り込むという新たな方針の雑誌が次々に登場してくる。なお、『主婦の友』『主婦と生活』『婦人倶楽部(クラブ)』『婦人生活』の婦人4誌が新年号合計557万部の販売記録をつくるのが71年で、以後婦人誌は衰退を始める(2000年現在、『婦人倶楽部』『婦人生活』は廃刊、『主婦と生活』は『すてきな奥さん』に代替した)。この71年には講談社の文庫本参入により第三次文庫本ブームが起きた。また、73年には第一次オイル・ショックによる出版用紙不足が出版界を混乱させた。ニューファミリー・マガジン、映画とのメディア・ミックスによる角川商法が喧伝(けんでん)されたのは77年である。78年7月、経営状態の悪化した筑摩(ちくま)書房が倒産する(80年10月に更生会社として新発足)。10月には公正取引委員会の突然の「再販制(再販売価格維持契約制度)見直し」発言で出版界の混迷はさらに深くなっていく。 1978年(昭和53)、ワープロが「ビジネス文書作成機」として宣伝され登場したとき、出版業、印刷業界はワープロへの関心は低かった。しかし、印刷業界では1980年代には電算植字(CTS)化が始まり、電子通信機器業界はビデオディスク、レーザーディスク、パソコン、家庭用ゲーム機、CD-ROMなどを次々に開発、市場に登場させていた。85年前後には出版界でもアップル社の開発したパソコン、マッキントッシュ導入によるDTP(デスクトップ・パブリッシング)が盛んになった。これら各種の新しい電子機器、情報機器は、出版物の製作、編集、印刷方法を一変させ、同時に出版流通事情をも激変させることになる。1980年代のニューメディア・ブームに続いて、90年代は出版界でも電子化が急速に進み、90年代後半にはインターネット関連の出版形態が関係者の主要な関心事となってゆくのである。 一方、1980年代末にはソ連崩壊が始まり、天安門事件、ドイツ統一が起き、90年代に入ると日本経済のバブルが崩壊する。政治・経済・社会状況の急変は、人々の価値観や消費行動に変化を促した。同時に、コンピュータなど電子技術の発達は、通信技術・通信機器の急速な開発をもたらし、世界をネットワーク化し、個人・家庭内に電子技術革命を持ち込んだ。そのいきおいは止まるところを知らず、メディアの世界はその渦中にある。紙に印刷するという表現形式は、もっとも安定した、知識の保存、伝達の手段とみられていたが、その中核であった出版界も急変の波に洗われている。 1450年、ドイツ・マインツの人グーテンベルクが発明し、以後の世界の学術文化の発達、宗教の普及にもっとも貢献した鉛活字の印刷術は、その役割をすでに終えたとみられている。鉛活字による印刷方式が消滅することなど1960~70年代のころは多くの人が予想だにしなかった。それほど変化は急である。 メディア制作、伝達の技術が変われば、それを受け取る側、利用する側においても、受容の態度が変化し、解釈方法も変わっていくだろう。とくに一方通行が主であったメディアが、双方向、多方向同時に発受信可能となれば、表現技術や表現の方法、表現する内容に影響しないわけにはいかない。従来は受信する一方で、発信の手段をもたなかった人たちが、いつでも発信する側にまわることが可能になったことで、メディア自体のあり方が問われている。なお、新しいメディアに対応する著作権法もまだ確立していない。 [小林一博] 書籍書籍の出版状況は出版科学研究所の「年報」によると、新刊点数は1970年1万9226点、80年2万7709点、90年3万8680点となっている。95年からは取次が扱う大量配本以外の新刊(いわゆる注文扱い新刊)も含めた統計基準に変わり、一挙に6万1302点となり、98年には6万5513点のピークに達したが、99年は6万5026点とやや減少した。推定発行部数は1970年の6億0692万冊が、77年に初めて10億1317万冊と大台に乗り、96年には15億0632万冊、97年15億0830万冊とピークに達したが、99年は13億6831万冊となっている。推定販売部数は、1970年の4億7159万冊が、80年には7億6450万冊と上昇し、88年の9億4379万冊がピーク。以後、微増減を繰り返し96年以降は減少の一途で、99年は7億9186万冊となっている。これは1982年の7億9697万冊とほぼ同水準である。販売金額は1970年2246億円が、80年6724億円、90年8660億円となり、96年1兆0931億円をピークに、99年は9935億円に落ち、1992年の水準に戻った(電子書籍その他の統計は未詳)。 分野別書籍新刊点数は、1999年では社会科学部門の1万3365点(占有率20.6%)がトップで、文学1万1367点(同17.5%)、コミックスを含めた芸術・生活1万0998点(同16.9%)と続き、他分野はいずれも1桁(けた)台である。 情報化社会志向が強まるなかで、人々はつねに新しい情報を求めて止まない。発信者側も出版物流通上のいくつかの問題のため流通事情が窮屈さを増すなか、新しい情報を発信する。発信する出版社(者)も年々増え続けている。しかし、情報提供型の本は陳腐化が早く、消耗品化してしまう。この繰り返しが高率な返品の主因となっている。 1946年以降のミリオンセラーリストによると、点数は1970年代以降が急増している。また、80年代以降はタレントものなどエンターテインメント系のものが目だつ。短期間に100万、200万部売りながら、数年たたないうちに店頭には見当たらなくなってしまう例が多い。 分野別にみて、児童書、学習参考書の占有率は低落を読みとれるが、文芸書や専門書は、ジャンル別占有率としては大きな変動はない。もっとも文芸書の内容、専門書の内容には大きな変化があるものの、それらはジャンル別統計値としては表れてこないのである。堅調そのものというか、上昇が際だつのは実用書の分野であるが、これも該当する範囲が広くなっており、実用書のなかでの盛衰は厳しいようである。 [小林一博] 雑誌雑誌は、学術誌、官公庁誌、会社・団体誌、同人誌などを含めると2万点を超えるが、出版市場に流通している雑誌の、1970年以降の推移は以下のとおりである(前掲「年報」より)。月刊誌1722点(1970)、2498点(1980)、2721点(1990)、3305点(1999)。週刊誌49点(1970)、59点(1980)、81点(1990)、89点(1999)。発行部数は月刊誌8億4133万冊、週刊誌11億0077万冊(1970)が、97年に月刊誌33億1056万冊、週刊誌18億7923万冊、合計51億8979万冊に達したが、99年には月刊誌30億9116万冊、週刊誌17億2394万冊、合計48億1510万冊に減少した。なお、月刊誌の発行部数が週刊誌を逆転したのは、1974年(昭和49)からである。推定実売部数のピークは95年の合計39億1060万冊(月刊誌22億7587万冊、週刊誌16億3473万冊)、推定販売金額のピークは97年の1兆5644億円(月刊誌1兆1699億円、週刊誌3945億円)である。99年は合計1兆4672億円(月刊誌1兆0965億円、週刊誌3707億円)の販売金額であり、減少傾向を示している。1976年(昭和51)に書籍の販売額を雑誌が逆転して以来、雑誌優位が続いている。ただし、97年からは書籍、雑誌ともに売上げ前年比減が4年連続となった。 年間の創刊誌数は、1980年以降では、80年235誌、83年244誌、84年238誌、85年245誌、95年202誌、96年200誌と17年間に200誌以上創刊した年が6回あった。1999年時点の発行数は、月刊誌3305誌、週刊誌89誌である。情報への対応が書籍より有利な雑誌の優勢は今後も続く、とみられている。しかし、インターネットの普及によって情報提供型の雑誌は不要になる、との見方もある。 [小林一博] コミックス出版先進国共通の現象とみられているが、日本の場合も出版の大衆化現象は顕著である。文庫本、新書判などを中心に低価格化、紙装仮製本、雑誌の増加が続いている。とくに、1980年代以降急拡大を続けていたコミックスは推定実売金額で94年の2520億円をピークに減少、コミック誌は95年の3357億円をピークに、以後減少を続けているが、99年時点でもコミックスは2302億円、コミック誌は3041億円、合計5343億円の実売金額を上げている。発行部数は99年コミックス6億3146万冊、コミック誌13億8254万冊である(出版科学研究所調べ)。コミックスも売れ行きは頭打ちであるが、出版物市場ではいまだ大きな比重を占めている。 [小林一博] 輸出入出版物の輸出入額は大蔵省(現財務省)関税局『日本貿易統計』によると、1996年の輸出が書籍183億4259万円、雑誌45億9840万円、99年が書籍147億6560万円、雑誌44億7200万円となっている。1996年の輸入は書籍292億5498万円、雑誌196億8499万円、99年書籍286億4310万円、雑誌179億4233万円であり、出版物は入超が続いている。なお、上記の『日本貿易統計』に含まれない「幼児用絵本及び習画本」は、99年には輸出4795万円(14か国)、輸入23億8747万円(21か国)となっており、ここでも圧倒的な入超である。また、出版物輸出先の最大国はアメリカで、99年の輸出額は書籍62億4715万円、雑誌8億3271万円である。輸入の最大国も同じくアメリカで、書籍101億3718万円、雑誌65億5566万円となり、いずれも2位以下に大差をつけている。 [小林一博] 書店の増加1972年全国の書店の総売場面積は通産省(現経済産業省)の調査によると79万8423平方メートルであった。これが94年6月末時点では265万1473平方メートルに拡張され、97年には、315万平方メートルを超え、さらに増床が続いている。一方、99年のコンビニエンス・ストアの店舗数は3万9754店、書籍・雑誌の売上げは5071億円(主要コンビニエンス・ストアの総売上げ額は6兆9116億円)と推計されている。 [小林一博] 情報と物流出版界を全体としてみたとき、書誌情報の整備、リアルタイムな情報提供は遅れている。さらに、その情報を物流と結びつけた読者サービス態勢は大幅な立遅れとなっている。個々にみると、大手取次、大手版元は、情報提供の改善、物流改善に熱心であり、1年ごとに進捗(しんちょく)の様子がみえる。しかし、読者側からみた場合の注文品対応の遅れは旧態のままである。 インターネットで情報が世界中でリアルタイムで駆け巡っているとき、出版界もようやくインターネットによる情報提供、取次主導によるオンライン書店など、急展開をみせているが、業界全体としては改善速度は遅々としている。急速な改革が必要とする声が多いのである。なお、日本書店商業組合連合会(日書連)が書店のSA(ストア・オートメーション)化に着手したのは1983年(昭和58)のことであり、取次の東販(現トーハン)、日販がそろって出版情報検索システムを発表したのも83年である。 [小林一博] 再販問題ほか1989年に開始された日米構造協議の議題として、規制緩和政策とともに、独占禁止法の適用除外事項である著作物の再販制が浮上したといわれる。以来著作物再販制は、公正取引委員会の研究会、小委員会で、再販制廃止の方向で議論が進められ、95年夏には中間報告が発表された。また、政府の行政改革委員会は規制緩和小委員会において、著作物再販を規制緩和の対象として、同じく95年7月再販廃止論と再販維持論を併記した「論点公開」を公表した。2001年3月公正取引委員会は再販制を当面存続するのが適当と結論をまとめた。出版物販売は再販制が法によって規定される以前の1919年から、全国均一の定価販売制をとってきた。これと1908年ごろに始まった委託販売制度が二つのシステムとして組み合わされ、出版物販売の主柱となってきた歴史をもっている。もし、再販制度が廃止されるようなことになると、出版物販売の態様は一変する、と予想されている。 消費税は、1989年(平成1)3月の初導入時と97年4月の税率アップの2回にわたって混乱した。89年は、書籍、雑誌ともに内税表示方式をとったためで、97年は書籍のみ表示を内税方式から外税方式に変更したためである。しかも、消費税法上、業界が統一基準を設けることができなかったことも、混乱を増幅する結果を招いたようである。 1990年代以降、停滞と混迷を続ける出版界であるが、新たな動きもある。1995年(平成7)から99年まで5回連続、米子市今井書店グループの提唱で開催された大山(だいせん)緑陰シンポジウムに総計5000名が参加し、出版界が当面する諸問題を各3日間にわたって討議し、記録集も刊行された。また、船橋学園読書研究会編『朝の読書が奇跡を生んだ』(1993・高文研)に触発され、2000年夏までには全国の小・中・高校約4000校で朝の10分間読書運動が展開された。これらが大きな刺激となって、出版界あげての読書推進運動が活発化した。現在、それらの読書運動が出版物の売上げを左右するほどの力はないが、やがては大きな地下水脈になるだろう、との期待はある。インターネット、電子書籍、また携帯電話などが従来型の出版物の売上げを減退させている、と推定されるなかで、ゆくえは定まらないながら、出版界も前向きな模索を続けているといえよう。 [小林一博] 世界ユネスコの発表によると、世界の書籍出版点数は、1975年約51万8300点、80年約60万5860点、85年約64万2760点、90年約48万3760点、96年約83万6550点となっている。出版点数の多い国は、1996年の統計によると、中国の11万0283点、イギリスの10万7263点が1位、2位で、3位以下で3万点以上は、ドイツ7万1515点、アメリカ6万8175点、日本5万6221点、スペイン4万6330点、ロシア3万6237点、イタリア3万5236点、韓国3万0487点。なお、統計未詳であるが、フランス、オランダも推定3万点台である(以上は『ユネスコ文化統計年鑑』によるが、発表後大幅な数字の訂正が行われることが多い)。 ヨーロッパの出版業界は、1999年の単一通貨ユーロの導入後、変化が一段と加速している。2001年末までは従来の自国通貨とユーロの二つを価格表示しなけれならず、ユーロの為替変動、オンライン書店の進出、国境を越えた書籍販売など、複雑な変動要因が絡みあっている。またアメリカ、イギリス、ドイツなどの出版資本による大型M&A(企業の合併・買収)も加わって、世界の出版業界は激変にさらされている。イギリスの大手メディア・グループのピアソンPearsonが、1998年にアメリカのサイモン・アンド・シュスターSimon & Schusterの教育・学術書部門を買収。同年、ドイツ最大の世界的なメディア企業であるベルテルスマンBertelsmannは、アメリカの出版大手ランダム・ハウスRandom Houseなどを買収して英文書籍出版の最大手となり、さらに99年アメリカの大手書店チェーン、バーンズ・アンド・ノーブルBarnes & Nobleが設立したオンライン書店の株式50%を取得して経営参加した。アメリカでも、2000年にインターネット関連大手のアメリカ・オンライン(AOL)とメディア大手のタイム・ワーナーが合併するなど、国境や業種を越えた合併や買収が相次いだ。 なお、2000年現在、法定再販制の国はフランス、ギリシア、ポルトガルなどであり、業者間協定による再販制実施国は、ドイツ、オーストリアなどである。アメリカ、イギリス、ベルギー、フィンランド、スウェーデンなどは非再販制である。なお、イギリスは1900年のNBA(Net Book Agreement=正価本協定)で再販制度を確立し、世界の代表的な再販制システムをとっていたが、91年からNBA反対運動が起きて自然消滅し、97年NBAに対して制限的慣行裁判所による違法判決が下され正式に廃止された。フランスは1979年にそれまでの再販制を一時廃止したが、82年に自由化が不評となり当時の大統領ミッテランの選挙公約で復活した。ただし、一定率の値引きを認める値幅再販制を採用している。ドイツの再販制については、EU委員会で論議の対象とされながらも今なお堅持されている。 [小林一博] 出版企画から読者に届くまで出版は、用紙、印刷、製本などの製造工程をたいてい外部に委託する。自社で工場をもって直接製造する例は皆無に近い。販売面においても、ほとんどの出版社は、読者に直接販売することは少なく、取次会社、書店、販売会社を利用する。出版社においては、企画立案、編集、宣伝広告などの業務を主として行う。企画、編集、製作、販売などの関連業務は、書籍、雑誌、教科書など内容によって異なるので、ここでは書籍を中心に述べる。 [小林一博] 企画書籍出版は、各社独自の出版方針、編集方針に基づいて立案される。企画にあたっては、市場調査、類書調査などのうえ、主題、執筆要領、著者、造本体裁、発行部数、配布方法、予価などの設定が行われ、印刷所、製本所、用紙などの材料が選定される。著者から原稿を持ち込まれることも多い。新規創業の出版社は、創業後に企画立案するのではなく、事前に出版方針や著者を決め、原稿などもあらかじめ準備されているものである。 [小林一博] 編集書籍の内容によって、原稿を依頼してから入手するまでの期間は異なるが、通常、1、2年はかかる。学術書、辞典・事典などの執筆は、10年、20年かかることも珍しいことではない。ワープロ、パソコンの普及によって、著者の原稿作成も電子化しており、フロッピーなどによる入稿が大半になった。原稿用紙に手書きの原稿はまれになったようである。また、編集作業も実務を編集プロダクションに委託する例が多い。原稿を入手すると、出版社(編集プロダクション)は、用字・用語や表記方法を定めた原稿整理(執筆)要領に基づいて、原稿を精読吟味し、疑問点は著者にただす。書き直しを依頼することもある。内容の検討が終わると、造本計画、組み方方針に沿って、割付け(レイアウト)、指定を行う。本文、見出し、付属物の文字の書体・大きさ、1行の字詰め、1ページ当りの行数、行間のアキ、写真・図表などの大きさ、挿入の位置などを決める。つまり印刷所への作業指示を行うわけである。なお、レイアウト、ページアップ(印刷工程にかかれる状態にページ毎に体裁を整えること)などの作業も出版社側がDTPで行う例が増えている。扉、序、目次、本文、索引、年表、あとがきなど本の構成順序については、それぞれの出版社に慣習化したルールがある。 [小林一博] 印刷・製本1980年代以降、明治初期に輸入され、出版物製作の基本であった鉛を主材とした活版印刷の方法は衰退し、かわって写真技術を応用した写真植字による印刷版づくり、コンピュータ・システム利用の電算植字(CTS)などの方法が主流になってきた。印刷所(写真植字工房)では、出版社の指示した組み方方針、割付けに従って、原稿どおり1字ずつ採字し、1ページごとにまとめ、一定量ごとに校正刷り(ゲラ刷りともいう)をつくる。編集者または専門の校正者は原稿と対照しながら校正刷りの誤り、組み違いを正す。著者による加筆、削除、訂正は、同時進行の形で行う。この訂正作業は赤色で指示するため、「赤字」「赤字を入れる」という。印刷所(出版社・編集プロダクション)は赤字に従って訂正する。最初の校正を初校という。再校、三校と作業を繰り返し、校了または責任校了にして終わる。 従来の鉛活字で組版をつくっていた場合、製作部数が少なく、重版の予定もないときはそのまま印刷した。これを原版刷りといった。製作部数が多い場合や重版の予定があるときは、凹型の紙型(しけい)をつくり、紙型に鉛を流し込んで凸型の鉛版をつくり、耐刷力を増す必要がある場合は各種のめっき加工をして印刷した。印刷形式は大別して凸版印刷、平版印刷(オフセットを含む)、凹版印刷であるが、鉛活字使用の活版はおもに凸版方式であった。写真植字、電算植字方式は平版、凹版方式をとるのが普通である。前述のように、DTP、CTSなどによる組版製作が主流になるにしたがって、従来の鉛活字による印刷方法は衰退し、また1990年ごろからは、著者がワープロ、パソコンで文字を入力し、出版社が校正を行い、フロッピーなどで印刷所に入稿するのが普通となり、印刷所での文選・植字の作業はほぼなくなった。著者、編集者、印刷所、これら3者の仕事の態様が激変したのである。印刷終了した刷本は、製本所に引き取られ、16ページを基本に折り本にされ、扉、口絵や、見返しといっしょに一冊分にまとめられ(丁合い)、上製本(本製本)なら糸で綴(と)じたうえ、表紙をつけて製本し、箱入れあるいはカバーかけを行って完成する。仮製本(並製本)の場合は、糸綴じにかわって針金綴じ、あるいは接着剤による無線綴じの方法による。見返しの省略も多い。 さらに新しい出版方式として、1990年代後半にアメリカでオン・デマンド出版の方法・技術が開発された。これは、コンピュータに蓄積された本の原版データを元に、読者からの注文に応じて必要な部数のみを印刷・製本・販売するシステムである。90年代終わりには日本にも導入され、2000年(平成12)にトーハンや日販、および大日本印刷や凸版印刷など取次・大手印刷会社主導のオン・デマンド出版が始まった。現在、オン・デマンド出版の普及は遅々としているが、やがてアメリカの学術出版と同様、専門書や学術文献などをオン・デマンド方式で出版する事例が増えるだろうといわれている。 [小林一博] 流通・販売一般の書籍では、製本が完了すると、出版社の指示で製本所は取次会社に納品し、残った分は出版社倉庫に搬入される。取次会社は事前に出版社と取り決めた方法で書店に配本する。出版社から取次会社への卸し率は、出版社別一本正味制と定価別正味制の2通りに基づくが、普通は定価の67~74%である。新規出版社の条件はさらに数%低く、そのうえ返品歩戻(ぶもど)しなどが加算され、取引条件はきびしくなっている。取次会社の手数料は原則として販売分のほぼ8.5%。書店の粗(あら)利益率は通常20~25%である。販売方法は委託制と買切り制に二分され、委託には、新刊委託、重版委託、長期委託、常備寄託がある。買切りには注文買切り、延べ勘定があるが、実際には注文買切り分についても返品が多く、完全買切り制の出版社は少ない。新刊委託は、出版社―取次会社間が6か月間、取次会社―書店間は4か月間となっているが、書店の売場の狭さと出版量の増大により、1週間以内に返品されることも珍しくない。 過大な返品率が業界内で問題化したのは1960年代からであるが、さまざまな返品減少対策にもかかわらず80年代以降さらに上昇を続け、98年の書籍返品率は41%に達した。なお、この返品が以前から公正取引委員会によって注目されていて、前述したように1978年10月の公取委員長の再販制(再販売価格維持契約制度)見直し発言となった。1956年(昭和31)6月から実施されてきた再販制は80年10月に一部修正され、「非再販本」の出版が可能になった。 出版物の流通ルートは、全国で二万数千店を数える書店(日本書店商業組合連合会加盟は約9000店)を活用する取次会社―書店のパイプがもっとも大きく、全体の約60%を占めている。これを取次―書店ルート(通称正常ルート)という。このほかに、訪問販売、通信販売、大学生協、キヨスク(鉄道弘済会(こうさいかい))、スタンド販売、スーパー(コンビニエンス・ストア)、宅配便などのルートがある。スタンド・ルートは、コンビニエンス・ストアの拡勢によって減少傾向にある。一方、インターネットを利用したオンライン書店が出現し、外資と提携したインターネットの活用、コンビニエンス・ストアと宅配便を結合させた新ルートの開発も進んでいる。書店の売場面積は平均20坪台(66平方メートル)と推定される。しかし、1990年代には1000坪(3300平方メートル)以上の売場をもつ書店が登場し、他業界からの新規参入も後を断たず、大型化、多店舗化の傾向が続いている。 なお、流通の円滑化と迅速化を促進し、書誌情報の一元化を図るため、「日本図書コード」が実施されている。これは、全世界の書籍を10桁(けた)の数字で表す国際標準図書番号(ISBN)を主体に、分類コード、価格コードなどを加えたシステムであり、現在はバーコード併用もほぼ定着した感がある。インターネット時代の電子商取引に適応するためには、さらなる出版情報の整備が必要との指摘もある。 [小林一博] 『寿岳文章著『図説 本の歴史』(1982・日本エディタースクール出版部)』▽『川瀬一馬著『入門講話 日本出版文化史』(1983・日本エディタースクール出版部)』▽『清水英夫・小林一博著『出版業界』(教育社新書)』▽『鈴木敏夫著『出版』(1970・出版ニュース社)』▽『S・アンウィン著、布川角左衛門・美作太郎訳『最新版 出版概論』(1980・日本エディタースクール出版部)』▽『箕輪成男著『歴史としての出版』(1983・弓立社)』▽『小林一博著『本づくり必携』(1983・日刊工業新聞社)』▽『村上信明著『出版流通とシステム』(1984・新文化通信社)』▽『小林一博著『出版業界――問題の焦点』(1992・柏書房)』▽『小出鐸男著『現代出版産業論――競争と協調の構造』(1992・日本エディタースクール出版部)』▽『清水英夫著『出版学と出版の自由――出版学論文選』(1995・日本エディタースクール出版部)』▽『日本出版学会編『出版の検証――敗戦から現在まで』(1996・文化通信社)』▽『箕輪成男著『出版学序説』(1997・日本エディタースクール出版部)』▽『高宮利行・原田範行著『図説本と人の歴史事典』(1997・柏書房)』▽『「新文化」編集部編『列島書店地図――激戦地を行く』(1998・遊友出版)』▽『小田光雄著『出版社と書店はいかにして消えていくか』(1999・ぱる出版)』▽『井家上隆幸・永江朗・安原顕著『超激辛爆笑鼎談・「出版」に未来はあるか?』(1999・星雲社)』 [参照項目] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 |
>>: Immigration control (English: immigration)
Recommend
Ectomycorrhizae - Gaikinkon
Mycorrhizae are fungi that grow mainly in the tiss...
Ishikawa fence guardian
?-786 A government official in the Nara period. I...
antiquarian bookshop (English)
...the general term for businesses that buy and s...
Kotooka [town] - Kotooka
A former town in Yamamoto County, northwest of Aki...
Wei County - Wei County
…It is also famous as a producer of Shandong toba...
Dolby system
…Even if there are slight differences in the leve...
Autumn drought - Autumn drought
… Oily weather: Hot and humid weather with no win...
Potentiometer - Electrical
This device uses the so-called null method to mea...
Bugula neritina (Bryophyte) - Bugula neritina
It is an exoproctidae of the family Mycorrhizae. I...
Upuuat - Upuuat
…In the Book of the Dead, he is depicted as weigh...
Downward erosion
The erosion of a river or glacier toward its base...
peppermint
〘Noun〙 (peppermint)⸨Peppermint⸩① A cultivated pere...
Stair-step moss
...This growth cycle repeats year after year, res...
hood
...hat with a crown and brim, hood, brimless cap,...
Child marriage - Youjikon
A marriage arranged by the parents with a child as...